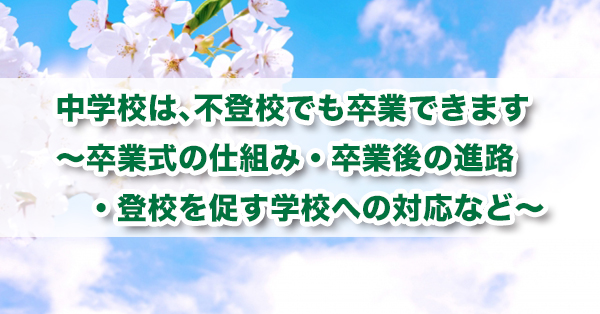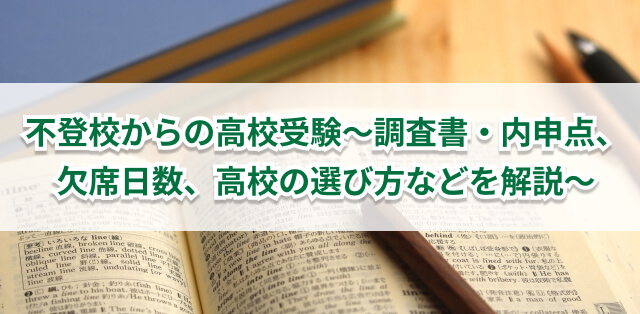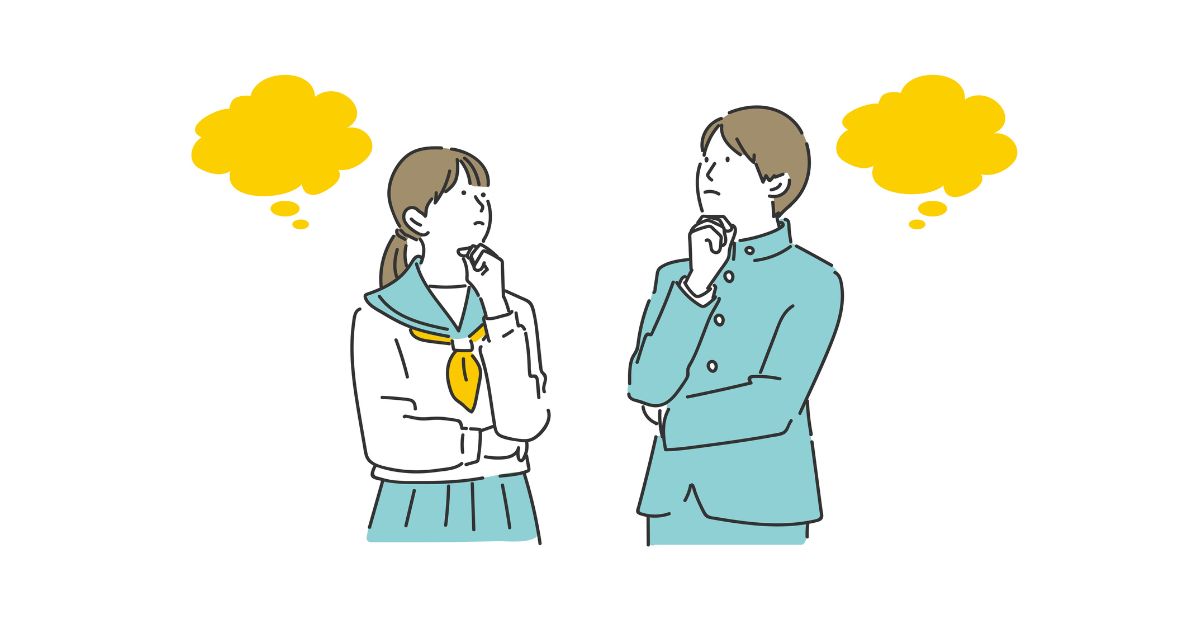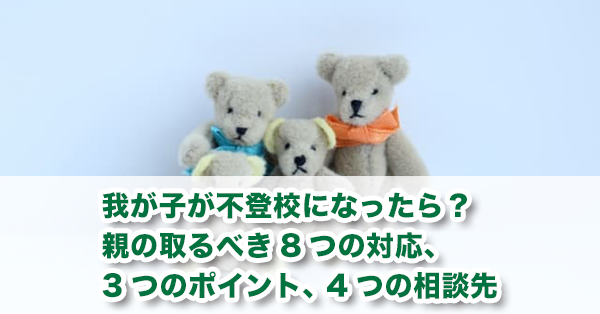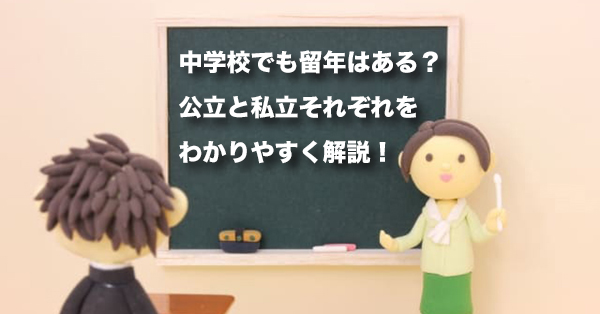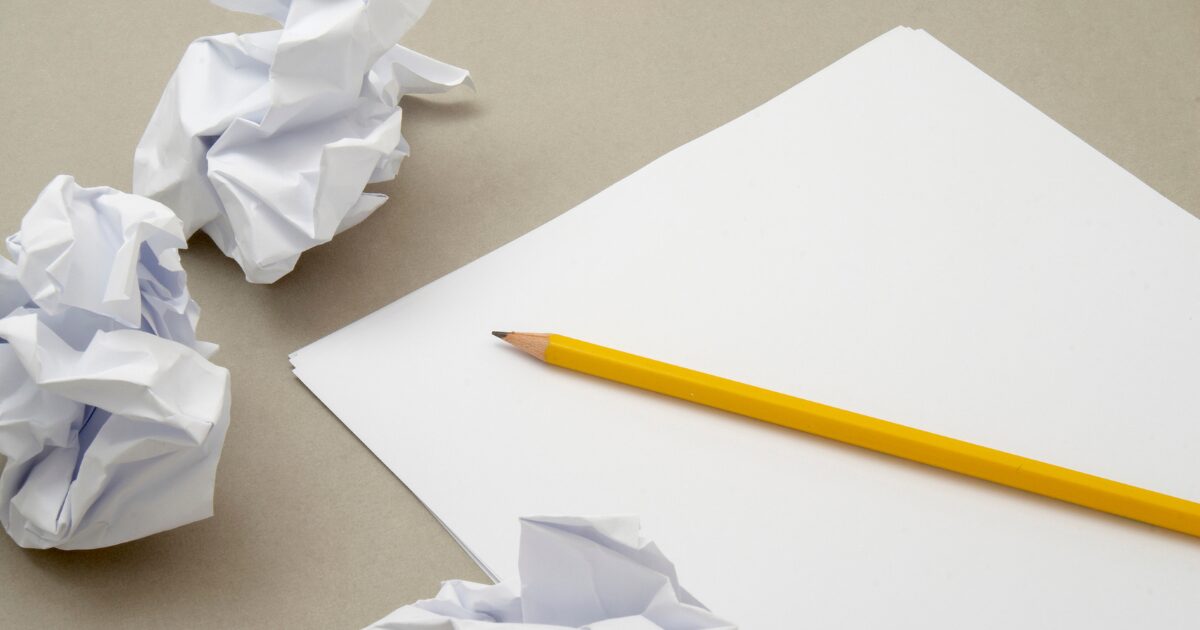不登校の中学生にできる親の対応 原因やその後の進路を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートするキズキ共育塾です。
中学生になると、勉強の難しさや学習環境の変化、人間関係などが原因で不登校になる人が少なくありません。
親御さんのなかにも、お子さんの卒業や進路が心配だという人がいると思います。
そこでこのコラムでは、中学生の不登校の現状や原因、選択できる進路などについて解説します。
親ができるサポートやNG対応についても解説しますので、中学生のお子さんの不登校で悩んでいる人には、必ず参考になるはずです。
共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの
アドバイス
子どもが不登校や行きしぶりになると、「無理に学校復帰を急がずに見守りましょう」とよく言われるでしょう。
しかし、子どもが不登校や行きしぶりになった親にとって、これほどいらだつメッセージはありません。
しかし、「無理せずに」は本当に重要なのです。みんな「無理せずに」ができずに失敗してきたからです。本コラムで書かれているポイントは、多くの失敗の上に積みあがってきた知恵です。ぜひご参考ください。
私たちキズキ共育塾は、不登校状態にある中学生のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
中学生の不登校とは?

不登校と聞くと単純に学校へ行っていない人をイメージするかもしれませんが、不登校には明確な定義があります。
不登校とは、なんらかの心理的な要因や交友関係や家庭環境を含む社会的な背景などが複雑に絡み合った結果、長期間にわたって登校しない、または登校したくてもできないでいる状態のことです。
不登校という状態は、文部科学省によって以下のように定義されています。
何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者をのぞいたもの
(参考:文部科学省「不登校の現状に関する認識」)
不登校の公的な定義には、要因・背景がある程度限定されていることに加え、欠席の日数が明記されているわけです。
ちなみに、不登校に近い区分として、長期欠席というものがあります。長期欠席は、病気や経済的な理由など、不登校の定義に含まれていない理由で欠席している状態を指します。
不登校の定義の詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
不登校の中学生は卒業できる?
通常は不登校であっても、1日も出席しなくても、中学校を卒業できます。
中学校は義務教育なので、出席日数が卒業の条件になることはありません。
特に公立の中学校では、不登校のままでも留年とはならず、卒業できるはずです。
一方、私立の中学校は学校ごとに決まり・基準があり、場合によっては不登校のために留年となる可能性があります。
また、学校側から「不登校で勉強できていないので、留年しますか」と確認された場合、それを受け入れると留年になることもあります。
もし欠席が続くようであれば、卒業や留年の扱いについて、念のために学校の先生に相談することをオススメします。
不登校の中学生の卒業については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
不登校の中学生の高校受験はどうなる?

中学生のお子さんがいる親御さんのなかには、不登校だと高校受験ができないのではないかと心配になる人もいるかもしれません。
結論から言えば、不登校でも受験・進学できる高校はたくさんあります。
ただし、志望校によっては、試験の点数以外に、出席日数や内申点が書かれた調査書が審査の対象になることがあります。
したがって、基本的には調査書の内容があまり問われず、学力試験の結果で合否が決まる私立高校などが志望校になるでしょう。
なお、不登校だからといって、必ずしも調査書の提出が求められる高校に合格できないというわけではありません。調査書の内容を良くするためにできることもあります。
不登校の中学生の高校受験や調査書については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
中学生の不登校の現状
文部科学省の調査によると、2023年度の中学校の在籍児童生徒数は、322万963人です。
そのうち、不登校の生徒数は21万6112人で、在籍児童生徒数の約6.7%を占めています。(参考:文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」)
また、中学校の不登校児童生徒数は年々増加しており、2013年度は9万5442人だったのに対し、2023年度は21万6112人と、2倍以上に増えています。(参考:文部科学省「平成 25年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」について」)
特に、新型コロナウイルスが流行した2020年と2021年を境に不登校の生徒数は急増しており、2014年から数えると、11年連続で過去最高を更新しているというのが現状です。(参考:文部科学省「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要」)
中学生の不登校の7つの原因

中学生の不登校の原因・理由として考えられるものは、以下のとおりです。
- 勉強面の悩みがある
- 人間関係に問題がある
- 新しい学校に慣れない
- 家庭環境に不安がある
- 他にやりたいことがある
- お腹が痛いなど体調が悪い
- なんとなく行く気にならない
ただし、以上のうちのどれか1つが原因とは限らず、複数の原因が絡みあって不登校になっていることもあります。
そのため、特定の原因が解消されたからといって、必ずしも不登校が解決するわけではないという点には注意が必要です。
また、これといった原因が無くてもなんとなく登校する気にならなかったり、本人も原因がうまく話せなかったりする場合もあります。
原因探しがお子さんを追い詰める可能性もあるので、無理に原因を求めないという姿勢も大切です。
中学生が不登校になる原因・理由については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
不登校の中学生の進路11選
不登校状態にある中学生には、以下のような進路が考えられます。
- 通信制高校
- 定時制高校
- 全日制高校
- 高等専修学校
- 高等専門学校(高専)
- 高卒認定試験
- 就職
- 留学
- 特別支援学校・高等部
- 高等特別支援学校
- チャレンジスクールなど
その他の選択肢として、特定の進路を選ばずに、フリーのライターや動画編集者として働く道もあります。一人で在宅で始められるため、比較的、負荷は少ないです。
ただし、安定して収入を得るには高いスキルと、一定の経験が必要なので、フリーランスを目指す場合はスクールやWeb講習などを経由することをオススメします。
不登校状態にある中学生の進路については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
不登校の中学生にできる親の対応8選

不登校状態にある中学生のために親が取れる対応は、以下のとおりです。
- 親がパニックにならない
- 学校と連絡を取る
- お子さんを休ませる
- お子さんの話を聞く
- 家庭内に解決すべき問題があるかを振り返る
- 家庭の居心地をよくする
- 「学校復帰するべき」という考え方から離れる
- 不登校についての情報を集める
重要なのは、お子さんのペースに合わせることです。心配になる気持ちもわかりますが、まずは親御さん自身が余裕を持って、お子さんに寄り添う態度を見せましょう。
その上で、不登校を解決する手段は1つではないことを念頭に話し合いましょう。今の学校への復帰にこだわりつづけることが、不登校の解決を遅らせる場合もあります。
親の対応については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
不登校の中学生にしてはいけない親のNG対応5選
不登校状態にある中学生にしてはいけない親のNG対応は、以下のとおりです。
- 放置する
- 理由を問い詰める
- 無理に学校に行かせようとする
- 「学校に行け」と叱る
- 「明日は行くから」を真に受ける
無関心は禁物ですが、だからといって理由を無理に聞き出そうとしたり叱りつけたりするのも、お子さんを心理的に追い込むことになるので良くありません。
また、登校意欲を見せていても、当日になると不安が高まって登校を拒否するなど、お子さんはさまざまな葛藤を抱えています。
したがって、お子さんの選択を余裕を持って受け止める姿勢を持つことが大切です。
不登校状態にあるお子さんにしてはいけない対応については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
不登校の中学生のために利用できる8つの支援機関

不登校状態にある中学生のために利用できる支援機関は、以下のとおりです。
- 教育支援センター(適応指導教室)
- 教育相談所
- フリースクール
- 子ども家庭支援センター
- 保健所
- 精神保健福祉センター
- 児童相談所
- ひきこもり地域支援センター
不登校状態にある中学生や親が利用できる支援機関については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
中学生のときに不登校を経験した人の体験談
この章では、キズキ共育塾に入塾した人のなかから、中学時代に不登校を経験した人の体験談を紹介します。
体験談①中学で二度の不登校から高校へ合格

Mさんは中学時代に人間関係が原因で2度の不登校を経験。
1度目は人間関係、2度目は登校を再開したが勉強についていけず不登校に。
登校を再開していない状態で進学できる高校を探しながら、キズキ共育塾へ入塾します。
完全個別で周りを気にすることなく学習に集中でき、志望校を見つけ対策することが出来ました。
本人の希望で大学進学コースのある高校への進学ですが内申点を問われない高校のため、Mさんは登校を再開しないまま中学を卒業されています。
Mさんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
体験談②ADHDで中学不登校から高校に進学
IさんにはADHDの特性があり、中学校は不登校でした。
キズキの創業者である安田祐輔さんにも発達障害があると知り、「通いやすそう」と思い、入塾しました。
それからは、講師にも恵まれ、楽しみながら通うようになりました。生活面でもメリハリがつき、明るくなったそうです。
その後、無事に高校に進学することができました。
Iさんは、「私の中学校はキズキだよね」と、楽しかったことや嬉しかったことをいまでも親御さんに話すそうです。
Iさんの親御さんによる体験談を詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
体験談③小中不登校から高校を経て大学へ進学

Wさんは小学5年生のころに不登校になり、中学校に進学してからも登校が難しい状態が続いていました。
中学校をなんとか卒業したあとは、全日制高校が合わないと考え、通信制高校に進学。
高校卒業後にキズキ共育塾を知り、大学受験の準備のために入塾を決めました。
不登校の期間が長かったので、はじめは他人の目をまともに見ることができず、会話で緊張してパニックに陥ることもありました。
でも、授業中に先生と趣味の話で盛り上がるときがあったりと、講師と生徒との距離が近かったからこそプレッシャーを感じずに頑張れました。
その後、Wさんは大学に合格しました。
Wさんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
体験談④不登校から高卒認定試験を経て大学へ進学
Hさんは、中学3年生の時に理由が思い出せなくなるくらい嫌なことがあり、不登校を経験します。
中高一貫校だったため高校には進学できましたが、中学と同様に登校しない日々が続いていました。
日本の学校を退学して海外の高校に留学することになります。そこで理系の面白さを知ったことがきっかけで理系大学への進学を志します。
理系大学へ進学するため海外の高校を退学して、高卒認定試験に独学で合格。その後キズキ共育塾で大学受験の対策を行い、立命館大学理工学部に合格されました。
不登校を経験し高校を卒業しなくても大学への進学は可能といえますね。
Hさんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
中学生の不登校に関するよくある質問
この章では、中学生の不登校に関するよくある質問を紹介します。
Q1.子どもの不登校は親の育て方に原因があるのでしょうか?

お子さんが不登校になると、育て方に問題があったのではないかと思う親御さんは少なくありません。
しかし、基本的には、親の育て方が不登校の直接の原因になることはありません。
そもそも育て方がどうであれ、中学生はある程度、自分の意思で物事を判断・選択して行動できる年頃です。
同じ環境で育てられた兄弟・姉妹でも、不登校になる人もいれば、ならない人もいます。
つまり、親の性格や育て方は直接的には関係ないのです。
ただし、虐待やネグレクト、家庭環境の悪化などが不登校の原因になる可能性はあります。
とはいえ、これはあくまでも例外です。自分の育て方に原因があるのではないかと思い悩む親御さんであれば、こうした例外に該当することはないはずでしょう。
不登校状態にあるお子さんがいる親が感じやすい悩みについては、以下のコラムで解説しています。是非ご覧ください。
Q2.不登校の中学生の子どもがいる親が心掛けるべきことは?
不登校状態にあるお子さんがいる親御さんは、まずはお子さんが自分の抱えている悩みを話そうと思える状況を作ることを心掛けましょう。
お子さんが不登校になると、あなたも戸惑うかもしれませんが、「そういうこともある」と受け入れるだけのおおらかさを保つことが大切です。
また、意外と忘れがちなのが親御さん自身のケアです。
お子さんに掛かりきりになっていると、親も余裕を失いやすくなります。それを避けるために、自分の好きなことに集中したり、リフレッシュしたりする時間を取りましょう。
悩みを抱えきれないという人は、不登校状態にあるお子さんがいる親同士のコミュニティに参加するのも1つの手です。
キズキでは、不登校の親専用のオンラインコミュニティ「親コミュ」を運営しています。
匿名で参加しやすく、同じ悩みを抱える親同士で気軽にチャットでコミュニケーションが取れます。ぜひ興味のある方は参加してみてください。
参考:親コミュ
Q3.不登校でも学習塾に通って問題ないでしょうか?

全く問題はありません。学校側から問題だと指摘されることも無いでしょう。
ただし、すべての学習塾が不登校の人に対応できるとは限りません。
受験合格を目的としている進学塾も、不登校状態で学校の勉強に追いつくことを目的としている人には不向きな可能性があります。
不登校状態にある人には、不登校に理解のある学習塾や、自分のペースで勉強を進められるスクールがオススメです。
不登校状態にある人の通塾については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ~適切な対応をしながら不登校のお子さんに合う進路を探しましょう~

不登校状態にある中学生でも卒業はできます。高校受験を含め、進路もたくさんあります。
お子さんが次のステップを踏み出すためには、周囲のサポートが必要です。
親御さん自身も、不登校状態にあるお子さんの対応に迷うことがあれば、できるだけ家族や専門家を頼ってください。
私たちキズキ共育塾でも、不登校状態にあるお子さんの勉強とメンタルをサポートしています。
ぜひお気軽にご相談ください。
Q&A よくある質問
中学生の不登校の原因について、教えてください。
以下が考えられます。
- 勉強面の悩みがある
- 人間関係に問題がある
- 新しい学校に慣れない
- 家庭環境に不安がある
- 他にやりたいことがある
- お腹が痛いなど体調が悪い
- なんとなく行く気にならない
詳細については、こちらで解説しています。
不登校の中学生にできる親の対応はありますか?
以下が考えられます。
- 親がパニックにならない
- 学校と連絡を取る
- お子さんを休ませる
- お子さんの話を聞く
- 家庭内に解決すべき問題があるかを振り返る
- 家庭の居心地をよくする
- 「学校復帰するべき」という考え方から離れる
- 不登校についての情報を集める
詳細については、こちらで解説しています。