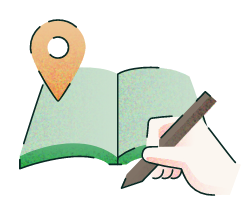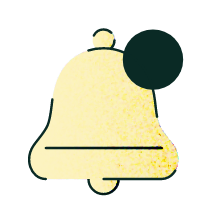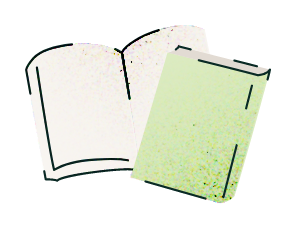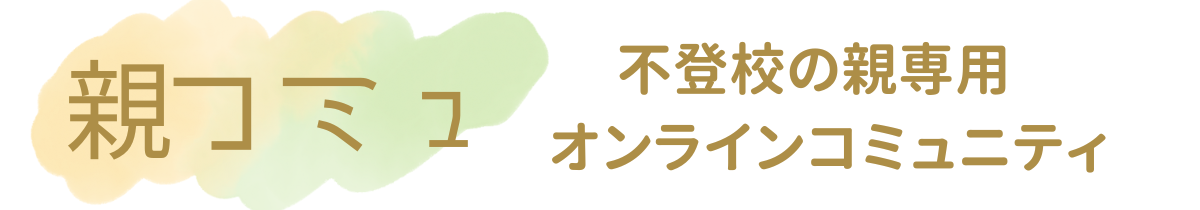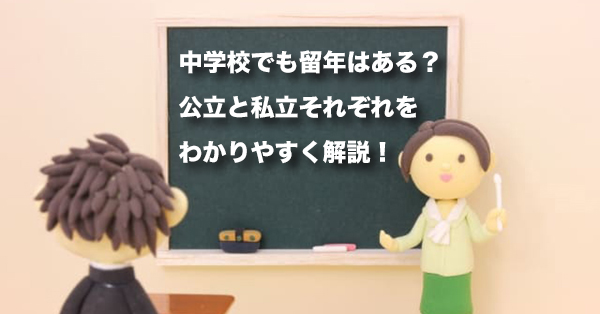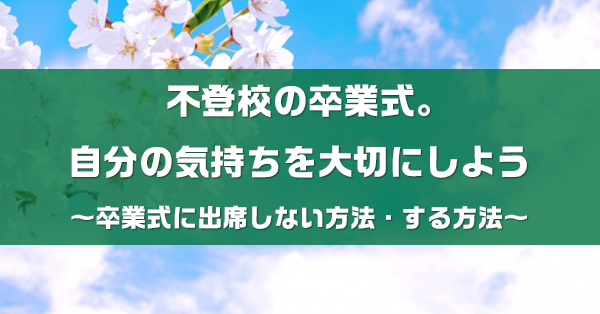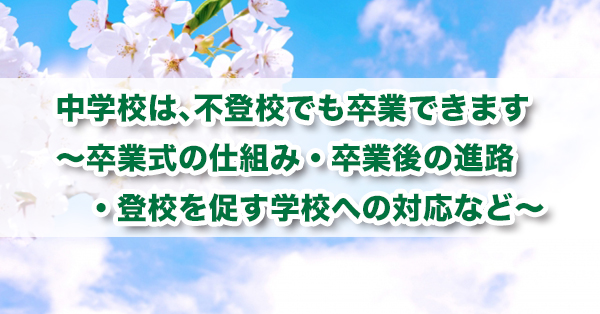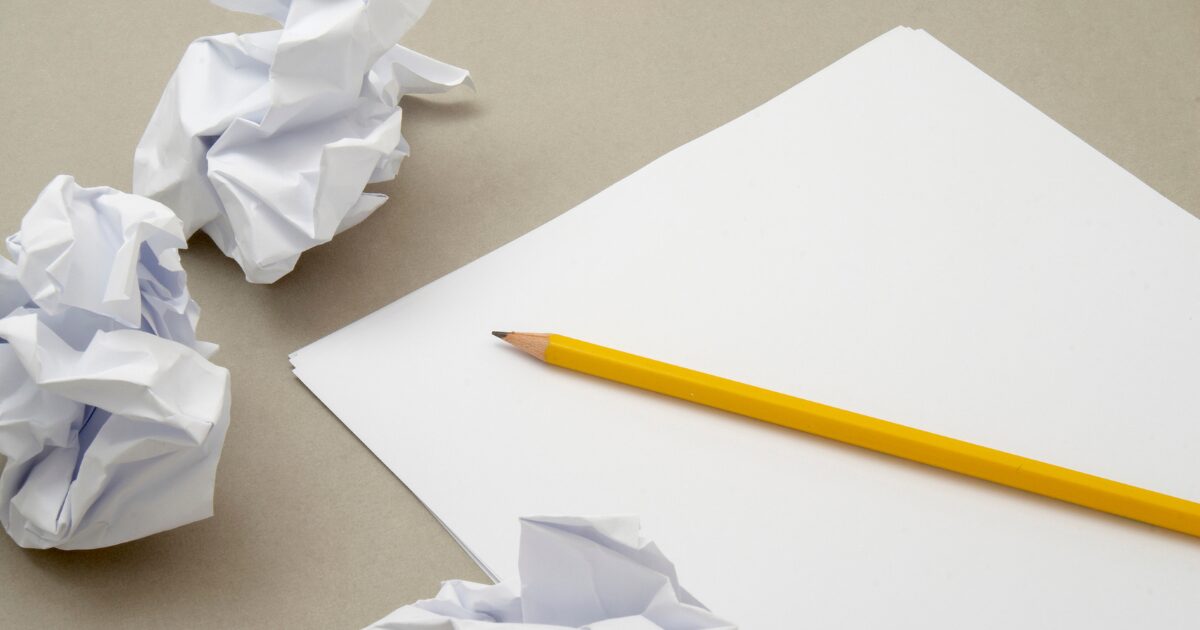中学校は不登校でも卒業できる 卒業後の進路を解説
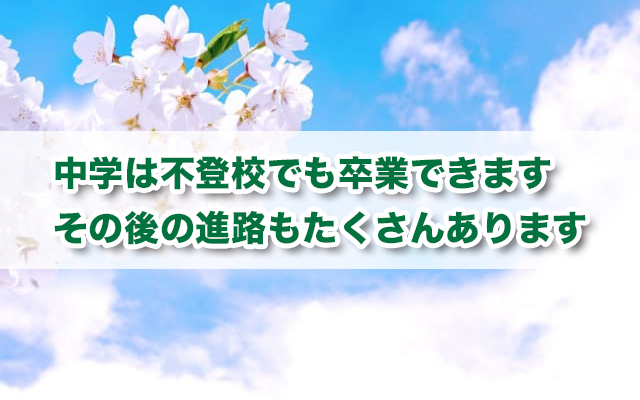
こんにちは、キズキ共育塾の内田青子です。
不登校の中学生の親御さんは、「このまま不登校が続くと中学校を卒業できないのでは…?」と不安を抱えているのではないでしょうか。
学校側から、「このまま出席できないと卒業させられません」と言われている方もいるかもしれません。
結論から先に申し上げますと、中学校は、不登校のままでも卒業できます。
このコラムでは、不登校の中学生が卒業するために注意すること、中学校を卒業した後の進路、卒業式には出るべきなのか?などについてお伝えします。
不登校についてお悩みのお子さんと、ぜひ一緒に読んでください。
共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの
アドバイス
卒業に関する正しい知識を身につけましょう
お子さん本人が希望すれば、公立中学校は1日も通わずに卒業できます。また、卒業式に出なくても、卒業証書を受け取らなくても、卒業できます。
この事実を知らずにどれだけの人が傷ついてきたかわかりません。
このコラムの内容は、とても実践的です。「知っていれば傷つかずに済んだ」と実感する知識がたくさんあります。
ぜひ一度、「ご自身の常識と違うかもしれない」という視点で読んでみてください。
私たちキズキ共育塾は、不登校にお悩みの人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
中学校は不登校でも卒業できる

中学校は、不登校でも(1日も出席しなくても)卒業できます。
小学校・中学校は義務教育です。
「義務」だから出席していないと卒業できないのでは…と思う方もいるかと思いますが、この「義務」とは、「子どもが学校に行く義務」ではなく、「保護者が子どもに学校教育を受けさせる義務」のことです。
中学校では、出席日数と卒業は関係ありません。
特に公立の小・中学校は、不登校のままでも留年とはならず、卒業できるのです。
例外として、学校側から「不登校で勉強できていないので、留年しますか」と確認されることがあり、それを受け入れると留年になります。
ただ、東京都の公立中学校で教諭として働いていた知人によると、「自分の知る限り、その提案を受け入れて留年した人はいない」とのことでした。
つまり、留年を強制する仕組みは、事実上ないということです。
ただし逆に、「勉強ができていないので留年したい」と子どもや親御さんの側から提案しても、受け入れられないことの方が多いようです。
私立の中学校は、学校ごとに決まり・基準があり、場合によっては不登校のために留年となる可能性もあります。
欠席が続いているようなら、卒業や留年について、一度学校の先生に相談してみてください。
「今の学校では留年になりそう」という場合は、公立の学校に転校して卒業する方法もあります。
公立にしても私立にしても、「留年して学び直した方がいいのか」「合わない学校を早く卒業して次のステップに進んだ方がいいのか」などは、お子さんの状況によって違ってきます。
中学校の出席日数と卒業の関係については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
卒業式は参加しなくてもよく、卒業証書も必要ない

中学校は、出席日数が不足していても卒業できるとお伝えしました。
「だけど卒業式には出席しないと、卒業証書がもらえないんじゃない…?」と不安に思う親御さんもいるかと思います。
お子さん自身も、不登校だと卒業式に出席しづらいかもしれませんね。
その点も心配する必要はありません。
卒業式に参加しなくても卒業証書はもらえますし、卒業証書をもらわなくても中学校を卒業できるからです。
卒業証書について補足すると、卒業後に必要となる場面はありません。
高校受験の際などに必要になることがある書類は、「卒業証書(筒などに入った賞状のような紙)」ではなく、「卒業証明書(事務的な書類)」です。
卒業証明書は、卒業式や卒業証書と関係なく、中学校に申請することで取得できます。
「卒業式」と「卒業証書」には記念以外の意味はありませんので、気にならないなら参加も受け取りも必要ないのです。
卒業式の参加と卒業証書の受け取りには、サポートや代替措置もある

ただ、卒業式や卒業証書には、記念の意味はあります。
お子さんに「卒業式には参加したい」「卒業証書はほしい」などの思いがあれば、出席方法や受け取り方法を学校と一緒に考えましょう。
前述の中学校教諭経験者に聞くと、不登校の人は、次のような形で卒業式に参加できることがあるようです(学校によって別の方法があることも考えられます)。
- 授業には行かないまま、卒業式の練習と本番にだけ参加する
- 卒業式本番だけに参加して、起立・着席などの練習が必要な「動作」には加わらない
- 保護者席で参加する
- 卒業式の後日、病欠や受験などで卒業式本番に参加できなかった人たちで集まって、改めて開催される少人数の卒業式に参加する
卒業証書は、学校に「卒業式には行かないけれど、卒業証書はほしいので、どうしたらいいか相談させてください」などと伝えると、受け取り方法について相談できるはずです。
聞いた話では、親御さんだけで後日受け取りに行く、という方法がありました。
卒業式と不登校の関係については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
中学校で不登校でも、卒業後は高校進学はできるし、した方がよい

中学校で不登校でも、卒業後の人生の選択肢を広げるためには、高校に進学することをオススメします。
高校は義務教育ではないので、絶対に進学しなくてはいけない学校(=保護者として進学させなくてはいけない学校)ではありません。
ですが、現代日本では、ほとんどの人が高校を卒業しています。
学歴が「中卒」だと、高卒以上の人に比べて不利になる場面が多いことは、残念ながら事実です。
例えば、就職に関しては、高卒以上に比べて求人の数・種類が少ないですし、就職後の待遇や出世に影響することもあります。
「複雑な家庭で育ったんじゃないか」「高校に行けない問題があったんじゃないか」と詮索をされる…もっと言えば、学歴差別を受ける可能性もあるのです。
学歴差別はする方が悪いのですし、お子さんの「味方」も必ず存在します。
また、中卒の学歴で楽しく充実して生きている人もいます。
ですが、繰り返すとおり、高校を卒業した方が選択肢が広がります。
中学不登校でも高校進学はできますし、自分に合った高校を選ぶことで、勉強したり、楽しく過ごしたりすることも、もちろん可能です。
「中学不登校だと、高校に進学できないんじゃないか…」と思う人もいるのですが、探してみるときっと意外にたくさんの学校があることがわかるでしょう。
疲れていて今は高校進学する気にならない人は、気持ちを整えてから改めて高校に進学することもできます。
お子さんが高校に行かない(進学しない)と言っている場合については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
中学不登校からの高校受験・進学では、内申点に注意が必要

中学校で不登校でも卒業・高校進学はできますが、中学で不登校だと高校受験の際に、不登校に伴う不利が発生することはあります。
簡単に言うと、「内申点が低いことで、受験・合格できる学校の選択肢が減る」ということです。
内申書(調査書)とは、中学校の出席日数、成績、生活態度などを中学校の先生が記した書類です。
内申書の提出を求められる方式の高校受験では、試験の合否は、「学力試験の点数」と「内申書(調査書)の点数」の合計で審査されます。
中学校で不登校だと、出席日数が少なかったり勉強ができなかったりすることで、内申書(調査書)の点数が低くなる可能性が高い(=不合格となる確率が上がる)、ということです。
…と言うと不安になるかもしれませんが、内申書(調査書)の点数を重視しない高校や、審査しない受験方式もたくさんあります。
具体的な選択肢としては、次の通りです(一部です)。
- 私立高校(内申書を重視しない高校や、内申書を審査しない受験方式がある)
- 通信制高校(一般的に、内申書を重視しない)
- 定時制高校(一般的に、内申書を重視しない)
- チャレンジスクール(不登校の生徒のための都立高校)
不登校でお子さんの内申書が心配な場合は、内申書を重視しない高校・受験方式を探してみてください。
ただ、内申書を重視する高校を志望する場合も、残りの学校生活で点数を上げられる可能性もあります。
学校によっては、「保健室登校」「フリースクールへの出席」「早退・遅刻しての出席」などを「学校の出席日数」として認めている学校もあるのです。
学校の先生と相談して、内申書の点数を上げるための対策を立ててもらいましょう。
なお、一般的に、内申書を重視する高校では、学力試験の点数も重視しています。
不登校で中学校に通えていなくても、塾などを利用して学力を伸ばすことはできるので、ご安心ください。
中学校不登校の子どもに対して親ができる3つの対応
不登校でも中学校を卒業できること、高校にも進学できることは、お伝えしてきたとおりです。
その上で、お子さんは親御さんの適切なサポートを受けることで、「今の苦しみ」を減らすこともできますし、「よりよい次の一歩」を探しやすくもなります。
また、中学を卒業する前にも、今在籍している学校への登校を再開したり、別の場所で楽しく過ごすこともできるようになったりします。
キズキ共育塾では、多くの不登校の生徒さんを支援しています。
この章では、キズキ共育塾の知見に基づき、不登校の中学生のためとなる親御さんのスタンス・親御さんにやってほしいことを、3つお伝えします。
対応①不登校の原因にこだわりすぎない

お子さんが不登校だと、なぜ不登校になったのか原因を知りたいと思う親御さんは多いでしょう。
しかし、お子さんが中学校に行けなくなった直接的な原因の追究・解決を目指すことが、不登校の解決には繋がらないことがあります。
逆に言うと、原因の直接的な追及・解決がなくても、次の一歩に進めることも少なくありません。
不登校の原因は様々で、複数の要因が複雑に作用しあって不登校が発生している場合もよくあります。
また、「不登校になった原因」とは別に、「不登校になってから、新たに生じた別の悩み」によって、登校を再開できないパターンもあるのです。
あくまで一例ですが、不登校になったきっかけが「担任の心ない一言」だったとします。
担任との和解によって登校を再開できることは、もちろんあります。
しかし、担任と和解しても、不登校中に「勉強についていけるか不安になった」「昼夜逆転で朝起きられなくなった」などの場合は、登校を再開することが難しくなることもあるのです。
逆に、担任との和解がないままでも、「年度替わりで担任が異動した」「学校以外の楽しい場所を見つけたことで、担任のことが気にならなくなった」「別の学校に転校した」「学校には行かないまま、塾で勉強して高校に進学した」などの「次の一歩」に進めることもあるでしょう。
不登校になった原因を探すべきではないとは言いませんが、原因の追及・解決はある程度にとどめておいて、「今がどうか。これからどうするか」に目を向けることをオススメします。
ただし、例えば次のように、不登校になった直接的な原因を無視してはいけないケースがあります。
- うつ病、統合失調症など精神的な疾患の可能性がある
- 発達障害があり、学業や人間関係に困難を抱えやすい
- 夫婦の問題、経済的問題など、子どもに悪影響を与える家庭内の問題がある
- いじめが関係する
不登校の原因については、追求・解決すべきかどうかも含めて、次項でご紹介する専門家を頼ることで、対応もわかります。
対応②専門家・第三者に相談する
お子さんと、親であるあなたの状況については、第三者や専門家の支援・サポートが必要です。
お子さんの不登校を誰にも相談せずに、家庭の中で悩みを抱え込み、親子で社会や学校から孤立し、家庭の中に引きこもることは、避けましょう。
あなた自身の友達や親戚や、専門的な知見を有する団体などを、ぜひ積極的に頼ってください。
専門家を訪ねた方がいいのは、お子さんやご家庭によって、「向いている対応」が違っているからです。
不登校の中学生について、書籍やインターネットでは、「厳しく接するべきだ」「叱ってはいけない」などと様々な情報が流れています。
その中のどれが正しくて、どれが正しくないかを一概に言うことはできません。
「優しく接する」ことで心を回復していくお子さんもいれば、「腫れ物に触るような対応をされている」と親に不信感を抱くお子さんもいます。
反対に、「厳しくされる」ことで親から理解されないと苦しむお子さんもいるでしょう。
あなたのお子さんに最適な対応は何なのかは、専門家を頼ることで具体的に見えてきます。
専門家とは、例えば次のような団体などが考えられます。
- 市区町村の相談窓口
- フリースクール
- 不登校の人たちの学び直しに詳しい塾・予備校
- 小児科・児童精神科
- 国家資格を持つカウンセラー
インターネットで、「不登校 相談 自治体」「子ども 不登校 相談」などと検索すると、いくつか候補が見つかると思います。
それぞれの団体は、理念・目的・手法などがそれぞれ違っています。
お子さんやあなたに合いそうなところが見つかった場合は、問い合わせてみましょう。
民間の団体には、残念ながら「内容に見合わない高額な利用料を請求するところ」などもありますので、評判や、公的団体との付き合いの有無などを軽く調べることが大切です。
対応③親は親で、自分の生活を充実させる

親は親で、自分の生活を充実させましょう。
「子どもが不登校なのに、私だけが仕事に行ったり、趣味を楽しんだりしていいのだろうか?」「子どもが苦しんでいるのに、自分だけ楽しく過ごすことはできない…」などと思われるかもしれません。
ですが、親が自分の人生を楽しみ、充実させることには、次のような効果があります。
(1)親子が社会から孤立することを防ぐ
親が子ども以外のことに目を向け、家庭外との繋がりを適切に保つことで、悪循環を防げます。
先ほども軽くお伝えしましたが、子どもの不登校に伴い、親子とも家庭外との繋がりがなくなり、家庭ごと孤立するケースがあるのです。
親が働きに出ていても、「楽しみ」のない生活では、心理的に孤立することもあります。
家族という密閉した空間の中に引きこもると、視野が狭くなり、親子の不安はますます増幅します。
親の過度な不安や心配が子どもの心を圧迫し、子どもは子どもでさらに不安を抱える…といった悪循環にも陥りかねません。
(2)親が大人のロールモデルとなることができる
親の一人の大人として充実している姿は、子どもに「望ましい大人のロールモデル」見せることにもつながります。
充実している親の姿を見ることで、子どもは「今は苦しいけど、将来は楽しいかも」と考えるようになる可能性があるのです。
子どもに「外の世界は楽しいよ」「大人になるっていいものだよ」ということを、ぜひ親御さんご自身が人生を充実させることで、伝えてください。
中学校から強く登校を促されるときの、6つの対応法
中学校や先生によっては、不登校のお子さんに強く登校を促す場合もあります。
- 出席日数が足りないと、3年生に上がれないぞ
- 卒業式に来なかったら、卒業させないからな
一部だと思いますが、先生からこのように強く言われることもあると聞きます。
先述したとおり、特に公立の中学校は、1日も登校しなくても卒業することは可能です。
先生から「登校する圧力」がかかった場合、「無視する」という方法もあるのですが、できれば学校との関係は良好にしておきたいでしょうし、先生が記入する内申書も心配でしょう。
ここからは、キズキ共育塾の経験から、中学校の卒業(進級・通学など)に関連して、先生から強く登校を促された場合の対処法を6つご紹介します。
前提:先生も「意地悪」をしているわけではないと認識する

まず、基本的には、先生が「学校に来い」と言うのは意地悪や悪意によるものではない、ということを前提として認識しておきましょう。
善意、熱血、その先生自身もどうしたらよいのかわからない、さらに上の役職の先生から登校させろと圧力がかかっている…。
考えられる理由は様々ですが、悪意ではなく、先生の指導経験や教育への考え方が、お子さんやあなたと噛み合なっていない「だけ」なのです。
もちろん、「先生に悪意はないのだから、言われたとおり登校するべきだ」というわけではありません。
また、例外として、不登校の原因が先生や学校にある場合もありますし、先生や学校の言うことが100%正しいとも限りません。
しかし、先生側にも事情や思いがあることを知り、最初から学校を「敵」のように考えない方が、お子さんにとってよい結果に結びつきやすくなります。
基本的に、先生は生徒のことを考えているのだという前提で、お子さんの事情を先生や学校側の思いにも配慮しながら伝えていきましょう。
対応①担任だけでなく、学校組織の様々な先生に相談する
担任の先生から何らかの「圧力」があったときは、学校に「組織」としての対応を求めましょう。
学校は組織です。担任の先生は、一人の教師であると同時に組織の一員です。
組織としてお子さんの不登校への対応方法が変われば、その先生も変わります。
担任の先生以外として、次のような人たちに連絡してみましょう。
- 学年主任
- 生徒指導主任
- 副校長
- 校長
- 教育委員会
- 学校問題解決サポートセンター
- お子さんやあなたと仲のよい先生
対応②先生が毎日電話をしてくるなら、「こちらから連絡します」と断る

先生が「今日は登校できそうですか」「今日の調子はどうですか」などと、毎日電話してくることもあります。
迷惑なら、電話をはっきりと断りましょう。
ただ、断りつつも、担任や学校との関係性は良好に保つことが大切です(また、お子さんを思って電話をかけている先生にも、気を使える場合は気を使いましょう)。
例えば「先生もお忙しいでしょうから、1週間に1回くらい(または登校できそうな日はなど)、こちらから連絡します」などの言い方であれば、角も立たないでしょう。
対応③医者やカウンセラーなど、学校外の「権威」を利用する
医者やカウンセラーなど、学校外の「権威」の言葉を利用する方法もあります。
「権威」の判断があれば、学校側も「来るように」とは強く言えなくなるはずです。
例えば、次のようなことが考えられます。
- 病院に行ったところ、今は休養が必要と言われた
- 学校の大切さはわかっているが、今は休むべき時期だと小児科で言われた
- 公認心理師から、少し休んで様子をみようと言われた
ただし、「適当に言う」のではなく、きちんと病院などに行った上で、「本当のこと」を言いましょう。
実際に病院などを頼ることで、お子さん自身にも自覚のなかった「病気」などがわかることもあります。
何かの「病気」があった場合は、診断書を提出することもできるでしょう。
対応④学校外の、勉強する場所やコミュニケーションの場所を利用する

先生が登校を強く促す理由の一つに、お子さんの勉強・進学・社会性への心配もあります。
前述のとおり、学校に行かないことで、勉強やコミュニケーションから離れることは事実です。
しかし、学校以外にも、不登校の子どもが勉強できる塾や家庭教師、コミュニケーションができる場所フリースクールや習い事などなどはたくさんあります(私たちキズキ共育塾もその一つです)。
そうした場所を探し、通い、「きちんと勉強は進めていること」「家庭外の人とも交流があること」を先生につたえましょう。
対応⑤母親だけで対応している場合は、男性(父・祖父・おじなど)が同席する
母親だけで学校に対応していると、先生があまり真剣に聞かない場合もあります。
意識的にせよ無意識にせよ、「女性だから」と軽く見られることがあるのです。
筆者も女性ですので、いろいろな場面で、不必要に無知に見られる、軽く見られるという経験を少なからずしてきました。
筆者がある企業に勤めていたとき、お客さまとトラブルになった際には、男性社員を表に出すという暗黙のルールがありました。
女性社員が対応すると憤っていたお客さまも、男性が対応に出ると、その男性がたとえ新入社員でも「話のわかる人間を出してくれた」と安心し、落ち着いて話を聞くのです。
学校の先生がこの例ほどの差別意識を持っているとは思いたくありませんし、話を聞かない理由が「女性だから」とは限りません。
ですが、いずれにせよ母親だけで学校と話してもうまくいかなかったり、相手が高圧的だなと思ったりしたときには、父親(あなたの夫)、祖父(あなた自身の父親)、その他男性の親戚などの同席を求めたり、対応を任せたりしてみてください。
また、あなたが男性の場合でも、「学校が自分の話を聞かない」と思ったときには、他の家族や親戚の同席を考えてみましょう。
対応⑥他の不登校の親と協力する・不登校親の会で情報を集める

学校が強く登校を促してきて、ご家庭だけでお子さんを守れないと思った場合は、他の(不登校の)子の親御さんと協力するという方法があります。
PTAを通じて依頼できるかもしれませんし、あなたと仲のよい親御さんが先生と話をしやすいならそちらを通じてできるかもしれません。
また、先ほどの第三者・専門家への相談とも関連して、不登校の「親の会」などに参加することも選択肢の1つです。
他の親御さんが、登校を促す先生にどう対応しているのかを聞くことができます。
体験談〜毎日電話がかかってきていたが、診療所と協力した結果、先生の対応が変わった〜
キズキ共育塾のA講師は、中学生のときに不登校になり、先生からのいわゆる「登校圧力」に悩まされました。
ここからは、A講師の一人称で、登校を促す先生に対応した体験談をご紹介します。
私は中学時代に不登校になりました。
そして、私も親も、担任の先生から毎日かかってくる「学校に来い」という電話に悩まされました。
後から話を聞くと、先生としては「自分のクラスから不登校が出てしまった!」という焦りがあったようです。
そして、当時は不登校という言葉や学校としての対応法が今よりも広まっていませんでした。
これも後からわかったのですが、私が不登校になったことで、担任の先生と部活の顧問の間でも揉めていたということです。
私の不登校について、先生も原因や対応がわからず、「学校に来い」と強く言うしかなかったのでしょう。
さて、毎日の電話に悩んでいた私と親でしたが、通っていた診療所が、先生もよく知っているところだったとわかったことで、事態が変わりました。
そこの診断書を提出したことで、先生が私の状況に理解を示すようになったのです。
毎日かかってきていた電話もなくなりました。
そして、一方的に「学校に来い」と言うのではなく、親身に相談に乗ってくれるようになりました。
その結果、他の先生に掛け合ってくれたり、課題を提出することで「出席」の扱いにしてくれたり、保健室でテストを受けられるようにしたりと、いろいろ便宜を図ってくれました。
公立中学校ですので、不登校のままでも卒業自体はできたでしょう。
ですが、こうした対応をしてもらったことで、勉強も高校進学も、全く不登校のままよりもスムーズに進んだと思います。
A講師のように、先生から強く登校するように言われている場合は、学校以外の人を通じて、先生に状況を説明する方法が効果を生むことがあります。
ぜひ積極的に、いろんな人や団体を頼ってください。
参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校ジャーナリスト・石井しこう、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。
このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。
このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。
公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら
- 【オリジナル書籍プレゼント】学校外で友だちができるBranchコミュニティ(Branch公式LINEが開きます)
私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。
まとめ:中学校は不登校でも卒業できます

中学校は不登校でも卒業はできます。
卒業式も出席したくないなら出席しなくても大丈夫です。
そして、中学校で不登校でも、卒業後のお子さんにはたくさんの進路・可能性が広がっています。
お子さんの将来のためにも、ぜひ、学校や不登校の専門家などを積極的に頼ってみてください。
このコラムが、あなたとお子さんのお役に立ったなら幸いです。
さて、私たちキズキ共育塾は、お悩みを抱える方々のための個別指導塾です。
生徒さんには、中学を不登校で卒業した方も大勢いらっしゃいます。
無料相談も承っておりますので、ご相談いただければ、「あなたのお子さん」のための具体的なお話ができると思います。
キズキ共育塾の概要をご覧の上、少しでも気になるようでしたらお気軽にご相談ください(親御さんだけでのご相談も承っていますので、あなただけでは相談しづらい…と思う場合は、親御さんにも声をかけてみてくださいね)。
Q&A よくある質問
中学校不登校の子どもに対して親ができる対応を教えてください。
中学校から強く登校を促されるときの対応法はありますか?
以下が考えられます。
- 担任だけでなく、学校組織の様々な先生に相談する
- 先生が毎日電話をしてくるなら、「こちらから連絡します」と断る
- 医者やカウンセラーなど、学校外の「権威」を利用する
- 学校外の、勉強する場所やコミュニケーションの場所を利用する
- 母親だけで対応している場合は、男性(父・祖父・おじなど)が同席する
- 他の不登校の親と協力する・不登校親の会で情報を集める
詳細については、こちらで解説しています。