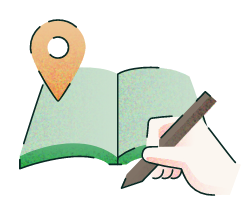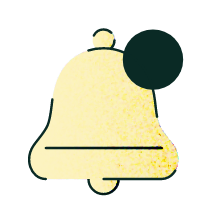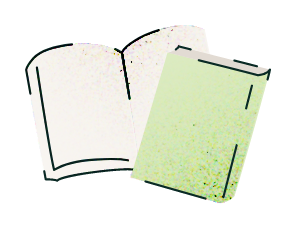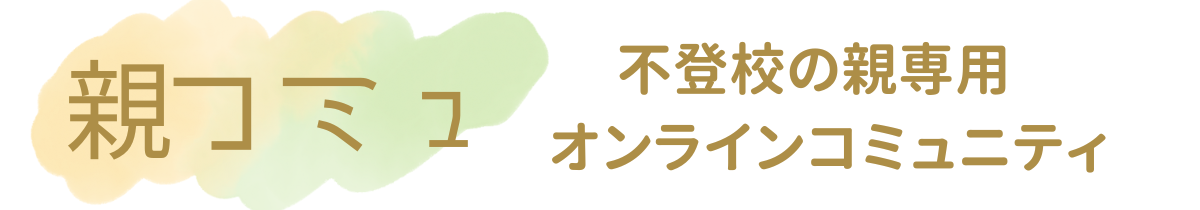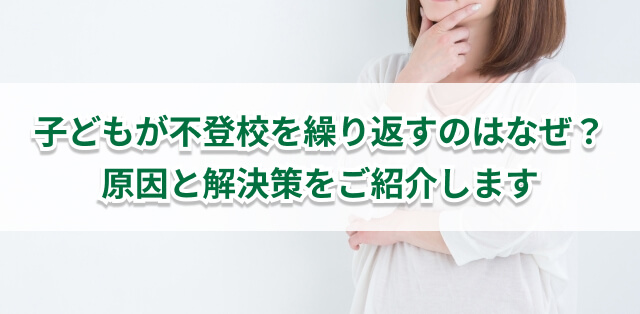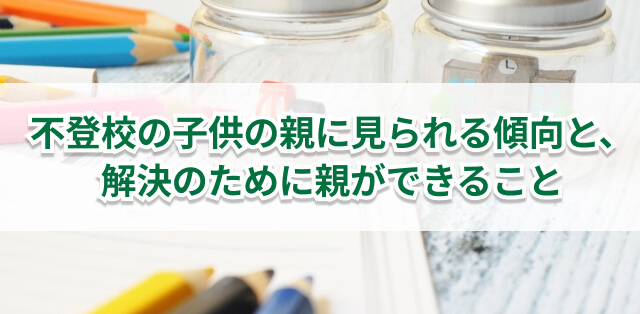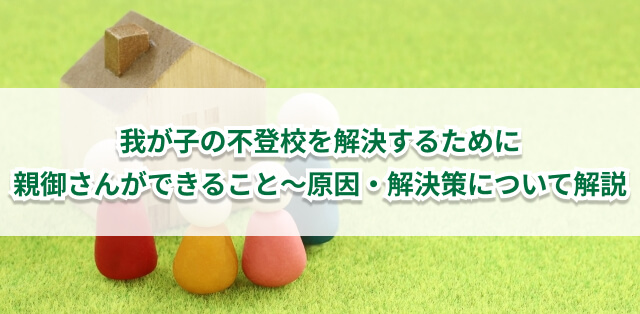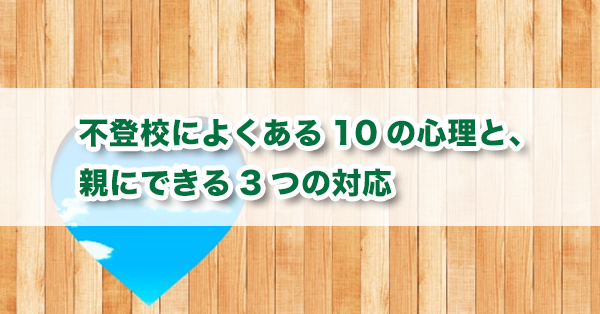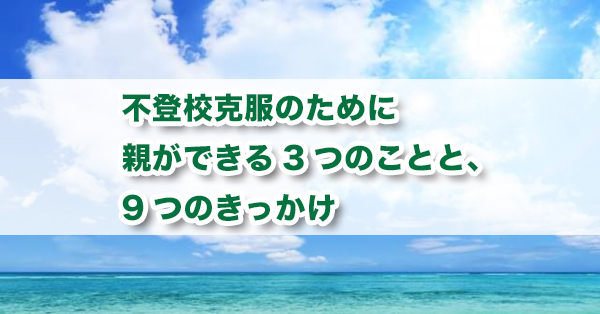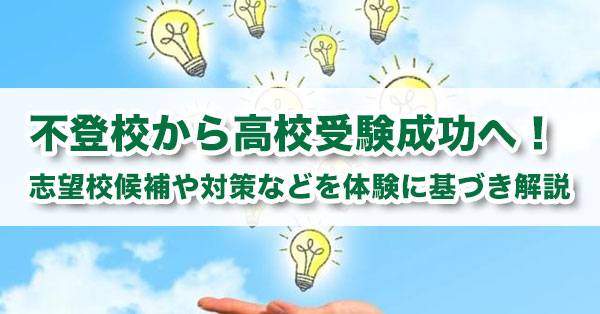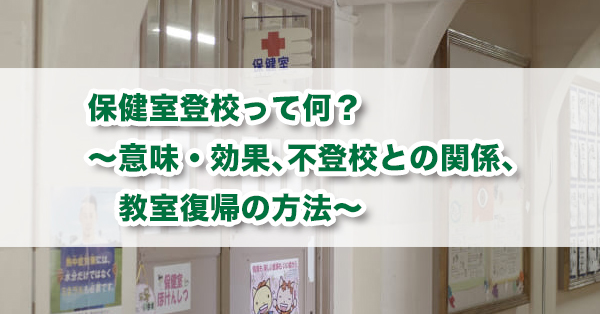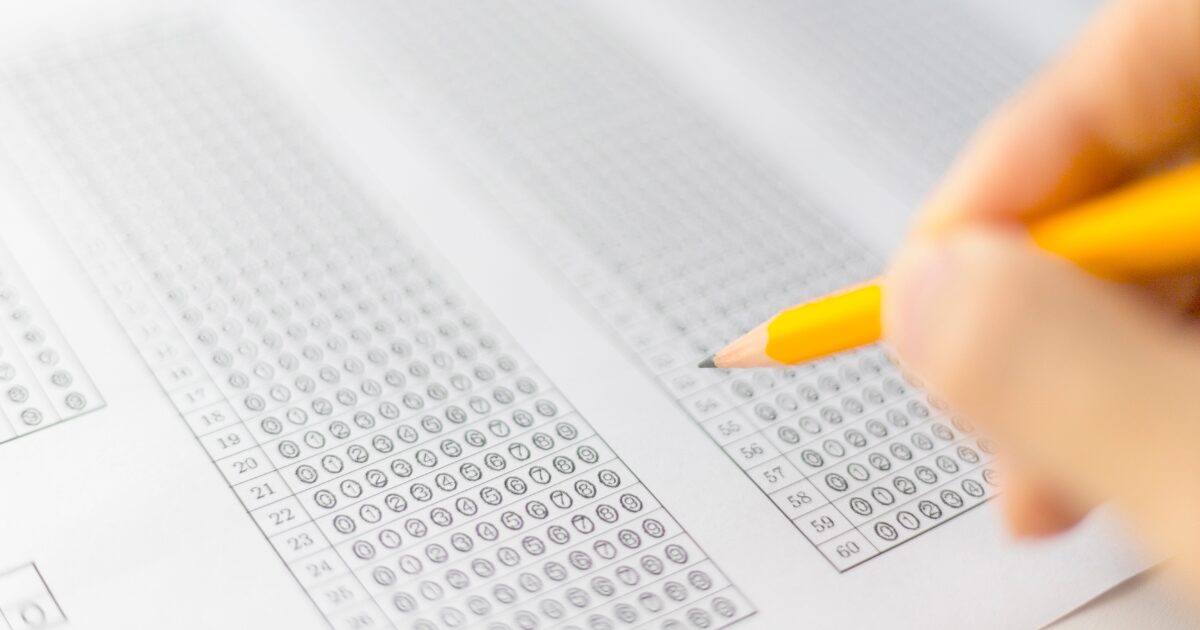子どもの不登校にお悩みの親御さんへ 解決のための対応を解説
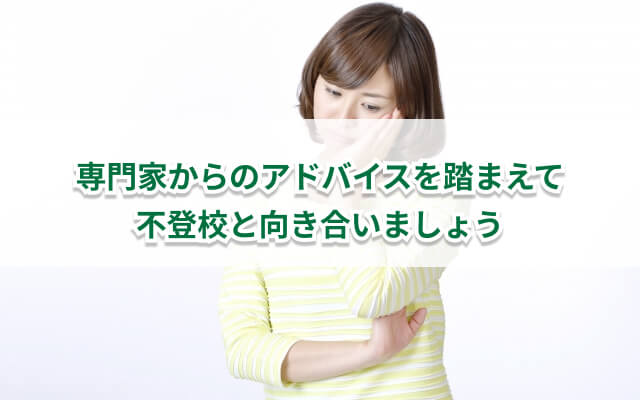
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたは、お子さんの不登校について、お悩みではありませんか?
私たちキズキ共育塾はこれまでに、不登校の悩みを持つ生徒さんの支援だけでなく、その親御さんからのご相談もたくさん受けてきました。
相談に訪れた親御さんの多くは、「どうしてわが子が不登校になったのか」と悩み、「自分に何ができるかわからない」「子どもの将来が心配でならない」と大きな不安を抱えています。
このコラムでは、お子さんの不登校について悩みを持つ親御さんが、解決のためにするべきことについて解説します。
このコラムが、不登校でお悩みのお子さんと親御さんにとって、次の一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの
アドバイス
不登校の子への対応は「原因追及をしすぎない」「家庭を子どもの居場所にする」など、これまで考えられてきた子育ての常識とは異なるものです。
親が知るべきこと、気持ちを入れかえるべきことは多いのですが、行きしぶりや不登校が長引いてからも、対応方針は変わりません。一度、原理原則を覚えてしまえば、心の傷が癒えるまでずっと使えるものです。ぜひご参照ください。
私たちキズキ共育塾は、不登校状態にある子どものための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
悩み①わが子が不登校になったのはなぜ?

子どもが不登校になると、「どうしてこの子が不登校になったのだろう?」と、親御さんは原因を追究しようとします。
「育て方が悪かったのでは…?」「親の自分に原因があるのかも…」と、ご自身を責める親御さんもたくさんいらっしゃいます。
ですが、虐待など一部の特別な理由を除いて、親御さんの育て方が不登校の直接の原因となることはありません。
また、「子どもの性格に原因があるのかも…」「不登校は子どもの甘えによるものでは…?」と考える親御さんもいらっしゃいますが、それらも直接的な原因ではありません。
実は、お子さん本人も、不登校の原因がわからないケースが多いのです。
不登校の子どもは、「学校に行きたい」「みんなと一緒がいい」と心では思っていても、「なぜか学校に行けない」「どうしても気持ちが進まない」といったように、学校に行けないことにジレンマを抱えています。
そして、「なぜ自分だけが学校に行けないのか」と、その原因が自分でもわからないことに悩んでいます。
このように、本人でも把握できない「原因」を追究することは、多大な時間と労力がかかります。
さらには、この原因を追求しても、不登校の悩みの解決にはつながらないことが多いのです。

例えば、先生の言葉に傷ついて不登校になったとしても場合、その先生が謝罪すれば必ず登校を再開できるかと言えばそうでもありません。
そもそものトラウマが取り除かれていなければ、登校を再開できないこともあるでしょう。
逆に、先生の謝罪がないままでも、子どもの心のケアをしっかりと行っていれば、転校して環境を変えるだけで、あっさり登校できるようになることもある、ということです。
以下の2つが、不登校の悩み解決のための重要なポイントになります。
- 不登校の原因を追究しすぎない
- 原因を知る(知ろうとする)ことは、あくまで現状把握のためだけに留めておく
不登校の原因やきっかけについて詳しく知りたい方は、以下のコラムもぜひご覧ください。
一方で、不登校には、見逃してはならない原因も一部あります。
- うつや統合失調症など精神疾患を発症している
- 発達障害が関係している
- 学校でいじめられている
- 家庭内に子どものストレスとなる問題がある(両親の不和、離婚、経済的問題など)
- 虐待
これらに該当する場合は、原因への対応が必要です。
そして、これらの解決には、医師や専門家を含む第三者への相談が必要不可欠です。
すぐに、当該の分野の専門家がいる支援機関を頼りつつ、問題の解決を図りましょう。
「虐待」と書くとドキッとする方も多いと思います。
お子さんに対して怒鳴ったことがない親などいませんし、子どもを家で休ませていることも「虐待にあたらないか」と心配する方もいるでしょう。
学校へ行かせないことは虐待ではありませんが、もし心配でしたら、厚生労働省の「児童虐待防止対策」をご確認ください。
悩み②不登校の子どもに対して親は何をすべき?
ここまでは「不登校の原因を追究しすぎない」とお伝えしました。
それでは、親は子どものために何をすればよいのでしょうか。
最も大切なのは、お子さんの「これから」に目を向けることです。
それを踏まえた上で、ここからは不登校に悩む子どものために、親ができる8つの対応を解説します。
対応①子どもの気持ちを受け止める

「学校に行きたくない」
お子さんからこういった言葉があれば、まずはその気持ちを落ち着いて受け止めましょう。
無理に子どもを学校に行かせようとしたり、「何か嫌なことがあったの?」としきりに理由を聞き出そうとしたりすることは、不登校に悩む子どもにとっては逆効果です。
登校を強要したり、悩みを聞き出そうとしたりすると、お子さんは親を脅威とみなし、敬遠するようになることもあります。
親が子どもの気持ちを受け止めて、「子どもの味方」になることが大切なのです。
対応②家庭を子どもの居場所にする
子どもの気持ちを受け止めると同時に、家庭を子どもにとって居心地のよい場所にすることも大切です。
子どもに限らず、人は「安心できる場所」があるからこそ、外の世界に出ていくことができます。
何があっても受け入れてくれる「安心できる場所」があれば、お子さんは外の世界に出て、勉強、部活、習いごとなどさまざまなことに向かって、積極的にチャレンジできるのです。
家庭をお子さんにとって居心地のよい「安心できる場所」にできるように努めましょう。
対応③不登校を「子どもにとって必要な期間」と考える

子どもが不登校だと、「一刻も早く学校に復帰させないと…!」と焦りを感じる親御さんもいます。
しかし、不登校は急に改善するものではありませんし、ある日突然学校に通えるようになるわけでもありません。
そして、学校に復帰するにも、保健室登校や別室登校から始めるなど、少しずつステップを踏む必要がある場合も多いのです。
不登校は、子どもが心の中で自身と向き合い、成長するために必要なことだと考えて、気長に見守りましょう。
安心できる家庭の中で、子どもは自身と向き合いながら、ゆっくりと回復していきます。
親が「この子にとって必要な時期なのだ」と考え、決して焦らないよう心掛けてください。
対応④学校や担任の先生とこまめに連絡を取る

お子さんが学校を休んでいる間も、学校や担任の先生とこまめに連絡を取りましょう。
親が先生とこまめに連絡を取り、学校を休んでいる間の宿題、授業の進捗、実施するテストの情報などを、随時確認しておくことも大切です。
もしお子さんに余力があれば、不登校期間でも勉強を進めておくことをオススメします。
不登校期間の勉強方法、勉強再開のタイミングについては、以下のコラムにまとめています。併せてお読みください。
また、お子さんが不登校の間は、勉強のこと以外にも、以下のような相談を学校(担任の先生)にすることが多くなります。
- 保健室登校や補習授業など、学校で対応してもらえないか
- 内申書について配慮を得ることができないか
こういった相談をする時のためにも、日頃から学校や担任の先生と良好な関係を築いておきましょう。
必要以上にへりくだる必要はありませんが、「学校が悪い!」と決めつけるような対応はせず、丁寧に接しましょう(残念ながら、結果として学校が悪いケースもあるとは思いますが)。
学校や担任の先生との関係を良好に保つことで、お子さんの不登校の悩みについて、学校側と連携しやすくなります。
対応⑤不登校についての情報を集めて選択肢を示す

お子さんがこれからのことに目を向けられるように、不登校に関する情報を集めて、これから先の選択肢をお子さんに示しましょう。
不登校の子どもは、「これからどうすればいいの…」「受験や進学、就職はできるの…?」と、先が見えないことについて悩んでいます。
親御さんが不登校についての情報を集めて、お子さんにこの先の選択肢を示すことで、お子さんの安心感に繋がります。
例えば、不登校からの復帰とは、必ずしも今通っている学校に戻ることだけを指すわけではありません。
「学校への出席日数として認められる可能性があるフリースクールに通う」「不登校の支援機関に通うことで学校に通わずに勉強を進める」など、復帰に向けての選択肢はたくさんあるのです。
また、学校に復帰をするとしても、保健室登校や別室登校のように、徐々に学校に慣れていく方法があることをお子さんに勧めることもできます。
高校生のお子さんであれば、通学しなくてもよい通信制高校へ編入することを提案してみてもよいかもしれません。
もちろん、「どの選択肢を示すか」については、お子さんが不登校になった経緯、現在の状況など、多くのことを踏まえて考える必要があります。
インターネットからも情報を集めることはできます。しかし、確実なのは「専門家を含む第三者に相談する」ことです(詳細は後述します)。
インターネット上にはたくさんの情報がありますが、その情報がお子さんにとって必ずしも適切であるとは限らないからです。
ですので、お子さんにとって最適な選択肢を示すために、不登校についての知見を持った専門家にアドバイスを求めましょう。
対応⑥親は自分の生活を充実させる

親御さんは自分自身の生活を充実させましょう。
中には、「子どもが不登校で悩んでいるのに、自分だけが充実した生活を送るなんて…」と思われる親御さんもいらっしゃるかもしれません。
しかし、親御さんが自分の生活を充実させることは、不登校の悩みの解決につながるのです。
親が自分の生活を充実させることには、以下のような効果が期待できます。
効果①親が子どもにかかりきりになることを防ぐ
親が子どもにかかりきりになると、それだけで精一杯になり、次第に不安が膨らんでいきます。
膨らんだ親の不安や心配は、「叱責」「悲観」「過干渉」「感情的になる」などの形で表れて、子どもの心を圧迫することもあるのです。
そのため、親は子ども以外のことにも目を向けて、心に余裕を持ってお子さんと接しましょう。
効果②親が大人のロールモデルとなることができる
親が充実した生活を送っていれば、一人の社会人として充実した姿を子どもに見せられます。
これによって、望ましい大人のロールモデルを子どもに与えられるのです。
「外の世界は楽しいよ」「大人になるってよいものだよ」と背中で見せることで、子どもの不登校を克服するための気力にもつながります。
対応⑦家族全員で不登校に向き合う

キズキ共育塾へのご相談の中には、「母親ばかりが不登校の子どもと向き合っている」「不登校の解決に向けて、父親がほとんど関与していない」などという状況も、一部で見受けられます。
また、祖父母が孫の不登校に理解を示さないといった悩みもよく聞きます。
夫婦の役割分担については、各家庭でそれぞれの考えや方針があるのかもしれません。
「不登校」という言葉がなかった世代の祖父母が、「孫が学校に行かないことを受け入れられない」という気持ちもわかります。
ですが、不登校の悩みを解決するには、家族全員で向き合うことが必要です。
大掛かりな話に見えるかもしれません。ですが、まずは「不登校は悪いことではない」「不登校は、どんな子どもであっても、どんな育て方をしていても、誰でもなりうる」という認識を持つことが大切です。
家族全員の不登校に対する認識が違っていて、夫婦間などが険悪になると、お子さんが家庭を「居心地の悪い場所」と感じるようになります。
ただし、次項で詳しく解説しますが、親御さんやご家族だけで抱え込まず、専門家を含む第三者へ積極的に相談することも大切です。。
対応⑧専門家に相談する

不登校の悩みを家庭内だけで抱える必要はありません。
不登校の解決には、専門家への相談が不可欠なのです。
不登校の解決策はお子さん一人ひとりによって違っており、あなたのお子さんにとって最適な解決策を見出すためには、専門家の判断やアドバイスが必要になります。
ご紹介してきた①〜⑦の方法についても、お子さん、ご家庭、学校などによって、「具体的にどうするか」は違ってくるでしょう。
そうしたことも、専門家を頼るときっと具体的なアドバイスがもらえます。
ここでの専門家とは、学校のスクールカウンセラーや市町村の相談窓口、民間の不登校支援団体など、不登校についての知見を持った人、または団体のことです。
専門家とお子さんの相性を見ながら、信頼できる専門家が見つかるまで、さまざまな相談機関に足を運びましょう。
詳しい相談先は、後ほど詳しくご紹介します。
「学校に行くべきだ」という考えを捨てる~学校に行かない選択肢〜

不登校に悩む親子を苦しめる要因の一つに、「学校に行かなくてはいけない」という意識があります。
キズキ共育塾へご相談いただいた親御さんの中には、以下のように考えている方もいました。
- みんなが通っているのだから、学校には行くべきだ
- みんなと一緒じゃなきゃ恥ずかしい
- 子どもが学校に行かなければ、将来困るのではないか
不登校になると、どうしても「学校に復帰すること」ばかりが目標になりがちです。
しかし、学校は絶対に行かなくてはならない場所ではありません。
お子さんの性格によっては、どうしても学校や集団生活に馴染めない場合もあります。
それは「悪い」ことではなく、一部の独創的で個性的な子どもには、集団に馴染めないということも起こりうるそうです。(参考:河合隼雄『子どもと悪』)
あなたのお子さんが学校に行けないのも、お子さんの際立った個性が学校という集団に馴染めないからなのかもしれません。
また、小中学校は義務教育ですが、必ずしも通学する必要はありません。
義務教育の「義務」とは、子どもが学校に行く「義務」ではなく、親御さんが子どもに教育を受けさせる「義務」のことです。
また、義務教育の間であれば、出席できない日が多かったとしても卒業できます。
高校も「絶対に行かなければならない」とは限りません。
一例ではありますが、現在通っている高校に行かない、または行けなかったとしても、大学受験・進学については、以下のようなルートがあります。
- 通信制高校(通学せず、レポートや家庭学習で卒業できる高校)に進学、編入する
- 高卒認定試験を受けて、そこから大学受験、専門学校受験を目指す
- 就職して働きながら、高卒認定試験を受ける
キズキ共育塾にも、何らかの事情で学校に行かずに、高卒認定試験や大学受験を目指し、無事に進学した生徒さんが多くいらっしゃいます。
お子さんがどうしても学校に馴染めない場合は、「学校に行かない選択肢」もぜひ考えてみてください。
不登校の悩みを相談できる4つの場所
最後に、不登校の悩みを相談できる場所をご紹介します。
不登校の相談先は、全国でさまざまな地域に存在しているのです。
お住まいの地域で一番利用しやすい相談先を見つけてください。
過疎地などで相談先が近くにない場合でも、電話やメールなどで相談できるところも多いです。ぜひ積極的に活用しましょう。
①自治体の相談窓口
主な自治体の相談窓口は、以下のようなものがあります。
- 児童相談所、児童相談センター
- ひきこもり地域支援センター
- 発達障害支援センター
- 教育センター(高校相当年齢) 各自治体のウェブサイトに詳細が記載されています。 「教育センター ○○(市区町村名)」で検索してください。
どこに連絡するべきかわからない場合は、お住いの市町村のウェブサイトから、総合窓口、または教育関連のページを開き、問い合わせてみましょう。
②不登校の支援団体

主な支援団体としては、民間の支援団体、NPO、フリースクール、キズキ共育塾のような不登校支援を行っている学習塾などが挙げられます。
心理面のサポートを重視しているところ、学習面のサポートを重視しているところなど、支援団体によって特徴は違っています。
また、フリースクールなど、学外の場所への出席が、学校の出席日数として認められることもあるのです。
これらの支援団体は、不登校の支援をしてきた経験とノウハウを多く持っており、無料で相談を受け付けているところも多くあります。
お住まいの市区町村名などと合わせてインターネット検索をすると候補が見つかるはずです(例:「渋谷区 不登校 支援団体」「東京都 不登校 塾」「台東区 フリースクール」など)。
気になる支援団体があれば、相談にだけでも足を運んでみてください。
また、以下のコラムでは、支援団体の探し方を解説しています。ぜひこちらも併せてお読みください。
③不登校の「親の会」
親の会は、不登校に関する悩みを持つ親御さんが集まって、悩みを相談したり、有益な情報交換をしたりすることができる場です(「親の会」というひとつの団体ではありません)。
同じ悩みを持つ人と話すことで、自分の不安やストレスをわかってもらえるなど、心理的負担の軽減にもなるでしょう。
全国の親の会の情報をまとめたウェブサイトもあります。ぜひ、お近くで開催されている親の会がないか調べてみてください。
④お子さんが在籍している学校

まずは、お子さんが在籍している学校に相談してみましょう。
学校はお子さんの状態を常に把握しているので、相談もスムーズに進むはずです。
担任の先生はもちろんですが、学校にはよってはスクールカウンセラーが在籍しています。
スクールカウンセラーは、学校に通う子どもたちの心のケアを行う専門家です。
子どもや親御さんのさまざまな相談に乗ったり、アドバイスをしたり、先生と連携して問題解決のために働きかけたりします。
担任の先生やスクールカウンセラーから、地域の他の専門家を紹介してもらえることもあります。そちらを参考いただくのもオススメです。
「不登校中の悩み」について、キズキ共育塾の講師の体験談
この章では、「不登校中の悩み」に関連する、キズキ共育塾の講師たちの体験談を紹介します。参考としてご覧ください(講師名は仮名の場合もあります)。
キズキ共育塾には、自身にも不登校経験のある講師がたくさんいます。また、無料相談では、さまざまな事例をご紹介可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
S.T講師の体験談
小学校3年生から中学校3年生まで不登校でした。自分の両親は過干渉でも放任でもなく、ほどよい距離で見守っていてくれたと感じています。
不登校だった期間は通信教材を使って勉強をしており、わからないところは父が教えてくれました。通信教材には提出が必要な定期テストがあり、その結果を見て足りなかった部分の分析や対策を一緒に考えました。テストの結果を聞くことは子どものプレッシャーになることもあると思います。ですが私は、父が勉強について気にかけてくれ、「やれば伸びる」と信じ続けてくれたことが、今の自分の基盤となる自信や肯定感につながっていると感じています。当時、自習を継続するモチベーションにもなっていたと思います。
一方母とは、勉強について話すことはなく、点数を聞かれたこともありません。両親から勉強の進捗を把握されるよりも、父とだけ話すという分担があったのも私にとってはよかったです。母とは日常的に一緒に出掛けたり、体験型の学習の機会をもらったりしていました。
振り返ってみると、「(不登校の)子どもにとって、過度な期待は負担になるが、なんの期待も持たれずに『好きにしていいよ』と言われることも苦しい状況なのではないか」と思います。子どものよいところや得意なところを親が積極的に教えることが、子どもののびやかさにつながるのではないでしょうか。(ただもちろん、お子さんへの対応は親御さんだけで行う必要はありません。サポート団体などをぜひ利用してみてください)
松本健一講師の体験談
私は、高校2年次に不登校になりました。
当時の悩みは、勉強の遅れや進級の不安、学校の先生やクラスメイトとの人間関係などさまざまにありました。中でも一番大きな悩みは、家族との関係でした。一日のほとんどを家で過ごしているため、必然的に家族との衝突も多くなります。家族に対する申し訳なさもあり、家族が不登校の自分のことをどう思っているのか気になって不安でした。
そんな中、母は私に家事の手伝いを頼むようになりました。最初は「めんどくささ」を感じていましたが、次第に「自分は家族に必要にされているんだ」「家にいてもいいんだ」と感じるようになりました。また、父は私に「自分の好きなようにすればいい」とよく声をかけてくれました。一見、冷たい言葉のように聞こえるかもしれません。ですが私にとって、この言葉は「私の学校に行かないという選択」を肯定してもらっていると感じられました。
このような両親のちょっとしたお願いや言葉がけで、私は家を安心できる居場所として感じることができていました。
S.Y講師の体験談
こちらを読んでくださっている方々は、出口のない暗闇にいるような心持ちでお過ごしになっていることと思います。可愛いお子さんが、どうしてこうなってしまったのだろう。ご自分の育て方を責めることもあるかもしれません。ご自分の愛情を疑うこともあるかもしれません。自分を苦しめるご家族やお子さんを一瞬憎く思ってしまい、そのことがまた自分を苦しめる。そんな日もあると思います。
私は、不登校を経験し、その後親として二人の子どもを育て、いまは講師として不登校の生徒さんに関わらせていただく立場にいます。多くの場合、子どもは自分の親が自分のために苦しんでいることを知っているように思います。私自身は「こんな子でごめんなさい」と思っていました。当時は親ガチャというような言葉はありませんでしたが、「親は不良品をつかまされた思いでいるだろう」と思っていました。
そんな生活の中でホッとできる時間もありました。専業主婦だった母がスイミング教室に通い始め、週2回、家を空けるようになったのです。母はカナヅチだったので全く意外な出来事でした。教室の後はスイミングでできたお友達とランチをして帰ることもあり、そんな日、私は部屋から出て、リビングやキッチンでのびのびと過ごしました。自分でホットケーキをつくってみたこともありました。私がキッチンで何かつくって食べているのを母が気づき、「お米を研いておいてね」「じゃがいもをむいておいてね」などと言われることもありました。そんなわけで母がいない間は、自分の部屋のほかにキッチンに居場所ができるようになりました。
母は母で、できないと思っていた水泳が少しずつ上達し、新しいお友達ができ、それがとても楽しいようでした。今日はこんなことをした、何を食べた、美味しかったと自分のことを明るく語るようになりました。
今ならわかります。母には母の戦いがあり、自分を保っていくために、私から離れる時間が必要だったのだと思います。母自らの決断だったのか誰かからのアドバイスだったのかはわかりませんが、母が外に出たことによって、私はずいぶん楽になりました。少なくとも母が楽しんでいるその間は、「ごめんなさい」と思う義務から解放されたように感じていました。
現在関わっている生徒さんからご家族のお話を伺うことがあります。多くの生徒さんは、現在の関係性に関わらず、お父さまお母さまが大好きです。照れながらも「小さい頃こんなことがあった」と思い出話をされるときもありますし、日常のちょっとした出来事をとても嬉しそうに話されることもあります。キズキの生徒さんの多くが不登校(経験者)です。その彼らが将来を見据えて勉強されている背景には、保護者の皆さまの辛抱強い愛情があると感じずにはいられません。
とりとめのない話となりました。最後に一つ。その暗闇に、私たちは一人ではないと思うのです。暗すぎるがゆえに見えませんが、必ず助けや解決策があると思います。キズキ共育塾も、その一部となれることを願っています。
参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校ジャーナリスト・石井しこう、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。
このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。
このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。
公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら
- 【オリジナル書籍プレゼント】学校外で友だちができるBranchコミュニティ(Branch公式LINEが開きます)
私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。
まとめ:親や家族だけで悩まず、専門家に相談しましょう

不登校の悩みを解決するために、親御さんが何をするべきかを中心にお話をしてきました。
不登校の原因は、本人にもわからないことが多く、原因を追究しすぎることは不登校の悩み解決にはつながらないことが多いです。
また、不登校の悩みは、家庭内のみで抱えることなく、スクールカウンセラーなど専門家に相談することが大切になります。
お子さんやご家族と相性のよい専門家を見つけ、そのアドバイスを受け入れつつ、家族全員で不登校に向き合いましょう。
キズキ共育塾では、たくさんの不登校の生徒さんが、学校復帰や受験に向けて学んでいます。
コミュニケーションを大切にした一対一の授業が、学校復帰に役立ったという声もいただいています。
教室から遠くにお住まいの方や外出困難な方には、スカイプでの授業も行っています。
不登校でお悩みでしたら、ぜひ一度、相談に来てください。
保護者様だけの相談も可能です。
お電話・メールでのご相談も受け付けています。
お子さんの不登校の悩みが解決しますようにお祈りしています。
/Q&Aよくある質問
不登校の子どものために親ができることはありますか?
一般論として、以下のような対応が考えられます。(1)子どもの気持ちを受け止める、(2)家庭を子どもの居場所にする、(3)不登校を「子どもにとって必要な期間」と考える、(4)学校や担任の先生とこまめに連絡を取る、(5)不登校についての情報を集めて選択肢を示す、(6)親は自分の生活を充実させる、(7)家族全員で不登校に向き合う、(8)専門家に相談する。詳細はこちらをご覧ください。
子どもの不登校を相談できるところはありますか?
たくさんありますので、安心してください。大枠として、以下のような相談先があります。(1)お子さんが在籍している学校、(2)自治体の相談窓口、(3)不登校の親の会、(4)その他、不登校の支援団体。詳細はこちらをご覧ください。