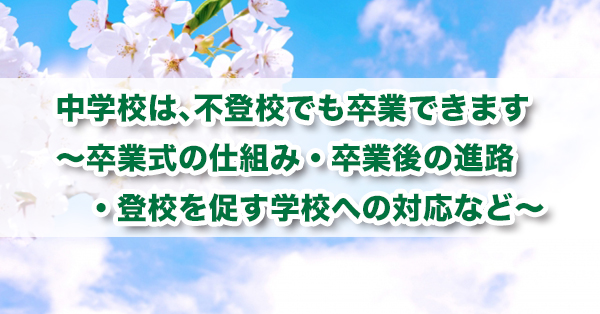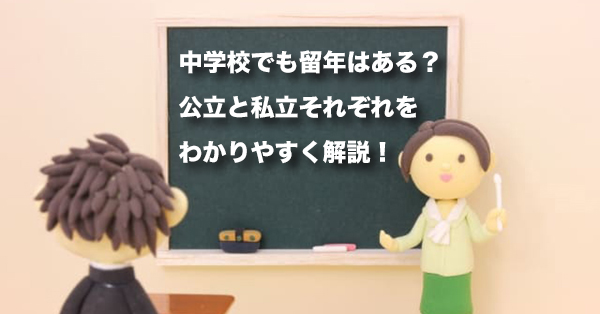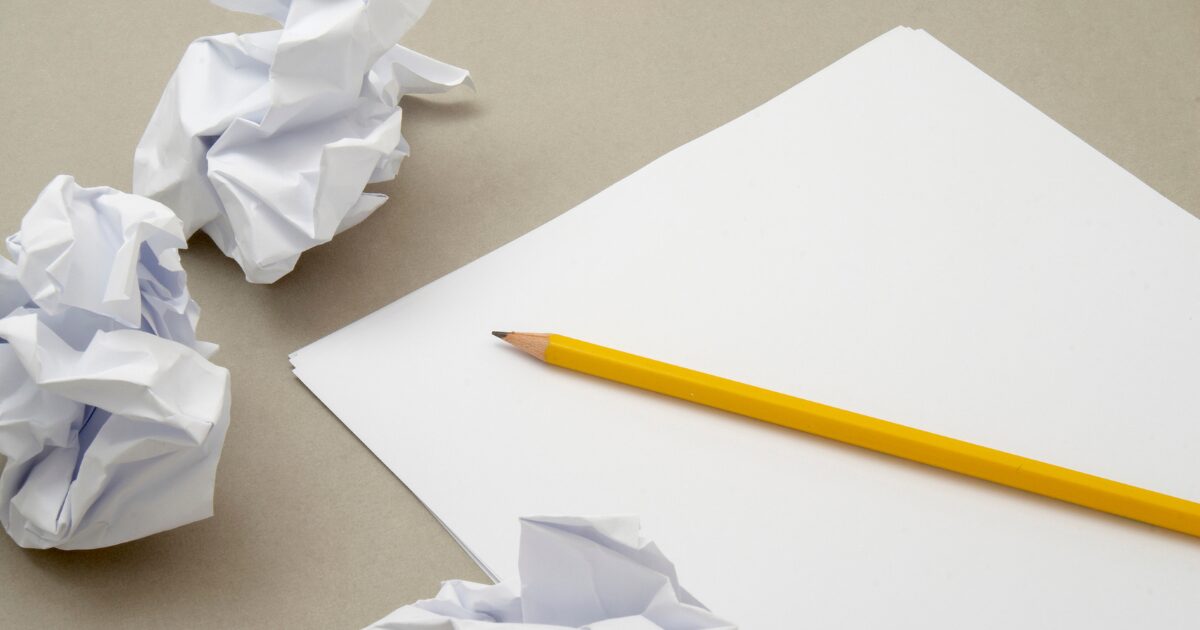中学校でも留年はある? 公立と私立それぞれを解説
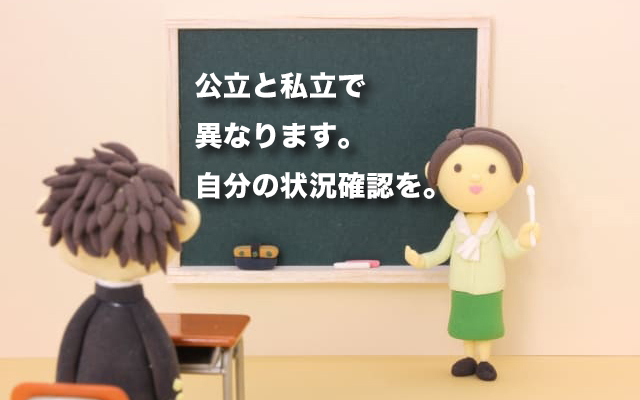
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
不登校状態にある中学生の人の中には、欠席が多い自分は、中学校で留年するのではないか?と心配している人がいるのではないでしょうか?
中学校に留年制度があるのかどうか、やはり気になりますよね。
このコラムでは、公立と私立それぞれ種類別に、中学校での留年について解説します。
それぞれ事例を紹介します。不登校で不安になっている方はぜひ読んでみてください。
共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの
アドバイス
公立の小学校・中学校は、不登校でも卒業ができます
このコラムでも書かれているとおり、小学校や公立中学校では、原則として留年はありません。
もっといえば、一日も学校へ行かなくても大丈夫です。
出席日数が少なくても、小6・中3の3月で卒業したいと思えば、校長先生の判断で卒業ができます。
「不登校のままでは、退学や留年になるのではないか?」と不安になるかもしれません。
ですが、国や制度は、基本的にあなたの味方です。
そのことを、ぜひ知っておいてください。
私たちキズキ共育塾は、学校が苦手な中学生のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
留年(原級留置)とは?

留年の正式名称は、原級留置(げんきゅうりゅうち)と言います。
普段使っている留年や落第という言葉は、学校制度上ではこの原級留置という言葉に置き換えられます。
学校には、学生に出席日数が少ないなど何らかの事情がある場合、その学生を原級留置にするかどうかを先生たちが検討する仕組みがあります。
この原級留置にするかどうかを決める会議のことを、進級判定会議や卒業判定会議などと呼びます。会議の名前は学校により多少異なりますが、判定会議で留年を決めるという流れは中学校だけでなく、小学校や高校でも同じです。
この判定会議で、対象となる学生が進級・卒業していいかどうかということが議論されるわけですね。
判定会議は、通常学年末に行われます。
しかし、現在の公立中学校の教育は年齢主義がベースになっているため、基本的には留年になることはありません。例外は、学校から「留年しますか」と聞かれて「はい」と答えたときです。留年を強制する仕組みはありません。
公立中学校の留年〜基本的には留年はない〜

まず、公立の中学校では基本的に留年はありません。
公立中学校で留年がほぼない理由は、日本が年齢主義という考え方をもとにして義務教育を行っているからです。
年齢主義とは、学生の年齢と学級をそろえようという考え方のことです。
この考え方から日本では、出席日数が少なかったり成績が悪かったりしても、基本的には進級・卒業できることが多いです。飛び級がないのも同じ理由によります。
「不登校だと、ずっと中学校を卒業できないのではないか…」という不安に悩む必要はありません。
小学校・中学校の義務教育にて年齢主義を採用している場合、同じ学年に同じ年齢の生徒が集まることになります。
同じ年齢とは、同じ学年の生徒同士の生年月日に1年以上の差がないということです。
そのため、学力や出席日数に大きな差があっても、同い年の人たちが同じ学年にいることになり、基本的に留年がない仕組みになっているわけですね。
年齢主義を採用していない国では、公立の中学校でも留年する場合があります。
さらに日本ではこの年齢主義が根強いため、生徒や親が留年を希望したとしても学校や教育委員会が却下するというケースが見られます。
公立中学校で例外的に留年することはある
公立中学校でも、例外として留年することはあります。不登校や入院で欠席日数が多い場合などに、学校(校長)から、「留年しますか?」と確認を受けることがあるのです。
この確認を受け入れると、留年となります。
ただし、中学校関係者に話を聞く限り、実際に留年を選ぶ人はとても少ないようです。
留年を強制する仕組みは、事実上ないと言っていいでしょう。
逆に、生徒や家族の側から、出席日数が少なくてきちんと勉強できていないために、留年したいと相談する場合も考えられます。
こちらも、相談したら必ず留年できるというわけではなく、むしろ留年となることは現実的に極めて少ないようです。後ほど、事例を紹介します。
留年を認めない事例:神戸市立小学校強制進級事件
留年拒否の有名な例として、1993年の裁判「神戸市立小学校強制進級事件」を挙げることができます。これは小学校のケースですが、義務教育という意味では中学校と同じです。
簡単にいうと、「いじめなどを理由に長期欠席していた児童と両親が原級留置(留年)を希望したけれど、学校側が強制的に進級させたため、それを不満として訴えた」という出来事です。
この事件でもやはり問題の中心は年齢主義でしたが、裁判所は進級は正当という判決をくだしています。
正当である理由としては、「留年を認めた場合、年齢によって精神年齢や運動能力、体格などに差が出てくるため、社会生活や日常生活での違和感に耐える努力が必要になり、留年を認めない場合よりも状況が悪化するため」というものでした。
ひきこもりや不登校でも、年齢主義によって留年にはならない

年齢主義によって、ひきこもりや不登校で欠席日数が多い場合でも、公立中学では留年を強制されることはありません。
出席日数が足りなかったとしても、進級は年齢に合わせて行われます。
ひきこもりや不登校で出席していなくても、基本的には進級・卒業するということです。
不登校・ひきこもりのまま中学校を卒業した人はたくさんいます。
興味のある人は、「中学 不登校 卒業」といったワードでインターネットを検索してみてください。
不登校のままでも中学校を卒業できると安心できる一方、もしかしたら中学校で勉強できていないから将来が不安と思うかもしれませんね。
ですが、学び直しを支援する団体や、出席日数が少なくても進学できる高校はたくさんありますので、必要以上に不安にならなくても大丈夫です。
課程主義の国は、公立中学校でも留年がある
年齢主義とは反対に、学力やカリキュラムの履修状況をもとに留年を判断する考え方を課程主義といいます。
ドイツ、フランス、フィンランドなどは課程主義を採用しているため、留年が多く見られます。
ちなみに、この課程主義は飛び級(アクセラレーション)制度とセットになっていることが多いです。
以下に挙げる教育再生実行会議の資料にも書かれているとおり、アメリカでは、「学力や能力に合わせて学年を選ぶべきだ」という課程主義が留年制度と飛び級制度を支えています。
もし日本の方針が変わって課程主義をとるようになったら、中学校でも留年がありえるようになるかもしれません(「学校制度(学制)-諸外国と比較」教育再生実行会議資料)。
ただし、現在の日本は年齢主義が基本になっているため、結論としては公立中学校では留年は基本的にはないということは覚えておいてください。
私立中学校の留年〜留年になった事例がある〜
私立中学校は、公立中学校よりも留年の可能性が若干高いです。
実はこれまで解説してきた年齢主義はあくまでも方針であり、法的に決まっているものではありません。だからこそ、公立中学校でも例外として留年はありえるということです。
そして、私立中学校の場合は、その例外の範囲が公立よりも広い傾向にあるのです。とはいえ、留年の数自体は決して多くありません。
私立中学校の留年の主な理由は、以下の3つです。
- 成績不良
- 病気療養
- ひきこもり・不登校など
全ての理由に共通して、「もう1年、しっかり学び直せる」というポジティブな見方もできます。しかし、恥ずかしい、友達と学年が離れるなどのネガティブな印象もあるかと思います。
理由①成績不良
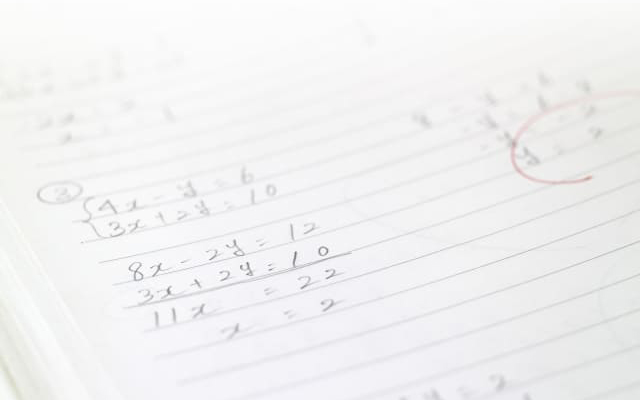
留年の理由として、成績不良が挙げられます。
判定会議では、この学年で必要なことを身につけたかどうかが、留年についての一つの判断材料として話し合われます。
その学年で必要な勉強を済ませていない場合は、進級・卒業に問題があると判断されると、留年になります。
例えば、東京都で名門校といわれている開成中学では、1年生のころから留年措置をとられる場合もあります。(出典:週刊現代「名門中高『授業についていけない子供たち』に退場勧告」)
玉川学園のウェブサイトにも、「学習到達度が不足していれば原級留置とします。」と明記しています。(出典:「Q&A|中学部・高等部|玉川学園」)
また、留年しても成績がよくならないときは塾通いをすすめられたり、転校をすすめられたり、といった対応をされるようです。
ちなみに開成ではありませんが、私の大学時代の友達にも成績不良のために私立中学校で留年したという人がいました。
一般的と言えるほど数は多くありませんが、私立中学では成績不良で留年する人は、一定数存在するのです。
理由②病気療養

2番目に挙げられる留年の理由として、病気療養というものがあります。
厳密には、出席日数が足りていない、そして授業に出ていないために勉強もできていないという理由ですね。
私立中学では、療養や入院によって出席日数が少なかった場合に留年になる、というケースが見られます。
本人や親が留年を希望して、学校が受け入れる、ということもあります。
病気を克服し、もう一度同じ学年に在籍して、しっかり学びたい、学んでもらいたいといった趣旨ですね。
例えば玉川学園でのように、病気に限らず「欠席が著しく多い場合、学習の到達度が著しく低い場合のみ、原級留置として再度学習させます。」という方針の学校もあります。(出典:「Q&A|中学部・高等部|玉川学園」)
病気療養が理由で留年というのは、私立中学では往々にしてあるということがわかります。
なお、保健室登校は登校にカウントされることがありますので、気になる場合はご自身の中学校がどういう仕組みなのか、確認してみましょう。
理由③ひきこもり・不登校など
近年、数を増していると考えられる留年の理由として、ひきこもりや不登校による出席日数不足があります。
こちらも厳密な言い方としては、欠席が多いから、そして授業を受けていないため成績もよくないから、となるでしょう。
留年したくない場合は、公立中学校への転校が考えられます。
同じ学校に在籍し続けたいけれど留年しても登校の再開が難しい場合には、フリースクールやサポート校が利用できないかを検討してみましょう。
フリースクールやサポート校は、不登校など、主には学校に馴染めない人たちのための教育施設です。
学校によっては、そうしたフリースクールやサポート校への出席を学校への出席とカウントできる場合があるのです。
カウントできる場合、フリースクールなどに通って勉強していれば、出席日数に余裕があれば留年にはなりませんし、また余裕がなくて1回は留年しても次の年度で再び留年する可能性は低くなります。
あなたの学校とフリースクールの連携について、気になるようなら確認してみましょう(必ず連携しているわけではないので、最終的には転校となることも考えられます)。
なお、フリースクールは、公立中学校に転校しても登校できるかわからないような場合や、転校先に馴染めなかった場合などにも利用可能です。
中学不登校からの高校進学については、コラム「大丈夫です。中学不登校からの高校進学」に事例付きでまとめてありますので、興味のある方はぜひお読みください。
補足:自分の状況をきちんと学校に確認しましょう
理由の①〜③に共通して、留年の判断は、基本的には学校が行います。
「テストでこの点数を取っているから自分は大丈夫」と思っていても出席日数が足りなければ留年する可能性もありますし、逆に「出席日数が足りないから自分は絶対に留年する」と思っていても成績が良ければ進級できることもある、ということです。
大事なことは、学校に自分の状況がどうなのかを確認することです。
自分は留年しそうなのかどうなのかを早いうちに確認しておくことで、その後の対策も見えてきます(例:進級のための補習を受ける、転校先の学校を探すなど)
自分だけで「OKだ」「もうダメだ」などと決めつけず、必ず学校に相談するようにしましょう。
まとめ〜中学校は留年せずに卒業できます〜

成績不良でも不登校でも、公立の場合はそのまま、私立の場合は転校するなどして、中学校は留年せずに卒業できます。
「ずっと中学校に在籍し続けなきゃいけないかも…」という不安は持たなくても大丈夫です。
とは言え、「学校に行ってないから、勉強ができていない。このまま進級・卒業して大丈夫だろうか。高校に行ったり就職したりできるだろうか」というお悩みがあるかもしれませんね。
現在は、学校に行っていない人や行けない人の勉強や進路をサポートする支援機関はたくさんあります。
また、出席日数が少なくても進学できる高校もたくさんあります。
そうしたところを見つけられると、勉強や将来についての不安も解消できますよ。
例えば、「○○市 フリースクール」「○○県 不登校 相談」などのインターネット検索をすると、サポート団体が見つかると思います。
このコラムが、中学校との向き合い方や、卒業後の進路を考えるいいきっかけになったなら幸いです。
さて、私たちキズキ共育塾は、不登校などのお悩みを抱える方のための個別指導塾です。
「中学で留年するかも…」と不安に思う状況にいる方のご相談も、これまでたくさん受けてきました。
授業では、勉強の話だけでなく、雑談や進路についての話も可能です。
少しでも気になるようでしたら、お気軽にお問い合わせください。
Q&A よくある質問