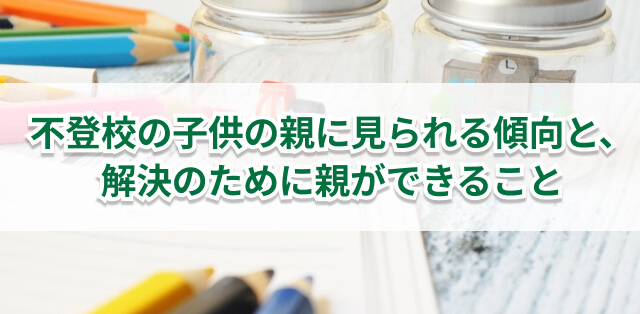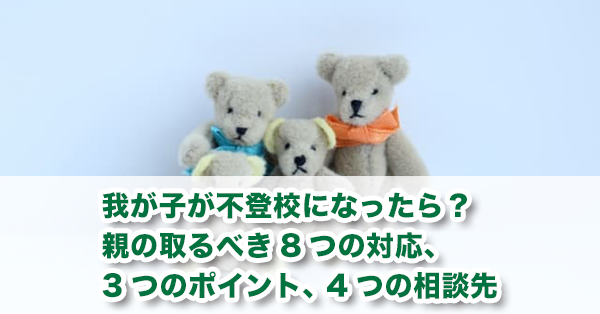お子さんの不登校に疲れた親御さんへ 親ができる対応や支援機関を解説

こんにちは。不登校のお子さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートするキズキ共育塾です。
不登校のお子さんを持つあなたは、以下のように疲れを感じているのではないでしょうか?
- 頑張ってきたけれど、もう疲れた…
- これ以上、何をしたらいいかわからない…
そんなお子さんの不登校に疲れた親御さんに向けて、このコラムでは、お子さんの不登校に関する親のよくある疲れや不登校のお子さんを持つ親に見られる傾向、不登校の子どもに見られがちな特徴、お子さんの不登校で疲れた親が前に進むための行動、不登校のお子さんを持つ親ができる対応を解説します。
あわせて、支援機関やキズキ共育塾の生徒さんの体験談を紹介します。
お子さんの不登校が「解決」し、親御さんの疲れた気持ちを和らぐよう、お役に立てましたら幸いです。
共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの
アドバイス
親が疲れるのは当然です。不登校に詳しい専門家を活用しましょう
まず、「こういう特徴がある親や子は不登校になりやすい」という一般論はありません。どんな家庭のお子さんも、不登校になりえるのです。これまでの子育てなどについて、ご自身を責めないでください。
次に、お子さんは、学校で傷ついたことで特殊な反応を見せると思います。そうしたお子さんへの対応に、親が疲れ、傷つくのは当然です。あなただけではなく、不登校のお子さんがいる誰しもが疲弊し傷つきます。
そんな親子のために、専門的な知見やアドバイスは心強い存在です。このページでも紹介するように、不登校に詳しい第三者・専門家を活用しながら、お子さんを支えていきましょう。
私たちキズキ共育塾は、不登校状態にある子どものための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
不登校は親の育て方と直接的に関係しない

最初にお伝えしたいのは、基本的・直接的には、不登校は親の育て方とは関係しません。
子どもが不登校になったとき、「自分の育て方が間違っていたのかも…」と悩み、さらに疲れたと感じる親御さんは多いです。
ですが、どのような子どもでも、さまざまなきっかけで不登校になり得ます。
文部科学省も、不登校について「取り巻く環境によっては、どの児童生徒にも起こり得ることとして捉える必要がある」としています。(参考:文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」)
例えば「自分がシングルマザーだから、子どもが不登校になったのかも…」と自分を責める親御さんがいます。
ですが、シングルマザーの家庭で不登校にならない子どももいます。また、両親がいて不登校になる子どももいるのです。
「過保護だったから」「厳しすぎたから」「コミュニケーション不足だったから」「仕事に熱中していたから」などの後悔も、同じです。
つまり、親の性格や育て方は、不登校と直接結びつかないということです。
ただし一部の例外として、虐待やネグレクト、家庭環境の悪化などが直接的な原因になることはあります。
いずれにしても、お子さんの不登校と向き合う上で最も大切なのは、親御さんやご家庭だけで抱え込まず、「お子さんや親御さんと相性が合う、信頼できる専門家や支援機関に相談をすること」です。
こちらで紹介する専門家、支援機関を利用することで、不登校のお子さんはもちろん、そして親であるあなたも、「次の一歩」に進めるでしょう。
「今も相談している相手がいるけれど、状況が変わらない…」という場合は、別のところに相談してみてもよいでしょう。
そして、親御さんご自身のケアも忘れずに行ってください。
お子さんの不登校に関する親のよくある疲れ3選
不登校の子どもを持つ親御さんは、さまざまな機会で「疲れた」と感じることがあるかと思います。
この章では、不登校の子どもを持つ親御さんがどのようなときに「疲れた」と思うのか、キズキ共育塾の生徒さんの親御さんからよくお聞きする話を紹介します。
「子どもの不登校で疲れているのは自分だけではない」と知るだけでも、気持ちが楽になるかもしれません。
ご紹介する事例は、あくまで一部です。ご自身が経験した子どもの不登校で疲れた理由がここにないからと言って、「自分の疲れは理解されない」わけではありません。
お疲れだとは思いますが、リラックスしてお読みください。
親ができる不登校のお子さんへの対応・接し方については、こちらで解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
不登校の子どもを持つ親が感じるストレスについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
疲れ①どのように対応してよいかわからない、状況が変わらない

子どもの不登校にどう対応してよいのかがわからない、状況が変わらないことで、「疲れた」と感じることはよくある話です。
具体的には、次のようなことが挙げられます。
- 自分だけ、家族だけではどうしたらいいのかわからない
- 子どもが何に悩んでいるのか理解できない
- 子どもとどう接すればいいのかわからない
- 登校を再開させた方がいいのか、しばらくこのままにしておいた方がいいのか迷う
- 頼ることができる相手がいるのかわからない
「どうしてよいかわからない…」と疲れていくうちに、子どもの状況が昼夜逆転などで悪化し、新たな疲れに繋がることもあります。
疲れ②子どもの将来に不安を感じる
不登校が続いている場合、子どもの将来について考えることが疲れにつながることがあります。
例えば、次のようなことが挙げられます。
- 出席日数が足りなくて、進級や卒業が不安
- 勉強についていけなくなり、成績が落ちることが心配
- 高校を中退することになったら、中卒になるので不安
不登校に加えて外出もしない場合は、「このままひきこもりになるかも…」という不安や心配もあるかもしれません。
疲れ③不登校になった原因は親にあると責められた

「不登校になったのは親の責任」と言われ、悲しい思いでいっぱいの親御さんもいらっしゃいます。
そのように言われることで、ご自身を責め疲れがどんどん溜まっていくのです。
現実として、母親が子育てを担当している場合、父親からでさえ「母親の責任だ」と責められることもあります。
特に「自分の育て方が原因で不登校になった」と思っている親御さんの場合、義父や義母のちょっとした言葉にも敏感になり、傷つくことがあるでしょう。
不登校のお子さんを持つ親に見られる4つの傾向
こちらで解説したとおり、基本的には、不登校は親の育て方と直接的に関係しません。
ただし、その上で不登校の子どもを持つ親御さんには、ある程度の共通した傾向はあります。当然、これは親御さんを責めているわけではありません。
牟田武生・NPO法人教育研究所理事長の著書『ひきこもり/不登校の処方箋―心のカギを開くヒント』には、さまざまな不登校の体験談が紹介されており、不登校の子どもを持つ親の人物像や考え方が詳しく書かれています。(参考:牟田武生『ひきこもり/不登校の処方箋―心のカギを開くヒント』
キズキ共育塾でも、「不登校の親に共通する傾向があれば知りたい」という声を多くいただきます。
そこでこの章では、同書の内容とキズキ共育塾の知見に基づき、不登校の子どもの親に見られる傾向を解説します。
繰り返すとおり、「この傾向が、子どもの不登校の直接的な原因である」という意味ではありません。
紹介する傾向が当てはまったとしてもご自身を責めず、「今後に活かす」ためと受け止めていただければと思います。
傾向①親自身に不登校の経験がない

1つ目の傾向は、「親自身に不登校の経験がない」ことです。
子どもはさまざまな理由で不登校になりますが、親に不登校の経験がないと、その過程・心境・状態に気づきづらい場合があります。
「子どもが不登校になるなんて思ってもみなかったから、実際に不登校になるまで心配していなかった」というパターンもあるでしょう。
また、親の理解を得られないことが、結果として不登校や、その長期化につながることがあるのです。
もちろん、親御さん自身に不登校の経験があるからといって、必ずお子さんを理解できるわけではありません。
経験があったとしても親子では事情は違っています。ですので、あくまで傾向としてご理解ください。
人は、自分が体験しなたことがないことに、強い不安を感じます。
子どもの不登校も、「このままだと、進学も就職もうまくいかないかもしれない…」と不安に思い、疲れることもあるかもしれません。
そして、子どもに「どうして学校に行かないの?」と聞いても、子どもからは納得できる回答がなかったり、どうすればよいのかがわからなかったりすることで、さらに疲れがたまっていくのです。
傾向②教育熱心
不登校の子どもの親御さんには、教育熱心な人も少なくありません。
これはさらに、大きく「親自身が教育・勉強・学歴などによって成功している」場合と、「親自身はあまり教育を受けられなかった」場合の2つにわけられます。
教育熱心なあまり、「子どもの負担・ストレス」や「子どもとのすれ違い」、ひいては「不登校になりそうな兆候」などに気づかない、または理解できないのです。
いずれにしても、親の意向と子どもの興味・関心が一致していたり、子どもが親の期待に応えられていたりするうちは、良好な関係が続くでしょう。
ですが、子どもは結果が出せなくなると自信を失っていきます。また、だんだんと親とは異なる方向に興味を持つこともあります。
結果として、そうした「勉強の悩み」や「進学校という合わない環境」などが、不登校につながる可能性があるのです。
「子どものためを思って、せっかく勉強できる環境を用意しているのに…」という親の気持ちと子どもの気持ちのすれ違いは、親御さん自身の疲れにもなるでしょう。
傾向③子どもとのコミュニケーションが少ない

子どもとのコミュニケーションが少ないことも、不登校の親御さんに見られる傾向の一つです。
コミュニケーションが少ない場合、親御さんには不登校になるまでの経緯がわからず、子どもが突然不登校になったように思えます。
コミュニケーションが少ない原因や状況としては、次のようなものが挙げられます。
- 仕事が忙しく、話す時間がない
- 子どもから鬱陶しがられるのを避けるために、あえて話しかけなかった
- 子どもから話しかけられないため、このままでいいと思っていた
- 親自身は十分なコミュニケーションが取れていると思っていた
お子さんは、一個人である一方で、「子ども」です。
親がうまくうながさないと、上手にコミュニケーションができないこともあるのです。
そして、子どもはその日にあったことや、思っていることなどを、親に聞いてほしいと思っています。楽しかったことだけでなく、悲しかったことや悩みを聞いてほしいこともあるでしょう。
子どもが親に甘えたり、安心して日常的なコミュニケーションができたりする環境・関係づくりを心掛けてみてください。
とは言え、「仕事を辞めて、子どもにつきっきりになる」ことは、あまりオススメできません。
「不登校の子どもを持つ親が仕事を辞めるべきではない理由については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
傾向④人の目が気になる
世間体や周囲の価値観など人の目を気にしすぎることも、傾向の一つです。
人の目を気にするのは、「しっかりした家庭でありたい」という気持ちの表れでもあるため、一概に悪いことではありません。
子育てについても、「ちゃんとした子どもに育てなければ」という思いから、これまでも努力されてきたのでしょう。
しかし、「生き方」や「子育て」には、絶対的に正しい、一つの基準はありません。
親が人の目を気にしていると、子どもは学校などに関する悩みについて「こんな悩みは相談できない…」と思い、コミュニケーションをためらい、不登校につながるかもしれません。
必要以上に人の目を気にすることだけでも、親御さん自身の疲れを感じるでしょう。
不登校の子どもに見られがちな4つの特徴
この章では、不登校の子どもに見られがちな特徴をお伝えします。
ただし、こちらで解説した不登校の子どもの親に見られる傾向と同様に、あくまで傾向なのであって、「この特徴があるから必ず不登校になる」というわけではありません。
当てはまる特徴があったとしても不登校にならない子どももいれば、特徴に全く当てはまらなくても不登校になる子どももいるということです。
参考程度に、気軽にお読みいただければと思います。
特徴①自信がない

1つ目の特徴は、「自信がない」です。
子どもは、これまでさまざまな経験をしてきた大人と比べると、未熟であることはもちろん、個性や人格が安定していないため、自分自身に対する自信を持ちづらい状態にあります。
だからこそ、学校に通い、周りの友人や同級生、先生たちと交流することで、自分の個性を見つけられたり、人格形成が進んだりすることもあるでしょう。
しかし一方で、学校は周りの人と勉強やスポーツ、身長、外見など、さまざまな部分で比較される場でもあるため、自信を失いやすい場でもあるのです。
そして、自信のなさから、「学校に行くのがつらい」「どうせ頑張っても上手くいかない」などの思いが強くなり、不登校になることがあるのです。
特徴②人間関係が苦手・怖い
人間関係が苦手であったり、怖いと感じていたりすることも、不登校の子どもに見られがちな特徴です。
学校生活の中では、コミュニケーション能力や場の雰囲気を感じ取る力の重要度が増しています。
もともと、コミュニケーションが得意な子どもであれば、あまり負担を感じないかもしれません。
しかし、もともと内気な性格だったり、人とのコミュニケーションに苦手意識がある子どもにとっては、この風潮が大きな負担となります。
そして、負担が大きくなると、「人と話すことが怖い」「怖くて人と会えない」といった気持ちになり、不登校につながることがあるのです。
特徴③将来への漠然とした不安がある

将来への漠然とした不安を抱いている子どもも不登校になりがちと言えるでしょう。
そもそも、将来の目標や夢は、誰でも持っているものではありません。また、持たなければいけないものでもありません。
しかし、目指すものがない状態から、「学校の勉強には、何の意味があるの?」「学校卒業後、生活していけるのかな?」などの不安や疑問が生まれることがあります。
そして、こういった疑問や不安について深く考え過ぎることで、心理状態が不安定になることがあるのです。
また、どんなに考えても答えが出ないことで、「学校に行ったところで将来は何も変わらない」と、学校に行く意味を見いだせなくなり、不登校になる子どももいます。
特徴④家族や学校に反発したい気持ちがある
最後に紹介する特徴は、「家族や学校に反発したい気持ちがある」という特徴です。
具体的には、次のような不満を抱えていることがあります。
- 校則や学校での暗黙のルールなどが息苦しい
- 家族関係に問題やストレスを感じている
- 周りの大人が自分を気にかけてくれないと感じている
家族や学校にストレスを感じる要因があることで、何とかそこから逃れようと反発して、不登校となるのです。
また、親が自分を見てくれないと子どもが感じている、またはきょうだいと比較されると子どもが感じていることで、自己肯定感が下がることがあります。
自己肯定感が下がると、親の関心を引くための手段として、不登校になるということもあるのです。
お子さんの不登校で疲れた親が前に進むための2つの行動
お子さんの不登校に悩み続けることで、親御さんが「疲れた」と思うのは当然です。
疲れを溜めないためには、または疲れた状態を改善するためには、どう行動すればよいのでしょうか?
そして、親御さんのどのような行動が、お子さんの「次の一歩」につながるのでしょうか?
この章では、不登校の生徒さんを多数支援してきたキズキ共育塾の知見に基づき、安田祐輔・キズキ共育塾代表による著書と現代ビジネスで公開したコラムの内容を一部編集した上で、不登校で疲れた親と子どもが前に進むための行動について解説します。(参考:安田祐輔『暗闇でも走る 発達障害・うつ・ひきこもりだった僕が不登校・中退者の進学塾をつくった理由』、安田祐輔「わが子をひきこもりから救った親がやめた「二つの行動」」)
行動①親は親で自分の人生を楽しむ

1つ目の行動は、「親は親で自分の人生を楽しむ」ことです。
逆に言うと、「外出しないで子どものことばかり考える」「子どもにつきっきりになる」状況は避けましょう。
親は、どうしても子どものことが気になるものです。不登校となればなおさら心配な気持ちは大きいでしょう。心配だからこそ、子どもに過度に干渉することもあるかもしれません。
ですが、親の心配が過剰だと、子どもは「親を心配させている自分」を責める可能性があります。
つまり、子どもは「自身の不登校の悩み」と同時に、「親への悩み・申し訳なさ」も抱えることになるのです。
まずは、親自身が習いごとをしたり、旅行に行ったりして、自分の人生を楽しんでください。そうすることで、心のゆとりができ、子どもへの過度な心配や干渉も減り、疲れたと感じることも減っていくでしょう。
そして、その姿をお子さんに見せてください。そうすれば、子どもの「親への心配」も軽減されていくでしょう。
「楽しく過ごす親の姿」は、子どもにとって「よい大人の見本」になります。
「今は不登校だけど、いつか親のように楽しく過ごしたい」と思うことが、お子さんの「次の一歩」にもつながることがあるのです。
家庭を離れてひとりで出かけたり、友人とカフェでゆっくりする時間を持ったりするのもよいでしょう。ぜひ、親御さんご自身が楽しめるもの・時間をつくるようにしてみてください。
行動②専門家や支援機関に相談する
お子さんの不登校、また親自身の疲れについては、積極的に専門家や支援機関に相談しましょう。
逆に言うと、あなた一人だけやご家庭だけで解決しようとすることは、あまりオススメできません。
こちらで解説したとおり、親は子どもの不登校も自身の疲れについても、「どうしたらよいか」がわからないものです。
不登校に関して経験豊富な専門家や支援機関であれば、それぞれのお子さんやご家庭の状況に応じて、的確な助言や支援ができます。
また、親御さんのケアを行っているところもたくさんあるのです。
また、専門家や支援機関は、親や家族でないからこそ、子どものための、客観的なアプローチができます。
親はどうしても子どもへの期待を捨てられないものです。
言葉では「あなたは自由でいいよ」と伝えたとしても、子どもは「親が言葉には表さない自分への期待」、例えば、登校の再開を望んでいることなどを感じ取り、プレッシャーにつながることがあります。
そのため、相談したり頼ったりできる相手を積極的に探してみましょう。
なお、相談できる専門家や支援機関を探す際に注意すべきこととして、その支援機関の方針や担当者の性格などによって相性はあります。
はじめに相談に行った支援機関が「合わない」と感じても、あきらめずに他の支援機関を探すことが大切です。
不登校のお子さんを持つ親ができる対応4選
こちらで不登校に関する親のよくある疲れを紹介しましたが、子どもの不登校に対して「どのように対応すればいいかわからない」と悩み疲れている親御さんは多いと思います。
この章では、不登校のお子さんに親ができる対応を解説します。
ここで紹介する対応・接し方を実践することで、すぐに不登校が解決するという訳ではありませんが、お子さんと信頼関係を築き、一緒に「次の一歩」を踏み出せるようになるはずです。
対応①子どもの状態を受け入れ、休ませる

お子さんが不登校になったら、まずはお子さんの状態を受け入れて、休ませることが大切です。
親御さんからすると、「無理にでも学校に行かせた方がよいのでは…?」と思い、叱ったり登校を促したりしたくなることがあるかもしれません。
しかし、お子さんは不登校になるまでの間に、さまざまな悩みや葛藤を抱え、心身ともに疲れ切っています。
そのため、まずは何よりも、お子さんの今の状態を受け入れて、休ませてあげることが必要なのです。具体的には、次のようなサポートを行うことをオススメします。
- 栄養たっぷりの食事を用意する
- しっかりと睡眠をとらせる
- 好きなことをさせる
- ゲームやスマホばかりを触っていても、温かく見守る
親御さんからすると「これだけでは何も変わらないのでは…?」と不安に思われるかもしれません。
ですが、しっかりと休むことができれば、お子さんから「何かしたい」「勉強を始めようかな」などと言い出します。
それまではお子さんの様子を見守ることに徹しましょう。
対応②子どもの話に耳を傾ける
お子さんの話に耳を傾けて、じっくりと話を聞くことも、とても大切なことです。
親御さんがしっかりと話を聞いてくれることは、お子さんの安心感につながるため、不登校からの「次の一歩」に進みやすくなります。
また、お子さんの話を聞き、お子さんの気持ちや状況を理解することも、これからのことを考えるために必要なことです。
ただし、話をしたくない状態のお子さんに対して、無理矢理話させようとしてはいけません。また、親御さんが聞き出したいことを、無理に話させようとするのも逆効果です。
こういったことをすると、子どもは「親=脅威」と思うようになり、心を閉ざす可能性があります。
そのため、お子さんが自分から話そうとするタイミングまで待ち、お子さんから話してくれた場合も、質問や意見は一旦伝えずに、話を聞くことに徹しましょう。
対応③家庭内に問題がないか考える

子どもが不登校になった場合、家庭のことを振り返ることも必要です。
こちらで解説したとおり、不登校の子どもは、何らかのストレスから親に反発したい気持ちを持っていることがあります。
たとえば、親の不仲・離婚や家庭内の関係性、経済的問題などで、ストレスを感じている子どももいるのです。
家族とはいえ、誰かと一緒に住んでいると問題が起きることは、仕方のないこととも言えるでしょう。
とはいえ、親御さんが気づかないところで、お子さんが家庭内の問題に傷ついていたり、ストレスを感じていたりすることがあります。
そのため、思い当たることがあれば、お子さんの気持ちを聞いてみたり、相談できる専門家や支援機関に問い合わせたりするなど、できることから取り組んでみてください。
対応④家庭を居心地のいい場所にする
お子さんが不登校になったら、家庭を居心地のいい場所にすることも大切です。
子どもにとっての居場所は、家庭と学校の2つのみであることが多いです。
その中の1つである学校に行けなくなった子どもにとって、家庭は唯一の居場所となります。
その居場所が、居心地が悪かったり安心感を得られなかったりすると、心が安らぐ場所がなく、不登校になるまでに疲れ切った状態から回復することが難しくなるのです。
居心地のいい家庭とは、「子どもが安心していられる場所」「わがままを言える場所」「人間関係に気を使わなくていい場所」などのことです。
親御さんは家庭がお子さんにとって「居心地がいい」と感じられる場所になるように、取り組んでみてください。
お子さんの不登校に疲れた親が相談できる4つの支援機関
お子さんの不登校を解決するには、専門家や支援機関への相談が効果的です。
この章では、子どもの不登校や親の疲れについて相談できる支援機関を紹介します。
支援機関①不登校の支援機関

現在の日本には、不登校の親子を支援するさまざまな支援機関があります。
例えば、以下のとおりです。
- 民間の支援団体
- NPO
- フリースクール
- 不登校の子どもを支援する学習塾(キズキ共育塾もその1つです。)
支援機関によって、以下のポイントで特徴が異なります。
- 心理面のサポートを重視しているところ
- 勉強を重視しているところ
- 「居場所」としての役割が大きいところ
- 参加者同士の交流がメインのところ
- 親の支援に力を入れているところ
フリースクールや学習塾では、「その団体への出席」が「在籍している学校への出席」とみなされることもあります。
これらの支援機関は、不登校の子どもを支援をしてきた経験とノウハウを多く持っており、無料で相談を受け付けていることも多いです。
インターネットで「不登校 支援」「不登校 塾」「フリースクール 〇〇市」などで検索すると見つかります。気になる支援機関があれば、無料相談だけでも利用してみてください。
支援機関②不登校の「親の会」
不登校の「親の会」とは、一般的には、子どもの不登校に関する悩みを持つ親が集まって、悩みを相談したり、有益な情報交換をしたりできる場のことです。専門家を招いての講演会を行うこともあります。
「親の会」という名前の一つの団体があるわけではなく、全国各地に名称も行っていることも異なる、さまざまな「親の会」があります。
有益な情報を得られることはもちろん、同じ悩みを持つ不登校の子どもを持つ親と話すことで、自分の不安や疲れをわかってもらえるなど、心理的な負担の軽減にもつながるでしょう。
一例として、不登校新聞社の「親コミュ」があります。また、「登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク」のウェブサイトでは全国の親の会を紹介しています。
参考:親コミュ
支援機関③自治体の相談窓口

お住まいの自治体の相談窓口も、信頼できる相談先です。
主には、以下のような支援機関があります。
- 児童相談所、児童相談センター
- ひきこもり地域支援センター
- 発達障害支援センター(発達障害が関係する、または関係すると思われる場合)
- 教育センター
自治体によって名称が異なることもあり、また各支援機関によって専門性にも違いがあります。
あなたのお子さんや親御さん自身にどの相談先に向いているのかは、お住まいの自治体のWebサイトで確認したり、お住まいの自治体の総合窓口に聞いてみたりしてみてください。
支援機関④親として信頼できる先生やカウンセラー
親として信頼できる学校の先生やカウンセラーがいる場合、相談してみるのもよいでしょう。
信頼できる先生に相談すると、進路選びに役立つ情報や、お子さんのこれまでの学校の様子や成績などに関する情報を得られます。
また、先生の経験からお子さんに向いている進路を教えてもらえることもあるはずです。
担任の先生との問題から不登校になっているなどの場合は、カウンセラーに相談するのもいいでしょう。カウンセラーは、臨床心理士や公認心理師だけでなく、学校に配置されているスクールカウンセラーも候補になります。
また、相談をした先生やスクールカウンセラーから、より専門性の高い専門家や支援機関を紹介してもらえることもあります。
「ただし、すでに相談したけれど、話が合わなかった」という話をよく耳にします。
その場合は、無理に相談をし続けることはありません。必要に応じて、成績や出席日数などの事務的な情報は確認することが大切でしょう。
「不登校でも大丈夫」と言える理由と体験談
お子さんの不登校に関連して「疲れた」と感じている親御さんは、「不登校を何としても解決しなければ…!」と思っている方が多いかと思います。
もちろん、お子さんが望んでいるのであれば、不登校が解決され再び学校に通えるようになることは、とても素晴らしいことです。
しかし、不登校は必ずしも解決しなければならないというわけではなく、「不登校でも大丈夫」と言えます。
これは、親御さんであるあなたを安心させるためだけに言っているのではなく、きちんとした理由があるのです。
そこでこの章では、「不登校でも大丈夫」だと言える理由と、実際に「不登校でも大丈夫」だと思える経験をしたキズキ共育塾の生徒さんの体験談を紹介します。
「不登校でも大丈夫」だということを知っているだけでも、疲れが和らぐこともあるかと思いますので、ぜひ読んでみてください。
不登校の「その後」にはさまざまな選択肢がある

「不登校でも大丈夫」と言える理由は、不登校の「その後」にはさまざまな選択肢があるからです。たとえば、次のような選択肢があります。
- フリースクールに通って新たな居場所を作る
- 学習塾や家庭教師を利用して勉強に取り組む
- 転校して学校生活を再スタートする
- 中退して就職し働く
- 中退して高卒認定試験を受ける
- 高認取得後に大学受験に挑戦する
進学や就職のためのルートとして、最も一般的なのが「学校に通う」ことだと思います。
しかし、今在籍している学校などに通わずに進学や就職を目指すことはできるのです。
もちろん、学校に通わないことで生まれるデメリットはありますが、別の方法でそのデメリットを回避することができます。
そのため、「子どもを今の学校に復帰させないと」「学校に行かないと将来が心配」などと思い詰めずに、広い視野でお子さんの将来について考えてみてください。
不登校を経験した人の進学・就職体験談
不登校を経験したAさんの進学や就職に関する体験談を紹介します。
Aさんは、高校2年生になった4月から、人間関係や授業のスピードなど合わないことが原因で不登校になりました。
その後は、現役で大学受験に挑戦したものの上手くいかず、アルバイトばかりをしていて、実質フリーターの状態が続いたそうです。
しかし、大学生活を楽しんでいる高校の同級生を見たことで、「大学に行きたい」と思うようになり、猛勉強を始めました。
結果的に、浪人一年目で志望校に合格でき、その後無事に卒業、就職をして現在に至るそうです。
Aさんは不登校を経験しましたが、今は次のように考えているそうです。
この私の経験からお伝えしたいことは、「『不登校だったから自分は社会に向いていない』『今さら頑張っても大学には行けない』といったあきらめや不安は必要ない」ということです。
不登校に対するマイナスイメージによって、私は「次の一歩」を踏み出すことをためらう時期が続いていました。
不登校には不登校なりの苦労があることも事実です。
私の場合は、不登校に対する負い目がよい方向に作用したため、「勉強を頑張ろう」と思えました。しかし、もっと早い段階で勉強を始めていれば、気持ちに余裕を持って、より充実した浪人生活を過ごせたのではないかと思うことが今でもあります。
不登校を経験した人、あるいは今も不登校で悩んでいる人は、「大学進学のために勉強に取り組む」「将来のことを前向きに考える」など、あきらめずに「次の一歩」を踏み出してください。
Aさんの経験談からもわかるとおり、一度不登校になったからと言って、進学や就職ができなかったり、将来が絶たれたりするということは一切ないのです。
不登校の状態のお子さんを見ていると、すぐにはお子さんの将来について前向きに考えることができないかもしれません。
しかし、少しずつでも前に進んでいくことで、お子さんの将来は開けていくのです。
とはいえ、親御さんだけでお子さんをサポートする必要はありません。専門家や支援機関などに相談したりサポートを受けたりすることができます。
親御さん自身も、お子さんの不登校についてお疲れだと思いますので、ご自身を労わりながら、お子さんのサポートを行っていただけたらと思います。
参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校ジャーナリスト・石井しこう、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。
このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。
このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。
公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら
- 【オリジナル書籍プレゼント】学校外で友だちができるBranchコミュニティ(Branch公式LINEが開きます)
私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。
まとめ〜お子さんの不登校に疲れたら相談先を探しましょう〜

不登校のお子さん自身ももちろんつらい思いをしていますが、悩みをすべて一人で抱えている親御さんのつらさや疲れは計り知れません。
「ありとあらゆる手を尽くしても、我が子の不登校は変わらない。もう疲れた…」とお思いかもしれません。
ですが、お子さんのことを、そして親御さんのことを支援する人たちが必ずいます。
お子さんの不登校に関することを親御さんやご家庭だけで抱え込まず、ぜひ積極的に支援機関を探してみてください。
お子さんとあなたが、よりよい「次の一歩」に進めることを、祈っています。
私たちキズキ共育塾は、お悩みを抱える方々のための個別指導塾です。
生徒さんには、不登校中の方、不登校を再発した方など、不登校に関連したお悩みを持つ方も大勢いらっしゃいます。
無料相談も承っております。ご相談いただければ、「あなたのお子さん」のための具体的なお話ができると思います。
キズキ共育塾のことが、少しでも気になるようでしたらお気軽にご相談ください。ご相談は無料です。また、親御さんだけでのご相談も承っています。
Q&A よくある質問