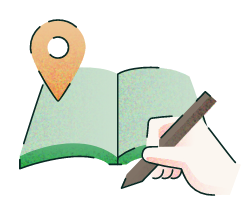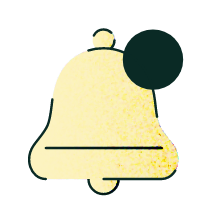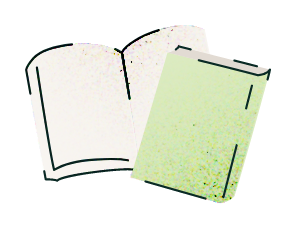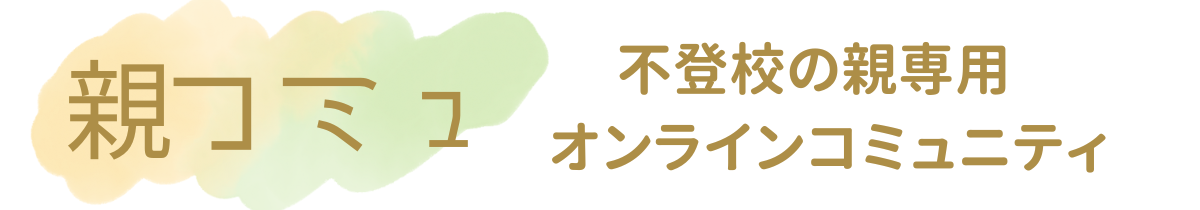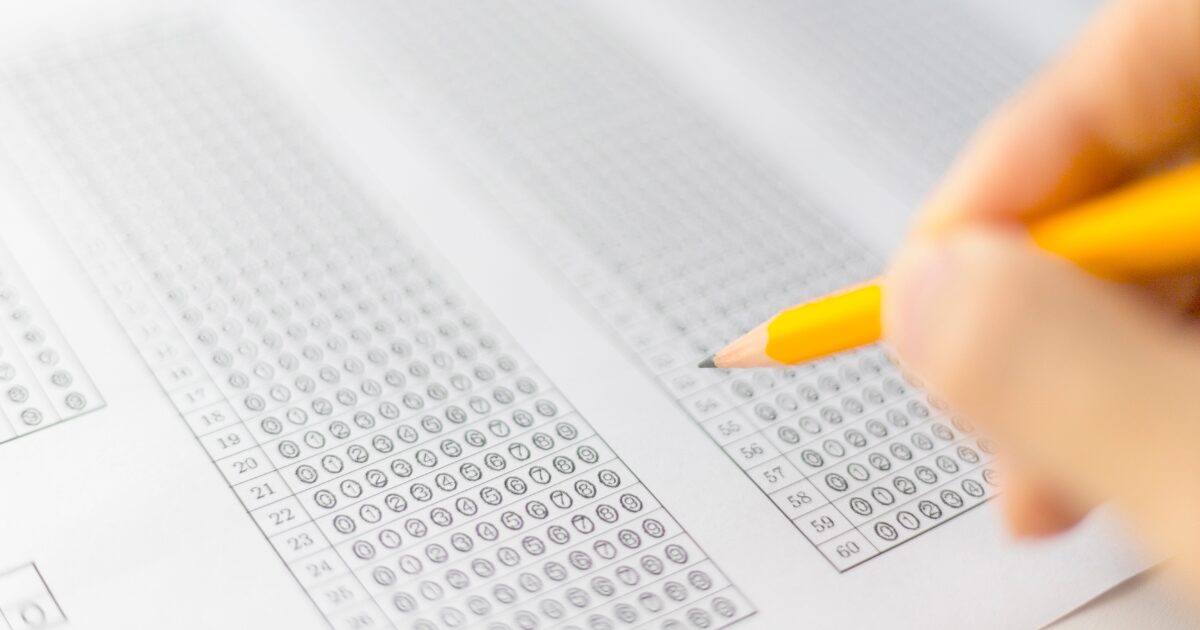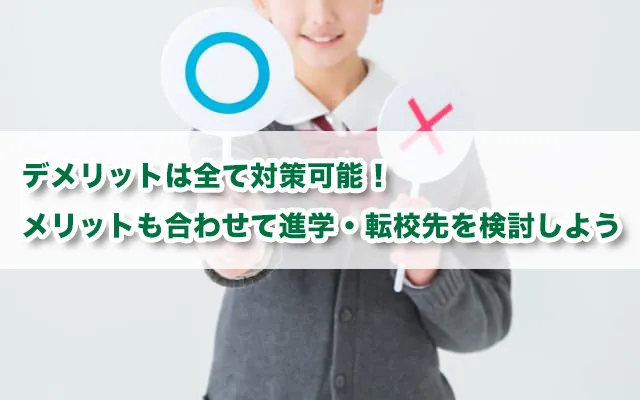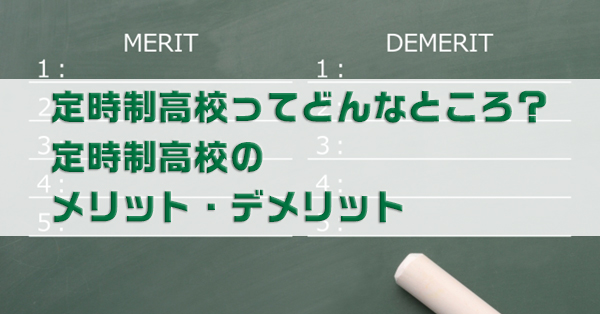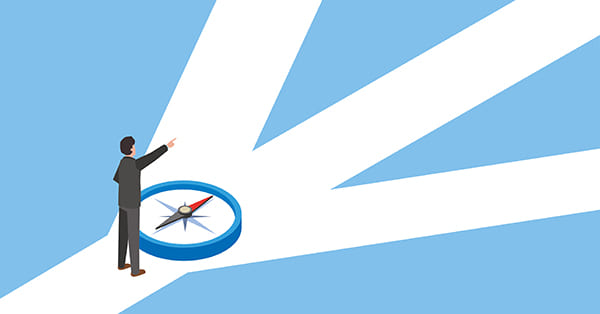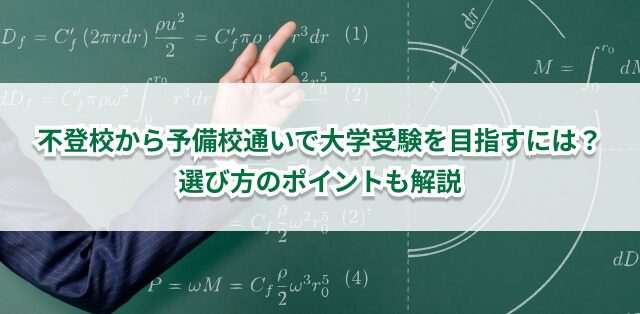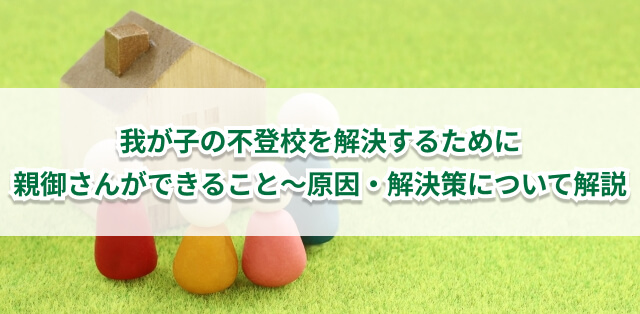不登校からの大学受験 必要な資格・8つのルート・体験談を紹介
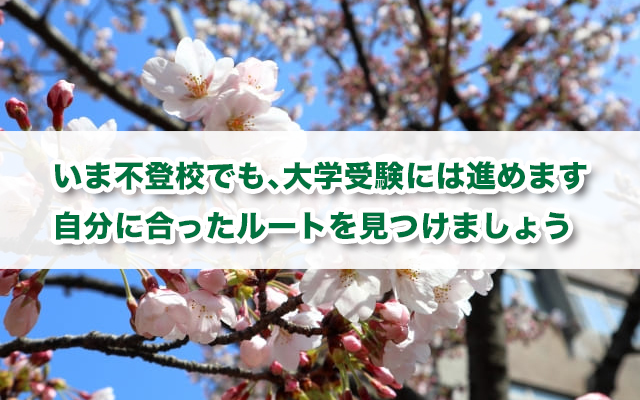
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾の石川孝之です。
中学校や高校で不登校だと、「大学に行きたいけど、不登校から大学受験はできる?」「不登校が不利にならないかな…」などの不安があると思います。
ですが、中学校や高校で不登校だったらといって、「大学に行きたい」という思いを諦める必要はありません。
結論から言うと、中学校や高校の頃に不登校経験があっても、大学受験・合格への道筋はたくさんあります。まずはご安心ください。
このコラムでは、不登校からの大学受験について不安や悩みを抱えるあなたに向けて、大学受験に向かうための8つのルートについて解説します。
また、親御さんに向けて、不登校のお子さんのためにできる対応についても解説します。あわせて、不登校から大学受験を成功させた体験談を紹介します。
共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの
アドバイス
このページで紹介されているように、「不登校からの大学受験」には、多様なルートがあります。高卒資格の取得方法も、あなたが思っているよりもハードルの低いものがあると思います。
また、大学の種類の1つとして、通信制大学もあります。有名なのは放送大学ですが、法政大学や中央大学などにも、通信制課程があります。他にもありますので、気になるなら調べてみてください。
通信制大学(大学の通信制課程)の特徴の一つに、「入学するために、大学受験の難しい勉強をしなくてもいい」があります。年齢と大学入学資格(高卒など)さえ満たしていれば、無試験で入学できるところもあります。
以上から、大学生になれないことは、ほとんどないのです。その点ではご安心ください。
高校までにしても大学にしても、学校は「自分が幸せになるための手段」です。広く選択肢を持って、あなたに合ったルート・方法を選んでほしいと思います。そして、よりよい学生生活を送る(よりよい選択をする)ためには、第三者に相談することが大切です。
私たちキズキ共育塾は、不登校からの大学受験を目指す人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
大学受験に必要な3つの資格
まず、不登校に限らず大学受験をするためには、以下の3つの資格のうちのどれか1つが必要です。
- 高校卒業(見込み)
- 高卒認定の取得
- その他の学校の卒業など
これは、中学校や高校で不登校を経験したかどうかは関係ありません。
そのため、「大学受験を目指したい」「大学に行きたい」という思いがあるあなたは、まずこの中のどの資格の取得するかを考えてみてください。
なお、学校や試験が苦手な場合は、「高校に進学しても、別の高校に転校してもまた不登校になる」「挑戦しても試験に合格できる自信がない」などの不安があると思います。
しかし、これまでの学校が合わないからといって、別の学校も合わないわけではありません。
また、試験は、相談できる詳しい人や自分に合った勉強法、自分に合った塾などを見つけられれば、これまでよりもきちんと対策ができます。
この後も何回か繰り返しますが、詳しい人に相談することで、あなたに向いている大学受験のルートがきっと見つかります。
資格①高校卒業

高校を卒業することで、大学受験をするための資格を取得できます。
高校には、以下の3種類があります。
- 全日制高校
- 通信制高校
- 定時制高校
どれも正式な高校であり、卒業すると大学受験ができるようになるのです。なお、厳密には、高校3年生の時点で、卒業見込みになっていれば受験できます。
どの高校も、3年以上高校に在籍して、必要な単位を取得する=出席日数やテストの点数・成績が基準を下回らないようにすると、卒業できます。
少し言い方を変えると、出席日数も成績も、基準を上回るだけで、毎日登校する必要も、テストで満点を取る必要もないのです。
このことを知っておくと、少し気が楽になるかもしれません。もちろん、大学受験のための勉強は高校卒業の基準とは別に必要です。
なお、以下のような要素は、学校によって異なります。
- 学費
- 授業レベル
- 進路指導・相談の充実度合い
- 生活指導の内容
- 部活や生徒会活動の充実度合い
- 校風
- 卒業後の進路の傾向
これらの部分は、資料請求や学校見学などを行ったり、知っている人に聞いたりすることで、より自分に合った高校を見つけられるでしょう。
資格②高卒認定
高校を卒業しなくても、高卒認定を取得すれば大学を受験できます。
高卒認定(高認)とは、正式名称を「高等学校卒業程度認定試験」という、文部科学省が実施する試験です。
高卒認定を取得すると、「高校を卒業した人と同等以上の学力がある」と認定され、高校を卒業していなくても大学・短大・専門学校などの受験ができるようになります。
試験は、毎年2回(8月・11月)実施されています。
高卒認定の試験を受けられる人は、「その年度で16歳以上になる、かつ大学入学資格のない人(=高校を卒業していない人か、高卒認定を取得していない人)」です。
高卒認定を取得するためには、国語・英語・数学など、全部で8〜10科目の試験での合格しなければなりません。
合否は、科目ごとに判定されます(国語と英語は合格、数学は不合格、というような感じです)。
1回の試験で全ての科目に合格する必要はありません。全ての科目で合格するまで何度でも受験できるのです。
また、一度合格となった科目の合格はずっと有効なので、再度試験を受ける必要はありません。
さらに、高校での勉強の進み具合(=取得単位数)によっては、受験を免除される科目もあるのです(逆に、高卒認定の取得によって、学校での授業が免除されることもあります)。
高卒認定は「比較的簡単な試験」と言われています。ただし、勉強が苦手な場合や、自分に合った勉強法を学びたい場合などには、高認対策を行うために塾に通うことをオススメします。
なお、高卒認定試験の受験費用は、受験科目の条件によって次のように異なります。参考:文部科学省※PDF「高等学校卒業程度認定試験」。令和4年度(2022年度)の金額です)
- 7科目以上受験する場合→8,500円
- 4科目以上6科目以下受験する場合→6,500円
- 3科目以下受験する場合→4,500円
ただし、「高卒認定の取得」は、正式な学歴にはなりません。
高卒認定を取得しても、その後に大学や専門学校を卒業しなければ、最終学歴が「中卒」のままである点には注意が必要です。
高卒認定について、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
資格③その他(学校の卒業など)

高校以外にも、いわゆる「高専」「(一部の)高等専修学校」の卒業なども、大学受験の資格となります。
「卒業」ではなく、「卒業『など』」と書いているのには、理由があります。
上記の学校は、卒業しなくても、3年以上在籍して必要な成績を修めると大学受験が可能になる場合があるのです。
中学卒業後の進路や高校(中退)からの転校先として、気になる場合は調べたり詳しい人に聞いたりしてみてください。
特に高等専修学校は、生徒の約2割が不登校経験者であり、不登校経験者への配慮がなされている学校が多いです。(参考:文部科学省※PDF「不登校経験者の自立を支える高等専修学校」)
ただし、不登校から大学受験を目指す場合は、一般的にはオススメしません(理由は次章の⑧で説明します)。
高等専修学校と高専の概要については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
不登校から大学受験を目指せる8つのルート
ではいよいよ、中学・高校で不登校の人(不登校を経験した人)が大学受験に進むための、8つのルートをお伝えします。
それぞれにオススメのポイントや注意点などがありますので、「自分に合いそうなものはどれか」を考えながら読み進めてください。
また、大学には行きたいけど、どれが自分に向いているルートなのかわからない方は、私たちキズキ共育塾にお気軽にご相談ください。
ルート①全日制高校を卒業

最初のルートは、「全日制高校へ進学・転校して、卒業を目指しながら、大学受験に備える」です。
このルートは、高校生か中学生かによって、オススメ度は変わってきます。
あなたが中学生の場合
全日制高校は、オススメのルートです。繰り返すとおり、「中学校が合わない」からといって、「高校も合わない」わけではないからです。
どのような全日制高校があるかを調べ、自分に合いそう・行きたいと思える高校を探してみてください(もちろん、後で紹介する通信制高校や定時制高校も合わせて視野に入れてOKです)。
また、「大学受験を考えているから」といって、「必ず普通科や進学校を選ばなくてはならない」わけでもありません。普通科や進学校の方が「大学受験のための勉強」が充実していることは事実です。しかし、高校は「大学受験の準備のため」だけに通うものでもありません。
何科を卒業しても「高卒」は「高卒」ですので、大学受験ができるようになります(ただし、適切に塾や家庭教師などを利用した方が効率的です)。
あなたが高校生の場合
全日制高校への転校は、現実的にあまりオススメできません。
まず、全日制高校のメリットは次のとおりです。
- いわゆる「普通の」高校生活を送れる
しかし、次のデメリットが、とても大きいです。
- (中退を経たかどうかに関わらず、)募集人数・受入時期・カリキュラムの関係上、転校のハードルが高い
- 新しい高校で「すでに出来上がった人間関係」に入っていくのが難しい
- 不登校だったことを隠したい場合、同級生などに心を開きにくい
これらのデメリットによって、不登校から全日制高校への転校しても、再度中退して通信制高校へ転校したり、高校に通わなくなったりする方も少なくありません。
もちろん、不登校から全日制高校に転校して成功した人もいると思いますので、全面的に否定するつもりはありません。
しかし、「全日制高校でなくてはならないか」をよく考えた上で、通信制高校や定時制高校などとも比較し、慎重に検討してください。
ルート②通信制高校を卒業

2つ目のルートは、「通信制高校へ進学・転校して、卒業を目指しながら、大学受験に備える」です。
このルートは、中学生と高校生の両方にオススメです。
通信制高校とは、「毎日学校に通学する」のではなく、「学校から送られてくる教材をもとに、自宅で勉強する」仕組みの高校です。
ただし、「全く通わなくてもよい」わけではなく、「スクーリング」という通学する必要がある日もあります(スクーリングの頻度は、学校によって異なります)。
通信制高校への進学・転校について、特に不登校に関連したオススメポイントは、次の3つです。
- 進学・転校のハードルが低い(受験が面接だけの場合も少なくない)
- 通学する日が少ないため、「学校」や「教室」などが苦手でも在籍しやすい
- 決まった時間割がないので、自分のペースで勉強できる
なお、注意すべき点は次の5つです。
- 世間からの偏見がある
- 大学受験が難しい
- 友達をつくる機会が少ない
- 勉強のペースがつかみにくい
- 生活リズムが崩れやすい
上記デメリットの詳細と対応法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
学費は、公立なら年間3~5万円、私立であれば年間10~100万円程度が目安です。
通信制高校はたくさんあります。学校見学や資料請求などを行った上で、自分に合いそう・行きたいと思える高校を探してください。
その他、通信制高校の詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ルート③定時制高校を卒業

3つ目のルートは、「定時制高校へ進学・転校して、卒業を目指しながら、大学受験に備える」です。
このルートも、中学生・高校生の両方にオススメです。
定時制高校は、全日制高校よりも遅い時間帯で授業を行う高校です。
より具体的には、主に次のような時間帯で授業を行われています。
- 夜の時間帯に授業を行う「夜間定時制」
- 朝と昼の時間帯に授業を行う「昼間二部定時制」
- 朝・昼・夜の時間帯に授業を行う「三部制」
不登校に関連して、定時制高校への進学・転校をオススメする理由は、次の3つです。
- 通信制高校同様、進学・転校のハードルが低い
- 通学するため、「学生生活」を楽しめる(クラスメイトとの交流、部活など)
- 不登校経験者、中退経験者、定年退職者など、多様な層が在籍するため、いろいろな人と交流できる
注意すべき点としては、次のようなものがあります。
- 中退率が高い
- 勉強のサポートが薄いことがある
- 卒業まで、4年かかることがある
特に③は、「全日制高校よりも1日あたりの授業数が少ない定時制高校」では、授業に必要な日数が全日制高校よりも多く、そのために3年では卒業できない場合があるのです(全ての定時制高校が卒業までに4年かかるわけではありません)
「いつまでに高校を卒業し大学受験をしたい、大学に行きたい」などの思いや計画がある場合は、卒業までの年数も検討して高校を選びんでください。
定時制高校のメリット・デメリットの詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
学費は、公立で年間13万円(以上)、私立で50万円(以上)、くらいが目安です。
定時制高校ならではの学校選びのポイントとしては、「通いやすい時間帯に授業を行う学校、通学しやすい場所にある学校かどうか」「多様な層が在籍するため、校風や雰囲気が自分に合うかどうか」を検討することが大切です。
まずは、学校見学や資料請求をして、情報を集めてください
その他、定時制高校の詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ルート④「高校進学(転校)・卒業」と「高卒認定」の両方を検討
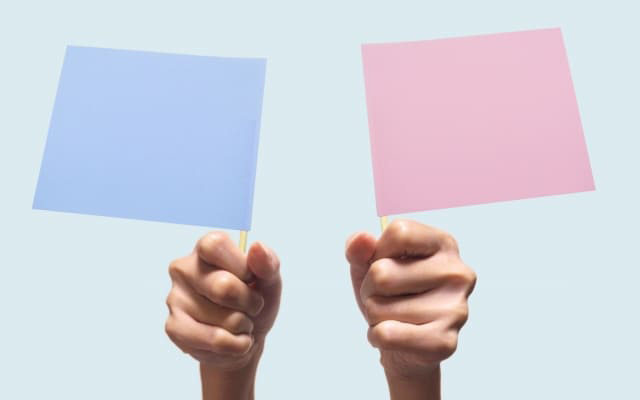
4つ目のルートは、「全日制・通信制・定時制高校へ進学・転校して、卒業と高卒認定の取得の両方を視野に入れた上で、大学受験にも備える」です。
このルートは、中学生と高校生の両方にオススメです(ただし、高校生の場合、前述のとおり「全日制高校への転校」はあまりオススメしません)。
高卒認定は、高校に在学していても受験できます。
この場合のメリットは、各高校のメリットに加えて、次のようなものがあります。
- 高校卒業と高卒認定の両方を目指しながら、最終的に「より自分に向いている方」を選べる
- 高校で授業や試験を受けることで、高卒認定の受験で免除科目が発生する可能性が高くなる
- 在学中に高卒認定を取得すれば、高校を中退しても大学受験ができる
- 高卒認定を取得すれば、「18歳の3月」に高校を卒業できない場合にも、大学受験が可能になる
注意点は、それぞれの高校のものに加えて、次のとおりです。
- 高校の学費と高卒認定の受験料の両方が必要になる
- 高校の勉強と高卒認定の勉強の両方が必要になる
ルート⑤「現在の高校に在籍継続」と「高卒認定」の両方を検討
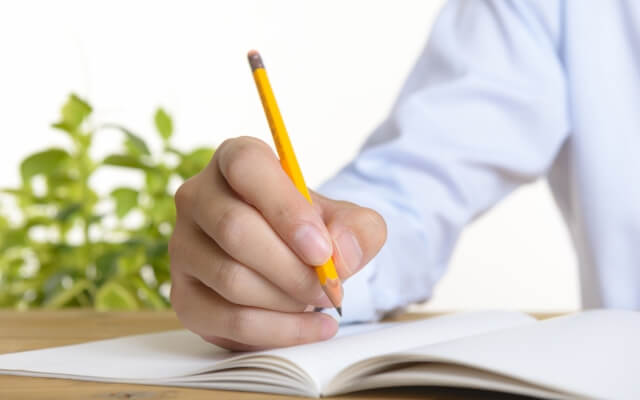
現在高校生であって不登校の方には、「現在の高校に在籍したまま、高卒認定の取得を目指しつつ、大学受験にも備える」ルートがあります(現在中学生の方も、今後の参考にぜひ読んでみてください)。
特に、「いま在籍している高校への登校復帰を検討している方」にはオススメです。
前述のとおり、高卒認定は、高校に在学していても受験できます。
このルートのメリットとしては、次のようなものがあります。
- 高認のために勉強することで、各科目の基礎知識や勉強習慣が身につくので、登校再開時に授業にも復帰しやすい
- 新しい学校を探す必要がない(現在の高校を卒業できる)
- 結果として登校を再開しなかった場合も、高卒認定によって大学受験ができる
一方で、注意点には、次のようなものがあります。
- 不登校期間が長引くと、学校の規則によっては、退学や留年になる可能性がある
この注意点を解消するためには、次項でご紹介する「保健室登校・別室登校」と組み合わせることを検討してみてください。
ルート⑥現在の高校を、保健室登校・別室登校で卒業

こちらも、今高校生で不登校の状態にある人に向いているルートです。
「教室への登校」ができなくても、保健室登校や別室登校を行うことで「出席」とみなされることがあります。
試験も保健室で受けることで、「出席日数」と「勉強」の両方を満たし、単位を取得し、現在の高校を卒業できるのです。
保健室登校・別室登校を出席とみなすかどうか、保健室・別室で試験を受けられるかどうかなどは、学校によって異なるので、気になる場合は高校に確認しましょう。
メリットは、次のとおりです。
- 新しい高校を探す必要がない(いま在籍している高校を卒業できる)
注意点は、次のとおりです。
- 教室に行かないので、授業を受けられない(勉強を教わる機会が減る)
学校では教科書を読んだりプリントをもらったりして自習しつつ塾などに通うと、より効率的に勉強できます。
ルート⑦高校進学せずに高卒認定(高校中退して高卒認定)
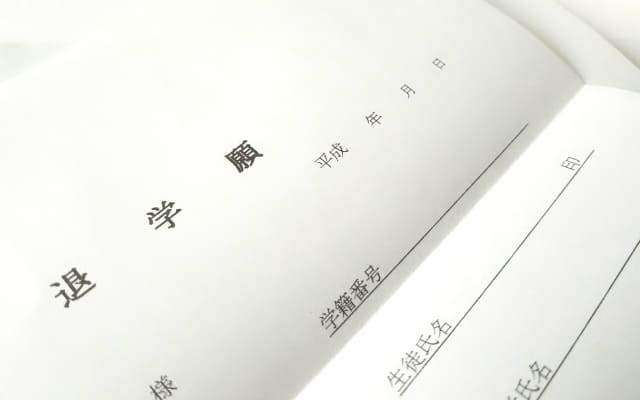
7つ目は、「高校進学(転校)・卒業を考えず、高卒認定で大学受験の資格を満たす」ルートです。
このルートは、中学生と高校生でオススメ度が違います。
あなたが中学生の場合
最初からこのルートを選ぶことはオススメしません。高校に進学しないことには、「高校が合うか合わないか(楽しいか楽しくないか)」がわからないためです。
「いまの学校」「これまでの学校」が合わないからといって、高校も合わないわけではありません。
不登校で悩んでいると、「自分は高校に行ってもまた不登校になる。だから高校に進学しても意味がない」「不登校の自分が進学できる高校なんてない」などと考えがちです。ですが、そうとは限りません。
まずは高校進学を視野に入れて、自分に合いそう・行きたいと思える高校や、不登校で内申点が低くても進学できる高校を探してみてください。
結果として「やはり高校には進学しない」「やはり合わなかったから中退する」ことを選ぶ可能性もあります。ですが、最初から「高校には行かない」と決めつけるのは、とてももったいないです。
あなたが高校生の場合
このルートは現実的に「アリ」です。高校中退後に高卒認定を取得して大学受験を目指す人は、少なくありません。
メリットは、次のとおりです。
- 「嫌な場所」である高校に通わなくても、大学受験ができるようになる
- 高校の学費が不要
注意点としては、次のとおりです。
- 高校という「所属」がなくなる
- 勉強や進路について、相談できる人を新たに見つける必要がある
「所属」がなくなった人は、精神的にダメージを受けやすい傾向があります。
高校生がこのルートを進む場合、例えば「高校中退者の大学受験に詳しい塾」など、「所属」と「勉強・進路相談」を満たせる場所を探すことがオススメです。
ルート⑧高専・高等専修学校の卒業など

最後のルートは、「高専や(一部の)高等専修学校に進学・再入学して、卒業などを見据えた上で、大学受験に備える」です。
中学生と高校生に共通して解説します。
紹介しておきながら失礼しますが、ともに、「不登校から大学受験を目指す・大学に行きたい」人には、一般的にはオススメしません(どちらも「悪い学校である」という意味ではありません)。
高専とは
高専は、工学・技術・商船など、「普通の高校」よりも濃い内容を学びます。専門的にしっかり学べる一方、授業内容に遅れるとすぐについていけなくなることもあります。
授業についていくために、毎日登校して、しっかり授業を受けるハードルが、不登校経験者には、少し高く感じられることもあるかもしれません。
高等専修学校とは
工業・農業・医療など、職業に直結した内容を学びます。生徒には不登校経験者も多く、学校として不登校経験者への配慮がなされていることも多いです。
しかし、職業に直結した内容を学ぶ分、大学受験に直結する内容の授業は手薄になりがちです。
ただ、高専・高等専修学校ともに、上記内容は一般論です。
不登校を経験していても高専では楽しく過ごせてしっかり学べる人もいます。また、高等専修学校に進学して大学受験の勉強は塾などで対策するのも、もちろん可能です。
何度も繰り返すとおり、「自分の性格など」と「その学校」の相性がどうかなどを、しっかり調べて詳しい人に相談してみてください。そうすることで、よりあなたに合い、行きたいと思える学校が見つかります。
高専と高等専修学校に関しては、次のコラムをご覧ください。
不登校で高校中退した後の転校では「在籍期間」に注意

あなたが高校生で、「高校を中退して転校すること」を考えている場合、中学生とは異なる注意点があります。
それは、「在籍期間」です。
前述したとおり、高校を卒業するためには、「3年間(以上)の在籍期間」が必要です(別途、単位も取得する必要があります)。
転校前の高校の在籍期間は、次の学校に引き継げます。
例えば、「最初の高校に1年間在籍していた場合、次の高校での在籍は2年間でOK」なのです。
ですが、中退の関係で「一つ目の高校」と「二つ目の高校」の間に「高校に在籍していない期間」があると、3年間の在籍期間を確保するために、「18歳の3月」に卒業できなくなります。
そうすると、大学受験は1年先送りになるのです。
現時点で高校に所属している場合、中退・転校の時期をよく考えておく必要があります。
とはいえ、高卒認定ルートや、高校卒業と高卒認定の両方を視野に入れるルートであれば、「18歳の3月」に高校を卒業できなくても大学受験はできます。
また、「高校は18歳の3月に卒業しなくてはいけない」ものでもありません。卒業が伸びたときには「受験勉強に使える時間が増えた」とポジティブに考えることもできるかもしれません。
高校中退・転校の詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
不登校からの大学受験では「塾・予備校」がオススメ
不登校から大学受験を目指す場合、学習塾や予備校に通うことをオススメします。
一人で取り組むよりも塾や予備校に通った方が、学習のスケジュールや学習内容を正しく判断しやすくなるからです。
以下、理由を具体的にお伝えします。
理由①学習計画・時間管理などのサポートを受けられる
大学受験は、時間との戦いです。
自分ではどのように学習計画を立てたらいいかわからない、自分で学習計画を立てていてもなかなかうまく進まない、などの場合があると思います。
学習塾や予備校に通うことで、計画的・効率的に勉強する方法やそのスケジュールまで塾講師のサポートが受けられるのです。
また、学習塾や予備校では、大学受験に関する情報も得られます。
大学受験では、年によって入試の出題傾向や内容が大きく変わることもあります。
塾や予備校などから、最新の情報を得ることはとても大切です。
理由②勉強の基礎・勉強法を教えてもらえる
不登校期間が長く、学校の勉強をしていなかった場合、基礎から学び直す必要があります。
小学校レベルからの学び直しなのか、高校レベルなのかなど、まずは勉強をどこから始めていくかを知ることが大切です。
自分に合う塾などを利用すれば、どこから学び直せばいいのかがわかり、基礎からの学び直しも効果的に行えます。
また、どのように勉強したらいいか、どんな勉強法が自分に合うか、などわからないことも多いと思います。
塾や予備校に通えば、あなたに合った勉強法を教えてもらえるため、効率良く受験勉強を進められます。
理由③志望校に合わせた勉強ができる
大学受験の特色として、志望校によって受験科目が異なります。
国公立大学が希望であれば5教科7科目、私立文系であれば英語、国語、社会、私立理系であれば英語、数学、理科などです。 私立大学の中には、1科目受験の大学もあります。
ただがむしゃらに勉強を進めるより、志望校・入試科目に合わせて勉強することが必要なのです。
また、あなたが行きたい大学の配点に合わせた勉強時間の配分も大切になります。
学習塾や予備校では、志望校に合わせた勉強対策を行えます。
また、個別指導塾では、志望校だけでなく、あなたにあった勉強法や学力に合わせて授業を組み立てもらえます。
私たちキズキ共育塾もその一つです。
理由④メンタルケア・精神的なサポートを受けられる
学習塾や予備校によっては、不登校の人のためのメンタルサポートを行っているところもあります。
長い受験生生活において、メンタルを健康に保つことはとても大切です。
メンタルの調子が悪いと勉強の手も止まります。そして、学習スケジュールが乱れることで、余計に精神的な焦りや不安につながります。
そのため、学習塾や予備校を利用することで、受験勉強をする上での伴走者を得ることは、とても重要なのです。
つらいことや苦しいことは気軽に塾講師らに相談して、一人で抱え込まないようにしてください。
塾講師の中には、自分と似たような経験をして悩んだことがある人や、自分の気持ちをよくわかってくれる人がいるため、大きな助けとなるはずです。
補足:「不登校からの大学受験」の関連コラム
ここまで、不登校の人には学習塾や予備校の利用がオススメな理由をお伝えしてきました。
もちろん、学習塾や予備校に通わないと大学には合格できないわけではありません。
あなたに合った大学合格への道があります。その道を探るきっかけになれば幸いです。
また、下記のコラムでもくわしく説明しています。ぜひ参考にしてみてください。
不登校からの大学受験でも「総合型選抜(旧AO入試)」を利用可能
総合型選抜入試とは、カンタンに言うと、「なぜその大学に行きたいのか、勉強したいのか」を面接や小論文などでアピールする受験のことです。
不登校でも、総合型選抜入試を利用できます。また、不登校経験を長く話すよりも、自分の熱意や実績をアピールして合格することもできるのです。
ただし、相手からの質問があったときや、自分がアピールしたい内容によっては、不登校経験を話す場面も出てきます。
その大学・学部に行きたい理由が不登校と関係するようであれば、それを面接で伝えることで高評価を受けることもできます。
例えば、次のようなことです。
- 体調を崩したのですが、自分に合う薬がありませんでした。○○という理念を持つ貴学の薬学部なら、かつての私のような人たちのための薬の開発に取り組めると思ったので、志望します
キズキ共育塾の生徒さんだけを見ても、「高校不登校・中退→高卒認定試験に合格→慶應義塾大学(総合政策学部)にAO試験で不登校に触れずに合格」などの例があります。
自分にどの入試が合っているか、また、それぞれの入試への対策をどうするかなどは、塾や専門的な指導をしている人に相談してみてください。
動画では、このコラムの内容に関連して、面接のある大学受験の際に不登校の経験をどう話せばいいかを解説しています。
ポイントは、「不登校をなかったことにはしない」「受けたい学部にあった答え方をする」「大学の特徴を見る」「一人で考えなくてもいい」です。ご興味がありましたら、ぜひご覧ください。
不登校から海外の大学を受験するのもアリ
高校中退後に「海外留学する」人もいます。
日本でずっと過ごす生き方とは異なる「成功」が見えてくるかもしれません。
留学して現地の学校を卒業すれば、日本でいう高卒資格とともに、その国の言葉も身につけられるため、一石二鳥だとも考えられます。
また、「日本の学校文化」や「それまでの生活地域の環境」に馴染めないことでの高校中退であれば、留学することで楽しい学校生活を送れるようになるかもしれません。
キズキ共育塾が知っている事例として、不登校からの留学先としては次のような例がみられます。
- アメリカ
- イギリス
- カナダ
- オーストラリア
- ニュージーランド
しかし、前述した高専同様、向いている人には向いている選択肢ではある一方で、こちらも「全員にオススメできる選択肢」ではないことは、正直にお伝えします。
それは、言語能力・お金・精神面・ビザなど、高校とは別の大変さがあるからです。
留学までに整えなくてはならない段取りも多く、高校中退後どうすればよいかわからない人が、勢いや「なんとなく」で実行するには、ハードルが高い面もあります。
ただ、「日本の大学」に限定せずに考えてみることがポイントです。
結果として、実際に海外の大学に行くかもしれませんし、「やはり日本の大学に行きたい」と思えば日本の大学へのモチベーションが上がることにもつながります。
日本の大学に入って、大学のプログラムから海外留学をするのもいいかもしれません。
視野が広くなることで、今は見えていない「何か」が見えてくることもあるでしょう。
もし本気で検討したい方は、家族と相談を重ねた上で、経験者や留学エージェントなどの意見を聞いてみてください
文部科学省「高校生の留学 トビタテ!留学JAPAN」のサイトで調べるのもオススメです。
短期留学が不登校克服につながることも
2週間ほどの短期留学に挑戦したことが、不登校克服のきっかけになることもあります。
一人で海外に行くことで価値観が広がることもあれば、そこで友達ができることもあるかもしれません。
一人でチャレンジできた体験が自信につながった生徒さんもいました。
環境をガラッと変えてみたい、海外に抵抗がないといったお子さんには、短期留学もオススメです。
なお、「いま住んでいる地域から離れたいから留学したい」のならば、外国ではなく、今住んでいる都道府県や市区町村以外の学校などに再入学・編入する選択肢もあります。
不登校からの大学受験以外の進路・選択肢
不登校からの進路は、大学へ行くことだけではありません。
不登校後の進路として、大学受験(大学入学)以外にも、さまざまな選択肢があるのです。
例えば、専門学校、高等専修学校、高等専門学校(高専)、高等学校卒業程度認定試験、就職などが選択肢となります。
ここからは、大学受験以外の進路をご紹介します。
選択肢①専門学校、高等専修学校、高等専門学校(高専)、高等学校卒業程度認定試験
専門学校では、職業に直結する勉強ができます。
高校までの学校と似ていて、時間割があらかじめ決まっており、クラス制度がある学校も多いです。
現時点で「強く興味のある職業」があれば、選択肢の一つになるでしょう。
高等専修学校も高等専門学校も、ともに中学校を卒業した人を対象としています。
高等専修学校は、5年制(商船科は5年6か月)で、工業分野と商船分野の2分野のみを学びます。
一方、高等専門学校(高専)は1年以上(3年制が多い)で、工業、農業、医療、衛生(調理、理容、美容)、教育・社会福祉、商業実務、服飾・家政、文化・教養など、文部科学省で定められた8分野を学べます。
なお、詳細は、下記のコラムで解説しているので、よければご覧ください。
選択肢②学校以外の就職サポート機関
専門学校以外にも、高卒後の就職をサポートする支援機関があります。
各公式サイトなどを見て興味を持てたら、ぜひ相談してみてください。
- 職業訓練校(ハロートレーニング)
- 地域若者サポートステーション(通称サポステ)
- 就労移行支援事業所
不登校から大学受験を目指す子どもに親ができる対応
ここまでご紹介してきたとおり、中学・高校不登校から大学受験を目指すルートはたくさんあります。まずはご安心ください。
とはいえ、不登校については、本人だけではなく親御さんも不安や悩みを抱えていらっしゃると思います。
この章では、不登校から大学や高校への進学を目指すお子さんを持つ親御さんに向けて、親御さんにできることをご紹介します。
対応①専門家に相談する

不登校から次の一歩に進むためには、第三者の援助が不可欠です。
逆に言うと、不登校や受験に関するお悩みを、親子だけ・家族だけで抱え込まない方がよいのです。
第三者とは、不登校に詳しい人や、不登校支援を行う団体などの専門家になります。
学校に在籍しているのであれば、担任、学年主任、スクールカウンセラーなどに相談してみてください。
次のような、お住まいの市区町村の相談窓口に相談する方法もあります。
- 児童相談所、児童相談センター(18歳未満)
- 教育センター(高校相当年齢)
- 引きこもり地域支援センター
- 発達障害支援センター(発達障害が関係する(かもしれない)場合)
名称などは自治体によって異なります。お住まいの自治体のウェブサイトで確認してみてください(窓口がわからない場合は、代表電話に連絡して確認しましょう)。
民間の不登校の支援団体には、全国の「不登校の親の会」や、私たちキズキ共育塾などがあります。
保護者だけ、または子どもだけで相談できる場所もあります。「まずは自分だけで」と思う場合は、保護者のみでも相談を受け付けているところを探してみてください。
また、最近はインターネットや電話で不登校の相談を受け付けているところも多いです。そのため、家の近くに相談機関がなくても、利用できます。
相談先については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
専門家には守秘義務があるので、相談に行ったからといってそれが周囲に知られることはありません。
ご本人だけ、親子だけ、ご家族だけで悩まずに、必ず専門家の助けを借りてください。
対応②親は親の生活を充実させる

親は親で、自分の生活を充実させることが大切です。
「子どもが不登校なのに、私だけが仕事に行ったり、趣味のサークルを楽しんだりしていいの…?」
このように思われるかもしれませんが、親は親で自分の人生を楽しむことが、不登校の解決に繋がります。
そうはいっても、子どもが苦しんでいるときに、心から楽しめないのが親の感情として当然でだと思います。
ですが、親が自分の生活を充実させることには、次のような効果が期待できるのです。
(1)親子が社会から孤立することを防ぐ
親が生活を楽しむことで、親子で社会から孤立することを防げます。
親子とも外との繋がりがなくなって、家庭ごと地域から(世間・社会から)孤立するケースがあるのです。
親が働きに出ている場合でも、子どものことで心にずっと不安を抱えていると、社会との心理的な距離が開いていきます。
地域や社会から孤立すると、家族という密閉した空間の中で、親の心・視点は子どもに向かう一方で、親子の不安はますます増幅するのです。
親の過度な不安や心配が子どもの心を圧迫していく…といった悪循環にも陥りかねません。
親が生活を楽しめるようになると、視野も適切に広くなり、社会からの孤立を防ぐことに繋がります。
(2)親が大人のロールモデルとなる
親の充実した生活は、大人のロールモデルを子どもに与えることになります。
充実している親の姿を見ることで、子どもは「いまは不登校で苦しいけど、大人になったらこんなふうに生活したいな」「そのために、受験勉強もがんばろう」と思えることがあるのです。
子どもに「外の世界は楽しいよ」「大人になるっていいものだよ」と示すことが、不登校の「次の一歩」につながります。
不登校から大学受験・進学をした人の体験談4選

私たちキズキ共育塾には、不登校から大学受験を行った生徒さんがたくさんいます。
この章では、不登校から大学受験・進学をした人の体験談を紹介します。今後のご参考にぜひご覧ください。
体験談①不登校から高校中退→高卒認定を経て大学受験
進藤明子さん(仮名、日本大学芸術学部合格)は、小学生のころから学校を休みがちでした。
進学した高校にも次第に通えなくなり中退し、生活リズムも崩れます。
「このままではいけない」と悩み続けた結果、もう一度勉強に取り組み大学受験をして、自分のやりたいことを見つけてみようと思いました。
キズキ共育塾で学ぶことで、勉強に加えて人間的にも成長し、AO入試で志望大学に無事合格しました。
体験談②不登校から高校中退→ひきこもり・高卒認定を経て大学受験
金井篤くん(仮名、関西学院大学社会学部・商学部ほか合格)は、高校で部活と勉強を両立することが難しくなったことをきっかけに、不登校を経て中退しました。
中退後は、半年ほどの引きこもり生活を送ります。
一度は塾に入りますが、そこにも馴染めず再び引きこもりになりました。
そんな中、友人が大学受験に取り組んでいることを知り、友達に負けたくない気持ちから、再び勉強をやり直してみることにします。
キズキ共育塾に入塾した後は、自分のペースで勉強を進められ、大学合格を掴みました。
体験談③「中学からの不登校」中高一貫校から転校→高卒認定を経て大学受験
堀内亮太くん(仮名、立命館大学理工学部合格)は、中学受験で中高一貫校に進学しました。
ですが、理由が思い出せないくらい中学校が嫌になり、不登校になります。
アメリカに行ったことをきっかけに海外に希望を持ち、オーストラリアの高校に転校したところ、今度は人見知りのためによりつらい状況になります。
その後、興味を持った物理を学べる大学に行きたいと思い、進学を決意。
高校を中退して独学で高卒認定を取得後、キズキ共育塾で受験勉強を行い、立命館大学に合格しました。
体験談④「勉強についてけない…」高校不登校から転校→大学受験
富田克祐くん(仮名、国士舘大学法学部合格)は、小中学校のときはすごくまじめな生徒でした。
ですが、入学した高校の体育会系っぽい雰囲気が苦手で、次第に勉強についていけなくなり、1年間の不登校を経験します。
その後、高校を転校しましたが、みんなと一緒に授業を受けるのが難しかったり、要求されるレベルが高すぎたりと、新たな問題を抱えました。
そんなときに、キズキ共育塾を見つけて入塾。
最初は授業を受けることさえ不安でしたが、少しずつ苦手を克服し、大学に合格しました。
補足:不登校から大学受験した人のブログもオススメ
ここまでキズキ共育塾での事例をご紹介しました。
ほかにも、インターネットで検索すると、不登校から大学進学した人のブログなども読めます。
参考に読んでみると、発見があるかもしれません。
不登校からの大学受験で気をつけるべきポイントに関する講師からのアドバイス
この章では、不登校状態にある人や不登校を経験した人などを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾の知見に基づき、不登校からの大学受験で気をつけるべきポイントに関する講師からのアドバイスを紹介します。
実際に不登校から大学受験を目指す人たちに勉強を教えている講師の生の声です。きっと参考になると思います。
また、私たちキズキ共育塾の無料相談では、実際のあなたのための、より具体的なアドバイスが可能です。ぜひご相談ください。
いま自分がどこにいるのか、進捗状況を把握する
不登校の中高生が大学受験を目指す際に気をつけるべきポイントは、「いま自分がどこにいるのか、進捗状況を把握する」ことだと思います。
なぜなら、学校に通っていない場合は見えづらいからです(学校などに通っていると定期テストなどで現在の自分のレベルが明確化されやすいです)。
もちろん、自分の進捗を明らかにすることで「自分はこんなにもできていないのか…」と不安を感じることもあるかもしれません。しかし、むしろ「ここができていないから、できるようにすればいいだけだ」と、改善点が見つかるいい機会だと捉えてみてください。進捗を把握して目標に向かって進みましょう。
学習塾などの、モチベーションを保てる方法を持つ
不登校の中高生が勉強を進めて行くときに、いちばん難しいのは、「モチベーションを保つ方法」だと思います。「勉強習慣をどのように作るのか」という問題とも関わってきます。
学校に通っていると、毎日授業が一定のペースで進み、テストが実施されることで、半ば強制的に勉強のペースを作っていくことになります。テストが近づいて来ると、クラスメイトで勉強の進捗を確認し合ったり、先生にテスト範囲の内容を質問しに行ったり…… さまざまな形で自分の勉強の到達状態を確認することになるはずです。
学校に行っていない状態で、あなた一人でモチベーションを保ち、勉強習慣をつかむことは、「無理」とは言いません。ですが、学習塾などの「勉強をサポートする存在」を持てると、より安心できると思います。
村下莉未講師のアドバイス
受験に必要な科目を検討する
勉強する科目(=受験に必要な科目)を、早めに検討することが重要になります。取り組む科目の数によって、学習スケジュールが大きく変わるからです。
まずは「高卒認定試験を受ける必要があるのか」を確認してください。
次に、「大学は国公立を視野に入れるのか」を決めておけるとよいと思います。私立の受験は3教科で済むことが多いですが、国公立では5教科が必要です。また、私立の場合は、受験する大学や学部が決まると、受験科目をかなり絞れます。
英語が不得意なら、中学校内容を1周する
中学の範囲で未習(よく覚えていない、よく理解していない)単元がある方へのアドバイスです。まず、志望校のレベルに関わらず、中学校の主要単元を1周し終えることをオススメします。
理由①高校の学習内容には、中学の学習内容の応用表現が多いです。「中学レベルの知識」が定着していると、学習内容を理解しながら覚えられて、修得しやすくなります。
理由②未修の部分があっても、中学内容の方が問題をある程度解けるため、勉強のモチベーションを保ちやすいです。
カトウアイ講師のアドバイス
志望校に、学生向けの就職や留学のサポートが充実しているかを確認する
大学生活はクラスで行動するよりも、個人で行動することが多くなります。一人暮らしを始めたり、海外留学したり、3年生以降は就職活動をしたりすることがあります。
そうしたことを気軽に相談できる環境が大学にあると、とても役立ちます。気になる大学があるなら、その大学の相談担当部署と話をしてみてください(学生課・学務課・教務課などの名前であることが多いです)。受験生の時点で親身になって相談に乗ってくれる大学は、入学した後も親身になって学生の相談に乗ってくれることが多いです。
I.M講師のアドバイス
現代社会に関する情報に触れる機会を増やす
社会情勢をはじめとする現代社会に関する情報に触れる機会を増やすことをオススメします。
いま何が話題になっているのか、どういったことが社会問題とされているのか、そういった情報を得ることで、進路選択に役立つことはもちろん、受験においてもさまざまな場面でプラスになります。
学校では意識せずとも多くの情報と触れる機会がありますが、不登校の場合には意識して情報を得る機会を設けることが必要になります。
情報源はインターネット、テレビ、書籍などいくらでもあります。意識していないと、どうしても「自分が興味のある情報」だけにアクセスする機会が多くなると思いますので、幅広く触れてみてください。
O.H講師のアドバイス
学力の悩み・不安は、塾などに相談する
私自身が高校に行かなくなってから大学受験までの間で、心配だったのはやはり「学力」でした。学校で習っていないところを網羅できるかどうか、そして正しく理解できているのかが不安でした。
いまは「不登校の人たちが学び直せる塾」などがありますから、相談するのがよいと思います。
志望校の情報をチェックする
気をつけて行ってほしいのは、「受験の事務的な情報を早めに集める(願書の取り寄せなど)」ことです。関連して、オープンキャンパスや、直前の入試対策を行っている学校もあります。塾なども利用しつつ、アンテナを立てて、志望校の情報をチェックしてほしいと思います。
私の当時はインターネットもなく、情報が入りにくかったですが、いまはネットで情報を集められます。また、塾などでも確認できるはずです。
不登校からの大学受験で気にしなくていいポイントに関する講師からのアドバイス
この章では、不登校状態にある人や不登校を経験した人などを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾の知見に基づき、不登校からの大学受験で気をつけるべきポイントに関する講師からのアドバイスを紹介します。
西島智裕講師からのアドバイス
大学(の人たち)に馴染めるかは気にしなくていい
気にしなくてよいポイントの一つに、「大学(の人たち)に馴染めるか」があります。
「全員と馴染める」とは言いません。ですが、大学の中にはさまざまなコミュニティがあります(授業、ゼミ、研究、サークルなど)。そのため、不登校を経験したかどうかに関係なく、「気の合う仲間がいるコミュニティ」は、中高時代よりも見つけやすい(築きやすい)と思います。
補足として、大学生活中の人間関係は、大学の外にも築けます(アルバイト、ボランティア団体、趣味関係など)。学校を超えた多種多様な人とのつながりも、中高時代よりもずっと見つけやすくなります。
①勉強は、教科書の順番どおりに進めなくてもよい
中学や高校の授業では、教科書を最初から順に進めていくと思います。ですが、自分で勉強する場合は、順番どおりに進めていく必要はありません。関連あるところをまとめて、あるいは、とっつきやすい範囲から開始することは、とても効率的です。
例えば、数学。三角比(数I)を学習した後、他の数IAの範囲は飛ばして、三角関数(数II)を進めてもよいと思います。また、社会や理科は、興味のあるところから教科書や参考書を読み始めるのもアリです。
②不登校経験は、就職活動への悪い影響はない
不登校中の生徒さんや不登校の経験がある生徒さんからよく聞く話に、「不登校の経験や浪人の年数が就職活動に影響しそうで不安」があります。
私は、キズキ共育塾の講師以外に、上場企業の人事部の採用業務にも従事しています。そんな私の経験から言うと、不登校や浪人の経験は、就職活動においてネガティブに働くことは決してありません。
就職の選考において、選考する側が見るのは、「そのとき」のあなたと、あなたのポテンシャル・将来性だからです。
ただし逆に、過去の経験(不登校や浪人の経験)は、伝え方次第で、有利に働かせることは可能です。「過去」は「いま(そのとき)と未来」につながっています。つらかった・悩んだ・他の人よりは時間がかかった「けれど、将来に向かって努力した」、そんな「成功体験」として伝えられれば、相手には魅力として映るからです。
他人との比較でつらくなるなら、ライバルを意識しなくていい
何かに取り組むとき、よくライバルがいるといいと言われます。たしかに、大学受験でもライバルがいることで勉強しようと意欲が出てくる場合もあります。ただしそれは、受験生みんなに当てはまることではありません。比較することで、自分のできていないところにばかりに目が向き、つらくなるパターンもあります。
ライバルがいると意欲が湧くのは、自分と相手を比較してもっとがんばろうと思うからです。比較することを通して、自分がもう一歩進むためには何が必要なのかを知って前に進むのです。
ですから、もし、あなたが比較してつらく感じているのなら、他人との差は気にしなくて大丈夫です。大切なことは、自分ができているところをまっすぐ認めてあげて、次は何が必要なのかなと考えて、少しずつ進んでいくことだからです。
不登校でも、総合型選抜で進学できる
不登校の人でも、総合型選抜の利用は可能です。大学進学をしたい理由に、不登校の体験が動機になっている場合もあると思います。総合型選抜を利用する際、不登校の体験を「今後」に結び付けることで、アピールポイントにすることも可能です。
例①情報系での志望理由→
中学・高校と、病気になって外出が難しい時期があったが、オンラインツールで授業を受けられたし、人とつながれた。今度は自分が役に立つアプリを開発したい。
例②教育系・心理系での志望理由→
一時期クラスになじめず不登校になった。そのとき、どこにも居場所がなくて本当につらかった。私がカウンセラーになって、全ての学校に、教室以外の居場所をつくりたい。
あなたの体験や思いに共感する人はたくさんいると思います。
不登校から大学受験・進学をした講師の体験談
この章では、不登校から大学受験・進学をしたキズキ共育塾の講師の体験談を紹介します。今後のご参考にぜひご覧ください。
F.N講師の体験談
私は、中学校は1年ほどしか通っていなくて、高校は単位制のところに行っていました。大学進学を目指したのは、「家族全員大学を出ているし、行くのが当たり前」みたいな感じだったので、そこまで深い理由はありませんでした。
高校は、自宅の最寄りから電車で7駅ほど離れたところでした。そのため、電車の中でたまに中学校の同級生を見かけることがありました。別に話しかけるわけでもなく、気づかれたら気づかれたでいいやくらいにどっしりと構えていましたが、それでもやはり、誰も知り合いがいない場所への憧れはありました。そのため、大学は、地元から離れたところを選び、思い切って一人暮らしを始めました。
いまでは、地元にいた頃には全く考えていなかったような新たな目標もでき、それなりに楽しく過ごせているます。大学に進学してよかったなと思います。
S.T講師のアドバイス
並走してくれる大人を見つける
中学の3年間は全く学校に行かず、通信教材で勉強をしていました。その期間に自習の習慣とやり方を身につけられたことは、大学受験の際にも大きな助けになりました。一度自習の方法を覚えてしまうと、「試験勉強は一人でやるのがいちばん効率がいい」と感じることも少なくありません。
意見交換や議論は集団授業でないとできません。ですが、理解や知識の定着を目指す学習は、自分がわかる部分は飛ばし、わからない部分には時間をかけられる個別授業や個人学習のほうが無駄がない(ことも多い)のです。
ただ、自分の意志で自習を続けるには、勉強を習慣化することやモチベーションの維持が必要になり、継続が難しいこともあるかと思います。また、どれくらいのレベルを目指して、どんなペースで、どんな勉強をしたらよいのか、自分で計画を立てられるようになるまで、私も時間がかかりました。
そんなときには、進捗状況を把握し、並走してくれる大人を見つけることがオススメです。不登校の人に向けて学習支援を行っている機関はたくさんあります。進み具合を知ってもらうことでモチベーションが保てたり、ペース配分を一緒に考えたりができると思います。
私は講師を務めていますが、キズキの授業時間も限られたものなので、すべての勉強を見守ることはできません。なので、「勉強そのもの」だけではなく、「勉強のやり方」をお伝えすることで、自分で自分の力を伸ばせるようお手伝いしたいと考えています。
「不登校は受験に不利」と感じることもあるかもしれません。ですが、私にとって不登校を経たことは、余計なプレッシャーを感じることなく自分のペースで勉強できるようになり、受験においてもプラスに働きました。目標は「受験」や「合格」かもしれませんが、ぜひ「学ぶ」ことそのもの、その過程も楽しんでみてください。
まとめ:不登校でも大学受験に挑戦できます

中学校・高校不登校でも、大学に行きたい気持ちがあれば、ルートはたくさんあるため、大学受験に挑戦できます。
また、「不登校の経験」があるからといって、大学受験で不利になることはありません。
とはいえ、「大学に行きたい」「大学受験に挑戦したい」と思っていても、実際に行動に移すとなると難しいと感じる人は多いと思います。
そういった人は、まず「今、不登校でも大学受験はできる」と理解・安心した上で、「より自分に合ったルート」を探してみてください。
そして、何度も繰り返すとおり、詳しい人に相談することがとても大切です。
あなたがこれから「よりよい道」を見つけられることを、祈っています。
さて、私たちキズキ共育塾は、お悩みを抱える方々のための個別指導塾です。
生徒さんには、不登校の当事者・経験者も大勢いらっしゃいます。
授業では、勉強の話に加えて、進路の話や「どうやって大学受験を目指すか」といった話も可能です。
ご相談は無料ですので、気になるようでしたら、キズキ共育塾の概要をご覧の上、ぜひお気軽にご連絡ください(親御さんからのご連絡も受け付けています)。
/Q&Aよくある質問