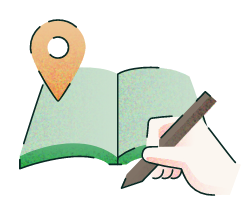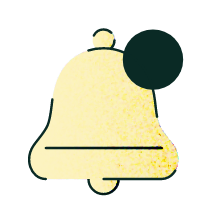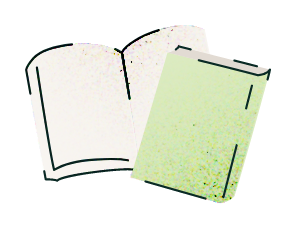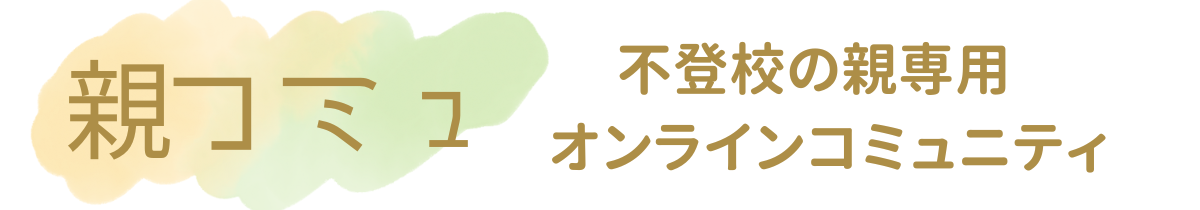不登校の子どもが勉強しない理由 親ができる対応を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
このコラムをお読みのあなたは、勉強しない不登校状態のお子さんについて、以下のようにお悩みではありませんか?
- 子どもが不登校になって勉強しないが、将来は大丈夫だろうか?
- 不登校になってからゲームばかりしていて勉強しない…親としてどうするべき?
- 勉強が遅れると進路・将来に影響しないだろうか?
- 通塾や家庭教師を子どもに提案したが断られた
しかし、「子どもの将来が心配…不登校で勉強しない状態を何とかしなければ!」とあせる必要はありません。
お子さんが不登校で、勉強しない期間があったとしても、その間の勉強の遅れを取り戻すことはできるのです。
このコラムでは、不登校の子どもが勉強しない理由や親ができる対応、勉強を再開するステップ、勉強を再開したきっかけ、勉強を再開する方法について解説します。
あわせて、キズキ共育塾の講師からのアドバイスやキズキ共育塾の講師の体験談、不登校の子どもが勉強を再開した事例を紹介します。
私たちキズキ共育塾は、勉強しない不登校状態にある子どものための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
勉強しない不登校の子どもでも勉強の遅れは取り戻せる

まず結論から言うと、勉強しない不登校の子どもでも勉強の遅れは取り戻せます。
勉強は、学校へ行く、行かないに関わらず、お子さんの進路や将来の可能性を広げる上で、大きな助けになることは間違いありません。
そのため、「子どもの勉強しない状態を何とかしたい」という親御さんの気持ち・心理は、とてもよくわかります。
ですが、勉強を再開するタイミングを見誤ったり、勉強にあたっての適切なサポートがなかったりすると、実践は難しいものでもあります。
また、不登校になると、学校に行っていた頃と比べて、どうしても勉強へのハードルが高くなります。
学校に行っている場合、学校に通い授業を受けることで、自然に勉強に取り組めます。しかし、不登校で勉強を進める場合は、主体的に準備を進めて取り組まなくてはなりません。
勉強しない期間があると、確かに、追いつくために多少時間は必要です。ですが、勉強が再開できれば、その遅れは取り戻せるものです。
例えば、学校の集団授業ではクラス全体に合わせた進度になりますが、自分に合った勉強方法を見つけられれば、不登校であっても自分に必要なカリキュラムに沿って効率的に勉強を進めることができます。
勉強の遅れ自体は過度に心配しなくても大丈夫なのです。
実際にキズキ共育塾の講師である筆者が担当する不登校状態にある生徒も、自分のわからない部分から順番に勉強していくことで遅れを取り戻していきます。
学生時代に不登校を経験した筆者自身の場合で言えば、自分で考えながら勉強することで、遅れを取り戻すだけでなく独学する力が身につき、勉強の楽しさも知りました。
子どもが勉強を再開するために、親御さんができることもあります。それは、勉強を再開するタイミングとサポートを見極めることです。
タイミングを見極めることで、勉強再開はうまくいきます。そして、親御さんが適切なサポートを行うことで、お子さんの勉強のやる気が継続しやすくなるはずです。
大切なことは、「遅れているから勉強を早く再開しなければ」と焦ることではなく、「勉強をしてみよう」という気持ちやパワーが湧いてくるような心の状態にしていくことです。
勉強しない不登校の子どもに親ができる対応については、こちらで解説します。
不登校の子どもが勉強しない7つの理由
この章では、不登校の子どもが勉強しない理由について解説します。
ただし、ここで紹介する理由は不登校の子どもが勉強しない理由のうちの一部です。実際のあなたやあなたのお子さんに当てはまらない可能性もゼロではありません。
あくまで参考としてご覧ください。
前提:理由の特定を焦りすぎない

まずは、勉強しない不登校状態のお子さんの心の状況について整理して、理由の特定を焦りすぎないようにしましょう。
学校に行けなくなったり勉強をしていない様子を見ると、「何があったの?」「理由を知りたい」と感じるものですが、子どもたち自身も、自分でもはっきりと理由が分からないことも多いのです。
「なんとなく元気がでない」「なんとなくやる気になれない」という気持ちしか実感できないことも多いでしょう。
不登校になったり、勉強しない状態に至るには、子どもたちそれぞれに固有で複雑な事情が絡み合っています。
「これが理由だ」と決めつけず、それぞれの置かれている状況を色々な視点から冷静にみていくことが大切になります。
理由①心のエネルギー不足
不登校で勉強しない状態になるにはさまざまな理由がありますが、基本的に共通しているのは、心のエネルギーが不足している状態ということです。
自分で意識する、しないに関わらず、日々の心配事や不安な気持ち、違和感や緊張感などが少しずつ蓄積し、限界まで頑張っていると、ある日、自分でもどうしようもないけれど心と体が動かないといったことが起きてきます。
つまり、色々なことをこなしたくても、通学や勉強などのさまざまな活動ができない心の状態になっているということです。
同じ出来事でも、感じ方や感性は人により異なります。
ほかの人から見たら些細に思えることでも、自分でも無意識であったとしても、大きな負荷となり本人に降りかかっていることもあるでしょう。
「元気に学校に通いたい」「勉強したりしたい」と思っているのに、気力がわかず、自分でも困っているという状況が不登校です。
この状態は心のSOSであり、今の状況によって自分の身を守れているということでもあります。ここからどうしていくかという前向きな視点で考えていきましょう。
それぞれに応じた、心のエネルギーを回復するサポートをするようにしていきましょう。
理由②勉強への苦手意識
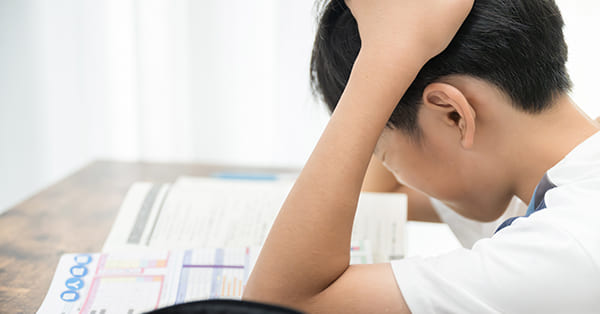
さまざまな経緯で、勉強に対する苦手意識やマイナスイメージを持っている場合もあります。
もともと勉強が苦手だったり、頑張ってもうまくいかなかったりという経験を繰り返していると、勉強といえば「怒られるもの」、「みんなの前で恥をかくもの」といったイメージが定着していることがあります。
「勉強をしなければ」という気持ちがあっても、苦手なものをこなすのは誰しも相当なエネルギーを必要とするため、なかなかやる気も起きなくなります。
反対に、勉強が得意であっても、自分にとってつらいものになっている場合もあります。例えば、以下のようなケースが考えられるでしょう。
- 親御さんが成績に関して非常に厳しい
- 膨大な宿題を課したりする学校に通っている
- 成績によるクラス分けなどで学校生活を楽しむような状況ではない
特に高校生の場合、勉強内容が難しくなるうえ、単位を取得できないと留年になることもあり、勉強面で困っていることが本人の大きな心の負担になっていることもあります。
加えて今後の進路や将来の就職なども考える時期になるため、家族からのプレッシャーを感じている場合もあるでしょう。
まずは勉強に対してのマイナスイメージを減らしていくことから始めましょう。
理由③勉強する必要性を感じていない
学校は、時間割に沿っていれば気づいたら勉強しているという環境です。勉強する意味などを特に考えなくても勉強をすることができます。
しかし、学校に通っていないと、時間割や宿題がないために、常に自分で自分を律する必要が出てきます。
また、自然に進学や受験を意識する環境にいないため、勉強する意義を自ら作り出さないことには、勉強する意味や必要性を感じられなくなることも多くあるでしょう。
さまざまなことに意欲が出る段階になってきたら、進学や受験のためではなく、自分の関心のあることを調べることから始めてみましょう。
理由④勉強の仕方が分からない
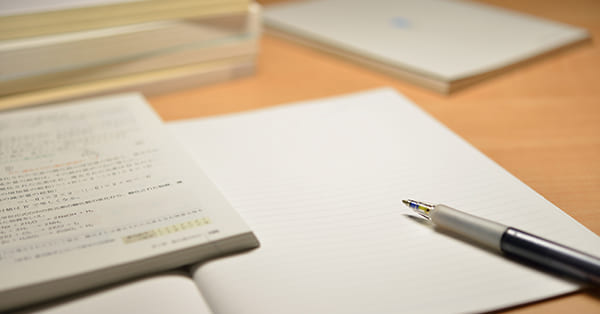
勉強をする気持ちがある場合でも、想像するよりも実際にはさまざまな準備が必要になってきます。
自分の現状を把握し、足りない部分を見極め、目標を決め、計画を立て、必要なテキストをそろえ、1日のスケジュールを決める。全てをひとりで行うのは大変難しいことです。
テキストひとつとってみても、膨大なテキストのなかから、どれが自分の必要なレベルに合ったものかを見極めることは簡単ではありません。
そもそも、どういった勉強方法なら頭に入りやすいかなども考える必要が出てきます。
このように、実際に手を動かすまでにはたくさんのハードルを超える必要があります。せっかく勉強する気があっても、方法を探しているうちにやる気が削がれることもあるでしょう。
全て自分でやる必要はありません。気軽に勉強方法などもさまざまな場所で相談していきましょう。
理由⑤子どもの特性と学習方法が合っていない
発達障害がある場合、一般的な学校生活では、気付かれないだけで本人には相当な負担がかかっているということもよくあります。
発達障害の特性が強く現れていれば、周りも気が付き、配慮してもらえる場合もありますが、本人や家族でも気付かない程度の特性がある場合もあります。
このような状況だと、自分でも理由が分からないまま、周りに理解してもらえないという悩みを常に抱えることになります。
「教科書の字をうまく追えない」「漢字の形を捉えづらい」「クラスメイトや先生とうまくコミュニケーションがとれずに孤立している」などの様子がある場合には、勉強にも大変な負荷がかかっていることがあります。
気になる場合は、発達障害の特性によるものである可能性がないか、専門家に相談してみてもよいでしょう。
理由⑥学習環境が整っていない

勉強したい気持ちがあっても、机の上にテキストを置くスペースもなかったり、机のまわりに気が散るものがたくさんあったりすれば、誰しも集中できないものです。
パソコン、スマートフォン、タブレット端末など、直接勉強に関係のないものにもすぐアクセスできる環境も、勉強しない理由になるでしょう。
それは本人の意志が弱いのではなく、誰しもそうだと思います。
勉強しようと思ったときに、集中できる環境が整っているかどうかは案外重要です。
きちんとした服装をすると何となくきちんとした気分になるように、かたちから入ると自然に気持ちも変わってくるものです。
まずは集中して勉強できる環境について考えてみることから始めましょう。
理由⑦生活リズムが崩れている
朝、登校する時間に間に合うように起床できないと、学校に行きづらくなるきっかけになりえます。
起床できない理由には、以下のような事情があるでしょう。
- スマートフォンやパソコン、タブレット端末などを夜遅くまで見ている
- ゲームを遅くまでやっている
- 起立性調節障害がある
起立性調節障害である場合には、自分でも理由も分からないまま起きられずに困っています。専門医に一度見てもらう必要があります。(参考:NHK健康チャンネル「起立性調節障害」)
スマートフォンやゲームをなかなかやめられない場合は、ほかに関心が持てるものを一緒に探したり、一緒に使い方のルールを決めるなど、本人の気持ちを聞いたり、話し合いから始めましょう。
ゲーム依存の状態になっている場合は、早めに病院に相談することが必要です。(参考:NHK健康チャンネル「やめられない怖い依存症!ゲーム障害はひきこもりの原因にも 治療法について」)
補足:病気や精神障害の可能性もあるため、専門の医師への相談も検討しましょう

気がかりなことや困っていることがあると、誰しも体調を崩したりやる気がなくなることがあるものですが、そういったものとは明らかに区別する必要がある体調不良もあります。
うつ病や強迫性障害、不安障害、起立性調節障害、統合失調症などの病気や障害によって、エネルギー不足になっている子どももいます。
歯磨きや入浴などの必要最低限の日常生活も難しくなってきている場合や何か気がかりな症状がある場合、単なる体調不良と区別するためにも、一度しっかりと専門の医師に相談することをオススメします。
勉強しない不登校の子どもに親ができる7つの対応
この章では、勉強しない不登校の子どもに親ができる対応について解説します。(参考:佐々木正美『続 子どもへのまなざし』、明橋大二『見逃さないで!子どもの心のSOS 思春期にがんばってる子』)
対応①子どもの気持ちを理解する
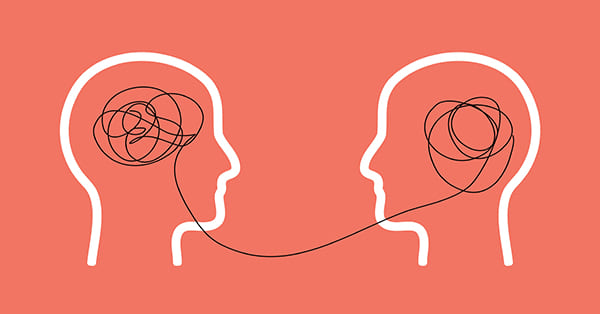
まず必要な対応は、子どもの気持ちを理解することです。もちろん、子どもの気持ちを理解することは、簡単なことではありません。
親子でも、感性や考え方がまるきり違うこともあるということに直面すると、実際にはすぐに納得できないことも多いからです。
例えば、「勉強は大事」というような、親にとって当然こうすべきという主張は、一般的には理にかなっていることも多いかもしれません。
しかし、子どもは不登校になるほどに、エネルギーを消耗している状況です。
そのため、子どものためと思って親御さんの考えを理解させようとするよりも、「子どもの気持ちを理解する」「心のエネルギーを回復するサポートをする」という道のほうが実際は近道です。
「自分の気持ちを理解してくれる」「自分の感じ方を理解してくれる」と子どもが感じることができれば、とても安心し、エネルギー不足だった心も少しずつ確実に回復に向かいます。
心にエネルギーをためることができれば、それがすぐに学校に登校したり、勉強に向かう、というかたちではなかったとしても、「さまざまなことをやってみよう」「やってみたい」という気持ちにつながります。
キズキ共育塾に通う不登校状態にある生徒さんや不登校を経験した生徒さんからは、以下のようなことをよく聞きます。
- 登校時間になると緊張してくる
- 登校時間になると親からのプレッシャーを感じる
- 学校に行けないことに罪悪感を感じる
- 学校に行けない自分はだめだと感じる
- 学校へ行きたい、でも行けないからつらい
- 友達や先生の目が恐い
- 勉強が遅れていて不安
このように、子どもたち自身は、親と同じようにさまざまな不安や恐怖を抱えています。
まずは一旦、親御さんの希望や要望、主張や提案をすべてやめてみて、「子どもの気持ちを知ろう、理解しよう」というところからスタートしてみることが必要です。
対応②子どもの気持ちに共感する
子どもの気持ちを知ることができた、または、できなかったとしても、「いま学校に行けないくらいの心の状態なのだな」と理解することができたら、次は子どもの気持ちに共感してみてください。
親であれば誰しも、「学校へ行くのは当然」「勉強はしっかりするべき」という気持ちがあります。
その気持ちに蓋をしようとしても、心から「行かなくても大丈夫」「勉強しなくても大丈夫」と思っていないと、表情や態度に不満が出るものです。
「休んでいいよ」と言いながらも、学校に行かない子どもに対する不安やいらだちが態度や表情に出ていると、「学校に行きなさい」と言っているのと同じように子どもに伝わります。
今は子どもをサポートする大事なタイミングだと考え、「学校に行かなくても100%大丈夫」と、安心させることに注力していきましょう。
子どもが今は学校に行かないという状態を認めて、「今はそういう気持ちだよね」とただ共感するということが必要になってきます。
もちろん、「学校に行ってほしい」「勉強してほしい」という親御さんの気持ちを無理に押さえ込む必要はありません。
ただ、その気持ちは置いておいて、「今のあなたの気持ちや考えは理解しているよ」「安心してね」「これまで頑張ったね」というような、子どもへの共感の気持ちがあれば大丈夫です。
その余裕を持つためにも、親御さんご自身の生活を充実させることも大切です。
子どもの気持ちを理解した上で共感することが、一番のサポートと言えます。
対応③リラックスできる環境づくり

不登校になったり、勉強する気持ちもおきないというときは、心が疲れきっているときです。
知らず知らずのうちに、気を使ったり、心が緊張して、糸が張り詰めている状態です。
学校でも緊張し、家でも緊張していると、リラックスできる場所は自分の部屋だけになります。外に向かうタイプであれば、家と学校以外のどこかということになってきます。部屋がない、外にも行けない場合には、どこにもほっとする場所がないということになってきます。
本人にとって、心からリラックスできたり、ほっと息をつける場所、緊張しないでいられる場所がないと、なかなか心が回復していきません。
まずはリラックスできる環境づくりをしていきましょう。可能であれば、本人のいる家をリラックスできる環境にしていくのが一番です。
その場合に大切なポイントは、悪気なくしている親御さんからの指示や提案、干渉をやめてみることです。
「これしたら?」「今日どうだった?」などの答えを求める質問や、「これをしなさい」といった指示でもなく、「今日こんなことがあったよ」「これがおいしかった」というような他愛もない話を気楽にするようにします。
子どもが何か返してきたり、自分から話してくれたら、関心をもって聞くなど、子ども主体のリラックスしたものにしていきましょう。
子どもが何か話したら、すぐに意見やアドバイスを言いたくなるのが親心かもしれませんが、「そうなんだ」と楽しく聞くだけで十分です。
緊張感のない、リラックスしたやりとりを目指しましょう。
普段からあまり会話がない場合には、挨拶するだけでもよく、無理におしゃべりする必要もありません。
肩ひじ張って会話を頑張るよりも、「今日寒いね」といったような一言でも、あたたかい気持ちで自然なやりとりをするほうが効果的です。
これらのことは実際やってみるととても難しく、つい指導、正論を言いたくなります。
親御さん自身も練習が必要なはずです。全てを完璧にやろうとせず、失敗しながらやっていこうという気持ちでやってみましょう。
目指すポイントは、お互いに気を遣わずに、リラックスした気持ちでいられること、こちらから発信は控え、向こうからの発信をゆっくり待つことです。
学校には行っていないけれど、家族とのコミュニケーションがスムーズで、気を遣わずリラックスでき、穏やかに毎日を過ごせているという状態が理想的です。
親子で一緒に何かをするというのも大変効果的です。
特に話さなくても、「一緒に買い物に行く」「一緒に料理をする」「一緒に子どもが好きなゲームをしてみる」など、気軽に楽しくできそうなことを行ってみてはいかがでしょうか。
対応④生活リズムを整える
家で普通に過ごせるようになってくると、子ども本人から「これがしたい」と言ってくれることも出てきます。もし、本人がしたいことがあれば、それを組み込んだ生活リズムを意識していきましょう。
何もなかったとしても、気にせず、少しずつ生活リズムを作っていくようにしてみてください。
朝起きて、ご飯を食べて、一緒に何か活動をし、お風呂に入り、歯磨きをして、寝る。
活動は何でもかまいません。家族に合った生活リズムをつくり、それに沿った生活を毎日していくのに慣れるようにします。
活動の中身が家事の手伝いなど家族のためになるものであれば、よりよいですが、本人にやりたいことがあればそれを優先します。
最終的には、学校の時間が、何かの活動に置きかわる以外は、学校に行っているときと同じ生活リズムになるようにしていければ理想的です。
また、スマートフォンやタブレット端末との付き合い方は親子で考える必要があります。
大人でも、必要がなくてもずっと見ているという状況になりがちなものです。子どもたちであれば、そうなるのは当然であり、子どもたちのせいではありません。
親御さんが一緒にルールを決めていく必要があるでしょう。近くにあると誰でも気になるものなので、夜この時間になったら電源を切って親が預かる、この時間になったら使用できない設定にするなど、一緒に話し合いルールを決めていきましょう。
その際大切なことは、現実的に実践できそうなルールにすること、話し合いながら選択肢をいくつか提示し、最終的には子どもに決めさせることです。
対応⑤学習環境を整える

学習環境を整えておくことで、やる気になったときに、やる気を削がずにスムーズに勉強を再開することができます。
また、学校に行かないと勉強が遅れてしまうという気持ちを和らげることにもつながります。
家でリラックスして元気に過ごせるようになってきたら、「勉強はしなくていいよ」「休んでいていいよ」という雰囲気よりも「家でもやりたくなったらいつでも勉強はできるよ」という雰囲気のほうが、本人もいざやりたくなったときに言い出しやすいと思います。
「いまから勉強する!」と宣言しなくても、自然にスタートできる雰囲気がよいでしょう。
通信教育や学習塾の資料を前もって取り寄せておくのも効果的です。
関心が少し出てきたときにぱらぱらと見られるようになっていると、「学習塾に通いたい」と自分から言わなくても自然に始めやすいのではないでしょうか。
対応⑥学習方法を選ぶ
不登校の場合、どの程度カリキュラムの空白があるかは個人によりそれぞれ異なります。
今の自分の学習進度を把握し、空白を見極めるというのは、簡単なことではありません。
効果的に勉強をするには、自分に合ったテキストや勉強方法を探すことがとても重要になります。
しかし、テキストひとつとってみても、なんとなくやる気が出るものと出ないものがあったり、勉強方法も、楽手塾に通うのか、オンライン授業にするのか、通信教育なのか、家庭教師なのか、さまざまな選択肢から選ぶ必要があります。
一度で自分に合うものをひとりで見つけることはなかなか難しいものです。
合わなかったら違うものにしようという気持ちで、学習塾に相談したり、家庭教師やオンライン個別指導の体験を受けてみたり、少しずつ試していくサポートをしていきましょう。
対応⑦専門家や支援機関に相談する

不登校や勉強について詳しい専門家や支援機関に相談するのも効果的です。
相談先が近くにない場合でも、電話やメールで相談できることが多いです。ぜひ積極的に利用してみてください。
「どのように接するべきか」「登校再開を目指すべきか」「勉強のサポート方法」など、様々な知見を持った相談先を頼ることで、より具体的に見えてくるはずです。
まずは、お子さんの在籍している学校に相談してみましょう。学校には、担任の先生をはじめとして、お子さんの現状を把握している方々がいます。
ご家庭ではわからない学校での様子や、成績・出席日数などを踏まえた上で、具体的な対策を一緒に考えることができます。
先生以外には、スクールカウンセラーに相談することも可能です。スクールカウンセラーは、普段から生徒さんの心のケアにあたっている専門家です。先生とは異なる視点でサポートを行います。
また、先生やスクールカウンセラーが最寄りの支援機関を紹介してくれることもあります。
例えば以下のような、自治体などが運営する公的な相談窓口もあります。
- 児童相談所、児童相談センター
- 教育センター
- ひきこもり地域支援センター
- 発達障害支援センター
自治体によって名称や機能が異なる場合もあります。お住まいの自治体の相談窓口については、自治体の公式サイトや代表電話で確認しましょう。
その他にも、不登校の支援団体、親の会、フリースクール、不登校に詳しい学習塾などがあります。私たちキズキ共育塾もその一つです。これらの団体は、それぞれに独自の理念、支援方法、事例、ノウハウなどがあります。
「〇〇市 不登校 塾」「〇〇県 フリースクール」などとインターネットで検索すると、お近くの候補が見つかると思います。
見つけた団体の理念や支援がお子さんに合いそうでしたら、問い合わせてみましょう。
勉強しない不登校の子どもが勉強を再開したきっかけ4選
この章では、キズキ共育塾の生徒さんを指導してきた筆者の経験を踏まえて、勉強しない不登校の子どもが勉強を再開したきっかけについて解説します。
ただし、ここで紹介するきっかけは勉強を再開したきっかけのうちの一部です。実際のあなたやあなたのお子さんに当てはまらないかもしれません。また、紹介したきっかけで必ずしも勉強を再開するとは限りません。
あくまで参考としてご覧ください。
きっかけ①興味や関心のあることができた

勉強というと、すぐに学校の定期テストのための勉強や、受験勉強を連想するものですが、勉強にもいろいろなものがあります。
一度、テストのための勉強から離れ、さまざまな体験をしてみたり、自分の関心のままに調べ物をしてみると、新たな興味関心が生まれることもあるでしょう。
例えば、勉強とは関係がないように見えるテレビやゲームで考えてみても、海外のテレビドラマなどには、キリスト教文化の常識を知るとさらに楽しめる内容になっていたり、流行のゲームなどにも、歴史を知ることでさらに深く理解できるつくりになっていたりします。
そのような趣味をきっかけとして、宗教や歴史などを勉強してみようという気持ちになることもあるでしょう。
趣味などを楽しむためには、小学校から高校までの勉強知識が役立つこともあるのだと実感できると、やる気も出てくるのではないでしょうか。
勉強といえばつらいもの、テストのためのもの、ではなく、自分の楽しみのため、自分の知りたいもののため、といった方向で考えていくと、勉強をしたいという気持ちへの近道になるかと思います。
きっかけ②将来の目標ができた
学校や勉強に関する心配事から離れ、自分の生活を穏やかに安心して過ごすことに集中していくと、少しずつ色々なことに関心が出てくると思います。
その興味関心にしたがって、さまざまなことを調べていくと、「こんなことができたらいいな」「これをやってみたい」と感じることが出てくると思います。
将来の目標というと壮大なイメージが浮かぶかもしれません。そうではなく、「こんなことをいつかできたらいいな」「こういった分野に関われたらいいな」といった気持ちも十分に将来の目標と言えるでしょう。
もちろん、「この学校に入りたい」「この仕事をしたい」というような具体的な目標も、勉強のやる気に直結していきます。
そこまで具体的ではなくても、小さなことでも自分にとっての楽しみや希望が持てると、だんだんとやる気につながっていきます。
まずはさまざまなものを調べてみたり、好きなことや興味が持てるものはないか考えてみると、新たな気づきにつながるのではないでしょうか。
きっかけ③周囲からのサポートを受けた
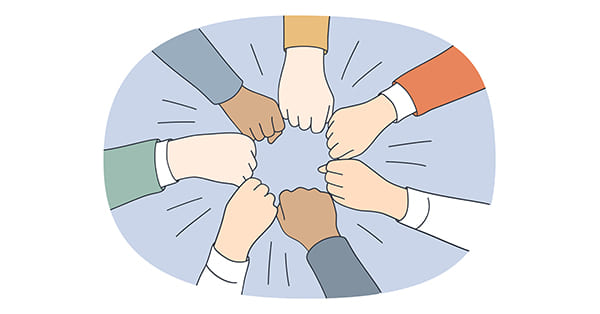
誰かに相談しようとすると、分かってもらうために色々と説明しなければなりません。そのうえ、説明しても理解されないこともあると思うと、「サポートを受けるほうが大変だ」「自分ですべてやったほうが楽だ」と感じることもあるかもしれません。
しかし、単に今感じていることを聞いてもらうだけでも気持ちが変わってきたり、予想外に参考になる話を聞けたりすることもあります。
悩みを解決してもらうためというよりは、「何かの参考になるといいな」くらいの気持ちで、誰かと話をしてみると、やる気につながることもあるでしょう。
勉強に関して学習塾に問い合わせメールをしてみたり、勉強とは関係のない、自分の好きなことの話を聞いてもらったりすることでも、やる気につながることがあるはずです。
自分の関心ごとに興味をもってもらったり、例えば家族に一緒に楽しんでもらったりなどすると、心のエネルギー回復につながります。
「少し新しいことを聞けたらいいな」というくらいの気持ちで、周りに話をしてみたり、さまざまな相談機関に問い合わせてみたり、気軽にサポートを受けてみると、意欲が出るきっかけになることがあるでしょう。
きっかけ④成功体験ができた
成功体験というのは、なにかのコンクールで1位をとるなどという話ではありません。「自分でやると決めたことを自分で達成する」体験のことも十分な成功体験です。
それは日常のどんなことでもかまいません。
「朝7時に起きる」「朝ごはんを食べる」「朝外に出て太陽の光を浴びる」「読書を5ページする」「英単語を5つ覚える」何でも大丈夫です。
大事なことは、人から指示や提案をされたものではなく、自分で決めたことであること、自分でやり遂げることです。
毎日1つずつでも小さな成功体験を積み重ねていくと、必ず自信になり、やる気が出てきます。
その気持ちを積み重ねていくことで、勉強にも気持ちが向いてくるきっかけになります。
もちろんこれらも、周りのサポートを受けながら少しずつ達成していけばよいでしょう。
勉強しない不登校の子どもが勉強を再開する4つのステップ
筆者の経験からすると、不登校によって勉強しない段階から、勉強を再開するまで、4つのステップがあると考えています。
この章では、勉強しない不登校の子どもが勉強を再開するステップについて解説します。
ただし、不登校状態にある子どもが全員同じステップを踏むとは限りません。あくまで参考としてご覧ください。
ステップ①安心して元気で過ごせている

勉強も含めて、何か行動を起こすエネルギーを得るためには、お子さんの健康状態が良好であることが大切です。
まずは、体調がよかったり、心理的に安定していたりしそうかを確認してみてください。
逆に、心身ともに健康な状態でないにも関わらず、無理に勉強を再開すると、長く続かなかったり、勉強を嫌いになったりすることがあります。
お子さんが安心して勉強を再開するためには、心理的に安定していて元気で安心して過ごせるようになることを優先することが大切です。
そして、元気で過ごせるようになるまでの間は、学校や勉強のことは気にせずに、お子さんの好きなことに安心して取り組める環境が必要になります。
テレビを見たり、ゲームをしたり、マンガを読んだり、ボーッと過ごすだけの時間も大切です。
筆者が学校を休み始めた頃は、何もやる気が起きませんでした。
しかし、学校のことを忘れてゲームをしたり、テレビで好きなスポーツ観戦をしていたりすると、少しずつですが心理的な余裕が生まれ、勉強にも気が向くようになりました。
ステップ②自発的に活動ができている
安心して元気で過ごせるようになったら、物事に自発的に取り組めているか、自発的に活動ができているかを確認しましょう。
「ゲームやスマホばかり触っているなら勉強してほしい」と思われることもあるかもしれません。
しかし、受け身的に何かを楽しむことと、勉強のように自発的に何かを行うことは、全くの別物です。
まずは、お子さんの好きなことでも構いません。自発的に活動できるようにサポートをしましょう。
例えば、簡単に始められるような習いごとに通うのもオススメです。
ステップ③一定時間集中して物事に取り組める

お子さんが自発的に活動できるようになったら、「一定時間集中して物ごとに取り組めるかどうか」を確認してみてください。
不登校で勉強を再開する場合、学習塾や家庭教師を利用することも多いかと思います。
その場合、授業は1時間〜1時間30分が基本となります。その間は授業に取り組めるだけの集中力が必要です。
ある程度の時間にわたって、お子さんが集中できる状態にあれば、勉強の再開はしやすくなります。
もしこの時点で、お子さんが好きなことや習いごとなど、自発的に何かに取り組んでいるのであれば、それを集中力の参考にすることもできるでしょう。
その取り組みを通して、「この子は集中力が養われてきたかな」「もう少し見守ることが必要かな」と、勉強再開に向けての目安にしてみてください。
ステップ④勉強の話題を出しても嫌がらない
自発的に一定時間集中して物ごとに取り組めるようになったら、勉強再開まではもうすぐです。
最後に確認しておきたいのは、「勉強の話題を出しても嫌がらないかどうか」です。
勉強と聞くと学校のことを思い出して、気分が悪くなったり、心理的な負担が大きくなる場合もあるのです。
勉強の話題を嫌がるうちは、無理強いすることなく、勉強を再開することは控えておきましょう。
好きなことを通じて学校以外の居場所ができたり、習いごとを通じて自己肯定感を持てるようになったりすると、勉強にも自然と取り組めるようになっていきます。あせらずに待ちましょう。
また、勉強の再開を提案する際は、決して押しつけにならないよう注意してください。
「そろそろ勉強しなさい」と押しつけるのではなく、「勉強やってみる?」と本人が「やる」か「やらないか」選べるような形がよいでしょう。
その際は、すぐ取りかかれるような問題やコンテンツを用意しておくと、「勉強できた」という小さな成功体験を積むことができるのでオススメです。
補足:不登校で勉強しない子どもの勉強再開に関しては、専門家や支援機関に相談しましょう

不登校状態にあるお子さんが勉強を再開するタイミングを親御さんだけで見極めることは非常に難しいはずです。
なぜなら、不登校状態にある子ども全員が、勉強再開に向けて同じステップを踏むとは限らないからです。
勉強再開に向けて長い時間が必要な子どもがいれば、短期間で勉強に対して意欲的になる子どもがいたりと、そのステップの踏み方もさまざまです。
また、親御さんは勉強の専門家でも不登校の専門家でもありません。
不登校からの勉強再開に詳しい学習塾などを利用することで、実際のあなたのお子さんにとっての適切なタイミングがわかると思います。
私たちキズキ共育塾では、多くの不登校を経験した生徒さんを受け入れています。無料相談も行っています。ぜひお気軽にご相談ください。
勉強しない不登校の子どもが勉強を再開する方法6選
お子さんが勉強できる環境を整える際、適切なサポートがあれば、今後のお子さんの勉強に取り組む姿勢や意欲につながるでしょう。
この章では、キズキ共育塾の生徒さんを指導してきた筆者の経験を踏まえて、勉強しない不登校の子どもが勉強を再開する方法について解説します。
不登校中の勉強法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
方法①家庭教師

お子さんが学校以外の外出も苦手な場合、家に来てくれる家庭教師がオススメです。
周りの目も気になりませんし、勉強が遅れていても自分のペースに合わせて学習できます。
ただし、集団の授業とは異なり、1対1の指導になるので、講師との相性が大切です。
まずは、体験授業を申し込んだり、不登校の支援実績がある家庭教師のサービスを検討してみたりするとよいでしょう。
方法②学習塾
外に出ることが問題ないのであれば、学習塾もオススメです。
学習塾は勉強のサポートとしてだけでなく、決まった時間に決まった場所に行くことで、生活リズムを安定させることにもつながります。
また、オンライン授業を受けることができる学習塾もあります。通塾よりは気楽に始めることができるかもしれません。
集団指導の学習塾だと遅れを気にして入りにくい場合は、個別指導の学習塾がオススメです。
私たちキズキ共育塾のように、不登校の子どもをサポートする学習塾もあります。まずは相談してみてください。
方法③フリースクール

お子さんによっては、フリースクールが選択肢の一つになるかもしれません。
フリースクールとは、何らかの理由から学校に行くことができない子どもたちが、学校の代わりに過ごす場所のことです。
民間の教育機関であるため方針はさまざまであり、基本的には学校に代わる学びの場を提供しています。
フリースクールは、勉強だけでなく、同世代の友人との交流の場にもなります。不登校の間に家庭外でのコミュニケーションが不足している場合には、それを補える場になるでしょう。
ただし、お子さんが集団生活が苦手で不登校になったという場合は、フリースクールに通うことで、再度ストレスを抱える可能性も考えられます。
まずは、気になるところがあれば、実際に訪問して話を聞いてみてください。
方法④通信教育
好きな時間に、自分のペースで学習を進めることがお子さんに向いている場合は、通信教育を利用するのも一つの手段です。
1か月ごとに課題を設けている通信教育もあるため、お子さんも勉強の目標を設定しやすくなるはずです。
また、長時間は難しいが、少しずつなら勉強できるという場合でも、通信教育であれば、自分のペースで学習を進められます。
かつ、基本自宅で学習が可能なため、「近くに家庭教師や塾がない」「まだ外に出るのが難しそう」といった場合にもオススメです。
しかし、自分のペースで学習を進められる分、自発的に取り掛かるまでに、お子さんが苦労する場合もあります。
その際は、お子さんと「1日の中でこの時間は一緒に勉強しよう」と提案して、学習のサポートをするとよいでしょう。
方法⑤動画授業(Youtubeなど)

お子さんが「ひたすら机に向かって勉強すること」が難しい場合は、動画授業がオススメです。
用意された問題を解いたり、必要なことをノートに書いたりすることで、お子さんは体力と気力を消耗します。
その点、動画授業だと基本的には見るだけの作業になりますし、机の上でなくても勉強が可能です。
さらに、最近の動画授業は非常にレベルが高く、自宅にいながら質の高い授業を受けることができます。
動画はYouTubeなどでも手軽に探すことが可能です。お子さんが勉強に対して感じているハードルを比較的容易に取り除くこともできるため、勉強を再開するきっかけになるかもしれません。
お子さんが動画授業に慣れてきたら、参考書を読む、問題集を解くなど次のステップに進めるとよいでしょう。
方法⑥学習マンガ
学習マンガも動画と同様に、勉強に取り組みやすい方法です。
歴史や古典など、教科書では難しく感じる内容でも、マンガであれば理解しやすくなります。
「学研まんが」や「角川まんが学習シリーズ」など、さまざまな出版社が学習マンガを発売しています。
マンガを楽しみながら学習できるので、勉強再開のきっかけにもオススメです。
参考①:Gakken学習まんが
参考②角川まんが学習シリーズ
勉強しない不登校の子どもに関するよくある質問3選
この章では、勉強しない不登校の子どもに関するよくある質問を紹介します。
Q1.「勉強しなさい」と言わないと、1日ゲームばかり。大丈夫?

ゲームが理由で明らかな体調不良になっていない場合は、大丈夫です。
大人でも、どうしても疲れているときに、お菓子を食べたり、お酒を飲んだり、さまざまな気晴らしをします。それを突然とりあげられるとつらいものです。
今は心身を回復する時期なのだと考え、スマホやゲームだけで勉強していなくても見守ります。
できれば、親御さんも一緒にゲームなどできるとよいでしょう。
信頼関係ができてきたら、そればかりだと体調が心配だと伝えてみてください。
制限時間は子どもに決めさせ、少しずつ短くしていきましょう。
一緒に楽しめる活動の時間、ゲームやスマホ以外の趣味の時間、最終的には勉強する時間、を増やしていくことを目指しましょう。
Q2.「見守って」と言われても、進学や就職が不安です。このままで大丈夫?
結論から言えば、大丈夫です。
いくら進学や就職を心配しても、何かその行動によってプラスになることはありません。
まずは、「今は行く状況ではないのだな」「勉強する段階ではないのだな」と頭を切り替えましょう。
学校に行かせよう、勉強させようとするよりも、心のエネルギーを回復することに注力していきましょう。結局はそれが近道です。
しかし、「重大なトラブルに巻き込まれている」「専門の医師にかかるべき体調不良がある」「発達障害性の特性により困っていることがある」などのような様子が見られる場合は、対応が必要です。
トラブルに巻き込まれているようであれば、「あなたを怒ったり、責めたり、一切しない。なにかとても困っていることやつらいことがあるなら、何でも話してほしい。親はあなたの味方だ」といったことを真剣に伝えましょう。
明らかな心身の体調不良や長引く症状、気がかりなことがある場合には、すぐに専門の医師に相談しましょう。
発達障害の特性がある場合も、専門の医師に相談してみましょう。親御さん自身の調子が悪い場合も、第三者に助けてもらうことが必要です。
Q3.甘えている状態、怠けている状態とどうやって見分ければよいでしょうか?

学校に行ける自分でいたいけれど、行けなくて困っているのが不登校です。心がまとまったお休みが必要なくらい疲弊している状態です。
不登校は、『心のサーモスタット』が切れた状態。これ以上、心が壊れるのを防ぐための、自然な、正常な反応です。(参考:明橋大二「見逃さないで!子どもの心のSOS 思春期にがんばってる子」 )
基本的には学校にいけない時点で、甘えや怠けではなく、「いけないくらい疲れているのだ」と考えてみるべきでしょう。
ゆっくり話を聞いて、少し励ましと休養をもらえば行けるパワーが出る子どももいますし、回復期の場合には家ではとても元気なことも多いでしょう。
しかし、基本的に学校に行けない時点で、それは甘えや怠けではありません。
自分で意識する、しないに関わらず、日々の心配事や不安な気持ち、緊張などが少しずつ蓄積し、限界まで頑張った結果、心がエネルギー不足になり、学校へ行ったり勉強するなどのさまざまな活動ができない状態になっています。
そこから回復するまでの期間は、人により異なります。
数日で回復する子どももいるかもしれませんし、何年も必要な場合もあります。
休むことによって、自分の身を守れているということでもあるので、それぞれに必要な回復期間を経て、心のエネルギーが回復すれば、自然に行動に出てきます。
甘えや怠けとは考えず、本人に必要なエネルギー補充をすることが一番の近道です。
また、たとえ仮に甘えや怠けと言われるようなものであったとしても、本人の気持ちを聞いたり、心のエネルギーが回復するようなやりとりを心がけることが、それらの対応としても結局は有効な方法です。
勉強しない不登校の子どもについてキズキ共育塾の講師からのアドバイス

この章では、勉強しない不登校の子どもについて、不登校状態にある人たちのための個別指導塾・キズキ共育塾の講師たちからのアドバイスを紹介します。
実際に不登校状態にある人たちに勉強を教えている講師の生の声です。きっと参考になると思います。
また、私たちキズキ共育塾の無料相談では、実際のあなたのための、より具体的なアドバイスが可能です。ぜひご相談ください。
O.H講師のアドバイス
勉強するようになるためにはどうするべきか、絶対的な正解は正直ないと思います。自分の経験としては、以下の2つが大切」だと思います。
①ガミガミ言わない
これは基本だと思います。ガミガミ言うと、勉強しようと思っている子どもの心理的な負担となり、逆効果のように思います。逆に、勉強をしたらほめるようにしましょう。
②親自身の楽しみを持つ
親自身の楽しみを持つと、心に余裕ができます。そして、楽しんでいる姿は、子どもがしっかり見ています。親が楽しんでいれば、子どもは楽しみます。そして、勉強につながっていきます。
待つ姿勢を持つことが大切
私の経験を踏まえてお話しします。基本的に、親は待つ姿勢を持つことが大切だと思います。
私自身、予備校生時代にひきこもりのような時期がありました。それまでの人生で父から『勉強しろ!」と言われ続け、気づけばプレッシャーに弱くなり、厳しい現実に直面しないように逃げていました。
それが、予備校の先生が父に待つよう説得し、父がプレッシャーをかけず待つようになると、自分の意志で勉強に集中して取り組むようになれたのです。結果、私は志望する大学・学部に合格できました。
親が自分の子どもに厳しく当たりたくなる気持ち・心理は、子どもの将来を案じているからだと思います。ですが、まずは子どもを信じてみる、すなわち、つかず離れずの距離で見守りながら待つことができれば、子どもの自主性は育まれていくと思います。それは決して放置ではなく、見守る姿勢だと思います。
山本郁美講師のアドバイス
調子が悪いときに休む勇気を持つことが大切
以前担当した不登校状態の生徒さんが、勉強しない状態から勉強できるようになるまでの話をご紹介します。なお、これは個人の特定につながらない、よくある話です。
その生徒さんは、ひきこもり状態になり、大学受験を目指す決意はしたものの勉強が始められない状態でした。
授業開始当初は、昔の苦しかった受験勉強の記憶から「勉強を想起させる空間にいること」自体が苦痛との話でした。そこで、まずは教室内で時間を過ごすことを目標に授業を行いました。一人になれる休憩時間を多く取ったり、勉強とは関係ない雑談をしたり…と工夫を重ねるうち、教室で過ごすことへの不安が少しずつ減っていきました。
また、生徒さん本人が、「授業に1か月通う」「参考書以外の本を図書館で借りてみる」などの小さな目標(を自分で定め、クリアするごとに報告してくれました。
そういう流れを経て、約半年かけて、少しずつ勉強を始められるようになっていきました。
その様子を見ていて感じたのは、調子が悪いときに休む勇気を持つことの大切さです。実際に勉強していなくても、頭の中が「勉強しなくては」という考えでいっぱいになり疲れている…というパターンもあります。あせったときこそ、いったん頭を空っぽにさせる時間を確保し、「休むことも勉強の一部!」ぐらいの気持ち、心理的な余裕をもって過ごすのもオススメです。
教える側として有効だった方法は、生徒さんに不安を数値化してもらうことでした。授業の最初に「今日の調子は100点中何点か」と申告してもらい、その数値に合わせて授業内容やペースを変えていました。
村下莉未講師のアドバイス
丁度よいレベルの短期ゴールを用意する
お子さんが学校に行かない状況に不安を抱えて、「どうするべきだろう…」と不安に思われる人も多くいらっしゃると思います。
まず、勉強できる状況にない場合は、精神的に回復することが先決になるかと思います。
その上で、勉強できるようにするコツは、丁度よいレベルの短期ゴールを用意することです。オススメは英検や漢検などの資格試験です。まずは好きな科目や得意な科目から取り組むとやりやすいと思います。
岩間俊宏講師講師のアドバイス
勉強をテーマにした動画を利用する
YouTubeなどの動画サイトが、大きく発展・多様化しています。勉強をテーマにした動画もあり、その内容もさまざまです。「問題の解き方」「メンタル維持の方法」「参考書の使い方」「学習計画の立て方」などです。そしてもちろん、不登校を経験した人も動画を出しています。
自分に近い人間の体験談は新鮮であり、意欲向上にもつながります。
勉強の話を嫌がらない段階であれば、いきなり机に向かわなくても、そういった動画をご家族で一緒に見ることも、勉強しない状態を解決するために有効です。
ただ、向いてる勉強法は人によってさまざまです。すぐに「これを始めてみよう」とうながすのではなく、「こういうやり方は合いそう?」「もう少し他の動画も見てみようか」など、お子さん本人の意見も積極的に聞いてみてください。
S.T講師のアドバイス
以下の2つは、小学校3年生から中学校3年生の間、不登校を経験したで私が感じたことです。
①学校に行かないことは、学習にとって不利なことではない、むしろ効率的
②学校に行かないで楽しく過ごすことに罪悪感を覚えなくていい
もちろん、不登校の人全員に当てはまるとは限りません。参考としてご覧ください。
私自身はずっと通信教材を使用し、5教科の勉強をしていました。平日は毎日やっていました。午前中だけ勉強にあてていれば学校の進捗状況には十分追いついていました。
今はわかりやすい教材もたくさんあります。ですので、机に向かう習慣さえつけていれば効率的に勉強できます。わからないところは父にたずね、父が関心を持ったり褒めたりしてくれることが継続のモチベーションになっていました。
語学に興味があったので小5から5年間英会話教室に行かせてもらい、楽しく英語を学んだことが今でも役に立っていると強く感じます。午後はフリースクールで遊んだり、本を読んだりしていました。
学校に行くことだけが勉強の方法ではありません。むしろ、自習には「自分で先生を選べる」「自由時間が増える」「自習スキルが身につく」といったメリットがあります。
無理に学校のペースに合わせる必要もないと思います。関心のある分野をとことんやってみるのも面白いですし、勉強以外のことに興味があるなら勉強は最低限やっていればいいという考え方もあります。
私は勉強を習慣にしたことで「やるべきことはやった」という気持ちでほかのことを思い切り楽しめるようになりました。学校に行けない自分を責めたくなるときは、1日1時間だけ勉強するなど、少しでもなにかをやってみるだけでも心理的な余裕が出てくるかもしれません。
私の場合は父がサポーターとなってくれました。ですが、近い関係の人ほど衝突が起こりやすかったりストレスがたまることもあると思います。自習学習向けのサービスや、不登校状態にある人向けの学習塾などはたくさんあります。まずは気軽に相談して、利用してみることをオススメします。
保護者の人は「はやく勉強させないと」「学校に追いつかないと」とあせりを感じることがあるかもしれません。ですが、勉強はいつからでもできるということが、不登校を経験して、キズキ共育塾での講師を経験した私が感じていることです。お子さんのことばかり気にされていると、双方にとってストレスになります。保護者さんも自分の時間を持たれたりするなどリフレッシュして、ゆったり構えていただければと思います。
F.Y講師のアドバイス
本人が勉強を始めようとしない場合、その状況は一人ひとりでさまざまです。
どんな状況かによって、講師や周りの人の対応も変わってきます。私がこれまで担当した生徒さんたちのエピソードをもとに、いくつかのパターンと、その対応法をまとめてみました(個人の特定につながらない、「よくある話」です)。
以下の対応以外にもたくさんのパターンがあると思います。問い詰めたり責めたりすることなく、本人が何に不安を感じているのかを汲み取るとよいのではないかと思います。
①身体的な不安がある
意外と多いのが、そもそも身体的に勉強できる状態ではないケースです。特に、周りの人から症状が見えず、本人もそのことを言い出せない状態だとわかりづらいです。具体的には「勉強しようとすると目の焦点が合わなくなる」「聴覚過敏・光過敏がある」「腹痛や頭痛がある」などです
実際に症状が出ていることもあれば、「症状が出るのではないか」という不安に悩んでいることもあります。本来は眼鏡が必要なのに恥ずかしくて講師に言えず、文字が見えないのを我慢していた…というケースもありました。
有効だった対応法
・ストレートに「いま、身体的に勉強できる状態?」と尋ねる
・身体的な不安が把握できた場合、逃げ場所をつくる(例:「断りなくいつでもトイレに行ってOK」と声かけをする、教室内で本人が少しでも落ち着ける場所を一緒に確保したりするなど)
・勉強時間を短くする、休憩を多く入れる(例:本人に時間配分を決めてもらい、それに口出ししない、久しぶりに勉強する場合は、「勉強時間5分、休憩30分」のような時間配分でも大丈夫と伝えて安心してもらう)
②他にやりたいことがある
どの年齢の生徒さんにも多いのが、おしゃべりをしたいということです。
相談というより、勉強に関係ない他愛のないおしゃべりを楽しみたいという生徒さんが多いように思います。小学生だと、おしゃべりに加えて、一緒に遊びたい」いうのも多いです。
おしゃべりや遊びの欲求がある程度満たされると、自然と勉強に移行する場合があります。勉強以外でやりたいことを聞き取って、まずはそれに付き合うのも一つの手でしょう。
③とにかく強制されるのが嫌
勉強させようとする周囲の思惑を読み取って、嫌悪感を抱いたり抵抗したりするパターンです。
その場合、思い切って勉強の話を封印し、「やりたいという気持ちになるまで、勉強しなくていい。こちらから声もかけない。ただし、勉強したくなったらいつでもサポートするので待っているね」と伝えてもいいかもしれません。
④勉強がわからないのが怖い
それまで長い時間をかけて「勉強がわからない」という経験が積み重なっており、勉強が怖くなっているパターンです。
そういう生徒さんには、クイズ形式など遊びの要素を取り入れたり、簡単なレベルからゆっくりスタートしたりと工夫すると効果的でした。
⑤評価されるのが怖い
「×をつけられるのが怖い」「採点されるのが怖い」というものです。
「×をつけられるのが怖い」「採点されるのが怖い」という生徒さんもいました。そういった生徒さんには、以下の対応が有効でした。
・テストを想起させる形式の教材を使わない
・赤ペンなどで採点しないと約束する
・本人と話し合って、×の代わりに「惜しい!」などの言葉を使うようにするなど
不登校状態から勉強再開したキズキ共育塾講師の体験談
この章では、不登校状態から勉強再開したキズキ共育塾講師の体験談を紹介します。
同じようなお悩みが解決した事例はたくさんあります。ご安心ください。
また、私たちキズキ共育塾の無料相談では、他の事例の紹介なども可能です。ぜひご相談ください。
体験談①〜岩間俊宏講師の体験談〜

両親は、不登校状態の自分を無理に学校に行かせるようなことは決してしませんでした。
メンタルがつらいときは学校を休ませ、適度な距離を保ってくれました。そのためもあってか、心理的な余裕が生まれ、少しずつ勉強にも取り組めるようになりました。
自分の場合は学校にも通えるようになりましたが、いま所属している学校への、登校再開が最適解とは限りません。
転校や、高校生の場合は中退からの高卒認定取得などの他の選択肢もあるということを親子で共有することが大切です。その際は、新しい環境で気持ちを切り替えて、前向きな方向で話ができるとよいと思います。
中高生は多感な時期であるため、気持ちの浮き沈みも激しくなります。中には一時的なものもあります。あせらずに見守り、お子さんの話を聞いていただければと思います。
勉強しない不登校の子どもがが勉強を再開した事例
私たちキズキ共育塾には、勉強しない不登校の子どもの支援事例が豊富にあります。
この章では、勉強しない不登校の子どもが勉強を再開した事例を紹介します。
事例①生活にメリハリがでてきた〜西巻礼さん(小学校6年生)の親御さんの声〜

小学校を不登校で、学校以外の外出も苦手だった子ども。これからの進路に不安を覚えていたときに出会ったのがキズキ共育塾でした。
一人ひとりの個別のペースを尊重してくれそうだったため、入塾を決意。
子ども自身も先生と会うのを楽しみにして、生活にメリハリがでてきたように思います。
授業中には、勉強以外に子どもが好きなキャラクターの話を一緒にしてくれているようで、そういった面でも信頼しているようです。
事例②ここなら大丈夫と直感〜福本ちひろさん(中学校2年生)の親御さんの声〜
入塾に際しては、親である私自身が子どもと講師との相性を気にしていました。特に講師の方が尊敬できる人物であるかどうかを重要視していましたね。
というのも、子どもが不登校になった原因の1つが、当時の担任教師の不誠実な対応とそれに対する不信感の大きさだったからです。キズキ共育塾は、入塾までの対応の時点で誠実さが伝わってきたので、ここなら大丈夫と直感しました。
こちらの話を急かすことなく、押しつけるような言葉もなく、とても安心しました。要望に対しても誠意ある対応を受けたので、いまでも感謝しています。
おかげで3人ものいい先生にめぐり会えました。子どもも信頼していて、先生のことが大好きみたいですね。
事例③学ぶことの楽しさを感じ始めている様子〜小倉智衣さん(中学校2年生)の親御さんの声〜

子どもは、中学校に登校できる日は午前か午後のどちらかだけで、教室以外の場への外出も週に1回程度でした。
キズキ共育塾は、これまで多くの不登校の生徒を受け入れていたことから、「こういう子どもの対応に慣れているだろうし、否定されたり受け入れられなかったりする可能性を心配をしなくてすむ」と考え、入塾を決めました。
唯一、「本人の体力がもつか」ということは不安でしたが、結果として問題なく通っています。生活リズムが崩れたり、心理的に余裕がないときでも、できる限り通塾しようとしています。学ぶことの楽しさを感じ始めている様子です。
家では、キズキで習ったことや先生と話した内容を細かく話してくれます。先生が面白いともよく話をしていますね。
先生から教わったことをとても大切にしているようで、家ではノートを何度も読み返しています。勉強に取り組むことで、少しずつ自信が出てきたように見えます。
参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校ジャーナリスト・石井しこう、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。
このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。
このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。
公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら
- 【オリジナル書籍プレゼント】学校外で友だちができるBranchコミュニティ(Branch公式LINEが開きます)
私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。
まとめ〜スモールステップで不登校で勉強しない状態を克服しましょう〜

お子さんが不登校になると、親御さんにはさまざまな不安があるでしょう。
もちろん、不登校で勉強しないお子さんの将来を不安に思い、「勉強しない状態を何とかしないと…!」とあせる気持ちはとてもわかります。
しかし、勉強を再開するには適切なステップを踏むことが大切です。
もちろん、お子さんの将来も大切ですが、まずは今のお子さんの状態を見極めながら、勉強が再開しやすいようにサポートしましょう。
うまく勉強が再開できた場合も、いきなり何時間も勉強できるわけではありません。
まずは1日5分、週1日からでも構いません。少しずつ慣れていきましょう。
また、テレビやゲームなどの息抜きのための時間を作ることも、勉強を長続きさせるためには大切です。
このコラムを参考にしていただき、お子さんの将来を心配しすぎず、あせりすぎずに少しずつスモールステップで取り組んでみてください。
私たちキズキ共育塾では、学校以外の学びの場として、みなさんの勉強をサポートしています。
無料で相談を承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
Q&A よくある質問