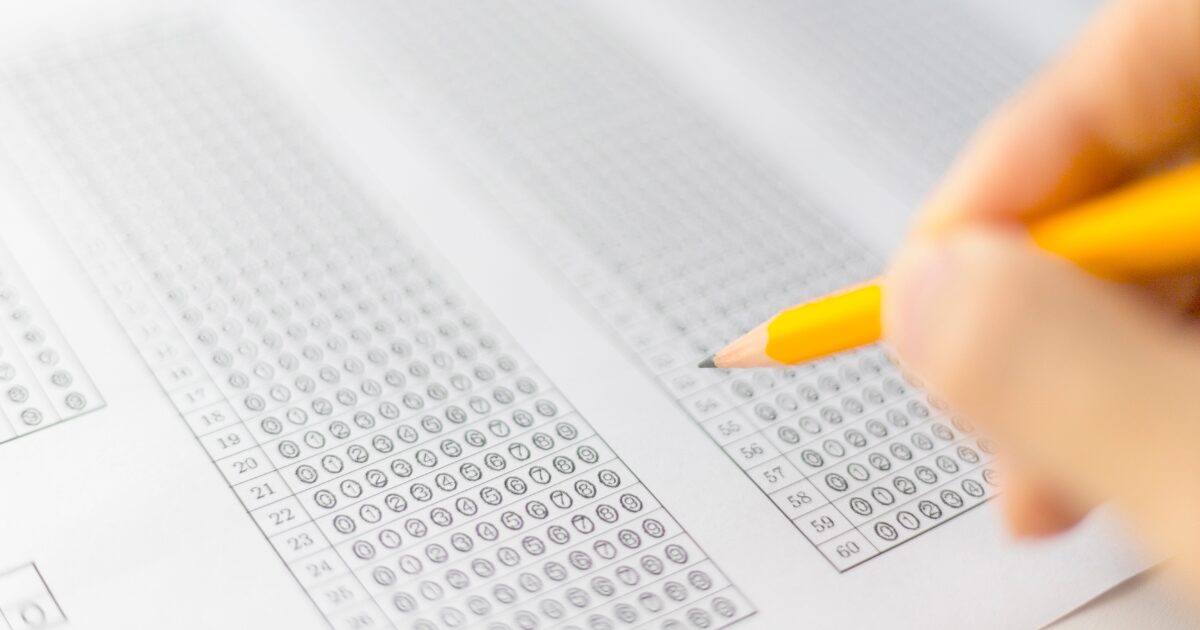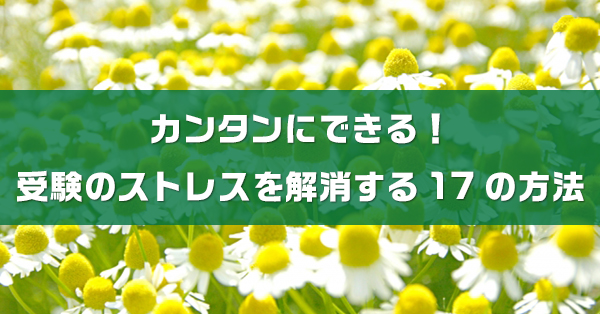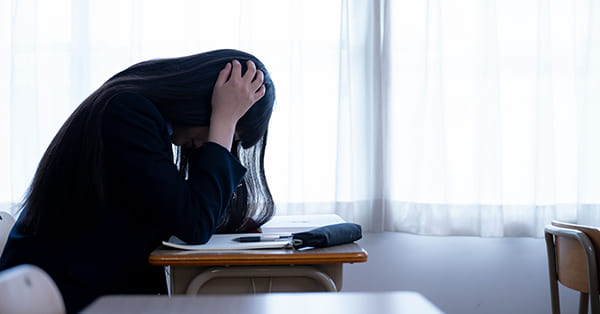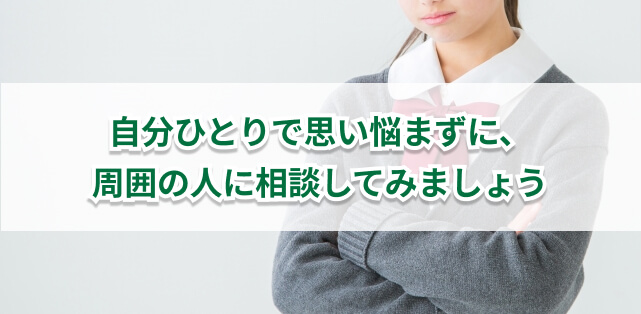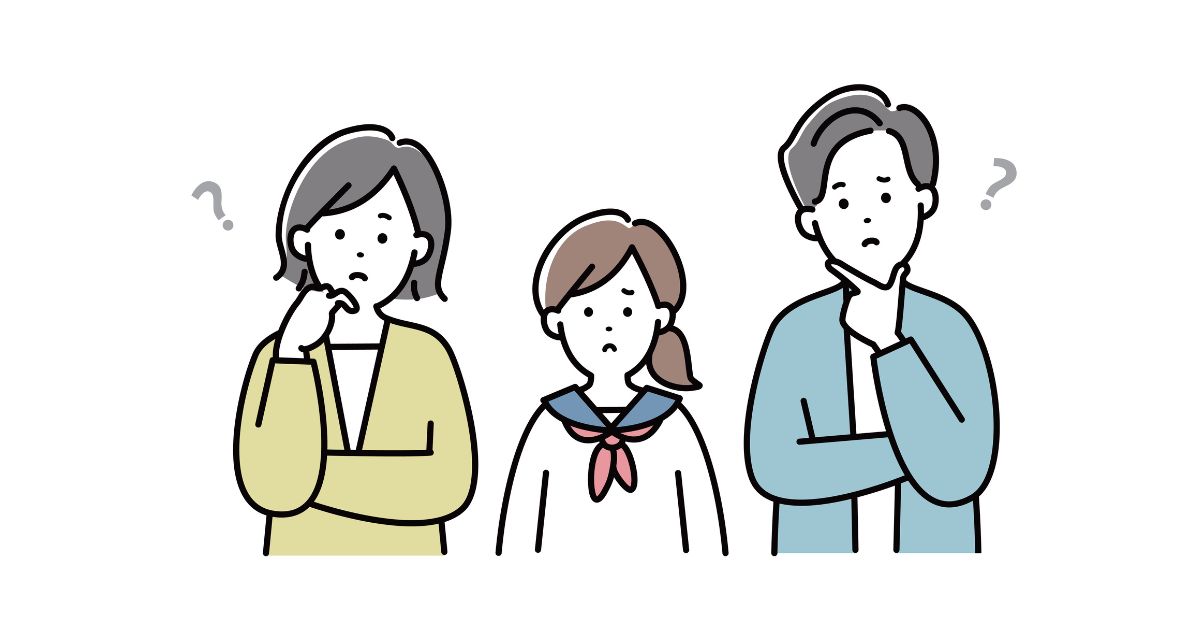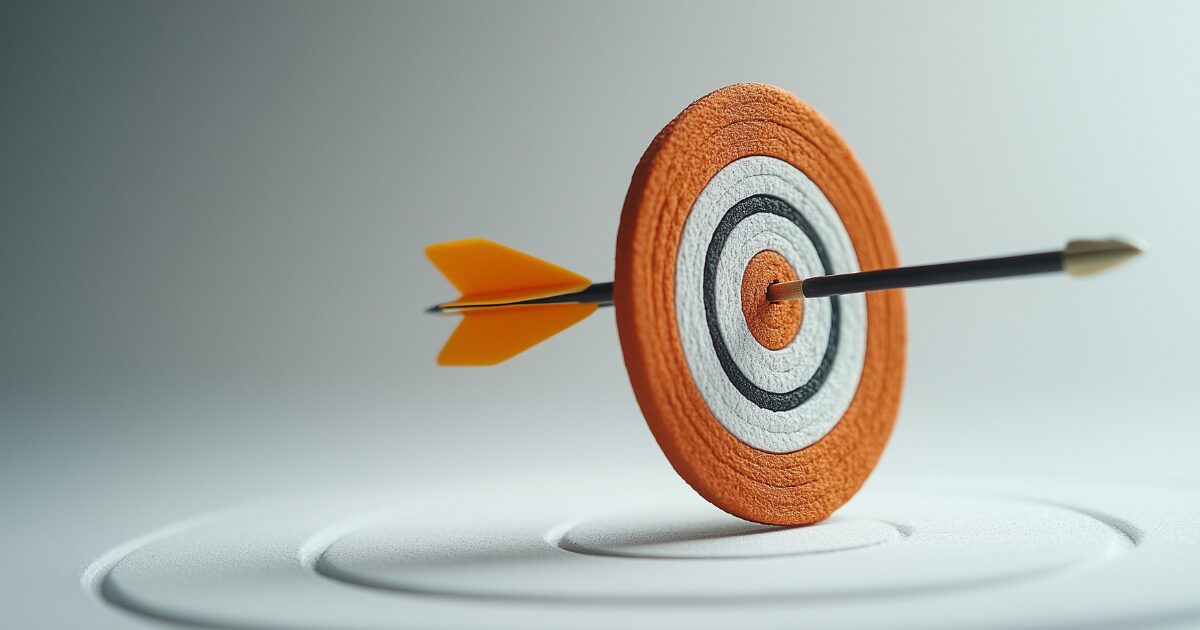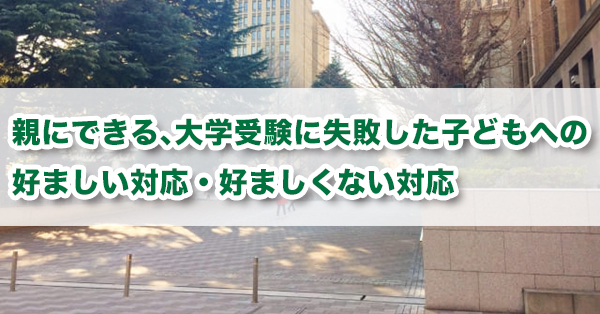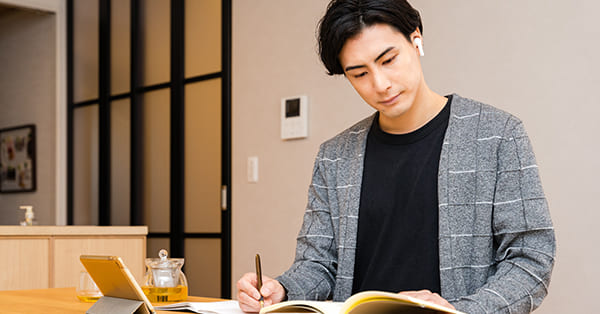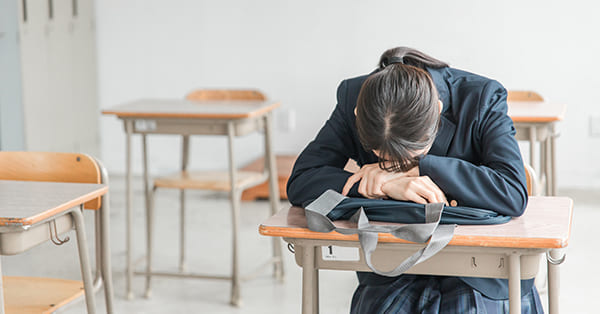中卒から大学受験に合格する方法 大学受験するルートを解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
このコラムをお読みのあなたは、中卒から大学受験をしたいのに、方法がわからず悩んでいるのではないでしょうか?
- どのルートで大学受験をするのがいいの?
- そもそも大学受験できるのかわからない…
結論からお伝えすると、中卒から大学受験をすることは可能ですし、さまざまなルートがあります。
このコラムでは、中卒から大学受験するルート、中卒から大学受験する際のポイント、気をつけたいこと、メリット、デメリット・注意点について解説します。あわせて、中卒からの大学受験に関する、キズキ共育塾の講師からのアドバイスを紹介します。
私たちキズキ共育塾は、中卒から大学受験を目指す人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などの無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
中卒から大学受験することはできるのか?

結論から申し上げますと、中卒からの大学受験は可能ですし、不可能ことではありません。
大学受験は現役高校生がするものと考える人は多いのですが、年齢を問わず、中卒から大学受験をする人は毎年います。
例えば、あとで説明する大学受験に向けたメジャーな選択肢のひとつに、高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)があり、この試験に合格して大学受験への切符を手にする人は、ここ2年では8000人近くいたのです。(参考:文部科学省「令和4年度第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果」)
| 年度 | 出願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 2021年度 | 2万215人 | 1万7704人 | 8097人 |
| 2022年度 | 1万9653人 | 1万7154人 | 7961人 |
この高卒認定試験は、あくまでもルートのひとつです。別ルートからも大学受験する人がいることを考えれば、中卒から大学を目指す人の数はもっと多いと考えられます。
ただし、どのルートでも最低限の学力は必要です。ある程度の勉強を通して、準備をしなくてはなりません。
また、高校卒業程度と同じくらいの学力を身につけた後に、本番の大学受験勉強が待っています。
特に、中卒のまま就職したことで勉強を続けられなかった人は、ブランクを埋める意味でも根気強い努力が必要です。
中卒から大学受験する6つのルート

この章では、中卒から大学受験するルートについて解説します。
最終学歴が中卒の人は、卒業後にそのまま就職をしたケースや、一度高校へ進学して中退したケースなど、通ってきた道はさまざまかと思います。
しかし、大学受験へのルートは、最終学歴が中卒になった経緯は問われません。
ただし、その人の学力や普段の生活のスタイルなどによっては、多少の向き不向きがあるかと思います。
また、場合によっては後述するように、中卒からの大学受験を総合的にサポートする学習塾などの支援を得た方が、大学受験しやすくなるケースもあります。
そうした点も踏まえて、自分はどのルートで大学受験を目指すのが向いているかを考えながら、一緒に見ていきましょう。
ルート①高卒認定試験の合格
最初にオススメしたいのは、高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)に合格して、大学受験を目指すルートです。
高卒認定試験とは、高校卒業と同程度の学力があることを公的に認める試験のことです。試験の合格によって、大学・短大・専門学校、一部の公務員試験などの受験が可能になります。
取得のためには、年に2回、8月と11月に実施される試験に合格する必要があります。
文部科学省によると、2021〜2022年では、約1.7万人が受験し、約8000人が合格しており、合格率は約50%ほどです。(参考:文部科学省「令和4年度第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果」)
高卒認定試験は、その年度で16歳以上、かつ大学入学資格のない人であれば、受験可能です。高校に在籍していても受験できます。
全部で8〜9科目を受ける必要があります。ただ、高校中退後に大学受験を目指すケースの場合、中退するまでに高校で取得した単位があると、受験を免除される科目もあります。
また、1回の試験で全ての科目に合格する必要はありません。一度合格となった科目はずっと有効となります。
受験にあたっては、そうした仕組みを理解した上で、効率的な学習環境を整えることが大切です。
高卒認定資格の勉強ができる学習塾もあります。
高卒認定資格に興味のある人は、ぜひ一度調べてみましょう。
高卒認定試験については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。。
ルート②通信制高校の入学・卒業
2つ目として、通信制高校に再入学・卒業するルートがあります。
通信制高校を卒業すると、最終学歴が中卒から高卒になります。
通信制高校とは、学校から送られてくる教科書や動画といった教材を使う、自宅学習が基本の高校のことです。
通信制高校では、基本的に授業への出席ではなく、レポートの提出や試験などで卒業単位を修得していきます。
出席する必要があるのは、スクーリング日と呼ばれる特定の日数のみです。最近では、毎日通学する通信制高校など、さまざまなタイプの通信制高校があります。
あなたのペースで単位を取ることができます。高校に進学したものの授業についていけずに中退した人や、中卒後に働きながら勉強して大学受験を目指したい人に向いているルートと言えるでしょう。
通信制高校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ルート③定時制高校の入学・卒業

3つ目のルートとして、定時制高校への再入学があります。
通信制高校同様、こちらも、卒業すると最終学歴が高卒になります。
定時制高校とは、昼、または夕方からの時間帯などに学校に通学し、授業を受ける高校のことです。
また、定時制高校の授業のコマ数は、1日4コマが目安です。そのため、全日制高校よりも自由な時間が多く、仕事や子育てをしながらでも通いやすいのです。
なお、卒業までに4年かかります。3年で卒業できる場合もあります。入学を考えている高校があるなら、そこのシステムをあらかじめ確認しておくことが大切です。
定時制高校には、高校中退や中卒後に就職した人など、様々な背景を持った人が多くいます。
同じ悩みや苦労を持つ人と情報交換をしながら勉強や学生生活に取り組めるので、比較的勉強が続けやすいでしょう。
定時制高校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ルート④通信制大学の特修生・履修生制度の利用
ルートの4つ目は、通信制大学の特修生・履修生制度の利用です。
通信制大学とは、大学から配布される教材や動画を用いて勉強したり、自分で資料を収集してレポートを書いたりして単位を取得する、自宅学習がメインの大学のことです。
特修生・履修生制度とは、こうした通信制大学での勉強を希望する人のうち、中卒や高校中退などの入学資格を持たない人向けに、入学を許可する制度を指します。
ただし、入学許可を得るための条件は、一定期間のうちに大学が定める履修科目を修めて、単位を取得しなければならないなど、学校によって異なります。
例えば、東京都にある東京福祉大学の通信教育課程では、半年以内に所定の単位(大学:16単位以上、短大:8単位以上)を習得することが、大学の正科生になるための条件と定められています。(参考:東京福祉大学「入学のしかた」)
こうした特修生・履修生制度を持つ通信制大学の数は、東京・神奈川・千葉・埼玉といったいわゆる首都圏だけでも、以下のように10校以上にのぼります。
以上のような通信制大学では、特修生・履修生制度にて定められている条件を満たすことで、中卒から大学進学する人が一定数います。
ご興味のある人は、通信制大学のWEBサイトをご覧の上、その大学の特修生・履修生制度について問い合わせてみるとよいでしょう。
ルート⑤大学の入学資格審査に合格
最終学歴が中卒であっても、各大学の定める個別の入学資格審査に合格することで、大学へ進学できます。
入学資格審査とは、個々人の学修歴などから、高等学校や大学を卒業した人と同等以上の学力があるか否かを判断する審査のことです。
これは、国の法律でも定められる学校教育法の施行規則に則って行われる審査です。
文部科学省はこの入学資格審査について、以下のような説明を行っています。
大学教育の活性化等を図る観点から、社会人等であって大学で学習を行う意欲と能力を有する個人について、大学教育を受ける機会を提供するため、大学や大学院への入学に関し、個別の入学資格審査により、各大学において、高等学校や大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者に対し、入学資格を認めることができます。
(参考:文部科学省「入学資格に関するQ&A(平成31年1月31日現在)」)
大学が個別に定めるこの入学資格審査に合格すれば、中卒でも大学進学ができるのです。
入学資格審査の内容は大学ごとに異なります。興味のある方は各大学に、詳細を問い合わせましょう。
ルート⑥専修学校の高等課程や高専を修了する

専修学校の高等課程を修了する、または高専を修了するルートもあります。(参考:文部科学省「高等専修学校から大学へ」)
専修学校とは、修業年限1年以上、常時40名以上の学生が在籍しているなどの条件で設置される教育施設のことです。
入学資格によって、高等課程・専門課程・一般課程の3つがあります。
学校教育法の基準では、以下のように定められています。(参考:文部科学省「学校教育法(抄)(昭和22年法律第26号)」)
- 修業年限が1年以上であること
- 授業時間数は、学科ごとに文部科学省が定める授業時数以上であること(年間800時間以上、夜間学科は450時間以上)
- 教育を受ける者が常時40人以上であること
中卒の人が専修学校に通う場合は、基本的に高等課程に進むことになります。
この高等課程のうち、修業年数が3年以上などの条件を満たした人で、文部科学大臣が指定した学科の修了者は、大学受験資格が得られることになっています。
ただし、大学入学資格を得られる専修学校は、文部科学大臣が指定するものに限定されます。興味のある専修学校が指定校になっているかという点にはご注意ください。(参考:文部科学省「(※5)文部科学大臣指定専修学校高等課程一覧(令和5年10月31日現在)」)
このルートで行くなら、興味を持った専修学校に一度問い合わせてみることをオススメします。
他に、高等専門学校(高専)があります。高専とは、実践的・創造的技術者を養成することを目的とした高等教育機関のことです。
5年一貫で、いわゆる五教科などの一般科目と、工学・技術・商船などの専門科目の両方を学びます。例えば、商船学科は5年6か月です。
高専は、修了後に大学への編入学が可能になります。
なお、専修学校・高専のいずれにしても、夜間学科以外の生徒は中学卒業直後の若い人たちです。
また一般的には高校の普通科で学ぶ内容よりも専門的な内容を学びます。
専修学校も高専も、向いている人には楽しい学校だと思います。ですが、第一目的が大学受験の資格を得ることであれば、現実的にはあまりオススメしません。
興味がある場合は、専修学校や高専に資料請求したり見学に行ったりして、大学受験以外の観点からも、自分に向いているかどうかをチェックしてください。
補足:全日制高校はあまりオススメできません
朝から夕方に授業がある高校のことを、全日制高校と言います。しかし、全日制高校への再入学はあまりオススメできません。
全日制高校では、朝から夕方までフルで授業が行われるので、自由度が低いです。また、通っている学生は、基本的には中学からそのまま進学してきた16歳から18歳までの生徒がほとんどです。
そのため、中卒後にブランクが空いた人や、不登校、ひきこもりが原因で高校へ進学しなかった人、中退した人などにとっては、環境に馴染むのが難しいことがあるのです。全日制高校に入学・再入学しても、高校を中退するケースもあります。
全日制高校への進学は絶対にするべきではないとまでは言いません。
ですが、高卒の資格を得るのであれば、現実的には通信制高校か定時制高校をメインに検討することをオススメします。
中卒から大学受験する際の5つのポイント

この章では、中卒から大学受験する際のポイントについて解説します。
「大学受験はしたいけど、自分にできるのかな…」「本当に合格できるの?」などの不安や疑問をお持ちの人は、ぜひ参考にしてみてください。
ポイント①大学受験・進学の目的を明確にする
1つ目のポイントは、大学受験・進学の目的を明確にすることです。
突然ですが、「なぜあなたは、大学受験・進学したいのですか?」と質問されたとき、明確な答えを言えるでしょうか?
上手く言葉にできない、思い浮かばない人は、一度この問いと向き合い、大学受験や進学の目的を明確にしましょう。
目的が明確でないと、「本当に大学に進学できるのかな…」「大学に行けたとしても卒業後はどうなる…?」など、迷いが生まれ勉強に集中しづらくなるからです。
人によっては、すぐに大学受験や進学する目的が明確にならないこともあります。
しかし、心配無用です。受験勉強や大学生活を通して、目的が見つかることがあるからです。
具体的な目標は、モチベーションの維持・向上に役立ちます。まずは一度自分自身と向き合う時間をとり、目的が見つからない場合はこれからお伝えする別のポイントを充実させましょう。
大学受験の目的については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ポイント②自分にあった大学を選ぶ
2つ目のポイントは、自分にあった大学を選ぶことです。
大学と一括りに言っても、以下のような種類があります。
- 通学制大学
- 通信制大学
- 短期大学
通学制の大学は一般的にイメージされる大学で、ほぼ毎日大学に通い講義や試験を受けます。夜の時間帯に授業を行う学部もあります。
一方で、通信制の大学では、通学せずにレポートや課題に取り組むことで単位を取得し卒業できます。なお、年に何日かのスクーリングはあります。
また、短期大学は4年間通う一般的な大学とは異なり、卒業までの期間は2〜3年です。
大学の種類以外にも、大学ごとに通う生徒やキャンパスの雰囲気、設備、サポート体制など、異なる点はたくさんあります。
もちろん、自分が学びたいことや将来就きたい職業につながることから大学や学部・学科を選ぶことは大切です。
ですが、「数年間通い続けられるか」「勉強に取り組み続けられるか」は、自分に合った大学を選ぶことが重要になります。
ポイント③入試科目を検討する
入試科目を検討することも、中卒からの大学受験ではとても大切なポイントになります。
大学受験では、試験に合格するために入試科目に特化して受験勉強をする場合が多いです。
しかし、合格することだけを考えていると、大学で必要になる知識を受験勉強の中で身につけられず、入学後に苦労する可能性があります。
そのため、大学で学びたいことをもとに、入試科目を選ぶことが大切なのです。
入試科目の選び方の例
- 大学でロボット工学を学びたいなら、大学受験の「理科」の選択では地学ではなく物理を選ぶ。
- 受験勉強を通じて物理を学ぶことで、入学後の勉強にも役に立つ。
- 逆に地学で受験した場合(受験勉強で物理を学ばなかった場合)、大学に入学してから物理を学び直すことになる。
もちろん、その科目があまり得意ではなければ、受験勉強に苦戦する場合もあります。ですが、そこで身につけた知識は、今後の人生で大きく役立つはずです。
とはいえ、どのように入試科目を選べばよいかわからない人もいらっしゃると思います。そういった人は、中卒から大学受験する人を支援するサービスを利用して、相談することがオススメです。
ポイント④効率よく勉強できる学習計画を立てる
受験勉強においては、効率良く勉強できる学習計画を立てることもポイントになります。
中卒から大学受験をしようと考えている方の中には、現在お仕事をされている方もいると思います。
仕事を続けながら大学受験に挑戦する場合、勉強できる時間が限られることはもちろん、全ての体力や気力を勉強に注ぐことはできません。
こういった状況で勉強を進めるためには、学習計画が必要なのです。たとえば以下のような例があります。
- 科目や単元の勉強順序を考える:数学の特定の単元を先に勉強しておくことで物理の理解が早まるなど
- 一日の中で効率よく勉強できるタイミングを知る:夜は集中できないけど朝から午後には集中できるなど
自分で学習計画を立てることが難しい場合は、大学受験を支援するサービスを積極的に活用しましょう。
ポイント⑤中卒から大学受験する人を支援するサービスを使う

5つ目のポイントは、中卒から大学受験する人を支援するサービスを利用することです。
大学受験を支援するサービスと言うと、学生が通う学習塾や予備校を思い浮かべる人が多いと思います。
ですが、通信教育や家庭教師などの中卒の人や社会人の人の大学受験を支援するサービスもあります。そういったサービスを活用することで、あなたに合った勉強法や志望校などが見つかりやすくなるはずです。
また、こういったサービスを利用する際は、以下の点を積極的に質問しましょう。
- 志望校探し
- 受験に向けたスケジュール
- 受験方式(一般入試、社会人入試、総合型選抜入試など)
- 受験勉強の方法
なお、私たちキズキ共育塾にも、中卒から大学受験を目指す生徒さんがたくさんいます。ご相談は無料で受け付けていますので、少しでも気になる場合はお気軽にご連絡ください。
ポイント⑥入試のスタイルを選択する
大学入試には、様々なスタイルがあります。自分に合った入試方法を選ぶことも、大学受験におけるポイントの1つです。
- 一般入試
- 総合型選抜入試(旧:AO入試)
- 社会人入試
一般入試とは、受験と聞いてよくイメージされる、学力試験による合否判定のことです。
一般入試の科目数は、受験大学が国公立か私立かによって、大きく変わります。
国公立大学の一般選抜の場合、共通テストと個別学力検査の2つを組み合わせて実施されます。また、科目は5教科7科目(英国数理社の5教科。かつ、理科・社会で2科目ずつなど)であることが多いです。
苦手科目を作らず、まんべんなく得点を獲得する必要があります。一部の大学では、調査書の内容も評価されることがあります。
実施日時は、以下のとおりです。
試験の実施日時
- 共通テスト:1月の第2週目の土・日
国公立の入試:前期日程は2月の下旬から、後期日程は3月中旬から
※公立大学のみ中期日程を実施しており、毎年3月8日以降に行われます
私立大学の一般選抜の場合、大学、学部、学科によって異なりますが、教科数は3教科が基本です。一般的には、以下のようなパターンが多いです。
- 文系学部:英語、国語、社会(日本史・世界史・地理などの中から一つ)
- 理系学部:英語、数学、理科(物理・化学・生物・地学の中から一つ)
その上で、大学・学部によっては、ある科目の配点を変えたり、重視したりすることもあります。例えば、数学の得点を重視するなどです。重視科目がある大学なら、少ない科目の中で、自身の得意科目を武器に受験に挑めるのです。
私立入試日程は、大学によって異なりますが、多いパターンは以下のとおりです。
試験の実施日時
- 前期日程:1月下旬~2月中旬
- 後期日程:2月下旬~3月
総合型選抜(旧AO入試)の審査内容は、自己推薦書・調査書、面接、志望動機、入学後にやりたいことなどです。学力試験がある大学もあります。
各大学が求める学生像に受験者がマッチしているかどうかが重要です。
高校を不登校でも受験できますが、卒業見込みがないと受られないため、卒業出来る出席日数は満たす必要があります。
総合型選抜は、9月から12月にかけて選考が行われることが多いです。
社会人入試とは、受験対象を社会人に限定した入試のことです。
社会人入試の特徴は、以下のとおりです。
受験資格
- 高校卒業や高卒認定の他に、年齢(○○歳以上)や社会人経験(○○年以上の勤務経験)などの条件が加わる
合否判断
- 学力試験よりも、面接・小論文・書類審査などがメインに審査される(学力試験が重要な場合もある)
- 社会人入試は、受験勉強に使える時間が限られている社会人が比較的受験しやすい入試制度です。
面接や書類審査では、以下のような質問で、将来を見通した判断の説明を求められます。
- その大学で学びたい理由
- 大学在学中から卒業後も含めたキャリアプラン
中卒から大学受験する際に気をつけたいこと

中卒から大学受験する際に気をつけたいのは、受験資格を得たことで満足して、大学受験に取り組まなくなることです。
高卒認定試験にせよ、通信制大学の履修生制度にせよ、高卒と同じ程度の学力を身につけるまでには、それ相応の努力が必要です。資格を得たときには達成感も得られると思います。
それは自信にもつながりますし、素直に自分をのめてよいことなのは間違いありません。
しかし、その達成感によって、「自分は力を出しきった!」と一種の燃え尽き症候群のようになり、勉強へのモチベーションが下がる人も、いないわけではありません。
そういうときは、大学受験への切符を手に入れるのは、あくまでもゴールに続く道のりの途中であることを思い出してください。
大学受験をする以上、あなたの目標は合格して大学進学すること、大学で勉強することにあるはずです。
中卒から大学受験できるところまで勉強をがんばったのは、もちろん素晴らしいことです。
しかし、そこで終わりにならないように、気を引き締めるようにしましょう。
とはいえ、例えば、高卒認定試験からそれぞれの大学受験までを、気を緩めることなく、あなたひとりの力でクリアするには、相当な努力が必要になるかと思います。
そのため、ご家族や友人といったあなたの周りにいる人や、受験予備校など、周囲の環境をうまく活用していくことが大切です。
中卒の人の大学受験を総合的にサポートする学習塾もあります。そういった学習塾などの専門機関とも話をすることで、大学受験はより効率的に進められます。
中卒から大学受験するメリット

この章では、中卒から大学受験するメリットについて解説します。
メリット①興味のある学問を学べる
1つ目に、大学では、興味のある学問を専門的に学び、知識などを身に付けられます。
また、同級生などとの交流、いわゆるキャンパスライフも楽しめるでしょう。
大学で得られる知識や人間関係の広がりは、それまでとは異なる方向性の人生の広がりにもつながります。
メリット②正社員として働ける割合が多い
正社員として働ける割合が多いことも、中卒から大学受験するメリットの1つです。
最終学歴が中卒の人と大卒の人を比べたとき、就職先の選択肢や給与の高さに大きな違いが出ることが知られています。
厚生労働省の統計によると、15~34歳までの若年労働者における正社員の割合は、以下のように異なります。(参考:厚生労働省「平成30年若年者雇用実態調査の概況」)
- 中卒で正社員:約35.4%
- 高卒で正社員:約56.3%
- 大卒で正社員:約80.9%
このように、大学を卒業している人の約8割が正社員として働いています。
もちろん、正社員として働くことだけが「よい」ことではありませんし、正社員ではない人が悪いということも一切ありません。
ですが、正社員として働きたいと考えている人にとっては、大きなメリットと言えます。
受験勉強のモチベーションが上がらないなぁ…と悩むときは、上記のようなメリットを考えることで、安心して取り組めるようになります。
中卒から大学受験するデメリット・注意点

実際に中卒から大学受験する場合に、知っておいた方がよいデメリットや注意点があることも事実です。
この章では、中卒から大学受験するデメリット・注意点について解説します。
もちろん、デメリット・注意点を乗り越える方法はあります。
そのため、必要以上に不安にならず、大学受験するかどうかを検討するための判断材料にしましょう。
中卒から大学受験を目指すためにも、ご自身にとってよい選択をするためにも、デメリット・注意点をチェックしてください。
注意点①入学金や授業料などまとまった費用が必要
大学で勉強するためには、入学金や授業料などの学費がかかります。入学する大学が私立か国公立か、理系か文系か、などによって具体的な金額は異なりますが、まとまった費用が必要です。
奨学金などを利用することもできますが、もちろん将来的にお金を返す必要があるため、そういった面も含めて検討しましょう。なお、中には返済不要な奨学金もあります。
注意点②長期間、勉強へのモチベーションを保ち続ける必要がある
長期間、勉強へのモチベーションを保ち続ける必要があることも、注意点の1つです。選ぶ大学の種類や学部によって異なりますが、一般的に大学は4年間通う必要があります。
今は大学受験や大学進学へのモチベーションが高い状態だと思うので、これから長期間勉強することに不安はないかもしれません。
しかし、実際に受験勉強を始めたり大学に入学したりすると、上手くいかないことや勉強以外の誘惑があり、勉強への気持ちを維持することが難しくなることもあります。
もちろん、常に勉強へのモチベーションを高く保たなければいけないわけではありません。ですが、勉強への意欲が完全になくなると、受験を途中で断念することになったり、大学を中退したりする可能性もあるのです。
モチベーションを保つ方法は、自分で試行錯誤したり、人に相談して探したりしてみてください。
注意点③大学を卒業しても就職が必ず上手くいくわけではない
大学を卒業しても就職が必ず上手くいくわけではないこともお伝えしておきたいと思います。
ここまでもお伝えしてきた通り、最終学歴が中卒の人と大卒の人を比べると、就職先の選択肢や給与の高さに違いがあります。
ですが、だからと言って、大学を卒業していれば、誰もが思い通りの就職ができるわけではありません。
就職活動を進めるためには、大学受験の勉強や大学での勉強とは別の対策が必要です。また、景気の動向によっては、求人が少ない年もあります。
昨今の大学には、学生の就職をサポートするキャリアセンターなどと呼ばれる機関があります。就活の対策は、そうしたところにも相談しつつ進めていきましょう。
なお、大学卒業直後に就職したところが自分に合っていなくても、そこから転職や起業をしていくことはもちろん可能です。
「中卒からの大学受験」について、キズキ共育塾の講師からのアドバイス
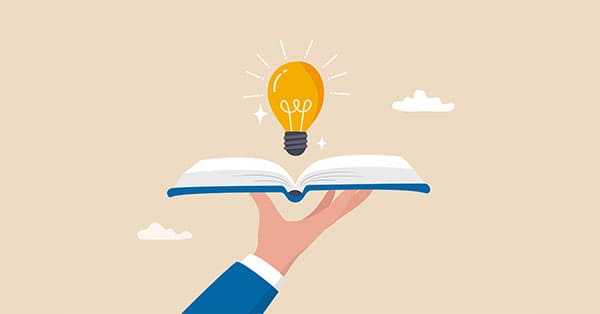
この章では、「中卒からの大学受験」について、学び直したい人たちのための個別指導塾・キズキ共育塾の講師たちからのアドバイスを紹介します。
実際に中卒から大学受験を目指す人たちに勉強を教えている講師の「生の声」ですので、きっと参考になると思います。
また、私たちキズキ共育塾の無料相談では、実際のあなたのための、より具体的なアドバイスが可能です。ぜひご相談ください。
近藤翔平講師のアドバイス
英語と数学の中学校内容を復習しておく
しておいた方がよいことは、「英語と数学の中学校内容を復習しておくこと」です。英語は単語と文法、数学は計算や基本的な公式を覚えることが大切です。
大学受験の参考書で扱う最初の単元は中学内容の応用となるため、スムーズに勉強をスタートさせられます。わからない部分は、塾などを利用してもよいですし、YouTubeでの解説動画の活用もオススメです。
村下莉未講師のアドバイス
高卒認定試験に向けて準備する
特に大学/短大/専門学校などの受験を目指す場合、しておいた方がよいことは、「高卒認定試験に向けた準備」です。
中学卒業後に高校などに進学していない方が大学などの受験を目指す場合、よくあるルートに「高卒認定試験の取得」があります。そのため、まずは高卒認定試験の情報収集をし、いつ・どの科目の試験を受けるかの見当をつけましょう(高卒認定に関する相談できる塾などはたくさんあります)。
高卒認定試験は、各科目の基本的な知識が問われます。そのため、中学校での学習内容の定着度合いの確認や、受験勉強に取り組むまでの基礎固めにもなります。
まとめ〜中卒から大学受験する方法はたくさんあります〜

中卒でも大学受験をするのは不可能なことではありません。
周りの人をうまく頼りながら勉強を続ければ、大学受験する方法はたくさんあります。
このコラムが、少しでも中卒から大学受験を目指している方の助けになれば幸いです。
なお、私たちキズキ共育塾では、学び直しからの大学受験を目指す方の学習をサポートしております。
学習面だけでなく、メンタル面も含めたサポートを行っておりますので、ひとりでお悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。相談は無料です。
Q&A よくある質問