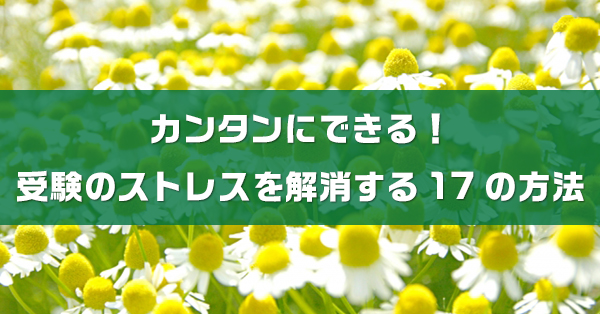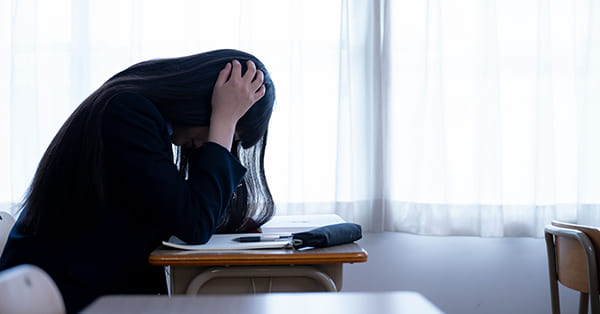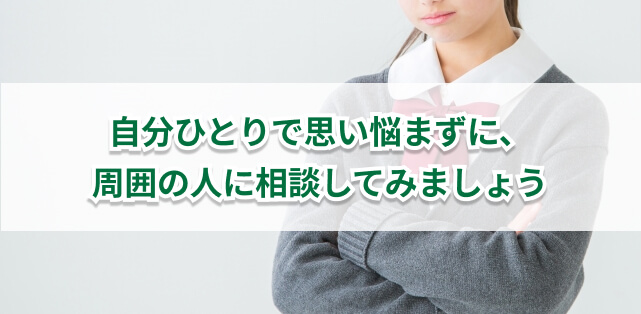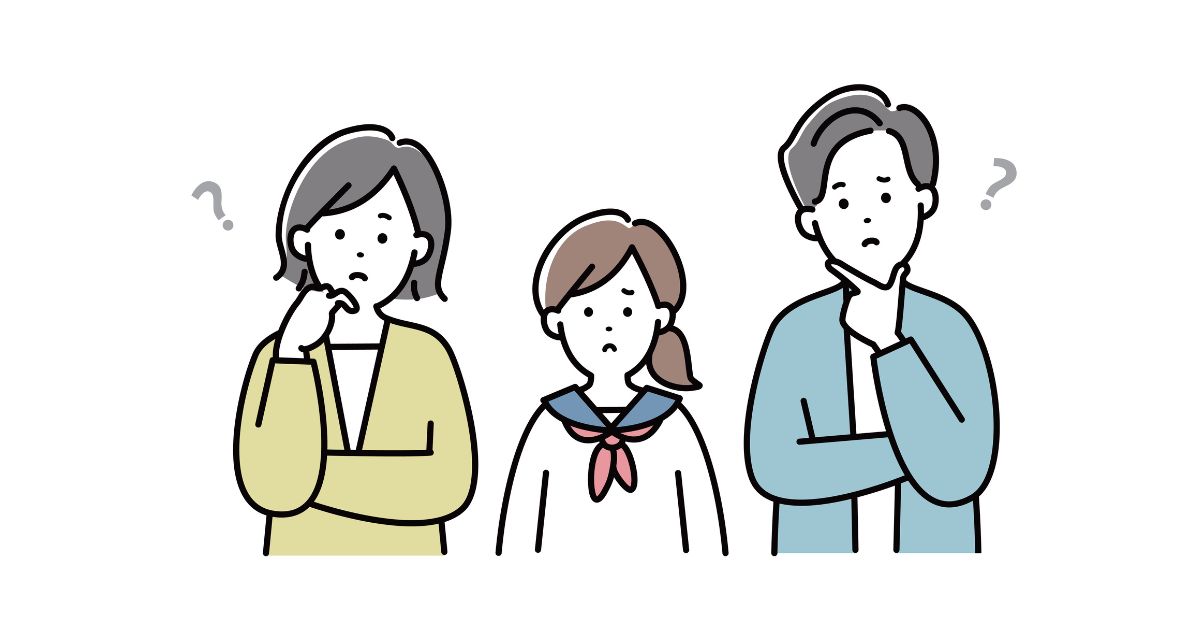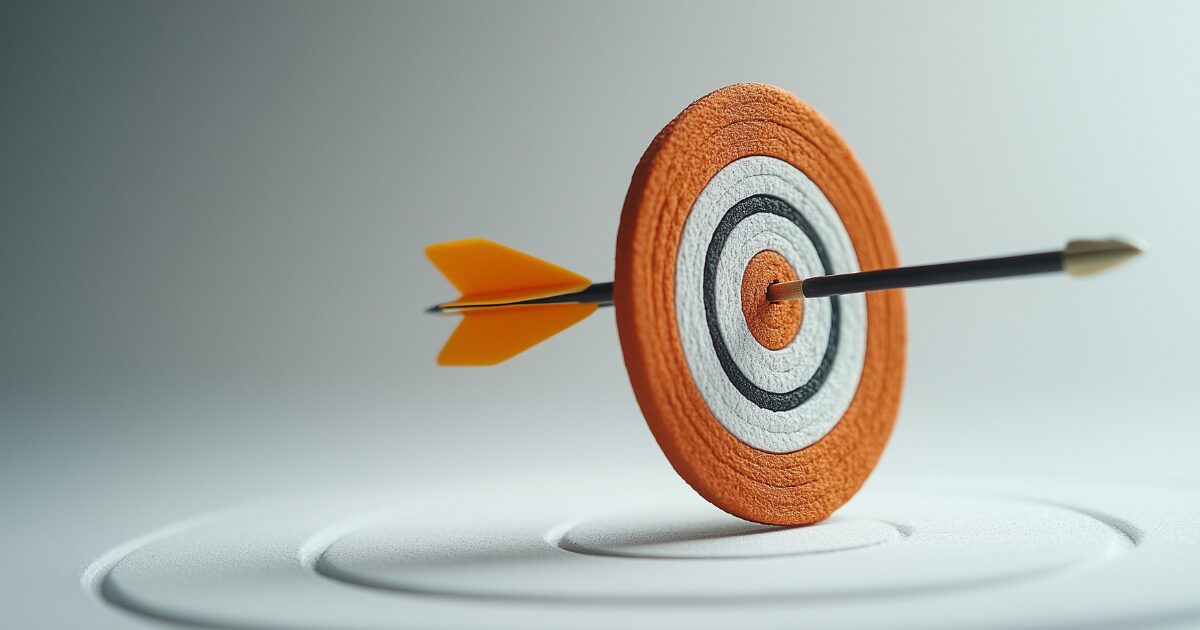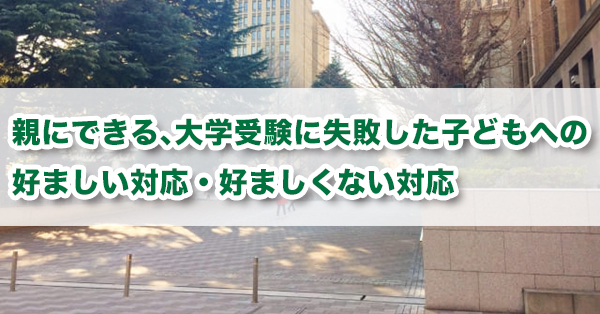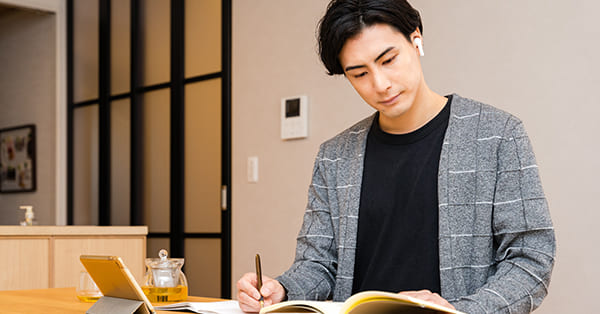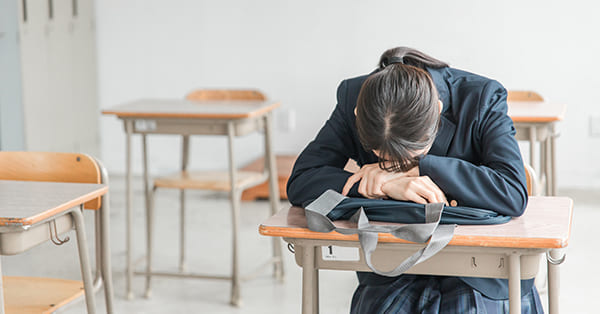「受験をやめたい」と考えるあなたへ 理由別に解決方法を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
受験生のあなたは、一度でも「受験をやめたい」と考えたことはありませんか?
受験勉強をしている間は、悩みや不安でいっぱいになる時期ですので、受験をやめたいと考えるきっかけも、きっと人それぞれにあります。
以下のように悩みはじめると、受験そのものに対して迷いを感じることもあるでしょう。
- 受験勉強しなきゃと頭ではわかっているのに、なかなか手につかない
- 受験勉強をやらされている気持ちが強く、受験なんてやめたい
このコラムでは、「受験をやめたい」とお悩みのあなたに向けて、受験をやめたいという悩みを解決する方法について理由別に解説します。
「受験をやめたい」と悩んでいるあなたの助けになれたらうれしいです。
私たちキズキ共育塾は、受験をやめたいと悩む人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
受験をやめたいと悩む2つのケース
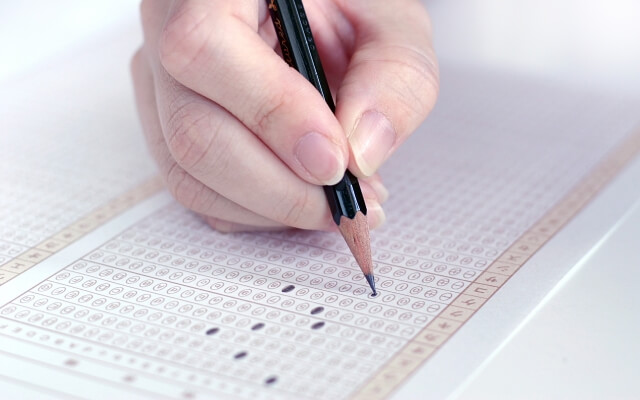
あなたはどうして受験をやめたいと思っているのでしょうか。
受験をやめたいと思うきっかけは人それぞれであり、状況もさまざまです。その上で、大きくは以下の2つに分類できると思います。
- 受験(や進学)はしたい、けれど勉強が手につかない、成績が思うように上がらないから受験をやめたい
- 自分は受験をしたいと思っていない。だけど、受験勉強をやらされている
この2つは、同じ受験をやめたいという気持ちでも、それぞれ悩みや不安を解決する方法は異なります。
ここからは、それぞれのケースごとに、悩みや不安を解決する助けとなる方法を紹介します。
勉強が思うように手につかなくて受験をやめたい場合の対処法
まずは、勉強が思うように手につかなくて受験をやめたい場合です。以下のような流れがあるようです。
- 受験勉強をしたい意思はあるけれど、勉強という行動に移せない
- 勉強を始めるのに時間がかかったり、気力を振り絞ったりする必要がある
- そのために罪悪感、焦りなどを持つ
- そして、「受験をやめたい」と思うようになる…
受験をしたいという意思があるのであれば、実際に勉強が手につくようになると悩みを解消でき、同時に受験をやめたいという気持ちも解消できるはずです。
さらに受験勉強へのモチベーションを上げる方法や、勉強に取り組む状態を作るための方法を紹介します。
方法①受験勉強をする意味を理解して整理する

人は、意味もわからずやること、意味を見出せないまま続けることに対して、苦痛を感じます。(参考:渋谷昌三『面白いほどよくわかる!心理学の本』)
受験勉強も、その意味がわからなければ、苦痛に感じることもあるでしょう。
この苦痛を軽減するためには、受験勉強をする意味を自分で理解し、整理することが大切です。
受験勉強を始めた当初は、その意味や理由を意識できていても、勉強を続けているうちに、勉強自体が目的となり、意味や理由自体を見失いがちです。
ですので、あなたが受験勉強をする意味(志望校に合格したい意味)は何か、一度整理をしてみましょう。
以下に、受験勉強をする意味や理由として考えられる一般的な例を挙げますので、あなたが受験勉強の意味を理解する上での参考にしてみてください。
(1)興味のあることを勉強したい

これは、特に大学受験で志望校を目指す人に当てはまるかもしれません。
興味があることを勉強したいという理由で受験勉強に取り組むあなたは、志望校で何をしたいのかを改めて考えてみましょう。
難しく考えず、以下のようにシンプルに自分のやりたいことを思い浮かべてみてください。
- 英文学を学びたい
- 人の心理を研究したい
- ロボット工学の仕組みに詳しくなりたい
こうして、自分のやりたいことを再確認できるだけでも、モチベーションは上がります。
よく考えてみたら、自分が学びたいことは別にあるかもしれないと感じても、それは全く問題はありません。
改めて新しい目標ができることで、自然と勉強の意欲は上がっていきます。
(2)将来やりたいことがある

進学した学校を卒業した後に、将来やりたいことを実現するために受験勉強をするという人もいるでしょう。
特定の学校を卒業しなければ取得できない資格などがある場合は、その実現に向けて受験勉強をする必要があります。
その資格を取って活躍する姿を思い浮かべることで、勉強のやる気が上がるのではないでしょうか。
もう一つのパターンとして、よく調べたら資格取得のためには大学進学(・大卒資格)は不要だったという可能性があります。
例えば、柔道整復師、看護師、理学療法士などの国家資格を得るには、大学(短大)と専門学校の二つのルートがあるのです。
専門学校にも入試はあり、大学の難易度もさまざまではあります。ですが、一般的には大学の入試よりも専門学校の入試の方が簡単です。
いわゆる五教科の受験勉強が苦手なら、あなたのほしい資格が大学じゃないと(大卒じゃないと)取得できないものなのかを改めて確認することで、受験勉強の負担が大きく減る可能性がある、ということです。
ただしもちろん、専門学校の場合も、資格を得るための勉強は必要になってきます。
また、大学は資格のためだけに通うものではありません。一般教養と呼ばれる幅広い知識を学べたり、学ぶうちに進路変更もできるということは覚えておきましょう。
いずれにせよ、やりたいことを実現するための方法をいろいろと探ったり、進路を再設計したりすることで、改めてモチベーションが高まり、受験勉強の意味を理解できることもあります。
(3)引っ越したい、一人暮らしをしたい

以下のような希望も、受験勉強(進学)をする意味の一つでしょう。
- 地方に住んでいるから、都会に出たい
- 都会を離れたい
- 親元を離れて、一人暮らしをしたい
- 興味のある地域に住みたい
「受験・進学の目的が『進学後の勉強』じゃなくてもいいんだろうか…」と思っている人もいるかもしれません。ですが、目的は人それぞれで自由です。
この場合、ただ漠然と都会に出たい、一人暮らししたいと考えるよりも、都会で何をしたいのか、一人暮らしで何を経験したいのかなど、より具体的に考えることができれば、受験勉強の意味も、より理解しやすくなるでしょう。
方法②受験勉強から得られるものを考える

受験勉強は、自分の目的や夢を達成する手段のひとつです。
ですが、ただの手段ではなく、受験勉強自体から得られるものも確かにあります。
ここでは、受験勉強からどのようなものを得られるのかを考えてみましょう。
(1)知識がつく

受験勉強を行うことで、さまざまな知識が身につきます。
細かい知識は受験が終わると忘れるかもしれません。ですが、漠然とした知識は覚えていることが多いです。
例えば、歴史の場合、具体的な人名や年号は忘れるかもしれません。一方で、この国のこの辺でこんなことがあったということは覚えている場合もあることでしょう。
受験勉強を通して身につけた知識は、受験以外の場所で活かすことができます。
例えば、旅行に行ったとき、事前にその土地の知識や魅力を知っているだけで、観光をより一層有意義にできます。また、その知識をさらに深めたりなど、旅行ひとつでも楽しみ方の幅が広がります。
その他にも、受験勉強を通して身につけた知識は、多くの身の回りの物事に深く関係しています。
知識があれば、きっと勉強や仕事以外の場面でも、人生をより楽しむことができるでしょう。
(2)さまざまな力がつく
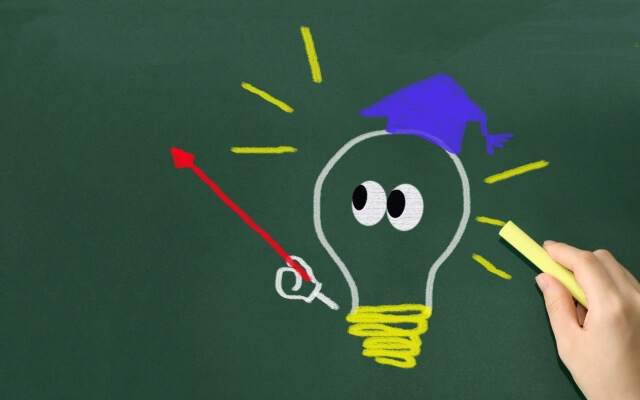
受験勉強を通じて、たくさんの力が身につきます。
例えば、その一つに論理的思考力が挙げられます。
受験問題の多くは、答えを導くためのヒントを問題文の中に散りばめてあります。
そのヒントをキャッチして組み立て、一つの答えを導き出すためには、論理的思考力が必要になります。
この場合は同時に、問題文の中からヒントをキャッチする観察力も身についていると言えるでしょう。
その他にも、あなた自身も気づかずに身についている力が、以下のようにたくさんあることでしょう。
- 長期間受験勉強を行うための忍耐力
- 志望校に合格するために、今は何を勉強するか、いつまでに何を勉強するか、ということを考える計画力
- 志望校を決める決断力
- わからない問題に対応する分析力
身につけたその力は現在進行形で、または困難やハードルが訪れた未来に必ず役に立ちます。
「この勉強を行うことでどんな力が身につくだろう」と考えながら受験勉強をすることも、モチベーションを上げる方法の一つです。
(3)自信がつく

受験勉強を忍耐強く続けたことで、自信をつけたという人もいます。
自分に自信が持てるようになりたいということをモチベーションに、勉強をするのもよいでしょう。
受験勉強でついた自信は、これから先、あなたに困難が訪れたとしても、それを乗り越えるための強みになります。
以下のように思うことで、訪れる困難に正面から立ち向かうことができます。
- こんなことくらい、受験勉強の苦しさに比べたらマシだ
- 受験勉強を乗り越えたのだから、これも乗り越えられる
そして、その困難を乗り越えることで、さらなる自信がつくことでしょう。
しかし、忍耐強く=無理をするということではありません。
無理をすることなく、適度な距離感で勉強に取り組むことが必要です。
方法③5秒ルールを意識する

5秒ルールとは、あれこれと色々考える前に、5秒のカウントの間に行動に移すというものです。(参考:メル・ロビンズ『5秒ルールー直感的に行動するためのシンプルな法則ー』)
あなたも、以下のようにやらない理由をつけて、勉強をしなかったことはありませんか?
- 昨日あまり寝ていないから、今日は勉強をやめておこうかな
- もう夕方で遅い時間だし、明日からにしようかな
脳は、やりたくないと思っていることに対して、やらない理由を考え出すとされています。
そして、その理由を考え出すまでの時間は、約5秒間と言われています。
何か行動を起こす際は、5秒のカウントを行い、ゼロになる前に行動を起こすと、その人のやる気のスイッチが入るというのが、この5秒ルールです。
あなたも、一度勉強に取りかかると、ある程度の時間続けて勉強ができたという経験をしたことがあるのではないでしょうか。
自転車も、漕ぎ出すまでは力が必要な一方で、漕ぎ続けるにはそれほど力が必要なくなります。
無理をしてはいけません。ですが、どうしてもやる気のスイッチを入れたいという際には、5秒ルールを意識することがオススメです。
方法④キリが悪いところで勉強を中断する

人間の習性には、中断している物事の方が記憶に残りやすいというものがあります。(参考:ヴィゴツキー『子どもの心はつくられる ヴィゴツキーの心理学講義』)
例えば、テレビCMの中で「続きはWEBで」のセリフを聞いたことはないでしょうか。
このセリフが気になって、そのモヤモヤを解消するために、実際にインターネットで検索した経験はありませんか?
こういったCMの手法も、中断している物事の方が記憶に残りやすいという人間の習性を利用したものだと言われています。
この習性は、もちろん勉強にも応用が可能です。
勉強への集中力が続かないと感じたら、一度キリが悪かったとしても、そこで手を止めてみましょう。
すると、キリが悪くて途中なのが気持ち悪いと感じるようになり、この気持ち悪さを解消するために、机に向かおうと思いやすくなるのです。
ですので、休憩を挟むときや一日の勉強を終えるときは、わざとキリの悪いところで中断して終えるようにしてみましょう。そうすると、休憩明けや翌日に再開しやすくなるかもしれません。
方法⑤誘惑がない場所で勉強する

自分の部屋で勉強をするには、ゲームやマンガといった誘惑を断ち切る強い意志が必要です。
ですので、誘惑が一切ない場所で勉強をするのがオススメです。
特に、あなたと同じく受験勉強をがんばっている仲間がいる場所は、自分も勉強をやる気にしてくれます。
具体的には、学校の図書館や塾の自習室といった場所です。
志望校の図書館が利用できる場合は、そこで勉強するのもよいでしょう。
大学の場合、図書館を一般に開放していることがあります。
以下は、東京での一例です。検索サイトなどで、あなたのお住まいの近くの図書館もぜひ調べてみてください。
また、こまめに勉強場所を移動するのもよいです。
長時間同じ場所で勉強することを苦痛に感じる場合は、時間などで区切って勉強場所を移動しましょう。席を移動するだけでも気分転換になります。
受験勉強をやらされている気持ちが強く、受験をやめたい場合の対処法
続いて、受験勉強をやらされている気持ちが強く、受験をやめたい場合です。
受験自体が自分の(積極的な)希望でなかったり、学校・学部などを親に指定されていたりするようなケースです。
ここからは、そんな悩みを持つあなたに向けて、少しでもそのモヤモヤした気持ちを解消できるようにお話しします。
STEP①受験勉強をやらされていると感じる理由を整理する

まずは、自分がどうして受験勉強をやらされているのかという理由を改めて整理した上で、言葉で説明できるようにしましょう。
以下のように、シンプルな理由でも問題ありません。
- 自分には受験以外のにやりたいことがはっきりしている
- 家族や周囲からの期待やプレッシャーが大きい
- 希望する学校・学部の受験が許されない
ここでは、ひとまず、なぜ受験勉強をやらされていると感じるのかを整理して、その理由を説明できるようになることが大切です。
STEP②周囲の人に相談してみる

受験勉強をやらされていると感じる理由をはっきりとさせたら、次に親御さん、ご友人や学校の先生など、あなたの信頼できる人に相談をしてみましょう。
特に、やりたいことがはっきりしている場合であれば、学校の先生に相談すると、受験以外の新たな進路が見つかるかもしれません。
逆に受験して進学することが、そのやりたいことを実現できる近道だと気づくこともあるかもしれません。
この時点で、あなたのやりたいことが学歴を重視しないものであるならば、その職業での成功者について調べてみて、自分の将来のお手本(ロールモデル)となるような人を決めてもよいかもしれません。
ご家族からのプレッシャーが大きいといった場合にも、最初に整理した理由を正直に親御さんへお話してみることが大切です。
受験勉強をやらされていると感じるのであれば、それは自分の意志や気持ちとは違う行動をしているということになります。
親御さんとお話しする際は、感情的にならず、冷静に話し合うことが大切です。
例えば、適度に周囲の目があるような静かなカフェや公園などを話し合う場所にすることで、冷静に話を進めることができます。
また、家族だけで話す以外に、学校の先生やスクールカウンセラーなどを加えて話し合うこともオススメです。
結果としてあなたの希望に合う進路に進めることもあります。また逆にあなたが受験に前向きに取り組もうと考えを改めるかもしれません。
しかし、話し合ってもあなたの希望と親の希望が合わない場合もあるでしょう。
親は絶対に正しいわけではないものの、逆に今のあなたの考えが絶対に正しいとも言い切れないのが難しいところです。そして、受験や卒業は毎日近づいてきます。
冷静に話し合いを続け、なかなか理解し合えないときは、未成年者に対する親の責任と理解して、親の指示を一度受け入れるのも手段のひとつです。
進学先であなたの考え方を変える人との出会いもあるかもしれません。新たにやりたいことが見つかることもあります。
また、高校や大学を卒業した後でも、自分がやりたいことに向けて再チャレンジすることは可能です。慌てることなく長い目で見て、目標を実現するということもよいかもしれません。
まとめ〜自分ひとりで悩まず、周囲の人に相談してみましょう〜

ここまでの話をまとめると以下のとおりです。
- 受験をやめたいという気持ちには2つのケースがある …勉強が思うように手につかなくて受験をやめたい、受験勉強をやらされている気持ちが強く、受験をやめたいの2とおり。
- 勉強が思うように手につかなくて受験をやめたい場合 …紹介したモチベーションアップの方法を実践してみましょう。
- 受験勉強をやらされている気持ちが強く、受験をやめたい場合 …受験をやめたい理由をしっかりと整理した上で、周囲の信頼できる人に相談しましょう。
どんな場合においても、大切なのは相談することです。
決して自分ひとりで思い悩んだり、先走ったりすることなく、周囲の人のさまざまな意見を聴いてから決断することをオススメします。
私たちキズキ共育塾も、あなたの悩みを解決する手助けができるかもしれません。
受験勉強を続けるにしてもやめるにしても、あなたの悩みや考えを、ぜひ一度私たちに聞かせてください。ご相談は無料です。
その上で、あなたに一番合った進路を、一緒に決めていけたらと思います。
Q&A よくある質問