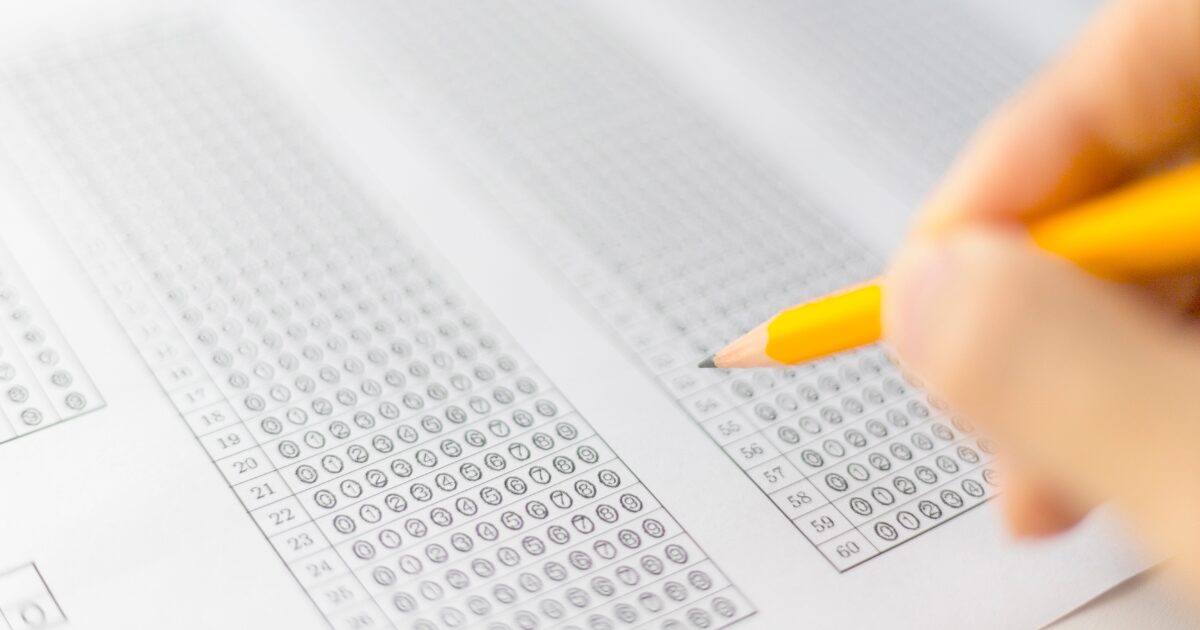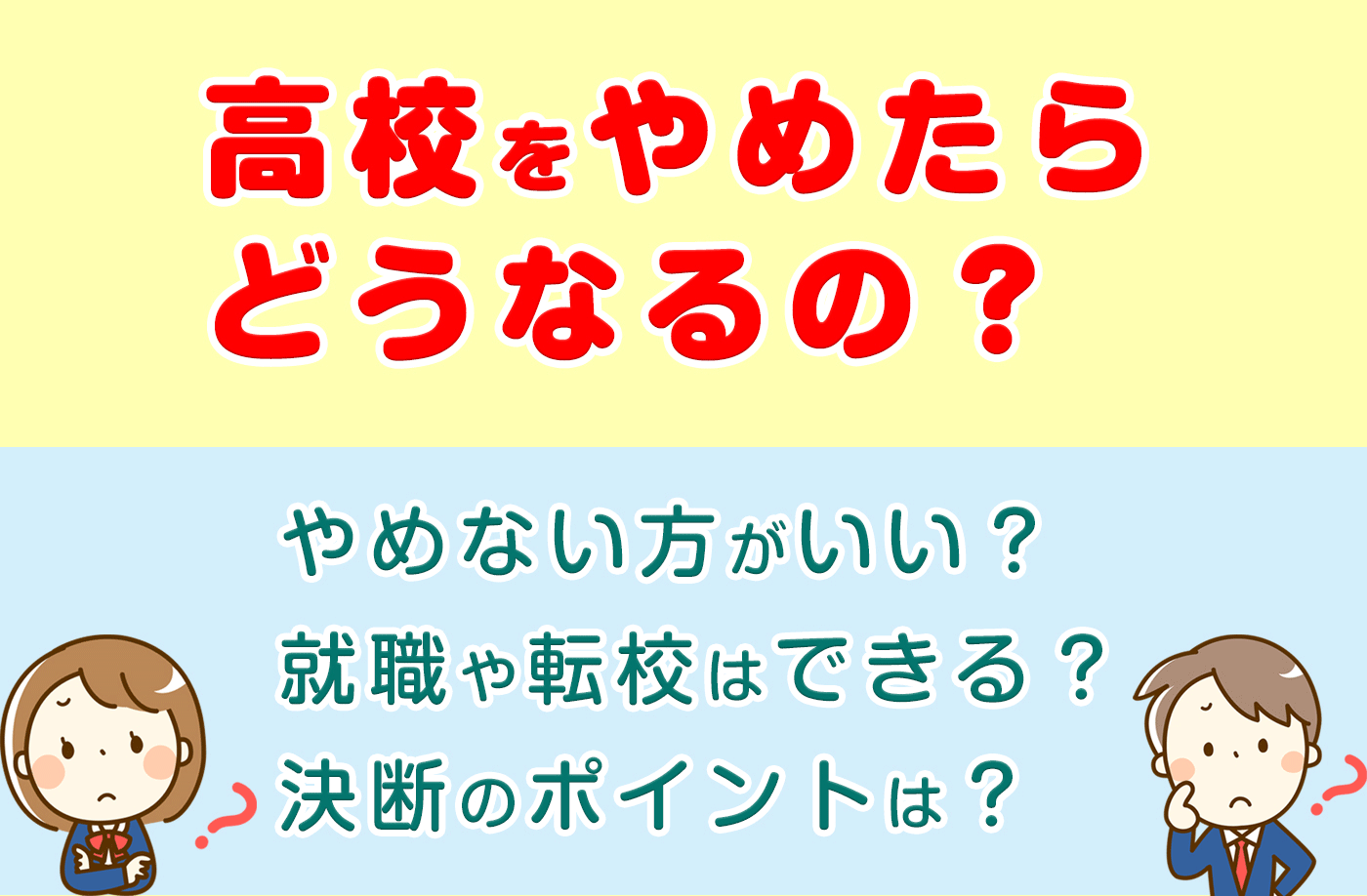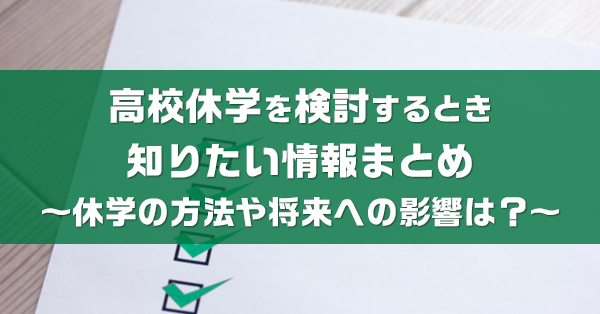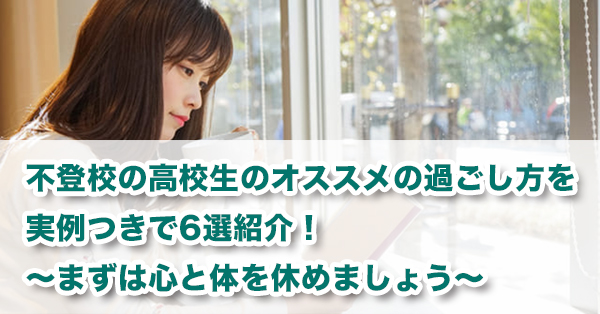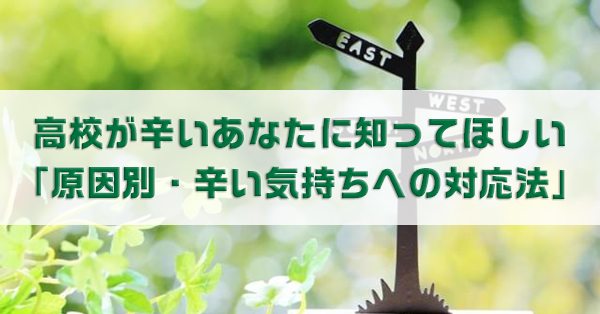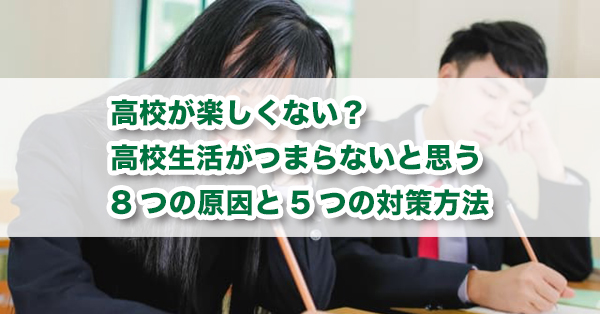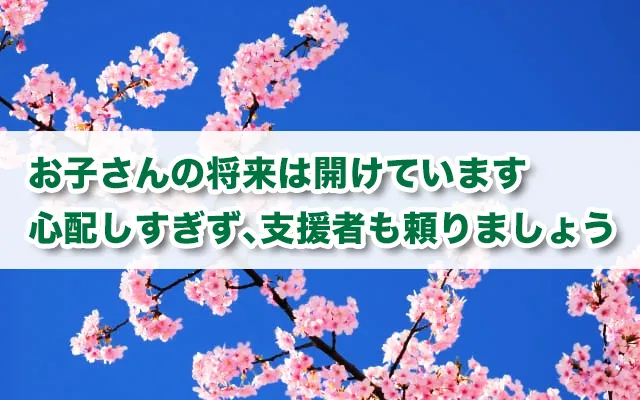高校休学を検討するとき知りたい情報まとめ 休学の方法や将来への影響を解説
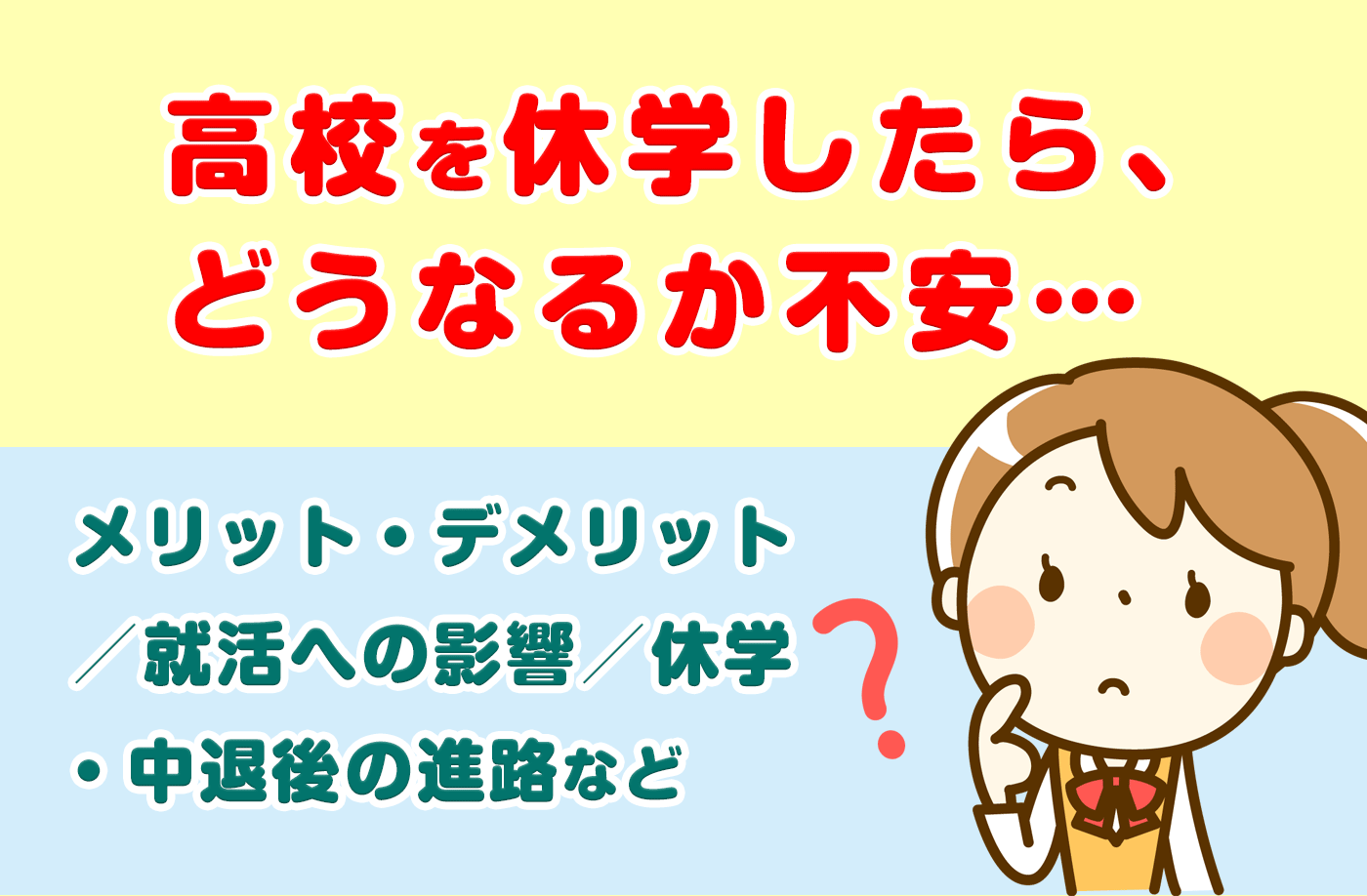
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾の岡田和哉です。
あなたは、デメリットが気になって、高校休学を決断できていませんか?
高校を休学したいと思う理由は、次のようにそれぞれです。
- 学校が合わなくて、このまま通い続ける理由がわからない
- やりたいことがあるので、いったん休学したい
- 不登校気味で、先生に休学を勧められている
「休学すると、デメリットも多そうで将来が心配」というお悩みもよくお聞きします。
このコラムでは、高校休学の手続き方法や高校休学のメリット・デメリット・影響今の高校に残る以外の選択肢について解説します。
このコラムを読むことで、「実際に休学するかどうか」「今後の進路の選択」のヒントが見つかると思います。
私たちキズキ共育塾は、高校休学を検討している人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
高校休学の手続き方法
一般的に、「休学届」を高校に提出して、校長先生に認められれば休学となります。
病気が理由で休学したい場合は、医師の診断書も必要です。
休学の手続きについては、校則に書かれていると思いますので、確認してください。
例えば、東京学芸大学附属高等学校の校則には、次のように記されています。
第24条 疾病その他特別の理由により,引き続き3月以上修学することができない者は,校長の許可を得て,休学することができる。
(東京学芸大学「国立大学法人東京学芸大学例規集」)
実際には、「校則を見ても、具体的にどう行動すれば休学できるのかがわからない(休学届の書き方や提出方法がわからない)」ということもありますので、校則を確認した上で、担任の先生や頼りになる先生に聞いてみることをオススメします。
高校休学のメリット・デメリット・影響
この章では、高校休学のメリット・デメリット・影響について解説します。
「高校を休学するかしないか」という決断は、時間をかけて考えても困ることはほとんどありません。あせらずに、よく考えることをオススメします。
①高校休学のメリット(よい点)
まずは、メリットです。
メリット①授業料が免除される
休学期間中は、授業料が免除されたり減額されたりする学校が多いようです。
休学ではない(長期の)欠席だと学費を払う必要がありますので、長く休むことが決まっている場合や、長く休む必要がある場合は、金銭的には休学した方が得になります。
ただし、休学中の学費の扱いは学校によって、また休学の理由によって異なります。あなたの高校が実際にどうなっているのかは、高校に確認しましょう。
メリット②自由な時間が増えて、様々な経験ができる
休学期間中は、学校に行く必要がありません。学校に行かない分、自由な時間が増えますので、様々なことを行えるようになります。
【例】(短期)留学、アルバイト、スポーツ・文化・芸術活動などへの集中的な取り組み
ただし、「様々なこと」は、高校を休学しなくても行える場合も多くあります。「休学しなくては○○はできない」と思い込まず、休学のデメリットも含めて様々なことを考慮し、周りの人によく相談しましょう。
②高校休学のデメリット
続いて、デメリット(注意点)です。
注意点①休学すると留年する可能性が高い
高校を卒業するためには、最低3年間の高校在籍期間が必要です。休学中の期間は在籍期間に含まれないため、原則的には、休学すると留年します(休学期間を在籍期間に含む高校もあるようですが、例外と考えた方がよいでしょう)。
また、高校を卒業するためには、各科目で合計74単位(以上)の取得も必要です。単位とは、「高校で必要な各科目を学んだ」という証明のようなものであり、各科目で、授業出席日数と成績が基準を上回れば取得できます。
休学のタイミングによっては、その学年での単位認定がされず、留年することになります。
※留年は悪いことではありませんが、「直近の将来がどうなるのか」ということは、考えておいた方がよいでしょう。在籍期間・単位認定ともに、「どういう休学をすると、自分はどうなるのか」を高校によく確認しましょう。
注意点②留年すると気まずい
留年は悪いことではありませんし、長い人生では大した話でもありませんので、留年しても気にする必要はありません。…と人から言われても、留年した本人は、気まずく感じることもあります。
「留年したという事実」「新しいクラスメイトと年齢が違うこと」「元の同級生が進級・卒業したこと」など。「自分は気にしないと思っていた」という人でも、実際にその状況になると気まずくなった、という人もいます。
「覚悟」というと大げさですが、休学して留年する場合には、「最初は気まずい思いをする可能性」は、考えておいた方がよいかもしれません。ただ、「自分が思うより、周りは自分のことを気にしなかったので、最初さえ乗り越えれば大丈夫だった」という声も少なくありません。
③高校休学の就職への影響

高校級額は、「絶対に不利」ということはありませんし、伝え方次第では有利にもなります。
実際に休学した場合、就職活動時の履歴書やエントリーシートなどには、「休学の事実」は、期間や簡単な理由と合わせて書くのが一般的です。
休学の理由は、面接で聞かれることが多いと言えるでしょう。
病気や怪我などの「仕方ない理由」での休学や、留学などの「前向きな理由」の休学の場合は、正直に伝えれば問題はありません。
また、ネガティブにとらえられやすい理由での休学だとしても、「その後どう過ごしてきたか、これからどうしたいか」を伝えれば大丈夫です。伝える内容や伝え方によっては、プラスになることもあります。
高校休学についてどのように伝えればよいのかわからないときは、同じように「高校休学を経験して、就職した人」に話を聞いてみるとよいでしょう。
ご紹介してきた高校休学のメリット・デメリットなどを考え、実際にどうするのか、次のような選択肢についてじっくり考えてみましょう。
選択肢の例
- 休学する
- 休学ではなく、(長期)欠席する
- 中退して、別の高校などに入り直す
- 中退しないで(書類上、高校に在籍していない日がないようにして)、別の高校などに転校する
今の高校に残る以外の選択肢は?
この章では、今の高校に残る以外の選択肢について解説します。
進路①通信制高校

高校中退後の編入先として人気が高いのが、通信制高校です。
通信制高校の特徴
- 毎日の通学が必要ない
- 入試は面接や作文のところも多く、無試験の学校もある
- 勉強は、学校から送られてくる教材を利用して、自宅学習を中心に進める
- 単位取得は、レポート提出・年に数回の登校授業・定期テストなどで行う
学校によって、文化祭などのイベントの有無や、卒業までに必要となる出席日数(スクーリング)が大きく異なります。気になる学校が見つかったら、特徴をよく調べましょう。
自分のペースで勉強したい方や、継続的な通学に苦手意識のある方にオススメです。
進路②定時制高校

定時制高校も、高校中退からの進路として洗濯しやすい高校です。
定時制高校の特徴
- 平日は毎日学校に通って授業を受ける
- 授業が、昼から夕方・夜にかけて行われる(朝から行う高校もある)
- 入試は面接や作文のところも多く、無試験の学校もある
- 昼間に働いている社会人や、高校を卒業していない高齢者なども在籍している
学校によっては、全日制高校よりも卒業までの在籍期間が長くなる場合もあります。気になる高校が見つかったら、その学校の制度をよく確認しましょう。
また、通学時間帯を選べる学校の場合、時間帯によって生徒のタイプが全く異なる場合もあるので、自分の性格と合うかなども確認することが大切です。
基本的には毎日出席する必要があるため、通学が苦にならない方や、友達と学校生活を送りたいという方にはオススメです。
進路③高卒認定試験
高校卒業程度認定試験(高卒認定、高認)とは、合格すると、高校を卒業せずに大学や専門学校の受験が可能になる試験のことです。
「働きながら」や「高校に在籍しながら」でも受験することもできます。
高認の特徴
- 試験に合格すれば、高卒資格が必要な大学や専門学校の受験・入学が可能になる
- 試験内容は、比較的カンタン(※)
- 満16歳以上であれば受験できる
- 年に2回、各都道府県で実施される
- 昔は「大検」と呼ばれていた
(※)試験内容は、大学受験などと比べるとカンタンなのですが、勉強に慣れていない方や、効率的に勉強したい方などは、高卒認定試験の対策を行う塾などに通った方がよいでしょう。
大学受験に現役年齢で受験したい方や、高校に通わずに大学などの受験資格がほしいという方にオススメです。
進路④全日制高校
全日制高校とは、いわゆる「普通の」高校です。
全日制高校の特徴
- 高校と聞いてよくイメージされる、「平日に、朝から夕方まで、学校で授業を受ける高校」のこと
- 病気や引っ越しなどの特別な事情がないと、転校できないことが多い
全日制高校は、高校を中退したかどうかに関わらず、転校生の受け入れ(転入・編入)はあまり行っていないので、現実的にハードルが高いことは、正直にお伝えします。
ただ、転校ではなく、もう一度高校受験を行い、一年生から改めて高校生活を始めることは可能です。
新しい環境で最初から高校生活をやり直したい方にはオススメです。
ですが、例えば同じ市内の別の高校に再入学したりすると、中学時代の知り合いや、部活で交流のあった人などがいたりすることもあるため、「全く新しい環境」とはならない可能性もあります。
他の高校同様、「自分が3年間その高校で過ごせそうか」とイメージして、どんな学校なのかを調べておきましょう。
別の高校などの選択肢の注意点

全日制高校以外の高校は、中退率が高く、大学進学率が低い傾向にあります。
一例として、2021年度のそれぞれの中退率は、次のようになっています。(文部科学省「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」)
- 全日制高校:0.9%
- 通信制高校:3.8%
- 定時制高校:6.9%
高校を(再び)中退することは「悪いこと」ではありませんし、高校を卒業したら大学に進学しなくてはいけない、ということもありません。
ですが、直近の将来で自分がどうなりたいか(なりたくないか)は、考えておいた方が、より楽しく(楽に、面白く、充実して)過ごせる可能性が高いでしょう。
休学後に(または休学せずに)別の高校に転校したり高卒認定合格を目指したりするなら、次のようなことを調べて、詳しい人や周りの人に相談して、しっかり検討して決断しましょう。
検討のポイント
- その高校が自分に合いそうか
- 高校卒業後の進路(大学進学・就職)について、その高校のサポート体制がどうか
- 高校のサポート体制が薄そうなら、自分が通えそうな塾などがあるか
- 高卒認定試験を受けるなら、高卒認定の対策やその後の大学受験の勉強などをどうするか
まとめ〜しっかり相談してから決断しましょう〜

実際に高校を休学してもしなくても、「その後」がどうなるかはあなた次第です。
ですが、あなた一人で悩みを抱える必要はありません。
学校の先生、友達、家族、塾、場合によっては医療機関の人など、いろんな人に相談したり、転校するなら候補となる高校を見学に行ったりした上で、今後どうするかを決断しましょう。
私たちキズキ共育塾も、休学に関するご相談をお受けしています。
相談は無料ですので、気になるようでしたらお気軽にご相談ください。
あなたの今後の生活がよりよいものになるよう、ご協力します。
/Q&Aよくある質問