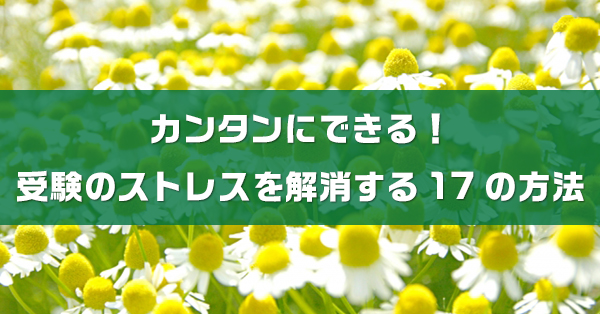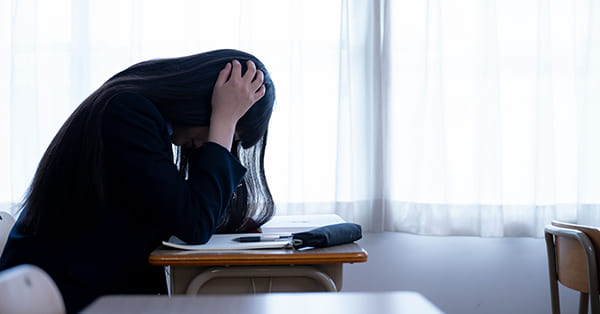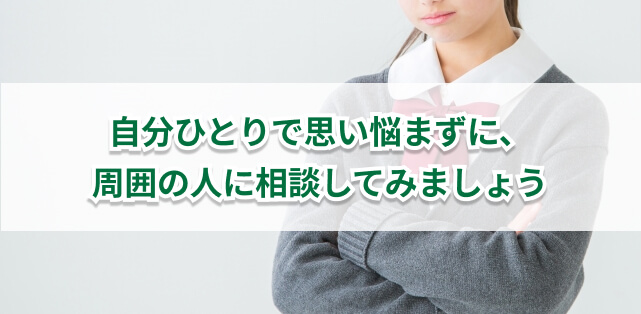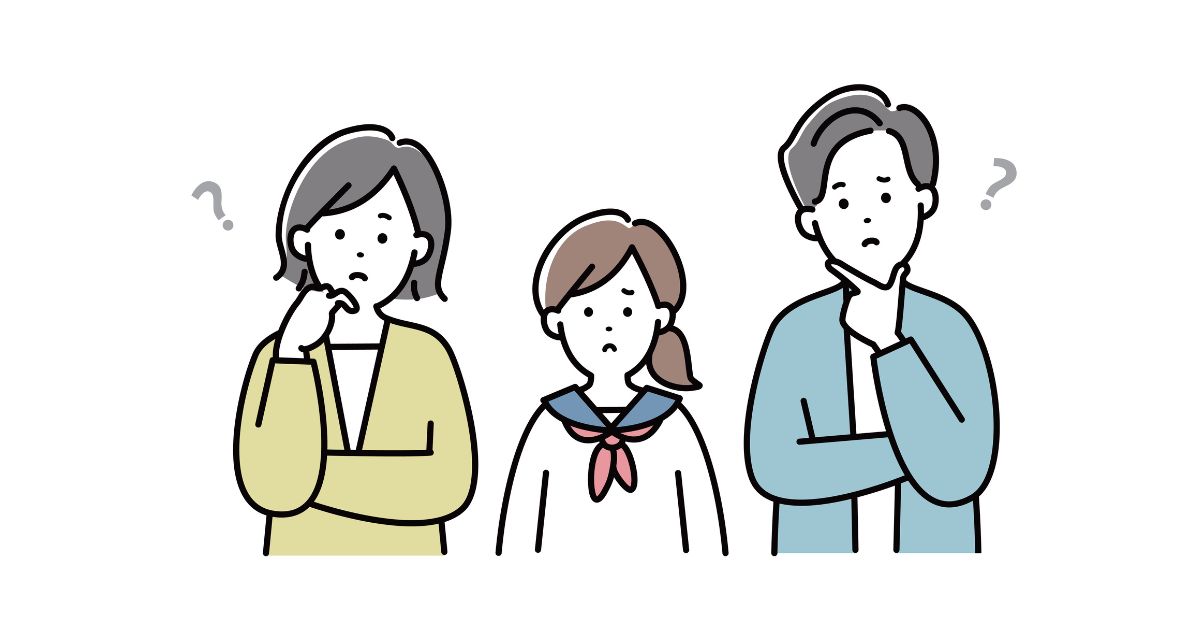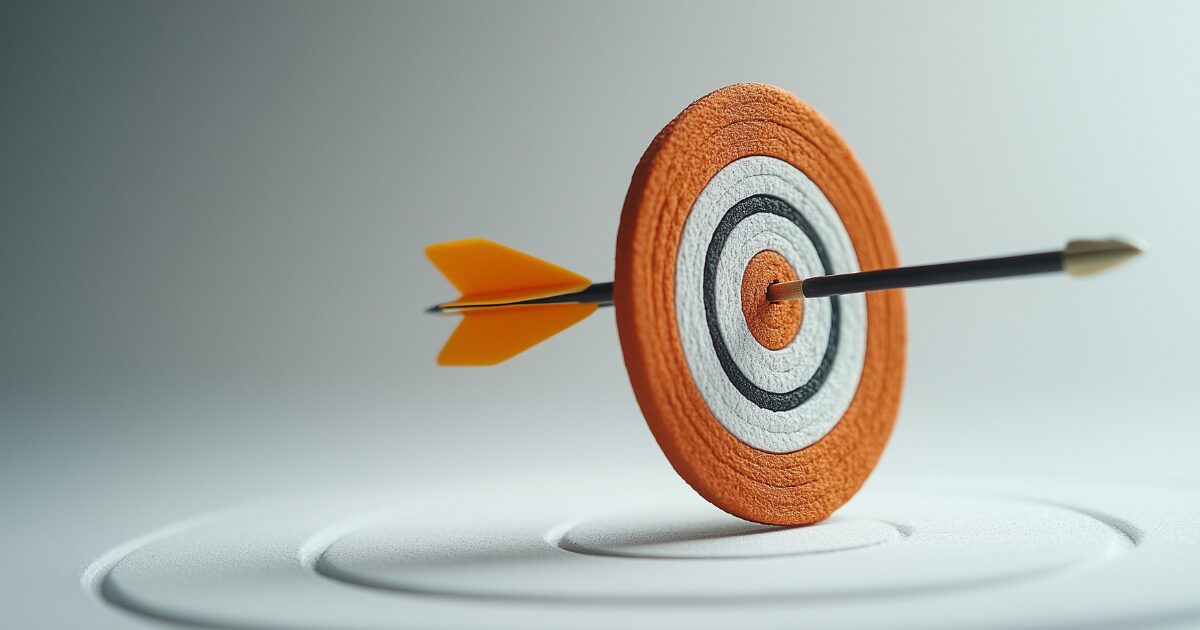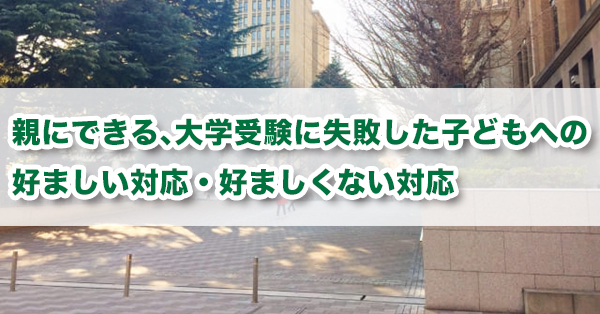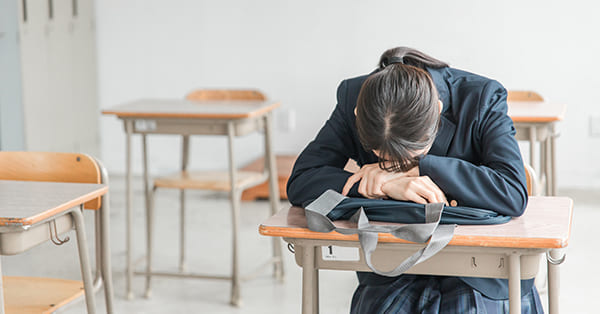社会人が大学受験を成功させるポイント8選 勉強方法を解説
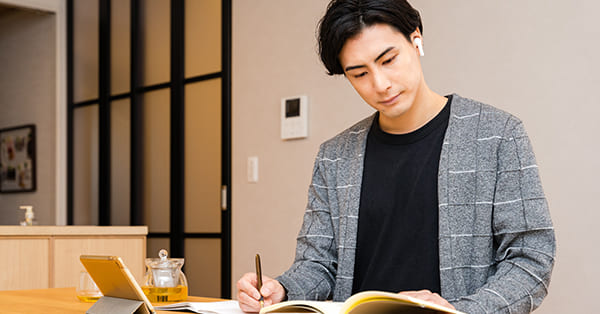
こんにちは。社会人の大学受験を完全個別指導で応援するキズキ共育塾です。
大学受験を考えている社会人のあなたは、以下のようなことでお悩みではないでしょうか?
- 具体的に何をしたらいいのかわかりません
- 実際に受験に挑んでも、受かるかどうか不安です
このコラムでは、社会人が大学受験を成功させるためのポイントや勉強方法、有利な理由、社会人が大学進学するメリット、社会人が大学受験する際の注意点を解説します。あわせて「社会人の大学受験」の成功体験談を紹介します。
社会人からの大学受験を目指す人は少なくありません。
そして、ポイントを押さえて受験に臨めば、社会人からの大学進学は充分に可能です。
あなたの「社会人の大学受験」に関するお悩み解決の一助となれば幸いです。
私たちキズキ共育塾は、社会人から大学受験を目指す人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
社会人が大学受験を成功させるためのポイント8選
この章では、社会人が大学受験を成功させるためのポイントについて解説します。
前提として大切なポイントは、「周りの人の力を上手に借りること」です。
大学受験に合格するためには、個人の努力はもちろん必要です。
ですが、社会人の大学受験をサポートする団体、ご家族、職場などの力を上手に借りることで、受験勉強も、その後の大学生活も、グッとスムーズに進みます。
なお、現時点で志望校や学びたい分野が定まっていない場合でも、各ポイントをこなすうちに定まっていくと思います。
ポイント①社会人の大学受験に詳しい学習塾などを利用する

1つ目のポイントは、「社会人の大学受験に詳しい学習塾などを利用する」です。
社会人の大学受験に詳しい学習塾・予備校・サポート団体などは、もちろん存在します。
受験・進学・周囲への相談などについて、あなた一人で考えるよりも、そういう学習塾などを利用するのがオススメです。
そうすることで、次のようなことについて、「あなたに向いた、よりよい案」がわかります。
- 志望校探し
- 受験に向けたスケジュール
- 受験方式(一般受験、社会人入試、総合型選抜入試(旧:AO入試)など)
- 受験勉強の方法
これから紹介する各ポイントについても、頼れる相手に積極的に相談することを心がけましょう。
なお、私たちキズキ共育塾にも、大学受験を目指す社会人の生徒さんがたくさんいます。ご相談は無料で受け付けていますので、少しでも気になる場合はお気軽にご連絡ください。
ポイント②家族に相談する
2点目は、「家族に相談する」です。ご家族に相談し、協力を得ることで、受験勉強はよりよい方向に進んでいきます。
特に相談が必要なのは、次のような方々です。
- 既婚者の方
- 「家族」や「実家」の家計を担っている方
- 家族に学費を頼ることを考えている方など
「言いづらいな…」と思って相談をためらっていると、勉強に身が入らなかったり、受験を途中で反対されたりすることがあるのです。
あなたの受験にご家族が関係する場合は、大学受験を検討しはじめた段階で、きちんと相談しましょう。
相談内容の例
- 仕事をどうするかも含めて、今後の収入や生活について話したい
- 受験勉強に集中したいから、一時的に家事や仕事を減らしたい
ただし、家族に反対されたとしても、「家族が反対する理由」を確認することで、対策や、その理由を上回るメリットなどを考えられるようになります。
どのように相談したらいいのかわからない人は、社会人の大学受験をサポートする学習塾などに、相談方法を相談してみましょう。私たちキズキ共育塾でも無料相談を行っています。
なお、「大学受験・進学について、お金も生活も、家族には影響がない」と思っている人も、家族仲が悪くない限りは、一応話しておくことをオススメします。
それは、次のような理由からです。
- 「思わぬ協力」を得られるかもしれない
- 「現時点であなたは知らないけれど、今後のあなたの生活に影響しそうな事情」があるかもしれない
ポイント③職場に相談する

大学受験について、職場の人たちにも相談してみましょう。
職場によっては、次のような配慮がなされる可能性があります。
配慮の例
- 時短勤務
- 残業が少ない部署・業務への異動・配置転換
- 退職ではなく、休職を選択可能
- 受験シーズンの連続休暇
- 業務に関連する学部の場合、お勤め先から奨励金がもらえることも
「受験勉強や大学進学のためには、退職するしかない」と思い込まず、人事や総務などの部署に相談してみましょう。
ポイント④大学受験・進学の目的を明確化する
4つ目のポイントは、「大学受験・進学の目的を明確にする」です。
目的がはっきりしていれば、進学後や卒業後のイメージがつきやすく、勉強のモチベーションにもつながります。
明確ではない場合、次のような迷いが生じて、勉強に集中できないことがあるのです。
- 本当に大学に進学できるんだろうか
- 大学に行けたとして、その後どうなるんだろうか
そうした迷いを解消するために、いま一度、大学受験・進学の目的を明確化することをオススメします。
目的を明確にするのが難しい場合は、他のポイントを充実させるようにしましょう。
大学に進学する意味については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ポイント⑤入試形式を決める

5点目は、「入試形式を決める」です。
主な例として、一般入試、社会人入試、総合型選抜入試(旧:AO入試)があります。
受験資格は、どの方式でも共通して、次のどれか一つは必要です。
受験資格
- 高校卒業
- 高卒認定の取得
- 高等専修学校や高専での一定の在籍・成績
高卒認定については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
高等専修学校・高専については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
入試形式の詳細については、こちらで解説しています。
ポイント⑥大学生活に必要な費用と卒業条件を調べる
6点目は、「大学生活に必要な費用と卒業条件を調べる」です。
まず、大学生活に必要な費用には、次のようなものがあります。
- 入学金
- 授業料
- 施設利用費
- 教科書代など
費目も金額も、学校によって大きく異なります。
次に、卒業条件というのは、「卒業のために、通常の授業・試験・レポートの他に、必要なことがあるかどうか」ということです。
例えば、次のようなものがあります。
- 1年間の留学が必須
- 卒業論文の執筆が必須
学費や卒業条件をよく調べて、現実的に進学や卒業が可能かを検討しましょう。
「可能である」とわかると、受験勉強のモチベーションはきっと上がっていきます。
ポイント⑦大学進学の目的から入試科目を検討する

7点目は、「大学受験の入試科目を決める」です。
社会人が大学受験の科目選択をするときには、「昔の得意科目・苦手科目」にこだわりすぎないことが大切です。
「自分は、何を学びたくて、大学に入ろうとしているのか」から考えましょう。
次の例から、考えてみてください。
進学目的の例
この方は、理科のうち、どの科目を選ぶべきでしょうか。
答え:物理 この方は、物理を選ぶべきです。 なぜなら、機械工学を学ぶためには、物理の知識が必須だからです。つまり、大学受験の勉強を通じて、大学の勉強の基礎となる部分を身につけておく必要があるのです。
「かつて得意か苦手だったか」という視点ではなく、「今から何を学びたいのか、そのために必須な科目は何か」という視点で、受験科目を選びましょう。
ちょっと大変かもしれませんが、大学生活にきっと役立ちます。
「大学で学びたい内容」と「受験科目」が直接的に関係ない場合には、好きな科目や得意な科目を選んでOKです。
例えば、法学部の受験なら、世界史と日本史のどちらを選んでもよいでしょう。
ポイント⑧効率のよい勉強計画を立てる
最後のポイントは、「効率のよい勉強計画を立てる」です。
仕事を続けながら大学受験を目指す方は、勉強に使える時間が限られている上に、仕事の悩みや疲労もあるでしょう。
退職した方も、勉強が思うように進まなければ、あせりやプレッシャーを感じます。
そうした状況は、効率のよい勉強計画を立てることで解決できます。
例えば、次のような例があります。
- 「科目や単元の勉強順序」を考える(数学の特定の単元を先に勉強しておくことで物理の理解が早まるなど)
- 「一日の中で効率よく勉強できるタイミング」を知る(夜は集中できないけど朝から午後には集中できるなど)
このように、勉強の計画をしっかり立てることで、大学受験を成功させることができます。
社会人が大学受験を成功させるための勉強方法4選
社会人から大学受験に挑戦する場合、勉強から離れている期間が長く「どのように勉強すればいいんだろう…?」と、不安になることも多いと思います。
この章では、社会人が大学受験を成功させるための勉強方法について解説します。
キズキ共育塾に通い大学受験に成功した社会人の生徒さんの経験をもとにお伝えします。参考になる情報が見つかるはずです。
勉強方法①基礎をしっかりと固める
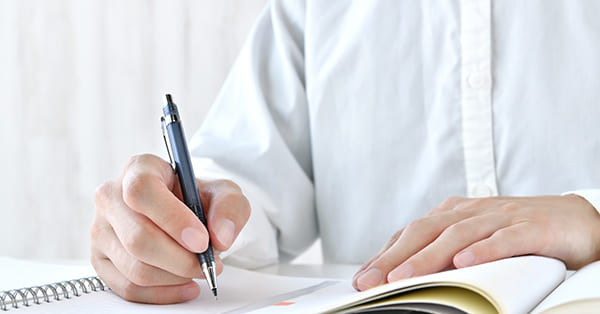
1つ目の勉強方法は、基礎をしっかりと固めることです。
社会人からの大学受験に限ったことではありませんが、受験勉強において基礎固めは非常に重要です。
勉強において基礎は土台となるため、基礎が固まっていると、応用問題や難易度が高い問題に取り組む際につまづく可能性が低くなります。
また、問題演習や模試の際の正答率も安定するので、受験勉強中の精神的な負担を軽減できるでしょう。
高岡さん(仮名)は、結婚・出産を経験後、シングルマザーとなり、「子どもを一人で育てなければならない」ということから、就職活動を始めました。
しかし、「自分が社会に誇れるものがない」という思いが強く、大学受験に挑戦することを考えるようになり、キズキ共育塾に入塾しました。
高岡さんは、これまで勉強に一生懸命取り組んだ経験がなく、基礎からの勉強に取り組むことになったそうです。
それまでまともに勉強をした経験もなく。現状の課題に合わせて、基礎から徹底的にやり直してもらうことができたので、本当によかったです。
勉強と子育てを両立しながら受験勉強に取り組んでいましたが、試験当日にお子さんが病気にかかるという思わぬ事態に直面しました。しかし、そんな中でも、高岡さんは諦めなかったそうです。
嫌な予感はしていたのですが、センター試験と二次試験の当日に娘が病気にかかってしまいました。幸いなことに大事ありませんでしたが、受験直前の受験勉強は全く手につかず。
それでも先生のアドバイスを信じて、徹底して復習だけを行うようにしました。本番はすごく緊張していましたが、キズキ共育塾で勉強していた英語には手応えがありました。
ただ、その他の教科についてはさっぱり。対策が間に合わなかったところもあったので、半分あきらめていました。だからこそ、合格を知ったときは本当に信じられませんでした。
高岡さんの大学受験が成功した理由は、「基礎をしっかりと固めていたこと」だけではないかもしれません。
しかし、試験直前のトラブルを乗り越えて合格をつかみ取ることができた要因の1つとして、基礎から勉強に取り組んだことがあったのではないでしょうか。
社会人からの大学受験の場合、大学受験にかかる時間や金銭面などを考えると焦りが生じ、少しでも早く勉強を進めたい気持ちが強いと思います。
しかし、基礎が固まっているからこそ学力は伸び、安定もしていきます。ぜひ、基礎を大切にして、受験勉強を進めてみてください。
高岡さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
勉強方法②小論文は、添削を求める
2つ目の勉強方法は、小論文につき、詳しい人への添削を求めることです。
社会人入試は一般入試とは異なり、小論文が審査項目の1つになることが多いです。そのため、受験勉強の中で小論文に取り組むことは、非常に重要になります。
他の試験は独学でも対策ができなくはありません。ですが、小論文(文章)は、「正しくかけているかどうか」を自分で判断しにくいのです。
塾講師などの詳しい人に添削してもらうことで、「試験に合格するための小論文」を書けるようになっていきます。
三上さん(仮名)は、高校卒業後に就職しましたが、働くうちに「やっぱり大学に行きたいな」と思うようになったそうです。
結婚や転職などさまざまなことがあり、一時は大学受験が遠のいていましたが、思いが消えることはなく、大学受験のためキズキ共育塾に入塾。
学習院大学文学部の社会人入試を第一志望にした三上さんでしたが、小論文の勉強にかなり苦戦したそうです。しかし、キズキ共育塾の授業の中で、講師に小論文を見てもらうことで、少しずつ上達していきました。
小論文も、書いたことがなかったので、基礎から教えてもらいました。
正直、「大人だし、勉強しなくても書けるんじゃないの?」と思っていたんですが、実際に書いてみると、我ながら本当に稚拙な文章で…。「読む」のと「実際に書く」のでは全く違うものだと実感しましたね。
特に小論文は、「書いたものを誰か(講師)に見てもらう」のがとても有効だと感じました。」
こちらの体験談からも分かるとおり、いざ小論文を書こうとしても手が動かなかったり、書けたとしても高評価を得られる内容・書き方になっているかわからなかったりします。当然、文章を書くのが上手だったとしても、合格できる小論文が書けるかどうかは別の問題です。
小論文を上達させるためには、自分以外の誰かに書いたものを見てもらい、客観的な評価・フィードバックを受け、試行錯誤を重ねることがとても大切なのです。
これは小論文以外にも、記述式の問題にも当てはまります。志望する大学の試験問題に、記述形式の問題がある方も、ぜひこちらの勉強法を取り入れてみてください。
三上さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
勉強方法③テクニックや技法を取り入れる

3つ目の勉強方法は、テクニックや技法を取り入れることです。
テクニックや技法と聞くと、少し怪しい感じがするかもしれません。ですが、効率的に問題を解けたり、文章の内容を正確に把握できたりするテクニックや技法があるのです。
関根さん(仮名)は、一度大学を卒業していましたが、これまでに何かを頑張ったという経験がなく、自分に自信を持てずにいました。
そんなときに、一緒に働く人達の姿を見て、「自分も頑張ってみたい。努力してレベルアップしたい」という気持ちが芽生え、大学受験に挑戦するためにキズキ共育塾に入塾しました。
志望校の社会人入試ではTOEICのスコアが必要でしたが、ブランクがある状態だったため学び直さなければなりませんでした。
パラグラフリーディングといった英語の読み方を習ったのですが、今まで自分が感覚的に英語を読んでいた事に気づかされました。
パラグラフリーディングの方法論を苦手だったリスニングにも応用し、ひたすら演習を重ねました。結果、TOEICでは、990点満点中820点をとることができました。
関根さんは、パラグラフリーディングという英文読解のテクニックを知ったことで、これまでよりも正確に文章を把握することができ、TOEICで高得点を取ることができました。
他の教科でも、こういったテクニックや技法があります。もちろん全てのテクニックや技法が、全ての人に合うものだとは限りません。
ですが、取り入れることで勉強の効率が上がったり、問題の正答率が上がったりすることもあるのです。
関根さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
勉強方法④試験問題よりも難易度の高い問題に取り組む
試験問題よりも難易度が高い問題に取り組むことも、オススメの勉強方法の1つです。
この勉強方法に取り組むことで、試験問題が比較的解きやすいと感じられ、試験本番で精神的にも時間的にも余裕が生まれます。
とはいえ、試験問題と同程度の難易度の問題を、ある程度問題なく解けるようになってから実践してほしい方法なので、はじめから無理に難易度の高い問題に取り組む必要はありません。
相川さん(仮名)は、短大を卒業後に就職しましたが、あるとき自分が置かれている環境に物足りなさを感じ始めたそうです。
アメリカ留学を経て、これまで以上に「勉強したい!」という思いが強まり、キズキ共育塾に入塾し大学受験のための勉強を始めました。
受験本番まで約3ヶ月と時間はありませんでしたが、キズキ共育塾で一生懸命に勉強に取り組んだおかげで、最初は緊張していたものの、試験問題を解くうちに心に余裕を持つことができたそうです。
先ほどもお伝えしたとおり、受験勉強では基礎固めが非常に大切です。
ですが、相川さんのように、試験問題よりも難しい問題を日頃から解くことで、試験本番でも余裕をもって問題を解けることもあります。
他の勉強法と比べると優先順位は高くありませんが、受験本番までに精神的にも時間的にも余裕がある場合は、ぜひこの方法を試してみてください。
相川さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
社会人が大学受験勉強を有利に進められる3つの理由
大学受験について、社会人ならではの有利さがあります。
この章では、社会人が大学受験勉強を有利に進められる具体的な理由について解説します。
理由①スケジュール管理能力が高い

1つ目の理由は、「スケジュール管理能力が高い」です。
目標を見据えたスケジュール管理は、高校生よりも社会人の方が圧倒的に得意です。
仕事のスケジュール管理では、業務を予定どおりに進行させるための能力も、予定どおりに進まなくなったときにリカバリーする能力も必要です。
この能力は、、大学受験の勉強においても、予習復習をどう進行管理するか、予定どおりに勉強が進まなかったらいつ取り戻すか…といったように、大いに役に立ちます。
仕事同様スケジュールを意識して受験勉強に臨みましょう。
理由②目的が具体的だからモチベーションを維持しやすい
社会人が有利な2つ目の理由は、「目的が具体的だから大学受験のモチベーションを維持しやすい」です。
高校生と比べると、社会人の方が大学受験の目的が明確であることが多いです。
大学受験に向けて勉強を続けるためには、モチベーションの維持が欠かせません。
目的が具体的であればあるほど、モチベーションは持続します。
例えば、次のような感じです。
- 大学に行って国際関係学を学びたい
- 大学に行ってロボットの作り方を学びたい
次のように、直接学問に関係しない目的でもOKです。
- 素敵なキャンパスライフを送ってみたい
- 楽しくサークル活動をしたい
- 大学で学んで自分に自信をつけたい
大事なのは、「大学で『何か』をしたい」と思っている、その気持ちです。
その「何か(=目的)」が達成されるイメージを持つと、受験勉強がはかどるはずです。
理由③「社会人入試」を選択できる

3つ目の理由は、「社会人入試を選択できる」です。
社会人入試とは、「大学受験・進学を目指す社会人を対象とした入試」のことです。
社会人入試は一般入試よりも受験科目が少なく、書類審査やキャリアが重視されるため、社会人が挑戦しやすい試験内容になっています。
社会人が受験できる大学の種類
この章では、社会人が受験できる大学の種類について解説します。
前提として、「社会人だから受験できない」といった大学はありません。
ですが、大学によって特徴が異なるため、それぞれの大学について知ったうえで、どの大学を志望するかが大切です。
たとえば、大学には、四年制大学と短期大学があります。それぞれ、通学期間や学べることに違いがありますので、大学選びの際に詳しく調べてみてください。
また、ネット上での情報収集だけではなく、詳しい人への相談や大学への直接の問い合わせなども積極的に行いましょう。
種類①朝から夕方に通う大学
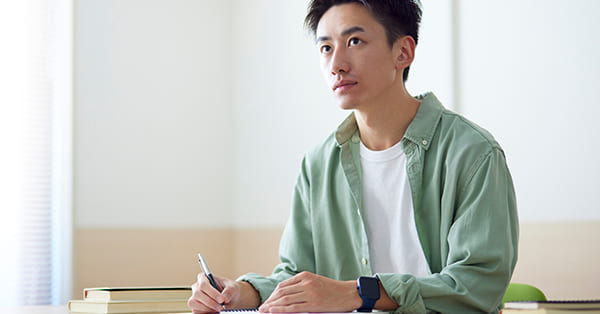
1つ目の種類は、朝から夕方に通う大学です。こちらの大学を「一般的な大学」としてイメージされる方は多いと思います。
昼間に仕事をしている方や、家事や育児で多忙な方にとっては、朝から夕方にかけて通う必要がある大学は、選択肢になりづらいかもしれません。
ですが、大学に通うための休職や時短勤務ができる方、仕事をやめることを考えている方、家事や育児を周りの人・関連サービスなどに頼れる方であれば、通える可能性があるでしょう。
一部では、制度として「大学通学のための休職・時短勤務」がある職場もあります。
お勤め先や、社会人・主婦・主夫の大学受験に詳しい人に相談することで「なんとかなる」こともありますので、まずは相談してみましょう。私たちキズキ共育塾でもご相談を受け付けています。
ほかにも、朝から夕方に通う大学には、次のような特徴があります。
- すべての学部・学科から選べる
- 学費が高くなりやすい
- 夜間学部(二部学部)と比べると若い学生が多い
- (昔と比べて)授業の出席確認・出席回数のハードルが厳しい
- グループワーク・実験などがある
- 先生との距離が近い
この中で、社会人だからこそ注意しておきたい特徴が、夜間学部(二部学部)と比べると若い学生が多いことです。
大学では、周りの学生と試験の情報を共有したり、協力して課題に取り組んだりします。そのため、若い人とのコミュニケーションや人間関係の構築が苦手な人は、朝から夕方に通う大学は向いていない可能性があります。
また、「授業に出席しなくても、試験や課題である程度の点数を取れれば単位をとれる」というイメージを持っている人も要注意です。
近頃の大学では、出席確認が厳しく行われている場合が多く、単位認定も試験や課題の評価に加えて「出席回数が全体の〇分の〇以上」などと決まっていることがあります。
朝から夕方に通う大学を志望したい方は、仕事や家事との両立に加えて、上記の特徴も踏まえて「自分に合うか」「入学後、問題なく通えそうか」を慎重に検討しましょう。
種類②夜間学部(二部学部)
2つ目の種類は、夜間学部(二部学部)です。
名前のとおり、夕方から夜にかけて授業が行われる大学(学部)なので、昼間に仕事をしている方でも仕事を辞めずに通えるでしょう。
ただし、近頃は夜間学部(二部学部)自体が少なくなっていたり、廃止されていたりしているというのが現状です。また、自宅から通える場所に夜間学部がないことも考えられます。
夜間学部(二部学部)を志望したい方は、各大学のウェブサイトで、「現在、夜間学部(二部学部)があるか」「今年度(以降に)も募集をしているか」について確認してみてください。
夜間学部(二部学部)には、夕方から夜にかけて授業が行われること以外にも、次のような特徴があります。
- 学費が安い
- 学生は社会人が多く、自分と似た状況の人たちと一緒に学べる
- 色々なバックグラウンドの人たちと出会える
特に、社会人の方だからこそ知っておきたい特徴は、夜間大学に通う学生の傾向です。
こちらで紹介した朝から夕方に通う大学の場合、若い学生が多い傾向があります。しかし、夜間大学の場合は、社会人を経験した人や働きながら通う人が多いです。
つまり、自分と似た状況の人や色々なバックグラウンドの人たちと一緒に学ぶことができるのです。
「周りに自分と似た状況の人がいると心強い」「色々なバックグラウンドを持った人と関わりたい」という人には、夜間学校が向いているでしょう。
種類③通信制大学・通信制過程

最後に紹介するのは、通信制大学・通信制課程です。
通信制大学・通信制過程では、大学のキャンパスに通う必要がなく、大学から送られている教材やネット教材をもとに勉強を進めていきます。
そのため、仕事や家事・育児などで多忙な場合であっても、時間の空いたときに自宅で勉強に取り組むことができるのです。
また、自宅から離れた場所にある大学も選択肢となり得るでしょう。一部、必要に応じて登校することもあります。
加えて、通信制過程は、いわゆる「有名な大学」にも設けられていることがあるので、気になる方はぜひ一度調べてみてください。
ほかにも、通信制大学・通信制課程には、さまざまな特徴があります。
- 通信制では学ぶことが難しい学部・学科がある
- 学費が安い
- 自分のペースで勉強できる
- 自分で勉強のスピード・スケジュールを管理する必要がある
- 卒業までに4年以上かかる可能性がある
- 周りの学生・教員などに質問しづらい
社会人だからこそ押さえておきたい特徴は、通信制では学ぶことが難しい学部・学科があることです。例えば、理系学部の通信過程の数は、文系学部の通信過程の数と比べると少ないといえます。
実験や実技などが多い学部・学科では、自宅での学習ができない可能性があります。そのため、希望する学部や学科によっては、通信制大学・通信制過程を選ぶことが難しいでしょう。
また、卒業までに4年以上かかる可能性があることも、押さえておいたほうがよいでしょう。通信制大学・通信制過程では、自分のペースで勉強できる一方で、勉強の進捗が遅くなると4年間では卒業できません。
卒業までにかかる期間が長くなると、自分や家族のライフプランはもちろん、働きながら通う場合は会社にも影響が出るでしょう。
通信制大学や通信制過程は、ハードルが低いように感じるかもしれませんが、他の大学とは違った特徴があるので、それらを押さえたうえで検討しましょう。
社会人が大学受験する際の入試形式
この章では、社会人が大学受験する際の入試形式について解説します。
形式①一般入試

「一般入試」とは、大学入試では最もメジャーな、いわゆる「学力一本勝負」の試験方式のことです。
一般入試の方法は、国公立大学と私立大学で異なります。
国公立
- 一次試験として、「大学入学共通テスト」を受験する
- 次に、各大学が作成する二次試験を受験する(一次試験の結果が悪いと、二次試験に進めない)
私立
- 大学独自の筆記試験を受験する(「大学入学共通テスト」の受験は不要)
- 大学・学部によっては、「大学入学共通テスト」の点数の提出が、筆記試験の代わりになることもある
形式②社会人入試
社会人入試とは、受験対象を社会人に限定した入試のことです。
「社会人入試」の特徴は、次のとおりです。
- 受験資格:高校卒業や高卒認定の他に、年齢(○○歳以上)や社会人経験(○○年以上の勤務経験)などの条件が加わる
- 合否判断:学力試験よりも、面接・小論文・書類審査などがメインに審査される(学力試験が重要な場合もある)
社会人入試は、受験勉強に使える時間が限られている社会人が比較的受験しやすい入試制度です。
面接や書類審査では、次のような質問で、将来を見通した判断の説明を求められます。
- その大学で学びたい理由
- 大学在学中から卒業後も含めたキャリアプラン
形式③総合型選抜入試(旧:AO入試)

最後は、総合型選抜入試(旧:AO入試)です。
総合型選抜入試では、大学側の求める人物像をもとに出願者の人格を判断して合否が決まります。
受験内容
- 従来は、書類審査や面接だけで出願者の個性・能力・目標などを審査していた
- 最近では、学力試験を課すところも増えている
試験内容や評価基準の点では、社会人入試と似ているともいえるでしょう。
ただし、総合型選抜入試は現役・浪人・社会人を問わず受験できることが多いので、社会人入試と比べて出願者が多くなります。
社会人入試で大学受験をするときの条件・流れ・難易度
この章では、社会人入試で大学受験をするときの条件や流れ、難易度について解説します。
①社会人入試の一般的な条件
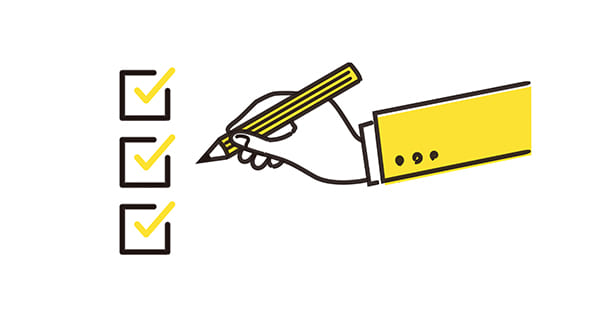
社会人入試で大学を受験するためには、一般的には、次の受験資格の両方をクリアする必要があります。
社会人入試の受験資格
- 大学受験(入学)資格を持つこと
- 年齢や社会人としての勤務年数
ただし、中には、勤務年数を問わず主婦やフリーターでも受けられる社会人入試もあります。受験したい大学に問い合わせてみてください。
「大学入学資格」については、次のどれか一つとお考えください。
大学入学資格
- 高校卒業
- 高卒認定の取得
- 高等専修学校や高専での一定の在籍・成績
高卒認定については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
高等専修学校・高専については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
「年齢や勤務年数」については、次のような条件があります。
年齢や勤務年数に関する条件
- 22歳以上の人が受験できる
- 3年以上の社会人経験がある人が受験できる
大学によって異なりますので、具体的に気になる大学があるなら調べてみましょう。
上記を踏まえて、出願の際は、一般的には以下のような証明書類等が必要になります。必要な書類の名称や内容は、大学によって異なるため、入学を希望する大学の出願情報を確認してみてください。
社会人入試の必要書類
- 入学願書
- 志望理由書
- 最終学歴の成績証明書や卒業証明書
- 推薦状(求められることは少ない)
「入学願書」とは、氏名・年齢・住所などを記入する事務的な書類のことです。大学から取り寄せることになります。
「志望理由書」とは、自分がなぜその大学・学部に入りたいのかを記入する書類のことです。合否の判定に大きく関わりますので、学習塾などで専門的な指導を受けて準備すると、合格につながる可能性が高くなります。
最終学歴の成績証明書や卒業証明書は、卒業した高校などに問い合わせましょう。発行に時間を要するため、早めの準備が必要です。
少数ではありますが、「推薦状」の提出を求めてくる大学もあります。推薦状とは、文字のとおり、「受験者をその大学に推薦する書類」のことです。推薦状は、一般的にはお勤め先の所属長や同僚に依頼することになるでしょう。こちらも、早めの準備が必要です。
②社会人入試の一般的な流れ
社会人入試に向けたスケジュールの一般的な流れについて、4月から大学受験に向けて準備を始めるケースを例に見てみましょう。
あくまで例ですので、4月から始めなくてはならない、という意味ではありません。
4月~ 大学に関する情報収集
- 社会人の大学受験に詳しい学習塾などへの相談開始
- 自分が学びたい分野や将来の目標の確認
- 志望校の学費、カリキュラム、入学・卒業条件などの確認
- 志望校の修学形式の確認(昼夜開講、夜間開講、通信制など)
- 志望校をある程度絞り込む
7月~ 出願準備と試験対策
- 志望理由書などの準備
- 証明書類などの発行申請
- 試験内容の傾向把握
- 試験勉強
9月~11月 出願と受験
- 出願や受験の時期は大学ごとに異なるため、要確認
- 出願方法も「インターネット出願」を受け付けているところとそうでないところがある
〜1月 合格発表と入学手続き
- 合格発表後は、所定の手続きに従って、期日までに学費の振り込みなどの手続きを進める
社会人入試では出願や受験の時期が「9月〜11月」であることが多いため、上記のようなスケジュールを例示しました。
ですが、大学によっては別の日程や、通年での募集を行っているところもあります。
各大学に合わせてスケジュールを立てることが大切です。
③社会人入試の一般的な難易度

社会人入試の一般的な難易度は、どの試験にも言えることですが、個人によって大きく異なります。
しかし、社会人入試の「有利な点」と「難しい点」を知れば、自分にとっての難易度をおおよそ推測することができるでしょう。
有利な点
- 入試科目が少ないことが多い
- 定員がはっきりと決まっておらず若干名になっているため、レベルが高い人が多いと合格者が多くなる可能性がある
- 面接や小論文などの試験で、これまでの人生経験が助けになることが多い
難しい点
- 同じ大学の中でも、学部によって社会人入試を行っているかどうかが異なる
- 試験で文章力を求められる
- 試験内容として面接が必須
- 年齢制限がある(若すぎると受けられない、何歳以上などの制限がある)
このように、社会人入試では小論文や面接の試験が行われることが多いため、これらが得意な人にとっては難易度が低く、逆に苦手な人は難易度が高いと感じるでしょう。
また、ほかのポイントについても、有利な点が多くあてはまる人と難しい点が多くあてはまる人によって、難易度は変わってくるはずです。
なお、実際に社会人入試を受ける生徒さんを指導してきたキズキ共育塾の講師の経験としては、「社会人入試は、ものすごく難易度が高い試験ではない」という感覚です。
具体的には、社会人入試のためにかかる期間は短ければ100日程であり、2年や3年と長期間勉強しなければ合格できないような試験ではない、ということです。
社会人が大学進学する3つのメリット
大学進学・卒業のメリットを、高卒と比較して、3つ紹介します。
大学進学のメリットを知ることで、あなたの大学受験のモチベーションアップや、「実際に大学受験をするかしないか」の決断に役に立つと思います。
メリット①充実した環境で専門的な勉強ができる

1つ目のメリットは、「充実した環境で専門的な勉強ができる」です。
高校までと大学での勉強は、次のように違います。
- 勉強内容:専攻科や専門分野を決めて勉強できる
- 先生:各分野の専門的な知識を有する先生(研究者・教授)から教えてもらえる
- 勉強方法:講義形式、ディスカッション、フィールドワーク、専門機器を用いた実験、長期に渡る共同研究など、さまざまな方法で勉強できる
- 図書館:専門書を多数所蔵している大学図書館で資料を探したり、自習したりできる
メリット②職種の幅が広くなる
2つ目のメリットは、「大卒の方が、高卒よりも職種の幅が広くなる」です。
学部で学んだ知識が必要な職種
学部と関係のない、関係が薄い職種
このように、大学を卒業することで、高卒よりも職種の幅が広がるというメリットがあるのです。
メリット③高卒よりも待遇がよくなる可能性がある

3つ目のメリットは、「高卒よりも待遇がよくなる可能性がある」です。
一般的には、高卒よりも大卒の方が、給料(初任給・生涯賃金)や出世において有利です。
退職金を含まない生涯賃金の比較は、次のようになっています。(参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構「ユースフル労働統計2023」)
- 大卒の男性:約3億2000万円
- 高卒の男性:約2億6000万円
- 大卒の女性:約2億5000万円
- 高卒の女性:約1億9000万円
また、正規雇用となる確率も、大卒の方が高いです。
15~34歳までの若年労働者における正社員の割合は、次のとおりです。(参考:厚生労働省「平成30年若年者雇用実態調査の概況」)
- 大卒の正社員割合:約80.9%
- 高卒の正社員割合:約56.3%
統計などを見る限り、給料・待遇・働き方などについても、大卒の方が高卒よりも「選択肢が広がる」ということは、事実と言ってよいでしょう。
しかしもちろん、労働の目的や価値はお金や出世「だけ」ではありません。また、非正規雇用は一概に「よくないもの」でもありません。
そして、「大卒だと、高卒よりも待遇が必ずよいわけでもない」のは、覚えておきましょう。
大学に進学する意味については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
社会人が大学受験する際の3つの注意点
社会人が大学受験を目指すときの注意点を、高校生や浪人生と比較して、3つ紹介します。
ただし、どれも「デメリット」というわけではなく「注意点」です。
「注意した上で、どうしていくか」を考えることで、大学受験は成功に近づいていきます。
こういう「注意点」についても、あなた一人で抱える必要はありません。
社会人の大学受験に詳しい塾などを利用すると、「あなたのための対策」が見つかります。これまでと繰り返しになる内容も一部ありますが、大切なことなので注意点として覚えておいてください。
注意点①受験勉強や大学生活と現在の仕事の兼ね合い
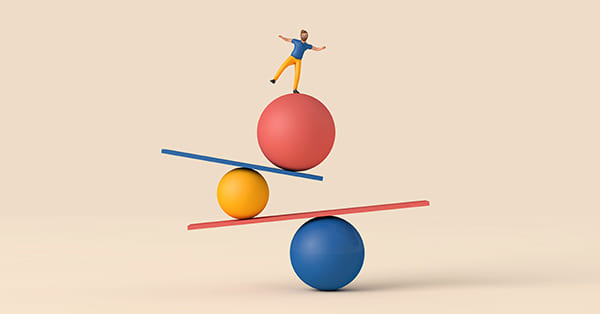
1点目として、「受験勉強や大学生活と現在の仕事の兼ね合い」を考える必要があります。
受験生活や大学生活を送る上で、仕事を辞めるか続けるかを判断しなくてはなりません。
- 退職する場合:勉強時間を確保できる代わりに、給料がなくなる
- 仕事を続ける場合:給料がある代わりに、勉強時間の確保が難しくなる
退職と仕事の継続には、一般的に「どちらが正解」と言える回答はありません。
なぜなら、次のようなポイントは個人や家庭によって異なるからです。
- 仕事の忙しさ
- 現在の学力
- モチベーション
- 目標の大学(学部)
- 資産など
- 合格後の大学生活の想定
特にあなたに配偶者や子どもがいる場合や、あなたが家計の中心を担っている場合などでは、「あなたの大学受験」であっても、「あなた一人の問題」ではないのです。
注意点②学費の捻出方法
2点目として、「学費の捻出方法」を考える必要があります。
仕事を辞める場合にはなおさらです。
社会人入試の面接では、在学中の生活費や学費について聞かれることもあります。
学費はもちろん学費以外の支出など、「大学在学中の家計をどこから捻出するか」については事前によく考えましょう。
ただし、社会人だからといって、「学費や生活費は、自分の収入や貯金だけで対応しなくてはいけない」わけではありません。
援助依頼や借金をするのも選択肢の一つです。親、きょうだい、配偶者、親戚、友人など、頼れそうな人がいるなら、正直に援助や借金を申し込むことは、恥ずかしいことではありません。もちろん、断られる可能性もありますし、返済が必要ならその計画も必要です。
また、奨学金も検討できるでしょう。社会人から大学進学をしても、応募できる奨学金はあります。奨学金については、こちらで解説しています。
注意点③卒業に向けた就職活動

最後は、「大卒としての就職活動」についての注意です。
特に仕事を辞めた方や、卒業後に新しい仕事に就きたい方などは、大学卒業を見越して就職活動を行う必要があります。
今から大学受験を行う場合、卒業は最短でも4年以上先のことですが、知っておいて損はないのでご紹介します。
社会人から大学に入った後の就職活動で、「新卒扱い」になるかどうかは、求人元によって異なります。
注意点
- 社会人経験がある方は、「新卒枠」に当てはまらないことがある
- 逆に、仕事から離れたことで、「中途枠」に応募できないこともある
いずれにしても、求人元によって扱いが異なります。
就職活動を行う場合には、各求人元に「自分が応募資格を満たしているか」を確認するようにしましょう。
なお、新卒で就職する場合には、社会人経験があっても、基本的には「初任給」からのスタートとなることも覚えておきましょう。
社会人から大学受験を成功させた5つの体験談
この章では、私たちキズキ共育塾の生徒さんの体験談を基に、社会人が大学受験を成功させた話について解説します。
ご紹介する全員が、志望大学・学部に合格しています。
繰り返すとおり、大学受験を成功させるためには、専門的な知見を持つ人に相談したり、学習塾を利用したりすることが効果的です。
体験談①スケジュール管理能力を活かしたAさん

Aさんは、仕事、プライベート、受験勉強の予定を手帳にキッチリ書きこむ几帳面な人でした。
講師が「昔からこんなに几帳面だったのですか」と聞いたところ、Aさんは「高校生のときは、こんなことは全くできませんでした」とのこと。
「社会人になって、嫌でもスケジュール管理せざるを得なくなった」――Aさんは、その経験のおかげで、大学受験の勉強も、具体的に計画・管理できるようになったそうです。
Aさんのスケジュール管理方法
- 大学受験までの全体的なスケジュールを把握する
- 勉強が仕事の都合で進まなかったときは、プライベートの予定を変更して勉強する
- 勉強が予想以上に進んだときは、思い切ってリフレッシュする
Aさんは、状況に合わせて柔軟かつ効果的にスケジュールを調整して、大学受験を成功させることができました。
体験談②大学進学の目的が明確だったBさん
Bさんは、高校卒業後には大学に進学せず、社会人としてずっと働いていました。
そして社会人としてさまざまな経験をするうちに、「教員になりたい」という目的が心の中に芽生えてきました。
その目的のために、Bさんは大学受験を目指し、キズキ共育塾に入塾。
Bさんはもともと勉強が得意ではなく、理解できるまで時間のかかる問題も多くありました。
そんなとき、Bさんは粘り強く、理解できるまで取り組み、積極的に講師に質問しました。
Bさんの「目的」による変化・効果
- 高校時代は、わからない部分があると勉強を続けられなかった
- それは、勉強に目的がなかったからだ
- 目的があると、わからない問題にもあきらめずに取り組めるし、それが楽しい
このように、具体的な目標はモチベーションの維持・向上に役立つのです。
体験談③勉強の遅れを積極的に取り戻したCさん

Cさんは、仕事を続けながら、大学受験を目指していました。
週に2日、仕事の帰りにキズキ共育塾で授業を受け、予習・復習は通勤の合間や休日に行っていました。
仕事で不測の事態が起きることも、少なくありませんでした。
授業の直前になって、Cさんから「仕事の都合で遅れます」という連絡をいただいたこともよくありました。
そんなときのCさんは、勉強の遅れを取り戻すために、講師に積極的な要望(例:「宿題を増やしてほしい」)を出していました。
仕事を辞めなくても、Cさんのように、積極的な姿勢を活かして大学受験に挑むことは可能なのです。
体験談④高校時代の苦手科目を克服したDさん
Dさんは、中学・高校時代に、社会科の「公民」分野が苦手でした。
一方、地理は得意で、高校卒業後も人並み以上の知識を持っていました。
Dさんの志望学部の受験では、地理と公民のどちらを選択しても問題ありませんでした。
ですが、Dさんが大学で学びたい分野には、公民の知識が必須だったのです。
Dさんは講師と話し合い、大学入学後のことを考えて、「得意だった地理ではなく、苦手だった公民で受験する」と決めました。
そして、授業や復習は次のように進めていきました。
Dさんの苦手科目克服法
- 中学生向けの教材を使って、基礎から学び直す
- 基礎が身についてから、高校内容・大学受験レベルの勉強に進む
- 学んだ内容を、自分で図式化する
- 復習や記憶定着のために、「学んだ内容を自分が人に説明すると考えて、どのようにまとめるか」を練習する
このような方法で授業を進めたことで、Dさんは、苦手だった公民の内容を理解できるようになっていきました。
体験談⑤30歳を超えてからの社会人入試で大学に合格したEさん

Eさんは、短大卒業後に就職して働いていました。そして、「もう一度勉強がしたい」と思い、大学受験への再チャレンジを決めました。
Eさんがキズキ共育塾に入塾したのは12月です。
直近の社会人入試は翌2月と、準備が間に合わない可能性も高い状況でした。
しかし、講師とも相談の上、「志望大学の社会人入試に向けた、効率よく勉強できる授業」を受けて、短期決戦に挑むことにしました。
Eさんの社会人入試対策
- 全ての勉強の基礎になる「文章力」を身に付ける
- そのために、小論文の演習を繰り返し行う
- 結果として、文章力・記述力だけでなく論理的な思考も身についた
身につけた文章力は、志望動機書を書くときにも大いに役立ちました。
Eさんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
キズキ共育塾の講師たちからの、「社会人の大学受験」のアドバイス
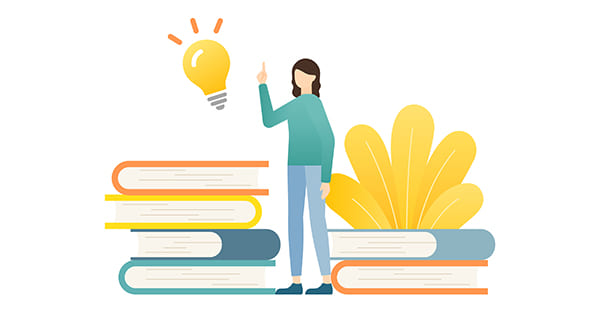
この章では、社会人のための個別指導塾・キズキ共育塾の講師たちからのアドバイスに基づいて「社会人の大学受験」について解説します。
実際に社会人の生徒さんと日々接している講師たちのアドバイスですので、きっと参考になると思います。
これまでの内容もキズキ共育塾の知見に基づくものであるため、一部重複する部分もあります。
また、私たちキズキ共育塾の無料相談では、「実際のあなた」のための、より具体的なアドバイスが可能です。ぜひご相談ください。
Y.N講師のアドバイス
「文系の、社会人入試」を利用する場合は、ほとんどの大学で面接と小論文が課されます。それぞれの対策が必要です。まずは志望校の学部・学科の専門分野についてあらかじめ調べて学んでおくことが大切です。
①小論文について
小論文では、関連分野について出題されると考えましょう。志望先でどのような過去問が出されていたかを参考に、類似の形式や題材を設定して複数回練習しましょう。
過去問はパスナビや大学の入試サイトに掲載されている場合が多いので、参考にしましょう。ネット上に出ていなくても、大学で直接過去問を閲覧できることがあります。ぜひ問い合わせてみてください。
また、説得力のある小論文を書くためには、時事問題に関する知識を身につけることが大変有効です。経済、社会、教育、法律分野の知識は、新聞を読むのが最も手っ取り早く、かつ確実です。
慣れないうちは、自分の関心のある記事やコラムなどを斜め読みする程度で構いません。ある程度続けていれば、さまざまな事件の経過や特定の問題を深掘りした解説記事などが目に入ってくると思います。新聞は紙媒体でも電子媒体でもいいのですが、紙媒体の方が一度に全体が視野に入るため、知りたい情報を効率的に認知できるメリットがあります。
②面接について
面接の対策で重要なのは、「大学に入って何を研究したいかを明確にしておくこと」です。そのため必要なことは、志望先にどのような専門分野やゼミがあり、講師の専門に自分が専攻したい分野があるかを調べておくことです。
特に社会人入試の場合、大学側に「この人を指導したい、我が大学で学んでほしい」と思わせなくてはなりません。「ここでしか学べない理由がある」と熱意を持って語れる人ほど、合格する確率は高くなるはずです。
志望理由は、自分のそれまでの経歴と関連付けられるといいですね。ただしそれが必須というわけではありませんので、しっかりした動機や理由が語れれば問題ありません。
以上いろいろ書きましたが、社会人を経て大学で学び直しをしたいあなたは、強い意志をお持ちだと思います。ご自分のよりよい未来のために、がんばってください。
O.S講師のアドバイス
①「現在の自分」に合わせたスケジュールを立てる
「社会人だから」というわけではないですが、頭を使う体力や集中力は、基本的に20歳前後をピークにどんどん衰えていきます。学生の頃の体力やテンションを想定してスケジュールを立てると、思いのほかスケジュールどおりに進まない事態もありえると思います。スケジュールなどは、「現在の自分」に合わせて作成しましょう。
②頼れる存在やコミュニティを利用する
学習塾・予備校などの「同じタイミングで同じ目標を持っている仲間がいる場所」に物理的に所属していないと、モチベーションの管理が難しかったり、進捗の比較が他人としにくくて不安になったりということがあると思います。しかし、特にコロナ禍のある現在では、「物理的な所属」が難しいケースもあるでしょう。私の場合は大学受験ではなく公務員試験の受験でしたが、それでメンタルをやられていた時期があります。
そういう状態が苦手な人は、社会人の大学受験をサポートする学習塾などの頼れる存在を利用したり、ネット上でもよいので何かのコミュニティに所属したり、という工夫が必要かも知れません。
具体的な計画を立てる
社会人の大学受験で留意した方がよいポイントは、「具体的な計画を立てること」です。
社会人の生徒さんからよくお聞きするのは、「今週は仕事が忙しくて勉強ができなかった」という言葉です。もちろん、「しかたない話」ではあります。ただ、「勉強ができなかった」という事実が積み重なっていけばいくほど、学力が身につかないだけではなく、「勉強したという自信」からも離れていき、受験への不安も強くなりがちです。
忙しい社会人が学力や自信を身につけるため注目すべき点は、漠然とした「勉強した・しなかった」ではありません。「どこができるようになって、何を克服できたのか、何を覚えることができたのか」などだと思います。そのために、「具体的な計画」が必要なのです。具体的な計画があれば、計画がうまくいかなかったときのリカバーもしやすくなります。計画のクリアを積み重ねていけば、学力、達成感(自信)、そして合格につながります。
これは、「いまから実際に大学(受験)を目指すべきかどうか」を考える際の一助となるアドバイス・判断材料です。
「自分への投資」という観点で検討する
大学に通うには、お金も時間もかかります。そのため、大学を目指すか否かは「自分への投資」という観点で検討するのがよいと思います。
検討した結果、「いまではなく、仕事でもう数年経験を詰んだ後に受験しよう」「専門性がより高い学部を目指そう」「大学受験ではなく転職する方がキャリアアップにつながる」など、より合理的で自身で腹落ちできる道を選ぶことができると思います。
D.M講師のアドバイス
入学方法が一般入試以外でも、気にしなくて大丈夫
「大学受験をするからには、『いわゆる一般入試(=学力のみの試験)』で挑まなければ」「一般入試以外で合格したことを、引け目に感じる」と思う人がいます。
ですが、自分が利用する・した入試の方法が一般入試以外のものだとしても、気にしなくてよいです。なぜなら、大学ではさまざまな学生がおり、また学ぶ理由も同様にさまざまあるからです。
キズキ共育塾の講師たちが伝える、社会人ならではの大学受験で有利なポイント

この章では、キズキ共育塾の講師たちから、社会人ならではの大学受験で有利なポイントを紹介します。
金城龍介講師のアドバイス
私自身、大学卒業後は全く勉強しておりませんでしたが、40歳手前から学習を開始しました。その中で感じた、「社会人ならではの有利な点」は3つあります。
①目的を達成できる能力を活かせる
社会人は、仕事で結果を出さないといけない経験を積んでいます。その経験(能力)を受験に使えば有利に働きます。例えば、過去問を見たときにどうやってこの問題を攻略するかなどは、目的を達成する能力が高い方ががぜん有利です。
②時間をうまく使える
効率的に時間を使う能力も、仕事で求められるものです。これも勉強に活かせます。
③能動的である
社会人で大学受験する人は、能動的なはずです。能動的であるということは、勉強での成果にもつながる可能性が高いです。特に目的意識が強い場合は、短期間でかなり成績が伸びます。
以上3点の理由で、私は社会人は大学受験に有利だと考えます。
お仕事をはじめ、社会人生活で自然と得た能力は、優位に働くと思います。
例えば私の場合、社会人になってから、扱う情報の量・幅は学生の頃よりも大きくなりました。また、関わる人たちも増えました。そのため、仕事を通じて情報処理能力がかなり強化されたと思います。
近年は、共通テストをはじめ、科目によらず、「問題を理解するための高い読解力と情報処理」が求められる形式の問題が増えています。そのため、私のように仕事を通じて自然と情報処理能力が鍛えられた方は、受験においてかなり有利だと思います。
三島雪よ講師のアドバイス
人間の心理や組織の仕組みを理解している
これは、「大学受験での有利」ではなく、「大学に入学した後の有利」の話です。
社会人は、学生に比べて、社会(=人間の心理や組織の仕組み)についてよく理解しています。
そのため、先生や学校などに対する関わり方を工夫することができます。より具体的には、単位を取得し、学問を身につけ、卒業して次の職業やフィールドにつなげたりすることが、いわゆる「学生年齢」の人たちよりも上手にできる、ということです。
大学での学びを、より効率よく自分の中に取り込むことができるのです。(逆に、私自身が現役学生の頃は、「社会」についての理解があまりなかったために、授業への取り組み方や単位取得などがうまくいかないことがありました)
大学受験を目指す社会人のよくあるQ&A5選
最後に、大学受験を目指す社会人の方からよく聞かれる質問をまとめてみました。
代表的なもの5つをQ&A形式でご紹介します。
Q1.働きながら大学で学ぶことは可能でしょうか?

A:働きながら大学で学ぶことは、もちろん不可能ではありません。ただし、志望校の地理的な条件や修学形態も考えましょう。
例えば、「通信制大学・学部」や「夜間学部(二部学部)」は、仕事と並立して通いやすい大学です。
通信制大学・学部・コース
- 勉強は、大学から送られてくる教材による自宅学習がメイン
- キャンパス(大学)に通って講義を受けるのは、学校が設定した「スクーリング日」のみ
- 単位認定も、レポートを提出することで認定される場合が多い
- 仕事を辞めない方や、家の近くに自分の通いたい大学・学部がない方にオススメ
夜間学部(二部学部)
- 授業は、夕方から夜にかけて行われる
- 授業は、大学に通って受ける
- 大学生活と昼の仕事を並立したい方にオススメ
- 残念ながら、昔に比べると数は減っている
「大学に行って授業を受ける、昼の学部」については、時短勤務や勤務時間の変更などが可能かどうかを職場に相談・確認しましょう。
「働きながら大学で学ぶことは誰にでもできる(カンタンである)」とは言いません。
ですが、最初から「無理だ」と決めつけずに、大学やお勤め先のことを調査・相談しましょう。そうすることで、あなたに合った方法で、仕事と大学を両立する方法が見つかるはずです。
仕事と大学生活を両立させるためには、「最初から留年を視野に入れる」という方法もあります。
例えば、4年制大学を5年間(以上)で卒業するという計画を立てると、1年間あたりの授業数が少なくなるので、時間的には仕事との両立がしやすくなる、ということです。
ただし、お金と時間がかかるので積極的にはオススメしません。
Q2.子育てをしながらでも大学受験はできますか?
A:子育てをしながらであっても、大学受験に取り組み、大学生活を送ることは充分可能です。
ただし、お子さんの年齢や状況などによってさまざまな優先順位が変わります。ですので、勉強のスケジュールを柔軟に調整し、効率のいい勉強計画を立てることが特に重要になります。
そのため、周りの人の協力や学習塾などの専門的なサポートを得ることが大切です。
キズキ共育塾でも、子育てをしながら一般受験で大学受験に合格した方がいます。
その方の体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
Q3.社会人でも奨学金を借りられますか?

A:社会人が利用できる奨学金はたくさんあります。
例えば、日本学生支援機構(JASSO)の貸与型の奨学金は、社会人も利用可能です。
また、独自に奨学金制度を設けている大学もあります。
奨学金の応募資格などは大学ごとに異なりますので、志望校に問い合わせてみる価値はあるでしょう。
Q4.自分の年齢で大学受験を目指せるか気になります
A:大丈夫です。年齢を理由に大学受験をあきらめる必要はありません。
若いころに比べると、新しいことを覚える能力は弱くなっているかもしれません。
お伝えしたように、注意すべきポイントもあります。
ですが、ご紹介した成功例のように、社会人ならではの「強み」を活かして合格することは充分できます。
私たちキズキ共育塾の生徒さんにも、大学受験に成功した社会人が大勢いらっしゃいます。
Q5.自分がどの大学・学部・入試方法が自分に向いているのかわかりません

A:社会人の大学受験に詳しい学習塾などを利用しましょう。
一口に「社会人」と言っても、目的や状況は一人ひとり異なるため、一概に「どこがいい」と言うことはできません。
社会人の大学受験に詳しい学習塾などに相談すると、「あなたの状況」に合わせて、具体的な志望校が見つかると思います。
私たちキズキ共育塾でも、社会人の大学受験について、無料相談を行っています。
まとめ〜社会人からの大学受験は充分可能です〜

あなたが思う以上に、毎年、大勢の社会人が大学を受験していますし、合格・進学もしています。
そう聞くと、モチベーションが上がりませんか?
社会人入試制度を設けて、社会人の受け入れ態勢を整えている大学も少なくありません。
「大学受験なんて無理だ」と決めつける前に、まずは大学受験に詳しい人や、専門の学習塾などに相談してみましょう。
このコラムが、社会人からの大学受験を目指す人の助けになったなら幸いです。
最後に、幕末の思想家、吉田松陰の言葉を紹介します。
悔いるよりも今日直ちに決意して
仕事を始め技術をためすべきである
何も着手に年齢の早い晩い(おそい)は問題にならない
学ぶのに、夢に挑むのに、遅いということはない。
幕末の動乱期に生きた彼の言葉は、そんな真実を表していると思います。
私たちキズキ共育塾の生徒さんには社会人も多く、毎年、さまざまな大学に進学しています。
ご相談は無料ですので、少しでも気になるようでしたら、お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。
経験豊富な講師とスタッフが、あなた個人の事情に応じて、あなたの学びを具体的にサポートします。
Q&A よくある質問
社会人です。大学受験を成功させたいです。
社会人が大学受験を成功させるためのポイントとして、以下が考えられます。
- 社会人の大学受験に詳しい学習塾などを利用する
- 家族に相談する
- 職場に相談する
- 大学受験・進学の目的を明確化する
- 入試形式を決める
- 大学生活に必要な費用と卒業条件を調べる
- 大学進学の目的から入試科目を検討する
- 効率のよい勉強計画を立てる
詳細については、こちらで解説しています。
社会人ですが、大学受験に合格できる勉強方法を知りたいです。
社会人が大学受験を成功させるための勉強方法として、以下が考えられます。
- 基礎をしっかりと固める
- 小論文は、添削を求める
- テクニックや技法を取り入れる
- 試験問題よりも難易度の高い問題に取り組む
詳細については、こちらで解説しています。