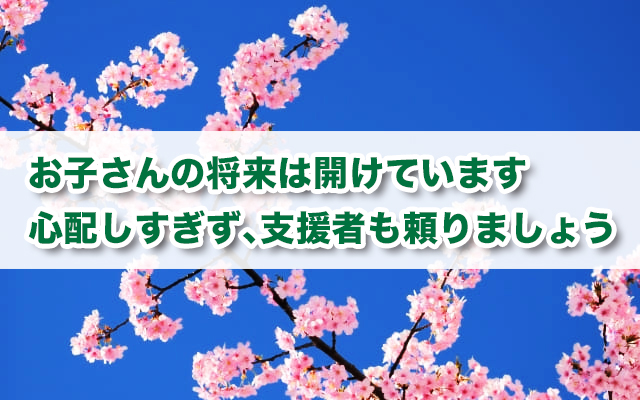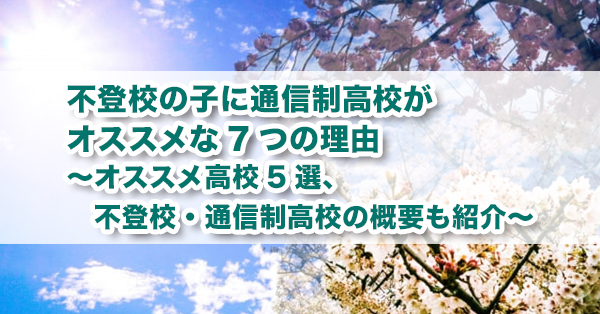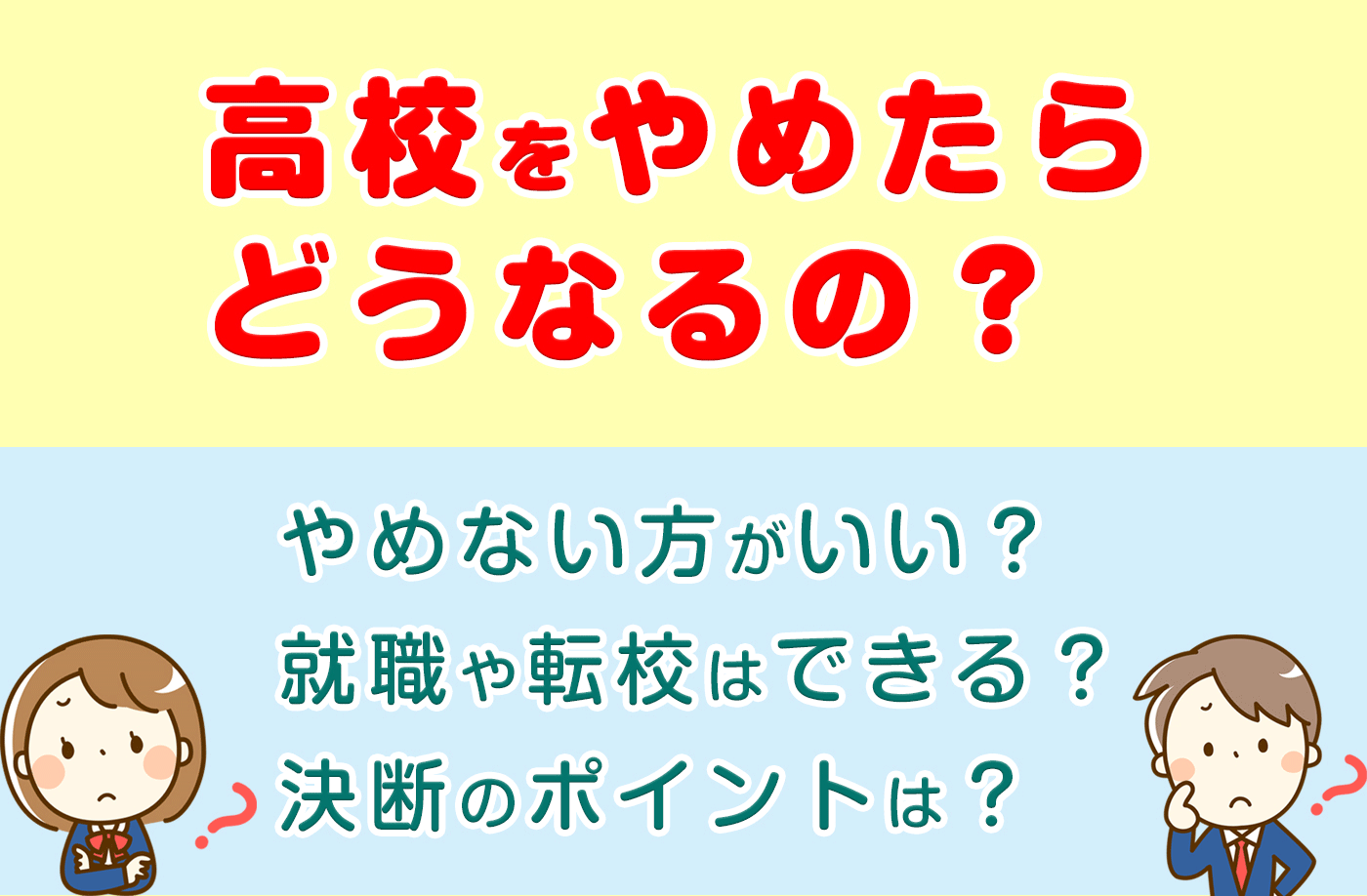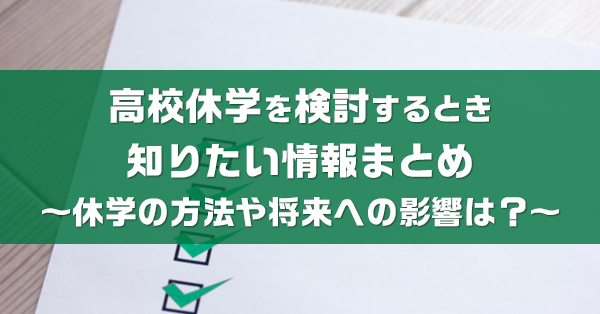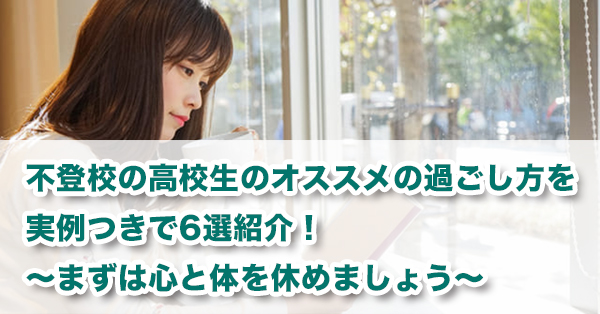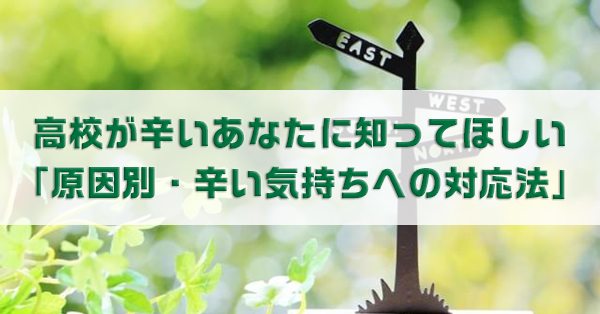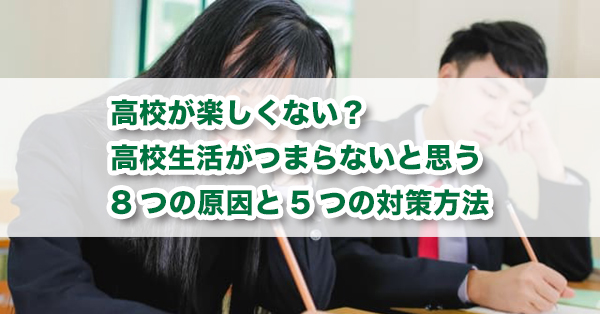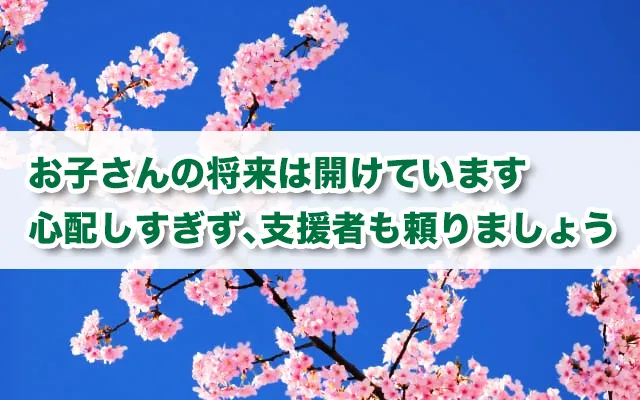進学校の高校生の不登校 進学校ならではの不登校の要因や親にできることを解説
私たちキズキ共育塾は、不登校期間の学習に関してお悩みの人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
最新データで見る、「高校生の不登校」の現状
進学校に限らず、不登校の児童・生徒は全国に存在します。
しかし、一口に「不登校」といっても、要因はさまざまです。個人的な状況から登校が難しい生徒さんのほか、家庭や学校に関する問題で学校へ通えない生徒さんもいます。
まずは不登校の定義や、高校生の不登校の現状を見てみましょう。
不登校の定義

文部科学省は、不登校の定義を以下のように定めています。
何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いた者
(参考:文部科学省「不登校の現状に関する認識」)
年間30日ということは、毎月2〜3日程度学校を休むと「不登校」の定義に当てはまることになります。長期的に学校へ行けないでいる子どもだけでなく、月に数日の頻度で休む生徒さんも不登校として数えられるのです。
「今日は学校へ行きたくないな」と思うことがあるのは、普通のことです。特に明確な原因がある場合は、それが解決されなければ、学校に行きたくない状態が長引くこともあるでしょう。
不登校は決して珍しいことではなく、誰にでも起こる可能性があると言えそうです。
不登校の高校生の割合は、約2.0%

それでは、高校生ではどのくらいの生徒さんが不登校の状態になっているのでしょうか。文部科学省の調査では、国立・公立・私立の総計で、約2.0%の生徒さんが不登校であることが明らかになりました。
(参考:文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」)学校ごとの割合では公立が約2.3%と、国立・私立と比べてやや多いです。
| 全体の生徒数 | 不登校の生徒数 | 不登校の生徒の割合 | |
|---|---|---|---|
| 国立 | 9622人 | 98人 | 約1.0% |
| 公立 | 194万1266人 | 4万4395人 | 約2.3% |
| 私立 | 101万2629人 | 1万6082人 | 約1.6% |
| 総計 | 296万3517人 | 6万575人 | 約2.0% |
とはいえ、いずれの学校でも、学年に1人か2人は不登校の生徒さんがいる計算です。
特に2022年度は、全国の小中学校で不登校の児童・生徒は10年連続増加し、小学生は10万5112人(約1.7%)、中学生は19万3936人(約6.0%)と、過去最大を記録したことも話題となりました。
不登校の児童・生徒数は増え続けています。
「高校生の不登校は約2.0%、約6万人」は、小中学校と比べると少ないと感じるかもしれません。しかし高校の場合は、小中学校と異なり、中退という選択肢があります。
中退した人は不登校には含まれません。不登校や長期欠席を経ずに中退する人もいるでしょう。
そのため、「高校に行きたくない」という悩みを持つ人、持っていた人は、上記の数・割合よりも多くなります。
不登校になった原因では「入学、転編入学、進級時の不適応」「学業の不振」も上位
高校生の不登校の要因の主たるものとしては、国公私の総計では「無気力・不安」などの「本人に係る状況」の総計は約55.9%と過半数を占めるものの、その後は「入学、転編入学、進級時の不適応」が約8.4%、「学業の不振」約5.6%と続きます。
学校の勉強についていけなくなることが、直接的・間接的に、不登校の要因となったケースも多いようです。「学校が係る状況」の合計は、不登校の主な要因全体の30%近くに上ります。
小学校・中学校の不登校の主な要因でも、「学業の不振」は約4.9%と大きな割合を占めました。同様に「本人に係る状況」が半数程度を占めるものの、その後は「いじめを除く友人関係をめぐる問題」が約9.2%、「親子の関わり方」が約7.4%と続きます。「学校が係る状況」の合計は、20%程度です。
また、高校生では6.4%程度だった「家庭に係る状況」の総計は、小・中学生では10%以上を占めました。
小・中学校の児童・生徒と比べると、高校生の不登校は、学校に係る要因が大きな影響を与えているようです。 (参考:文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」)
ただしこの調査は、文部科学省によるものです。民間の調査では異なる傾向が示されることもあります。
進学校の高校生ならではの不登校の要因

進学校には、さまざまな地域から学業が優秀な生徒さんが集まってきます。授業のレベルも高度です。中学校までは成績の良かった人でも、思うように成績が伸びないことがあります。
こうした進学校特有の環境が要因で、不登校になる人も少なくありません。
この章では、キズキ共育塾の知見に基づいて、進学校の高校生ならではの不登校の要因について見ていきます。
要因①勉強についていけない
高校では、在籍する生徒さんのレベルにあわせて授業が実施されます。進学校では偏差値の高い生徒さんが高く、ほかの高校と比べて難しい内容を学ぶのが一般的です。
中学までと同じように勉強しているだけでは授業についていけず、自信を失う生徒さんもいます。
進学校へ進むのは、中学までは優秀な成績を収めてきた生徒さんです。自分は勉強が得意であるという思いから、最初から目標を高く設定することもあるでしょう。
その結果、これまでとのギャップに悩むことになるのです。
本来、進学校へ進む生徒さんは、勉強が好き・得意なはずです。現時点の自分に合う目標を設定し、効率的な勉強ができれば、勉強も含めて、高校生活を楽しめるのではないでしょうか。
なかなか考えていたような結果が出ないときは、環境がこれまでと違うことを認識し、学習方法を見直してみましょう。
要因②課題やスケジュールがハード
進学校では、課題やテストの回数が多いこともあります。授業で学んだことを自宅で復習し、わからなかったところを確認しようと思っても、宿題をこなすだけで精一杯ということがあるのです。
こうしたハードなスケジュールをこなすため、私生活や睡眠の時間を削るようになると、精神的にも大きな負担となります。
高校生になると、勉学以外のスケジュール(部活やアルバイトなど)を増やしたいと思うこともあるでしょう。それなのに、勉強をこなすだけで時間がなくなり、ほかのことができなくなることがあるのです。
趣味や友人との集まりに参加できなくなると、人間関係でも悩みを抱えることになるかもしれません。また、進学校以外に進学した友人がいままでどおりに生活しているように見えると、強いストレスを感じることもあるでしょう。
さらに睡眠や食事の時間がおろそかになると、体調にも悪影響を及ぼします。心身のバランスが崩れることで集中力を失い、課題や勉強をこなすのがさらに難しくなるという悪循環に陥りかねません。
義務教育を終え、より大きな自由と責任を手にする高校生活は、さまざまな悩みや問題にぶつかる時期でもあります。
特に進学校では、ハードなスケジュールが心身に負担をかけやすい環境にあります。無理をしすぎず、できるだけリラックスできる環境を整えて、体と心を休めてあげましょう。
要因③同級生との比較
進学校には、学業が優秀な生徒さんが集まっています。クラスメイトは、中学校では上位の成績だった人ばかりです。簡単に成績上位者になれないのは、当然のことかもしれません。
しかしこれまで、「勉強で同級生に劣る」という経験がなかった人にとっては、初めての挫折となるかもしれません。
「一般論としては学力を着実に身につけている状態」なのに、「順位としての結果(=同級生と比較した結果)が悪い」ために落ち込むこともあるでしょう。
いままで勉強面で頼られたり、褒められたりしてきた人は、できないことを認めるのを恐れることもあります。同級生にも実際には苦手なことがあり、それぞれ悩んでいるものですが、まるで自分だけが落ちこぼれたような劣等感にさいなまれるのです。
また、責任感や向上心が強く、努力で困難を乗り越えてきたタイプの人は、人に頼るのが苦手なことがあります。授業でわからないことがあってもクラスメイトに尋ねることができず、孤立したように感じることもあるでしょう。
「自分だけができない」という思いが焦りにつながって無理をした結果、さらに勉強の効率を下げることにもなりかねません。
同級生に引け目を感じるようになると、学校に行くのがつらくなります。うまく友人関係を築くことも難しくなるでしょう。そうして、不登校の状態が長引くケースも珍しくありません。
同級生も、同じように悩んでいるかもしれません。機会があれば、友達に勉強の悩みを打ち明けてみましょう。
補足:不登校の「原因」にこだわらないことも大切

不登校には、明確な原因がなかったり、わからなかったりすることも多いものです。
また、わかりやすい原因に無理にあてはめたり、無理やり原因を突き止めようとしたりすると、状況の悪化を招くこともあるかもしれません。
不登校になった原因を周囲が無理に突き止めようとすると、本人はまるで取り調べを受けているように感じ、罪悪感や葛藤が増える可能性もあります。
不登校の原因を考えるときには、次のことに注意してください。
- 子どもにはそれぞれの性格や特性といった個性がある
- 原因もそれぞれなので、無理に決めつけない
また、不登校の原因を解明することが、直接「次の一歩」につながるとは限りません。原因がはっきりしているケースでも、その解決策はさまざまです。
例えば、「学校の授業についていけないことで不登校になった」場合を考えてみましょう。この場合は次のような状態になれば、「不登校が解決した」と言えそうです。
- 登校を再開する
- 学校の授業についていけるよう必死でがんばる
一方で、こうした直接的な解決ではなく、それぞれの子どもにあった解決策が必要なことがあります。たとえば、以下のような解決策が考えられます。
- 通信制高校に転校する
- 自分に合った塾で勉強する
不登校に限らず、子どもの不調に対する答えは、ひとつではありません。原因を追究することよりも、子どもの状況をよく見て、多角的に対応することが大切です。
子どもが不登校になったとき、親にできる5つのこと

子どもが不登校になったときは、「早く学校へ行かせなければ」と焦るかもしれません。
しかし、不登校は不調の始まりではありません。そうなるまでに、すでに子どもは悩み、苦しんでいます。限界を迎えて動けなくなった子どもは、まずはゆっくり休ませてあげることが大切です。
ここでは、子どもが不登校になったとき、親にできる5つのことを見ていきましょう。
対応①専門家に相談する
まずは、専門機関を利用するようにしましょう。
専門機関とは、「高校生の不登校」に関するケアや進路、勉強の情報を持っている場所のことです。具体的には、以下のような機関があります。
- 児童相談所、児童相談センター(18歳未満)
- ひきこもり地域支援センター
- 教育センター
- 子育て相談窓口
発達障害と思われる特性との関係が疑われるときには「発達障害支援センター」に相談するのもおすすめです。
また、民間にも、不登校の人を支援する団体や我々キズキ共育塾のような学習塾など、相談できる場所はたくさんあります。
こうした機関は、不登校の子どもの状態についての知識はもちろん、その後の進路や勉強方法についてのノウハウも蓄積しています。専門機関を頼ることで、子どものこれからについて具体的な方向性を知れることも大きなメリットです。
さらにカウンセラーや職員と話しをすることで、親御さん自身のストレス緩和にもつながります。
多くの場合、親は不登校の専門家ではありません。必要なときに必要な支援を受けられるよう、自治体のサポート体制や近くの専門機関について、事前に調べておきましょう。
対応②子どもが学校を休むことを受け入れる
「学校に行かなくてもいいよ」と、言葉にしてお子さんへ直接伝えることも大切です。
なかには「子どもは学校に行くものだ」という固定観念があって、なかなかそうはできない親御さんもいるでしょう。また、「学校に行かなければ、進路や勉強で、ほかの子と差が出る」と思うかもしれません。
しかし、無理に学校へ行かせても、子どもの学力は伸びません。彼らには、将来について考える余裕もないのです。
不登校になった子どもは、休む時間を必要としています。勉強や進路のことは、少しずつ、その子にあった形で考えていきましょう。親御さん自身の固定観念を一度見直してみるのも、きっとよい経験になると思います。
多くの場合、不登校の子どもは、学校へ行かなくてはならないという葛藤を抱えています。
親から見るとサボっているように見えても、苦しんでいるのです。焦りのあまり、親が登校を強要することは、子どもの心を傷つけます。親御さんは子どもを支え、安心できる場所を作るよう心掛けてあげてください。
「休んでいい」と言うと、子どもが「見捨てられた」と感じそうだと不安なときは、褒める言葉をかけてあげてください。「がんばったね」とこれまでのことを労われるだけで、子どもの心が休まることもあります。
子どもに寄り添い、いまの在り方を認めてあげることで、お子さんが再び立ち上がるための時間を与えてあげましょう。
対応③転校や塾の利用も検討する

不登校になった子どもは、勉強が嫌いになったわけではありません。進学校の勉強についていけないと感じるのは、勉強ができるようになりたいからです。
お子さんは再び自信を取り戻し、前向きに進路を考えたいと願っています。
また、不登校に悩むお子さんが、親御さんへの申し訳ないという気持ちから、「せっかく入学したのに、他の高校に行きたい(塾で勉強したい)なんて言えない」と思って本音を言えないという場合があります。
そうした状況にある子どもには、少しずつ勉強できる環境を整えてあげるのもよいでしょう。教室へ入ることに抵抗があるようなら、保健室や別室での登校が可能かどうか、学校と相談してみてください。
せっかく進学校へ通っていても、自分に合わない授業や環境では学力は身に付きません。
実際に授業を受けて、教育方針などが子どもとあわない場合には、転校することもひとつの方法です。また、塾や通信教育など、学びの環境そのものを変えることも効果的です。
「転校してもいいよ」「塾で勉強してもいいよ」と明言することで、お子さんは安心して「次の一歩」を探すことができるようになるかもしれません。
そのほか、趣味や遊びのように思えることも、子どもがやりたいと言い出したことは積極的に勧めてみましょう。そうした活動を通じて、自己肯定感を取り戻すこともあるからです。
学校だけが学びの場ではありません。学習のための場所や方法には、さまざまな種類があります。
専門家に相談しながら、子どもにとって最もよい環境を探してみましょう。
もちろん、「やりたいこと」を無制限に認めるというわけにはいきません。
その際は、お子さんの要望をどの程度認めるかについても、前に述べた「専門機関」などに相談してみましょう。そうすれば、より具体的な対応策が見えてくると思います。
対応④復帰を焦らず、子どもの「いま」を気遣う
子どもの不登校が長引くと、焦りを感じるのは普通のことです。「このまま学校へ行けなかったら…」などと不安になるときもあるでしょう。
しかし、一番悩んでいるのはお子さんです。本人も散々葛藤し、がんばった末に「不登校」を選んでいるのです。
学校へ行かなければと思えば思うほど、苦しみは強くなります。親御さんが心配する姿を目にして、さらに自分を責めてしまうかもしれません。
前述のように、再び学校へ通えるようになることだけが、不登校の解決ではありません。不登校の原因となった問題が解決しないままに登校を再開しても、再び精神的な負担を抱えることになるからです。
子どもの状態は、日々変化します。昨日までは大丈夫だと思っていても、朝になったらやはり登校できない、ということもよくあります。
大切なのは、そのときそのときに必要な支援について考え、将来のことを気にし過ぎないことです。
転校や塾の活用も選択肢にいれ、まずは子どもの「いま」を、豊かな時間にすることを目指しましょう。
対応⑤自分自身の生活も大切にする
高校生の子どもは、思春期を迎え、自立と依存の狭間で揺れています。親を頼りたい反面、自分一人でなんとかしたいと葛藤しています。
子どもが自立を目指して苦悩しているときは、親はそっと見守ることも大切なことです。
不登校になり、子どもが家にいる時間が増えると、親との接触時間も長くなります。心配のあまり、あれこれと手を出したくなるかもしれません。
しかし、子どもは自分の問題と向き合う時間を必要としています。親は子どもから離れ、自分自身の時間を大切にすることで、大人としての生き方を子どもに示しましょう。
人生のロールモデルとなりうる大人が身近にいることは、子どもにとってもよいことです。学校に通わず、人と違う生活を送る子どもは、自分がなにをすればよいのかわからず、無力感に襲われることがあります。
そうしたとき、生き生きと自分の人生を楽しんでいる親の姿は、ひとつの指針となるはずです。
親と子どもの適切な距離感は、親子の関係性によっても違います。
どの程度子どもと接すればよいのかわからないときは、専門家に相談しましょう。
不登校の高校生には通信制高校が向いている?

不登校の高校生が転校を考えたとき、「通信制高校が向いている」と言われることもあるかもしれません。
すべてのケースであてはまるわけではありませんが、一般的に、通信制の高校は不登校の子どもに適した特徴を持っているのは事実です。
次は、不登校の子どもが通信制の高校を選ぶメリットについて、考えてみましょう。
通信制高校とは?
通信制高校とは、学校から配布される教科書や動画などの教材を用いて行う、自宅学習がメインの高校です。
通信制高校の主な特徴は、以下の通りです。
- 「レポートの提出」「スクーリング(対面での授業)」「試験」などで単位を修得する
- 全日制高校に比べて、他の高校から転入・編入してきた人が多い
- 卒業すれば学歴は「高校卒業」になる
2020年の調査では、通信制過程に在籍する生徒のうち、学校が所在する都道府県と、隣接する一つの都道府県の2地域に在住する人が入学できる高校である狭域通信制高校では約48.9%、3つ以上の都道府県から入学できる高校である広域通信制高校では約66.7%の生徒さんが「小・中学校及び前籍校における不登校経験がある」と回答しています。
また、通信制課程の年度途中入学者数は、全体として増加傾向にあることも指摘されました。(参考:文部科学省「高等学校通信教育の現状について」)
同じ境遇にある生徒が多いことも、不登校の子どもが通信制高校を選択しやすい理由のひとつかもしれません。
不登校の高校生が通信制高校を選択するメリット
不登校の高校生が通信制高校に向いていると考えられる理由には、以下の3つが考えられます。
- 自分のペースで勉強できる
- 履修コースを柔軟に変えられる
- 人間関係に悩む機会が減る
通信制高校では、自宅学習がメインです。自分にあったペースで学習できるので、規則正しい生活が送れないお子さんでも、勉強を続けることができます。
また登校の回数も少ないので、日常的にたくさんの人と接する必要もありません。
さらに、私立の学校ではスクーリングの回数も変更できるなど、履修コースを柔軟に変えられます。
人間関係をあまり気にせずに済むことも、通信制高校へ通うメリットです。
不登校を経て、大学生になったキズキ共育塾の生徒さんたちの体験談3選

キズキ共育塾では、たくさんの不登校の生徒さんを支援しています。
この章では、不登校を経て大学生になった生徒さんの体験談を紹介します。
体験談①不登校になり、高校を退学。高卒認定試験を経て、立教大学へ
成田さんは、高2の夏に高校に行けなくなりました。進学校の生徒だった彼は、大量の課題に苦労しながらも、「普通の高校生活を送っていた」と言います。
成田さんが不登校になったことに、明確な理由はありませんでした。ただ高校に行っている理由がよくわからなくなり、考える時間が必要になったそうです。
学校へ行かない期間は昼夜逆転の生活になり、ゲームをしたりアニメをしたりして過ごす時間も多くなりました。
罪悪感はありながらも、考える以外にやることがなく、親も心配していました。不登校が長引き、登校を再開できなくなった成田さんは、そのまま高校を中退しました。
一方で、大学へは行きたいと思っていました。高校を退学した時点で高卒認定試験の受験を検討していた成田さんは、インターネットでキズキ共育塾を見つけます。
高校在籍時に取得した単位によって、いくつかの受験科目は免除されました。キズキ共育塾やネットの動画を通じて学ぶうち、勉強のおもしろさを実感した成田さんは、高卒認定試験に合格。その後も勉強を続け、立教大学文学部に入学しました。
大学生活では、哲学をとおして、将来のことを考えていくそうです。
成田さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
体験談②1年間の不登校から再出発! 一人ひとりに寄り添う授業で実力が身についた〜国士舘大学合格〜
小・中学校の富田さんはとてもまじめで、成績も常に上位でした。しかし高校に進学すると、「まじめな生徒」でいることに難しさを感じるようになります。
学校の雰囲気があわなかった富田さんは、次第にクラスでの居場所をなくしていきました。成績もどんどん下がります。
不登校になった後は、体がだるいと感じる日が続きました。寝て過ごすことが多くなりましたが、勉強の必要性は感じていました。
転校し、受験対策として通塾も始めましたが、やはり通い続けるのが難しくなっていきます。そんなときに出会ったのが、キズキ共育塾でした。
面談で「ここならやっていけそうだ」と感じた富田さんは、キズキ共育塾へ入塾します。不登校になってからは家族以外と話す機会もなかなかありませんでしたが、キズキ共育塾では先生といろいろな話をし、打ち解けることができました。
キズキ共育塾で自分のペースにあわせた学習を続け、富田さんは国士舘大学法学部へ進学しました。
富田さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
体験談③「自分のやりたいこと」を探すため、大学受験を決意〜日本大学合格〜
進藤さんは、小学校5年生のころから、学校に行ったり行かなかったりするようになりました。中学校まではなんとか卒業し、高校に進学したものの、次第に通えなくなり、中退します。
そのまま生活リズムを崩した進藤さんは、何をしたらいいのかもわからず、時間だけが過ぎる日々を送っていました。
「このままではいけない」と悩んだ結果、進藤さんは、大学に入って自分のやりたいことを見つけてみようと決心します。キズキ共育塾に入塾したのは、そんなときでした。
キズキ共育塾では、自身にも高校中退の経験のある先生が担当になりました。独学で高卒認定資格を取得後、大学に進学した先生の存在は、進藤さんの支えになったそうです。
気分の浮き沈みが激しく、授業を休んでしまうこともありましたが、キズキ共育塾ではいつでも受け入れてくれる雰囲気がありました。そんな塾だからこそ、進藤さんも辞めることなく通い続けることができました。
高卒認定資格を取得した後も引き続きキズキ共育塾に通い、進藤さんは日本大学芸術学部に進学しました。入学後はライティング講座や演劇学科の授業なども受けたいと思っているそうです。
進藤さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校ジャーナリスト・石井しこう、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。
このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。
このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。
公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら
- 【オリジナル書籍プレゼント】学校外で友だちができるBranchコミュニティ(Branch公式LINEが開きます)
私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。
まとめ~「学校に行かないこと」が、ポジティブな結果を生むこともある~

進学校には、ほかの高校と比べて特有の厳しさや困難さが存在します。
勉強が難しいというだけではなく、環境の変化や同級生との関係性が、思春期の子どもの心に大きな影響を及ぼすのです。
学校へ行くのがつらくなった時には、休むことも必要です。親御さんは子どもの変化を受け止め、安心できる居場所を作ってあげましょう。そして一緒に、これからのことを考えてあげてください。
家庭では解決できそうもないときには、専門家のサポートを受けることも重要です。
キズキ共育塾では、不登校をはじめ、悩みを抱えるお子さんに寄り添います。
勉強の不安はもちろん、生活のことや進路についてもご相談ください。お力になれると思います。
無理せず、自分のペースで、ゆっくりと新しい日常を作り上げていきましょう。
Q&A よくある質問