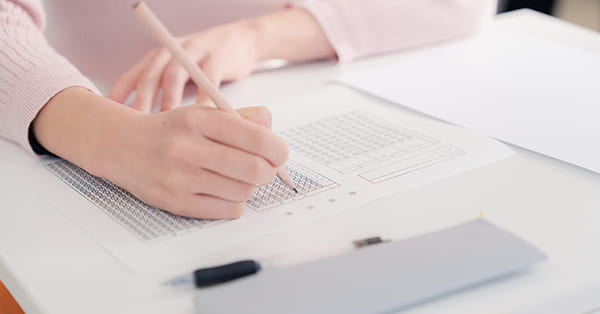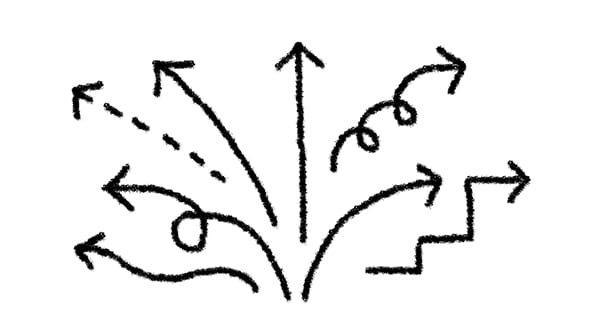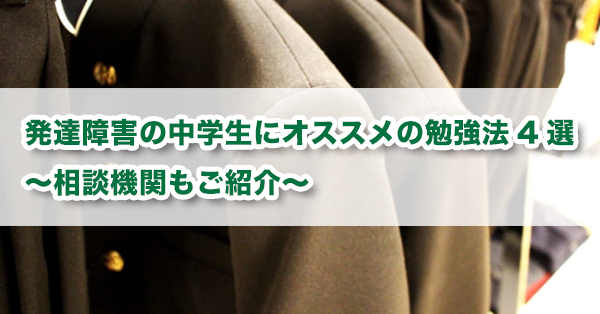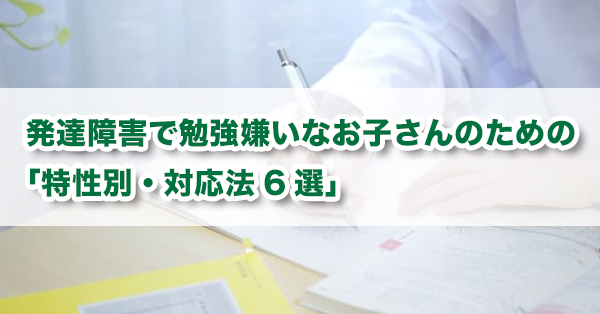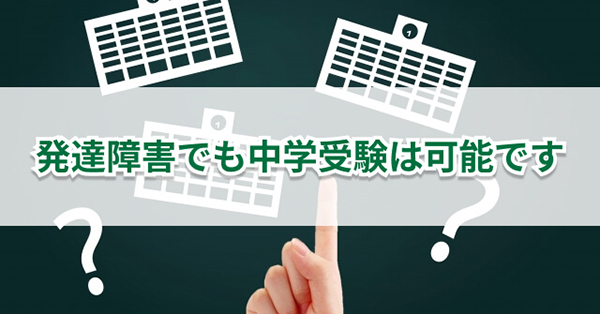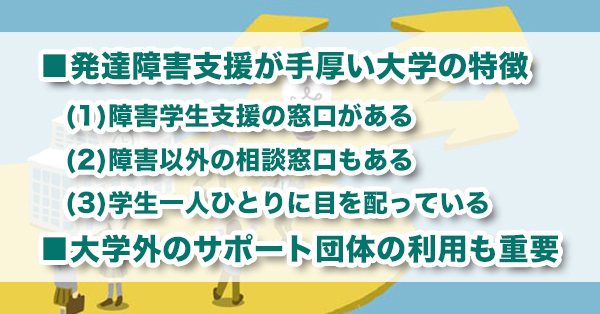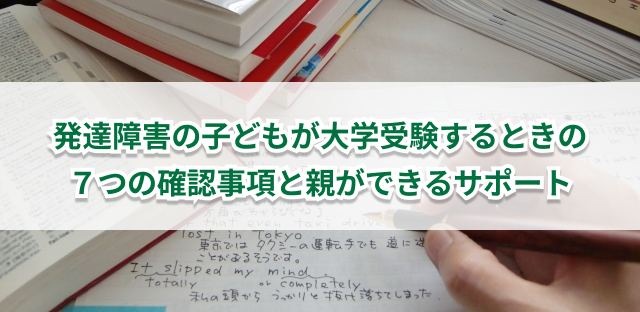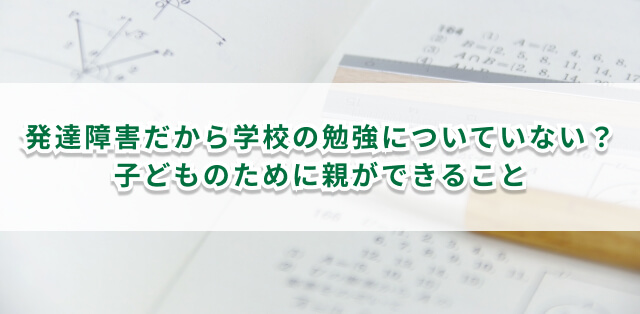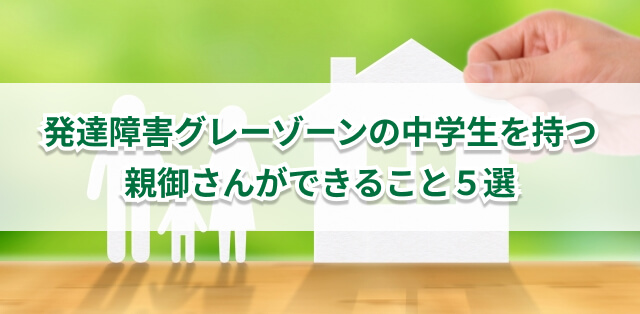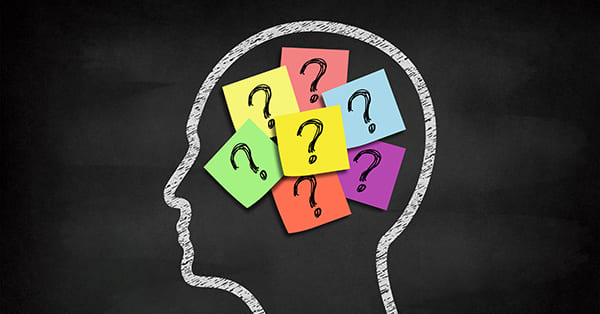発達障害のある人の進路 小学校・中学校・高校別に進路選択のポイントを解説
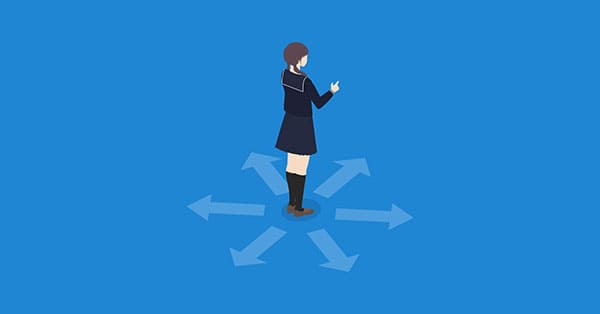
こんにちは。発達障害や不登校・中退などのお子さんを勉強・メンタルの両面から完全個別指導で応援するキズキ共育塾です。
ご自身の発達障害について悩んでいるあなたや、お子さんの発達障害について悩んでいる親御さんは、今後の進路がどうなるのか不安も大きいと思います。
成長するにつれて進学か就職かという選択もしていかなければなりません。
最適な選択ができるよう情報収集しておきたいとお考えのことが多いでしょう。
このコラムでは、発達障害のあるあなたやお子さんが進むことができる進路について解説します。
このコラムをお読みいただくことで、発達障害のあるあなたやお子さんが歩んでいくであろう将来のことが、きっとイメージしやすくなるはずです。(参考:鈴木慶太『親子で理解する発達障害 進学・就労準備の進め方』)
私たちキズキ共育塾は、進路に悩む発達障害のある人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
発達障害のある人の進路選択のポイント6点
この章では、発達障害のあるあなたやお子さんが進路選択のときに気をつけたいポイントを解説します。
前提として大切なのは、発達障害のあるあなたや親御さんだけで抱え込まず、周囲の人を適切に頼ることです。
ポイント①在籍している学校に相談する

1点目は、まず身近なところで、在籍している学校に相談することです。
あなたやお子さんの学校生活や勉強の興味といった進路選択に関わる情報だけでなく、支援機関や支援制度に関する情報も得られるはずです。
ポイント②医師や支援機関に相談する
2点目は「医師や支援機関に相談する」です。
医師や支援機関に相談することで、適切なアドバイスが受けられるでしょう。
発達障害のあるあなたやお子さんの進路に関する支援機関は、以下が挙げられます。
- 専門医や臨床心理士などの専門家
- 発達障害支援センター
- 発達障害のある人向けの塾
- 障害者就業・生活支援センター
あなたやお子さんの進路で悩んだ場合は、1人で抱え込まず専門家に相談することが大切です。
それぞれの支援機関の詳細については、こちらで解説しています。
ポイント③特性を考慮して進路を選ぶ
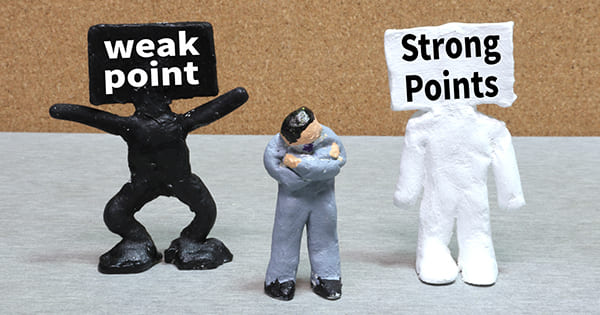
3点目は、特性を考慮して進路を選ぶです。
発達障害のあるあなたやお子さんは、得意・不得意や向き・不向きが比較的はっきり出やすいと言われています。
たとえば、ASDの特性に関連して、特定分野への強いこだわりがある場合には、専門性を磨いたり、専門職に就いたりすることで、強みをいっそう伸ばすことができるかもしれません。
特性に合った進路を選ぶことは、あなたやお子さんのストレスを軽減するだけでなく、自己肯定感を養うことにもつながります。
何ができて・何ができない・やりづらいか、何をするのが好きで・何が苦手か、といった特性を理解し、進路選びに活かしましょう。
ポイント④準備は早めに進める
4点目は、準備は早めに進めることです。
発達障害のあるあなたやお子さんが受けられる支援制度を調べたり、申請に必要な書類などを準備したりするのには、ある程度のまとまった時間が必要です。情報収集や申請の手続きなどは、余裕をもって準備を進めましょう。
こちらで解説する高校入試の特例申請のように、受験の願書提出よりも前に申請が必要となることもあります。
周囲と同じスケジュール感で動いていると、支援を得られにくい場合があるのです。
ただし、今後「〇〇の申請締め切りを過ぎていた!」なんてことが発覚しても慌てないでください。まずは落ち着いて代替手段はないかなどを詳しい人や支援機関に相談するようにしましょう。
実際に進学や就職が決まった場合においても、早めに受け入れ先と相談・調整しておくとよいでしょう。
その方が発達障害のあるあなたやお子さんが馴染みやすく、先方も慌てることなく修学や就労がスムーズに進みます。
ポイント⑤自分自身・お子さんの意思を尊重する

5点目は、自分自身・お子さん本人の意思を尊重することです。
進路を決めるときには、自分自身・お子さん本人の意思を尊重するようにしましょう。
発達障害は、脳の機能の偏りというあなたやお子さん自身ではどうしようもない部分が原因です。
合わない環境による困難・苦労などについても、努力ですべてをカバーすることは難しいでしょう。
発達障害の苦労は本人の努力で全てカバーできるはずと、合わない環境で無理や我慢が続くと、意欲の減退や精神的なストレスに繋がることがあります。
さらには、うつ病や適応障害といった二次障害・精神疾患につながる可能性もあります。
もちろん、発達障害に由来する苦労は、ある程度は工夫でカバーできますし、支援する人たちもたくさんいます。
とはいえ、大きな無理や負担にならないようなちょうど良い環境を見つけ出すことが何よりも大切です。
そのときにカギとなるのは、あなたやお子さんの合っていそうだなという感覚です。
ここなら続けられそうというあなたやお子さんの意思を尊重することで、より良い環境が見つけやすくなるのです。
親として発達障害の子どもの進路を決めてあげなくてはと、親御さんだけで追い込むことがないようにしましょう。
ポイント⑥各進路の特徴を理解して判断する
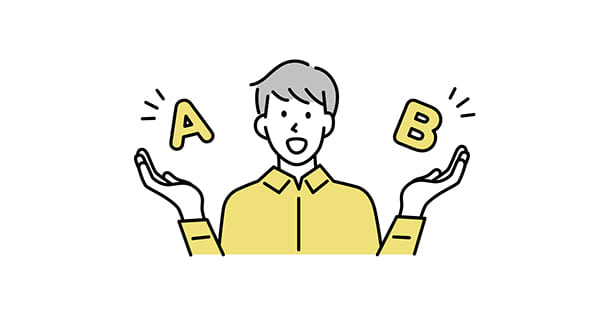
最後のポイントは、各進路の特徴を理解して判断することです。
例えば、高校へ進学することに決めたとします。
全日制高校と通信制高校では、通学と自宅学習のどちらを基本にするかといった大きな違いがあります。
全日制高校ではクラスメイトとの交流が多いため、人と接することが好きな人には向いているかもしれません。
しかし、ASDのように、コミュニケーションにおいて特性が目立ちやすい場合には、通信制の方が勉強しやすいといったケースも考えられます。
このように、各進路の特徴を理解した上で、あなたやお子さんの特性と照らし合わせて判断することが大切です。
小学校・中学校編:発達障害のある人の3つの進路

この章では、発達障害のあるあなたやお子さんの小学校、中学校での進路について解説します。
ここでも、学校の先生やスクールカウンセラー、医師や支援機関などに都度相談することを忘れないようにしてください。
特に、小学校や中学校の時期は、子どもの発達や変化が著しいです。
親御さんはこの時期に、お子さんの悩みが深刻になっていないか、細やかに気を配ったり、さりげなく相談に乗ったり、進路を一緒に考えたりすることが特に大切です。
ただ、卒業するまで同じ学級・学校に通わなければならないというわけではありません。
学校の先生やスクールカウンセラー、医師や支援機関などと相談しながら、状況に応じて環境を変えることもできます。
これらの点に注意しながら、進路の候補を確認していきましょう。(参考:文部科学省『?特別支援教育』、文部科学省『特別支援学級及び通級指導に関する規定』)
| 進路 | 特徴 |
|---|---|
| 通常学級 | 大人数でクラスが編成される、 スタンダードな学級 |
| 特別支援学級 | 障害のある子ひとりひとりに応じて 適切な教育を行うために編成された、 少人数(上限定員8人)の学級 |
| 特別支援学校 | 幼稚部・小学部・中学部・高等部があり、 心身に障害のある児童・生徒専門に 教育指導を行っている学校 |
進路①通常学級

1つ目は、通常学級です。
通常学級とは、基本的には教師1名に対して、生徒40名(小1は35名)などの大人数でクラスが編成される学級のことです。
通常学級のメリットは、発達障害のない人と一緒に学べることです。
一方で、場合によってはクラスメイトとうまくコミュニケーションを取れなかったり、勉強についていくのが困難になったりするケースも見られます。
ただしこれは、必ず発生するわけではなく、可能性として考えられるデメリット・注意点に過ぎません。
何らかの困難が生じたときは、学校の先生やスクールカウンセラー、医師や支援機関などと相談の上で合理的配慮を受けられる可能性があります。
合理的配慮とは、障害のある人と障害のない人との均等な機会を確保すること、また障害のある人に困難があったときに改善するための措置を取ることを指します。
例えば、LD/SLDのある人であれば、特別にタブレットのような電子端末の使用許可を得るといったことが、この合理的配慮にあたります。
また勉強とは別に、障害に応じた特別指導を受けられる通級指導教室(通称:通級)を組み合わせることで、大きな困難を感じることなく進級・卒業できる場合もあるでしょう。
通級指導教室は、障害のある本人が通常の授業のほかに一部の授業を別の教室で受ける制度です。
サポートを受ける場合は、学校の先生やスクールカウンセラーとの相談が基本になります。
あなたやお子さんが発達障害に伴う悩みを抱えているときは、まずは相談してみましょう。
進路②特別支援学級

2つ目は、特別支援学級です。
特別支援学級とは、障害のある子どもそれぞれに応じて、適切な教育を行うために、上限定員8人の少人数でクラスが編成される学級のことです。
指導は学校の先生やスクールカウンセラーと保護者が一緒に作成した個別の指導計画・教育支援計画に基づいて行われます。
大きなメリットは、あなたやお子さんの障害に合わせた指導を受けられる点です。
学校の先生やスクールカウンセラー、保護者、支援機関を中継したり、相談もできたりする特別支援教育コーディネーターが配置されており、安心感が高い点も特徴です。
基本的に、学校に設置された特別支援学級内で指導を受けます。その上で、給食や体育、音楽の時間は通常学級で行動するなど、子どもの状況によって柔軟な対応が取られています。
ちなみに、特別支援学級を設置していない学校もあります。
進学の際には、あらかじめ確認するようにしましょう。
進路③特別支援学校

3つ目は、特別支援学校です。
特別支援学校とは、心身に障害のある子どもに対し、障害の特性に配慮しながら自立に必要な教育指導を行っている学校のことです。
幼稚部、小学部、中学部、高等部があり、それぞれ幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた教育を行っています。
こちらで解説した特別支援学級と同様に、発達障害以外にも、知的障害や視聴覚障害など、様々な障害のある子どもが在籍しています。
それぞれが、個別の指導計画・教育支援計画に基づく指導を受けています。
特別支援学校は、1クラス平均3人で構成される少人数教育が基本です。
学校の先生は通常の教員免許に加えて、特別支援学校の教員免許を持っており、障害への知識・理解が深い点も特徴です。
その他のメリットとして、教科書についての配慮があり、視覚や聴覚に障害のある子どもや、計算能力に困難を抱える子ども向けに作成された教科書を使用しているため、LD/SLDのある子どもでも勉強しやすいという点もあります。
また、ほかの学校の行事に参加したり、地域の人とイベントやボランティア活動を通じて交流したりといった機会もあります。
なお、入学条件は学校によって異なり、障害者手帳が必須ではない学校もあります。
特別支援学校を検討される際は、自治体の教育委員会に問い合わせる、地域の特別支援学校のホームページから問い合わせるなどして、早めに準備を進めましょう。
中学校卒業編:発達障害のある人の8つの進路

この章では、発達障害のあるあなたやお子さんの中学校卒業以降での進路について解説します。
中学校卒業以降は、進路の選択肢が広がります。
進路選択の際は、それぞれの学校の特徴を理解した上で判断することが大切です。
また、受験の際には、こちらで解説する高校の特例申請のように特別措置を受けられる場合もあります。
進学の手続きは、学校の先生やスクールカウンセラー、医師や支援機関などと相談しながら早めに準備を進めることが大切です。
| 進路 | 特徴 |
|---|---|
| 全日制高校 | 平日の朝から夕方に授業を行う、 通常修了年限が3年間の一般的な高校 |
| 定時制高校 | 昼、または夕方からの時間帯などで 授業を受ける高校 |
| 通信制高校 | 自宅学習がメインの高校。 レポート提出やスクーリングなどで 卒業単位を修得する |
| 高等専修学校・ 高等専門学校 | 職業に直結した専門的な知識や 技能を学べる学校 |
| 特別支援学校・高等部 | 個別の指導計画に基づき、 障害に合わせて通常の高等学校相当の 教育を実施 |
| 高等特別支援学校 | 特別支援学校の小学部・中学部などがなく 高等部のみを単独で設けている学校 |
| チャレンジスクール、 クリエイティブスクールなど | 発達障害や知的障害、 不登校になった生徒などに支援教育を行っている、 都道府県独自の学校 |
| 高卒認定試験 | 高校を卒業した人と 同等以上の学力があるかどうかを 認定するための試験 |
| 進学せずに就職する | 中学卒業後にすぐに就職せずに、 障害者職業能力開発校などで 職業訓練を受ける道もある |
| 起業やフリーランスになる | 起業やフリーランスを目指すなら 高いスキルや知識が必要 WEBライター・WEBデザイナー・ プログラマー・システムエンジニアなど |
進路①全日制高校

1つ目は、全日制高校です。
全日制高校とは、高校と聞いて一般的にイメージされる、平日の朝から夕方に授業を行う、通常修了年限が3年間の課程の高校です。
全日制高校では、発達障害のない人と一緒に学んだりと同じ経験をすることができる点がメリットです。
一方で、進級や卒業に必要な出席して授業を受ける、定期考査で合格点や赤点以上の点を取ることが負担になることもあります。
全日制高校は、発達障害の程度が軽い場合には、多少の苦労があることや工夫が必要なことは否定しませんが、進路として有力な選択肢になり得ます。
その上、小学校、中学校同様に発達障害の特性に対して、電子端末の使用などの合理的配慮を受けられる可能性もあります。
発達障害の程度が軽くない場合でも、最初から入学や通学、卒業は無理だと決めつけずに、支援体制について学校に確認・相談してみましょう。
合わせて、校風や体制、進路指導といった基本事項の確認も忘れずにしてください。
進路②定時制高校

2つ目は、定時制高校です。
定時制高校とは、全日制高校と異なり、昼、または夕方からの時間帯などで授業を受ける高校のことです。
定時制高校の授業のコマ数は1日4コマが目安です。全日制高校よりも自由な時間が多く、調子を見ながら通いやすい特徴があります。
その代わり、高校によっては卒業にかかる年数が4年になるところもあります。
発達障害があるかどうかにかかわらず、高校中退者や学び直しの方など、様々な背景のある人が在籍しており、年齢を越えた幅広い交流を持つことが可能です。
そのため、全日制高校の同質性・均質性に息苦しさを感じやすいという子は、定時制高校を候補に入れるのもよいかもしれません。
なお、定時制高校では、こちらで解説する通信制高校と同様に、技能連携校へ並行して通うことができます。
技能連携校とは、就職に役立つような技能教育を行う高等専修学校のことで、条件次第ではそこで学んだ単位を高校の卒業単位に充てることができます。
定時制高校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
進路③通信制高校

3つ目は、通信制高校です。
通信制高校とは、学校から送られてくる教科書や動画といった教材を使う、自宅学習がメインの高校です。基本的に授業への出席ではなく、レポート提出やスクーリングなどで卒業単位を修得していきます。
学校に行く必要があるのは、基本的にスクーリングと呼ばれる特定の日のみです。
毎日ではないので対人関係の負担がかなり軽減されます。
通信制高校は、学校が決めた時間割で授業を受けるのではなく、受ける授業を自分で決められる単位制の高校であり、学年の概念がないことが多いです。
好きな時間に一人ひとりのペースで勉強を進めていくことができます。ただし、3年間で卒業したい場合は、3年間のうちに卒業までに必要な科目を全て学び終える必要があります。
全日制高校の授業のペースに不安がある場合にオススメです。また、登校日数が少ないので、人とのコミュニケーションが苦手な人にもオススメです。学校によっては、登校日数を多く設定することも可能です。
全日制高校、定時制高校と同様に、卒業すれば高卒となり大学受験できる点もメリットです。
日常的に登校するのは困難でも、学校行事を楽しみたい、集団行動を通じて社会性を養いたいという場合は、文化祭やスポーツ大会などを多く催している通信制高校を選択することもできます。
また、あなたやお子さんだけでは通信制高校での勉強が難しい場合は、発達障害のある子どもの指導実績がある塾で補うという方法もあります。
通信制高校と連携するサポート校という制度もありますので、合わせて検討してみるとよいでしょう。
通信制高校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
進路④高等専修学校・高等専門学校

4つ目は、高等専修学校、高等専門学校(高専)です。
高等専修学校と高等専門学校(高専)の2つは、いずれも職業に直結した専門的な知識や技能を学べる学校です。(参考:文部科学省『中学卒業後のもう一つの進路 高等専修学校』、 全国高等専修学校協会『高等専修学校とは?』)
高等専修学校のポイントは、職業もしくは実生活において必要な知識・技能を習得できる専修学校の一課程であるという点です。
工業/農業/医療/衛生/教育・社会福祉/商業実務/服飾・家政/文化・教養の8つの専門分野を学ぶことができます。
修業年数3年以上かつ特定の条件を満たす課程を修了すると、大学受験資格が得られる点もメリットと言えるでしょう。全ての高等専修学校と高等専門学校ではないため、注意が必要です。
加えて、発達障害のある人が全体の約9%在籍しており、発達障害へのサポート体制を整えた学校も多いという特徴もあります。
ただし、高等専修学校卒業は、学歴上の高卒とは少し異なるため、注意が必要です。
高等専門学校のポイントは、技術者になるために、いわゆる五教科などの一般科目と、工学・技術・商船などの専門科目の両方を学べる点です。
高等専門学校は、より高度な技術者・専門職を目指すための学校なので、難易度が高いという特徴があります。
いずれの学校も、自分の特性や傾向を専門職への就労に結び付けたい人などに向いているかもしれません。
大学や専門学校からも当然ながら各関連分野に就職する道があります。
あなたやお子さんが興味がありそうなら、具体的に向いていそうか、発達障害に関する支援体制はあるかなどを、学校に個別で確認するようにしましょう。
進路⑤特別支援学校・高等部

5つ目は、特別支援学校・高等部です。
特別支援学校・高等部では、個別の指導計画に基づき、障害に合わせて通常の高等学校相当の教育を施しています。
幼稚部から中等部までとの違いは、就労を目指した職業教育にも力を入れている点です。
具体的には、以下のような職業訓練が行われています。
- 企業への職業実習
- 農作業
- 工芸品の製作体験など
特別支援学校・高等部のポイントは、卒業した際の学歴が高卒ではなく、特別支援学校高等部卒になる点です。
卒業すれば、大学受験の資格を得ることができます。ただし、就職の場面では、特別支援学校高等部卒では高卒の求人に応募できない可能性があります。対応は企業や役所などによって異なるため、確認が必要です。
特別支援学校・高等部の卒業が高卒にならない理由は、学校教育法において、高等学校と特別支援学校が別々に定義されているためです。
法律上は異なる種類の学校として扱われているので、高卒にはならないということです。(参考:「文部科学省「学校教育法(昭和二十二年三月二十九日法律第二十六号)」)
高卒という学歴を得たい人は、こちらで解説した通信制高校などに通う必要がある点には注意が必要です。
進路⑥高等特別支援学校

6つ目は、高等特別支援学校です。
高等特別支援学校とは、特別支援学校の小学部、中学部などがなく高等部のみを単独で設けている学校のことです。
障害のある人の中でも、一般企業への就職ができる可能性が高い人に対して、就労に向けた教育に力を入れています。
特別高等支援学校は、職業訓練を念頭に置いたカリキュラムになっているため、卒業後に大学へ進学して勉強したいという人を想定していません。
そのため、こちらで解説した特別支援学校・高等部と同様に、学歴上は特別支援学校高等部卒というかたちで、就職の場面では高卒とは区別される点には注意が必要です。大学受験資格は得られます。
進路⑦チャレンジスクールなど

7つ目は、チャレンジスクールなどです。
チャレンジスクールとは、小学校・中学校時代に不登校の経験のある人、長期欠席などが原因で高校を中途退学した人などを主に受け入れる東京都立高校のことです。
ほかの地域でも似たような趣旨の学校があり、それぞれ独自のネーミングがついています。
チャレンジスクールは、総合学科の定時制・単位制高校です。 自分のライフスタイルや学習ペースに合わせて、午前部・午後部・夜間部の三部の中から選んで入学できます。
幅広い選択可能科目を設置したり、カウンセリング体制を充実させたりと、様々な事情を抱えた人のニーズにあわせた新しい試みを行っています。
チャレンジスクールと似たような学校は、東京都以外にも存在します。ほかの道府県でも似たような趣旨の学校が設けられている場合があります。
- パレットスクール(埼玉県)
- クリエイティブスクール(神奈川県)
- フレキシブルスクール(神奈川県)
- フロンティアスクール(神奈川県)
- インクルーシブ教育実践推進校(神奈川県)
- エンパワメントスクール(大阪府)
チャレンジスクールなどについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
進路⑧高卒認定試験

8つ目は高卒認定試験です。
高卒認定試験(正式名称:高等学校卒業程度認定試験)は、高校を卒業した人と同等以上の学力があるかどうかを認定するための試験です。文部科学省が実施しており、高認とも呼ばれています。(参考:文部科学省「高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)」)
高校中退で最終学歴が中学卒業になった人や、何らかの事情で高校進学を断念して社会に出た人などが、改めて大学に進学したいなどと思ったときに利用できる試験です。
合格者には、大学・短大・専門学校の受験資格が与えられるほか、一部の国家資格や公務員試験の受験が可能になります。
高卒認定試験に合格しても、その後に大学、短大、専門学校などを卒業しない場合は、最終学歴は中卒のままである点には注意が必要です。
高卒認定試験については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
進路⑨進学せずに就職する

最後は、進学せずに就職するという進路です。
中学校卒業後、進学せずに就職した場合、最終学歴は中卒です。
中卒とは文字通り中学校を卒業した人のことであり、多くの場合は最終学歴が中学校卒業の人を指します。
発達障害があるかどうかに関わらず、中卒の学歴で就職し、楽しく充実した人生を送っている人は、もちろんいます。
ただし一般論としては、中卒で働くことは、求人数や待遇の面から、積極的にはオススメしません。
学歴が中卒であることが悪いという意味では決してありません。ですが、残念ながら現代日本の現実では、中卒とその後の学校の卒業では、選択肢や待遇が大きく変わるためです。
厚生労働省の「平成30年若年者雇用実態調査結果の概況」によると、中卒の人の勤務形態は以下のとおりです。
- 正社員:約35.4%
- 正社員以外の労働者:約64.0%
高卒で働いている人の正社員の割合が約56.3%であることと比べると、約20%以上の開きがあることが分かります。(参考:厚生労働省「平成30年若年者雇用実態調査結果の概況」)
正社員の割合が少ないということは、非正規雇用はよくないという意味ではもちろんありませんが、働き先や待遇の選択肢が少ないということです。
そして、発達障害がある場合、選択肢が少ないという状況は、苦労につながる可能性が高いのです。
ただし、もちろんあなたやお子さんの個性は人それぞれです。
発達障害のある人の就労に詳しい人の協力を得るなどすれば、ぴったりの職種・就職先に巡り合える可能性はもちろんあります。
また、一旦は中卒で働いてみたけれど、やっぱり大学や専門学校で学びたいといった場合、日本では再チャレンジできる制度が整っています。
中卒については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「中卒でも就職できる? 中卒の人にオススメの仕事や就職活動を成功させるポイントを解説」
進路⑩起業する/フリーランスになる
そのほかの進路として、起業やフリーランスを目指す選択肢があります。
起業する/フリーランスになる進路についてはこちらであわせて解説します。
補足①:障害者職業能力開発校

補足として、障害者職業能力開発校という進路もあります。
中卒で働きたい場合や、高校・大学などの卒業後になかなか職種・就職先が見つからない場合などは、国が設置し都道府県が運営している障害者職業能力開発校に入校するという方法もあります。
障害者職業能力開発校では、就労に必要な自己管理から、アプリ開発、総合事務といったビジネススキルの訓練まで、1日8時限まで訓練を受けることができます。
ただし、入校するためには医師からの診断書が必要なことに加えて、障害者職業能力開発校が実施する選考に合格する必要があります。
募集は入学する前の年の12月頃から始まるため、前もって窓口となるハローワークに必要な書類や準備を問い合わせるようにしましょう。
補足②:発達障害のある人が進路を選択するときの特別措置

発達障害のあるあなたやお子さんが進路選択をするときには、特別な措置を得られる場合があります。
たとえば、入学試験の際に、以下のような合理的配慮を受けられます。
- 別室受験
- 試験時間の延長
- 問題用紙の読み上げ
- 介助者の同席
- 監督者による口述筆記
- 面接の際の回答を急かさない
こうした特例申請は、基本的には在籍校で申請を行い、教育委員会を介して手続きが進められます。
ここでは、高校入試の特例申請の手続きの流れを挙げておきます。
- 在籍する中学校に申請の相談をする
- 中学を通して教育委員会へ連絡がいく
- 教育委員会から中学校経由で申請用紙をもらう
- 必要事項を記入して中学校に提出する
申請用紙が受理されたら、在籍校や受験校、教育委員会が受験者の障害特性や中学校での指導状況を考慮し、上記のような措置が取られることになります。
特例措置を希望する場合は、在籍する学校にできるだけ早い段階で相談するようにしましょう。
申請の締め切りが受験の願書提出よりも早いことが多いため、注意が必要です。(参考:文部科学省『高等学校の入学試験における発達障害のある生徒への配慮の事例』)
高校卒業編:発達障害のある人の4つの進路
この章では、発達障害のあるあなたやお子さんの高校卒業以降での進路について解説します。
| 進路 | 特徴 |
|---|---|
| 各種大学 | 複数学科を兼ね備える総合大学のほか 美術大学や商業大学などもあり |
| 専門学校 | 医療・介護・デザイン・服飾・アニメなど、 専門分野ごとに就職に結びつくような 実践的な知識や技能の習得を目指す学校 |
| 進学せずに就職する | 一般就労のほか、 福祉的就労(就労継続支援A型・B型事業)、 公的な職業訓練機関や就労支援サービスもあり |
| 起業やフリーランスになる | 起業やフリーランスを目指すなら 高いスキルや知識が必要 WEBライター・WEBデザイナー・ プログラマー・システムエンジニアなど |
進路①各種大学

1つ目は、各種大学への進学です。
大学には、複数学科を兼ね備える総合大学のほか美術大学や医科大学など、専門ごとに多様な種類があります。修学年数も4年生の大学から、2年生の短期大学など様々です。
基本的には、発達障害のあるあなたやお子さんの興味・関心や、将来就きたい職業などを考慮して選ぶことになるかと思います。
大学の形態は、各キャンパスに通って講義・演習を行うスタイルのほか自宅学習が基本となる通信制大学もあります。
通信制大学であれば、レポートや課題をこなすことで単位を取得し、卒業することができます。
そのため、集団で講義を受けるのが苦手な発達障害のある人も、自分のペースで勉強できます。
大学によっては、発達障害のある人向けに、受験時の特別措置を実施している場合があります。
そして、入学後も障害学生支援室など、様々なサポートを受けることができます。
- 専門の支援員による修学相談
- 講義やレポート提出のスケジュール管理などのアドバイス
大学進学を検討しているなら、早めに学校の先生や受験校に問い合わせるようにしましょう。
進路②専門学校
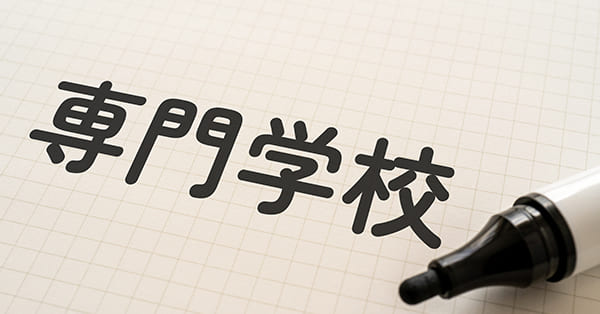
2つ目は、専門学校です。
専門学校とは、医療や介護、デザイン、服飾、アニメなど、専門分野ごとに就職に結びつくような実践的な知識や技能の習得を目指す学校のことです。
基本的に、卒業にかかる年数は2年ですが、学校によっては3年や4年のところもあります。
特定の職能を身につけて、就職に活かしたい人にオススメです。
また、大学同様に、専門学校でも相談次第では発達障害の特性に応じた合理的配慮を受けることが可能です。
LD/SLDで文字の読み書きに時間がかかる場合には、写真撮影や電子端末の使用許可が得られるなどの合理的配慮を受けられます。
具体的な配慮の内容・程度は学校ごとに異なります。発達障害の特性を伝えた上で問い合わせてみるとよいでしょう。
進路③進学せずに就職する

最後の進路は、進学せずに就職することです。
2024年現在、高卒で就職した人は約10万人います。(参考:文部科学相「令和6年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況(令和5年10月末現在)に関する調査について」)
中卒での就職の項でご紹介した正社員の割合データも改めて見てみましょう。
15~34歳までの若年労働者における正社員の割合
- 中卒:約35.4%
- 高卒:約56.3%
- 大卒:約80.9%
大卒に比べると、正規雇用での就労はやや難しい傾向にあります。
そのため給与や待遇・キャリア面を総合的に考えると、大卒で就職した方が希望の就職先を見つけやすいかもしれません。
とはいえ、これ以上進学するよりも早く働きたいという人には就職が大きな選択肢となるでしょう。
高卒の詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
高卒でそのまま就職するのが難しい場合には、こちらで解説した職業能力訓練開発校やハローワークなど、発達障害のある人に向けた公的な職業訓練機関を利用するのも有効です。
特に通信制高校や定時制高校に在籍する人は時間の融通が利きやすいため、学業と並行して職業訓練を受けることも可能かもしれません。
就職にあたって一般就労が難しい場合は、福祉的就労という選択肢もあります。
一般就労とは、民間企業のほか公的機関などに就職し、ほかの従業員と同様に労働者として働く就労形態のことです。
障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)に基づき、障害のある人を一定の割合で雇用しなければならないと定められているため、障害のある労働者が、障害の特徴や内容に合わせて働きやすくするため、安心して働くための雇用枠である障害者雇用枠が設けられているところも多いです。(参考:e-Gov法令検索「障害者の雇用の促進等に関する法律 第一章第二条」)
対して、福祉的就労とは、障害があることで一般就労が難しい人を対象とした、障害者就労施設で働く就労形態のことです。
こちらは、国の施策として障害者に対して就労支援する福祉サービスであり、専門的なサポートを受けながら働いたり訓練を受けたりすることができます。
福祉的就労の代表的なものには次の2種類があります。
- 就労継続支援A型事業所(A型作業所):雇用契約に基づく就労が可能な人が対象
- 就労継続支援B型事業所(B型作業所):雇用契約に基づく就労も困難な人が対象
就労継続支援A型事業所(A型作業所)と就労継続支援B型事業所(B型作業所)については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
参考記事:
キズキビジネスカレッジ(KBC)「就労継続支援A型事業所(A型作業所)とは? 仕事内容や利用の流れ、体験談などを利用経験者が解説」
キズキビジネスカレッジ(KBC)「就労継続支援B型事業所(B型作業所)とは? 作業内容や事業所選びのコツなどを10年間の通所経験者が解説」
また、就労移行支援事業所という就労支援サービスもあります。
就労移行支援とは、一般企業などへの就職を目指す、病気や障害のある方向けに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(通称:障害者総合支援法)に基づいて行われる福祉サービスのことです。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
実際のサービスは、国の基準を満たした様々な就労移行支援事業所が行います。
就労移行支援事業所では、体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができます。
さらには、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援事業所については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「就労移行支援とは? 支援内容やメリット、利用までのステップを解説」
なお、やっぱり大卒での求人に応募したい、学び直しをしたいという人は、働きながらでも大学受験を目指すことはできますので、就職をした後にも状況に合わせて進路を変更することは充分可能です。
進路④起業する/フリーランスになる

そのほかの進路として、起業やフリーランスを目指す選択肢があります。
起業やフリーランスは、自身の知識やスキルを活かして新しい事業を起こし、組織に属さずに働く方法です。(参考:銀河『発達障害フリーランス 属さない働き方のすすめ』)
高い専門性が求められますが、働く場所を自分で決められる、時間の制約がないなどの魅力があります。
また、仕事内容によっては人と関わる機会が少なく、会社員よりも人間関係の悩みが少ない働き方だと言えます。
起業やフリーランスは就職にない魅力があるため選択肢の一つとして考えても良いでしょう。
ただし、起業やフリーランスは自分で仕事を取り続ける必要やクライアントとコミュニケーションが求められるケースもあります。
自身が起業やフリーランスに向いているかは、特性によって変わるため慎重に検討しましょう。
なお、起業やフリーランスを目指しやすい職種として下記のような仕事があります。
- Webライター
- Webデザイナー
- プログラマー
- カメラマン
- システムエンジニア
- イラストレーター
自分がどの仕事に向いているか、フリーランスに向いているか分からない人は、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「ADHDの人がフリーランスに向いているかをズバリ語る!」
補足:進学や就職の前に支援機関の利用がおすすめ
進学や就職の前に、支援機関を利用することをおすすめします。
支援機関では進路に関する相談ができ、円滑に進学や就職できる可能性が高まります。
例えば、就労移行支援事業所を利用すれば会計やプログラミングなど、ビジネススキルが身につき就職につなげやすくなります。
こちらで具体的な支援機関を紹介しています。進路について相談したい内容がある人は参考にしてください。
発達障害のある人の進路に関する支援機関

発達障害の子の進路に関してどこで相談したらよいのかと考えている人は、以下の専門家や支援機関で相談することがおすすめです。
それぞれ解説しているので、就学や就職など目的にあわせて相談してください。
支援機関①医師や心理士
発達障害のある人を多く見てきた医師や心理士からは、学校の先生などとは別の視点からのアドバイスを得られます。
特に、まだ発達障害であるかどうかわからないという人の場合は、まずは病院を受診するようにしましょう。
支援機関②発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは、各地に設置されている公的な専門機関です。
発達障害の診断がなくても、進路の話題に関わらず、無料で相談することができます。
発達障害情報・支援センター「発達障害者支援センター・一覧」
支援機関③発達障害のある人向けの塾
発達障害のある人に特化し、数多くの指導実績がある塾なら、進路選択についてより具体的な助言を得られるでしょう。
支援機関④障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、障害者の職業生活における自立を図るために設置された公的機関です。
全国に設置されているため、就職に不安がある場合は近くの施設で相談してみましょう。
なお、2023年4月1日時点で全国に337箇所設置されています。
厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」
補足:その他の支援機関
外部の専門家の助力を得られないかを検討してみてください。
また、学校生活や親子関係など進路以外の悩みがある場合、支援機関については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ〜発達障害のある人でも進路の選択肢はたくさんあります〜

発達障害のあるあなたやお子さんに合いそうな進路は見つかりましたか?
繰り返しにはなりますが、進路選択の際に大切なのは、あなたや親御さんだけで抱え込まずに、周囲の人に相談することです。
学校の先生やスクールカウンセラー、医師や支援機関、塾の先生など、頼れる人は大勢います。
このコラムが、発達障害のあるあなたや親御さんが少しでも楽になる手助けとなれば幸いです。
Q&A よくある質問
発達障害があるのですが、進路選びのポイントを知りたいです。
発達障害のある人の進路選びのポイントとして、以下が考えられます。
- 在籍している学校に相談する
- 医師や支援機関に相談する
- 特性を考慮して進路を選ぶ
- 準備は早めに進める
- 自分自身・お子さんの意思を尊重する
- 各進路の特徴を理解して判断する
詳細については、こちらで解説しています。
子どもは発達障害があります。どういうところに相談すればいいのでしょうか?