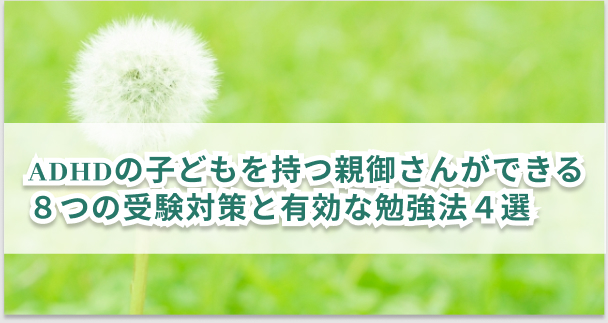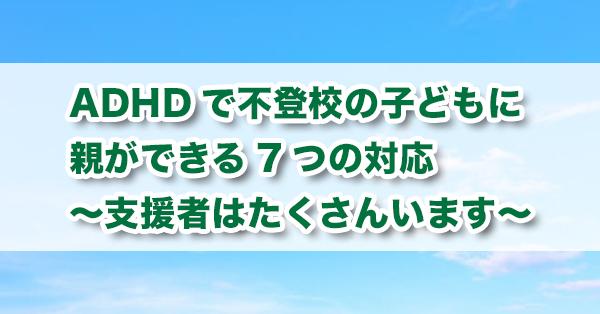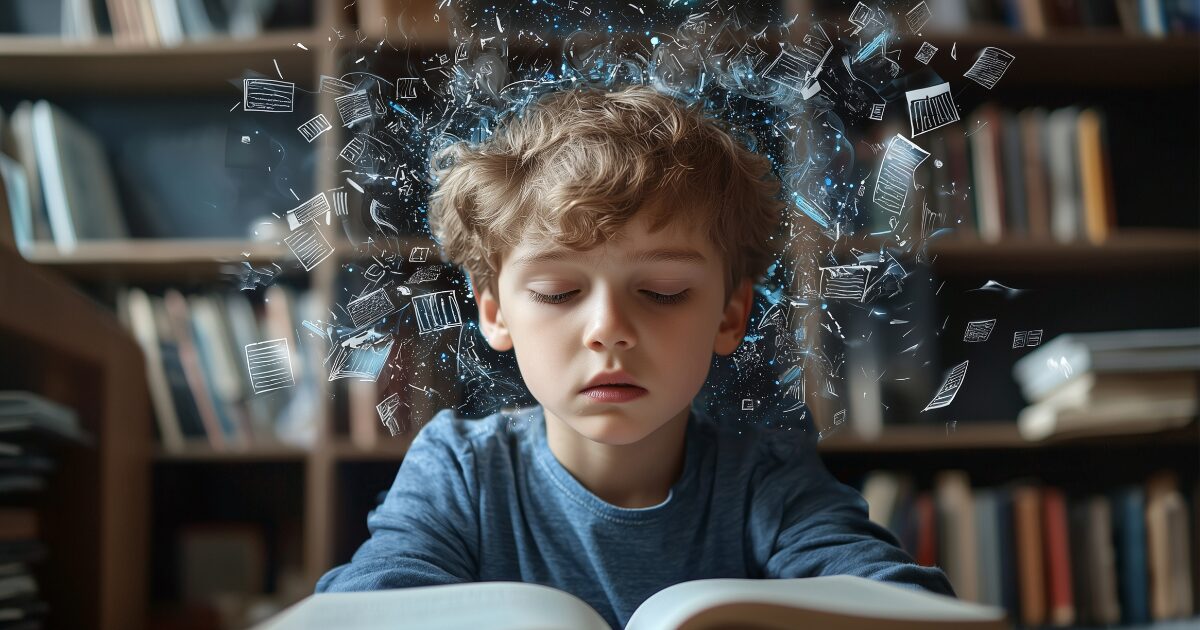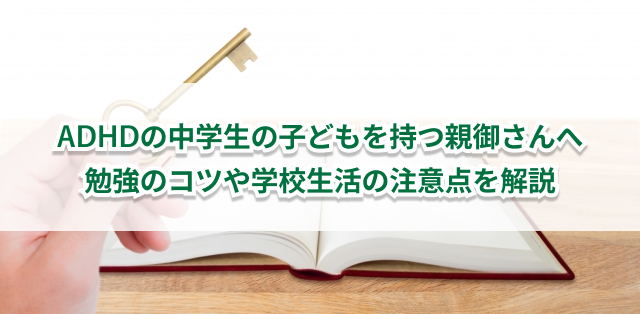ADHDのある子どもに親ができる受験対策 有効な勉強法を解説
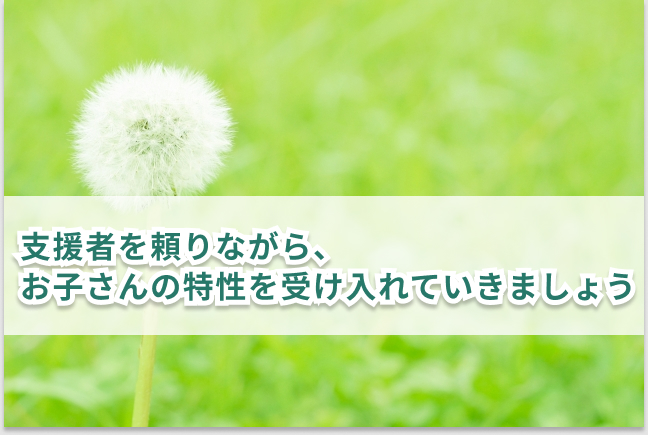
発達障害のお子さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートするキズキ共育塾の寺田淳平です。
ADHDのあるお子さんの親御さん、あるいは「うちの子はADHDかもしれない」と思っている親御さんは、受験について以下のようにお悩みではありませんか?
- ADHDのある子どもが受験で気をつけるべきポイントは?
- ADHDのある子どもの受験に際して親ができる対策は?
- ADHDの特性に合った受験勉強の仕方がわからない
上記のように悩みを抱える親御さんは、少なくないかと思います。
このコラムは、ADHDのある子どもが受験時に困りやすいポイント、親御さんができる受験対策、特性に合った勉強法について解説します。
受験を目指すADHDのお子さんの親御さんは、ぜひ一度、読んでみてください。(参考文献:司馬理英子『ADHD 注意欠如・多動症の本』、 本田秀夫・日戸由刈『ADHDの子の育て方のコツがわかる本』、鈴木慶太『親子で理解する発達障害 進学・就労準備の進め方』)
私たちキズキ共育塾は、受験を目指すADHDのある子どものための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
ADHDの子どもが受験に際して困りやすいポイント4点
まず、ADHDのお子さんが受験に際して困りやすいポイントを紹介します。
困りごとのいくつかは、家庭よりも学校や塾での勉強の場で、よく見られるものです。
そのため、担任の先生や塾の講師とも情報共有しながら、お子さんに困りごとが生じていないかを把握することが大切になります。
ADHDのお子さんの困難を把握する際の参考として、以下のポイントを確認してみてください。
ポイント①興味のない勉強や授業に集中できない

1つ目は、興味のない勉強や授業に集中できないことです。
ADHDの子どもは、自分が興味のある事柄には強い集中力を発揮しやすいのですが、そうでない事柄には注意散漫になり、集中力が持続しづらい傾向があります。
また、小学生・中学生の場合は、高校生と比べて、まだ精神的にも成熟していない子どもたちが机を並べることになります。
そのため、互いにちょっかいを出したりすることも多いでしょう。
ADHDの子どもは、このように注意の対象が他に向くと集中が削がれやすいため、勉強や授業に集中できない、先生の話が頭に入ってこないということが起こりやすいのです。
ポイント②なかなか勉強に手をつけることができない
2点目は、なかなか勉強に手をつけることができないことです。
ADHDの特性から机が散らかっている、教科書やプリントを分類・整理ができない、といった状況が生じることもあります。
こうした整理整頓ができない状況下だと、勉強を始めようにもどこから手を付けてよいかわからないと、お子さん自身が困っている場合があるのです。
そのため、お子さんが勉強を始めることに抵抗を感じているケースが少なくありません。
また、自室で勉強をするときは、お子さんの周囲にスマートフォンやゲーム、マンガなどがあることも多いでしょう。
それらに気を取られた結果、勉強に意識が向かなくなったということも、ADHDのお子さんには顕著に見られることがあります。
このように、勉強に手をつけることができないというのも、よく聞かれる困りごとです。
ポイント③持ち物や予定を忘れやすい

3つ目は、持ち物や予定を忘れやすいことです。
特に、衝動性が強いADHDのお子さんは、不意に思いついたアイディアや欲求に気を取られやすく、それまで考えていたことを忘れて、別のことに意識が向くと言われています。
さらに、整理整頓が苦手な傾向があるお子さんの場合は、必要な持ち物を探している間に、別のことに気を取られた結果、そのまま忘れて出掛けるということが少なくありません。
また、予定があっても直前まで気が回らなかったり、課題のスケジュールを先延ばしにしたりするというのも、ADHDの特性としてよく挙げられます。
そのため、次章で解説するように、親御さんの方で予定のリマインドをしたり、持ち物の確認を手伝ったりすることが大切です。
ポイント④内申点に影響しやすい
最後は、ADHDの特性について、学校の先生の理解が不十分な場合は、内申点に影響しやすいという点です。
これまで解説してきた、授業に集中できない、忘れ物や遅刻が多い、といった特徴は、ADHDの理解が十分でない先生から、「不真面目だ」「努力が足りない」などと誤解されて、内申点を低く付けられるケースがあります。
そのため、特に受験を控えた時期になると、ADHDの特性が学校の内申点に関わることが悩みになる場合も多いようです。
お子さんの内申点が気になる場合には、内申点があまり影響しない私立の学校を探すなど、事前に調べておくことも大切です。
ADHDの子の親御さんができる受験対策8選
ここからは具体的に、ADHDの子の親御さんができる受験対策を紹介します。
前提として大切なのは、ADHDや受験に関する悩みをご家庭だけで抱えないことです。
担任の先生、発達障害のサポート団体、かかりつけ医など、専門家を含む第三者へ積極的に相談するようにしてください。
親御さんとお子さんの努力だけで解決するのではなく、周囲に協力を求めながら、以下の受験対策を実践しましょう。
対策①特性を理解して受け入れる

1つ目は、特性を理解して受け入れることです。
ADHD(による困りごと)は、子どもの努力次第でカバーできると考えていませんか?
努力や工夫でなんとかなる部分は、もちろんあります。
しかし、ADHDは先天的な脳の機能の偏りに起因するため、本人の努力だけではどうにもならない面も多くあるのです。
カバーできる場合もできない場合も、お子さんが日常生活を送る上で、周囲の人から配慮を得られるよう、親御さんがお子さんの特性を理解して受け入れることが大切になります。
また、ADHDに伴う特性を受け入れることは、一種の個性としてお子さんを尊重することにつながり、結果としてお子さんの自己肯定感を高めることにもなります。
とりわけ、受験期にはお子さんと周りの学生さんを比べて、親御さんの方でも「どうしてうちの子どもは○○ができないのだろう」と考えこむ機会が増えるかもしれません。
そういうときは、まずはお子さんの特性を受け入れた上で、どんな困り事を抱えているのか、何が得意で何が苦手なのかといった理解を深めることから始めるようにしましょう。
対策②担任・医師・カウンセラーに相談する
2つ目は、担任・医師やスクールカウンセラーに相談することです。
担任と医師・カウンセラーへの相談を並行的に行うことで、お子さんへのよりよい対応がわかっていきます。
担任の先生は、お子さんの学校での状況をよく知っています。
学校での様子をしっかり聞くとともに、医師やカウンセラーから得られたお子さんの特性についても伝えるようにしましょう。
学校にスクールカウンセラーが在籍しているようであれば、そちらへの相談も有効です。
すでに診断が出ている場合には、担任の先生から、ADHDのお子さんが学校生活や受験に際して受けられる特別な配慮について教えてもらえるでしょう。
逆に、担任の先生から聞いた学校での様子を医師やカウンセラーに伝えることで、医学的な観点からのアドバイスも受けやすくなります。
特に、小さい頃からお子さんを診ているかかりつけ医であれば、お子さんの特性に詳しいため、より的確なアドバイスが得られるでしょう。
対策③支援機関や学習塾を利用する

3つ目は、支援機関や学習塾を利用することです。
お子さんのADHDに関連するお悩みについては、支援機関に協力を求めるのも対策の一つです。
例えば、全国各地には、無料で相談できる公的な支援機関がたくさんあります。
特に、発達障害者支援センターでは、医師による診断書がなくても、お子さんのADHDに関する相談を受け付けています。
公的な支援機関については、発達障害者支援センターも含めて、お住まいの市区町村の障害福祉課でお近くの相談窓口を確認することができます(市区町村によって担当部署の名前は異なりますので、担当部署がわからない場合は代表窓口に聞いてみましょう)。
また、公的機関だけでなく、発達障害のある子どもを指導した実績がある学習塾を頼るのもオススメです。
特に、個別指導を行っている塾であれば、ADHDに理解のある講師が、お子さんの特性に配慮した、きめ細やかなフォローを行っています(私たち、キズキ共育塾もその一つです)。
受験に留まらず、進学後の勉強の進め方や、進路の選び方、将来のことなど、幅広い相談に対応している塾も少なくありません。
ぜひ、親御さんやお子さんが相談しやすい支援機関や指導塾を探してみてください。
対策④予定や持ち物の確認を手伝う
予定や持ち物の確認を手伝うというのも、親御さんができる大切な受験対策です。
ADHDの特性による物忘れなどは、家族のサポートや道具を使った工夫で、ある程度カバーができます。
具体的には、以下のような方法がオススメです。
- 予定の数日前と当日に家族がリマインドする
- リマインダー機能付きの予定管理アプリを使う
- 持ち物や予定をリスト化して壁や玄関に貼り付ける
アプリなどのツールを使うときには、お子さんが認識しやすいもの、内容が頭に入りやすいものを選ぶようにしましょう。
また、持ち物などを忘れないように、出かける前に余裕を持ってきちんと整理しておく、必ず一つのバッグにまとめておく、といった工夫も効果的ですので、試してみてください。
対策⑤無理をしないで適度に休ませる

5つ目は、無理をしないで適度に休ませることです。
ADHDの子どもは、同級生とのコミュニケーションや、学校での勉強に悩むことが少なくないため、ストレスや疲れを感じやすい傾向にあります。
特に、受験期には心理的なストレスが重なることで、うつ病や適応障害のような二次障害を併発するお子さんも中にはいます。
そのため、特に体調が悪いわけでなくても、休みたいと訴えた場合には、お子さんの意思を尊重して、できるだけ休ませることが大切です。
また、お子さんだけでなく、親御さん自身も、自分の時間を取ってリフレッシュし、休むことが必要です。
ADHDの子どもの対応で、親御さん自身に疲れがたまると、敏感なお子さんはそれを察知して、自分が迷惑を掛けているかもしれないと、後ろめたさを感じるかもしれません。
お子さんにとって家庭が安心して休める場所になるように、親御さんも適度に休むことを意識しましょう。
対策⑥受験時の特例措置を申請する
6つ目は、受験時の特例措置を申請することです。
ADHDの確定診断があるお子さんの場合、受験時に特別な措置を得られる場合があります。
高校受験の例になりますが、ADHDの子どもが受けられる具体的な特別措置として、別室受験、保護者の別室待機などを文部科学省は掲げています。(参考:文部科学省「資料2 高等学校の入学試験における発達障害のある生徒への配慮の事例」)
こうした特例申請は、基本的にはお子さんが在籍している学校を通じて申請を行い、教育委員会を介して手続きが進められます。
特例申請をする場合は、お子さんの在籍している学校に相談するようにしましょう。
申請の締め切りは受験の願書提出よりも早いことが多いため、親御さんの方でも情報収集・スケジュール管理をしていただくことをオススメします。
対策⑦親の会に参加して情報収集する

7つ目は、親の会に参加して情報収集することです。
ADHDに限らず、発達障害には、その特性に応じた親の会が各地に存在します。
親の会に参加することで、同じような発達障害の子の保護者と意見交換をして有益な情報を得たり、受験の悩みを共有できて気持ちが楽になったりといったメリットが期待できるでしょう。
興味のある方は、「発達障害 親の会」と検索すれば、ご紹介した団体以外にも、多くの団体の活動をお調べいただけます。
例えば、「JPALD(特定非営利活動法人 全国LD親の会)」では、東北や関東など、各地を6ブロックに分けて、保護者による情報交換会、勉強会、発達障害の子の友達作り、イベントなどを催しています。
JPALDは、LDと銘打たれてはいますが、ADHDやASD(自閉症スペクトラム症)など、様々な発達障害の当事者やそのご家族が一緒に活動しています。
なお、親の会は、それぞれに目的や性質が異なりますので、もし一つの会が合わなかったとしても、別の会を探してみることをオススメします。
対策⑧ペアレントトレーニングを受ける
最後はペアレントトレーニングを受けるです。
ペアレントトレーニングとは、発達障害の親が、効果的な親としてのスキルを学ぶことができる講座のようなものです。
親の子どもへの接し方を見直す意味でも非常に有効だと言われています。
ペアレントトレーニングの内容には、以下のようなものがあります。
- 各発達障害の特性について理解を深める講習
- 各発達障害に見られる行動を分類して理解する
- 子どもの良いところへ目を向ける練習する
- 効果的な指示の仕方や好ましくない行動を取ったときの対処法を勉強する
- 同じ悩みを持つ親御さん同士で情報交換をする
医療機関や教育機関などで指導者を招き、毎週決まった時間に上記のようなトレーニングを実施します。
インターネットで「(お住まいの市区町村名)+ADHD+ペアレントトレーニング」などと検索すると、お近くの講習会が見つかると思います。
お住まいの地域の施設で行われているペアレントトレーニングに参加すれば、年長のお子さんを持つ親御さんから、受験先などで得られる支援について、詳しい話を聞ける可能性もあります。
ADHDのお子さんのサポートを充実させたいという親御さんは、お近くの機関で実施されているペアレントトレーニングを探してみてはいかがでしょうか?
ADHDの子どもに有効な勉強法4選
この章では、ADHDの子どもに有効な勉強法を紹介します。
ADHDのお子さんが受験勉強をする上では、特性を活かすことが重要です。
ADHDに限らず、発達障害のある子どもが周囲と同じやり方に合わせようとすると、特性をお子さん自身の努力でカバーしようとして無理が生じたり、負担が増えたりすることもあります。
それを避けるためにも、子どもの特性を個性として受け入れて、周囲の協力を得ながら、その個性を活かす方法を模索してみてください。
なお、特性が様々である以上、ご紹介する勉強法があなたのお子さんに合うかどうかはわからない、ということは正直にお伝えします。
ご紹介する勉強法は、ADHDの子どもでも向いた勉強法はあるという安心材料にしていただいた上で、実際のあなたのお子さんの勉強法については、ご紹介してきたような支援団体などと話をすることで、より具体的に見つかっていくと思います。
勉強法①短時間の勉強を重ねる
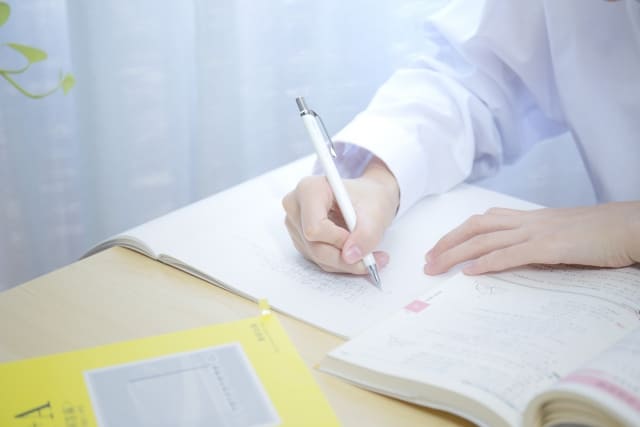
1つ目は、短時間の勉強を重ねるという勉強法です。
お子さんによっては、ADHDの特性によって、興味のない科目に対して集中力が持続しづらい場合があると思います。
しかし、受験勉強では、苦手な科目にも取り組まなければなりません。
そういったときは、できるだけ集中している時間が短く済むように、短時間の勉強を積み重ねることが有効です。
具体的には、親御さんがお子さんと一緒に、解くべき課題や問題を短時間でできるくらい細かく分けるとよいでしょう。
親御さんにとっては多少手間かもしれません。ですが、その日にやる分の課題や過去問を1単元、1回分ごとにコピーして渡すなど、ちょっとした工夫で、お子さんは継続して取り組みやすくなります。
ぜひ、課題を小分けにして、短時間の勉強を積み重ねやすいように、サポートをしてみてください。
勉強法②ゲーム性を取りいれる
ゲーム性を取りいれた勉強法も有効です。
ゲーム性を取り入れることで、集中力が持続しづらい特性があるお子さんも楽しみながら勉強できますので、比較的モチベーションが保ちやすくなります。
例えば、次のような例があります。
- 親御さんの方で問題を出してクイズ形式にする。
- ○分間でいくつ英単語を覚えられるかを計測して、記録を更新できるか試す。
また、発達障害専門のクリニックを開院している司馬理英子先生は、目標が達成できたら好きなお菓子を食べられるなど、ご褒美や景品を表にして掲げておくのも有効だと述べています。
ぜひ、お子さんに合った、勉強を楽しみながらできる工夫を取りいれてみてください。
勉強法③褒めて伸ばすことを意識する

勉強法というよりは親御さんが意識したいポイントとして、ADHDの子どもは褒めて伸ばすことが特に大切です。
受験勉強期には、親御さんが成績や評価に過敏になるあまり、ついお子さんに厳しく接することもあるかもしれません。
そういった親御さんの姿勢は、お子さんの自信喪失を招くこともあります。
そのため、「今日もよくがんばったね」「今日は苦手な科目にも取り組めたね」といったように、小さななことからでも構いませんので、お子さんを褒めることを意識しましょう。
お子さんを褒めることは、お子さんの自信を養うことにもつながります。できるだけ機会を見つけて褒めるよう、心掛けてください。
勉強法④勉強の前後に整理整頓の時間をつくる
勉強の前後に整理整頓の時間をつくることも大切です。
特に、ご家庭では、自室やリビングで受験勉強に取り組むことになると思います。
しかし、机上が散らかっていたり、テーブルの上に余計なものがあったりすると、ADHDのお子さんは注意散漫になりやすいため、集中力を持続するのが難しくなります。
意識して勉強に必要なもの以外は机に置かないようにすることが重要です。
勉強の前後に整理整頓の時間を設けることで、勉強が比較的はかどるようになるでしょう。
ぜひ、お子さんが集中しやすい環境づくりに取り組むようにしてください。
改めて、ADHD(注意欠如・多動性障害)とは?
最後に、改めてADHDの特性を詳しくご紹介いたします。すでにご存知かもしれませんが、これまでに紹介した内容の理解も深まると思いますので、ぜひご覧ください。
ADHDは、正式名称を注意欠如・多動性障害(Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)という、発達障害の一種です。
ADHDの特性の一例として、計画を立てた上でも、意図せずして他のことに注意が向いた結果、約束や予定そのものを忘れるということがあります。
そのため、学校生活や勉強の場面で苦労することがあると言われています。
また、2013年にアメリカ精神医学会の定める『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』においてはじめて成人のADHDが規定されたことで、近年では子どもに限らず大人のADHDも注目を集めています。 (参考:岩波明『大人のADHD:もっとも身近な発達障害』、日本精神神経学会「今村先生に『ADHD』を訊く」)
①ADHDの2つの特性
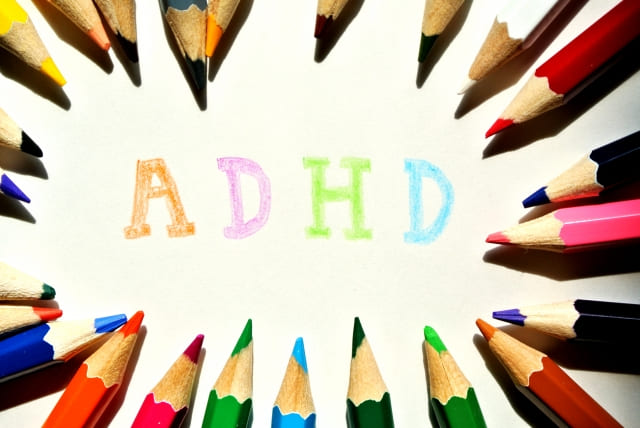
ADHDには大きく分けて2つの特性があります(特性の程度や現れ方には個人差があります)。
- 不注意:忘れ物やミスが多く、確認作業が苦手
- 多動・衝動性:気が散りやすく、貧乏ゆすりなど常に身体を動かしていないと落ちつかない
特に中学生・高校生は、この2つの特性が学校生活や勉強の場面で、具体的な形となって現れることが多いです。
多動・衝動性の特性は、成長するうちに目立たなくなる場合もあり、青年期以降にその特性が見られなくなる人もいます。
なお、ADHDは病気とは異なり、あくまで目立ちやすい特性があるというだけです。
日常における過ごし方を工夫することで、お子さんは持っている力をしっかりと発揮することができますので、ご安心ください。
②診断を受けていない場合は、病院にいきましょう
ある人がADHDかどうかは、医者でないと判断できません。
そのため、お子さんがADHDかどうかの診断をまだ受けていない場合は、まずはサポート団体や病院に行って相談するようにしましょう。
サポート団体の例として、発達障害者支援センターがあります。
③ADHDの強みと弱み

ADHDの特性は、もちろんお子さんの強みになることもありますし、時と場合によっては弱みになることもあります。
例えば、ADHDの特性が見られる人には、以下のような長所があると言われています。
- 発想力に富んでいてアイディアが豊富
- 好奇心旺盛でチャレンジング
- 興味のある分野に強い集中力を発揮する
- 決断から行動までが速い
- 感覚に優れていて周囲の環境に敏感
しかし、反対に、特性が以下のような短所として現れる場合もあります。
- 記入漏れなどのミスをしやすい
- 物事に優先順位をつけるのが苦手で先延ばししやすい
- 整理整頓が苦手で物を失くすことが多い
- 他人の意見に耳を傾ける前に発言したり行動したりする
ADHDのお子さんについては、できるだけ特性の長所を活かして能力を伸ばすことを意識しましょう。
その上で、短所をカバーできる対処法を、お子さんが少しでも身につけられるように、親御さんがしっかりとサポートすることが大切です。
ただしもちろん、親御さんだけでなんとかしようとする必要はなく、後述するような支援者を頼ることも重要です。
④ADHDの子どもが気をつけたい二次障害とは?
ADHDのお子さんについては、二次障害に気をつけてください。
二次障害とは、発達障害の特性に伴う社会生活上の困難などが原因で、心に傷を負うことにより発症する抑うつ状態や精神疾患を言います。
学童期におけるADHDの子どもは、家族や学校の先生に発達障害の知識がないと、忘れ物や遅刻の多さを特性として理解されず、本人の努力不足として見られることがあります。
また、衝動的に行動することで、クラスメイトと衝突し、人間関係が悪化するケースもあるでしょう。
そうしたことが続くと、ADHDの子どもは、自己肯定感を養うことができなくなります。
自分は何をやってもうまくいかないと、長期的に意欲を失うことにつながりやすいのです。
特に、中学校・高校進学といった節目には、学校の勉強が難しくなったり、部活動が始まったりします。
そのため、学校生活で困りごとを抱える機会も多く、特に注意が必要です。
また、受験期には勉強だけでなく、手続き面やスケジュール管理もシビアになりますので、ADHDのお子さんは普段以上にストレスを溜め込みやすくなるでしょう。
お子さんの気持ちが沈んでいるようであれば、無理をしないように休ませつつ、学校の先生やスクールカウンセラー、精神科の医師を頼るようにしましょう。
二次障害の症状をきっかけに病院を訪れて、初めて子どもが発達障害だと判明することもあります。
そのため、お子さんが発達障害ではないかと疑っている親御さんは、お子さんに少しでもメンタル面の不調が現れたら、決して無理をさせないようにしましょう。
まとめ〜ADHDの子どもは、サポート次第で受験を成功させることができます〜

ADHDの子どもが困りやすいポイントから、具体的な受験対策、勉強法までを解説してきました。あなたのお子さんに役立ちそうな情報はありましたか?
繰り返しにはなりますが、前提として大切なのは、お子さんの特性を受けいれることです。
他のお子さんが実践している受験対策をそのまま適用するのではなく、ADHDの特性にあった受験対策を行いましょう。
その際には、親子間だけで問題を解決しようとせず、医師や担任の先生、指導塾の講師の先生に相談して、上手にアドバイスを取りいれるようにしてください。
周囲の助言を参考にして、お子さんに合った受験対策を講じることができれば、志望校への合格に、より近づけるはずです。
このコラムが、ADHDの子どもの受験で悩んでいる親御さんの助けになれば幸いです。
さて、私たちキズキ共育塾は個別指導塾であり、ADHDのお子さんや不登校のお子さんの勉強を支援してきた経験が豊富です。
キズキ共育塾は、無料相談も承っておりますので、ご相談いただければ、ADHDのお子さんの勉強や受験などについて、「あなた」のための具体的なお話ができると思います。
キズキ共育塾の概要をご覧の上、少しでも気になるようでしたらお気軽にご相談ください(親御さんだけでのご相談、お子さんと親御さんご一緒でのご相談も承っております)。
/Q&Aよくある質問
ADHDの子の受験について、親ができることを知りたいです。
- 特性を理解して受け入れる
- 担任・医師・カウンセラーに相談する
- 支援機関や学習塾を利用する
- 予定や持ち物の確認を手伝う
- 無理をしないで適度に休ませる
- 受験時の特例措置を申請する
- 親の会に参加して情報収集する
- ペアレントトレーニングを受ける
ADHDの子どもに有効な勉強法を知りたいです。
- 短時間の勉強を重ねる
- ゲーム性を取りいれる
- 褒めて伸ばすことを意識する
- 勉強の前後に整理整頓の時間をつくる