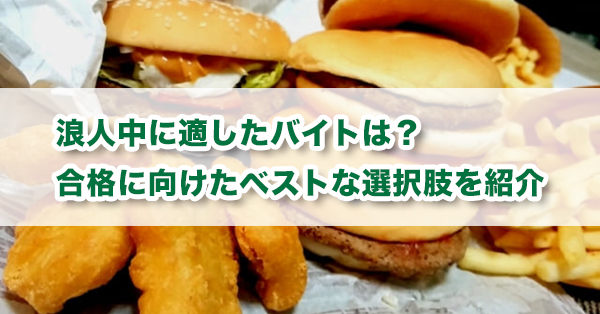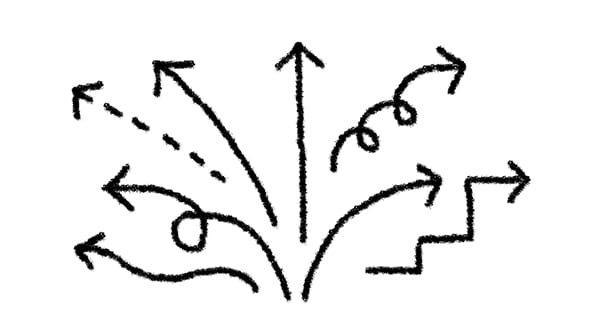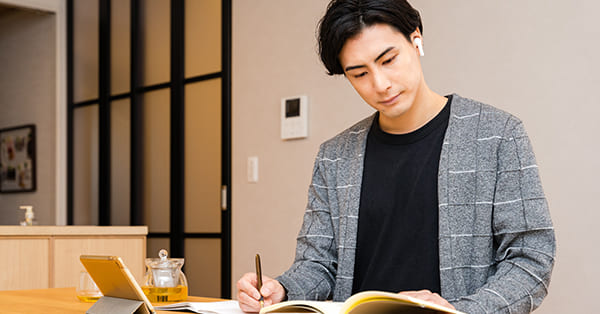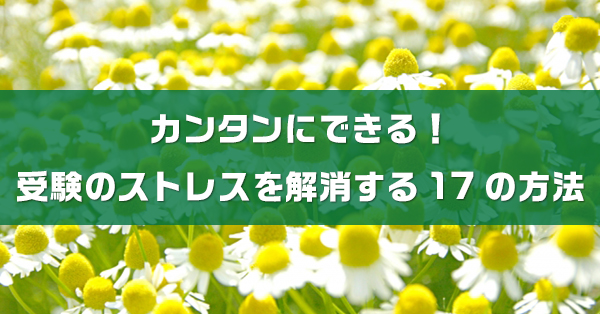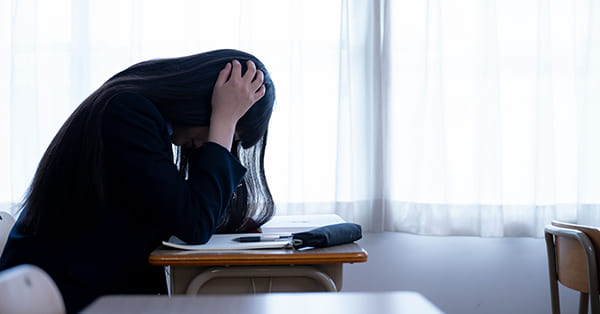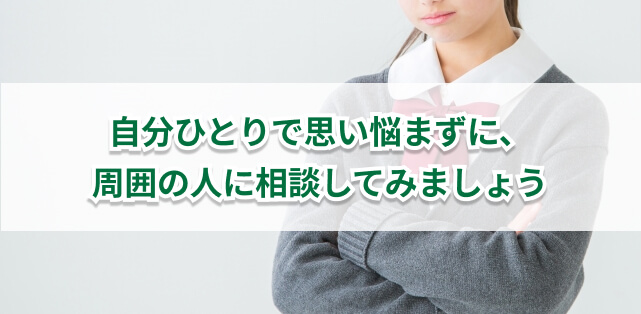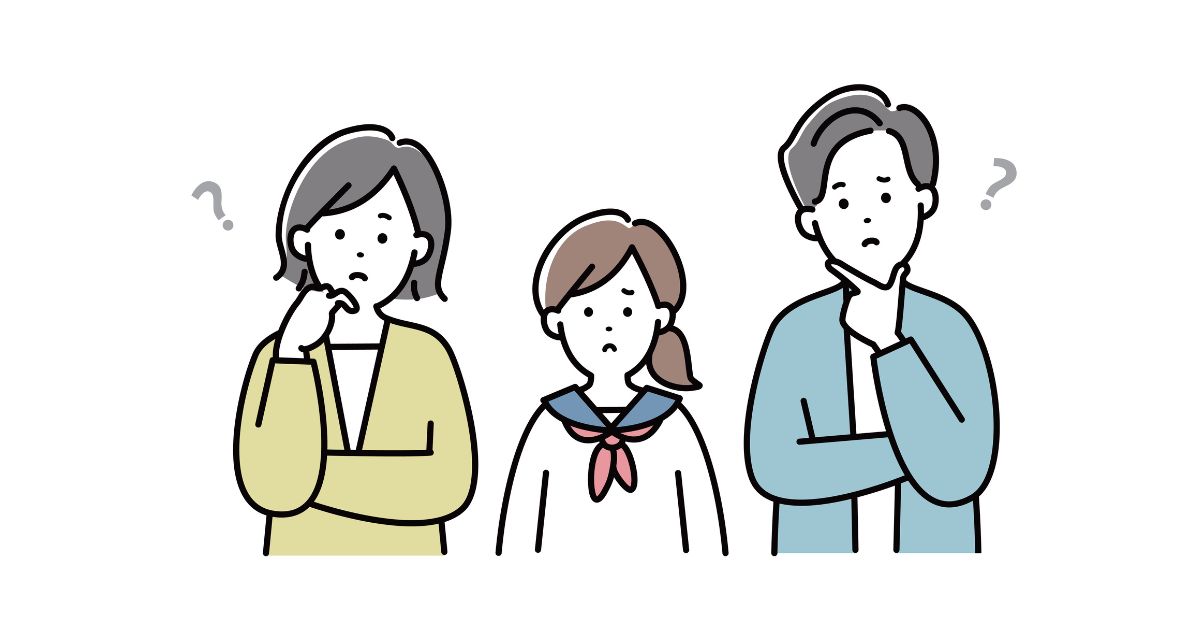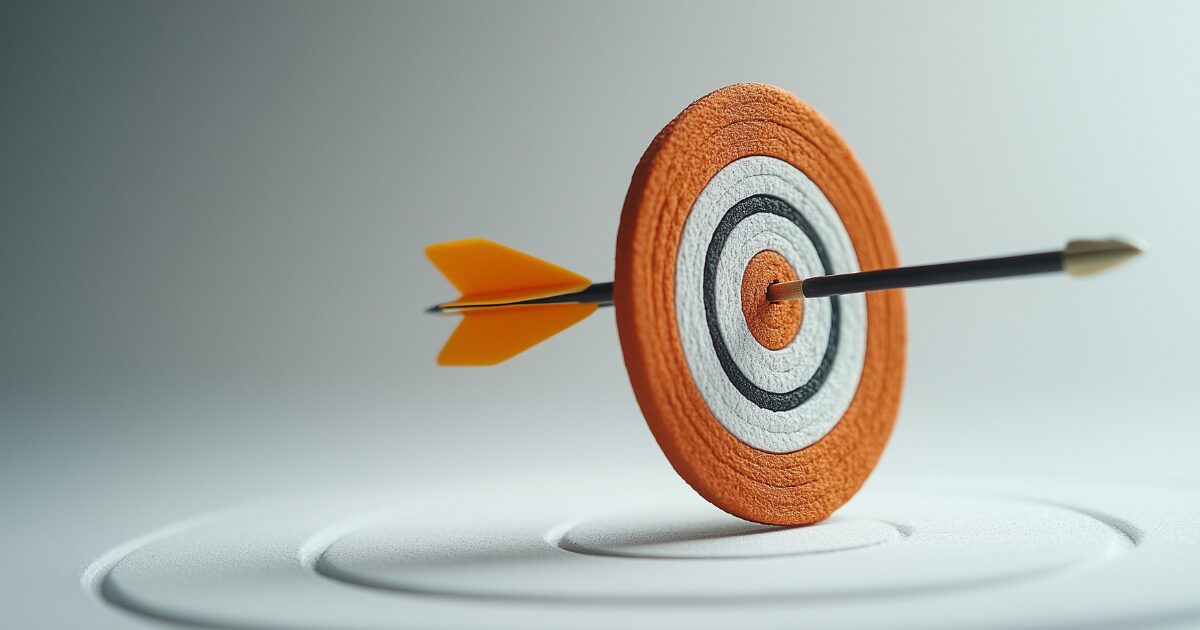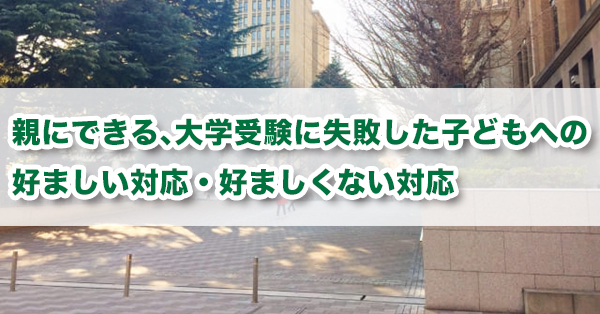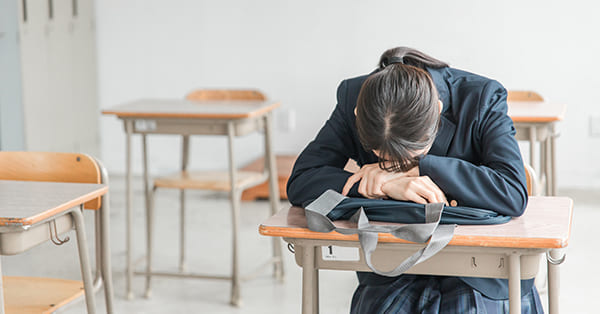大学受験に失敗した子どもに親ができる対応 NG対応を解説
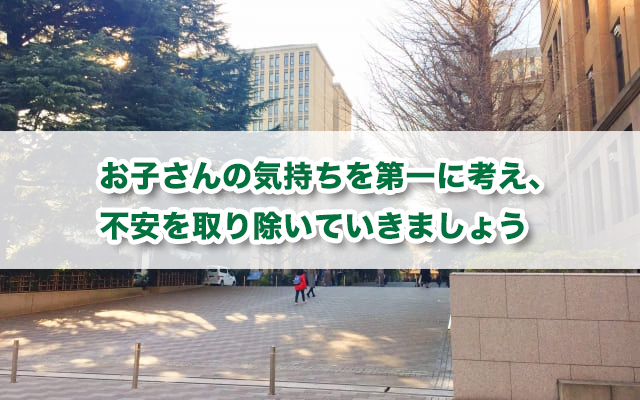
こんにちは。一人ひとりに寄り添う完全個別指導塾・キズキ共育塾の藤井祐太朗です。
このコラムをご覧のあなたは、「大学受験に失敗したうちの子に、どんな言葉をかけてやれるだろう。どんなことをしてやれるだろう」と、お悩みではありませんか?
- 不用意なことを言って更に傷つけないようにしないと…
- 叱咤激励して、人生の厳しさをわからせないと!
- 親としてどういう言動をとったらよいのか
こんなふうに、思いあぐねているかもしれませんね。
今回は、大学受験を失敗したお子さんに、親であるあなたがどういった言葉をかけるのがよいのか、どういった行動をするのがよいのかについて、私自身の体験、友人の話、塾講師としての経験に基づいてご紹介します。
お子さんが「次に一歩」に進むため、そして親であるあなたのお悩みを軽くするため、少しでもお役に立てれば嬉しいです。
私たちキズキ共育塾は、大学受験に失敗した人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
大学受験に失敗した子どもに親ができる3つの対応
まずは、大学受験に失敗したお子さんのために、親がとった方がよい対応、お子さんにとって好ましいと思われる対応を紹介します。
対応①お子さん本人の気持ちを一番に考える

まずは大前提として、お子さん本人の気持ちを一番に考えましょう。
大学受験に失敗して一番傷ついているのは、誰よりもお子さん本人です。
親は焦らずに一歩引きつつ、基本的にはいつもと変わらない態度で、(いつもより少し優しく)接するとよいでしょう。
お子さんを思う気持ちはとてもよくわかります。ですが、大学受験に失敗してすぐの時期に、親が励ましの言葉をかけたり、叱咤激励をしたりしても、逆効果になることもあります。
「そんなことわかってるよ!」「親に何がわかるんだ!」「なんでそんなこと言われなきゃいけないんだ!」などと反感を持たれては、お子さんとのすれ違いが生じるかもしれません。
態度はいつもと変えなくても、お子さんのことは常に気を配り、気持ちを汲み取ったり、変化を見逃さないようしたり、つぶさに観察してみることをオススメします。
対応②チャレンジをほめる
受験結果については触れず、大学受験という「チャレンジ」をほめることもよいでしょう。
大学受験に失敗した理由は、いろいろと考えられます。
学力不足、本番当日の体調不良、受験会場の雰囲気に気圧された、(遠くの大学を受験した場合は)移動の疲れや不慣れさなどなど。
そういったハンデと戦って受験に挑んだという経験は、立派に誇るべき部分です。
大学受験自体が、本人にとっては一大決心だった可能性もあります。
受験をしたという事実は、本人にとって大きな経験となったはずです。
チャレンジをほめることで、お子さんは失敗の「次」に進みやすくなります。
ただし、これについても、お子さんには「ほめられたいタイミング」や「触れられたくないタイミング」があります。
前述の「子ども本人の気持ちを一番に考える」で述べたように、いつほめるのがよいか、お子さんの心情の変化をつぶさに観察しましょう。
対応③お金のことを正直に話す

大学受験の失敗に伴って発生するお金の話題には、親子で正直に向き合うようにしましょう。。
例えばですが、「浪人生活を始めるために、予備校代や生活費などが新たに必要となる場合」が考えられます。
現在の家計や将来の見通しなどについては、お子さんに正直に伝えた方がお互いのためになります。
具体的には、「お金については心配しなくていい」「月に何円までなら大丈夫」「余裕がないから、どうするか一緒に考えよう」といったことです。
「余裕がない」のであれば、親子で一緒に奨学金やアルバイトなどを探すことで、現実的に大学受験ができる環境を整えていきましょう
なお、親御さんから見て、受験勉強期に勉強をほとんどしていなかったり、遊んでいたりなどで、浪人や再受験にまつわるお金を出すことにどうしても抵抗がある場合もあるかもしれません。
そのようなときは、お子さんに「大学に行きたい気持ち」「これからどう勉強するか」「勉強スケジュール」などを、プレゼンテーションしてもらう、といった方法もあります。
お子さんとしても、「これからの方針」を自分で再確認できます。
大学受験に失敗した子どもにNGな対応3選
では次に、親がお子さんに取るべきではない対応例をご紹介します(前章の裏返しである内容もあります)。
もし、これまでに次のような対応をしていても、変に落ち込まず、後述するような専門機関も利用しながら、お子さんのための「次の言動」を考えていきましょう。
対応①大学受験について気安く話題にする

大学受験に失敗した子どもは、「普段なら気にならないような発言」に非常に傷つく可能性があります。
普段どおりの接し方を心がけながらも、お子さんが傷つきそうな話題からは離れてみましょう。
例えば、お子さんが深刻にならないよう、大学受験の失敗を、あえて笑い話などの明るい方向に持っていく感じで話題に出すかもしれません。
ですが、失敗を経験したばかりの子どもにとっては、デリカシーに欠ける発言や無神経な発言に映るかもしれません。
失敗を笑い話にすることは悪いことではありませんが、時期を見計らいましょう。
もっとも、あまりに不自然に大学受験の話題を避けるのも、「腫れ物に触る」対応になってしまいがちなので避けた方がよいです。
また、安易に学歴をあおるテレビ番組も多くあります。
お子さんが自ら観る分にはよいですが、一緒に食卓を囲みながらテレビを観る際には、テレビ番組の選択にも注意が必要です。
対応②受験についてあれこれ言う
大学受験について、前項のように気安くではなく、真剣にならば話題にしていいかというと、一概にそうとは言えません。
大学受験について、親にあれこれ言われることを嫌う子もいます。
親にとっても大きな心配事ではあります。そして、学費を出すのは親かもしれません。ですが、親の方がパニックになったり落ち込んだりしてはいけません。
不安に駆られても、お子さんにはその姿を見せないようにしましょう。
例えば、失敗を恐れるあまり、浪人時の最初から志望校のランクを下げる提案は、お子さんの自尊心を傷つけます。自己肯定感を低下させる可能性があります。
「志望校を変更した方がいいかも…」と思っていても、親から早め・積極的に提案するのではなく、お子さんから相談されたときやお子さんが悩んでいるようなときに、「試しに○○大学も受けてみたら?」のように提案するようにしましょう。
また、不安にかられると、お子さんと他者の比較もやりがちです。
兄弟、お子さんの友人、親の友人の子ども、同年代の有名人などと比較しないようにしましょう。
他人は他人と割り切り、等身大のお子さん自身を見てください。
対応③親が独断で進路を決める
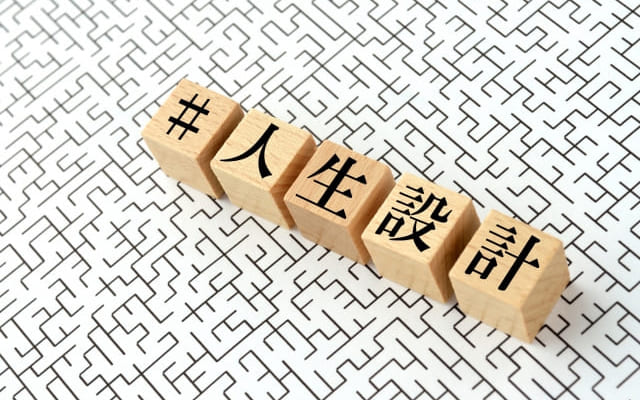
大学受験年齢の子どもは、生活費や学費を親が負担しているとしても、一人の個人です。
親は、お子さんの意見を無視して進路を決めないようにしましょう。
わかりやすい例で言えば、次のようなことを言うのはやめましょう。
- 「大学に落ちたのだから、資格の取れる専門学校に行こう」
- 「来年はもっと偏差値の低い大学を受験しよう」
- 「第二志望の大学に合格しているんだから、第一志望のための浪人はせず、そこに進学しよう」
そもそも浪人して再受験するかどうかについても、親は静観するのがよいでしょう。
もちろん、お子さんに相談を持ちかけられたら、客観的な視点でアドバイスをすることはやぶさかではありません。
いずれにしても、親の主観的な希望は極力伝えず、お子さんの意志を尊重する進路選択をしましょう。
大学受験に失敗後の進路
それでは、大学受験に失敗したあとは、どのような進路があるのでしょうか。
ここでは、一例を紹介します。
お子さんから相談を持ちかけられた際の参考にしていただければ幸いです。
ご本人向けとしては、以下のコラムが参考になるかもしれません。よければ参考にお読みください。
進路①浪人する
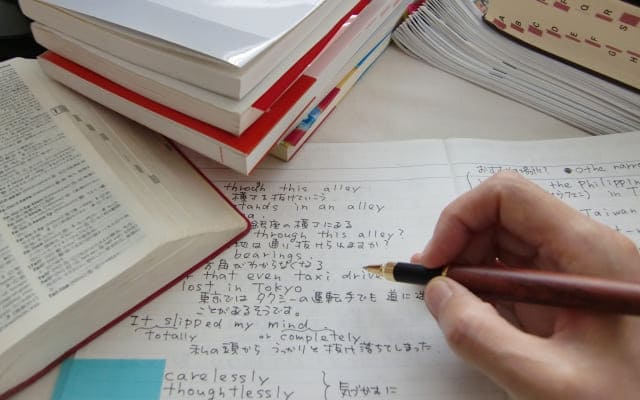
第一志望の大学に入学するために、浪人するパターンです。
浪人生が勉強する環境は、大きく2つに分けられます。
(1)塾・予備校・家庭教師などを利用する
勉強や受験の専門家である、塾・予備校・家庭教師を利用することで、効率的に受験合格に近づきます。
集団指導の塾や予備校では、第一志望合格を目指すという同じ目的を持った生徒が通っているため、よい刺激になります。
完全個別指導の場合や家庭教師の場合は、お子さんの「現在の学力」と「目標に必要な学力」に基づいた指導が受けられます。
どちらにしても、受験を見据えて、「勉強のやり方」から「受験までのロードマップ・ペース」まで指導してくれるところも多いです。
お金はかかりますが、お子さんが勉強の仕方に迷っていたり、一人で勉強を続ける自信がなかったりしそうな場合はオススメです。
(2)自宅や図書館で勉強する
塾などを頼らず、お子さんが自分で勉強を進める方法もあります(いわゆる「宅浪」というものです)。
金銭的な負担が少なく、自分のペースで勉強できます。
現在は、ネットの無料教材なども利用できます。
勉強の方法から時間、計画のすべてを自分で決めたいという人にオススメです。
ただし、「自分の勉強方法が合っているのかわからない」「このペースで間に合うかわからない」といった不安は生じるでしょう。
宅浪の詳細は、以下のコラムご覧ください(本人向けの記事ですが、親御さんが読んでも参考になると思います)。
進路②第一志望以外の大学に進学する
併願校に合格している場合は併願校に、それ以外の場合は3月入試などに合格して大学に進学するパターンです。
どうしても第一志望じゃなきゃ嫌だ!という人以外にはオススメです。
浪人するよりも大学生活を一足早く体験できます。
入学してみると、第一志望へのこだわりが消えたり、想定とは違っても有意義で充実した大学生活を送れる可能性もあります。
なお、合格した大学に通いながら、第一志望合格に向けた受験勉強も続ける「仮面浪人」という進路もあります。
仮面浪人では、途中で気が変わって受験勉強をやめても今の大学に通えます。
ただし、入学金・授業料などは当然発生しますし、大学の課題をこなしながら受験勉強するのが大変なことも事実です。
進路③専門学校に進学する

大学受験の失敗の後に、専門学校に進学するパターンがあります。
専門学校は、一般的には大学と比べて入試が簡単です。また、3月に受験することができるところもたくさんあります。
専門学校では、就職に役立つ資格や専門スキルを身につけることができます。
大学とは違う観点の学びにも興味がある方、専門学校を通じて取得できる資格や就ける職業に興味のある方にはオススメです。
また、国が認めた専門学校を卒業すると、4年制大学への編入学を目指すこともできます(参考:文部科学省「専門士・高度専門士の称号とは」)。
進路④就職する
進学せず、就職するパターンです。
この場合の就職には、「正規雇用」以外にも、アルバイトなどの非正規雇用も含みます。
大学(や専門学校)は、必ず行かなくてはいけない場所ではありません。
大学生になるよりも一足早く働き始めることで、社会人として成長できます。
また、自分でお金を稼ぎ、社会の一員として活動することで、視野が広がったり生活が充実したりすることもあるでしょう。
ただし、「高卒」と「大卒」を比較すると、高卒の方が選択できる職種の幅が狭いことは事実です(給与等の待遇が劣る可能性もあります)。
とは言え、お子さんが働いて楽しく過ごしていれば、わざわざ「大卒と比較して」悩む必要はありません。
その上で、理由はなんであれ、一度就職したお子さんが、いつか「やはり大学に行きたい」と言うかもしれません。
前述の仮面浪人などと同じく、働きながら勉強して大学を目指すことは、もちろん可能です。
仕事と勉強を両立するのは大変かもしれません。ですが、無理な話ではありません。
社会人の大学受験については、以下のコラムをご覧ください(こちらも本人向けですが、親御さんの参考にもなると思います)。
進路⑤留学する

海外留学し、語学力などを身につけるパターンです。
大学に合格していない状態での留学は「語学留学」がメインになるでしょうが、現地の大学に合格して通うというルートもあります。
大学の場合、日本の大学とは入学の時期が異なる国であれば、「次の受験までの1年」を待たずに大学生になれることもあります。
日本とは言葉も価値観も異なる国での生活は、日本の大学進学とは別の観点での「知識」や「経験」を得られます。
海外留学の経験は、何にも代えがたい経験になり、その後の人生に活かせます。
一方で、お金がかかること、苦労もあること、明確な目的意識がないとダラダラ過ごす可能性があることなどから考えて、「誰にでもオススメできる選択肢」ではないことは、事実としてお伝えします。
親自身のための3つのストレスケア
これまでは、「親御さんがお子さんにできるケア」について紹介してきました。
しかし、お子さんに配慮するあまり、親がストレスを溜め込むことは好ましくありません。
それは親自身のためでもありますし、お子さんのためでもあります。
子どもは、親が自分の時間を有意義に過ごしていることを確認できると安心します。
また、楽しそうな時間を過ごす親を見ることで、自分の将来に対して希望が湧くこともあります。
あなたが今、ストレスを感じているようでしたら、ストレスを緩和、解消することを始めましょう。
ここでは、親自身にできるストレスケアの方法を3つお伝えします。
ケア①同じ悩みを抱える人に相談する

あなたと同じように、子どもが大学受験に失敗した経験を持つ友人・知人・親戚がいれば、相談してみましょう。
大学受験に失敗したときにどう思ったか、どういった言動が好ましいかといったことを、体験を踏まえてアドバイスしてくれるかもしれません。
または、いま現在で、ご自身と同じような境遇の友人・知人・親戚と話すこともオススメです。
話をすることで、お互いによい影響を与え合うことができるかもしれません。
一人で(家族だけで)悩んでいると、どうしても行き詰ることが多くなります。
誰かに話すことですっきりしたり、共感をもらえて安心したりすることもストレスの解消につながります。
ケア②子どもと関わらない時間を過ごす
お子さんから離れて、自分一人の時間、友達との時間、夫婦の時間を持つことも有効です。
お子さんから離れて有意義な時間を過ごすことで、ストレスが緩和されます。
趣味の活動などもあるでしょうし、「具体的な何か」をしないリラックスできる環境に身を置く場合もあるでしょう。
特に後者の例としては、アロマ、マッサージ、入浴、睡眠など、自分なりのリラックスできる環境を探してみましょう。
特に睡眠が足りていないと、ストレスがたまりやすくなるので注意です。
ケア③専門機関を利用する

専門機関を利用することもオススメします。
ここで言う専門機関とは、子ども(や親である自分)のことを相談できる機関のことです。
少しハードルが高いと感じるかもしれません。ですが、家庭内だけで悩みを抱え込んでいると、ストレスがたまる悪循環に陥ることがあります。
専門機関に相談すると、「具体的な悩みに対する具体的な解決策」が見つかったり、漠然とした不安が軽くなったり、話をするだけでストレスが緩和されたりします。
一般的なカウンセリングは、民間企業や病院等の医療機関で受け付けています。
また、お住まいの自治体によっては相談窓口を設けています。
インターネットで、「○○市 相談」などと検索すると候補が見つかりますので、ご自身に向いていそうなところに問い合わせてみましょう。
進学に関する家計の心配に対する支援なども、自治体で紹介してくれることがあります。
また、民間の塾・予備校・家庭教師なども、大学受験の失敗・浪人・今後の方針についての相談を受け付けているところがあります(私たちキズキ共育塾でも、無料相談を受け付けています)。
勉強や受験の専門家からは、カウンセリングとはまた異なる視点で、お子さんへの接し方や進路について、具体的なアドバイスがもらえると思います。
まとめ〜あなたのストレスケアも大切にしましょう〜

大学受験に失敗したお子さんへの、親としてのしてほしい対応・やめた方がよい対応、親自身のためのケアをご紹介してきました。
お子さんを気づかいつつも、あなたのストレスケアも大切にしましょう。
何度も繰り返しとなりますが、友人や専門機関をはじめとした第三者に相談することをためらわないでください。
この記事が、あなたのお子さんの「次の一歩」と、あなた自身のお悩み解決に向けた一助となったなら幸いです。
さて、私たちキズキ共育塾は、お悩みを抱える方々のための個別指導塾です。
生徒さんには、大学受験に失敗をきっかけに通い始めた方も大勢いらっしゃいます。
無料相談も承っています。ご相談いただければ、「あなたのお子さん」のための具体的なお話ができると思います。
キズキ共育塾をご覧の上、少しでも気になるようでしたらお気軽にご相談ください。ご相談は無料です。また、親御さんだけ・お子さんだけでのご相談も承っています。
Q&A よくある質問