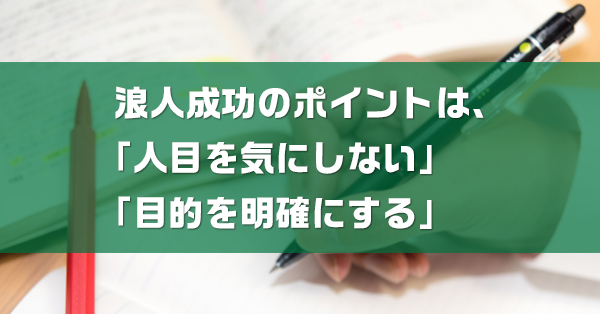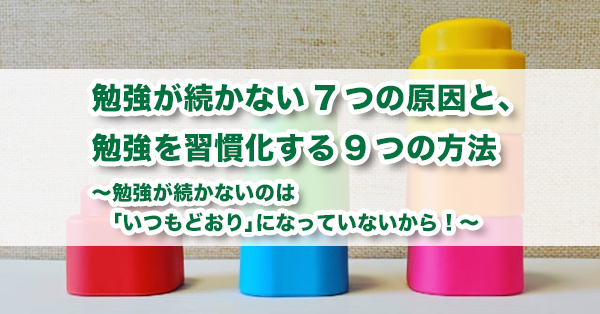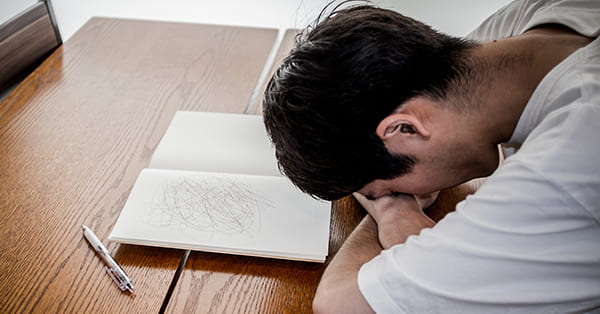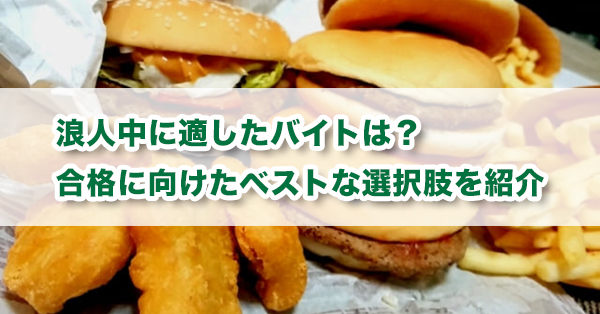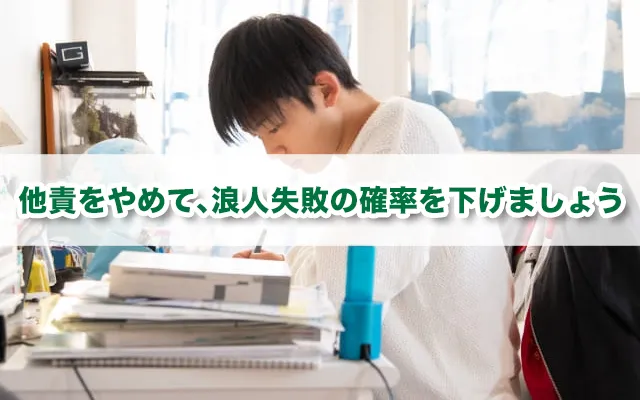宅浪とは? メリットや成功させる勉強方法を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたは今、宅浪するかどうかを迷っているのではないでしょうか?
また、ネットで宅浪は成功しない、宅浪はやめとけという情報を見て不安になっているかもしれません。
このコラムでは、宅浪の概要や成功率、メリットやデメリット・注意点、宅浪失敗のよくあるパターン、宅浪に向いてる人・向いてない人、成功させるための勉強方法、モチベーションを保つ方法について解説します。
たしかに、ネット上では、宅浪はやめておけ、成功しないという意見も多いです。
しかし、宅浪でもきちんと勉強・生活すれば問題ありません。
いま宅浪をしている、または宅浪を検討しているあなたの参考になれば幸いです。
私たちキズキ共育塾は、宅浪から大学受験を成功させたい人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
宅浪とは?
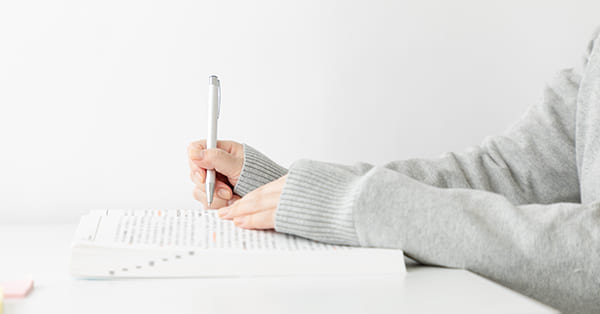
宅浪とは、自宅浪人の略であり、高校卒業後に予備校・学習塾へ通わずに在宅で勉強して大学合格を目指すこと、または目指す人のことです。
宅浪は苦手科目に時間を使ったり、得意科目をさらに伸ばしたりなど、自分のペースで勉強を進められます。
逆に、予備校・学習塾に通う浪人よりも、計画性や規則正しい生活習慣が求められるのも事実です。強い意志を持ち、どうしても行きたい大学がある人に宅浪を選ぶ傾向が見られます。
どのような状況にせよ、宅浪を検討する場合は、そのメリットとデメリットを把握したうえで考える必要があります。
宅浪の成功率

宅浪の成功率について公式なデータはありませんが、一般的には10%以下と言われています。
じゅけラボ予備校が2023年に実施した調査によると、浪人経験者のうち、浪人1年目では約30%しか第一志望の大学へ行けていません。(参考:じゅけラボ予備校「【調査レポート】浪人の成功率。50%の浪人生が最終的に第一志望大学に合格!」)
この30%のうち、多く見積もって半分が宅浪だったとしても、合格率は15%になるので、宅浪の合格率が10%前後というのは間違っていないかもしれません。
予備校・学習塾のように勉強時間が決められておらず、自分一人で勉強計画やモチベーション管理をしなければいけない事を考えると、宅浪の合格率は低いと思っておいていいでしょう。
宅浪のメリット〜宅浪は楽しいって本当?〜

宅浪のメリットとしては、以下が考えられます。
- 予備校・学習塾・家庭教師などの費用がかからない
- 勉強する時間・場所・教材・方法などを、自分で自由に決められる
- 予備校・学習塾の雰囲気が苦手な人は、その空気を味わわなくて済む
以上のメリットを活かせれば、宅浪を成功させられる確率が上がります。
宅浪とは、予備校・学習塾代が払えない人だけがするものだと思う人もいるかもしれません。
しかし、それだけではないのです。
宅浪は好きな場所で一人静かに勉強できますし、試したいと思った勉強方法もすぐに実行できます。
そのため、自分で計画・スケジュールを立てたり実行したりして、試行錯誤することが好きな人からすると、楽しいと感じられるかもしれません。
宅浪のデメリット・注意点〜宅浪はやめとけ・成功しないと言われる理由〜

宅浪のデメリット・注意点としては、以下が考えられます。
- 勉強方法や勉強計画・スケジュールを自分一人で考えなくてはならない
- 家族以外に話す人がおらず、孤独になる
- 誘惑に負けて遊んでも、止めてくれる人がいない
宅浪成功のためには、以上のデメリット・注意点を乗り越える必要があります。
もちろん、このデメリット・注意点を乗り越えられるのであれば、宅浪への不安を感じる必要はないでしょう。
ですが、デメリット・注意点をメリットよりも大きいと感じる人もいるはずです。一人になると、弱くなったり自制が効かなくなったりすることも少なくありません。
こういったところに、宅浪は成功しない・やめとけと言われる所以があるのかもしれません。
宅浪を成功させるには、デメリット・注意点を理解し、失敗のよくあるパターンを把握しておきましょう。
宅浪失敗のよくあるパターン
この章では、宅浪を失敗するよくあるパターンを紹介します。
宅浪を検討・実施しているあなたを不安にさせるつもりは決してありません。
ですが、珍しいパターンの失敗ではないということは事実としてあらかじめお伝えします。同じ失敗をしないように、把握しておいてください。
前向きでフルスロットルな初期

浪人が決まった3月は、とても前向きです。
この時期の浪人生は、時間が豊富にあると思っています。
「せっかく浪人するのだから、〇〇大学を目指そう!」と、希望に胸を膨らませます。
そして、1日の勉強スケジュールを立てます。
ずっと家にいるわけだし、1日10時間勉強しようと、はじめからフルスロットル。
数学も英語も他の教科も、めいっぱいスケジュールに詰め込みます。
はじめはがんばって勉強します。
しかし、テキストが後半に進むにつれて内容が難しくなると、予定どおりいかないことに気づきます。
「ちょっと息抜きするか…」。こうして、すぐに休憩をとる癖がつくのです。
休憩自体は悪いことではありません。ですが、自分の部屋にも街にも、たくさんの誘惑があります。
ちょっとの休憩のつもりが、スマホをいじってSNSをぼーっと眺めたり、マンガを読み始めたり、ショッピングモールに出かけたり…、そして気づいたら何時間も経っていた。
そんな生活が習慣化します。
それでも4月、5月くらいだと、まだ受験当日まで余裕があると思うのです。
あわてだす夏
しかし、そんな状態が8月まで続くと、慌てることになります。
現役受験生や予備校・学習塾に通う浪人生が成績を伸ばし始める時期だからです。
自分は勉強していないので、そのことを強烈に意識します。
そして、ようやく勉強計画・学習スケジュールを見直します。
ところが勉強方法がわからないので、また無理な目標を立てます。
適切な目標設定も…1日にこなすべき量も…科目ごとのバランスも…何も具体的に決められない。決めても達成する体力がない。そんな状況におちいるのです。
そして受験当日

あっという間に時間が経ち…その年の受験も不合格に。
こういう話は、宅浪あるあるとしてよく語られます。
では、具体的にどうすれば宅浪を成功できるのでしょうか?
効果的な勉強やモチベーション持続のためには、どのようなことに気をつければいいのでしょうか?
浪人生活については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
宅浪に向いてる人・向いてない人
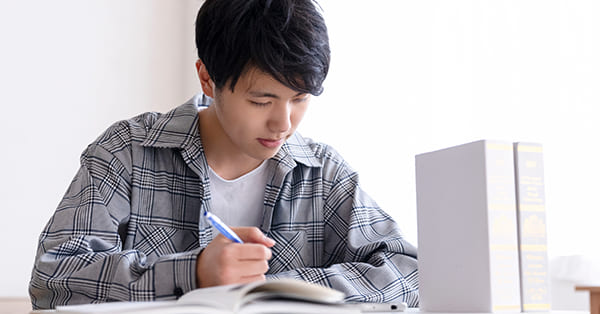
宅浪には、向いてる人と向いてない人がいます。
宅浪の特徴から考えると、宅浪に向いてる人・向いてない人は以下のように分けられます。
宅浪に向いてる人
- 一人で計画的に進めたい
- メリハリをつけて勉強したい
- 規則正しい生活を送れる
- 受験について相談できる人がいる
宅浪に向いてない人
- 自分で計画を立てるのが苦手
- 友達と一緒に頑張りたい
- 生活リズムが乱れがち
- 受験について相談できる人がいない
以上の条件に当てはまるから宅浪すべきである、当てはまらないから宅浪は諦めた方がいいというものではありません。しかし、宅浪するかどうかは人生に関わる決断と言っても過言ではありません。
少しでも不安があるなら、宅浪を経験した人に話を聞いたり、学校の先生や予備校・学習塾に話を聞きに行ったりするのがオススメです。
宅浪を成功させる4つの勉強方法
予備校・学習塾のメリットを宅浪に取り入れれば、失敗を回避しやすくなります。
一般に、宅浪になくて予備校・学習塾にあるものとして、以下のような例が挙げられます。
- 一緒に勉強する仲間・ライバル
- プロ講師の授業・添削指導
- プロ講師によるスケジュール管理
- 質問しに行ける体制
- 授業の予習・小テストなどの短期目標
- アウトプット・演習の機会
以上を踏まえて、この章では、宅浪を成功させる勉強方法について解説します。
方法①勉強のルールをつくる

はじめに、勉強のルールをつくります。
具体的には、1科目の勉強は、1日に1回・60分だけやる、テキストを1日10ページ進める、などです。
しかし、この方法には、以下のようにいくつもの弊害が考えられます。
- テキストの途中でつまずき、目標達成できないことがある
- 時間に追われる感覚がないので、ダラダラしてしまう
- メリハリがつけられず、ストレスがたまる
時間を基準に目標を設定すれば、目標を達成できないことはありません。
とはいえ、のんびりしていると60分で1ページしか進まないことがあります。
しかし、実際やってみると、テキパキ勉強するスイッチが入ります。
「この時間内に1章は全部終わらせてしまおう!」という意識で取り組むと、試験本番のように時間内に間に合わせる勉強が自然と身につきます。
スケジュールを立てる上でも、この方法は有効です。
浪人生は1日10時間勉強しなければならないという声もよく見受けられますが、漠然と10時間という数字を掲げても意味がありません。
時間を区切って勉強していると当然ですが、いつも本番に間に合わないという危機感を抱きます。
すると初めて、この科目は1日2時間勉強しないとだめだということに気づきます。
そう気づいたら、1日に60分の勉強を2回に増やせばいいのです。
全科目をこのように調整すると、自然と1日8時間くらいは勉強するようになります。
例として、宅浪開始直後3月〜4月の1日の勉強時間を紹介します。
午前(8~12時)
- 数学3:解法アウトプット60分
- 英語:長文演習60分
- 化学:演習60分
午後(14~19時)
- 数学3:演習インプット60分
- 物理:演習60分
- 数学・科学の歴史に関する読書:30分×2(昼と夜に分散)
- 英語のWikipediaを読む:30分
夕食以後(21~23時)
- 数学・科学の歴史に関する読書:60分
- 英語のWikipediaを読む:30分
宅浪開始時に長時間勉強する習慣がない場合は、1回の時間を少なめにしたり、1日の科目数を少なくしたりと、少しずつ始めて次第に勉強時間を増やしていくことをオススメします。
またこの方法は、メリハリをつけるための訓練にもなります。
60分経ったら最低15分は休憩して、勉強しない時間をつくるのです。
このようにルールをつくっておけば、その15分は自由に使うことができます。
そして、その15分で休憩やリフレッシュをすれば、ストレスをためすぎず勉強が長続きします。
方法②インプットとアウトプットのバランスをとる
予備校・学習塾のカリキュラムは、インプットとアウトプットのバランスがとりやすいです。
インプットとは、解法、公式、文法、単語、年号など、新しい知識を得ることです。
アウトプットとは、復習や演習などで、インプットした知識を実際に使うことです。
インプットとアウトプットをバランスよく行うことで、知識は定着していきます。
予備校・学習塾では授業で知識を入れ、家では復習や演習をすれば、インプット・アウトプットをバランスよく取り入れられますよね。
宅浪では、テキストを進めるインプットに夢中になり、復習や演習というアウトプットがおろそかになる人が多いのです。
アウトプットの時間をきちんと勉強に取り入れましょう。
具体的には、次のような方法があります。
アウトプットの方法
- 演習の時間をつくる
- 中学生に教えるつもりで脳内授業する
- 白紙に覚えたことを書きまくる
- 模試や過去問で実力を確認する
私が実際に行った例を2つ紹介します。
数学のように演習が大切な科目の場合、以下のように、勉強時間をインプットとアウトプットにわけると効率がよいです。
- 解法を覚える勉強60分
- 演習する時間60分
政治経済のように暗記が重要となる科目の場合、以下の手順で脳内で授業を行います。
- 頭の中で、自分を先生役と生徒役にわける
- 先生役に起こった出来事を説明させる
- 生徒役に「なんで?」などと質問させる
- その質問に回答して授業・ストーリーを進める
これによって、知識を物語として整理することができます。
方法③模試を受ける
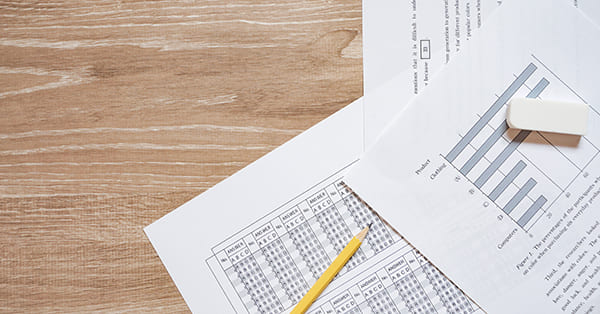
宅浪している人は、模試を受けることがとても大切です。
予備校・学習塾に通っていれば、受験を見据えて授業が進んでいくため、予習・復習も含めてスケジュールに従っていれば、自然と目標に近づいていきます。
しかし、宅浪の勉強はどうしてもマイペースになるため、停滞する恐れがあります。
マイペースを打破するために、模試はいい刺激になるのです。
自分の力がごまかされずに数値化されるため、自分の勉強を評価するのには最適です。
頻繁に受けた方が実力やペースを小刻みに確認できるのですが、時間もお金も必要になります。そのため、現実的に可能な範囲で受けましょう。
方法④解説が豊富なテキストを使用する
宅浪では、数学の証明問題や英作文などの添削指導を受けられないという側面があります。
数学にせよ、英語にせよ、添削指導を受けられないと不安ですよね。
そのため、宅浪生が使うテキストは、添削指導の代わりとなる模範解答に多くのページを割いているものをオススメします。
その模範解答を一言一句まちがえずに真似していきます。
そして、「この一文はなぜ必要なのだろう?」と考えながら勉強してみてください。そうすることで、その問題だけでなく類似の問題もより深く理解できるようになるのです。
その他に、インターネットにも高校科目をわかりやすく解説してくれるサイトがあります。
浪人成功のためのポイントについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
宅浪で受験へのモチベーションを保つための5つの方法
予備校・学習塾に通っている浪人生は、一緒に勉強するライバルがいます。
ライバルがいると、以下のように、刺激をモチベーションとして勉強を続けられます。
- さぼるとライバルに後れを取ってしまう
- 一緒に大学に受かりたい
しかし宅浪は孤独です。
この章では、そんな孤独な生活を乗り切る、宅浪で受験へのモチベーションを保つための方法について解説します。
方法①規則正しい生活をする

宅浪に限らず浪人生全員に言えることですが、受験勉強において規則正しい生活はとても大切です。
特に睡眠は乱れやすいので注意しましょう。
受験の世界には、四当五落という、睡眠時間が4時間の人は合格し、5時間の人は落ちるという意味の言葉があったように、安易に睡眠を削る発想がありました。
しかし、睡眠不足では、勉強の質は当然落ちます。
1日、2日であれば根性で何とかなるかもしれませんが、受験は長期戦です。
ベストコンディションを常に保つためにも、睡眠をおろそかにしてはいけません。
方法②散歩をする
勉強に息抜きは大切です。
その中でも、散歩は最も手軽でメリットが多い方法と言えます。
宅浪すると、生活が不規則になり、不健康になりやすいです。
勉強に集中することは、とても大事です。しかし、かといって外出しない・運動しないといった生活になると、体内時計が狂ったり、体がなまったりします。
散歩して太陽光を浴びるだけでも、体が軽くなり気持ちも前向きになります。
また、歩くと頭が整理されます。勉強が煮詰まらないときは、散歩してリフレッシュしてみてください。
方法③遊びの時間をつくる

宅浪中だからといって、禁欲的になりすぎるのはよくありません。
きちんと、趣味のための時間を確保しましょう。
そのためには、勉強時間をきっちり定め、勉強は勉強でしっかり行うことが重要です。
- 図書館では勉強し、家では遊ぶ
- 1日8時間勉強して、それ以外の時間は遊ぶ
このように、メリハリをつけることをオススメします。
ただし、中毒性の高い趣味はオススメできません。
例えば、スマホゲームやSNSなどはなるべくやめた方がいいでしょう。
ほどほどのところでやめられる趣味で息抜きするのがオススメです。
方法④読書する時間をつくる
読書をする時間をつくることもオススメです。
受験勉強はやらされているという意識がどうしても生まれるものです。その意識があると、勉強する楽しさは感じにくいと思います。
読書は、自分の意志で自由に読むものを決められるため、受験勉強の窮屈さを一時的に忘れられるでしょう。
また、国語の勉強としても役立ちます。
特に、長い文章を読むことに慣れていない人は、読書習慣を身につけるだけでも文章を読むことへの抵抗感が大きく減らせるでしょう。
1日20分でも構いません。読書の時間をつくることをオススメします。
方法⑤日記を書く

宅浪中は、日記を書くようにしましょう。
その日の出来事、気分、勉強したことなどを素直に書いてみてください。
文章にすると気持ちがすっきりしますし、何を勉強したのか見直すこともできます。
また、勉強する意味を見失いそうになったとき、勉強のモチベーションが下がったとき、成績が思うように伸びないときは、なぜ自分が大学に入りたいのかを日記に書くとよいです。
書いているうちに初心を思い出し、またやる気が出てくるからです。
宅浪では、モチベーションが保ちづらいことはもちろん、毎日勉強を続けることが難しいと感じる人もいると思います。
勉強を習慣化する方法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
浪人するなら宅浪か予備校・学習塾かどっちがいい?

基本的に、予備校・学習塾に通いながら大学合格を目指すのがオススメです。
なぜなら、予備校・学習塾であれば受験情報もゲットできる上、予備校・学習塾が持つ過去のノウハウを活かして効率的に勉強できるからです。
もし、近くに予備校・学習塾がない場合でも、オンラインで授業を受けられるケースがあるので調べてみてください。
ただし、経済的に厳しいなど、予備校・学習塾に通えない理由があるなら、このコラムで紹介した内容を押さえつつ、宅浪を成功させられるように頑張ってみましょう。
いずれにせよ、勉強のアドバイスをくれたり、目標に合ったカリキュラムを提案してくれたりするので、一度予備校・学習塾に話を聞きに行ってみてください。
宅浪するかどうかを決めるのは、それからでも遅くありません。後悔しないように、たくさん情報を集めてみましょう。
まとめ〜あなたに合った方法で宅浪を成功させよう〜

宅浪は成功しないという声もありますが、適切な勉強と生活を続けることができれば、成功します。
最近はインターネットの教材も増えています。そのため、勉強の手段・方法という観点で考えると、昔よりも宅浪は成功しやすいのではないでしょうか。
しかし、SNSや動画サイトなど、誘惑も昔より増えていることには注意が必要です。
しっかり勉強し、生活リズムを整えることを意識し、宅浪を成功させましょう。
さて、宅浪を続けるうちに、「やっぱり無理かも…」「このままでは難しいかな…」などと思うことがあるかもしれません。
そんな悩みや不安を抱えたままでは、勉強に集中できませんし、生活も乱れがちになります。
そんなときは、思い切って宅浪をやめる、というのも一つの手段です。
あなたにあった予備校や学習塾、家庭教師がないか、探してみましょう。
もしかすると、宅浪すると決めたときとは状況などが変わり、向いてるところが見つかるかもしれません。
私たちキズキ共育塾は、不登校・引きこもり・浪人などのお悩みを抱える人のための個別指導塾です。
ご相談いただければ、あなたのための勉強法・生活スタイルを一緒に考えることができます。ご相談は無料です。少しでも気になるようでしたら、お気軽にお問い合わせください。
Q&A よくある質問