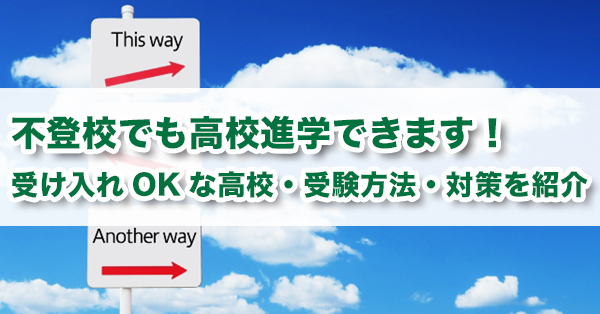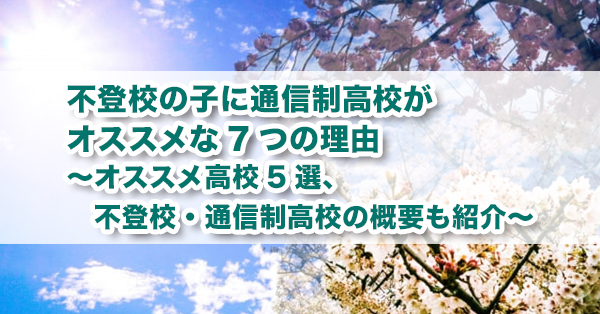不登校とひきこもりの違いとは? 子どもへの接し方を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
自分の子どもが不登校やひきこもりの状態になったとき、あなたならどう対応しますか?
無理に原因を探したり、強引に外に連れ出したりするのは逆効果です。
まずはお子さんを受け入れ、寄り添いながら、長い目でサポートすることが必要になります。
とはいえ、お子さんの状況や心理がわからずに不安になるのは、親としては普通のことです。
このコラムでは、不登校やひきこもりの定義から、不登校やひきこもりの原因、子どもの心理、不登校やひきこもりの状態にある子どもへの対応・接し方などについて解説します。
あわせて、不登校かつひきこもりの経験をした人の体験談を紹介します。
不登校かつひきこもりの状態にあるお子さん自身にも、ぜひお役立ていただければ幸いです。
共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの
アドバイス
ご家族や親御さんだけで抱え込まず、専門家を利用しましょう
不登校や引きこもりの心理や対処法は、あまり知られていません。
このコラムに書かれている内容を読むと、「甘やかしすぎではないか」と思うかもしれません。ですが、これらの対処法は、不登校や引きこもりを経験した親子が、血と涙を流してたどり着いた結論です。
生半可な思いで書かれているものではありません。とはいえ、疑問を感じる部分もあると思います。
家庭内や親御さん一人だけで抱え込まずに、伴走してくれる専門家や支援団体などを利用することで、「実際のあなた(のお子さん)のためにできること」が見えてきます。
私たちキズキ共育塾は、不登校やひきこもり状態にある人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
不登校とひきこもりの違い
不登校やひきこもりと聞くと、「学校へ行っていない」「家から出られない」と、漠然としたイメージを持つかもしれません。
しかし、不登校やひきこもり状態の人も、ときには学校へ行ったり、外出したりしていることは珍しくありません。また、不登校とひきこもりはそれぞれ定義が異なります。
この章では、不登校とひきこもりそれぞれの定義について解説します。
不登校とひきこもりの定義を簡単にまとめると、以下のとおりです。
- 不登校:病気や経済的な理由以外の理由で年間30日以上の欠席をしている状態
- ひきこもり:6か月以上継続して社会的参加のない状態
- 不登校かつひきこもり:病気や経済的な理由以外の理由で年間30日以上の欠席があり、6か月以上継続して社会的参加のない状態
文部科学省による不登校の定義

不登校という状態は、文部科学省によって以下のように定義されています。
何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者をのぞいたもの
(参考:文部科学省「不登校の現状に関する認識」)
年間30日以上ということは、単純に計算すると、特定の要因で月に2〜3日程度休む人は不登校と判断されることになります。不登校は、それほど特異な状態ではないことがわかりますね。
不登校の詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
厚生労働省によるひきこもりの定義
ひきこもりという状態は、厚生労働省によって以下のように定義されています。
ひきこもりとは、「様々な要因の結果として社会的参加 (義務教育を含む就学, 非常勤職を含む就労, 家庭外での交遊など) を回避し、原則的には6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい) を指す現象概念である。」
(参考:厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」)
他者と関わらない、一人だけの散歩やランニングなどをしている人も、ひきこもり状態とされるのです。
ひきこもりの詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
不登校またはひきこもりの状態にある人の割合

不登校やひきこもりの状態にある人は、どのくらいいるのでしょうか?
ひきこもりの子ども・若者は、増加傾向にあることが指摘されています。
内閣府によると、15歳~39歳では約2%が、40歳〜69歳では約3%が広義のひきこもりであるとされました。(参考:内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査 (令和4年度)」)
これは15歳〜39歳では約50人に1人、40歳〜69歳では約30〜40人に1人の割合です。
また、文部科学省によると、小・中学校の不登校児童生徒数は29万9048人と、過去最多となりました。(参考:文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」)
不登校やひきこもりの状態にある人が増えた背景には、コロナ禍による社会的要因も指摘されています。
不登校・ひきこもりの3つの原因
厚生労働省が発信する情報プラットホーム「ひきこもりVOICE STATION」では、ひきこもりの主な原因として、⼈間関係や病気、受験の失敗などを挙げています。(厚生労働省「ひきこもりVOICE STATION」)
また、文部科学省の調査では、不登校になった原因は大きく「学校」「家庭」「本人」の3つにわけられるとされています。
この章では、それらの資料を参考に、不登校・ひきこもりの原因について解説します。(参考:内閣府「平成28年度若者の生活に関する調査報告書」、文部科学部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」)
ここで紹介する原因はあくまで一般的な例です。
状況を理解・検討するための参考としてご覧ください。
原因①精神的な要因

不登校やひきこもりは、精神的な問題が要因となることもあります。「自分に自信がない」「周囲の人たちより劣っている」といった感情から、登校や外出を苦痛に感じるようになるケースです。
また、精神的な病気や障害が原因となっているケースもあります。例えば、ひきこもりに関連する病気や障害として、以下が挙げられます。
- 統合失調症
- 不安障害
- 双極性障害
病気や障害がひきこもりの原因となっている場合は、自分の力だけでは改善できません。病院を受診し、きちんと治療を受けることが大切です。
原因②人間関係の悪化・いじめ
人間関係の悪化やいじめも、不登校やひきこもりの原因のひとつです。
文部科学部科学省の調査では、「学校に係る要因」として、以下の項目が挙げられました。
- いじめ
- いじめを除く友人関係をめぐる問題
- 教職員との関係をめぐる問題
- 学業の不振
- 進路に係る不安
- クラブ活動、部活動等への不適応
- 学校のきまり等をめぐる問題
- 入学、転編入学、進級時の不適応
このうち「いじめを除く友人関係をめぐる問題」が全体の約9.2%ともっとも多く、次いで「学業の不振」が約4.9%、「入学、転編入学、進級時の不適応」が約3.1%となるなど、人間関係に関わる要因が上位を占めています。
また、ひきこもりの原因でも、人間関係は主な原因のひとつに数えられています。
原因③家庭の悩み

不登校やひきこもりでは、「家庭に係る状況」が要因となることもあります。
文部科学省の調査において、不登校の要因とされた家庭の状況は、以下のものです。
- 家庭の生活環境の急激な変化
- 親子の関わり方
- 家庭内の不和
このうち一番多いのは「親子の関わり方」で全体の約7.4%。次いで「家庭の生活環境の急激な変化」が約2.6%、「家庭内の不和」が約1.6%となりました。
またひきこもりになった子どもたちは、そうでない子どもと比べ、家族や友人に「悩みを相談できる」「本音を話せる」と答えた割合が低いことも明らかになりました。
一方で、どのような家庭でも子どもがひきこもりになる可能性はあると考えられています。
親御さんは「親のせいだ」と過剰に自分を責めることはせず、子どもの状態を冷静に受け止めてあげてください。
不登校やひきこもりの状態にある子どもの5つの心理
不登校やひきこもりの状態にある子どもは、どんなことを考えているのでしょうか?
この章では、ひきこもり状態だった人の経験などをもとに、不登校やひきこもりの状態にある子どもの心理について解説します。(参考:磯部潮『不登校・ひきこもりの心がわかる本』)
心理①自分に自信が持てない

まだ若いお子さんは、さまざまな社会体験を積んできた大人と比べると、人格と個性が安定せず、自分に自信を持ちづらい状態です。
この時期は学校に通い、同級生や先生と交流することで、人格形成が進みます。
しかし学校生活の中でのつまずきや、成績の比較などによって自信を失い、不登校やひきこもりになることは珍しくありません。
自分に自信が持てずに自暴自棄となり、「自分は何をやってもダメだ」という絶望感におそわれる子どももいるようです。
心理②人間関係全般が怖い
現代は、コミュニケーション力を重視する風潮が強い時代です。
学校生活ではクラスや部活などの人間関係で、プレッシャーを感じる場面が増えています。
特に、もともと周囲との雑談が苦手だったり、内向的な性格だったりする子どもの場合、より強く負担を抱えることになります。
こうしたプレッシャーが学校での人間関係のみに収まれば、不登校になったとしても、ひきこもりになることは少ないでしょう。
しかし人間関係の全体で強いプレッシャーを抱えた状態では、「人と会うことが怖い」と感じ、社会的参加を回避するようになるのです。
不登校やひきこもりの状態にある子どもの多くは、こうした心理状態に陥っています。
心理③学校や家族に反発したい

不登校やひきこもりの子どもは、学校の規則・制度に息苦しさを感じ、反発したいと思っていることがあります。
また、家族に対する不満やストレスが原因となって、不登校やひきこもりになるケースもあります。
例えば、子どもが「両親が自分のことを気に掛けていない」と感じ、親の興味を引いたり、困らせたりするために、学校へ行かない選択をしていることもあるようです。
こうした心理状態の不登校やひきこもりの状態にある子どもは、その子なりの不満やストレスを溜め込んだまま、主張を控えていることがあります。機会を見て、きちんと話を聞くことが大切です。
心理④将来に漠然とした不安がある
まだ若く可能性があるとはいえ、すべての子どもがはっきりした夢や目標を持っているわけではありません。
以下のような疑問から、将来に対して漠然とした不安を抱く子どもがいるのです。
- この勉強が将来、何の役に立つんだろう?
- 学校を卒業するまでに、やりたいことが見つかるのかな?
- 将来どうやって生活していけばいいんだろう?
文部科学省の調査によると、不登校の要因として「『不安』の傾向がある」と分類される児童の割合は、小・中学校で約33.3%、高校で約23.3%と、高い割合を示しています。(参考:文部科学省「平成30年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」)
こうした「将来に対する漠然とした不安」が、学校へ通うことをやめたり、部屋に引きこもったりする原因になると考えられるのです。
心理⑤原因がわからずに混乱している

不登校の状態にある子どもは、実は自分自身でも「原因がわからない」と悩んでいる可能性があります。不登校のはじまりが「何となく学校へ行きたくない」という、漠然とした感情だったという子どもは少なくないのです。
中には、その漠然とした感情がなぜ起こるのかがわからず、原因探しに集中して、そのまま考え込む子どももいます。
しかし、不登校やひきこもりには、明確に「これだ!」と言える原因がなく、ほとんどの場合で原因を特定できません。
結果として、原因がわからずに混乱している状態のまま、不登校やひきこもりが継続するケースがあります。
また、そうした原因探しが、不登校やひきこもりの解決に直結するとも限りません。
例えば、不登校になった言葉について相手が謝罪すれば、必ず登校を再開できるわけではないのです。
そもそものトラウマを取り除けていなければ、登校できない状態が続くこともあります。
原因を探して謝罪などの解決の場を設けることよりも、子どもの心をケアしたり、転校して環境を変えたりすることで、あっさり登校できるようになることもあるのです。
なお、不登校の原因については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
不登校やひきこもりの状態にある子どもへの接し方と対応5選
この章では、不登校やひきこもりの状態にあるお子さんがいる親御さんに向けて、子どもへの接し方や対応法について解説します。
「我が子にどう接していいかわからない」「助けてあげたいけれど、なにをすればいいのかわからない」と悩んだときには、ぜひ参考にしてください。
対応①感情的にならずに見守る

1つ目の対応は、「感情的にならずに見守る」ことです。
不登校やひきこもりの状態でいる間、家で漫画を読んだり、ゲームをしたりするお子さんは多いと思います。
その姿が、親御さんの目から見て、怠けているように見えることもあるでしょう。
そんなときは「そんな暇があるなら学校に行けるだろう」と感情的に叱りたくなるかもしれません。しかし、そのように厳しく接することで、お子さんの気持ちはよけいにふさぎ込み、解決が遠ざかる可能性があります。
特に強引に登校させたり、外出させたりすることは、状態を悪化させることにつながります。
以下のように考え、できるだけ気長に接して、お子さんを見守ることが大切です。
- この子にとって必要な充電期間だ
- 気晴らしをすることも大切だ
ただ、気長に見守ることを意識していても、その間に大きな焦りに襲われて、不安やストレスを感じる親御さんもいるかもしれません。
その場合は、親御さん自身のストレスを意識的に発散・リフレッシュすることが大切です。
不登校のお子さんがいる親御さんが抱えやすいストレスへの対処法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
また、支援機関などに相談することで、不安やストレスが大きく緩和されることがあります。
親御さんだけで悩みを抱え込まず、積極的に支援機関を利用してみてください。
対応②意見を尊重する
2つ目の対応は、「意見を尊重する」ことです。
これは、お子さんが落ちつきを取り戻して、自発的に会話をするようになるなど、心理状態が安定した時期に意識してほしいことです。
お子さんが不登校やひきこもりの状態になると、親御さんは混乱し、アドバイスのつもりで説教することがあるかもしれません。激励するつもりで「不登校は甘え」と言ったり、原因となったいじめの犯人などを捜したりしたくなることもあるでしょう。
しかしまずは、お子さんの話をしっかり聞き、意見を受け入れてあげてください。
不登校やひきこもりの子どもは、「もしかすると自分は甘えているだけかも…」という不安を抱えながら、勇気を持って親御さんに相談しています。
頭ごなしにお子さんの考え方を否定したり、もっとこうすべきだと一方的なアドバイスを投げかけたりすると、お子さんは自信を失い、解決までの期間がさらに長くなる可能性があるのです。
お子さんが相談を持ち掛けてきたときには、まずは受け止めて、相手の意見を尊重するように意識してみてください。
対応③生活リズムの乱れに注意する

不登校やひきこもりの場合、決まった時間に寝起きして食事を取るなどの習慣が失われがちです。
そのため、昼夜が逆転するなど、生活のリズムに変化が起こることも少なくありません。
登校を再開できても、生活リズムが乱れたままでは、眠気から来るストレスが原因となってお子さんが心身に不調を招くこともあります。
中には、不登校やひきこもりの原因になった精神的なショックは癒えても、生活リズムが元に戻らないために、不登校やひきこもりの状況が継続しているケースもあるのです。
不登校の子どもの昼夜逆転については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
対応④支援機関に相談する
精神的な病気や障害がある場合に限らず、専門家や支援機関に相談することは大切です。
まずは身近な相談先として、担任の先生やスクールカウンセラーが挙げられます。あわせて、国や自治体が設置している相談窓口など、支援機関にも相談しましょう。
支援機関には、不登校やひきこもりの解決に向けての知見を持った専門家が在籍しています。
お子さんの不登校やひきこもりの要因に応じた、適切なアドバイスを得られることも多いため、積極的に活用されることをオススメします。
代表的な支援機関は、以下のとおりです。
- 児童相談所、児童相談センター(18歳未満)
- ひきこもり地域支援センター
- 発達障害支援センター
- 教育センター
各自治体のWebサイトに詳細が記載されています。
「教育センター 〇〇(市区町村名)」というように検索してください。
お子さんの状況に適した支援機関がわからない場合は、お住いの地域の役所の総合窓口や代表電話でも確認できます。
また、民間の支援機関やフリースクール、私たちキズキ共育塾のような不登校の支援を行っている学習塾に相談するのも、有効な手段のひとつです。
不登校やひきこもりの解決のためのサポートが得られるだけでなく、親御さんのストレスを軽減するきっかけにもなるはずです。
対応⑤親御さん自身が元気な姿を見せる

5つ目の対応は、「親御さん自身が元気な姿を見せる」ことです。
「自分のせいで、親が思い悩んでいる…」と、不登校やひきこもりの状況に罪悪感を覚えるお子さんもいます。
また、親御さんが不安や焦りを言葉として出さなくても、お子さんにその心情が伝わって、プレッシャーに感じることもあります。
親御さん自身が元気な姿を見せることで、不登校やひきこもりから抜け出すきっかけとなるかもしれません。
親御さん自身が生活を楽しみ、元気な姿を見せることは、子どもに安心感をもたらすだけでなく、「大人として望ましいロールモデルを見せること」にもつながります。
それによって、お子さんが「自分ももっと自立しよう」「こんな大人になりたい」と思えるようになることもあるのです。
「子どもが不登校で悩んでいるのに、私だけが元気にはなれない」と思われる人もいらっしゃるでしょう。
親として、当然の感情だと思います。
しかし、親御さんの元気な姿を見せることは、不登校やひきこもりの解決には欠かせません。
お子さんが将来の希望を持てるように、まずは親御さん自身が生活を充実させて、元気な姿をお子さんに見せるようにしてみてください。
不登校やひきこもりの状態が長期化したときの対処法2選
不登校やひきこもりを解決するには、長い時間がかかることもあります。進学や就職の時期が近づくことで、お子さん自身の考え方が変わることもありえます。
この章では、十分な休息期間を取り、お子さん自身が「状況を変えたい」と考えられるようになってきたら試してほしい対処法について解説します。
対処法①転校・編入を検討する

不登校やひきこもりが長期化したときには、環境を大きく変えることもひとつの方法です。いまの学校を退学し、ほかの学校へ編入することも検討しましょう。
高校生の場合は、通信制高校など、学びのスタイルが違う学校もあります。自分にあった学校に入学することで、学校生活が楽しめるようになるかもしれません。
また、大学への進学を新しい目標にして、学習意欲が戻ってくることもありえます。
不登校やひきこもりからの転校や進学については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
対処法②専門家の支援を受ける
不登校やひきこもりを改善するためには、専門家や支援機関に相談することは大切です。
親御さんは不登校・ひきこもりの専門家ではありません。はじめてのできごとに、戸惑う場面も多いことでしょう。さらに、お子さん自身も自分の状況について客観的な判断ができず、不安に感じているかもしれません。
専門家や支援機関は、そうした状態の親と子どもの両方について、深い知識を持っています。親子が双方にとって必要な支援を受けることで、解決できる問題もあるはずです。
また、客観的な知識やほかの人の体験談などを聞くことで、互いの状況についての理解も深まります。
困ったときにはぜひ、専門家や支援機関に相談してくださいね。
不登校かつひきこもりの経験者による体験談
この章では、不登校かつひきこもりを経験したキズキ共育塾の寺田淳平講師の体験談を紹介します。
ここで紹介するものは、不登校かつひきこもりの経験をした人の体験談のうちのひとつです。
あくまで参考としてご覧ください。
何となく「学校に通いたくない」

私が定義通りの不登校になったのは、高校2年生になったばかりの4月でした。
はじまりは何となく「学校に通いたくない」という気持ちです。
不登校生活の当初は、「この心理状態の原因は何か」を考えており、その原因を解消すれば自然と学校へ行きたい気持ちになるはずだと思っていました。
そのときに、思いついた不登校になった原因は、おおよそ以下のようなものです。
- クラス替えで人間関係に不安を感じはじめた
- 授業の進度が合わなかった
- 担任の先生が苦手だった
- 家族が病気になって不安だった
ですが、不登校になった原因をいくら考えても、「これが決定的な原因だ」と自信を持って言うことはできませんでした。
また、「その原因が解消したら、また学校へ行きたくなるのか?」と自問すると、そういうわけでもなさそうでした。
最終的には混乱するだけで、原因を考えるだけでもつらく感じるようになりました。
「そっとしておいてほしい」という本音
考え込むうちに不登校の期間が長引き、人と接する機会が減った結果、以前よりも一層自分のコミュニケーション力に自信が持てなくなりました。
その頃に私が特に嫌だったのが、家族が無理にでもコミュニケーションを取ろうとしてきたことです。
不登校になると、学費を払っている両親に対する罪悪感が出てきます。
その両親の期待に応えたいという思いはもちろんありましたが、応えられる心理状態では決してありません。心に余裕ができるまでは、「そっとしておいてほしい」というのが本音でした。
結果的に、家族との接触も避けるようになり、部屋に引きこもる時間は増えていきました。
適切な距離感やコミュニケーションのタイミングへの配慮が必要

私の経験からお伝えしたいことは、不登校やひきこもりの解決のためには、適切な距離感やコミュニケーションのタイミングへの配慮が必要ということです。
お子さんとコミュニケーションを取ること自体は、決して悪いことではありません。
親御さんが「何とか子どもを支援・サポートしたい」と思うのは、当然のことでしょう。
ですが、不登校やひきこもり状態の子どもは、コミュニケーションを取りたくても取れる心理状態ではありません。そのため、無理なコミュニケーションが余計にお子さんを追い詰めていることがあるのです。
多少はがゆく感じても、無理にコミュニケーションを取ろうとせず、お子さん自身が「話そう」と思えるまで見守ることが、不登校やひきこもりを解決するためには重要です。
なお、私の場合は、自分から話せるくらいに気持ちが回復し、考えが多少まとまってから担任の先生との三者面談の機会を設けていました。そして保健室登校を開始し、不登校かつひきこもりの状態から脱出しました。
その後は、休みを挟みながらではありましたが、留年することなく卒業まで高校に通い続けられました。
不登校・ひきこもりに関するQ&Aまとめ
この章では不登校・ひきこもりに関するQ&Aを紹介します。
キズキ共育塾でも多く寄せられる、不登校やひきこもりに悩む人たちからのご相談・質問をピックアップしました。
同じ疑問をお持ちの人も多いと思います。ぜひ、参考にしてください。
Q1.家庭環境が不登校やひきこもりの原因になる?

不登校やひきこもりのお子さんの中には、家庭環境が一因になっているというケースも存在します。しかし、それはあくまで、原因のひとつです。
不登校やひきこもりは、さまざまな要因が複雑に絡みあっている場合がほとんどです。
要因の一つに家庭環境があったとしても、学校生活や勉強における要因など、お子さんがさまざまな面で悩みを抱えていることも少なくありません。
また、不登校になった原因と不登校が継続している原因は、別であることが多くあります。
仮に、不登校になった原因が家庭環境にあったとしても、その後に生活リズムが乱れたり、交遊の機会が減って対人恐怖を抱いたりしたことが、不登校が継続している原因となっていることもあるのです。
つまり、家庭環境が一因になることはあっても、それがすべての原因ではありません。
なお、不登校と家庭環境の関係については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
Q2.ひきこもりは病気や障害?
ひきこもりは、病気や障害の一種ではありません。
ただし、ひきこもりと病気や障害が関連したり、ひきこもりの背景に病気や障害が関連している場合はあります。
例としてよく挙がるのが、ひきこもりをきっかけにクリニックを受診したところ、発達障害であることが判明したというケースです。
発達障害の一種であるASD(自閉症スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)などの場合、コミュニケーションに関連する障害や、特定分野へのこだわりといった症状が、社会生活や学生生活に困難を来たす場合があります。
そうした困難から、うつ病などの精神疾患を二次障害として発症し、ひきこもりになることがあるのです。
もちろん、必ずしもひきこもりの人の全員に発達障害があるわけではありません。
ですが、その症状に合致している点が多いと感じた場合は、病院や発達障害者支援センターなどに相談してみてください。
なお、発達障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校ジャーナリスト・石井しこう、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。
このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。
このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。
公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら
- 【オリジナル書籍プレゼント】学校外で友だちができるBranchコミュニティ(Branch公式LINEが開きます)
私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。
まとめ〜無理なコミュニケーションを求めないことが大切です〜

不登校やひきこもりのお子さんを手助けするためにまず大切なのは、お子さんが話そうという気持ちになるまで無理なコミュニケーションを求めないことです。
まずは、お子さんが自分のペースを取り戻し、これからのことを考える余裕が出てくるまで、長い目で見守るようにしましょう。
その上で、親御さんも自分自身の生活を充実させ、お子さんの問題をひとりで抱え込まないようにしてください。また、第三者への相談を積極的に行うことが大切です。
このコラムが、不登校やひきこもりのお子さんの対処法や接し方に迷われているあなたの助けになれば幸いです。
私たちキズキ共育塾では、不登校やひきこもりの悩みから、次のステップへ進もうとしている人たちを支援しています。
高校・大学受験、高卒認定試験、学校復帰などについての無料相談も随時行っております。お悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。
Q&A よくある質問