どこからがひきこもり?定義は? 原因や社会的背景を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
「学校に行きたくない」「ずっと家にいたい」と思うことは、誰にでもあります。
けれどその状態が、長く続いたらどうでしょうか?「もしかして自分はひきこもりなのかも」と、不安に感じるかもしれません。
ひきこもりと聞くと、家から一歩も出なかったり、誰とも会話をしなかったりする状態をイメージするかもしれません。しかし、実際には、ひきこもりと呼ばれる人たちの範囲はもう少し広そうです。
このコラムでは、ひきこもりの定義や現状、区分、原因・背景、回復する流れについて解説します。あわせて、ひきこもりの子どもに親ができる対応についても解説します。
家から出たくない気分になったときはもちろん、ご家族が「ひきこもりになったのかも」と心配されている人も、ぜひ参考にしてください。
私たちキズキ共育塾は、ひきこもり状態にある人のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
ひきこもりとは?

ひきこもりとは、さまざまな原因から自宅以外での就学・就労などの社会的な活動の機会を避けて、長期にわたって自宅に留まり続けている状態のことです。(参考:ひきこもりVOICE STATION「まず知ろう!「ひきこもりNOW」!」https://hikikomori-voice-station.mhlw.go.jp/information/、厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」)
ひきこもりは、厚生労働省によって以下のように定義されています。
ひきこもりとは、「様々な要因の結果として社会的参加 (義務教育を含む就学, 非常勤職を含む就労, 家庭外での交遊など) を回避し、原則的には6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい) を指す現象概念である。」
(参考:厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」)
ここでいう社会的参加には、学校や仕事に行くことのほか、家族や同居人以外の人との交流なども含まれます。
外出していたとしても、それが他者と関わらない形の外出の場合は、ひきこもりに該当します。例えば、近所のコンビニへの買い物のために外出をしていても、他の人との交流がない場合は、ひきこもりと見なされることがあります。
反対に、外出をほとんどせずに通信制高校に在籍している人やリモートワークをしている人などは、就学・就労をしているため、ひきこもりに該当しません。
ひきこもりの現状

ひきこもりの子ども・若者は、日本全国に約146万人いると言われています。(参考:総務省「人口推計(令和5年(2023年)4月確定値、令和5年(2023年)9月概算値)(2023年9月20日公表)」)
同様の問題は、東アジアを中心に世界的に認知されるようになっています。
最近では、フランス国内に数万人のひきこもりがいると報道されたことが話題となりました。こうした状況の背景には、新型コロナウイルスの感染拡大が影響を及ぼしていることが指摘されています。ひきこもりは、日本国内のみにとどまらない世界的な問題と言えるでしょう。(参考:マダム・フィガロ「「ひきこもり」がフランスで増加中。日本との共通点は?」、内閣府「ひきこもり支援者読本」)
ひきこもりの区分
この章では、内閣府が実施した調査に基づき、ひきこもりの区分について解説します。(参考:内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査(令和4年度))
区分①広義のひきこもり
広義のひきこもりとは、外出する機会が少ない状態が6か月以上続いている場合の人のことを指します。
具体的に、以下の状態にある人が、広義のひきこもりに該当します。
- 趣味の用事のときだけ外出する
- 近所のコンビニなどには出かける
- 自室からは出るが、家からは出ない
- 自室からほとんど出ない
なお、これらの条件に当てはまった場合でも、以下に該当する人のうち、一定の条件を満たした人は、広義のひきこもりには該当しません。
- 妊娠した
- 介護・看護を担うことになった
- 自営業をしている
同調査では、15歳~39歳では約2%が、40歳~69歳では約3%が広義のひきこもりであると定義されました。これは、15歳~39歳では約50人に1人、40歳~69歳では約30~40人に1人の割合です。
区分②狭義のひきこもり
狭義のひきこもりとは、こちらで解説した広義のひきこもりに該当する人のうち、ほとんど外出しない状態にある人のことを指します。
具体的に、以下の状態にある人が、狭義のひきこもりに該当します。
- 近所のコンビニなどには出かける
- 自室からは出るが、家からは出ない
- 自室からほとんど出ない
区分③準ひきこもり
準ひきこもりとは、こちらで解説した広義のひきこもりに該当する人のうち、趣味の用事のときだけ外出する人のことを指します。
準ひきこもりの状態まで含めると、多くの人がひきこもり状態に当てはまりそうです。
ひきこもりの原因と背景
厚生労働省が発信する「ひきこもりVOICE STATION」では、ひきこもりの主な原因として、以下の項目が挙げられています。(参考:内閣府「平成28年度若者の生活に関する調査報告書」)
- 不登校
- 職場になじめなかった
- 就職活動がうまくいかなかった
- ⼈間関係がうまくいかなかった
- 病気
- 受験に失敗した
- ⼤学になじめなかった
これらの要因は、大きく、「社会的要因」「家庭的要因」「病気や障害」に分けられます。
それぞれの特徴や子どもの様子をまとめました。(参考:厚生労働省「ひきこもりVOICE STATION」)
原因①社会的要因

ひきこもりの原因には、職場や学校での人間関係や居心地の悪さ、文化的な摩擦が一定の割合を占めています。
とくに思春期のひきこもりには、心の発達が深く関連すると言われます。思春期には、子ども特有の「なんでもできる」という万能感が薄れ、現実と実力のギャップを意識し始めるころです。
また、受験や友人との関係性を通じて自信を失ったり、自我が揺らいだりすることもあります。(参考:兵庫県精神保健福祉センター「ひきこもりを理解するために」)
キズキの生徒さんだったAくん (中3)もそうでした。
彼は「学校が合わない」と感じて不登校になり、そのままひきこもりの状態になったのです。Aくんは「俺は人とうまく関われないし、勉強もできないから、大人になっても仕事に就けないと思う」と言っていました。
しかし、本当はAくんにも「なんとかしたい」と思う気持ちがあったのです。キズキ共育塾で勉強とメンタル面の支援を受け、自分の強みに気づくことによって、彼は最終的に、高校へ入学することができました。
Aくんのエピソードやひきこもりからの自立に関するコラムは、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
近年であれば、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、外出の機会が減りました。人と接するチャンスが制限されただけでなく、学校や新しい環境での人間関係の構築が難しくなったケースもあります。
思春期の年代の子どもたちのなかには、ほとんど同級生と対面で接する機会もないままに学生時代が終わった人もいるでしょう。
そうした環境下において、社会的要因によるひきこもりが増加しています。ひきこもりからの回復には、支援の見直しの必要性も指摘されました。(参考:NHK「「ひきこもり」推計146万人 主な理由“コロナ流行”内閣府調査」 )
こうした社会的な要因によるひきこもりの人を支えるには、専門家と相談しながら、じっくり向き合う必要がありそうです。
原因②家庭環境
子どもがひきこもりになると、親御さんは「自分の育て方が悪かったのかも」と悩むものです。
しかし多くの場合、親の接し方は、ひきこもりの直接的な原因とはなりません。どのような家庭のどのような子どもも「ひきこもり」になり得ると考えられています。(参考:内閣府「ひきこもり支援者読本」)
一方で、子どもにとっての家庭環境の感じ方には、ある程度傾向があるようです。
内閣府の「こども・若者の意識と生活に関する調査 (令和4年度)」では、広義のひきこもり状態にある群とそうでない群の回答者では、家庭や家族に対する考え方に差があることが示されました。(参考:内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査 (令和4年度) )
そのなかでも、特に両者の差が大きい項目で「どちらかといえばあてはまる」または「あてはまる」と回答した人の割合を比較してみましょう。
家族・親族とあなたのかかわりのなかで、「何でも悩みを相談できる人がいる」と感じますか
- 広義のひきこもり群:約44.4%
- それ以外:約73.3%
家族・親族とあなたのかかわりのなかで、「他の人には言えない本音を話せることがある」と感じますか
- 広義のひきこもり群:約43.8%
- それ以外:約71.8%
家族・親族とあなたのかかわりのなかで、「いつもつながりを感じている」と感じますか
- 広義のひきこもり群:約65.3%
- それ以外:約85.8%
ひきこもりの状態にある人は、家族や親族に本音を打ち明けたり、悩みを相談したりするのが苦手という傾向です。こうした状況は、必ずしも親御さんの接し方に問題があるわけではありません。
なぜなら同様の質問を「友人関係」に置き換えた問でも、同様の傾向が見られるからです。
思春期特有の揺らぎや性格等の要因から、困難な状況をひとりで抱え込みやすい状況にあると、ひきこもり状態になりやすい傾向にあると言えそうです。
原因③病気や障害

病気や障害が原因でひきこもりの状態に陥った場合、因果関係や関連性の判断が難しいことがほとんどです。
病気・障害が原因でひきこもりになっているケースもあれば、ひきこもり状態が原因で精神疾患などになっているケースもあります(なお、病気障害が関係する場合、厳密には「ひきこもり」の定義には合致しません)。
ここでは、病気や障害からくる失敗経験や人間関係での摩擦が原因でひきこもりとなる可能性のある例を、いくつか紹介します。(参考:日本精神神経学会/監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』)。
①統合失調症
統合失調症の症状に、「誰かに嫌がらせを受けている」「だまされている」「見張られている」などの「被害妄想」があります。
そうした症状があると、部屋にひきこもり、社会的参加をしない選択をする場合があるのです。
統合失調症を発症すると、自分では自身の状態に気づかないこともあるので、心配なときは家族が病院に連れて行くことも大切です。
②不安障害
不安障害の症状である分離不安症や選択性緘黙(かんもく)が、ひきこもりの原因になることもがあります。
分離不安症とは、愛着のある人から離れることに極度の不安を抱く障害です。
家から離れて学校や仕事場所へ出かけることに不安を感じるため、社会的参加に持続的な抵抗や拒否が見受けられます。
また、選択性緘黙は家庭などでは話しているにも関わらず、特定の社会的状況(学校や職場など)において、話すことができない障害です。
これらの症状が、ひきこもりの原因となることがあるのです。
③双極性障害
双極性障害は、うつ病と躁状態が見受けられる障害です(躁状態の強度には差があります)。
うつ状態の際にひきこもりになる可能性がありますが、躁状態のときには活発になるので、見落とされやすい事例かもしれません。
ひきこもりからの回復3ステップ
ひきこもりからの人は一見、楽そうに見えても、実は心のエネルギーを使い果たしていることはよくあります。
ひきこもりの状態を理解する上では、「実際の心のエネルギー量」と「見せかけの心のエネルギー量」にずれがあることを理解しておく必要があります。
兵庫県精神保健福祉センターの公表している「ひきこもりを理解するために」では、心のエネルギーが満たされていく過程を下記の5つのステップで解説しています。 (参考:兵庫県精神保健福祉センター「ひきこもりを理解するために」)
- 無気力の状態
- 安心感
- エネルギー、興味関心がわく
- 楽しさを感じる
- 自分のやりたいことを見つける
これらを参考に、回復までの流れを大きく3つにまとめました。
ステップ①無気力から安心感へ

ひきこもりになったばかりのとき、心はひどく消耗しています。まずは、しっかり休むことが重要です。ストレスを感じる場所を避け、人との接触を減らして、心のエネルギーを蓄積するのです。
このとき、家庭をはじめとした「安心できる場所」があることが重要になります。
家族に気を使うなど、家でうまく休めないときには、支援施設を頼るのもよい方法です。本人がリラックスできる環境で、十分な休息を取りましょう。
「自分はここにいてよい」という安心感が、次のステップの足掛かりとなります。
ステップ②気持ちがより前向きに
心が十分に休まると、趣味や外のできごとに興味を向ける余裕が戻ってきます。
この段階で、少しずつ外へ出ることが増えるかもしれません。しかし、完全に回復したと考えて、学校やコミュニティへの復帰を急かすのは禁物です。
ここではまだ、外の世界が安全かどうかを手探りで確認している状態です。無理をすれば、心のエネルギーが再び失われることもあります。
本人が興味を持ち、もっと知りたいと希望したタイミングで、情報を集める手助けをしましょう。
ステップ③社会へ戻る準備が整う

ひきこもりの人は、休んだり、外に出たりを繰り返しながら回復していきます。
ときには、再びひきこもり状態に戻ったように感じられることもあるでしょう。しかし本人が自信を取り戻し、社会に戻る準備が整えば、社会復帰を考えるタイミングがくるはずです。
家族や周りの人は、本人のペースを大切に、適度な距離感で支えてください。(参考:兵庫県精神保健福祉センター「ひきこもりを理解するために」)
ひきこもり状態の子どもの気持ち

ひきこもり状態になった子どもたちは、どんな気持ちでいるのでしょうか。
この章では内閣府の「こども・若者の意識と生活に関する調査 (令和4年度)」の調査結果から、ひきこもり状態にある人の心理について考えていきましょう (各数字は「どちらかといえばあてはまる」または「あてはまる」と回答した人の割合の合計です)。(参考:内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査 (令和4年度)」)
広義のひきこもり状態にある群とそうでない群の回答者では、自己肯定感に関する項目でも大きな差が出ました。
「自分には自分らしさというものがあると思う」と感じている人は、広義のひきこもり群では約66.7%なのに対し、それ以外の回答者では約84.5%と、20%近い差があります。
また「今の自分が好きだ」という問いでも、ひきこもり群は約36.1%、それ以外では約60.5%です。
さらにひきこもり群の半数以上が「自分は役に⽴たないと強く感じる」と回答するなど、自己肯定感の低さがうかがえます。
また、学校の友人や家族とのつながりに関してもネガティブな回答の割合が高くなっています。
現在の居場所(ほっとできる場所、居心地の良い場所など)に関しては、居心地のいい場所として「学校」を挙げた人は、ひきこもり群では約23.5%と、それ以外の人の半分程度に留まります。
一方で、SNSなどの「インターネット空間」と答えた人は、ひきこもり群では約72.9%と、それ以外の人の約56.3%を大きく上回ります。
ひきこもりの状態にある人は、対面でのコミュニケーションを苦手としています。
一方で、インターネットなどの匿名の環境であれば、安心して人と関わることもできるようです。
ひきこもりの人は「無気力」なのではなく、自分にあった方法で外部とコミュニケーションを取る方法を模索している状態にあるのかもしれません。
ひきこもりの子どもに親ができる3つの対応
この章は、子どもがひきこもりになった (もしくは「なりそう」と心配している) 親御さんへお伝えしたいことです。
前述のとおり、子どもがひきこもりになる要因はさまざまです。親御さんや家庭環境だけが原因とは限りません。まずは自分を責め過ぎず、ゆったりとお子さんを受け止める心の準備を整えましょう。
子どもがひきこもりになったときにできることについては、こちらのコラムも参考にしてください。
対応①まずは「ありのまま」を受け止めて

内閣府の調査では、ひきこもりの人は家族や親族に悩みを打ち明けづらいと感じていることも明らかになりました。
特に思春期の子どもは、「親に守ってもらいたい」という気持ちと「自分自身でなんとかしたい」という気持ちが拮抗しています。(参考:内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査 (令和4年度)」)
反抗的になったり、親の無理解を責めたりするのは普通のことです。その本心は、「親から認められ、信頼されたい」ということに集約されます。
ひきこもりになった子どもの苦痛は、ひきこもりになる前から続いています。
家から出なくなるのは、SOSサインのひとつにほかなりません。自分の気持ちをうまく整理できず、どうしたらよいのかわからずに、戸惑っているのです。
そんなとき、あれこれとアドバイスしたくなるのは親の気持ちとしては当然です。助けてあげたいと思うからこそ、声をかけ、手を貸して、なんとか外に連れ出したいと思うかもしれません。
しかし、まずは、目の前の子どもを受け入れてください。学校へ行けず、家から出られず、友達にも会えなくなった状態を、そのまま認めてあげてください。そしてそっと、見守りましょう。
子どもは、身近な人に、自分のことを受け入れてほしいと感じています。一緒に暮らす家庭に、子どもが、そのままでいられる場所をつくってあげることが、ひきこもりからの回復の第一歩となるのです。
対応②家庭を「安心できる場所」に
内閣府の調査では、「ほっとできる場所、居心地の良い場所」に「家庭」を挙げたひきこもりの人の割合は、約68%に上りました。
ひきこもり以外の回答者の約87.4%と比較すると少ない印象ですが、7割近い人が家庭に安心感を見出していることがわかります。(参考:内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査 (令和4年度)」)
一方で、「そう思わない」と回答したひきこもりの人は約26%と、それ以外の人の2倍以上の割合です。
内閣府の調査では、「安心できる場所」が多い人ほど自己肯定感が高く、将来への希望やチャレンジ精神の数値も高い傾向が明らかになりました。
この傾向は、「相談できる人がいる場所」や、「困ったときに助けてくれる人がいる場所」の数の項目でも同様です。
また、こうした場所を多く持つ人ほど、「自分の考えをはっきり相手に伝えることができる」傾向も高いことがわかりました。
一方で、「安心できる場所」をたくさん持っている人は「社会生活や日常生活を円滑に送ることができなかった状態が改善した経験があった」割合も高くなっています。
生活に課題を抱え、困難な状態を経験した人ほど、支えてくれる人とのつながりをたくさん持っていることが読み取れます。
ひきこもりの人は、自己肯定感が低いことも特徴のひとつです。まずは「家庭を安心できる場所」とし、それを足掛かりに、そうした場を増やしていくのもよいのかもしれません。
対応③専門家の支援を利用しましょう

ひきこもりの人を支えるのは、家族だけの仕事ではありません。民間・公的機関を問わず、ひきこもりの人を支援する団体や専門機関はたくさんあります。
たとえば「ひきこもりの親の会」のような団体や、メンタルクリニック、カウンセラーもそのひとつです。もちろん、キズキ共育塾もお力になります。
親御さんにとっては、子どもの状態を恥ずかしく思ったり、他人の手を借りたりすることが引け目に感じられるかもしれません。
けれど、専門家の支援を利用した方が、状況をよい方向に変えていきやすくなります。また前述のとおり、「安心できる場所」が多ければ多いほど、子どもの状態が安定する傾向にあります。
ひきこもりへの支援の在り方も、改善され続けています。適切な施設や団体を利用し、専門家と協力しながら、お子さんの回復を見守りましょう。
キズキ共育塾では、ひきこもり経験のあるスタッフによる「ひきこもり支援団体の探し方」についてのコラムも掲載しています。こちらもぜひ、参考にしてください。
ひきこもり・不登校・ニートの違い
「ひきこもり」と「不登校」「ニート」は関連の深い言葉です。それぞれに密接に関連することも少なくありません。
こうした状態にある人々に対し、横断的な支援を行っているところも多くあります。私たちキズキ共育塾も、そのひとつです。
とはいえ、それぞれの言葉には、異なる定義が設定されています。ここでは「ひきこもり」「不登校」「ニート」の違いを確認しておきましょう。
ひきこもりと不登校の違い

ひきこもりと不登校の違いは、「日数」と「社会的参加の有無」です。
ひきこもりは「6か月以上社会的参加がない状態」なのに対して、不登校は「年間30日以上学校に行っていない状態」のことを表します。
文部科学省では、不登校のことを、次のように定義しています。
何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの
(参考:文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」、文部科学省「不登校の現状に関する認識」)
一方で、不登校の定義には、社会的参加の有無についての言及はありません。
例えば、不登校でも、習い事に通う、友達と交流するなどを行っていれば、「ひきこもり」には分類されないのです。
厚生労働省と文部科学省の定義をまとめると、次のようになります。
- 学校に所属しておらず、社会的参加していない状態が6か月以上継続している場合は、「ひきこもり」
- 学校に所属していて、年間30日以上の欠席があり、学校以外の社会的参加がある場合は、「不登校(だけどひきこもりではない)」
- 学校に所属していて、年間30日以上の欠席があり、学校以外の社会的参加も6か月以上ない場合は、「不登校かつひきこもり」
ひきこもりとニートの違い
ニートとは、「Not in Education,Employment or Training」の頭文字を取ったイギリスの造語のことです。直訳すると「就業、就学、職業訓練のいずれもしていない人」になります。
また、日本では、厚生労働省が次のように定義しています。
総務省が行っている労働力調査における、15~34歳で、非労働力人口(※)のうち家事も通学もしていない人 ※ 15歳以上人口のうち,「就業者」と「失業者」以外の人のこと (参考:厚生労働省「よくあるご質問について」)
したがって、ひきこもりとの違いは「15歳以上35歳未満かどうか」かつ「主に家の中だけで生活しているかどうか(社会的参加があるかどうか)」です。(参考:立命館大学,西田亮介「ニートとひきこもり」)
各相違点をまとめると、以下のとおりです。
- 年齢に関係なく、社会的参加をしていない状態が6か月以上継続しているのは、「ひきこもり」
- 15歳以上35歳未満で、通学・就業・職業訓練や就職活動のいずれも行わないが、社会的参加はしている場合は、「ニート(だけどひきこもりではない)」
- 15歳以上35歳未満で、社会的参加していない状態が6か月以上継続し、通学・就業・職業訓練や就職活動・家事のいずれも行わない場合は、「ニートかつひきこもり」
なお、毎日を主に家の中で過ごす人でも、「主婦・主夫」や、在宅で業務を行う「フリーランス」などは、一般的にはニートやひきこもりには含まれません。
また、現在仕事をしていない若者のなかでも、就職活動中の人や、まだ活動はしていないけれど就職を希望している人は、ニートには該当しないとされています。
自宅での学習を中心に受験準備を進める浪人生なども除外してよいでしょう。
ただし、ニートとひきこもりは重複するケースもかなりあるようです。2007年度の調査では、ニート全体の半数弱である49.5%がひきこもり状態であるという数値も出ています。(参考:厚生労働省「ニートの状態にある若年者の実態及び支援策に関する調査研究」)
ひきこもりについてのよくある3つの質問
ひきこもりは、社会全体から見れば少数派です。自分や、子どもがひきこもりになったとき、参考になる例が身近にあるとは限りません。
次は誰に聞けばいいかわからない、ひきこもりについての疑問についてお答えします。
Q1.就職など、将来への影響は?

ひきこもりになったからといって、進学や就職ができなくなるわけではありません。
不登校の場合と同じように、進学に必要な資格(高卒や高卒認定)を取れば、大学受験も可能です。現在では、オンラインでの学習も一般的になってきました。人と会うのが苦手でも、学ぶ方法はたくさんあります。
まずはゆっくり休み、心と体の調子を整えてから、自分がこれからどうなりたいのかをじっくり考えるのがよいでしょう。
ひきこもりを経て大学へ進学した生徒さんのインタビューも、ぜひ参考にしてください。
Q2.ひきこもりの子どもも、外出するの?
広義のひきこもりには、趣味のために外出をする人も含まれます。また、狭義の場合でも近所のコンビニ程度の外出は珍しくありません。
ひきこもりの定義のポイントは「社会的参加」です。積極的に人と交わり、社会の中に溶け込んでいるかどうかが、判断の基準となります。
Q3.「大人のひきこもり」って?
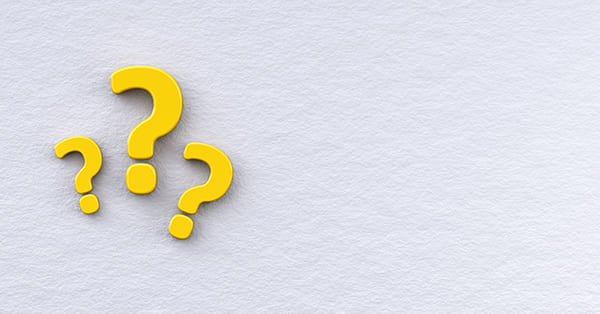
大人のひきこもりは、近年、国の大きな課題として取り上げられるようになりました。厚生労働省の発表では、40歳から64歳のひきこもりは、2018年の時点で約61万3千人にも及びます。(参考:厚生労働省「生活状況に関する調査(平成30年度)」)
社会問題となっている8050問題も、こうした問題のひとつです。
8050問題とは、高齢の子どもを、さらに高齢の親が世話するという構図です。ひきこもりになった人が歳を重ね、生活能力のない状態で高齢になることから起きる現象です。
ひきこもりは、長期化しやすいことも特徴と言われます。現代のひきこもりをとりまく状況が改善しなければ、今後も8050問題は社会的な課題として、残り続けることになるのです。
まとめ~ひきこもりからの回復には、専門家の力を借りて~

ひきこもりの定義は、「社会的参加をしていない状態が6か月以上継続している状態」です。
原因はさまざまであり、病気や障害ではなくとも、誰しもがひきこもりになる可能性があります。
ひきこもりからの回復には、ある程度の時間と労力を要します。本人はもちろん、それを支える人も、負担を抱え過ぎない体制を作ることが重要です。専門家の力を借りて、じっくり向き合いましょう。
公的な定義に当てはまるかどうかに関わらず、ひきこもりに対してはさまざまな支援団体があります。
さて、私たちキズキ共育塾は、ひきこもり・不登校・ニートなどの当事者・経験者を、学習面とメンタル面からサポートしています。
一人ひとりのお悩みに寄り添い、丁寧な個別指導で学び直しを徹底的に支援します。
少しでもお役に立てることがあれば、お気軽にお問い合わせください。親御さんだけでのご相談も可能です。
お子さんや家族の皆さんが次の一歩に進めるよう、心から祈っています。


















