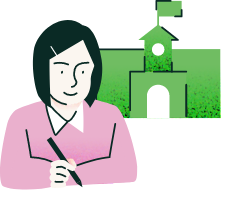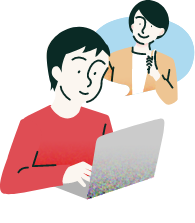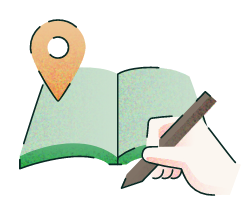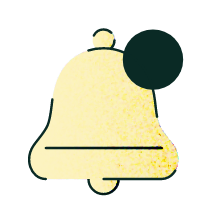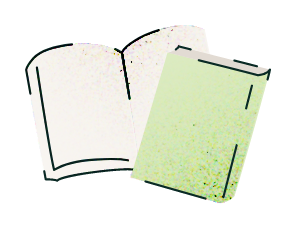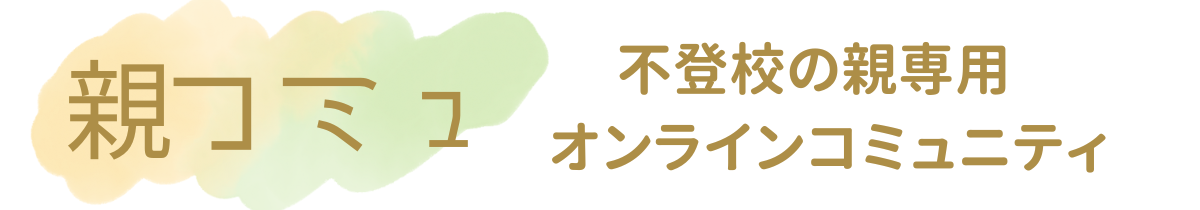「学校が合わない」と言われたら?子どもがそう思う理由・対処法を解説
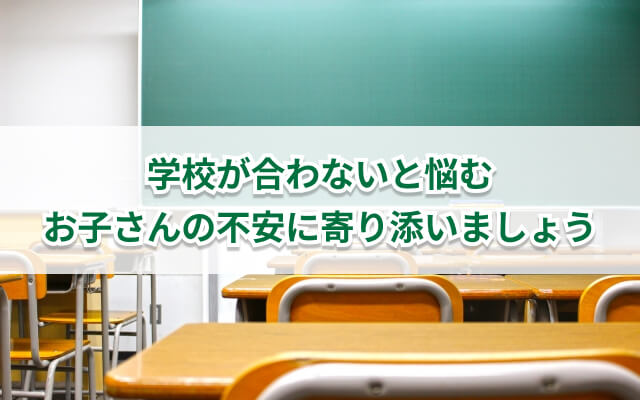
こんにちは。学校が苦手なお子さんのための完全個別指導塾・キズキ共育塾の濱野です。
あなたは今、「クラスの人たちや雰囲気など、学校が合わない」とお子さんに言われ、お悩みなのではないでしょうか?
学校が合わないことが原因で、不登校になる場合もあります。
お子さんが「学校が合わない」と言う具体的な理由は、何でしょうか?
このコラムでは、主に中高生の子どもが「学校が合わない」と感じる理由と、その対処法をお伝えします。
学校が合わないと感じることは、特別なことやおかしいことではありません。お子さんにあった対処法が見つかり、一歩前に進むことができましたら幸いです。
共同監修・不登校新聞社 代表理事 石井志昂氏からの
アドバイス
「僕(私)は学校に合わない」と言って、行きしぶりや不登校になる子も多くいます。
学校が合わないと感じる理由は人それぞれですし、言語化できないことも含めて、そう感じる理由は複数に渡る場合が多いです。
保護者の方は、「子どもが学校生活を営めない。“普通”から外れてしまう」と焦らなくても大丈夫です。お子さんの気持ちを受け止めながら、本人がイキイキする場を探していきましょう。
目次
「学校が合わない」とお子さんが感じる理由
「学校が合わない」とお子さんから急に言われても、子供の気持ちや状況を理解することが難しいと思う親御さんもいらっしゃると思います。
子どもが「学校が合わない」と感じる理由は、どのようなものがあるのでしょうか?
特に中学校や高校に通う思春期のお子さんの気持ちは、親御さんには理解しづらいこともあります。
ここでは、ひとつひとつ具体的に「学校が合わない」と思う理由をご紹介していきます。お子さんへの理解を深めるためにも、ぜひ参考にしてみてください。
理由①学校というシステムが合わない
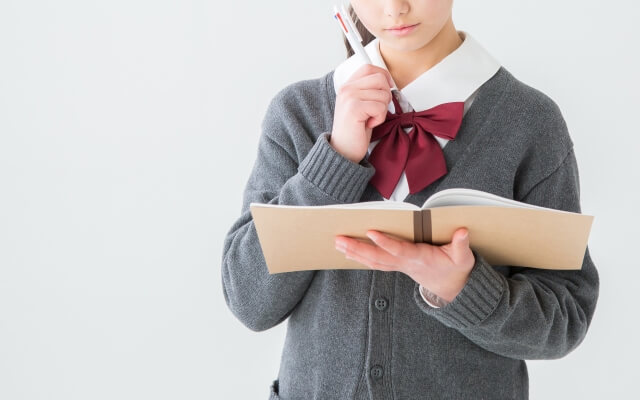
1つ目の理由は「学校というシステムが合わない」です。
2018年に行われた日本財団のアンケート調査では、「教室にいるけど学校が辛いと感じている」「本当は授業に参加したくない」「登校はするけど、教室には入りたくない」と感じている中学生が、全国で約33万人にのぼるという結果が出ました。(参考:日本財団『不登校傾向にある子どもの実態調査』)
- 子ども一人ひとりに個性があるのに、合わない教育を押し付けられている
- 集団生活が苦手なのに、毎日みんなと同じ行動をさせられる
このように、自分の居場所としての「学校」に違和感を抱き、学校での人間関係のあり方、先生の教育方法などのシステムに疑問を持った結果、そのつらさを周囲に理解されずに悩む子どもは珍しくないのです。
さて、「つまらない授業を受けることが苦痛」とお子さんに言われたら、「それは単なるわがまま・甘えではないか」と思う親御さんもいらっしゃるでしょう。
しかし、子どもたちは決して勉強に興味がないわけではありません。
自分の好きなことや追求したいことが学べる環境、そして自分のペースに合った学習環境があれば、学校に通いたいと思う子どもが多い、ということも日本財団の調査で明らかになっているのです。(参考:日本財団『無理してまで学校に行く必要があるのか?子どもと親、大人たちの考えは?』)
調査の中には、「中学校や高校では授業に興味がなかったけれど、大学に行ってから学ぶ意欲がわいた」と回答した子どもがいます。
つまり、中学校や高校などの学校というシステム、授業の内容、進め方が合わないということが考えらるのです。
また、学校というシステムそのものが合わないと感じる理由には、「学校は集団生活を避けられない」ということにもあります。
お子さんが集団行動を苦手に感じて、ひとりで過ごそうと思っても、学校というシステムの中ではなかなか難しいものです。
「休み時間は本を読みたいけれど、友達がいないと思われそう」「ひとりで教室にいるのが寂しい」と思い、行動に移せない子どもも珍しくありません。
このように、常に人目を気にしながら行動しなければいけないのは、学校特有のシステムによるものかもしれません。
理由②校則が合わない

2つ目は「校則が合わない」です。
文部科学省の調査によると、「学校のきまりなどをめぐる問題」が原因で、不登校になっている子どもがいるとの結果が出ています。(参考:文部科学省『令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果』)
学校の決まりの中で不満を抱きやすいものの一つが「校則」です。
例えば、小学校のときには校則がゆるく、服装や髪形などは自分の好きなようにできていたとします。
しかし、中学校に入学すると、その自由が校則により制限されるようになるのです。
校則で定められた服装(制服)で登校し、学校によっては髪型も校則で指定されています。
「なぜ髪型や髪色を細かく決めるのか」がわからず、一方的に強制されることに違和感を抱く子もいるでしょう。
このような校則をめぐって、トラブルが起きることもあります。
私が中学生のとき、クラスメイトで髪の毛が茶色い子がいました。
彼女は染めているのではなく、生まれつき茶色の髪の毛なのです。
それにも関わらず、「染めているのではないか」と先生に疑われ、何度も嫌な思いをしたそうです。
厳しい校則のもとでは、もともと天然パーマなのに「パーマを掛けているのではないか」と疑われる人もいます。
そういった先生の対応や言葉に傷つき、「学校が合わない」と感じる子どももいるのです。
理由③人間関係が合わない

3つ目は「人間関係が合わない」です。
学校での行動は、基本的に「クラス単位」です。
毎日、自分のクラスで過ごし、体育祭や文化祭、修学旅行などの学校行事もクラスごとでまとまって行います。
そうすると、同じクラスメイトがずっと一緒にいることで、クラス独自の雰囲気やノリが生まれ、それに合わない場合はストレスを感じるようになります。
クラス替えは基本的に1年ごとなので、クラスの雰囲気やノリが合わなくも、次の年まで上手くやっていかなければいけません。
また、クラスメイトとのケンカや言い合いなどが起きた場合、しばらくは気まずい思いをするでしょう。
そういったことを避けるために、極力トラブルのないよう慎重に行動するようになり、自分の個性を出せないことにストレスを感じることもあるのです。
また、最近では、SNSを通してのトラブルも問題になっています。(参考:総務省『インターネットトラブル事例集(平成29年度版)』)
なかでも、LINEなどでのトラブルは問題になることもあります。
LINEは、文字での会話が基本なので、感情を伝えにくく誤解を生むことが多いです。
そのため、ささいなことでトラブルになり、仲間外れにされたり、悪口を言われるようになることがあります。
高校生の子どもを持つ私の知人は、「子どもは、家にいる間はずっとスマホを手放すことがない」と言っていました。
家に帰ってきたお子さんは、SNSを通じたクラスのメンバーとの交流のために、ずっとスマホを気にしているそうです。
お子さんは、「誰かが情報を発信したあとには、いち早く反応して乗り遅れないように」と気を遣います。
話についていけなくなると次第に孤独を感じるようになり、特にLINEなどで既読がついているのに返事がないと不信感につながるなど、SNSでの人間関係にも気を遣うことが多いのです。
そのため、家に帰ってきても人間関係に神経をすり減らし、気持ちが休まることがありません。
理由④部活が合わない

4つ目は「部活が合わない」です。
希望に満ちて部活に入ったとしても、「思っていたものと違う」と違和感を抱くこともあります。
その原因のひとつに、活動時間の長さがあります。
小学校でもクラブ活動はありますが、中学校や高校の部活動は本格的になります。
朝練や放課後の練習は長時間に渡り、土日も練習や試合のスケジュールを組まれていることも少なくありません。
小学校のときは帰宅後は友達と遊び、土日は家族と過ごしていた時間が、すべて部活動に費やすことになり、自由な時間が減ることにストレスを感じるのです。
また、部活が合わないと感じる原因には、「先輩・後輩の上下関係」にもあります。
小学校では優しかった近所のお兄さんお姉さんや先生が、「同じ部活の厳しい先輩」になった場合、その変化に戸惑うのです。
先輩になったとしても後輩を指導する立場として、気軽に話せる機会も減ることがあります。
その結果、先輩や後輩、顧問の先生に気を遣い、ストレスを感じることが増え、学校が合わないと思うようになる子供もいるのです。
理由⑤校風が合わない

5つ目は「校風が合わない」です。
実際の校風は、その学校に入学しないとわからないものです。
例えば、進学校の場合は、成績に重きを置く学校も珍しくありません。
中にはテストの結果が掲示され、成績ごとにクラス分けする学校もあります。
その結果、成績が悪い状態が続くと自信を失い、クラスメイトや先生からの視線が冷たく感じることもあるようです。
入学前にその学校の校風を理解していても、入学してから実際に体験することも多いのです。
また、「自由な校風」に魅力を感じる人は多いかもしれません。
自由な校風の学校は、本人の自主性を尊重するので、何でも自由に挑戦できることが多いです。
しかし逆に、「行動が自己の責任に任されることが多いため、細かく面倒を見てくれるわけではない」という状況もあり得ます。
そういった環境は、言われたことを着々とこなすことが得意な子どもにとっては、手助けが少なく不安に思うこともあります。
つまり、入学前に「自分に合う学校」と思って入学したとしても、入学後に学校が合わないと思うこともあるのです
理由⑥授業のペース・レベル・方針が合わない
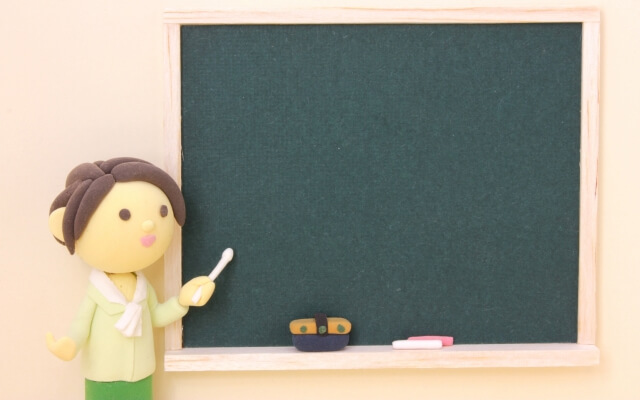
6つ目は「授業のペース・レベル・方針が合わない」です。
学校での授業は、クラス全員に向けて行われます。
全員に対して同じ内容と同じスピードで授業を行うので、当然ながらそのペースに合う人と合わない人が出てくるのです。
また、塾に通っていている子は、学校での授業は簡単で物足りなさを感じるでしょう。その一方で、授業についていけないことで、勉強を苦手に感じる子もいるはずです。
また、高校での勉強では、レベルや授業方針が合わないという声も耳にします。
高校に入学するためには入試があり、その入試に合格した、学力が同じレベルの子たちが高校には集まります。
しかし、周囲が同じレベルの子たちだからといって、安心できるわけではありません。
特に進学校では、基礎ができていることが暗黙の了解のようにあり、授業内容が高度であることが多いです。
併せて、予習・復習が前提で、前回の内容をすべて理解したとして授業が進められていきます。
そのため、わからないことが増えていくと、その遅れを取り戻すことが次第に難しくなるのです。
実際に、進学校に入学した友人のお子さんは、「入学して授業の難易度やスピードの速さに驚いた」とあせりを感じていました。
せっかく第一志望の学校に入学したのに、授業についていけなくなると、「自分のレベルに合わない学校に入ったのではないか」と不安になることもあるのです。
理由⑦通学環境が合わない

7つ目は「通学環境が合わない」です。
小中学生では、公立の場合は自宅の近くの学校に通います。一方、私立の場合は初めての電車通学やバス通学を経験することも多いです。
そして、お子さんが高校生の場合は、公立・私立を問わず、自宅から離れた学校に通うこともあると思います。
家から離れたところに通う場合、通学時間が長くなり、中には往復3時間以上もかかる場合もあると聞きます。
当然、学校から遠いところに住んでいる人は、授業に間に合うように家を早くでなければいけません。また、部活で朝練がある子はさらに家を早く出るので、睡眠時間も短くなるでしょう。
また、自転車で30分以上かけて通学する子の場合は、体力を消耗するうえに、多少の雨でも自転車に乗る必要があります。
学校に着いたときには疲れていて授業に集中できず、帰宅後もしばらく休憩をとることが多かったという友人のお子さんもいました。
このように慣れない電車やバスに乗ること、長時間の自転車通学は、親御さんの想像以上に疲れが溜まるのです。
この繰り返しによって通学することがつらく、不登校になる子もいます。
入学後に「学校が合わない」とならないためには、学校の雰囲気や校風、偏差値などに加えて、通学環境がお子さんにとって無理がないものかを確認することが大切です。
理由⑧他にやりたいことがある

最後は、お子さんに「他にやりたいことがある」です。
学校生活を送っているうちに、勉強や部活とは別に、やりたいことが見つかることもあります。
やりたいことが見つかって、真剣に取り組もうとすると、いま受けている授業や学校生活に物足りなさを感じるようになるのです。
例えば、興味のある分野の専門知識を高めるために、高専に転校して学び直したいと思うこともあるでしょう。
そして、今通っている学校で受ける興味を持てない授業や、学校生活そのものが苦痛になり、「学校に行かない選択肢」を考えるようになるのです。
また、経済的に困難な状況にあるご家庭などでは、家族や親御さんを助けたいという気持ちから、「学校に通わずにバイトをしたい」「就職をしたい」という希望を持つ子もいます。
このように、「学校に通うことはいまの自分には合わない」と思い、いまの環境がもどかしいと感じるようになるのです。
「学校が合わない」と感じた人の体験談

学校が合わないと感じる理由は、人それぞれです。
原因がひとつの場合もあれば、さまざまな要因が重なって、悩みが大きくなることもあります。
キズキ共育塾にも、学校が合わないと感じたことがある人がたくさんいます。
ここで、過去のコラムから、その体験談の一部を抜粋してご紹介します。
参考コラム
私が明確に学校を嫌いになったのは、高校2年生のときでした。
それまでにも、大きな学校行事や緊張する発表の前などに、ぼんやりと「学校へ行きたくない」と思うことはありました。
特に私が疲れていたのは、学校の人間関係です。
私の学校には、何年生になってもクラス内にグループの上下関係がありました。
俗にいう「スクールカースト」ですね。
高校2年生のときには、その上下関係が強いクラスになってしまったのです。
違うグループの人と話すときにも気を遣う上に、授業やグループ学習で発表するときには場の空気を読んで発言できないと「シラケる」という緊張感がありました。
「学校には勉強をしに来ているのに、どうして勉強以外のところでこんなに疲れなきゃならないんだろう?」
この時点で、私は「学校が嫌いだ」と明確に思うようになっていたのです。

以上、体験談の一部をご紹介しました。
これは、「人間関係が原因で学校が合わない」と感じたケースです。
私の高校時代にもスクールカーストはありました。
スクールカーストとは、生徒間に自然発生する人気の度合いを表す「序列」のことです。(内閣府『平成25年度青少年問題調査研究会 第1回講義録』)
私の場合だと、スクールカーストの頂点になっていたのは、クラスで目立つ人や、人気のある人、テニス部やバスケ部など運動部に所属している人たちでした。
その人たちがクラスでの決定権を持っていて、何かを決めるときは彼らの意見が優先されるようになり、他の人たちはそれに従うことが多かったです。
彼らと同じ意見や気持ちであれば、楽しい学校生活が送れます。ですが、そうでない場合は理不尽な思いをすることもあります。
例えば、みんなが盛り上がっているところに反対意見を言えば、周囲から「この人は空気が読めない」と思われます。
その結果、気まずい思いをしたくないので、「自分の意見は絶対に言わない」ということが当たり前になっていたのです。
その場の雰囲気を壊さないように気を遣うのは、学校という集団生活特有のものかもしれません。
社会人になれば、会議などで意見を求められるのは当たり前のことです。みんなの顔色を伺って発言しない、ということはまずありません。
中学や高校での学校生活は、このように大人とは違う独特な常識があることが多いのです。
「学校が合わない」と悩むお子さんへの対処法
ここまで、お子さんが「学校が合わない」と感じる理由をいくつかお伝えしました。
あなたのお子さんに当てはまりそうなケースもあったのではないでしょうか?
理由がわかれば、対処する方法も見つかります。
ここからは、学校が合わないお子さんへの対処法を解説します。
対処法①無理に学校に行かせない

お子さんにとって学校が合わずに、そのまま休みがちになると、不安も大きいでしょう。
「今日は学校に行ってくれるかも」と、親御さんが毎日期待して、お子さんの様子を見ることもあると思います。
休みが続くようになると、「無理にでも学校に行かせた方がよいのでは…?」と思うこともあるかもしれません。
しかし、そこで無理やり学校に行かせることは、よい手段とは言えません。
なぜなら、お子さんは、学校が合わないことで心身ともに疲れており、十分な休養を必要だからです。
そのような状況で、学校に行かない理由を問いつめたり、無理やり学校に行かせたりすれば、お子さんへの負担が増していきます。
まずは、お子さんをしっかり休ませ、学校が合わないことですり減ったエネルギーを回復させましょう。
そして、十分な休息をとれば、気持ちも落ち着き、学校を休む理由を話してくれるはずです。
このときに、「無理をしなくても大丈夫だよ」と伝えるだけで、お子さんはきっと安心します。
「学校が合わないなんて甘え・言い訳」などとお子さんを否定せず、家庭が安心できる場所になるよう、お子さんを信頼し見守りましょう。
対処法②学校以外での居場所をつくる

学校に合わないと感じる場合、学校でうまくやれないことに自信を失うこともあります。
しかし、学校が合わないと感じることは、決して特別なことではありません。
学校以外(アルバイトや習いごとなど)で自分の居場所を見つけ、イキイキとしている子もたくさんいるのです。
私の知人のお子さんも、学校が合わないことで悩んでいました。
自分と合う子がおらず、友達といえるような仲間がいなかったそうです。しかしひとりでいる勇気もなく、無理に周りの人たちに合わせて上手くやっていました。
しかし、人に合わせることにだんだん疲れてきて、学校を休むようになりました。
「学校がすべて」と考えていると、悩みが深くなります。しかし、彼女には学校の他に居場所があったので、そこからの回復が早かったそうです。
その子はダンスが好きで、ダンススクールに通っています。
学校と違ってダンススクールは楽しく、ダンスがうまくなりたいという同じ目標に向かう仲間がいます。
人に無理に合わせる必要がなく、本当の自分を出して、友達と付き合うことができるそうです。
学校が合わないお子さんは、「合わない自分が悪いのではないか」と思うことも少なくありません。
しかし、いろいろな個性の人がいるのですから、「全ての人に合う学校」というのは現状難しいかもしれません。
そのため、学校以外に本当の自分を出せる場所を作ることが大切です。。
先程のダンススクールに通うお子さんは、ダンスを通して自信をつけることができました。
その結果、学校にも行けるようになり、充実した毎日を過ごしているようです。
学校が合わないと感じていても、居場所があれば自信を失うことはありません。
お子さんがやりたいことや好きなことを探していけば、きっと居場所は見つかるはずです。
対処法③転校先を探す

いまの学校が合わないことで、不登校になる人もいます。
そして、学校に行けない日が多くなると、進級や卒業が難しくなります。
その場合は、「合わない今の学校」にとどまるのではなく、他の学校に転校することも選択肢のひとつになります。
文部科学省の調査によると、高校を中退した人のうち、25.2%の人が別の高校に転校しています。(参考:文部科学省『令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果』)
25.2%というと少ないように思うかもしれません。ですが、高校中退の理由の中で「別の高校への転校」は2番目に大きな割合を占めます。
毎年、多くの人が他の高校に転校しているのです。
いまの学校が合わないと感じているのであれば、無理をして通い続ける必要はないかもしれません。
転校する大きなメリットとして、これまでの環境をリセットできることが挙げられます。
学校の校風が合わなかったり、人間関係がうまくいかなかったりする場合、転校は大きな転機になるはずです。
よい先生との出会いが学習の意欲を高めることにも繋がったり、よい仲間との出会いにより充実した学生生活を送ることができるようになったりするでしょう。
毎日通うことが難しいのであれば、通信制高校への転校もできます。働きながら学校に通いたいのであれば、定時制高校への転校も検討してみるとよいでしょう。
全日制にこだわることはなく、お子さんに合う学校に転校することで、無理なく学校に通えるようになることもあります。
「学校が合わない」と相談された際には、お子さんの話をしっかり聞き、一緒に寄り添って進路を考えてみてください。
合わせて人気のページ
対処法④信頼できる専門家に相談する

これまで、学校が合わない場合の対処法をお伝えしてきました。
家庭内で解決できることもあります。ですが、一番大切なことは、信頼できる相談先に頼ることです。
家庭内だけで悩みを抱え込むと、親御さんもが疲れきってストレスを溜めることになります。
- 不登校の原因は、本当にいまの学校と関係があるの?
- 人間関係でつまずいた場合はどうすればいいの?
- 転校先はどうやってみつけるの?
「学校が合わない」とお子さんから言われたことについても、専門家に相談することで解決できる場合も多いです。
まずは、学校の担任の先生やスクールカウンセラーに相談することをオススメします。
その他にも教育支援センターや児童相談所、フリースクールなどがあります。
- 児童相談所、児童相談センター(18歳未満)
- ひきこもり地域支援センター
- 発達障害支援センター
- 教育センター(高校相当年齢) 各自治体のウェブサイトに詳細が記載されています。 「教育センター ○○(市区町村名)」で検索してください。
不登校の悩みを相談できる団体や機関は他にもたくさんあるので、専門家の力を借りて少しでも早く悩みが解決しましょう。
参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校新聞、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。
このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。
このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。
公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら
私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。
まとめ:「学校が合わない」と悩むお子さんの不安に寄り添いましょう

中学校や高校に通う子どもは、思春期を迎えることによる気持ちの変化や、学校ならではの特殊な環境などにより、親には気づかないところで、深い悩みを抱えていることが多いです。
問題に早く気づき対応するためには、日頃からお子さんと密にコミュニケーションをとることを意識してみてください。
そして、お子さんの小さな変化にも気づけるよう、見守ることが大切です。
しかし、お子さんの変化にいち早く気づいたとしても、親御さん自身だけでは解決することが難しい場合もあります。
「学校が合わない」と悩んでいるのは、あなたのお子さんだけではありません。
また、学校というシステムに合わないことは、おかしいことでもダメなことでもないのです。
キズキ共育塾では、学習面だけでなくお子さんの精神面のフォローもさせて頂いております。
問題に一緒に取り組み、自信を持てるようになった結果、前に一歩踏み出すことができた生徒さんがたくさんいらっしゃいます。
学校が合わないとお子さんが悩んでいらっしゃいましたら、まずはキズキ共育塾にご相談ください。