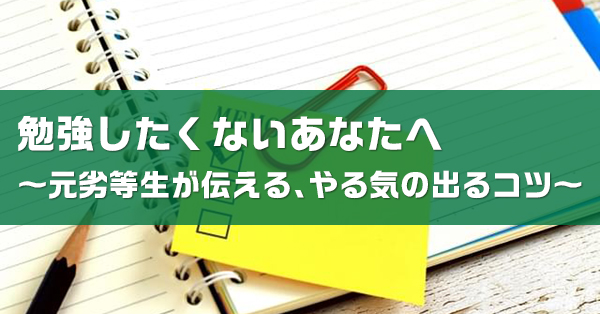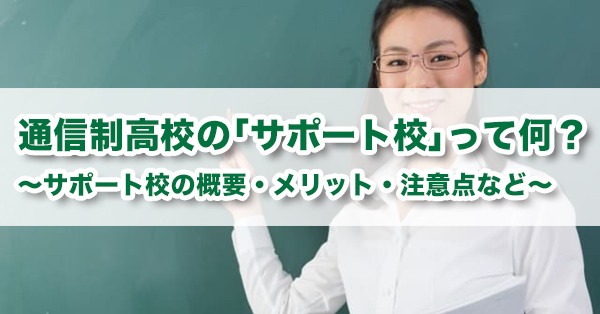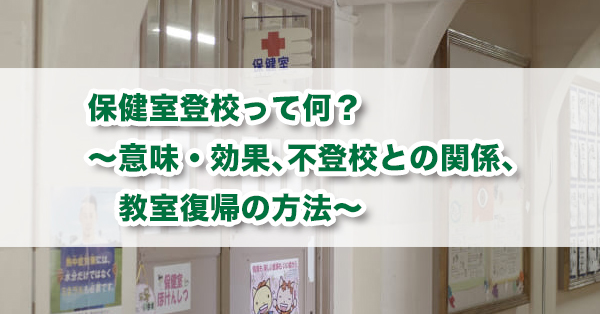学校が嫌いなあなたへ 対処法や別の選択肢を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたは、以下のような学校が嫌いな気持ちで、悩んでいるのではないでしょうか?
- 理由はわからないけど、学校が嫌い…
- 行かないといけないのはわかってるけど、学校が嫌いで行きたくない…
筆者も学校が嫌いだったうちの一人です。学校嫌いのために、高校では不登校になった経験もあります。
ですが、学校が嫌いな気持ちを受けいれたことで、最少出席日数で無事に高校を卒業できました。
このコラムでは、学校が嫌いな理由やオススメの対処法、今の学校以外の選択肢について解説します。
あわせて、親・先生以外の相談先や筆者の体験談、学校が嫌いだった人が次のステップに進んだ体験談を紹介します。
学校が嫌いな学生さんだけでなく、学校嫌いのお子さんを持つ親御さんも、お子さんと接する上でのヒントになるかもしれません。よろしければお子さんと一緒にお読みください。
共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの
アドバイス
学校は、サボっていいのです
昔から学生たちは、いかにサボりながら学校を卒業したか、いかに学校生活で豪快に手を抜いてきたか、などを自慢話として語ってきました。
あなたも、学校側の事情やシステムに必死に合わせる・ついていく必要はありません。学校は、サボっていいのです。このコラムを読んでみてわかるとおり、耐えながらも学校に通った筆者はとてもつらそうでした。
筆者のように最少日数の出席だけで卒業する方法もあれば、別の学校に行く方法もあります。いずれにしても、自分を殺してまで学校に通う必要はありません。それは、昔も今も変わらないのです。
今所属している学校をサボったとしても、あなたが次の一歩に進むための方法は必ずあります。
私たちキズキ共育塾は、学校が嫌いな人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
学校が嫌いな7つの理由
学校が嫌いになる理由はたくさんあると思います。
また、あなた以外にも学校が嫌いな人がたくさんいることを知ってください。
この章では、文部科学省などの資料や、筆者が見聞きしてきた不登校を経験した人の意見をもとに、学校が嫌いになる代表的な理由について解説します。(参考:文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」、千葉県「不登校の要因と背景」、日本財団「不登校傾向にある子どもの実態調査」)
ただし、ここで紹介する理由はあくまで一例です。実際のあなたに当てはまらないかもしれません。また、紹介した理由で必ずしも学校が嫌いになるとは限りません。参考としてご覧ください。
理由①教師・友達との関係がうまくいかない

教師や友達との人間関係は、学校嫌いや不登校の原因になりえます。
文部科学省の調査でも、不登校の要因として「いじめを除く友人関係をめぐる問題」が約9.2%、「教職員との関係をめぐる問題」が約0.2%と、人間関係の問題が10%前後を占めているのです。(参考:文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」)
教室で長い時間授業を受ける学生にとって、教室内の人間関係は、学校の好き・嫌いの判断に大きく影響します。
教師や友人との関係がうまくいかない場合、学校が嫌いになるのは当然と言えるでしょう。
理由②嫌がらせ・いじめを受けている
嫌がらせやいじめも、代表的な学校が嫌いになる理由です。
家族や先生が気づきにくい場合もある上に、自分から家族や先生に相談することを恥ずかしく思う人もいるでしょう。
メディアでも学校の対応が批判されることが増えてきたため、相談できないことの深刻さも知られてきています。しかし、それでも充分とは言えないのが現実です。
嫌がらせやいじめで学校が嫌いになって通いたくない人は、一度勇気を出して信頼できる周りの大人や専門機関などに相談してみましょう。
いじめの原因や対策については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
理由③朝起きられない

学校は始業時間が決まっているため、朝起きるのが苦手な人にとっては通学が大変です。
また、登校できたとしても昼夜逆転の生活になっていると、眠気と戦いながら授業を受ける必要があります。そうなると、学校がつらくなり、学校を嫌いになりやすいのです。
夜遅くまでゲームをしたり、スマートフォンばかりを触ったりしている人は、特にこの傾向が強いでしょう。
また、病気が関連して朝に起きられないケースもあります。気になる場合は、一度病院に行って受診することを検討してみてください。
朝起きる方法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
理由④学校のイベントが嫌い
定期的に催される学校のイベントが嫌い・苦手ということも、学校嫌いの理由としてよく挙がります。
運動の苦手な人であれば運動会や体育祭、集団行動の苦手な人であれば学園祭の催しや準備などでストレスが溜まりやすく、学校が嫌いになりやすいのです。
また、学内行事ではグループ行動がメインになります。そのため、こちらで挙げた人間関係が難しいと感じている人にとっても、イベントがつらく感じることも多いでしょう。
理由⑤授業の進度が合わない
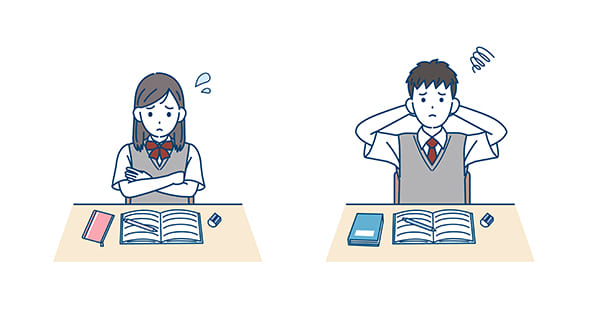
授業の進度が合わず、学校が嫌いになるケースもあります。
例えば、以下のとおりです。
- 学習塾などでの勉強が進みすぎて、学校の勉強が無意味に感じられるケース
- 勉強についていけずに授業が苦痛に感じられるケース
どちらにしろ、学校で過ごす時間の多くは、座って授業を受ける時間です。自分に合わなければ毎日毎日、嫌な時間を過ごすことになるでしょう。
勉強のやる気が出る方法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
理由⑥学校のルール・暗黙の了解に縛られたくない
学校には、校則や暗黙の了解がたくさんあります。
そうしたルールに縛られることがわずらわしく、学校が嫌いになるケースも少なくありません。
例えば、筆者は、毎日同じ制服を着て同じ時間に通学するのが嫌いでした。
ほかにも、以下のように学生はさまざまなルールに縛られています。
- 好きな髪型にできない
- アルバイトができない
- 部活で謎のルールがある
- 課題や宿題が大量に出される
ルールに納得できない、一応納得はしているけれどストレスになる、などの場合に、そのルールが原因となり学校嫌いになるのです。
なお、どうしても遅刻する、どうしても課題提出を忘れる、などルールを守ることが難しい人の中には、発達障害などが関係する可能性も考えられます。
気になるようでしたら、一度病院に行って検査を受けてみるのもよいでしょう。
発達障害やアスペルガー症候群については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
理由⑦集団よりも一人でいる方が楽

学校では、集団行動が基本です。
1人で過ごす方が楽だ感じる人にとって、集団行動を強いられることは学校嫌いの一因になります。
しかし、学校は、科目の勉強をするだけでなく、社会生活や人間関係を学ぶ場でもあります。そのため、集団行動をある程度は受け入れることが必要です。
とはいえ、自分にどうしても合わない集団はありますし、またそもそも1人の方が楽だと感じるのも一つの個性です。
「集団に馴染めない自分はダメな人ではないか…」と落ち込んだり不安になったりする必要はありません。
学校が嫌いな人にオススメしたい4つの対処法
「学校が嫌い」と思うことを、なんとかする方法はたくさんあります。
この章では、学校が嫌いな人にオススメしたい、学校と折り合いをつけるための対処法について解説します。
大切なのは、学校が嫌いと一言で完結させるのではなく、具体的にどこが嫌いなのかを考えること、そして、周囲の人を適切に頼ることです。
対処法①「学校嫌いは変なことではない」という意識を持つ

学校が嫌いな人に覚えておいてほしいのが、「学校が嫌いなのは、変なことではない」ということです。
学校が嫌いなのはあなただけではありません。 そして、無理に学校を好きになる必要もないのです。
人によって、環境の合う・合わないは、どうしてもあります。
まずは、学校が嫌いな気持ちが変だとは思わず、自分の気持ちを素直に受け入れてみてください。
対処法②学校の好きなところ・嫌いなところを書きだす
2つ目の対処法は、学校の好きなところと嫌いなところを紙に書きだすことです。
単に、学校が嫌いと一言で片付けていると、学校の何が嫌なのかがわかりません。
嫌いなところを具体的に紙に書きだすことで、あなたにとって学校の何がストレスになっているのかが見えてきます。
そして、ストレス源がわかると、具体的な対処法や、親・学校への相談内容も見えてくるはずです。また、周りの人に自分の気持ちを伝える時の説得力も生まれるでしょう。
加えて、学校の好きなところも書き出してみてください。そうすることで、「嫌いな部分もあるけど、好きな部分の方が大きいから大丈夫だな」と考えが変わり、悩みが減ることがあるからです。
学校嫌いでお悩みの人は、ぜひ一度好きなところと嫌いなところを紙に書いてみましょう。
対処法③耐えられないことは家族や先生に相談する

学校で耐えられないことがあるときは、家族や先生に素直に相談してみてください。
大人であっても、悩みを一人で抱え込むと心身の調子を崩すことがあります。悩みの解決方法がわからないのは仕方のないことなのです。
周りのさまざまな人を頼ることで、悩みは解決できる可能性があります。
親や先生など、周りの大人をどんどん頼ってみてください。
人によっては、知り合いに自分の悩みを話すことが恥ずかしかったり、周りの誰が信用できるのかわからなかったりすることもあると思います。
自分の周りの人を頼れないときは、役所やNPO法人が運営する相談窓口を利用することがオススメです。
例えば、インターネットで「〇〇市(町) 中学生 悩み相談」と検索すると、相談窓口が見つかります。
人に相談すると気持ちが軽くなりますし、自分一人よりも具体的な解決方法が見つかりやすくなるでしょう。
対処法④本当に学校が嫌いで登校したくないときは休む
4つ目の対処法は、本当に学校が嫌いで登校したくないときは休むことです。
嫌いな学校に無理に登校すると嫌な記憶が染みつき、次の登校が余計につらくなります。
そのため、これまで紹介した方法も試しつつ、思い切って休んでください。
学校を休むことは悪いことではありません。一度休んで、気力・体力が回復すれば、学校が嫌いな気持ちがやわらいでいきます。そして、また元気に登校できるようになるはずです。
しかし、一度休んだ後に登校再開する気にならず不登校になると、出席日数が少なくなります。
そうなると、授業についていけなくなったり、人間関係が希薄になったりする可能性があるのです。
また、中学生は高校入試に影響があったり、高校生は留年・退学の可能性があったりする可能性があることも、覚えておいてください。
とはいえ、そんな場合でも、必要以上に不安になる必要はありません。
こちらで解説するように、今の学校以外にも、選択肢はたくさんあるからです。
学校が嫌いな人に伝えたい、今の学校以外の選択肢
この章では、どうしても今の学校が嫌い・合わないと感じている人に向けて、今の学校以外の選択肢について解説します。
昔に比べて、学校嫌いだったり不登校だったりする人を対象とした学びの場が増えています。
そのため、あなたに合った学びの場が見つかるはずです。これからお伝えする内容を参考にして、学校が嫌いと思う気持ちが和らぐ選択肢を探してみてください。
選択肢①フリースクール

フリースクールとは、ひきこもりや不登校の人など、学校に馴染めない人たちのための教育機関のことです。
主に、NPO法人や個人によって運営されています。
学習面に力を入れていたり、精神面や生活面での支援が中心であったり、人との交流が盛んだったりするなど、運営方針は団体によってさまざまです。
共通するのは、通う人にとって安心できる居場所としての側面が強いことです。
そのため、今通う学校に対して学校が嫌いと思っている人でも、安心して通えるでしょう。
なお、フリースクールは、スクールとは言うものの、正式な学校ではありません。
そのため、高校生の年齢の人がフリースクールを入学・卒業しても、正式な学歴には反映されません。
ただし、あなたの学校がフリースクールと提携している場合は、フリースクールへの出席日数が学校への出席日数としてカウントされます。
また、フリースクールで勉強して高卒認定試験に合格すれば、大学受験も可能になります。
自分に合うフリースクールがあるか、学校との提携があるかなどが気になる場合は、まずはインターネットで調べてみましょう。
選択肢②通信制高校
通信制高校とは、通信教育で学習する単位制の高等学校課程のことです。
全日制高校や定時制高校のように毎日通学する必要がないため、場所を選ばずに勉強できる点が特徴です。
また単位とは、その科目をしっかり勉強した証明のようなものです。高校で卒業要件を満たすためには、一定以上の単位の取得が必要です。
通信制高校での勉強は、学校から送られてくる教科書や動画などの教材を利用して、自宅で行います。成績は、レポートの提出やテストの点数で決まります。
卒業の要件を満たせば、高校卒業資格が得られ最終学歴が、高校卒業(高卒)になります。
学校嫌いで学校に極力通いたくない人、人間関係や集団行動が苦手な人にオススメです。
通信制高校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
選択肢③定時制高校

定時制高校とは、夜間、もしくは昼間の決められた時間に通学して、学校で学習する高等学校課程のことです。
1948年に勤労青少年(就業などのために全日制高校に進学できない青少年)のために発足しました。
定時制高校は、全日制高校より1日の授業時間が少ないことが多く、通学する時間帯も朝・昼・夜など選べます。
全日制高校とは異なる時間帯にも授業を受けられるため、朝起きることが苦手な人にオススメです。(参考:文部科学省「三 新制高等学校の発足:文部科学省」)
また、定時制高校では、元不登校の人や高校中退を経験した人など、さまざまな事情を抱えた人に出会うことができます。 そのため、今の学校の雰囲気や人間関係は嫌だけど、自分と似た境遇の人と関わりたいという人には、向いている環境と言えるでしょう。 通信制高校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。 サポート校とは、通信制高校に通う生徒のために、通信制高校の仕組みやカリキュラムに対応して学習を支援する、学習塾や予備校のような教育支援機関のことです。 サポート校では、以下のような支援を行っています。 サポート校は、通信制高校の生徒は必ずいけないというものではありません。 また、サポート校は名前のとおり通信制高校の勉強のサポートが目的なので、サポート校で授業を受けただけでは単位は取れません。 サポート校にも特色があり、日常の勉強に加えて大学受験のサポートをしているところもあれば、ITやデザインなどの専門知識を学べる学校もあります。 特に、勉強嫌いで不登校になり勉強が不安な場合は、進学を考えている通信制高校にサポート校があるかということもポイントになるでしょう。 サポート校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。 学校嫌いで不登校の状態になると、勉強が遅れることを不安に思う人もいるかもしれません。 しかし、学校に行っていない状況でも、学習塾などを利用して勉強を進めることは可能なのです。学習塾に通うと以下のようなメリットが得られます。 また、学習塾には以下のようなさまざまな種類があるため、自分に合った環境で勉強ができます。 中には学習面だけでなく、メンタル面やコミュニケーション面などのサポートを行っている塾もあります。私たちキズキ共育塾もそのひとつです。自分に合った学習塾を探してみてください。 高卒認定試験とは、正式名称を高等学校卒業程度認定試験と言います。 さまざまな理由で高校等を卒業していない人のために、高校を卒業した人と同等以上の学力があると文部科学省が認定するための試験です。 かつて存在した大学入学資格検定(大検)という試験が、2005年度(平成17年度)から名称と一部内容を変更して移行したものです。 合格のためには、全部で8〜10科目の筆記試験に合格する必要があります。 合格すると、高卒資格が必要な大学・短大・専門学校の受験や、一部の公務員試験の受験が可能になります。 また、一部の民間企業では、高卒とみなして応募できるようになります。 高卒認定試験は高校在学中でも受験できます。 そのため、転校・留年からの高校卒業と高卒認定の取得の両方を目指し、早く得た方の資格で大学を受験することも可能なのです。 なお、高卒認定試験の合格は学歴にはなりません。 合格後に専門学校や大学などを卒業しなければ、最終学歴が中卒のままであることは覚えておいてください。 高卒認定試験については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。 学校が嫌いという悩みは、親や学校の先生以外に相談することもできます。 この章では、学校が嫌いな人のための親・先生以外の相談先を紹介します。 いざ相談するとなると、「人に相談するような悩みではないかも」「相談窓口を使うのは大げさすぎるかも」などと、迷うことがあるかもしれません。 しかし、あなたの悩みを1人で抱える必要はありません。また、誰かに話を聞いてもらうことで気持ちが軽くなったり頭がスッキリしたりすることもあります。 「親や先生には相談しづらい、したくない」と思っている人は、ぜひ参考にしてみてください。 1つ目の相談先は、スクールカウンセラーです。 スクールカウンセラーは、児童生徒の心のケアを行う専門家です。そのため、学校が嫌いという悩みについても、しっかりと受け止め、話を聞いてもらえるでしょう。 ただし、スクールカウンセラーは、常に学校にいるわけではないこともあり、特定の曜日・時間に学校を訪問するという場合もあります。 そのため、スクールカウンセラーに相談したい場合は、担任の先生以外でも構わないので、話しやすい先生を見つけて「スクールカウンセラーと話したい」ということを伝えてみてください。 2つ目の相談先は、チャイルドラインです。 チャイルドラインは、18歳未満の子どもが無料で利用できる相談窓口です。電話に抵抗がある場合は、チャットでの相談もできます。 参考:チャイルドライン 3つ目の相談先は、よりそいホットラインです。
こちらは、どんな人でもどんな悩みでも相談することができる相談窓口です。
参考:よりそいホットライン 4つ目は、あなたのいばしょチャット相談です。 24時間365日、年齢や性別を問わず誰でも無料・匿名で利用できるチャット相談窓口です。 5つ目は、ユキサキチャットです。 不登校・中退・経済的困難など、さまざまな事情がある13~19歳までの進路・就職・生活に関する相談を受け付けています。 参考:ユキサキチャット 筆者は高校2年生の始めから卒業するまで学校が嫌いで、ほとんど学校に通いませんでした。しかし、最少出席日数で高校を卒業できています。 学校が嫌いだった筆者が最少出席日数で卒業できた理由は、以下の2つだと思います。 この章では、学校が嫌いな人の学校との向き合い方の例として、高校時代に学校が嫌いだった筆者自身の体験談を紹介します。 私が明確に学校を嫌いになったのは、高校2年生のときでした。 特に私が疲れていたのは、学校の人間関係です。 私の学校には、何年生になってもクラス内にグループの上下関係がありました。俗にいうスクールカーストです。 高校2年生のときは、その上下関係が特に強いクラスになりました。 違うグループの人と話すときはとても気を遣います。その上、授業やグループ学習で発表をするときにも、場の空気を読んで発言できないとシラケるような緊張感がありました。 「学校には勉強をしに来ているのに、どうして勉強以外のことでこんなに疲れなきゃならないんだろう?」。この時点で、私は「学校が嫌い」と明確に思うようになっていました。 さらに、1年生のときから学習塾に通っていた私は、学校の授業の進み具合が遅く感じていました。 こういったことが重なり、学校の人間関係や勉強のことを考えるうち、学校に通う意味がわからなくなりました。 そして、高校2年生の梅雨の時期に熱っぽさを感じて休んだ日から、登校するのが面倒になり、そのまま不登校になりました。 不登校になると、さまざまな考えが頭をよぎります。 個人的につらかったのは、両親を心配させていたことです。 子どもが不登校になった親御さんの中には、お子さんを怒る人もいらっしゃるでしょう。 ですが、私の両親は逆で、気を遣いすぎるあまり、はれ物を扱うような対応になっていました。 怒ることも気を遣うことも愛情からだと頭では理解できますが、どちらの状況も不登校である立場からするとつらいものです。 私の場合は、「自分は親を心配させている親不孝者だ」と思い、罪悪感が強かったことを覚えています。 そんな状況が続いた高校2年生の夏に、担任の先生が家庭訪問に来てくれました。 そして、「学校の何が嫌いなのかを紙に書いてみたら?」と提案してくれたことで、流れが変わりました。 私は自室に戻り、自分が考える学校の嫌いなところを、以下のように書き出しました。 そして、こうした学校の嫌いなところがなくなったら、学校に通えるかもしれないと考えたのです。 私は後日、母親と先生がいる三者面談の場で、学校の嫌いなところを話しました。 甘えだと言われるかもしれないという不安があり、とても怖かったのをよく覚えています。 ですが、自分にとって学校がどれくらい嫌いなのか、なぜ学校が嫌いなのかを必死で訴えました。 そして、私がどれだけ苦しんでいるかを知ってもらえたのか、その後は、どうすれば学校に通えるかを3人で考えられるようになっていきました。 そのときに先生が話してくれた話の中で、いまでも印象に残っている言葉があります。 「学校が嫌いなら嫌いでもいい。無理に好きにならなくても大丈夫。自分に合った方法で通って卒業すればいいよ」。この言葉で、気持ちが楽になったことを覚えています。 そして、クラスの人間関係や教室の雰囲気に耐えられないなら、毎日でなくてもいいし時間も気にしなくていいから、まずは夏休み明けに保健室登校から始めてみようという結論になりました。 なお、保健室登校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。 私の場合は、保健室であれば学校に通うことに抵抗がありませんでした。そのため、夏休み明けからは、しばらく保健室登校を続けました。 先生から、「教室に戻ってみてはどうか?」と提案されることがときどきありました。ですが、自分の調子と合わせて切り替える方法で、自由にさせてもらえました。 個人的に驚いたのが、私のほかにも保健室登校をしている人がたくさんいたことです。 教室にいる同級生と比べておだやかな性格の人が多く、人数も少なかったため、居合わせた人とさまざまな話をしました。 どうして学校が嫌なのかを教えてくれる人もいて、共感できることも多く、気持ちが楽になりました。 3年生になってからも、教室で授業を受けたり、保健室登校をしたり、家で自習したりと、自分の気持ちを周囲に相談しながら学校嫌いと折り合いをつけていました。 そして、私は最少出席日数で高校を卒業できたのです。 卒業するときに担任の先生から、「君の出席日数は、歴代でいちばん少なかったぞ」と言われました。 その後は大学に進学・卒業し、今は社会人として働いています。 筆者の経験からお伝えしたいのは、「学校が嫌いでもなんとかなる。将来が閉ざされているわけではない」ということです。 この章では、学校が嫌いだった経験のあるキズキ共育塾の生徒さんの体験談を紹介します。 学校が嫌いで不登校になっても次に進める、世の中にはいろいろな選択肢があるなど、あなたの視野や考えが広がるきっかけになるはずです。 広橋さん(仮名)は、中学受験に合格し中高一貫校に進学しましたが、学校の勉強についていけず不登校になりました。 また、中学受験を経験したことによる受験の燃え尽きもあったそうです。 そして、親からの提案もあり、1年生の秋くらいには別の中学校に転校。 転校後は、高校受験で不利になる出席日数の3分の2を下回らないことを意識しながら、自分のペースで学校に通っていました。 こちらの学校でも内部進学で高校に進学することはできましたが、人間関係がみんな同じ地点からスタートする環境に身を置きたいという思いから外部進学を決意したそうです。 そして、高校受験のためにキズキ共育塾に通い始めました。 勉強が順調に進まないこともあったそうですが、講師のサポートもあり無事志望校に合格することができました。 広橋さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。 成田さん(仮名)は、高校2年生の頃に学校に行けなくなりました。 学校が嫌いになった明確なきっかけがあったわけではないそうですが、自分が高校に行っている理由がよくわからなくなり、考える時間がほしくなったそうです。 不登校になってからは、ゲームや漫画、アニメばかりの昼夜逆転生活になり、学校に復帰することはなく高校を中退しました。 しかし、なんとなく大学に行きたい気持ちがあったため、キズキ共育塾への通塾を開始。基礎から地道に勉強し直しました。 そして、高卒認定試験に合格、大学受験でも第一志望校に合格することができました。 成田さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。 堀内さん(仮名)は、中学3年生の頃に理由を思い出せないくらい学校が嫌いになり不登校になったそうです。 その後、海外に興味を持ち実際に留学しましたが、人見知りな性格のため現地の学校でもつらい状態が続き、転校、そして退学しました。 日本に戻ってからは、独学で高卒認定を取得し、大学受験のためにキズキ共育塾に通うことになりました。 堀内さんは、キズキ共育塾の落ち着いた暖かい雰囲気が自分に合っていると感じ、安心して勉強に取り組むことができたそうです。 そして、立命館大学理工学部に合格することができました。 堀内さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。 中村さん(仮名)は、高校の指導方針や先生の対応などが合わないことから成績が悪化。 さらに、クラスメイトから悪口を言われるようになり、「居場所がない」と感じ、不登校、そして半年間引きこもることになったそうです。 そんな時に、親からキズキ共育塾を勧められ、乗り気ではなかったものの通塾することになりました。 はじめは、勉強をしていなかった期間のブランクを感じたそうですが、講師のサポートに勇気づけられ、なんと半年間で志望校合格をつかみ取ることができました。 中村さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
大切なことは、学校が嫌いであることで劣等感を覚えたり、自尊心を失ったりしないことです。 とはいえ、学校が嫌いだと、毎日がつらく苦しいと思います。ですが、学校が嫌いなことはおかしいことや変なことではありません。また、あなたを助けてくれる人はたくさんいます。 学校が嫌いな自分を認め、信頼できる人に相談することで、次の一歩を踏み出せます。 このコラムが、あなたの学校嫌いを見つめ直すきっかけになれば幸いです。 さて、私たちキズキ共育塾は、一人ひとりに寄り添う完全個別指導塾です。 生徒さんには、学校が嫌いで不登校中の人や中退した人もたくさんいます。 授業では、勉強だけではなく、学校にどうやって復帰するか、学校に復帰しないなら、どこに転校するか、転校しないならどうするかといったさまざまな相談ができます。 あなたのための学校嫌いの話ができると思います。少しでも気になったらお気軽にご連絡ください。親御さんからの相談も受けつけています。
Q&A
よくある質問
選択肢④サポート校
選択肢⑤学習塾

選択肢⑥高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)
学校が嫌いな人のための親・先生以外の相談先
相談先①スクールカウンセラー

相談先②チャイルドライン
相談先③よりそいホットライン

相談先④あなたのいばしょチャット相談
相談先⑤ユキサキチャット

学校が嫌いだった筆者が最少出席日数で卒業した体験談
学校が嫌いになった理由はスクールカースト

両親を心配させたことがつらかった
きっかけは担任の先生の提案

「学校が嫌いなら嫌いでもいい」
保健室登校をしながら、学校嫌いと折り合いをつけた

将来が閉ざされているわけではない
学校が嫌いだった人が次のステップに進んだ体験談
体験談①勉強のレベルが合わず不登校に。転校を経て高校合格

体験談②学校に行く意味がわからなくなり中退。高認取得後に第一志望校合格
体験談③学校が嫌になり不登校に。退学・留学を経験し大学に進学

体験談④いじめによる不登校を経験。半年間の引きこもり期間を経て志望校に合格
まとめ〜「学校が嫌い」はおかしいことではありません〜