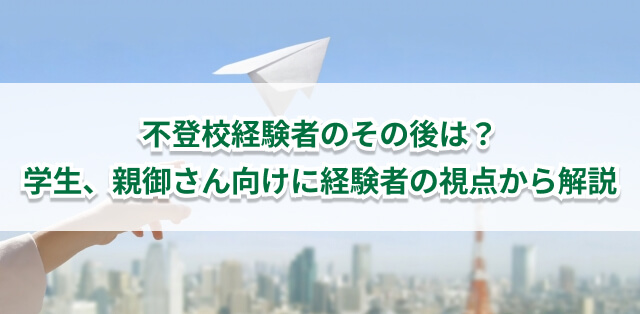不登校の回復期とは? 回復期のサインや親の接し方を解説
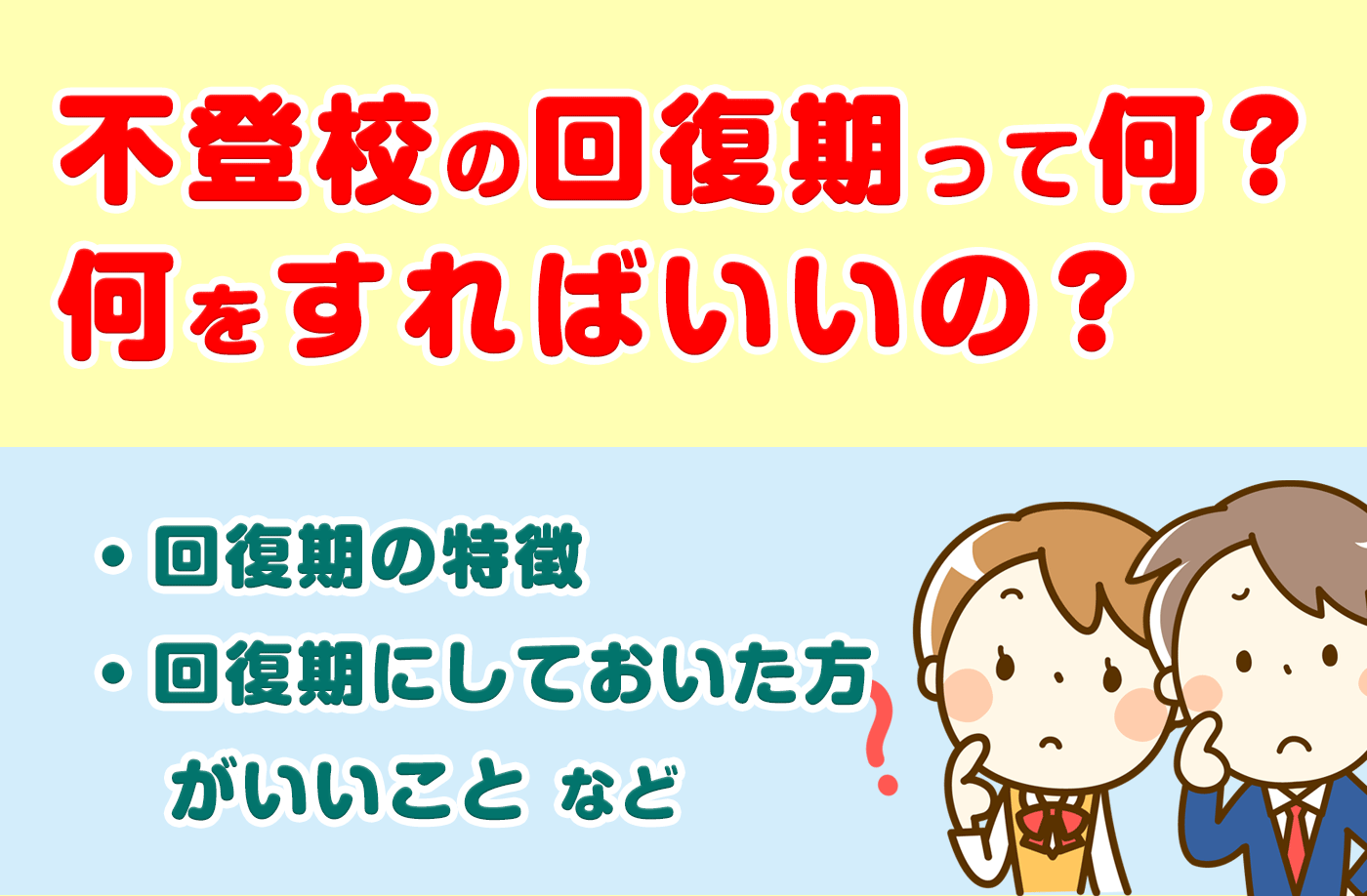
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
不登校状態にあるあなたは、毎日どう過ごしたらいいかわからず悩んでいませんか?
どう過ごすべきかという考え自体は、とても前向きな発想ですね。いまのあなたは、不登校の回復期にあるのかもしれません。
不登校の回復期とは、心の活力が湧いきて活動的になる、不登校の過程においてとても重要な時期です。
この回復期の過ごし方次第で、その後何かにつまずいたときの回復力も変わってきます。
このコラムでは、半年近くの不登校状態を経験した私の経験を踏まえながら、不登校の回復期とは何か、回復期のサイン・兆し、回復期にしておくとよいことなどについて解説します。
このコラムが、不登校に悩むご本人の回復のきっかけに、そして親御さんの助けになりましたら幸いです。
このコラムは、主に不登校の回復期にいるご本人に向けて書いています。ですが、「不登校の回復期の子どもが逆戻りしないか心配」「回復期のお子さんとどう接してよいかわからない」親御さんにも役立つ内容となっています。
共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの
アドバイス
不登校は必ず回復します
いま学校へ行けなくなったあなたにお伝えします不登校状態からは、必ず回復します。
しかし、そのためには思っている以上の時間が必要です。なぜなら、いまのあなたは、自分でも信じられないほどに疲れているはずだからです。(不登校状態になると、自分でも異常かもと思うほど睡眠時間が長くなり、よく寝る人も多いです)
このコラムに書いてあることは、経験者それぞれの所感ですが、不登校状態にある人の多くに当てはまると思います。これからの自分にどのようなことが起こるのか、このコラムを参照にしてみてください。
私たちキズキ共育塾は、不登校状態にある人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
不登校の回復期とは?
不登校の回復期とは、不登校状態の次の一歩に踏み出す元気が出てきた段階・時期のことです。不登校状態から回復するうえで、非常に大切な段階と言えます。
例えば、周囲の人との会話が増えてくる、学校や進路を気にした発言をするなどが、回復のサインと言えます(回復のサインは、後ほど詳しくお伝えします)。
ただし、不登校の回復期とは、医学的・科学的な言葉ではありません。
また、不登校状態から回復期になるまでの期間は、人によってまたは原因や環境によっても違います。「不登校状態になってから○か月経つと回復期に入る」など、期間などに関する明確な基準もありません。
例えば、以下のようなケースも考えられます。
- 不登校の明確な原因が解決して、1か月もかからずに回復期に入る
- 原因は解決していないけれど、回復期になった
- 原因が解決したかどうかに関わらず、なかなか回復期に入らない
不登校の回復期になるかどうかやそのタイミングやそれまでにかかる期間は、人それぞれ異なります。そのため、まずは「あせらなくても大丈夫」だとを覚えていてください。
次に、ここで言う次の一歩とは、いまの学校(クラス)への登校再開だけではありません。
登校再開以外にも、以下のような選択肢があるのです。- いまの学校(クラス)に登校を再開する
- クラスには行かないけど、保健室に登校する
- 学校には通わないけど、塾で勉強を始める
- 別の学校に転校する
このように、前に進むための行動の全てが不登校の次の一歩なのです。
いまの学校(クラス)への登校再開以外に不登校の次の一歩はたくさんあることを覚えておくと、気持ちがグッと楽になると思います。
いずれにせよ、不登校状態からの回復度合いを段階ごとに分けて、その段階ごとの特徴としておくとよいことを考えること自体は、とても有効です。
そこでこの章では、特別支援教育士である下島かほる先生の監修した『登校しぶり・不登校の子に親ができること』に沿って、回復までの段階を見ていきます。
①不登校状態から回復までの3つの段階

下島先生によると、不登校状態から回復するまでの段階は、以下の3つに分けられるそうです。
- 不登校開始期(初期)
- ひきこもり期(中期)
- 回復期(後期)
具体的な期間は人によって異なりますが、各段階の特徴は以下のとおりです。
①不登校開始期(初期)
「不登校開始期」では、腹痛や頭痛といった体調不良などで学校を休む日が増え始めます。遅刻・早退・保健室での勉強をすることが増えるなど、本格的な不登校状態に移っていく境目です。
②ひきこもり期(中期)
「ひきこもり期」では、学校に行かずに、ほとんどの時間を家で過ごすようになります。昼夜逆転生活になったり、学校の話がイヤだったり、家族との関わりを避けたりするなどの様子が見られます。
③回復期(後期)
「回復期」は、学校での人間関係、勉強、将来への悩みなどで疲れた心に、エネルギーが溜まってくる時期です。この回復期を経て、それぞれの不登校の、次の一歩へ進めるようになっていきます。
②不登校の回復期が大切な理由

不登校の回復期が大切な理由は、2つあります。
理由①
回復期は、次のステップを踏みだす「転換点」です。
回復期に、前向きな気持ちを邪魔されたり、ショックなことがあったりすると、ひきこもり期に逆戻りすることがあります。
そのため、回復期にどう過ごすかを考えることは、逆戻りを防ぎ、不登校の次の一歩に進むためにとても重要なのです。
とはいえ、のちほど説明するように、回復期に前のめりになりすぎると、ブレーキが利かなくなり、疲れることもあります回復期であったとしても、「ときにはブレーキを掛けることも必要」と、覚えておいてください。
理由②
回復期に自分の気持ちを前向きにするコツをつかむことで、その後の人生にも活きてくる回復力がつきます。
近年、心理学の世界では、ショックな出来事が起こったときに、ガマンして耐えるのではなく、すぐに回復することが大切だと言われています。
この回復力のことを、心理学の用語で「レジリエンス」と言います(参考:内田和哉『レジリエンス入門 折れない心のつくり方』)。
この「レジリエンス」を人生の早い段階で意識して鍛えることで、社会人になっても折れない底力がつくようになります。
不登校状態からの回復期を、自分が前向きになる方法を知るための貴重な機会だと、ポジティブに捉えてもよいでしょう。
不登校の回復期の5つのサイン
この章では、不登校の回復期のサインをお伝えします。自分に当てはまらないサインや兆しを探してみてください。
不登校の回復期のサインは、以下のとおりです。
- 周囲の人との会話が増えてくる
- 学校や進路を気にした発言をする
- 暇を持て余すようになる
- 外出の機会が増える
- 自主的に勉強を始める
以下、それぞれのサインを詳しく解説します。
注意
「これから説明するサイン・兆しがなければ、不登校の回復期ではない」わけではありません。
例えば、会話が増えてくるというサインがありますが、元々あなたが会話の多くないタイプであれば、会話が増えないことは自然なことです。
逆に、「この特徴があるから自分は回復期になった、元気になった」と期待しすぎないことも大切です。焦らずにあなたのペースで、慎重に過ごすことを心掛けてみてください。
サイン①周囲の人との会話が増えてくる

回復期のサインの1点目は、「周囲の人との会話が増えてくる」ことです。
- 両親・きょうだいなどの家族
- 友達
- 親戚
人によってはこの段階で、以下のような人たちと不登校からの次の一歩に関する相談ができるようになります。
- 学校の先生
- スクールカウンセラー
- 塾の講師やスタッフ
- その他、不登校状態にある学生をサポートする団体など(私たちキズキ共育塾もその一つです)
回復期には、自分から発言したり、人の意見を聞いたりするなどの余裕が見られるようになります。
内容は、学校や勉強の話題に限らず、ゲームやアニメなどの趣味、ニュースなどが多いでしょう。
サイン②学校や進路を気にした発言をする
2点目は「学校や進路を気にした発言をする」です。
ひきこもり期には学校や進路のことをできるだけ考えたくない場合が多いですが、回復するにつれて今後のことが気になってきます。
また、会話が増えたり、暇を持て余したりするようにもなるのです。そういった状況・状態が重なって、実際に自分の将来や進路に関する話題を口に出すことが増えてきます。
サイン③暇を持て余すようになる

3つ目のサインは「暇を持て余すようになる」です。
これは、不登校の状況から実際に動き出す前の兆しとも言えます。
不登校状態から回復してくると、心の余裕とともに何か行動を起こしたい気持ちが出てきます。
これは不登校に限らず、うつ病などで気持ちがすり減っていた人にも見られるサイン・兆しです。
そう言った心理状態のとき、家や部屋のような限定された空間にいると退屈に感じて、暇を持て余すようになります。ただし、最近ではネットゲームやマンガアプリなど、家でも暇をつぶす手段が増えてきています。そのため、こうしたサインが直接的には出てこない人もいるかもしれません。
そんな人は、以下のように「自分は本当にゲームやマンガを心から楽しんでいるのか?」を、自分自身と向き合いながら考えてみましょう。
- 暇を持て余しているから、ゲームをしているのではないか?
- 退屈をつぶすために、マンガを読んでいるのではないか?
あなたが今、暇や退屈を感じていれば、不登校の回復期に入ったと考えてもよいかもしれません。
サイン④外出の機会が増える

4つ目のサインは「外出の機会が増える」です。
不登校の回復期に入ると、「動き出したい・行動したい」などの気持ちが出てきます。その欲求がより外向きに表れてくると、外出の機会が増える傾向が現れるのです。
ただ、あなたが元々インドア派だった場合、こうした変化はない場合もあります。そういう人は、積極的な外出願望ではなく、以下のような外出への抵抗感も考えてみてください。
- 以前よりも、外出がイヤではなくなった
- コンビニにお菓子を買いに行くくらいなら、気にしなくなった
そういう傾向があれば、不登校の回復期に入ったと考えてもよいかもしれません。
サイン⑤自主的に勉強を始める

最後のサインは「自主的に勉強を始める」です。
ひきこもり期などは、学校へ行かなくなったのを機に、そのまま勉強をするのも面倒になり、教科書や参考書に手をつけなくなることも多いです。
しかし、不登校の回復期になると多少のあせりもあって、「そろそろ勉強を始めないと」と思い、勉強を再開する人が多くなります。
自主的に勉強を始めることで、自然と学校や進路のことを考えるようになり、不登校からの次の一歩がより具体的になっていきます。
先ほども述べたように、次の一歩は学校(クラス)とは限らず、以下のような選択肢が考えられるのです。
- 塾
- フリースクール
- 適応指導教室
- オンラインの教材(スタディサプリなど)
フリースクールや適応指導教室は、不登校などの何らかの理由で学校に行きづらい人たちが通う教育施設です。
学校によっては、塾・フリースクール・適応指導教室への出席を学校への出席とカウントできる場合もあります。
気になる場合は、在籍している学校と気になる施設に問い合わせてみましょう。
不登校の回復期にしておくとよい3つのこと〜体験談を紹介〜
不登校の回復期のサイン・兆しが見え始めた時にしておくとよいことは、以下の3つです。
- いろいろな人の話を聞いたり、相談したりする
- 体力を元に戻すための運動をする
- 自分だけのリラックス法を身につける
以下、これらの3つのことを、私の体験談を交えながら詳しくお伝えします。
自分が「不登校の回復期の段階にいるかも」と思う人は、参考になると思います。
体験談①いろいろな人に話を聞いたり、相談したりする

最初に取り組んでほしいことは、いろいろな人の話を聞いたり、相談したりすることです。
私が不登校状態になった原因は、主には以下の2つでした。
- 授業のスピードが合わないこと
- 学校の人間関係に慣れないこと
ひきこもり期の私は、不登校状態になった原因を頭の中で考えて堂々巡りしていました。
しかし、不登校の回復期に入ると「周りの人の考えを聞いてみたい」と思うようになり、両親や学校の先生への相談することが増えました。
人に話を聞いたり、相談したりすることのメリットとして、「自分では思いつかなかった意見をもらえる」「自分の考えを理解してもらえる」などが挙げられます。
また、話すことで自分の考えがまとまってきて、今後の進路をシンプルかつ前向きに考えられるようになることもあるはずです。
そして、この行動が不登校からの回復のきっかけとなりました。
私の場合は、学校はイヤだけど勉強はしたかったため、保健室登校を始めました。
解決策が見つかったのは、いろいろな人の話を聞いたり、相談したりすることを実践した結果だと思っています。
体験談②体力を元に戻すための運動をする

次にオススメしたいのは、「体力を元に戻すような運動をする」ことです。
ひきこもり期は、家にいることが多いため、体力が落ちています。
登校を再開する場合、基本的には通学して朝から夕方まで勉強する上に、体育の授業で体力を使う日もあります。
登校を再開しない場合でも、次の一歩に踏み出すためには、体力が必要です。次の一歩に踏み出した際に疲れすぎることがないよう、体力を元に戻す運動を始めてみましょう。
私は回復期になってから、以下のような簡単な運動をしていました。
- 2日に1回、夜30分程度のジョギング
- 3日に1回、腕立て伏せや腹筋などの筋トレ
運動をすると体力がつくだけではなく、気持ちもスッキリしました。
ただし、あくまでも体力を元に戻すくらいの運動にとどめて、疲れる手前でやめることが大切です。
前のめりになりすると、体調が崩れたり気持ちが落ち込みひきこもり期に逆戻りしたりする可能性があるためです。
ブレーキを踏みながら余裕を持ちつつ、取り組みましょう。
体験談③自分なりのリラックス法を身につける

最後にオススメしたいのは、「自分なりのリラックス法を身につける」ことです。
疲れた気持ちを回復させたり、リセットしたりする方法を知ることで、レジリエンス(回復力)を向上させられます。リラックス法には、「その場で短時間でできること」と「家で時間をかけてすること」の2つがあります。それぞれに自分に合う方法を身につけることが大切です。
私自身の経験から効果的だと感じたリラックス法には、以下のようなものがあります。
①~③が「その場で短時間でできること」、④~⑥が「家で時間をかけてすること」です。
- 目を閉じて深呼吸する
- 手をぐっと握って離すことを繰り返す
- 両肩を3秒間上げてパッと力を抜く
- お風呂に長く浸かる
- 好きな音楽を聴く
- ストレッチをする
私の場合は、不登校の回復期に、①④⑤を組み合わせた「お風呂で音楽を聴く」リラックス法を身につけました。この方法を身につけたことで、疲れている状態でもすぐに回復できるようになりました。
回復期にいると感じているなら、自分に合ったのリラックス法を探してみましょう。
【支援事例】キズキで不登校から回復した生徒さん
私たちキズキ共育塾には、「不登校から回復していった生徒さん」が大勢います。以下、一部の声をご紹介します(名前は仮名です)。
西巻礼さん(小学校6年生)の親御さんの声
小学校を不登校で、学校以外の外出も苦手だった子ども。これからの進路に不安を覚えていたときに出会ったのがキズキ共育塾でした。
一人ひとりの個別のペースを尊重してくれそうだったため、入塾を決意しました。
子ども自身も先生と会うのを楽しみにしていて、生活にメリハリがでてきたように思います。
授業中は、勉強以外にも子どもが好きなキャラクターの話を一緒にしてくれているようで、そういった面でも信頼しているようです。
福本ちひろさん(中学校2年生)の親御さんの声
入塾に際しては、親である私自身が「子どもと講師との相性」を気にしていました。
特に講師の方が尊敬できる人物であるかどうかを重要視していましたね。
というのも、子どもが不登校になった原因の1つが、当時の担任教師の不誠実な対応とそれに対する不信感の大きさだったからです。
キズキ共育塾は、入塾までの対応の時点で誠実さが伝わってきたので、ここなら大丈夫だと直感しました。
こちらの話を急かすことなく、押しつけるような言葉もなく、とても安心しました。
要望に対しても誠意ある対応を受けたので、いまでも感謝しています。
おかげで3人ものいい先生にめぐり会えました。子どもも先生を信頼していて、先生のことが大好きみたいです。
小倉智衣さん(中学校2年生)の親御さんの声
子どもは、中学校に登校できる日は午前か午後のどちらかだけで、教室以外の場への外出も週に1回程度でした。
キズキ共育塾は、これまで多くの不登校状態にある生徒を受け入れていたことから、「こういう子どもの対応に慣れているだろうし、否定されたり受け入れられなかったりする可能性を心配をしなくてすむ」と考え、入塾を決めました。
唯一、「本人の体力がもつか」ということは不安でした。ですが、結果として問題なく通っています。生活リズムが崩れたり、気持ちが乗らないときでも、できる限り通塾しようとしています。学ぶことの楽しさを感じ始めている様子です。
家では、キズキで習ったことや先生と話した内容を細かく話してくれます。先生が面白いともよく言っていますね。
先生から教わったことをとても大切にしているようで、家ではノートを何度も読み返しています。勉強に取り組むことで、少しずつ自信が出てきたように見えます。
不登校の回復期の子どもへの親の接し方
不登校の回復期にいるお子さんとの接し方は、感情的にならずに、見守ることが大切です。
不登校の回復期はエネルギーが湧いてくる時期なので、外へ行ったり友達と遊んだりすることが増えてきます。そのため、親御さんは、以下のような複雑な気持ちをお持ちになることもあるかもしれません。
- 元気があるなら学校へ行ってほしい
- 余裕があるなら勉強してほしい
命令口調で「勉強しなさい」と言いいたくなることもあるかもしれません。
また、お子さんが不登校のときには、親御さんもストレスを感じるものです。
しかし、あまり感情的にならずに、お子さんを見守ることに徹してください。
特に、登校再開をあせらせるような発言をすると、かえってお子さんを追い詰めることにつながるもしれません。すると、回復期からひきこもり期に逆戻りする可能性があるのです。
「いまはそういう時期なのだ」と考えましょう。そして、親御さん自身も自分の時間を取ったり、あまりお子さんのことを考え過ぎないようにしたりするなど、セルフケアに専念することが大切です。
また、「不登校を経験した後の進路」や「不登校の間に通える塾など」などを調べておくと、お子さんが相談してきたときに安心感を与えられます。
その上で、以下の点には注意が必要です。
注意
回復期では、お子さんがエネルギッシュになるあまり、夜更かししたり、遅くまで外出していたりすることがあります。
生活リズムが乱れているとき、疲れている様子があるときには、声をかけてください。
生活リズムが乱れると、睡眠の質が悪くなったり、疲れから心の調子を崩したり、お子さんの状態がひきこもり期に逆戻りしたりと、さまざまな面で悪影響が出る可能性があります。
不登校経験者のその後や、不登校状態にある子を持つ親御さんのストレス対処は、以下のコラムで詳しく解説しています。ご興味がありましたらご覧ください。
まとめ:不登校の回復期を充実させましょう

不登校を経験した1人の意見として、回復期への道のりや、回復期から実際に次の一歩に進むまでの時間は、多少長い場合でも心配する必要はありません。
不登校の回復期では、「自分はこれから何をするべきか」「どうやって気持ちを立て直すか」を自分なりに考えたり試したりすることが増えます。
その過程には、学校の勉強では味わえない学びや発見、楽しさがあるはずです。
また、親御さんがお子さんを急かすような声掛けをすると、お子さんの状態がひきこもり期に逆戻りする可能性があります。
不登校状態にあるご本人も親御さんも「不登校だから」と必要以上に心配したり、焦ったりすることはありません。不登校の回復期を充実させて、ぜひそこで得た経験を今後の人生に役立てましょう。
このコラムが、不登校に悩むご本人の回復のきっかけに、そして親御さんの助けになりましたら幸いです。
さて、私たちキズキ共育塾では、不登校の悩みから次のステップへ進もうとしている人たちをサポートしています。
高校・大学受験、高卒認定試験、学校復帰などの無料相談も行っています。不登校でお悩みを抱えているなら、ぜひ一度ご相談ください。
Q&A よくある質問
不登校の回復期のサインを教えてください。