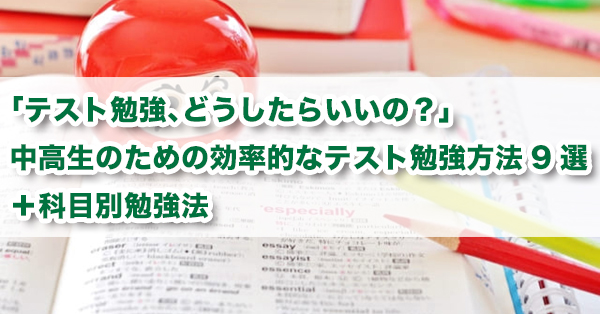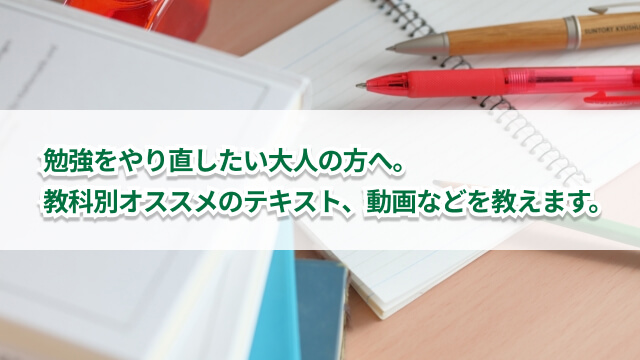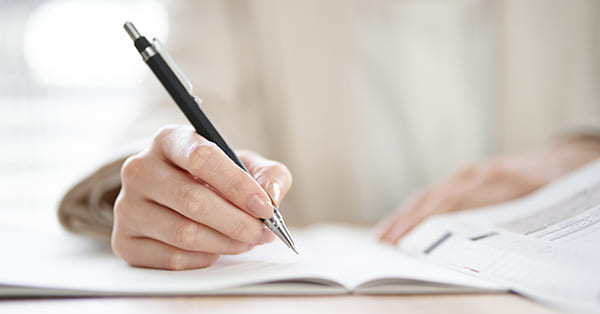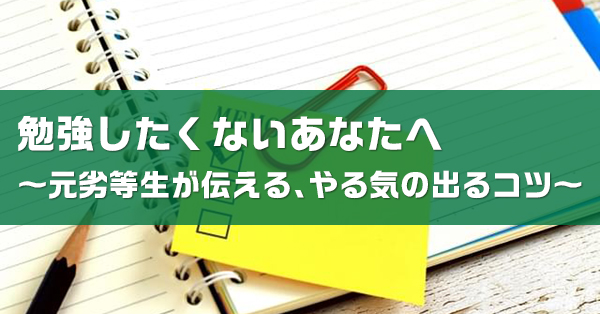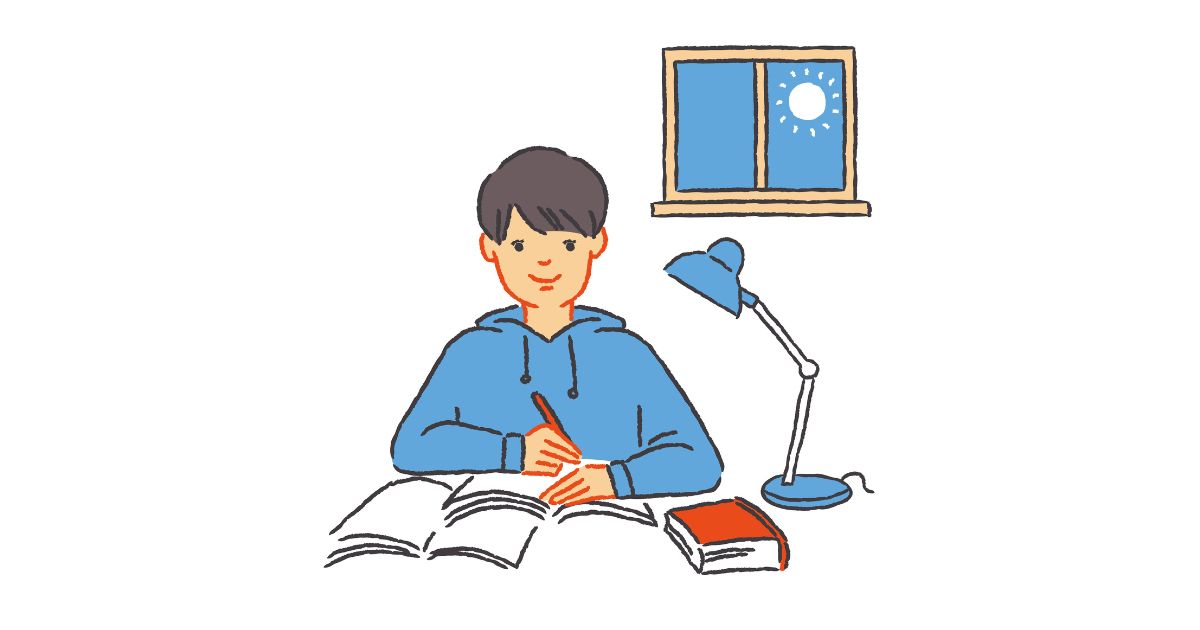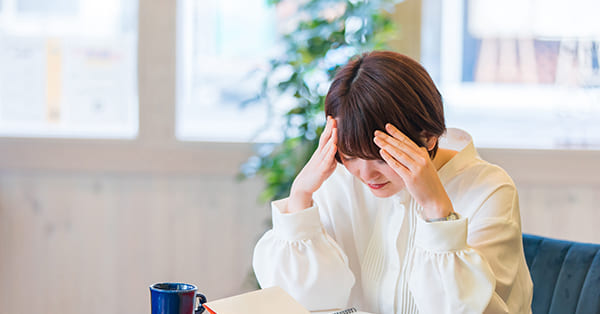勉強が続かないあなたへ 勉強を習慣化する方法を解説
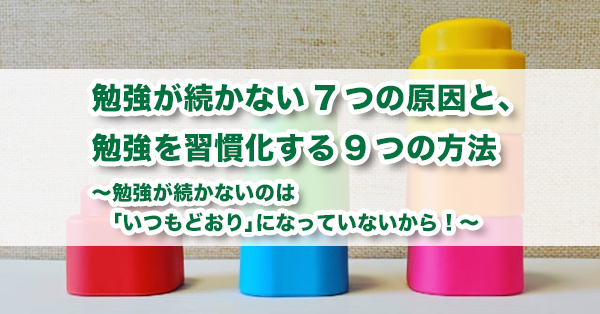
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたは、以下のようなお悩みを抱えていませんか?
- 勉強をがんばりたい気持ちはあるけど、どうしても集中力が続かない
- テスト前など必要なときしか、勉強できない
- もっと長時間集中して、勉強ができるようになりたい
このコラムでは、勉強が続かないと悩む人に向けて、勉強が続かない原因と勉強を習慣化する方法について解説します。
例えば、わざとキリの悪いところで勉強を中断したり、勉強する時間や場所を決めるといった方法が有効です。
中学生や高校生などはもちろん、学び直しや資格の勉強に取り組む社会人にも役立てていただける方法をお伝えします。
このコラムが、「勉強が続かない」と悩むあなたが、勉強を習慣化する助けとなれば幸いです。
私たちキズキ共育塾は、勉強が続かない人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
勉強が続かない7つの原因
この章では、勉強が続かない原因について解説します。
勉強が続かないと一括りに言っても、その原因は様々で、原因が違えば対策も変わってきます。
そのため、自分に当てはまるものはないか、考えながら読み進めてください。
原因①習慣になっていない
人間には、変化を嫌がりいつもどおりを維持しようとする傾向があると言われています。
つまり、勉強が続かないのは、勉強が習慣になっていないからかもしれません。
そのため、中学生や高校生の時は勉強ができていても、社会人になってから勉強する習慣がなくなっていれば、勉強が続かない可能性が考えられるのです。
また、毎日学校で勉強をしている中学生や高校生の学生であっても、自主的に勉強をする習慣が身についていなければ、勉強が続かない場合も多いでしょう。
原因②目標がない

大学受験に合格する、資格を取るなどの目標が持てないと、なかなか勉強へのモチベーションは維持できません。
勉強する目的をつくること、目的を見つけることも、勉強を続けるために大切なことです。
原因③勉強をがんばりすぎている
自分に合った勉強量を大きく超えると、肉体的にも精神的にも疲れます。
勉強は、単にたくさんやればよいというものではありません。
例えば、中学生や高校生であればテストや受験のため、社会人であれば資格取得のために、毎日睡眠時間を削って勉強していませんか?
適切な量で効率よく勉強することが大切なのです。
仮に、一度長時間勉強できたとしても、そのときの大変さが強く印象に残って、勉強に気持ちが向かなくなる可能性が考えられます。
原因④誘惑が多い

あなたの勉強が続かないのは、勉強以外のものに意識が向いているからかもしれません。
特に、スマホは一度触りだすと手放すことが難しくなり、気がついたら時間がたっていて勉強できなかったということがあるでしょう。
これは、中学生や高校生などの学生だけでなく、社会人にも当てはまるので、勉強を続けられるようになりたい場合は、スマホとの付き合い方を見直す必要があるかもしれません。
また、勉強を始められたとしても、そのとき勉強している科目以外の教材が机に出ているだけで、気を取られることがあります。
勉強を続けるためには、勉強だけに集中できる環境を整えることが大切なのです。
原因⑤成長が実感できない
勉強が続かない原因として、成長が実感できず、達成感が得られないせいでやる気が起きないことも考えられます。
特に、受験勉強は、始めてから成績に反映されたり結果が出たりするまでに時間がかかることが多いです。
そのため、高校受験・大学受験に取り組み始めたばかりの中学生や高校生は、「勉強が続かない…」と悩むことも多いでしょう。
また、社会人であっても、これまで全く勉強したいことがない分野の現況をするとなると、成長が実感できず、途中で投げ出したくなることもあると思います。
成長を実感するためには、目標を細かく設定するなどして、達成感を得られるように工夫することが大切になります。
原因⑥学習環境が悪い
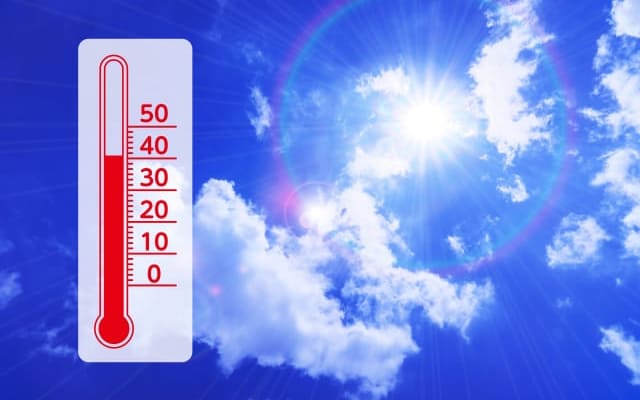
学習環境が悪いことも、勉強が続かない原因になります。
例えば、以下のようなことがある人は、部屋を片付ける、防音カーテンにするなどの工夫をしてみてください。
- 勉強部屋や机が片付いていない
- 騒音がある
- 部屋が暑すぎる、寒すぎる
中学生や高校生の場合は、自分のお金だけで環境を整えるのは難しいかもしれないので、親御さんや保護者の方に相談してみましょう。
原因⑦勉強に飽きている
以下のようなこが原因で、勉強に飽きてしまい、勉強が続かないこともあります。。
- いつも同じ場所で勉強している
- 同じ科目ばかり勉強している
- 暗記などの単純作業が多い
特に、資格取得のために勉強をしている社会人の方であれば、似た内容で飽きてくることもあるでしょう。
飽きやすい人は、たくさんの科目を交互に勉強するなどの変化を加えると、勉強を続けやすくなるかもしれません。
勉強を習慣化する方法9選
この章では、勉強を習慣化する方法について解説します。
前提:勉強を習慣化するために大切なこと
勉強があなたの習慣になっていないと、勉強がストレスになります。
勉強を続ける一番の近道は、勉強を習慣化することです。(参考:古川武『30日で人生を変える「続ける」習慣』)
つまり、勉強を食べることや寝ることと同じように、当たり前のものにするということです。
さて、まずは勉強を習慣化する際に大切なことをお伝えします。
それは、習慣化のために勉強を毎日続けることです。
習慣化する上では、毎日ちょっとでもいいから行動することが重要になります。
つまり、習慣化のためには、1%と100%よりも0%と1%の違いの方が大きいのです。
しかし、生活している中で、どうしても勉強ができない日があるでしょう。
こういった場合は、あらかじめ「勉強ができない日はこうしよう」と、ルールを決めておいてください。
例えば、用事が入って勉強時間が確保できないときは、10分だけでもいいから昨日の復習をするなどです。
そうすると、根づいた習慣がリセットされにくくなり、勉強できなかったときの罪悪感も軽減されます。
また、ダイエットや日記など、勉強以外にも習慣化できるとよいものはたくさんあります。
方法①わざとキリの悪いところでやめる
わざとキリの悪いところで勉強をやめるのは、勉強を習慣化する際に有効です。
達成できなかったことや中断したものほど記憶に残りやすいという現象があります。
続きが気になるという、ツァイガルニク効果と呼ばれるものです。
毎週のドラマやアニメがキリの悪いところで終わり、続きが気になった経験がありませんか?
これは、ツァイガルニク効果によって引き起こされたものです。
勉強も同じように、あえてキリの悪いところで勉強をやめることで、中断したことが強く記憶に残り、勉強を続けやすくなります。
方法②勉強する時間や場所を決める
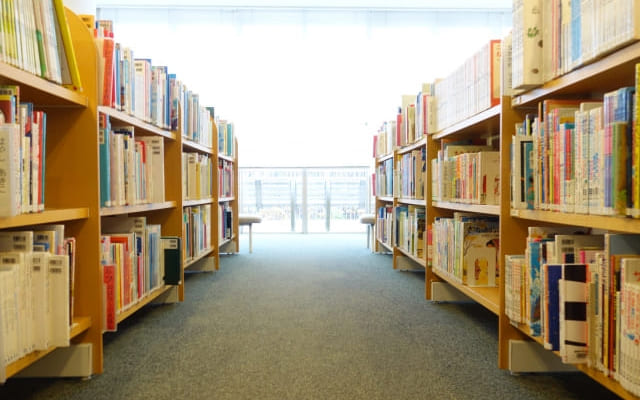
勉強する時間や場所をあらかじめ決めておくことも、習慣化に有効です。
特定の時間、特定の場所がスイッチとなり、勉強に入りやすくなります。
例えば、以下のようなことです。
- 通学時間は単語帳を読む
- 学校から家に帰る前に、図書館やカフェに行って勉強する
- 夜ごはんを食べて、30分休んだら勉強する
- 寝る前に15分だけ勉強する
私自身、毎朝の通勤時間の中で15分間を英語のリスニングを特訓する時間にしています。
この特訓は私の習慣になっており、通勤時間になると自然とやる気がわいてくるので、ストレスを感じることなく毎日続けられています。
いつもどおりの時間にいつもどおりの場所で勉強する。このいつもどおりが、勉強を習慣化するための力になるのです。
方法③目標を決める
目標がない人は、勉強する上での目標を決めましょう。
具体的には、中学生や高校生などのであれば学校のテストで10番以内に入ること、受験生であれば○○大学に合格することなどの目標はどうでしょうか?
また、社会人であれば、資格を取得して希望の会社に転職する、昇進のために勉強するなどの目標になるかもしれません。
目標がないまま勉強を続けることは困難です。目標を持つことで勉強へのモチベーションを維持しやすくなります。
とは言え、「志望校が決まらないし、行きたい学部や学科もない…」という人もいるでしょう。
そういった場合は、この参考書を1か月で終わらせる、1週間に英単語を100語覚えるなどの小さい目標を設定してみてください。
小さい目標は、達成感を得やすいので、勉強を続けやすくしてくれます。
方法④計画を立てる

目標が決まったら、学習計画を立てます。
1日2時間自宅で勉強するなど、簡単に決めてもよいですし、1週間の勉強計画をつくる、カレンダーに細かく計画を書き込むなど、より具体的にしてもよいでしょう。
その際、時間、場所、学習内容が明確だと、さらに勉強に入りやすくなります。
長期の計画を考えたいときは、最終目標から逆算して計画を立てると効果的です。
ただし、どんな計画を立てるときも、以下のように無理な計画は立てないようにしましょう。
- 最終目標が高すぎる
- むやみやたらと、空いている時間をすべて勉強に費やす
- いきなり難しい参考書をやる
無理のある計画を立てたせいで日常生活に支障が出ては、勉強どころではなくなります。
取り組みやすい計画を立てて、自分に合ったペースとレベルで小さく始めてみてください。
また、中学生や高校生であれば部活や学校行事、社会人であれば仕事などとの兼ね合いを考えておくことも大切です。
方法⑤決めた勉強時間を守る
勉強の計画を立てたら、決めた勉強時間は必ず守りましょう。どうしても勉強できない日については、例外的な計画を考えておきましょう。
自分で設定した勉強時間を大きく超えると、習慣がくずれる可能性が高いからです。
例えば、Aさんが1日1時間勉強すると決めていたとしましょう。ある日Aさんは、調子がよかったので3時間も勉強しました。
3時間勉強した次の日、Aさんは「昨日3時間も勉強したし、今日は1時間やらなくてもいいや」と考えました。結果、その日勉強したのは30分。これ以降、Aさんの勉強時間は1日1時間から徐々に遠ざかっていき、最終的に勉強の習慣自体がなくなりました…。
Aさんは、「昨日がんばった分、今日は楽にしよう」と考えました。
このように、一度でも勉強時間が決めた時間を大きく下回ると、勉強の習慣は崩れやすくなります。
1日1時間と決めたなら、毎日1時間前後で収めるようにしましょう。
勉強時間を増やしたい場合は、次のように少しずつ増やしていくことがオススメです。
- 1週間ごとに10分ずつ増やす
- 1か月後は毎日2時間にする
方法⑥勉強の記録をつける

記録をつけると、勉強へのモチベーションがあがりますし、自分の学習を客観的に判断できます。
その際、以下のように、できるだけ簡単に記録を取りましょう。
- 手帳、カレンダー、スマホ、パソコンなど記録媒体を決めておく
- やったかどうか〇×だけ書く、勉強した内容と具体的な時間を入力するなど、記録方法を決めておく
記録を取ることが面倒くさくなると、ストレスが生まれ、習慣化が邪魔されるので注意してください。
方法⑦ながら勉強から始める
そもそも勉強を始められない人は、ながら勉強から始めてみましょう。
例えば、以下のようなことです。
- 音楽を聴きながら
- テレビをつけながら
- スマホで動画を流しながら
- お菓子を食べながら
勉強だけとなるとやる気は出ないけど、好きな音楽を聴きながらであれば勉強できる人は多いでしょう。
ただし、普通に勉強するよりも集中力は落ちるので、勉強のペースをつかめたら、ながら勉強は徐々に減らしてみてください。
方法⑧飽きない工夫をする

勉強に飽きる人、飽きている人は、勉強の仕方にひと工夫加えてみてください。
例えば、以下のような感じです。
- いろいろな科目を交互に勉強する
- 飽きてきたら得意科目に切り替える
- 勉強時間を15分ごとなど細かく区切る
また、筆箱、シャーペン、ノートなどの勉強道具を好きなキャラクターのもの、好きなデザインのものなど好きなものに変えるのも、やる気が上がるのでオススメです。
方法⑨学習塾などを利用する
一人での勉強が難しいと思ったら、学習塾などに勉強の習慣化をサポートしてもらいましょう。
例えば、以下のような人たちが考えれられます。
- 学校や学習塾、家庭教師の先生
- 両親や親戚
- 友人、学校の先輩
誰かと協力して物事に取り組むと責任感が生まれます。それは勉強も同様です。
アドバイスをもらったり、習慣化できているか評価してもらったりすると、勉強のモチベーションを維持しやすくなります。
ほかの方法について、あなた向きの具体的内容についてもアドバイスがもらえると思います。例えば、「今の自分に適した目標ってどのあたり?」「自分の受験目標に対して、1日何時間くらいの計画がいいの?」「自分のながら勉強に向いてる音楽って何?」などがあるでしょう。
また、学習塾や家庭教師というと、中学生や高校生が通うもというイメージがあるかもしれませんが、社会人が通えるところもあります。私たちキズキ共育塾もそのひとつです。
気になる人は、ぜひ一度調べてみてください。
まとめ〜「勉強が続かない」は習慣化で改善できます〜

自分に合ったやり方を見つけることで、だれでも勉強の習慣化は可能です。
また、勉強を習慣化ができれば、長時間集中できるようにもなっていくでしょう。
「自分は意志が弱いから、勉強を続けることなんてできない」とあきらめないでください。
このコラムを読んだみなさんが、勉強の習慣化を実現できることを願っています。
さて、私たちキズキ共育塾は、一人ひとりに寄り添う完全個別指導塾です。
「勉強を習慣にしたいけどやっぱり一人じゃ難しい」と思ったら、ぜひ一度ご相談ください。
あなたのための、勉強を続ける方法を一緒に見つけられると思います。
Q&A よくある質問