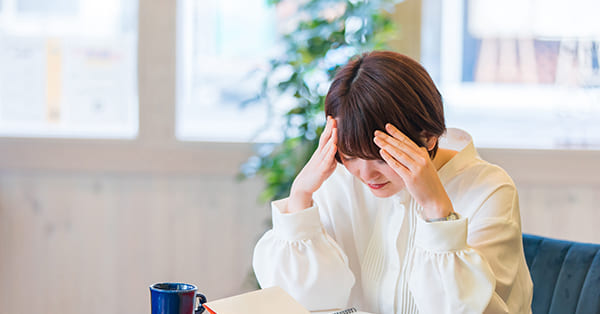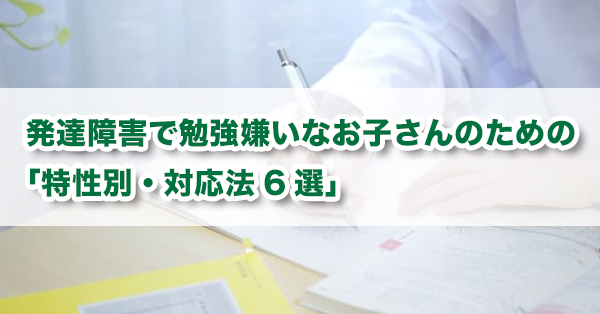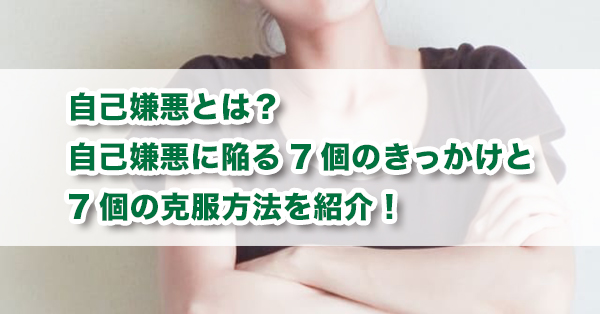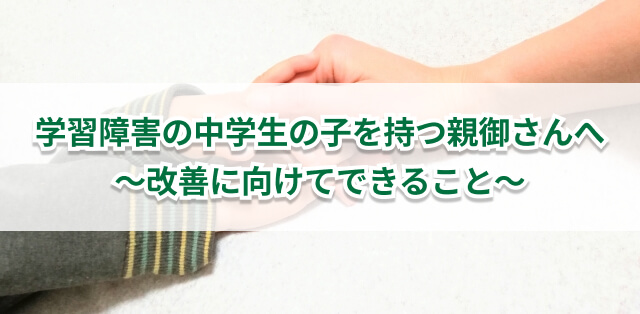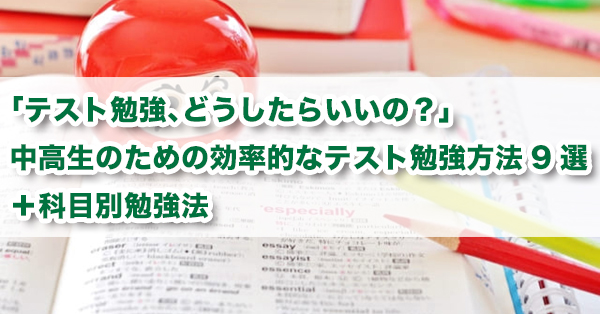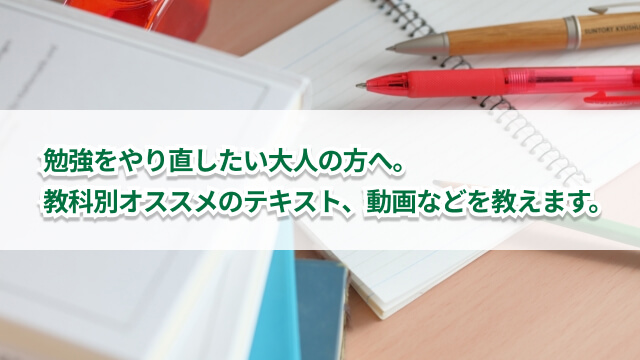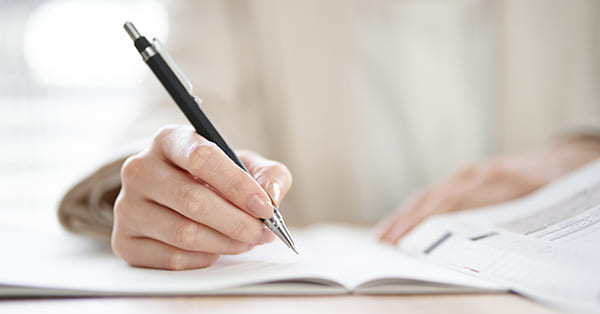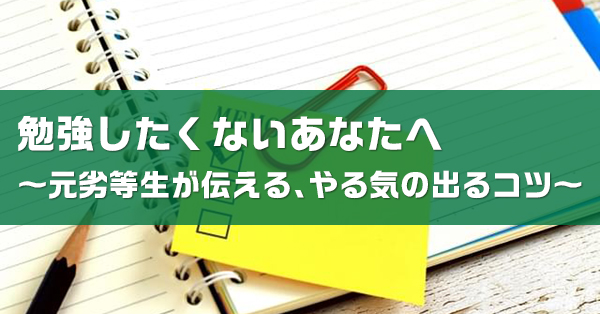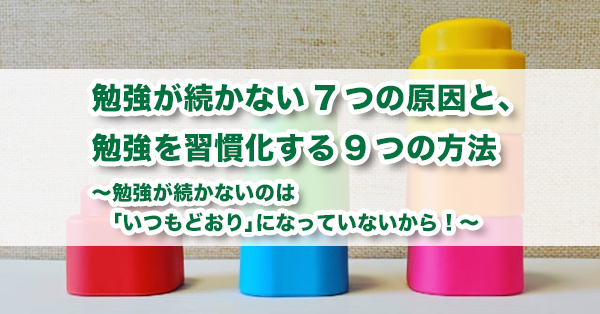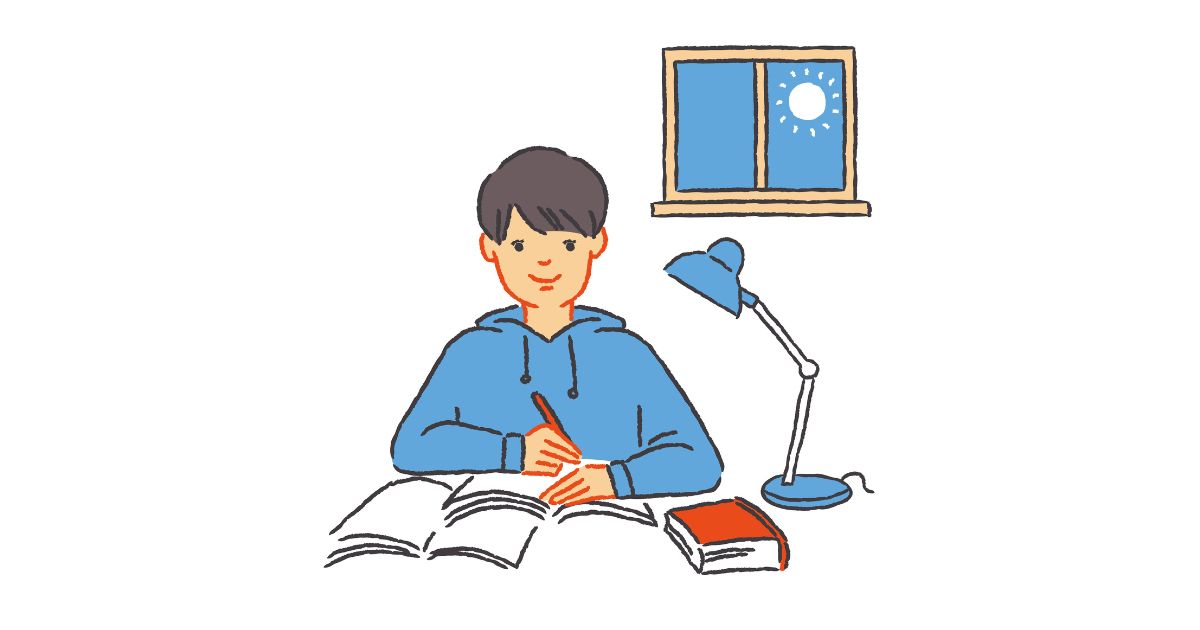どうして勉強できない? 原因と勉強できるようになる方法を解説

こんにちは。勉強できないとお悩みの人を完全個別指導で応援するキズキ共育塾です。
あなたは、「自分は勉強できない」と、お悩みではありませんか?
筆者も、中学生までは勉強できない落ちこぼれでした。勉強が嫌いで、好きな科目は1つしかありませんでした。どれくらい勉強できなかったかというと、中3の夏に受けた模試では、偏差値が26だったほどです。
しかし、勉強を工夫して何とか高校に合格。そして、その後大学にも合格しました。
このコラムでは、「勉強できない」とお悩みのあなたに向けて、勉強できない理由や環境に関する原因、克服方法について解説します。
かつて勉強ができなかった当事者として、また、現在塾講師・家庭教師として働く者として、勉強できない人へのアドバイスを体験談とあわせて紹介します。
このコラムを読んだあなたが、少しでも「今は勉強できない。でもこれからは何とかなるぞ」と希望を持っていただければ嬉しいです。
私たちキズキ共育塾は、勉強ができないことにお悩みの人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
勉強できない自分を嫌いになる前に

「自分は勉強できない」と悩むあなたは、自己嫌悪に陥ったり、劣等感(れっとうかん)を感じやすいかもしれません。
しかし、勉強できないのは色々な方法を試す中で変えられます。
自分が嫌いになりかけている人に向けて、自分のことが好きになる方法をお教えます。
それは「自分との約束を守る」ことです。
例えば、「英単語を5つ覚える」「昼休みに10分間数学をやる」でも何でもいいです。まずは、小さな目標を立てて、自分との約束を守りましょう。
自分との約束を守ることで、自分が好きになり、自己肯定感(じここうていかん)が上がります。
自己肯定感が高いと「失敗することはあっても、いつか上手くいく」と思えるので、勉強が継続してできるようになります。
ぜひ、自分との約束を立てて、守るようにしてください。
勉強できない4つの理由
私は、キズキ共育塾以外でも、家庭教師やボランティアなどでたくさんの子どもに勉強を教えてきました。
さまざまな生徒さんとお話しをする機会も多々あるのですが、「自分は、勉強できないんです…」というお悩みを、本当によくお聞きします。
私が見てきた限り、勉強できない理由はいくつかあります。
この章では、勉強できない理由を4つ紹介します。
理由①基礎学力がない
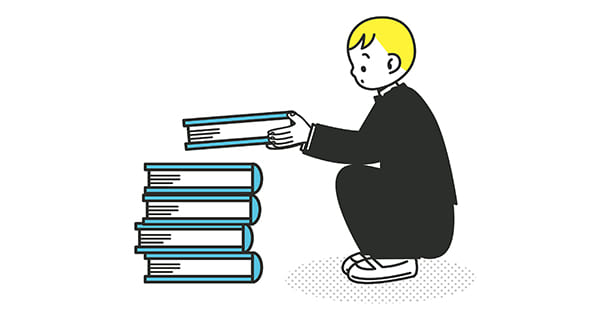
勉強できない理由の1つ目は、「基礎学力がない」です。
例えば、中学校の主要教科は、小学校の頃に比べて高度な単元を扱います。
算数の場合、科目名は数学に変わり、基礎計算を使う前提で、定数や方程式などを勉強するようになります。
高校入試でも、記述問題や思考問題などを問われる場合があります。
しかし、「高度な問題」を解くために問われるのは、実は小学校内容の基礎的な学力です。
例えば、2018年の神奈川県の高校受験の問題には、2桁の割り算の知識+αの知識があれば正解できるものがありました。
65ab÷5a
(参考:2018年 神奈川県 公立高校入試問題を一部編集)
この問題では、数字は65÷5を計算し、文字(定数)はab÷aを計算します。割り算や多項式の基礎的な学力があれば解ける問題です。
逆に言うと、基礎的な学力がついていないと、この問題を解くために何をどうしたらいいのかわからないのです。よく言われる、「何がわからないのかわからない」状態かもしれません。
以前、私が数学を指導した、中3の男の子の例をお話しします。
ご両親からは、「勉強できない。クラスではビリから2番目だ」と紹介されました。
彼は、2桁の割り算がわかっていないために問題が解けず、途方に暮れていました。つまり、小3から小4の頃の基礎学力のつまずきが、中3時点での「数学ができない」につながっていたのです。
そこで私は、基礎学力の定着のために、授業の冒頭に簡単な計算問題を解くところから授業を始めました。
彼は少しずつ小学生の内容を総復習し、次の数学のテストで、はじめて2桁台の点を取りました。
その後も、別の教科も含めて基礎から学び直すことで、彼は次第に勉強ができるようになりました。
基礎学力の時点でつまずいて「勉強できない」場合、基礎から学び直すことで成績が伸びます。
基礎から学び直せる塾や方法を探しましょう。
理由②勉強の仕方がわからない
勉強できない理由の2つ目は、「勉強の仕方がわからない」です。
そもそも「勉強の仕方」とはどういうことでしょうか?
単語をノートに写したり、テキストを読んだりすることでしょうか?机に座って黙々と問題を解くことでしょうか?
私の思う「勉強の仕方」とは、「自分に合った方法で学ぶこと」「自分に合った勉強方法を知ること」です。
自分に合わない「勉強の仕方」をしているために勉強できない人は、「自分の強みを生かした勉強法」を見つけると、勉強できるようになります。あなたの特性を理解して、あなたに合った勉強の仕方を探しましょう。
では、どうやったら自分に合った方法がわかるのでしょうか。
方法の1つに、「認知特性を理解すること」があります。
人によって、「外界からの情報をどうとらえ、どう覚えるか」という認知特性は異なります。
例えば、「聴覚優位(ちょうかくゆうい)」「視覚優位(しかくゆうい)」という言葉をご存知でしょうか?
聴覚優位とは、耳で聞いた情報を処理するのが得意なことです。
聴覚優位の人の勉強法は、以下のとおりです。
- 重要部分を繰り返し声に出す
- 覚えたいことを歌にしてまとめる
視覚優位とは、目で見た情報を覚えるのが得意なことです。
視覚優位の人の勉強法は、以下のとおりです。
- 勉強の内容を文字に加えて絵や図にしてまとめたものを見る
- 漫画やイラストで解説された参考書を使う
視覚優位の人には、目で見たものを3次元でとらえるのが得意な人もいます。
このタイプの人には、ドラマ仕立ての動画を見たり、自分の頭の中でキャラクターを作ってドラマ化して覚えたりするのもおすすめです。
聴覚優位の人が文字メインで覚えようとしたり、視覚優位の人が先生の話す内容メインで学ぼうとしたりしているために、勉強できない場合があります。
また別の例として、ハーバード大学の心理学者ハワード・ガードナー氏による「マルチプル・インテリジェンス」があります。
簡単に言うと、全ての人間には8分野の知能があり、自分の得意・不得意分野を知ることで、自分に合った「勉強の仕方」などもわかるというものです。
8分野の知能
- 言語的知能
- 論理・数学的知能
- 空間的知能
- 音楽的知能
- 身体運動的知能
- 対人的知能
- 内省的知能
- 博物的知能
わかりやすいように単純化した例として、次のように、得意な知能に合わせた「勉強の仕方」ができるようになれば、勉強できない状況を解決できます。
- 「対人的知能が高い」人は、誰かと一緒に対話形式で勉強する
- 「音楽的知能が高い」人は、替え歌にして暗記事項を覚える
先ほどの「優位」と同じく、自分の特性や知能に合わない「勉強の仕方」をしているために勉強できない状態を作り出している可能性があります。
理由③モチベーションがない

勉強できない3つ目の理由は、「モチベーションがない」です。
もう少し具体的に説明すると、以下の3つの気持ちが勉強のモチベーション低下を招いています。
- 勉強が、どう自分のためになるのかわからない
- 勉強したって、いいことなんてない
- 勉強しても、何にも変わらない
モチベーションのなさが原因で勉強できない場合、勉強のモチベーションを考えることが大切です。
「勉強してよいことがある」と思えないために勉強できない人は、勉強のためのモチベーションが必要です。
「なぜ勉強するのか」「勉強すると、将来がこう変わる」「勉強すると、こんないいことがある」といった、希望につながることを考えましょう。
理由④自信がない
「自信がない」ことも勉強できない理由となりえます。
「勉強しても、わからない」という経験をたくさんした人は、自信をなくすでしょう。
その結果、「どうせ勉強したって自分はできるようになんかならない」と考えて、勉強しなくなる場合があります。
これらが、勉強できなくなる悪循環につながる可能性もあります。
「がんばってもできない」体験で自信をなくし、「勉強してもどうせ無駄」と無気力になっている人は、自信を取り戻す必要があります。
できるところまで戻って学習したりして成功体験を積み上げていくことで、勉強できるようになります。
成功体験を積むことで、「自分はやればできる」という自信と、「勉強したらできるようになる」という希望が持てるようになります。
勉強できない環境に関する4つの原因
あなたの意思に関わらず「環境」が勉強への取り組み方ややる気に悪影響を与えている可能性もあります。
この章では、勉強できない環境に関する4つの原因を紹介します。
原因①家で集中できない

家で集中できない場合、考えられるケースには以下があります。
- 雑誌や趣味のものが目につくところに置いてある
- 自室がない
- 家族が立てる生活音が気になる
- 気がゆるんで寝てしまう
家は、学校や塾と違って、自発的に勉強しなければならない上に、気が散りやすい要素が揃って(そろって)います。
家で集中できない場合は、以下の対策を検討してみましょう。
- 図書館や自習室を活用する
- 放課後は学校でできるだけ勉強する
- 友達と一緒に勉強する
- 机の上を片付ける
家で集中できない人は、家で無理に勉強しようとせず、学校や図書館の利用も検討しましょう。
原因②部活や習い事で忙しい
部活や習い事で忙しく、勉強時間が確保できない人もいます。
「親に言われたから」という理由だけで続けている習い事があるなら、一度お休みしてみるのはいかがでしょうか。
また、部活で疲れ切っている場合は、15分程度の仮眠を取ると心身ともにリフレッシュできます。
部活や習い事で忙しい場合、スキマ時間の有効活用が必須です。
学習アプリをインストールして移動中に起動するなど、工夫して勉強してみましょう。
「何をするか」より「何をしないか」を考えることで、時間を作りやすくなります。
何となく続けている習い事を整理したり、ダラダラした友達とのおしゃべりを短くするなど、やめられそうなことがあればチャレンジしてみましょう。
原因③スマホ・ゲームが近くにある

ちょっとだけのつもりで見始めたスマホで、時間を奪われる(うばわれる)ことはよくあります。
スマホで新しい情報を手に入れたり、ゲームでレベルが上がったりすると、脳から神経伝達物質の「ドーパミン」が放出されるため、なかなか自分ひとりではやめられなくなります。(参考:日本心理学会「ネットとゲームへの依存が脳に及ぼす影響」)
スマホ・ゲームは勉強前に物理的に距離を取るのが一番です。
スマホ・ゲームを自分一人でやめられないという人は、家族に協力してもらいましょう。
「電源を切って預ける」「勉強が終わるまで見えないところに置く」など、使い方を工夫しましょう。
原因④親の教育方針に問題がある
あなたの親御さんを悪く言うつもりも、親子の不仲をあおるつもりもありません。
ですが一般論としては、頭ごなしに「勉強しなさい!」とガミガミ叱ったり、テストの点数だけを見て良し悪しを決める親御さんが、勉強できない原因になることもあります。
子どもの学力が高い傾向にある家庭環境の例には、以下があります。(参考:お茶の水女子大学「保護者に対する調査の結果と学力等との関係の専門的な分析に関する調査研究」)
- 子どもの起床・就寝時間(起きる時間と眠りにつく時間)を一定にしている
- 毎朝朝食を食べさせている
- 子どものプライバシーを尊重(そんちょう)している
- 子どものよいところをほめる
- 普段子どもの勉強を見ている
親が頭ごなしに叱って(しかって)くるという人は、先生や塾の先生など、親以外に相談できる大人を見つけて、勉強できないことを相談してみましょう。
親御さんは子どもの幸せを願うからこそ叱っていますが、叱り方が間違っていることもあります。
叱られてつらい場合は、スクールカウンセラーや都道府県の電話相談員など、信頼できる大人に相談してみましょう。
勉強できるようになる6つの方法
「勉強できる」には、次の2つの意味があります。
- 成績が上がる
- 自発的に勉強するようになる
まずは、「自発的に勉強するようになる」ことをめざしましょう。コツコツ努力していけば、必ず成績は上がります。
この章では、勉強できるようになる方法を6つ紹介します。
方法①勉強のやり方を変える

勉強できない場合、こちらで解説したとおり、勉強のやり方が合っていない可能性が高いです。
例えば、テストで間違ったところをそのままにして復習しなかったり、何冊も参考書を買ってどれも中途半端に投げ出したりしていませんか?
今までの勉強方法で結果が出ていないなら、思い切ってやり方を変えてみましょう。
- 参考書を1冊に絞って(しぼって)何度も繰り返して解く
- 間違ったところを定期的に復習する
- 単語の暗記をノートに書きとっていたなら、アプリに変えてみる
上記のように、自分に合った方法を探しましょう。
自分に合った学習方法がわからない場合、塾の先生や学校の先生、そして成績のいい同級生に聞いてみるのが一番早いです。
自分に合いそうな方法を見つけて、効率的に成績を上げる方法を探していきましょう。
方法②勉強を習慣化する
ほとんどの方が、歯みがきをしないと気持ち悪いと感じるのではないでしょうか。それは、歯みがきが習慣化しているからです。
勉強も一緒で「勉強をしないと気持ち悪い」レベルまで習慣化してしまえば、勝手に勉強するようになります。
勉強を習慣化するには、次の方法があります。
- 前日に翌日にやることを細かくリストアップする
- とにかく机に座って手を動かす
- 簡単な問題から始める
- できたものをリストに線を引いて消していく
何か作業を始めると、脳がドーパミンを出し、やる気が出ます。これを「作業興奮」と言います。
手を動かすことで、脳が「もっと作業を続けて」と指令を出すので、勉強を習慣化するためにはとにかく、手を動かすことからスタートしましょう。
また、前日にリストアップしていたものが完了したら、横線を引いて消していくと達成感が得られ、やる気につながるのでおすすめです。
これらを毎日繰り返すと少しずつ勉強する習慣ができるので、まずは手を動かすことに注力してみてください。
方法③勉強する環境を整える

こちらやこちらで解説しましたが、勉強道具以外のものが目につく環境では、気を取られて、勉強に集中できません。
まずは机の上を片付け、勉強道具以外のものが視界に入らないようにしましょう。
机を壁に向かって設置したり、勉強道具以外のものを箱に入れて足元に置くのもおすすめです。
家庭の生活音や家族の話し声が原因で集中できないときは、図書館や自習室も利用しましょう。
方法④自分に合った勉強法を見つける
こちらで解説したとおり、目で見たものを記憶しやすい「視覚優位」の人、耳で聞いたことを記憶しやすい「聴覚優位」の人など、人それぞれ特性があります。
暗記が苦手な人は、何度も音読したり、アプリで音声を聞きながらゲーム形式で覚えていくのもおすすめです。
また、25分間の作業と5分間の休憩を4セット繰り返す「ポモドーロ・テクニック」は、集中しやすいため、取り入れてみるのもいいでしょう。
集中力を高める自然音とポモドーロのカウントがセットになっている動画がインターネット上にアップロードされているので、勉強の習慣化に使ってみてください。
方法⑤小さな目標を設定していく
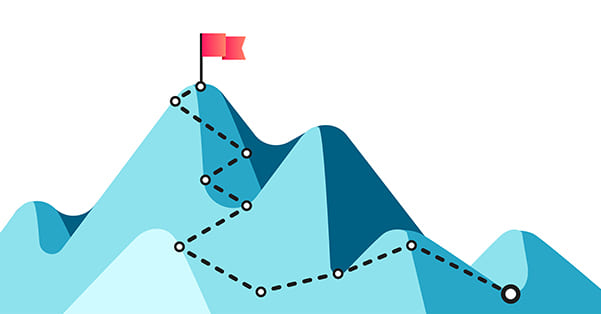
勉強できない人は、いきなり100点を目指そうとせず、まずは小さな目標をクリアして、成功体験を積みましょう。
例えば、前回受けたテストを復習して、「前回よりも10点プラスにする」「次のテストは前回より5点プラスにする」など、小さな目標を立てて、着実にクリアするようにします。
小さな目標を作り、達成していくことで、徐々に自信がつきます。まずは、小さな成功体験をたくさん積みましょう。
方法⑥親や支援機関のサポートを受ける
勉強できないだけではなく、勉強についていけなくて学校に行きたくないなど、悩みが深刻な場合は、親や支援機関(しえんきかん)のサポートを受けることも検討しましょう。
親世代や大人は、学力以外に社会で必要とされる能力を知っているからです。
勉強できない人のための塾など、支援機関はたくさんあります。
自分の将来を見据えた(みすえた)進学先を探してもらうなど、親や支援機関にサポートしてもらうことで、視野が広がることもあります。
勉強できないことは他人に相談しにくいかもしれませんが、思い切って相談して、サポートを受けましょう。
勉強できない人への5つのアドバイス
勉強ができないことで、自己嫌悪(じこけんお)に陥ったり(おちいったり)、周囲と自分を比べて落ち込む人もいるでしょう。
しかし、勉強ができないのは、努力の方法で変えられます。
ここからは、勉強ができない人へのアドバイスを5つ紹介します。
これまでの章と重複(ちょうふく)する内容もありますが、大切なことなので参考にしていただけると幸いです。
アドバイス①勉強をあきらめない
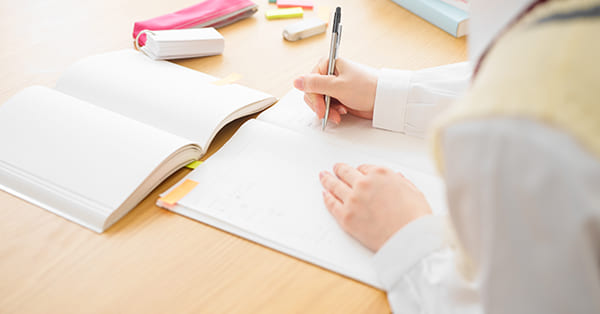
「今」勉強できないとしても、勉強をあきらめないでください。
なぜなら、自分に合う勉強法が見つかれば、挽回(ばんかい)できるからです。
勉強をあきらめると、わからないところは永遠にわからないままで、それ以上進歩することはありません。
少しずつでもいいので、勉強を続けましょう。
アドバイス②自分に合った勉強法を見つける
自分に合った勉強法を見つけるようにしてみましょう。
「認知特性が自分ではよくわからない」という人は、苦手なことを紙にリストアップしてみましょう。
世界史の暗記が苦手な人が、なぜ苦手なのかを深掘りしたところ、視力が低く「゛」と「゜」が見分けられなかったので、英語表記で覚えることにした、という例があります。
ぜひ、自分に合った勉強法を見つけてみてください。
アドバイス③将来の進路を考えてみる

「このまま勉強ができなかったら…」と考えると、不安で動けなくなる人もいます。
そこで、あえて「もし勉強ができたら?」と考えてみてください。
以下のように、「勉強ができたらしたいこと」をリストアップしてみましょう。
- 勉強ができたら宇宙に行きたい
- 有名人と一緒に仕事がしたい
- 博士号を取りたい
ワクワクすることがモチベーションとなるかもしれません。
アドバイス④親や先生に相談する
勉強できないと、親や先生など、大人に相談しにくいという人もいるでしょう。
しかし、大人からしても悩みを打ち明けてくれないと、なかなか苦しみはわからないものです。
- 〇〇で困っている
- どんな勉強法が向いているかわからない
- 将来こんなことをしたいが、行くべき大学がわからない
どのようなことでもいいので親や支援機関に相談してみましょう。
親や支援機関に相談しにくいことがあれば、無料の電話相談から、各自治体(市役所など)の相談窓口につないでくれることもあります。
ひとりで抱え込まず、周囲の大人に相談してみましょう。
アドバイス⑤勉強以外のことでも活躍する

勉強できないからといって、すべてができないと決まったわけではありません。
部活や習い事で活躍することで、思わぬ進路が拓けることもあります。
自分が好きで続けられることがあるのは、立派な強みです。
「勉強が苦手だけれども、〇〇は誰にも負けない」というものがある場合は、ぜひ継続しましょう。
「勉強できない」を乗り越えた筆者の体験談
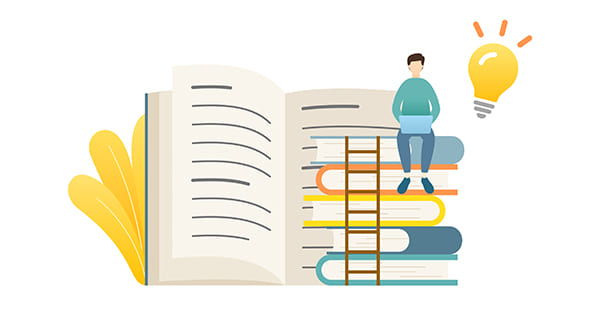
この章では、筆者が「勉強できない」を乗り越えた経験をお話します。
私は、中3のときに不登校になりました。私が「勉強できない」と実感したのは、そんな不登校になったばかりの中3の秋でした。
当時の私は、次のような思いを抱えて、勉強できない状態でした。
- 「高校受験もあるし、勉強しなきゃ」という焦りはある
- 焦り(あせり)はあるが、元々勉強が苦手で、基礎が身についていない
- 「勉強したらこれからの自分がよくなるイメージ」も湧かない
- 先生から「成績と出席日数の関係で、高校に進学できないかも」と言われて、モチベーションも低い
学校の先生をはじめ、いろんな人から「成績も悪いし、不登校の経歴がある生徒は高校には行けない可能性が高い」と言われたことで、さらにモチベーションは低下。
「これから勉強したって高校に行けないのか…」と絶望して、余計に勉強をしなくなり、ますます勉強ができなくなるという悪循環(あくじゅんかん)になった経験があります。
ですが、中3当時の私にはなりたい職業があったんです。それを叶えるためには大学に進学する必要がありました。
そして大学に進学するためには、高校、特に大学に進学実績の高い高校に行った方がよいと気がつきました。
調べてみると、中学での出席日数が問われない高校も、受験科目が少ない高校も見つかりました。
そのことを知ったことでモチベーションが上がり、私を心配してくれる家族の言葉によって、将来に少しずつ希望を持てるようになり、受験勉強を始められるようになりました。
私の場合は、「モチベーションがない」と「基礎学力がない」という状態を解決することで、「勉強できない」という状態を抜け出したということです。
その後、私は大学に進学することもできました。
まとめ〜ひとりだけで悩まずに、専門家に相談しましょう〜

勉強できない理由を解決できれば、少しずつ勉強できるようになります。
そうは言っても、勉強できない理由や特性、「どこでつまずいているのか」などは、あなたやご家族だけでは理解・解決に至ることが難しい場合も多々あります。
ご家族だけで悩まずに、学校、塾、家庭教師、カウンセラーなどに相談すると、それぞれのお子さんに合った具体的なアドバイスがもらえると思います。
私たちキズキ共育塾でも、無料相談を行っています。
どうかお子さんに寄り添い、「子どもはきっと勉強できるようになる」と信じてほしいと思います。
お子さんも親御さんも、希望を持っていただけたなら幸いです。
Q&A よくある質問