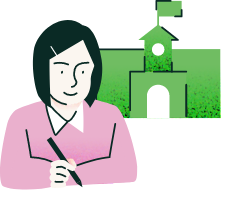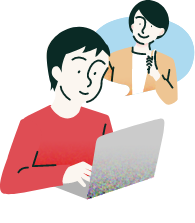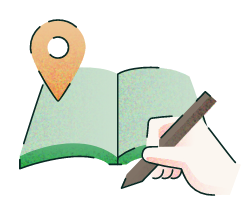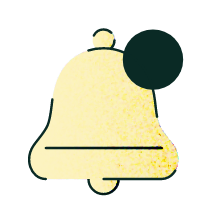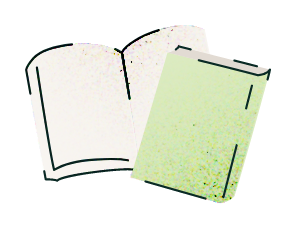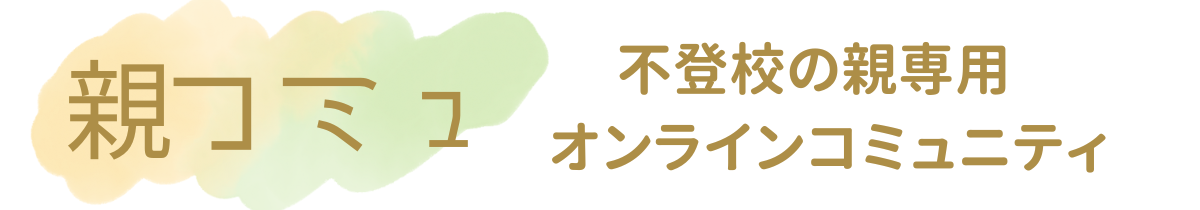自己肯定感とは? 自己肯定感が低い原因や高める方法を解説

こんにちは。お悩みのある人たちのための完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたは、「自己肯定感」という言葉を聞いたことがありますか?
最近は、インターネットやテレビでも広く使われるようになった言葉ですね。
- 勉強に身が入らない
- 仕事がうまくいかない
- 恋人ができない
そのような悩みの背後には、「自己肯定感が低い」という原因が潜んでいるかもしれません。
このコラムでは、自己肯定感の概要や高い人の特徴、低い人の特徴、高めることで得られるメリット、高める方法、高める上での注意点などを解説します。
目次
自己肯定感とは?〜読み方・意味を解説〜

「自己肯定感(じここうていかん)」とは、よい部分も悪い部分も含めて、自分のあり方を積極的に評価できる状態、自分の価値や存在意義を肯定的に評価できる状態のことです。(参考:実用日本語辞典「自己肯定感」)
精神科医の水島広子氏によると、自己肯定感とは以下のとおり、「ありのままの自分を良いと思える気持ち」のことをいいます。 「自己肯定感」とは、「優れた自分」を誇りに思うことではありません。「ありのままの自分」をこれでよいと思える気持ちです。 (参考:水島広子『自己肯定感持っていますか?』) 例えば、「有名なA大学に合格した僕はスゴい!」という思いだけでは、「自己肯定感が高い」とは言えません。自己肯定感が高い状態とは、次のような状態です。 このように、自分のいいところと悪いところ、両方含めて自分にOKを出せる状態を、「自己肯定感が高い」と言います。 こういう思考ができないと、次のような状態に陥り、「自分はダメなんだ」と落ち込むことになります。 この章では、自己肯定感の高い人の特徴について解説します。 「自己肯定感が高い」とは、自分のいいところと悪いところの両方にOKを出せる状態を言います。 つまり、自己肯定感が高い状態になると、自分の悪いところも含めて自分自身を認められるようになります。他人と比較する行為が少なくなり、比較して落ち込むことがなくなるのです。 例えば、こちらで挙げた例でいえば、「面白いことが言える人」や「交友関係の広い人」と比べることなく、自分の良さに目を向けることができています。 「自分は自分、他人は他人」という線引きがきちんと出来ているからこそ、ポジティブに現実を捉えることができます。 『「自己肯定感」を高める子育て』によると、私たちの脳には「プラス脳」と「マイナス脳」があり、プラス脳になると、「周りの人に耳を傾けて、きちんと判断し、ものごとを受け入れることができる」と記されています。(参考:ダニエル・J・シーゲル、ティナ・ペイン・ブライソン、桐谷知未・訳『「自己肯定感」を高める子育て』) 自己肯定感が高い状態とは、正に「プラス脳」が働いている状態です。 自分の意見と他人の意見が異なる時でも、否定的な反応や感情的に攻撃することなく、事象を捉え、受け入れることができます。 放課後NPOアフタースクール代表理事の平岩国康氏の『子どもの「やってみたい」をぐいぐい引き出す!「自己肯定感」育成入門』では、下記のように書かれています。 「長所」と同じくらい、子どもの自己肯定感を上げてくれるものは何でしょうか?それは「夢中になれるもの・好きなこと」だと思います。いつもみんなの中で自信がなさそうにしょんぼりしていた子が、コマ回しや将棋など、得意な遊びや得意な分野が見つかったことをきっかけに、自信をつけていくようになった例を、たくさん見てきました。 (参考:平岩国康『子どもの「やってみたい」をぐいぐい引き出す! 「自己肯定感」育成入門』) このように、「やってみたい」という気持ちが「できた」という達成感に変わると、小さな成功体験を味わうことができます。この成功経験によって自信がつき、高い自己肯定感に繋がります。 自己肯定感が低いと、様々な問題を抱えます。 水島氏は、自己肯定感が低い人は、「自分をいじめているようなもの」だと言います。(参考:水島広子『自己肯定感持っていますか?』) 少し厳しい言葉にも思えますが、「自分のダメなところ探し」をすることで、自分を傷つけていじめているのです。 こちらで挙げた例で言えば、「ギターが上手でオシャレな自分」を忘れ、「成績が悪い自分」ばかりに注目して、自分で自分に「ダメな奴」とのレッテルを貼っている状態です。 自己肯定感が低い人は、自分の欠点ばかりに目を向けるため、「自分は他人より価値のない人間だ」 と思い込んでいます。 「価値がない自分」が「価値のある他人」と接するわけですから、様々なトラブルを抱えるのです。 では、具体的に、どのような傾向によって、どのような問題が起こるのでしょうか? ここからは、水島氏の著書も参考に、「自己肯定感が低いと起こる問題」を、いくつかご紹介したいと思います。 自己肯定感の低い人は、「私なんて」という意識があり、自信を持つことができません。何かにチャレンジする前にあきらめることもあります。 人生を前向きに進めることが難しくなります。 自己肯定感の低い人は、無理をしてがんばりすぎる傾向があります。 何かができないと、次のように、自分を不要に追い詰めるのです。 自己肯定感の低い人は、「ありのまま自分」を他人に悟られると、「嫌われる」「侮られる」と思い込んでいます。 それを避けるために、過度に強気な態度に出る場合があります。 例えば、ちょっとしたミスを注意されたときには、「それくらいわかっています!」と強く反抗するようなことです。このように、人間関係を、無用にこじらせるのです。 自己肯定感の低い人は、考えや行動に自信が持てないために、「自分はこうしたい」という気持ちを相手に伝えることができません。 自分の気持ちを抑えて人に合わせ、振り回されることになります。 聞きたくない友人の愚痴につき合うなどは、自己肯定感の低さの現れです。 自己肯定感の低い人は、自分に関係のないことにも「自分が悪いからではないか」と反応します。不機嫌な友達を見て、「私が何かしたから機嫌が悪いのかな?」と思うなどもその一例です。 これも、健全な人間関係の妨げとなります。 自己肯定感の低い人は、「私みたいな人間が他人に喜びを与えられるはずがない」と考えがちです。 人に何かをしてあげたいと思っても、「私なんかにされても嬉しくないだろう」とためらいます。 反対に、人が何かをしてくれても、「私は親切にされる価値がない」と素直に受け取ることができません。人間関係は、自分と他人の双方向のやり取りで生まれます。 「人にしてあげること」「人からしてもらうこと」ができない人は、人と親しくなりづらいと言えます。 その他にも、自己肯定感が低い人には、次のような傾向がありがちです。 自己肯定感が低くなる原因として、過去の挫折経験や周りの誰かと比較する癖などが考えられます。 というように、小さな失敗や些細な出来事がトラウマとなり、ネガティブな思考へと変化することは起こり得ることです。自己肯定感を下げる要因となるので注意しましょう。(参考:平岩国康『子どもの「やってみたい」をぐいぐい引き出す! 「自己肯定感」育成入門』) 自己肯定感が高まると、自信がつき、自分や相手に対して寛容的になります。 そして、個人の成長や良好な人間関係が築けるようになります。 この章では、自己肯定感を高めることで得られるメリットについてお話しします。 自己肯定感が高い人は、ありのままの自分を受け入れ、自分自身を認めることができる人です。 こちらで挙げた例で言えば、「勉強は苦手だけど、ギターが得意でファッションセンスがある」というように、長所と短所の両方をきちんと理解できています。 そうすると、自身の強みを活かして行動したり、苦手なことに関して助けを求められるようになります。 これが、「私は勉強が苦手だから、偏差値の高い大学には行けない」で考えが止まると、「自分は他人より価値のない人間だ」 と否定的に感じるかもしれません。 自己肯定感が高くなると、自分の良い部分と悪い部分の両方を認め、自分自身を正しく理解できるようになります。 『「自己肯定感」を高める子育て』によると、自己肯定感を高める重要な要素の一つに「共感力」があると語られています。(参考:ダニエル・J・シーゲル、ティナ・ペイン・ブライソン、桐谷知未・訳『「自己肯定感」を高める子育て』) 共感力とは、他人を思いやる力のこと。共感力がある人は、いらだちや怒りを感じにくく、安易に決めつけることが少ないという特徴があります。 自己肯定感が高い人は「共感力」を兼ね備えているので、否定的な言葉で他人を傷つけることはありません。また、「自分は自分、他人は他人」という線引きができるので、自分の考えを無理に押し付けることもなくなります。 また、自己肯定感が高いと感情任せに他人を攻撃することがないので、周囲の人と良好なコミュニケーションを取ることができて人間関係がよくなります。 この章では、自己肯定感を高める方法を、キズキ共育塾の事例などから、6つ紹介します。(参考:水島広子『自己肯定感持っていますか?』) 自己肯定感を高めるには、「小さな達成感」の積み重ねが有効です。 結果が数字など目に見える形で表れるものは、自己肯定感を高めやすいでしょう。 次のような方法があります。 私たちキズキ共育塾は、自己肯定感を高めたい人のための、完全1対1の個別指導塾です。 生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。 外見を変えると、自信がついてきます。 外見を変えると言っても、大きなイメージチェンジの必要はありません。 あまりお金をかけず、校則や家庭の決まりなどの範囲内でも、十分外見を変えることができます。 例えば、次のような方法があります。 髪型、服、メガネについては、雑誌などを参考にして探すのもいいでしょう。店員さんに、予算や校則などを伝えた上で、「自分に似合いそうなものをお願いします」と頼む方法もあります。 あなた自身が「好きな自分」に出会えたり、周りの人から「最近変わったね」と言われたりすることで、自己肯定感は高まります。 友達や恋人など、自分を認めてくれる存在も大切です。 友達や恋人までいかなくとも、「楽しく話ができる相手」ができるだけで気持ちは変わります。一人で悩んでいても、「話ができる相手」はできません。 外に出て、人と交流しましょう。学校や職場など日常的に通う場所以外でも、人との交流は可能です。 例えば、次のような方法があります。 人と交流し、人から認められることによって、自己肯定感は高まっていくものなのです。 自己肯定感が低い人は、「自分はこうしたい」がはっきり言えないために、人に振り回される傾向にあります。 「本当はこうしたい自分」を押し殺すので、どんどん苦しくなり、「相手との本当のつながり」をつくることができません。 まずは「本当はこうしたい自分」を大切にして表現することが必要です。 「こうしたい」を伝える第一歩として、「YES」「NO」が言えるようになりましょう。したいこと、嬉しいことには「YES」。嫌なこと、都合が悪いことには「NO」。 誘いを断ると悪いなと思う場合には、自分の事情を伝え、「また誘ってね」など一言付け加えるといいでしょう。正当な理由でNOと言うことは、悪いことではありません。 「YES」「NO」が言えるようになると、「自分はこうしたい」「こうしてほしい」という気持ちも、適切に他人に伝えられるようになります。 相手の事情とあなたの「YES」「NO」が折り合わない場合にも、しっかり話し合うことで、「自分の心」が見えてきます。 あなたの「正当なNO」に対して理不尽な態度を取る人とは、思い切って距離を置くことをおすすめします。 自己肯定感を高めるためには、「ダメな自分」をさらけ出してみましょう。 「ダメな自分」をさらけ出してみると、そこまでダメじゃないとわかったり、客観的評価を聞いて自分を受け入れられたり、ということも多くあります。 「成績が悪いから自分はダメだ」と思っている人は、信頼できる友達に「私、成績が悪くて悩んでるんだよね」と打ち明けてみてください。 「そんなことないよ」「気にするほどじゃないでしょ」と言われると、悩みがスッと消えることもあります。逆に、「うーん、確かによくないかもね」などと言われたときには、落ち込むかもしれません。 ですが、客観的に指摘されることで、「これからどうするか」を前向きに考えることができたり、心の落ち着きを取り戻せたりします。 また、「数学ができないだけで、社会の成績は悪くないでしょ」「成績は悪いかもしれないけど、 私は○○ちゃんが好きだよ」などと、あなたのいいところも指摘してくれるかもしれません。 水島氏は、「『ありのままの私』を 一度でも受け入れられた体験をすると、今まで考えられなかったようなエネルギーが湧いてきます。」と、著書の中で言っています。(参考:水島広子『自己肯定感持っていますか?』) 自己肯定感を高めるには、「あなたの欠点も含めて好きだよ」と、誰かに言ってもらうことが大切です。 他にも、「他人を無条件にリスペクト(尊重)する」ことも大切でしょう。 自己肯定感が低い人は、「自分に対する思考」に歪みが生じている可能性があります。 認知療法を使って、「認知の歪み」を治しましょう。 「療法」と言うと難しそうに聞こえますが、自分で行う簡単な方法もあります。 例えば、自己肯定感が低い人が不機嫌な顔の友達を見て、「私が悪いことを言ったからかな」と心配になったとします。 不機嫌な友達を見て、パッと「私が悪い」と考えるのは、思考の歪みです。 認知療法では、まず、自分がどのような「思考の歪み」に基づいて物事を見ているのかを知ります。 表に、以下のようなことを書いていきます。 このように、違った視点からの考えを知ることで、瞬間的に「自分が悪い」と考えている「思考の歪み」に気づき、改善していくことができます。
自己肯定感が高い人の特徴3点
特徴①他人と比較しても落ち込むことがない

特徴②落ち着いて物事を考えられる
特徴③「夢中になれるもの」を持っている

自己肯定感が低い人の特徴と原因6点
特徴①「私なんて」と思ってしまう

特徴②がんばりすぎる
特徴③過度に強気な態度に出る

特徴④他人に振り回される
特徴⑤他人の言動を自分のせいだと思う

特徴⑥人と親しくなれない
補足:その他の特徴

自己肯定感を高めることで得られる2つのメリット
メリット①自分自身を正しく理解できる

メリット②人間関係がよくなる
自己肯定感を高める方法6選
方法①小さな達成感を積み重ねる

(例:新書や名作と言われる小説を読破する)
(例:降りたことのない駅やバス停で降りてみる)
(補足:パズルなどの既製品も有効です)
(例:英検、漢検、スポーツの級、そろばんの級、書道の級など)方法②外見を変える
方法③人と交流する

方法④「YES」「NO」を言えるようになる
方法⑤「ダメな自分」をさらけ出してみる

方法⑥認知療法を行う
状況(5W1H)
朝。
一時間目の後。
Aちゃんに話しかけると不機嫌だった。
そのときの気分
そのときの考え
代わりの考え
今の気分
ただし、自己肯定感があまりにも低い人は、「代わりの考え」を自力で考えることが難しい場合があります。
そのような場合は、カウンセラーなどの専門家を頼り、一緒に行うことをお勧めします。
自己肯定感を高める上での注意点〜「自己受容」が鍵〜

自己肯定感を高める第一歩として重要なのが、「自己受容」をすることです。
自己受容とは、「その人が置かれている現実の状況を受け入れること」であり、自己肯定感を築く土台になります。
例えば、「仕事が覚えられない」と悩むAさんのケースで考えてみましょう。
- 仕事が覚えられない。だから自分はダメなんだ。
- 仕事が覚えられない。だから毎日教えてもらったことを復習して、自分にできる最大限の努力をしよう。
前者は、「仕事が覚えられない」という現状に対し、「だから自分はダメなんだ」と自己否定をしています。その一方で後者は、現状を受け入れ「その上で自分ができること」に目を向けています。
人が置かれている現実の状況には、すぐには変えられないことや自分の意志では変えられないことがあります。だからこそ、今の状態を受け入れた上で、今の自分ができることに目を向ける必要があるのです。
前者のように現状を否定をすると、自己肯定感が下がり、自分が嫌いになります。自己肯定感を高めるためには、「ありのままの状態を受け入れる」ことが大切です。
自己受容については、以下のコラムを解説します。ぜひご覧ください。
子どもの自己肯定感を高める方法2選
この章では、視点を「保護者」に変えて、自己肯定感についてお話ししたいと思います。
「子どもの自己肯定感を高めたい」と考える親御さんは多いですよね。
しかし、そう思う一方で「具体的に何をしたら良いかわからない…」と頭を抱える方がほとんどではないでしょうか。
そこで、放課後NPOアフタースクール代表理事の平岩氏の著書を参考に、子どもの自己肯定感の育み方を解説します。(参考:平岩国康『子どもの「やってみたい」をぐいぐい引き出す! 「自己肯定感」育成入門』)
方法①変化に気づく

平岩氏曰く、教育熱心で一生懸命な親ほど、「成果」に注目して褒めることが多いそうです。しかし、平岩氏は「成果を褒める」よりも「変化に気づく」ことが重要とお話しされています。
- 子どもがテストで良い点数を取った
- 野球の試合でホームランを打って勝った
これは「良い点数」や「ホームランを打った」というように、成果を褒めている状態です。
成果だけを評価されると、子どもは「価値があるのは自分ではなく、〇〇ができる自分」という気持ちが生まれます。
良い点数が取れなくなったり試合で活躍できなくなると、「自分はすごくない」と自己肯定感が下がるきっかけになるのです。
だからこそ、成果に注目するのではなく、努力している姿勢や小さな成長に目を向けて評価することが大切です。
- テストで良い点を取るために、勉強時間を積極的に確保していた
- 試合で活躍するために、誰よりも素振りの練習をしていた
というように、子ども自身がどんな努力をして得た結果なのかに目を向けるようにしましょう。
方法②子どもの成長を喜ぶ存在になる
子どもが自己肯定感を持つ条件として、平岩氏は「自分(子ども)の成長を喜んでくれる人がいるかどうかが重要になる」と話しています。
実際に「お父さんやお母さんが喜んでくれるから頑張る」という思いで努力をする子どもは少なくないそうです。
学校や課外活動では、成績や実績で評価されることが多く、努力したことが全て報われるとは限りません。しかし、親という立場なら、成果だけでなく「挑戦したプロセス」に目を向け、認めることができます。
- テストで良い点を取るために、たくさん勉強して偉かったね
- チームを勝たせるために、誰よりも熱心に練習を頑張ったね
大切なのは、子どもが挑戦したことに目を向けて、第三者の視点で喜ぶことです。
親御さんが「子どもの成長を誰よりも喜ぶ存在」になることで、子どもの自己肯定感が育っていきます。
まとめ〜自己肯定感を高め、幸せに生きていきましょう〜

ここまで自己肯定感について解説してきました。
あなたの自己肯定感が高まり、幸せに生きられるよう祈っています。
さて、こちらで紹介した自己肯定感の高め方のひとつである「小さな達成感を積み重ねる」の発展形として、「しっかり勉強する」という方法もあります。
「勉強して知識を得て努力して大学に合格した」。このような体験は、自己肯定感を大きく高めてくれます。
私たちキズキ共育塾では、勉強によって自信をつけ、自己肯定感を高めていった生徒さんも多くいらっしゃいます。
また、授業では、勉強の話だけでなく、悩み相談や雑談もできます。
自己肯定感の低さに悩んでいるのでしたら、ぜひ一度ご相談ください。相談は無料です。
Q&A よくある質問