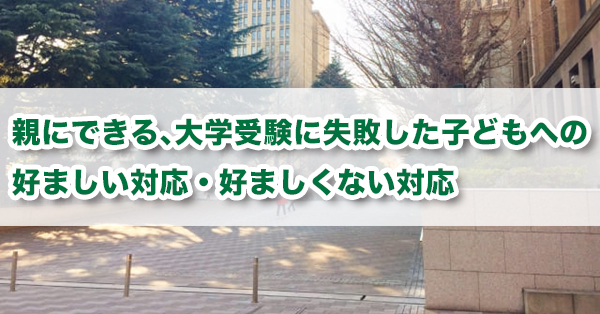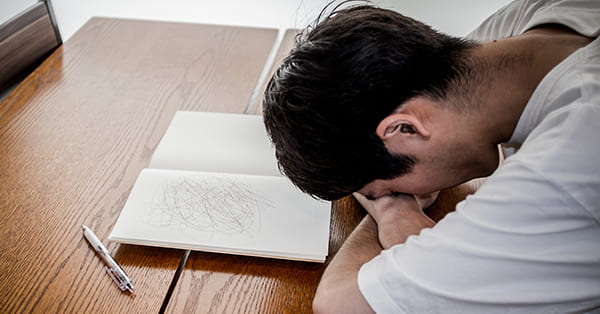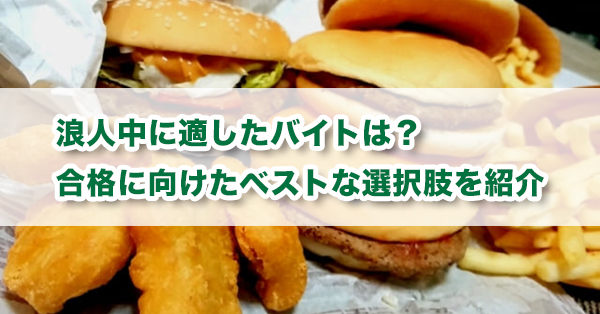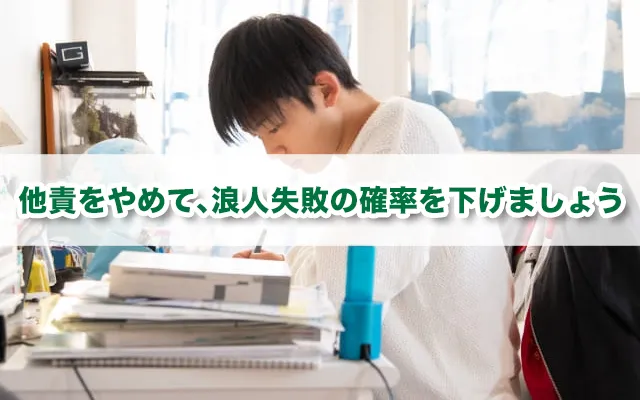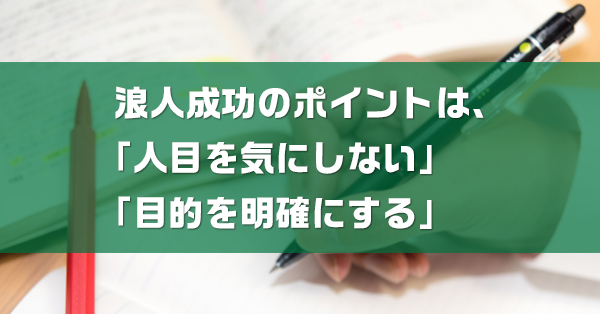浪人失敗の原因とは? 浪人に失敗しないための方法を解説
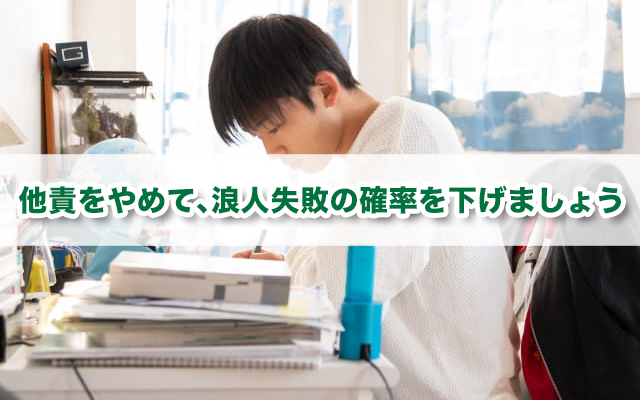
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
浪人中または浪人をしようか迷っているあなたは、「浪人しても失敗するかも…」と不安を感じているのではないでしょうか?
このコラムでは、浪人に失敗しやすい人の特徴、浪人に失敗しないための方法、浪人に失敗したときの対処法について解説します。
なお、このコラムは、あなたを不安にさせるためのものや、あなたを脅すためのものではありません。
そのため、これからお伝えする浪人に失敗しやすい人の特徴などが今のあなたにもし当てはまっても不安にならず、「これから改善していけば大丈夫」とポジティブに捉えるようにしてください。
「浪人に失敗したくない」「浪人生活を充実させて合格したい」と思うあなたのお役に立ちましたら幸いです。
私たちキズキ共育塾は、浪人中の勉強にお悩みの人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
浪人に失敗する原因
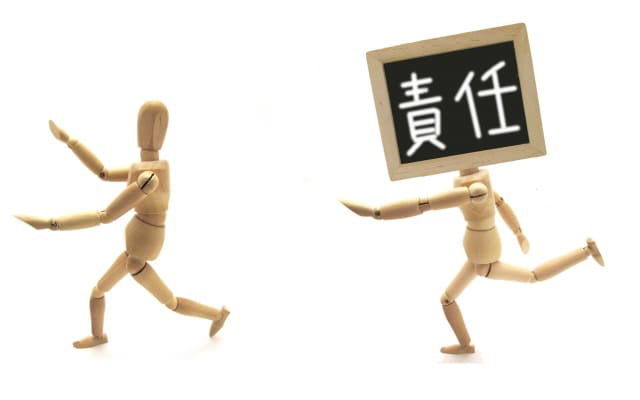
一般的に、浪人の失敗とは第一志望の学校に不合格であり、浪人の成功とは第一志望の学校に合格と考えられます。
そのため、浪人失敗を防ぐ方法として、以下のようなことを思い浮かべるかもしれません。
- みんなが通ってる大手の予備校に行く
- 予備校で評判のよい先生に教わる
- 1日最低10時間は勉強する
もちろん、これらが効果的な場合もあります。
ですが、大手の予備校よりアットホームな個人塾が向いてる人もいます。また、誰もが評判のよい先生の授業を受けられるわけではありません。
さらに、志望校とあなたの相性によっては、1日の勉強が10時間では足りない、もしくは10時間もいらない場合もあります。
つまり、以上の方法は、誰にでも有効な方法ではないのです。
では、誰にでも有効な浪人失敗を防ぐ方法とは、どのような方法なのでしょうか?
その方法を見つけるために、誰もが共通して持つ生活習慣や行動に注目してみます。
浪人に失敗しやすい人の生活習慣や行動には、共通点として他責思考が隠れているのです。
あなたは、受験に失敗したことについて、以下のように人のせいにしたことはありませんか?
- 塾が悪かったんだ。来年は他の塾にしよう
- 僕もあの先生に教えてもらえていたら、成績が伸びたかもしれないのに…
受験に失敗して落ち込んでいると、失敗を人のせいにしたくなることもあると思います。
うまくいかないことが続けば、何をやっても無理だとネガティブな気持ちになることもあるでしょう。
また、実際に予備校や先生があなたに合っていなかった可能性もないとは言い切れません。
ですが、他責思考をやめて自分に向き合うと、今まで見えていなかった失敗の原因が見えてきます。そして、浪人失敗の可能性を下げることにもつながるのです。
こちらで解説する浪人に失敗しやすい人の特徴には、浪人に失敗したことを人のせいにする他責思考が隠れています。
例えば、以下のようなことを考えたことはありませんか?
- 友達から誘われたから遊んでも仕方ない
- 学力が伸びないのは塾のせいだ
- 授業で居眠りするのは、先生のせいだ
- 予定が予備校しかないんだから、生活が乱れても仕方ない
- ○○先生、神授業! ××先生、マジ眠い
- 親が「大学行け」って言うから仕方なく勉強している
このように、勉強がうまくいかないことを他人や環境のせいにするのが、他責思考です。他責思考の人は、自分に関連することを、自分で責任を持って考え行動できていないのです。
もちろん、うまくいかないことの全てがあなたのせいではありません。
あなたの言い分が正しいこともありますし、悪い他人もいるでしょう。また、自分を責めてばかりいるのもよくありません。
ですが、何でもかんでも「他人が悪い」「自分は悪くない」と考えていては、勉強も人生も、前向きには進みません。
逆に、他責思考を手放し勉強を続ければ、浪人に失敗する可能性は下がるのです。
浪人に失敗しやすい人の5つの特徴
筆者は、キズキ共育塾の前にも、いくつかの塾で講師やスタッフとして働いた経験があります。
いろいろな塾でたくさんの生徒の合格と不合格を見てきた経験から、浪人に失敗する人、第一志望校に合格しない人たちには、いくつかの特徴があるを感じていました。
もちろん、この特徴があると必ず浪人に失敗するわけではありません。
以下、浪人に失敗しやすい人の5つの特徴を、詳しく解説します。
特徴①誘惑に負けている

勉強しようと思っていたのに、友達の誘いやその場の雰囲気に流されて遊びにいっていませんか?
飲み会、合コン、遊園地など、時間に余裕がある浪人生は、このような誘惑も多いです。
また、「誘惑に負けちゃダメだ!」「家で1人で勉強しよう!」と心を入れ替えようとしても、家の中も誘惑の宝庫です。
布団でゴロゴロ、ゲームをピコピコ、お菓子をモグモグ…。適度な息抜きはするべきですが、毎日誘惑に負けていたら勉強が進みません。
その結果、浪人失敗の可能性が高まるのです。
特徴②塾に通って安心している
塾に通っていることで、志望校に合格できると思っていませんか?
有名な塾に通っている、毎日ちゃんと授業を受けている、などと安心していませんか?
確かに塾に通えば、学力が伸びる可能性が高いです。中には、塾の授業だけで合格する人もいるかもしれません。
ですが、全ての受験生・浪人生が塾に通っているだけで合格できるわけではないでしょう。
同じように塾に通っていても、塾以外ではしょっちゅう遊んでいる浪人生と、塾から帰っても予習・復習をしている浪人生では、塾で得られる効果が全く違うのです。
特徴③不健康な生活をしている

あなたは今、規則正しい生活を送っていますか?
浪人生になってから、朝寝坊や夜更かし、不摂生などが増えていませんか?
中には、「学校に通っていたときは、こんな生活リズムではなかったのに…」と思う人もいるかもしれません。
海外旅行の時差ボケと同じように、一度崩れた生活習慣をもとに戻すのは大変です。
風邪をひきやすい、授業中に眠いなど、受験勉強を妨げる症状が出てきたら要注意です。
特に、宅浪をしている人は、生活が不規則になりやすく不健康な生活になりやすいことを覚えておいてください。
宅浪を成功させる方法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
特徴④こだわりが強い
塾の先生を選り好みしたり、先生によって授業に優劣をつけたりしていませんか?
例えば、「有名な先生の授業しか受けたくない」「あの授業はつまらないから、さぼっちゃおう」などと思っていませんか?
自分なりの考えをもって行動することは悪いことではありません。実際につまらない授業もあると思います。
ですが、なんでもかんでも自分の思いどおりに好き勝手に行動するのは危険です。
過去に受験に失敗した経験がある浪人生のあなたの受験勉強には、少なくとも間違っている部分や足りない部分があります。
先生たちの短所に着目して授業を受けない人よりも、先生たちの長所を貪欲に吸収する人の方が、成長することは明らかです。
スポンジが水を吸収するように、勉強に取り組む姿勢が大切なのです。
どんな先生からも学ぼうとする姿勢が薄れてきたら、黄色信号だと思うようにしてください。
特徴⑤受験が自分の意志ではない

親などの周りの人から「大学くらいは行っておきなさい」と言われて、受験に取り組んでいませんか?
そういう人は、「どこに進学すればいい?」と迷い、「何のために受験をしているんだろう…」と不満を抱きがちです。
明治、青山、立教、中央、法政…あなた自身に明確な受験の目的がなければ、有名な大学を思い浮かべるかもしれません。
ですが、そんな状態では主体的に勉強に取り組めませんし、「難しい。受かる気がしない、どうしよう…」と悩むことに繋がります。
浪人に失敗しないための8つの方法
この章では、浪人に失敗しないための方法について解説します。
実際にキズキ共育塾に通っていた生徒さんの経験談に基づいたものもあるので、浪人中または浪人を検討しているあなたにも役立つはずです。
また、こちらで解説した浪人に失敗する可能性を高める他責思考をやめるための方法や事例も交えて紹介します。
思考や行動をいきなり変えるのは難しいかもしれません。また、8つの方法の全てにいきなり取り組むのは大変です。
まずは気楽に読み進め、塾や予備校などの利用も検討しながら、これからどうしていくかを考える材料にしてください。
方法①生活習慣を整える

まず、早寝早起きと朝ごはんをしっかり食べることが大切です。(参考:農林水産省「 「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進」)
生活リズムが整えば、健康的に過ごせるようになります。あの先生の授業は眠い、浪人中は生活が乱れても仕方ない、などの他責の考えを防ぐことにもつながるはずです。
また、私たちの体には、体内時計と呼ばれる機能があります。
体内時計とは、25時間の周期で睡眠や体温、血圧、ホルモンの分泌などのコントロールを行う機能です。(参考:農林水産省「みんなの食育」)
一日は24時間なので、このズレを調整する必要があります。
朝日を浴び、朝食を取ると、この体内時計がリセットされ、一日の生活リズムが整うのです。
生活リズムが整えば、以下のような症状が解消されると言われています。
- お腹が減って、イライラ
- 脳がボーっとして、勉強に集中できない
- 体がダルい
人にはそれぞれの生活スタイルがあり、それぞれの生活リズムがあることは当然です。ですが、多くの試験は朝早くから実施されます。
そのため、受験生・浪人生の間は、受験に適した生活習慣(早寝早起き、朝ごはん)が大切なのです。
方法②とりあえず机に向かう
勉強のやる気が出ていない状態でも、とりあえず机に向かって勉強を始めることが大切です。
やる気がなくても、いいのです。
そもそもやる気なんて存在しない、という脳科学の説もあります。
薬学博士で東京大学薬学部教授の池谷裕二先生の言葉を引用紹介します。
仕事、勉強、家事などのやらないといけないことは、最初は面倒でも、やりはじめると気分がノッてきて作業がはかどる。そうした行動の結果を「やる気」が出たから……と考えているだけ
つまり、とりあえず机に向かって、勉強を始めることが大切なのです。
とりあえず机に向かう姿勢が身につけば、勉強がはかどり始めます。そして、「塾に通ってるから大丈夫だよね」「友達から誘われたから遊びに行こう」といった他責につながる行動が減っていくはずです。
とはいえ、机に向かっても何を勉強すればいいかわからない人も多いと思います。
方法③好き嫌いしない

「この授業、つまらないな」「この先生、嫌いだな」と思っても、好き嫌いせずに最後まで話を聞くことが大切です。
どんなことでも、学ぶことやおもしろいことがあるはずと考えること、そして好奇心を持って授業を受けてみてください。
好奇心を研究しているカリフォルニア大学の神経科学者であるDr. Charan Ranganath、Dr. Matthias Gruberと心理学者のBernard Gelmanたちは、実験によって以下のことを結論づけました。
好奇心をもった脳の状態は、学ぼうとしているその問題に対する学習・記憶効率を高めてくれる
States of Curiosity Modulate Hippocampus-dependent Learning via the Dopaminergic Circuit. Gruber MJ, Gelman BD, Rangnath C. Neuron. 2014 Oct 1.
つまり、受験勉強でも、科目や先生などによって好き嫌いせずに、好奇心を持つこと、少なくとも興味を持つことが大切なのです。
好き嫌いをしなければ、勉強方法や先生に対するこだわりなどの他責につながる行動が減ります。そして、勉強もはかどるのです。
また、親が言うから大学に行こうとしている場合も好奇心を持てば、こういう理由で大学に行きたい(または行かずに就職などをしたい)など、自分なりのモチベーションが出てきます。
方法④自分に合った方法・教材で勉強する
自分に合った方法・教材で勉強することも、とても大切です。人によって、合う方法は異なるのです。
暗記方法の例
- 声に出した方が覚えやすい
- ひたすら紙に書く方が覚えやすい
勉強場所の例
- 自宅が一番集中できる
- 塾やカフェなど生活空間から離れた方が勉強が捗る
教材の例
- イラストや図がたくさん載っている方が理解しやすい
- 文章で丁寧に解説されているの方テキストの方がわかりやすい
キズキ共育塾に通う生徒さんの中にも、自身に適した教材や方法で勉強に取り組んだことで、無理なく勉強を続けられた生徒さんがいました。
以下、キズキ共育塾の生徒さんの声を紹介します。
担当の先生と、とてもよい関係を築けたので、キズキに通うようになってから勉強面も生活面も落ち着いていきました。
教材と勉強量が自分に合っていると感じました。また、授業をすべてオンラインで完結できたこともよかったです。
このように、自分に合った教材や方法で勉強ができれば、前向きに勉強を続けられたり、効率よく学習が進んだりするのです。
とはいえ、自分一人で自分に適した教材や勉強方法を見つけるのはとても難しいですし、時間がかかることが多いです。
浪人中の貴重な時間を有効的に活用するためにも、勉強・受験のプロのサポートを受けられる塾や予備校などの利用を、検討してみてください。
方法⑤しっかりと基礎を固める

浪人する場合でも、基礎固めに取り組むことが大切です。
受験勉強において、基礎固めは欠かせません。
基礎は学力の土台となるため、基礎固めができていれば新たな単元でもスムーズに理解できます。また、難しい問題を解く場合も、基礎が固まっていれば、基礎を応用して問題を解けるのです。
キズキ共育塾の生徒さんの例を紹介します。
最初に使った教材は、先生と話して、まずは基礎からの学び直しという観点で選びました。
基礎の部分は、勉強が得意だった高校1年生とか2年生とかの内容なので、「そこから…?」と思ってちょっとイヤな部分もありました。
ですが、「実際にできていない」という現実があるので、「ちゃんとやらなきゃな」と気持ちが引き締まりました。
この生徒さんは、基礎固めをしっかりと行ったことで、自分では難しいと思っていた大学に合格できました。
全くゼロから勉強し直す必要はありません。ですが、できていない部分や不安なところと向き合うことが、浪人失敗を回避することにつながります。
ご紹介した生徒さんの経験談は、以下の体験談でさらに詳しくご覧いただけます。
方法⑥演習を通して本番形式に慣れる
演習を通して本番形式に慣れることも、浪人に失敗しないための方法になります。
浪人をしてどれだけ準備をしていても、試験本番では緊張するものです。
「問題の難易度が上がっていたらどうしよう…」「本当に合格できるのかな…」と考えていると、緊張感が高まりいつもどおりの力を出しきれないことも珍しくありません。
本番で実力を発揮できるための方法として、例えば、普段行う問題演習をテスト形式にすることによって本番形式に慣れるがあります。
キズキ共育塾の生徒さんの例を紹介します。
化学の授業で主に取り組んだのは、本番で緊張する癖を治すことでした。私は極度のあがり症でした。
なので、普段の問題演習からテスト形式で行い、本番に慣れるよう努力しました。授業前に時間を計って問題を解き、授業ではその答え合わせと解説を行うんです。とにかく、習うより慣れろ、という感じでした。
そのおかげで、「わからないところがあっても、とりあえず解ききることが大事」と前向きに考えられるようになりました。試験の途中で手が止まることもなくなり、すごく成長できたと感じています。
このように、日頃の勉強の中でのちょっとした工夫や心掛けが、浪人失敗を回避することに繋がるのです。
ご紹介した生徒さんの経験談は、以下の体験談でさらに詳しくご覧いただけます。
方法⑦大学進学の明確な目的を持つ

浪人に失敗しないためには、大学進学の明確な目的を持つこともとても大切です。明確な目的があることで、浪人・勉強のモチベーションを保てます>。
キズキ共育塾の生徒さんの例を紹介します。 このままでは浪人してもどこにも受からないのでは…という不安で頭がいっぱいだったことを覚えています。 そんな僕が、ネジを巻きなおして精いっぱい勉強に打ち込めるようになったのには、二つのきっかけがありました。 (中略) 二つ目は、やりたいことが見つかったことです。授業では、科目の解説だけでなく、面白い新書の紹介などもしてもらっていたのですが、それらの読書を通じて、マスコミ分野に興味を持ったのです。 それまでは「何にために大学に行くのだろう…」と確信を持てずにいましたが、やりたいことを発見できたことで、気持ちを切り替えることができました。 一浪して迎えた二回目の受験の結果は、補欠合格。手放しで喜べはしませんでしたが、3月に補欠から正式な合格に昇格できました。 この生徒さんと同じように、浪人中はどうしても「今年本当に合格できるのかな…」と不安が頭によぎると思います。 そんな不安や心配を和らげる方法の1つが、大学進学の明確な目的を持つことなのです。 目的がはっきりしていると、不安や心配以上に、将来への期待感や頑張ろうと思う気持ちが大きくなります。 不安や心配から勉強に手がつかない人は、一度ご自身と向き合って大学に進学する目的を考えてみてください。 ご紹介した生徒さんの経験談は、以下の体験談でさらに詳しくご覧いただけます。 信頼できる人や安心できる環境で勉強することも、重視していただきたい方法の1つです。 浪人中は、現役での大学受験以上に不安が大きくなるため、心のよりどころがあることがとても重要になります。 キズキ共育塾の生徒さんの例を紹介します。 キズキ共育塾の先生は受験についての知識が豊富で、私の疑問にもしっかりと答えてくださって、とても頼りがいがありました。 私の学習状況にも合わせてくれるし、どの先生も質問しやすい雰囲気で、居心地のよさを感じました。 講師の方々が過去に同じように勉強し直して大学へ合格したエピソードを聞いたりもし、安心することができました。 受験計画は、SFCを第一志望に、早慶、MARCHの受験を設定し、1年後の受験を目指して勉強を始めました。 この人たちから教わって勉強していれば、1年後は必ず大学に行ける――そう信じて。 この生徒さんは、キズキ共育塾の講師や塾の雰囲気が合い、浪人中でも安心して勉強に取り組めたそうです。 とはいえ、人によってどのような人が信頼できるか、何があれば安心できる環境か、などは異なります。 塾や予備校を探す際は、自分自身が「信頼できる」「安心して勉強できる」と思えるかを慎重に見極めてください。 ご紹介した生徒さんの経験談は、以下の体験談でさらに詳しくご覧いただけます。 残念ながらどんなに浪人に失敗しない方法を尽くしても、うまくいかないことはあります。 規則正しい生活リズムなのに、しっかり勉強もしているのに、「どうして、私だけ・僕だけ、うまくいかないの…」と思うこともあるかもしれません。 ですが、「もう、何をやっても無駄」とあきらめるのは早いです。 なぜなら、浪人に失敗してもこれからのあなたの選択や行動によって、人生は開けていけるからです。 この章では、浪人失敗から再び立ち上がるための対処法を、メリット・デメリット、エピソードもあわせてご紹介します。 第一志望ではなくても、受かった学校がある場合は、その学校に進学するのも1つの方法です。 第一志望の学校ではないので、進学しても満足感が少ないかもしれません。 ですが、第二志望(以下)の大学であっても、大学進学の目的によっては第一志望にこだわる必要はありません。その大学で過ごすうちに楽しくなることもあります。 受かった学校に進学した事例を紹介します。 僕(筆者)が大学に行きたいと思ったのは、高校生時代に物理学会に参加したことがきっかけで、僕も大学で物理を勉強したい、物理について議論できる友達がほしい、などの気持ちがあったからです。 現役時代にも浪人時代も、第一志望の大学には不合格で、第二志望の大学に合格しました。つまり、第一義的には浪人に失敗しています。 ですが、第一志望の大学に合格しなかったものの、物理を勉強する目的は第二志望の大学でも達成できるため、浪人は成功したのです。 実際に、進学した大学では物理を勉強でき、また議論しあえる友達もでき、とても楽しい大学生活でした。 第一志望の学校を目指してもう1年がんばることも、1つの選択肢です。 すでに勉強を積み上げてきているので、さらにもう1年がんばれば、第一志望の大学に受かる可能性は高まるはずです。 一方、「あと1年もある」と考えてダラダラ過ごすと、学力もあまり上がらず、また不合格になることも考えられます。 ですが、第一志望の大学に合格しなかったとしても、できることは全部がんばったことで、満足感を持てるはずです。 もう1年浪人した事例を紹介します。 Aくんは、現役時代は先生に勧められるままに、今の成績で合格できる大学を受験し、実際に合格しました。 ですがAくんは、何の達成感もなく始まった大学生活で無気力になり、大学不登校を経て中退しました。 そんなAくんは、改めて大学入学を目指すべく浪人をしたのですが、結果として、第一志望の大学には合格しませんでした。 第一義的には浪人に失敗したAくんですが、本人は「大満足です!」と言っていました。 これは、Aくんの浪人の目的が、今年一生懸命に勉強して、努力の成果として大学に合格することと、自分の興味のある学部に進学することだったからです。 現役時代の、興味のない学部に、ほぼ勉強せずに合格して無気力になったことを踏まえての目的でした。 第二志望だった大学で学ぶ現在のAくんは、勉強や人間関係などが充実した大学生活を送っています。 大学は、必ず行かなくてはならないものではありません。 大学でしたいことがあるかもしれませんが、一旦進学せずに就職してみる方法もあるのです。 受験勉強と就職活動、大学生活と労働、どちらがあなたに向いてるのかは、やってみなければわからない部分があります。 就職を経験したからこそ、改めて大学進学の意欲が湧くことがあります。 また、逆に働くことが向いてるようであれば、親に言われて大学進学を目指していた人は、向いてない受験勉強を続けなくてもよくなります。 一度就職したらもう大学に進学できないこともありません。働くうちに「やっぱり(自分の意思で)大学に行きたいな」と思うようになったら、そこで勉強を再開すればよいのです。 ひとまず進学せずに就職した事例を2つ紹介します。 Bくんは、高校卒業後には大学進学の意思はなく、大手流通会社に就職しました。 自社工場の生産管理を独学のプログラミングで効率化し、楽しく仕事をしていました。 ですが、さらに業務改善をするにはより深い知識が必要があると感じるようにもなり、大学進学を目指すため退職。 予備校に通いながら、大学受験を目指します。受験勉強に苦労し浪人生活は2年かかりましたが、持ち前のやる気と根性で、見事志望校に合格したのです。 Cさんはイタリアに興味があり、その歴史や言語を大学で学びたいと思っていました。 家に大学進学のお金がないことをうすうす知っていた彼女は、高3の年に国立大学を受験して失敗。 浪人しようにも、費用の問題で予備校には行けません。それでもどうしても進学をあきらめたくなかったCさんは、1年間働いてお金を貯めました。 そのお金で予備校に通い、2年後に受験。見事、志望校に合格したのです。 先ほど紹介した、もう1年浪人することの延長になりますが、第一志望校へ合格するまで、浪人を続けることも選択肢の1つです。 あきらめずにがんばることで、希望が叶うことがあります。 大学に入ることに、年齢は関係ありません。 ですが一方で、残念ながらがんばり続けても叶わない場合もありますし、浪人生活を何年も続けるのは大変です。 無責任に「何年でもいいから続けよう」と言うつもりはありません。逆に「○年経ったらあきらめよう」とも言いません。 また、この方法を実施する場合は、ご自身(やご家族)の状況などもしっかり考え、詳しい人にも相談し、途中で①〜③の方法に切り替えることも柔軟に考えることが大切です。 ここでは、あきらめないことで大きな自信と満足感を手に入れた人を紹介します。 志望校に合格するまで受験を続けた事例を紹介します。 キズキ共育塾の講師・飯田先生は、5年間の浪人の末、慶應義塾大学の総合政策学部(SFC)に合格しました。 彼は、受験に失敗するたびに「1年がんばった自分をまずほめよう。そして、現状を受け入れよう」と考えていました。 その上で、また1年続けたいか自問し、「よし、もう一度がんばろう」と思える目的が見つかれば、また1年がんばる。 1年1年自分を見つめ直して、ほめるところはほめ、改善するところは改善する。そうして毎年、毎年、自分を励まし、自分を承認し続けた彼は、大学合格とともに大きな自己肯定感を手に入れたれたのでした。 こちらで解説した、受験が自分の意志ではないあなたも、自分を見つめ直してみると受験の目的が明確になるかもしれませんね。 このコラムを読んでいる方の中には、浪人に失敗したお子さんに対して、どう声をかけたらいいかわからず悩んでいる親御さんがいらっしゃるかもしれません。 大学受験に失敗したお子さんに対する親御さんの好ましい対応・好ましくない対応については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。 こちらで紹介した事例からは、一見失敗したように見えることでも、考え方を変えれば失敗ではなくなることがわかります。 例えば、何年も浪人して何度も受験に失敗しているあなたは、気付かぬうちに何年も努力できる粘り強さを手に入れているかもしれません。 現時点で学費がない人も、「お金がなければ稼げばいいんだ」などのポジティブな行動があれば、進学の道が開きます。 多浪の経験も、毎年が改善のチャンスだとポジティブに捉えれば、ただの失敗ではなくなります。 失敗が続いても、ポジティブシンキングを試し、自分の思う成功に辿りつくまでやり抜く人になればよいのです。 とはいえ、ネットの情報を見て「浪人に失敗したらひきこもりになるの?」「浪人に失敗した人の末路はどうなるの?」などの不安な人もいると思います。 受験の失敗がひきこもりにつながる理由については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。 この章では、浪人失敗を回避できた生徒さんの事例を紹介します。 ぜひ参考にしてみてください。こちらでも紹介した生徒さんの事例ですが、浪人失敗を回避できた事例としても改めてご紹介します。 石巻さん(仮名)は、受験を経て進学した中学校で、授業についていけない、人間関係が上手くいかない、などのことを経験し、不登校になりました。 また、人間関係でのつらい経験から、周りの視線が怖くなり、外出が難しくなっていきました。大学受験のためにキズキに入塾したものの、以下のような不安な気持ちを抱えていたそうです。 入塾後も、勉強にはやっぱり苦労しました。高校3年生で受験をした大学にはすべて落ちてしまい、実力不足を痛感しました。 実は、この時期はまだ本腰を入れて勉強することができていなかったんです。やらなければいけないということはわかっていても、どうしても手が動かない状況でした。 このままでは浪人してもどこにも受からないのでは…という不安で頭がいっぱいだったことを覚えています。 しかし、あるきっかけがあり、勉強に打ち込めるようになったそうです。 一つ目は、安田さんから「とりあえず毎日キズキ共育塾に来て自習してみようよ!」と発破をかけられたことです。 キズキ共育塾は、勉強を強制することは絶対にしませんが、だからこそ、この発破がけは本当に僕のことを考えてくれているからこそなんだろうなと思いました。 それからは、ともかく毎日キズキ共育塾に来て、少しずつ自習に取り組めるようになりました。 二つ目は、やりたいことが見つかったことです。授業では、科目の解説だけでなく、面白い新書の紹介などもしてもらっていたのですが、それらの読書を通じて、マスコミ分野に興味を持ったのです。 それまでは「何にために大学に行くのだろう…」と確信を持てずにいましたが、やりたいことを発見できたことで、気持ちを切り替えることができました。 その結果、補欠合格だったものの最終的には正式な合格に昇格し、大学に進学できました。今では、さまざまなアルバイトや趣味、一人旅行などに挑戦しているそうです。 このように、石巻さんの場合は、信頼できる人からの声掛けと大学進学の目的を明確にすることで、浪人失敗を回避できました。 浪人することを考えると、どうしても失敗が頭に浮かぶと思います。 ですが、あなたに合った教材・勉強方法・環境・人などとの出会いで、浪人失敗を回避できる可能性は高められるのです。 ご紹介した生徒さんの経験談は、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。 繰り返しになりますが、何でも人のせいにすることも、何でも自分のせいにすることも、浪人生活に限らず、あなたのためによくありません。 他責思考を適切にやめ、自分をよい方向に変えていくことが大切です。そうすることで、浪人失敗の確率を下げられます。 ポジティブシンキングで自分を見つめ直せば、受験の目的が明確になり、きっと勉強もうまくいくはずです。 とはいえ、生活習慣を整えようとしてもどうしてもできない、合わない先生の授業を真面目に聞いたけどやっぱり指導方針が合わない、など、悩みが解消できないこともあると思います。 また、他責思考をやめられない、やめようと思ったけど難しい、他責が何なのか自分ではよくわからないなどの場合もあるかもしれません。 ですが、どのような場合であっても、あなた一人で浪人生活をなんとかしようと思う必要はないのです。 浪人生活を失敗させないためには、浪人の指導や支援に詳しい人に相談することが大切です。 勉強は予備校や家庭教師などがあります。生活に関しては親や友達に相談してみたり、相談内容によっては自治体の相談窓口・医療機関・カウンセラーなども頼れます。 いろんな人に相談することは他責思考ではありません。あなたが安心して相談できる人を、適切に頼ってみてください。 あなたの浪人生活が失敗せず、目的が達成されるよう、祈っています。 さて、私たちキズキ共育塾でも、多くの浪人生が学んでいます。 キズキ共育塾は、勉強だけでなく、進学の目的や生活習慣などにも、完全個別指導で、あなたのための授業を実施します。 生活習慣も、東京医科大学の志村哲祥先生と共同で実施している睡眠改善プログラムも効果をあげています。 少しでも気になるようでしたら、ぜひ一度無料相談をご利用ください。
Q&A
よくある質問
方法⑧信頼できる人・安心できる環境で勉強する
浪人に失敗したときの4つの対処法
対処法①合格した学校に進学する

対処法②もう1年浪人する
対処法③進学せずに就職する

対処法④志望校に合格するまで受験を続ける
補足:大学受験に失敗した子どもに対する親の好ましい対応・好ましくない対応
浪人失敗も考え方次第で成功になる

浪人失敗を回避できたキズキ共育塾の生徒さんの事例

まとめ〜浪人失敗を防ぐために他責思考を手放そう〜