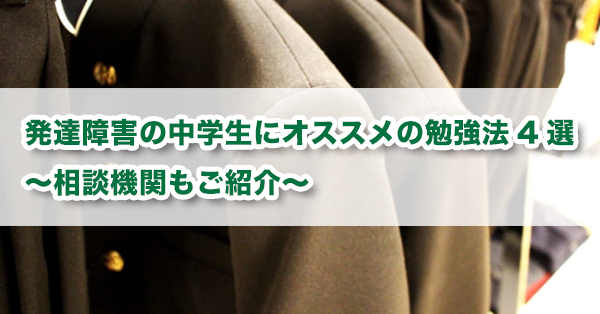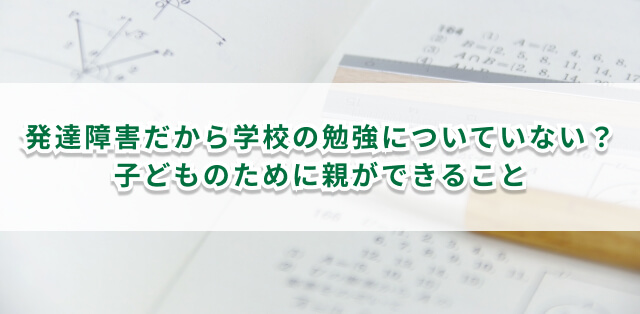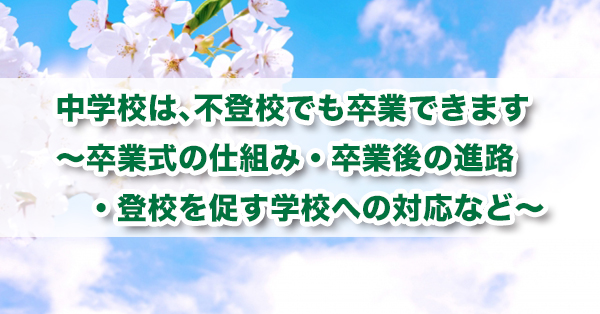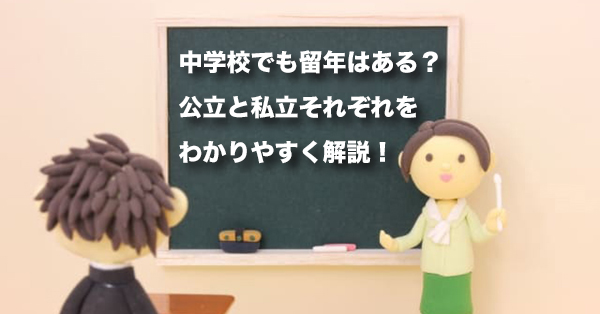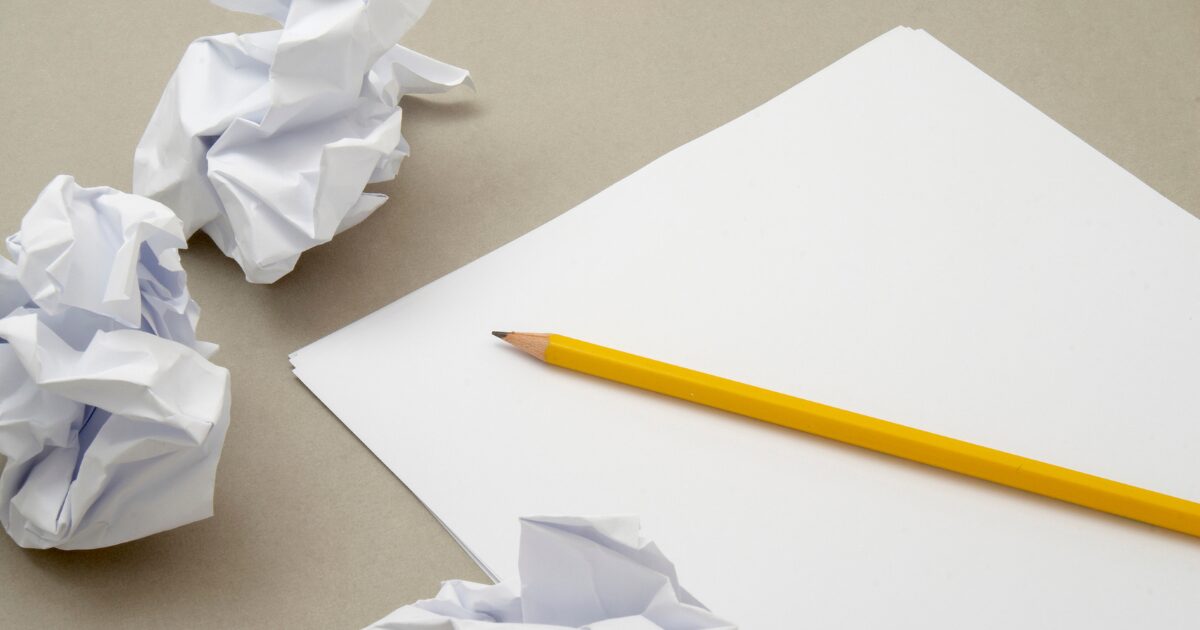勉強できない中学生に親ができる対応 勉強できない理由を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
このコラムをご覧になっているあなたは、以下のような悩みを抱えているのではないでしょうか?
- うちの中学生の子どもは勉強ができない…どうしたらいいの?
- 中学生で勉強ができないと、将来の選択肢が狭まるかも…
中学生になると勉強の難易度が上がるのはもちろん、定期テストも行われ、高校受験も迫ってきます。
親御さんはなんとかして成績を上げようと、学習塾に通わせたり、通信教材を試したりと、さまざまな苦労をしているかと思います。
しかし、お子さんは勉強ができないのではなくて、今の勉強方法が合っていないのかもしれません。
このコラムでは、中学生が勉強できない理由や親ができる対応などについて解説します。あわせて、勉強方法を変えることで成績が上がった成功事例を紹介します。
このコラムが、お子さんの可能性を広げることはもちろん、中学生のお子さんの勉強について悩む親御さんの助けとなりましたら幸いです。
私たちキズキ共育塾は、勉強できない中学生のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
中学生が勉強できない3つの理由
この章では、中学生が勉強できない理由について解説します。
中学生のお子さんが勉強をする意欲があるのに成績が上がらないという場合は、参考にしてください。
理由①自分に合う効率的な学習方法を知らない

中学生になると小学生の頃と比べ学習内容が多岐にわたり、勉強の難易度も格段に上がります。
そのため、効率的な学習方法を知らないと学校の勉強についていけなくなったり、定期テストで思うような結果を出せなかったりするのです。
暗記1つをとっても、人それぞれ合う学習方法は異なります。
- 反復すると覚えやすい
- 紙に書いた方が覚えられる
- 単語帳を使うと覚えづらい
自分に合う効率的な学習方法を身につけられれば、勉強がこれまで以上に進むため、勉強に対するモチベーションが増し、おのずと勉強するようになるでしょう。
理由②集中力が続かない
いざ勉強をしようと取り掛かっても、なかなか集中力が続かず身が入らないという場合もあります。
集中力が続かない理由は、以下のようにさまざまです。
- 勉強中の周りの騒音が気になる
- 勉強部屋の照明が適切でない
- 睡眠不足や体調不良で健康な状態にない
- 勉強机が散らかっている
- スマートフォンや漫画など周りに誘惑が多い
このように、勉強が続かないのは必ずしもお子さんだけに理由があるのではなく、勉強をする環境が問題の場合も多いです。
また、お子さんの日常生活の中の習慣やスマートフォンとの付き合い方なども影響している可能性があります。
お子さんが勉強を始めてもすぐにやめたり、他のことをしたりすると感じる際は、勉強をする環境や日常生活の様子から見直してみるとよいでしょう。
理由③健康状態や生活リズムに何らかの問題がある

中学生になると部活動や友人との交流、習い事などで、小学生の頃よりも忙しくなります。
さらに、ホルモンバランスの変化などで、心身の状態も変わりやすいため、健康状態や生活リズムが乱れがちです。
健康状態や生活リズムが乱れていると、勉強に取り組みたい気持ちがあっても集中できなかったり、勉強に取り組めていたとしても思うように問題を解けなかったりすることがあるのです。
また、定期テストや模試の当日に、体調不良や寝不足があると、これまで勉強してきたことを十分に発揮することができず、一生懸命勉強したのに結果が出ないという状態になることもあるでしょう。
睡眠不足や食生活の乱れ、スマートフォンの見過ぎやストレスの蓄積など、心身の調子を乱すものはないか、今一度見直してみるとよいでしょう。
補足:勉強できない理由には発達障害が関連していることがある
発達障害とは、脳内の情報処理や制御に偏りが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。
発達障害の特性の中で勉強面で関連してくるのは、以下のようなものがあります。
- 先生の話を最後まで聞いたり、指示に従ったりできない
- 文字を読むことや文章を書くことが苦手
- 相手の気持ちを考えたり、未来を予測したりという推論ができない
発達障害の特性が影響して勉強に関する困りごとを抱え、勉強についていけなくなるお子さんも少なからずいます。
お子さん自身が発達障害とうまく付き合っていくためには、まずは親御さんが発達障害について深く知ることが大切です。
発達障害のあるお子さんへの勉強面のサポートについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
また、発達障害のあるお子さんをサポートをしている学習塾などもあるので、ぜひ利用してみてください。私たちキズキ共育塾でも、発達障害の特性に悩むお子さんのサポートをしています。
いつでも無料相談を受け付けているので、お困りごとがあればぜひ相談してくださいね。
勉強できない中学生に親ができる7つの対応
以下のように、一生懸命勉強しているのに勉強ができない中学生のお子さんは少なくありません。
- 学校の授業をしっかり受けている
- 自宅でも学習に取り組んでいる
- 学習塾に通ったりもしている
そんな中学生のお子さんは、自分に合う効果的な勉強ができていないことが考えられます。具体的には、いつ、何を、どれだけ、どのようにやるかが明確になっていないのです。
やみくもな勉強は効率が悪く、一生懸命勉強していても、勉強ができない状態は変わりません。
この章では、勉強できない中学生に親ができる対応について解説します。
対応①現在の学力を知る

まずは、お子さんの現在の学力を把握することが大切です。
どの単元をどこまで理解しているか、どの単元のどこから理解していないのかを、細かく確認しましょう。
わからない単元をそのままにしていることで、そのあとに学習する単元や発展問題ができなくなることは、よくあることです。
また、現在の学力がわかれば、勉強が必要な単元、量、難易度などが見えてきます。
しかし、親御さんだけでお子さんの学力を明確に把握するのは、難しいかもしれません。
そのため、以下のような方法で、お子さんの学力を把握してみてください。
- 三者面談・家庭訪問・参観日などで学校の先生に相談する
- 学校のテスト・模試・習熟度テストの結果を学習塾に持って行って相談する
- 学習塾を利用しお子さんの状況を見てもらう
家庭学習で市販の教材を使っている場合は、その教材の単元別の理解度や正答率を、相談の際に伝えるとよいでしょう。
学校や学習塾への相談は、お子さんの性格や状況によって、以下のようなパターンが考えられます。
- はじめは親だけで相談する
- 親子で一緒に相談する
- まずはお子さんに任せる
対応②つまづいた部分を明確にする
勉強でつまずいた部分から丁寧に学び直すことで、勉強ができない状況は解決に向かいます。
例えば英語の場合、中1の始めにbe動詞を学習します。be動詞は、英語の勉強の基礎です。
筆者の経験上、be動詞を理解できなかった子どもは、その後の単元も芋づる式に理解できていないことが非常に多いです。
また、数学の場合、例として次の問題をご覧ください。
- 65ab÷5a
この問題では、数字は65÷5を計算し、文字(定数)はa÷aを計算します。この問題は、割り算と多項式の基礎学力で解けます。
しかし、基礎学力がないと何がわからないのかわからない状態になります。発展形の問題やその後の単元なども、理解することが難しいでしょう。
be動詞、割り算、多項式など、つまづいた単元から学び直せば、少しずつ今の単元まで理解できるようになります。
つまり、どこかの単元でつまづいたことで勉強ができない状態になっている中学生のお子さんは、つまづいたところから学び直すことが必要不可欠なのです。
また、1つのわからない単元を克服できたとしても、その後に新たなわからない単元に出合ったときは、学校や学習塾に相談するようお子さんに伝えましょう。
対応③お子さんに合う勉強法を知る
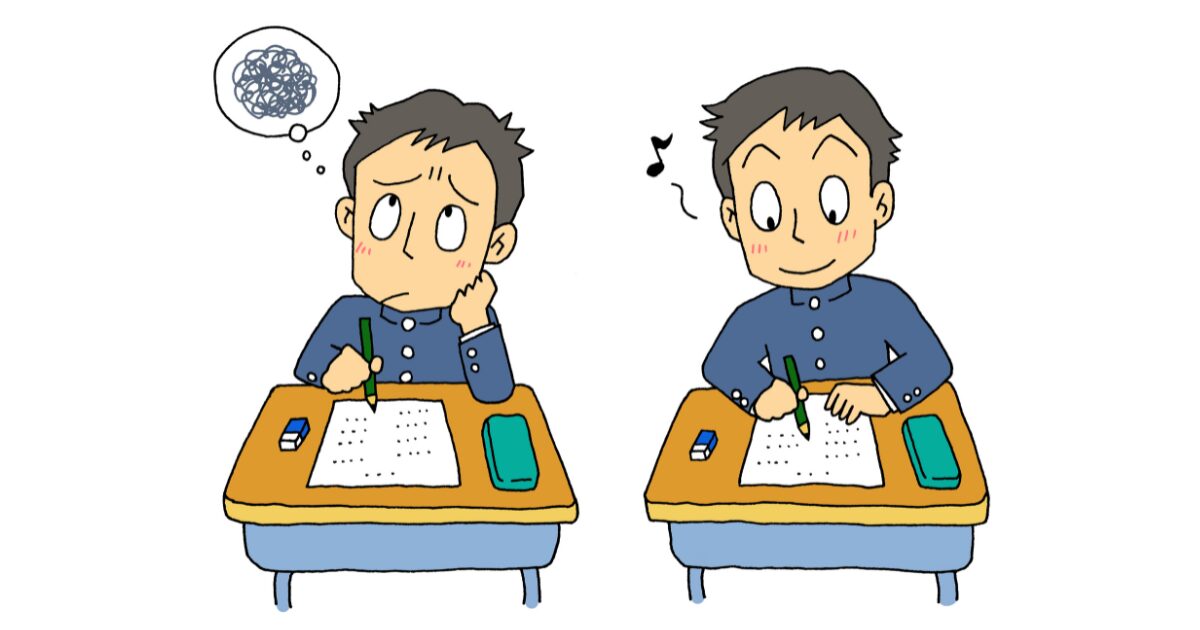
現在の学力を把握し具体的な目標が定まれば、おのずと成績は伸びていき、勉強ができない状態は少しずつ改善されます。
ただし、並行してお子さんに合う勉強法を見つけることが大切です。
勉強すると言っても、方法はたくさんあります。合わない勉強法を続けていると、なかなか成果が出ないことがあるのです。
逆に、お子さんに合う勉強法が見つかれば効率よく勉強を進められ、成果が出やすくなります。
勉強法は無数に存在するため、お子さんに合う勉強方法を見つけるために、試行錯誤を重ねましょう。
参考までに、いくつか例を紹介します。
勉強方法の例
- 家で集中できなければ、外で勉強する
- お子さんが効率的に勉強できる時間帯を把握する
- 集中するために時間制限を設ける・タイマーをセットする
- 寝る前に知識を身につけ、朝起きてから問題演習を行うなど、お子さんにあった勉強サイクルをつくる)
- 英単語や古文単語をふせんに書き、目につく場所に貼る(例:表に英語、裏に日本語訳を記入するなど)
- 勉強に関する作品から学ぶ(例:『ドラゴン桜』『ビリギャル』など)
もう少し具体的な勉強方法の成功事例は、こちらで紹介します。
対応④目標を定める
現在の学力を把握できたら、次は目標を定めましょう。わからない単元が見つかり学び直すときも、同様です。
目標を決めていないと、勉強内容があいまいになる恐れがあります。
そして、あいまいな勉強をしていると各単元の基本を理解できても、少し難しい問題になると理解できなくなるのです。
- 目標の悪い例
- 次のテストで70点取る
- 1日3時間勉強する
以上の目標は、目標を数値化している点はよいのですが、少し不十分です。
具体的な行動につなげるためには、目標数値に加えて目標達成のために、いつ・何を・どれだけやるかを明確にしましょう。
例えば、以下のようなイメージです。
目標のよい例
- 次のテストで70点取る→そのために、1日にテキストを◯◯ページずつ進めていく
- 1日3時間勉強する→苦手な単元は◯時間勉強して、得意な部分は◯分だけ勉強する
現在の学力を把握していれば、目標の具体化はそれほど難しくありません。
目標設定の方法でも、以下のようなパターンが考えられます。
- はじめはお子さんに任せる
- 親御さんとお子さんで一緒に決める
- 学校の先生や学習塾の講師と話しながら決める
お子さんと親御さんの状況に合わせて、実際に取り組めそうな方法を選びましょう。
対応⑤認知特性を理解する
少し難しい話になりますが、認知特性を理解することも重要なポイントのひとつです。
認知特性とは、情報をどう認識し、どう覚えるかの人それぞれの特徴のことです。これは、人によって異なります。
この認知特性は、勉強法にも関係します。例えば、聴覚優位視覚優位などの言葉を聞いたことはあるでしょうか?
- 聴覚優位:耳で聞いた情報を処理することが得意
- 視覚優位:目で見た情報を覚えることが得意
聴覚優位のお子さんの勉強法として、重要部分を繰り返し口に発したり、歌にしてまとめたりなどすると効果的です。最近は重要な暗記項目を歌でまとめるyoutuberもいるため、その動画を利用するのも一手です。
視覚優位のお子さんの勉強法として、勉強の内容を、文字だけでなく、絵や図にまとめたものも見たりすると、より深く理解ができます。
いくつか勉強法を試すことで、お子さんが聴覚と視覚のどちらが優位か、どの勉強法が向いているかなどが次第にわかっていきます。
また別の考え方として、ハーバード大学の心理学者、ハワード・ガードナー氏によるマルチプル・インテリジェンスがあります。
簡単に言うと、全ての人間には8分野の知能があり、自分の得意・不得意分野を知ることで、自分に合った勉強方法などがわかるのです。
8分野の知能
- 言語的知能
- 論理・数学的知能
- 空間的知能
- 音楽的知能
- 身体運動的知能
- 対人的知能
- 内省的知能
- 博物的知能
わかりやすいように単純化すると、以下のようになります。
- 対人的知能が高いお子さんは、教師や友達などの人と一緒に対話形式で勉強する
- 音楽的知能が高いお子さんは、替え歌にして暗記事項を覚える
このように、一生懸命勉強をしていても結果が出づらい場合は、お子さんに合った勉強方法を探し、実践することが大切なのです。
対応⑥栄養管理に気をつける

成長期にある中学生にとって、栄養管理は非常に重要です。
バランスの良い食事を摂れていなければ、頭もうまく働きません。
毎日朝食を食べられるように早めに起こす、水分補給をするように促す、食事バランスを可視化できるアプリを教えるなど、毎日の食事の栄養バランスを整えるサポートを行ってみてください。
また、親御さんご自身がご多忙でお子さんの食事面まで気にかけることが難しい場合は、家事代行サービスなどの利用もオススメです。
対応⑦良質な睡眠をとる
睡眠不足だと集中力が続かなかったり、頭が働かなかったりするため、勉強に取り組みづらくなることはもちろん、勉強をしても生産性が上がりません。
つまり、睡眠の管理も成績の向上に大きな影響を及ぼすのです。そのため、親御さんは、以下のようなことを行って、お子さんが良質な睡眠をとれるようにサポートしてみてください。
- 毎日同じ時刻に就寝するように声をかける
- 8時間以上の睡眠を確保できるように睡眠の大切さを伝える
- お子さんにあった寝具をそろえる
- 寝る前の食事やスマホを控えるように伝える
また、親御さんやほかのきょうだいが夜更かしをしていると、お子さんも早く寝ようという気持ちにはなりづらいため、無理のない範囲でご家族で早寝早起きに取り組んでみてください。
勉強できない中学生の進路や将来の選択肢
勉強ができないことで中学校の勉強についていけず、将来や進路について不安を感じるお子さんや親御さんも多いと思います。
この章では、勉強できない中学生の進路や将来の選択肢について解説します。
選択肢①学力に合った高校に進学する

勉強ができない状態であっても、学力に合った学校を選べば、全日制の公立高校への進学も可能です。
また、学校の勉強についていけていない場合は、内申点など気になる点は多いかと思います。しかし、私立高校の中には、内申点をあまり見られなかったり、事情を配慮してくれたりする学校もあります。
一般的に偏差値が高い高校は、大学への進学率の高さなどの理由から入学希望者が多く、倍率が高くなる傾向があります。
一方、偏差値がそれほど高くない高校であれば、受験者数もあまり多くなりにくいため、入学できる可能性も高くなるのです。
現在の学力を踏まえて進路についてお子さんと話し合ったり、担任の先生や学習塾の先生などと相談したりしながら、お子さんの志望校を決めましょう。
選択肢②通信制高校や定時制高校に進学する
高校を選ぶ際、全日制高校だけでなく、通信制高校や定時制高校も視野に入れるとよいでしょう。
通信制高校や定時制高校では、さまざまな事情を抱えた人を受け入れている学校が多いため、中学校での成績や内申点を重視していない傾向になります。
通信制高校では、入試に学力試験がない学校もあるため、勉強が苦手な中学生のお子さんでも入学試験を突破しやすいでしょう。
また、定時制高校は、多くの場合学力試験を実施していますが、全日制高校の学力試験よりも内容が比較的易しい傾向にあります。
通信制高校でも定時制高校でも、卒業すれば全日制と同じように学歴が高校卒業となります。
ほかにも、通信制高校や定時制高校ならではの特徴が多くあるため、お子さんに合う選択肢を見つけるためにも、ぜひ検討してみてください。
通信制高校や定時制高校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
選択肢③高卒認定試験を受ける

高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)は、文部科学省が実施しているもので、高校を卒業した人と同等以上の学力があるかどうかを認定するための試験です。
高校卒業の学歴にはなりませんが、合格すれば大学や専門学校への受験資格、一部の国家資格や公務員試験の受験が可能になります。また、民間企業の採用試験などでは、高卒認定試験の合格を高卒と同様に扱うところもあります。
高卒認定試験を受けるためにも勉強は必要になります。独学での勉強が難しいと感じる人は、経験豊富なスタッフに相談しやすい高卒認定試験の対策を行っている学習塾を利用してみるとよいでしょう。
高卒認定試験の概要や高卒認定試験を目指す人にオススメの学習塾については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
勉強方法を変えることで成績が上がった成功事例

この章では、勉強方法を変えることで成績が上がった成功事例として、キズキ共育塾の青柳講師(仮名)の成功事例を紹介します。
全てのお子さんに適した勉強法というわけではありませんが、1つの事例として参考にしてください。
青柳講師は、中学生時代に勉強法を変えることで成績を上げることができたと言います。
例えば、もともと苦手だった英語の場合、好きな洋楽の歌詞翻訳で学力が伸び、学年1位にまでなったそうです。
また歴史の場合、教科書の内容に興味を持てず、ただ暗記することが苦痛だったそうですが、司馬遼太郎の小説で歴史を面白く感じるようになり、歴史を流れで覚えられるようになったと話します。
もともと、好きでも嫌いでもなかった地理は、ゲーム(桃鉄)をすることで、楽しみながら地域の特産品などを覚えていったとのこと。
他の科目については、日頃から、周囲にあるものを化学や生物の知識を当てはめていき、見るものに勉強を結びつけて考えるようになってから、成績が変わっていったそうです。
勉強に対する意識としては、勉強法を柔軟に考えるようにしたと、青柳講師は語ります。
例えば、数学の証明問題を解く際、普通に解くと時間がかかってストレスだったそうですが、問題を解く前に解答を読んで、理解を深める方法に変更したことで、時間短縮、反復演習、定着度増加ができたそうです。
このように、自分に合った方法を見つけることで、勉強に意欲的に取り組めるようになり、効果も上がります。
また、勉強を通して試行錯誤や工夫する力は、学力以上に大切なものだと言えるでしょう。
とはいえ、勉強方法は、お子さんと親御さんだけで見つけたり試したりしなければいけないわけではありません。
中学生のお子さんは、まだ子どもです。そして、中学生の勉強は、小学生の頃と比べて複雑で難易度が高くなっています。
また、親御さんもお子さんの勉強につきっきりになるのは難しいでしょう。
お子さんに合った勉強法を探したり試したりするためには、学校の先生や学習塾、家庭教師など、勉強の専門家への相談がオススメです。
親御さんには、以下のようにご協力していただければと思います。
- お子さんが家庭で安心できる環境をつくる
- お子さんが勉強の専門家に、適切に相談するようにする
まとめ〜勉強できないことは克服できます〜
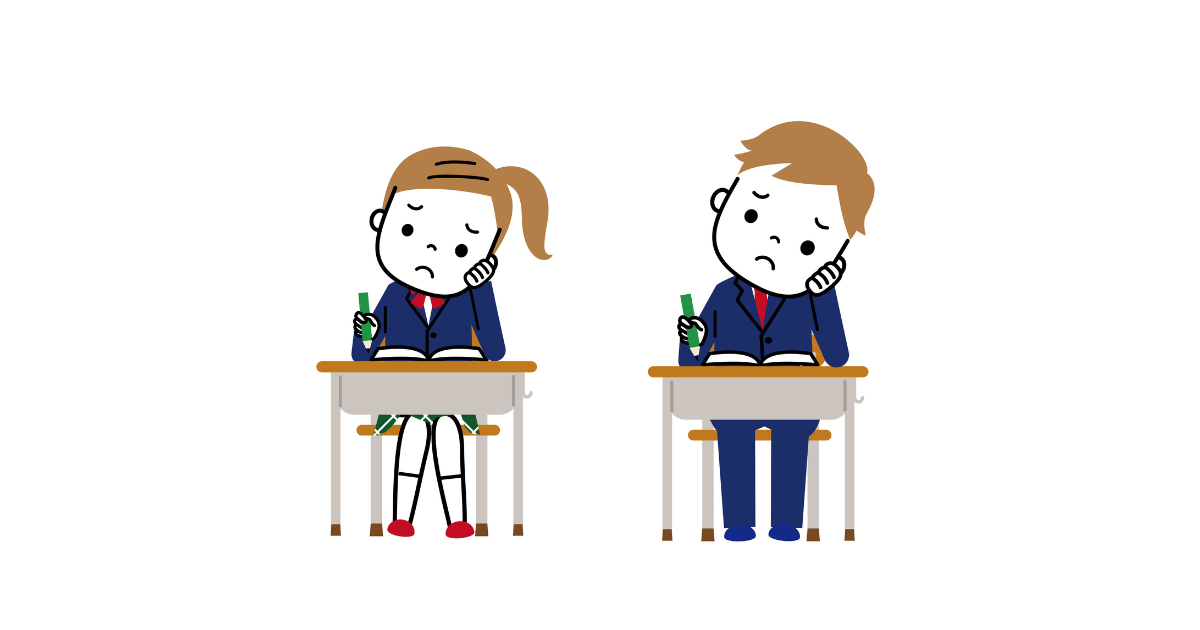
勉強できないお子さんの姿を見て、焦ったり不安になったりする親御さんは少なくないでしょう。
しかし、お子さんが勉強できない理由を明確にしたり、お子さんに合う勉強法を見つけたりすることによって、勉強できない状況は変わります。
また、効果的な勉強方法を見つけるために工夫した経験は、この先の人生において科目の勉強以上にお子さんの強みとなるはずです。
お子さんの勉強法は、親御さんやご家庭だけで考える必要はありません。学校への相談はもちろん、学習塾に相談することも大切でしょう。
私たちキズキ共育塾でも、無料相談を行っています。お気軽に御相談くださいね。
キズキ共育塾にも、毎日たくさんの生徒さんが訪れます。はじめは渋々勉強していた生徒さんが、自主的に生き生きと取り組むようになる姿は、とてもうれしいものです。
勉強は、可能性の扉を開く手段の一つです。最適な学習法が見つかれば、お子さんにとって、より幸せな未来につながるでしょう。
お子さんにぴったりの学習法が見つかり、その無限の可能性が開花することを願っています。
Q&A よくある質問