ひきこもりを脱出する方法 脱出した人の特徴やきっかけを解説

生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
ひきこもりで悩んでいるあなたは、以下のような不安を抱えているのではないでしょうか?
- 自分はこれからずっと外出できないのかも…
- ひきこもりから脱出したいけど、脱出できる気がしない…
ひきこもりは、ほんの少しのきっかけで脱出することが可能です。
このコラムでは、私がお会いしてきたひきこもりを経験した方々の体験談に基づいて、ひきこもりから脱出した人に見られる特徴、きっかけ、ひきこもりから脱出する考え方・行動について解説します。
「ひきこもりから脱出したいけど、どうしたらいいかわからない…」と悩むあなたのお役に立てば幸いです。
私たちキズキ共育塾は、ひきこもりから脱出したい人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などの無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
ひきこもりとは?

厚生労働省のひきこもりの評価・支援に関するガイドラインによると、ひきこもりは以下のように定義されています。
(ひきこもりとは、)様々な要因の結果として社会的参加 (義務教育を含む就学, 非常勤職を含む就労, 家庭外での交遊など) を回避し、原則的には6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい) を指す現象概念である。
なお、ひきこもりは原則として統合失調症の陽性あるいは陰性症状に基づくひきこもり状態とは一線を画した非精神病性の現象とするが、実際には確定診断がなされる前の統合失調症が含まれている可能性は低くないことに留意すべきである。
(参考:厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」)
具体的には、調査の中で以下のように回答した人をひきこもり状態にある者としています。
「ふだんどのくらい外出しますか。」との問いについて、以下の①~④に当てはまる者であって、「現在の状態となってどのくらい経ちますか。」との問いについて、6か月以上と回答した者
①趣味の用事のときだけ外出する
②近所のコンビニなどには出かける
③自室からは出るが、家からは出ない
④自室からほとんど出ない
ただし、上記の回答をしていても、ほかの質問項目から病気であることや自宅で仕事をしていることがわかる場合は、ひきこもりには該当しないとされています。
ここまでの内容をまとめると、ひきこもりの定義は以下のようになります。
- 学校や仕事、交友関係などの社会的参加をしていない
- 外出をしない、もしくは他者との交わらないかたちでのみ外出している
- ①~②の状態の要因が、病気や自宅での仕事ではない
ひきこもりから脱出することの難しさ
この章では、ひきこもりから脱出することの難しさについて解説します。
なお、どのくらい難しいか、何人中何人がひきこもりから脱出できているかなどに関する公的な調査結果などはありません。そのため、その他のデータをもとに解説します。
ひきこもり状態にある人の数

内閣府の調査では、ひきこもりに該当する人の割合は、以下のようになっています。(参考:内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査 (令和4年度)」)
- 15歳~39歳:約2.05%
- 40歳~69歳:約2.02%
この割合を、国内の15~64歳の人口(約7401万人、2023年4月時点)に当てはめて計算すると、約146万人の人がひきこもりの状態であることが推測されるのです。(参考:総務省「人口推計(令和5年(2023年)4月確定値、令和5年(2023年)9月概算値) (2023年9月20日公表)」)
ひきこもり期間の平均
ある家族会の調査からは、ひきこもりの期間が長期化していることが分かります。(参考資料:厚生労働省「第4部 全体のまとめ ご本人の平均ひきこもり期間(家族調査)」)
ひきこもり期間の推移
- 2010年度:約9.6年
- 2011年度:約10.2年
- 2012年度:約10.3年
- 2013年度:約10.5年
- 2014年度:約10.7年
- 2015年度:約10.2年
- 2016年度:約10.8年
- 2017年度:約10.8年
- 2018年度:約9.6年
- 2019年度:約12.2年
この数字はある家族会のなかでの調査に限られたものですが、ひきこもりの平均期間は10年前後となっており、その期間は増減ありつつ年々長くなっているのです。
つまり、ひきこもりから脱出できない期間が長くなっているとも言えます。
ひきこもりから脱出した人に見られる4つの特徴
キズキ共育塾に通う生徒さんの中にも、ひきこもりを経験し、そこから脱出した生徒さんがたくさんいます。
そこでこの章では、キズキ共育塾の生徒さんの経験談に基づいて、ひきこもりから脱出した人の特徴について解説します。
ただし、特別な特徴ではなく、ひきこもりの当事者の方がご紹介する特徴をすでに持っていたり、今はなくてもやがて芽生えたりすることが多くあります。
その上で、次章でご紹介するようなきっかけと出会ったり考え方や行動を変えたりすることで、次の一歩に進めます。
ご紹介する内容は、先輩たちの成功事例として、気軽にお読みください。
特徴①「何か」への意欲がある

1つ目の特徴は、「何か」への意欲があることです。
中高一貫校に通っていた岡本さん(仮名)は、授業についていけなくなり落ちこぼれに。その後も勉強での挫折経験が重なったことで、精神的に落ち込みがちになり、不登校そしてひきこもりになりました。
ひきこもりの状態は数年続きましたが、あるとき以下のような思ったそうです。
そんな(ひきこもり)生活を数年続けるうちに、精神が少しずつ落ちついていきました。
そして、高校時代の友人にふと目を向けると、みんなとうに大学生になっていました。彼らを見ていると、「自分も、大学進学をしたい」という気持ちが湧いてきました。
岡本さんの場合、大学進学への意欲が、ひきこもりからの脱出に繋がりました。
ほかにも、ひきこもりから脱出する人は、「就職したい」「自立したい」「家族を安心させたい」など、何らかの意欲を持っていることが多いように思います。
岡本さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
特徴②負けたくない気持ちがある
2つ目の特徴は、負けたくない気持ちがあることです。
高校での部活動の厳しさや人間関係がこじれによって、高校生活が上手くいかなくなった金井さん(仮名)は、部活を退部したことをきっかけに不登校、そしてひきこもりになりました。
その後、学習塾に通うことに挑戦しましたが、合わない環境やついていけない授業などが要因となり、ひきこもりに後戻り。「人生が終わった」と思うほど落ち込んだそうです。
ですが、そんな時に友人のSNSが目についたそうです。
彼(友人)が、受験の話題に触れているのが目についたんです。「こいつには負けたくない。」そいつには妙なライバル意識がありました。
もし偶然出会ったときに、僕の肩書が高校中退のままだったら合わせる顔がないと思ったんですよね。友達と胸を張って話ができるようになりたい。
こんな僕でも一から勉強をやり直せそうな塾を探し始めました。
このように、負けたくない気持ちは次のステップに進むための原動力になります。金井さんの場合は、「友人に勉強で負けたくない」という思いでした。
ほかにも「学校に通っている人よりもいい大学に行きたい」「バカにしてきた友人を見返したい」などの気持ちが、原動力になるかもしれません。
ただし、負けたくない気持ちが強くなりすぎると勝つことにこだわるあまり、自分にとってよい選択ができなくなることがあります。
負けたくない気持ちを原動力にしつつも、自分に合った進路や選択肢を選ぶよう心掛けましょう。
金井さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
特徴③危機感がある

3つ目の特徴は、危機感があることです。
内田さん(仮名)は、高校受験ではじめて失敗を経験したことで自信を失い、自信を取り戻すために猛勉強をしたものの、無理がたたり体調不良になり高校を中退、そしてひきこもりになりました。
ひきこもりになってから1年くらいたった頃に、体調が安定してきたためアルバイトを開始。この時点で、すでにひきこもりを脱出したと言えますが、アルバイト生活の中で以下のような危機感を抱くようになったそうです。
アルバイトの開始によって徐々に生活リズムも安定しましたが、一方で、高校中退やフリーターに対する社会の厳しさも知ることになりました。
そして私は、自分の現状に危機感を覚え、19歳になる年の春、大学受験を決心しました(もちろん、高校中退やフリーターを一概に「ダメだ」と言うつもりはなく、あくまで「私の場合は」、ということです)。
内田さんの場合、危機感を抱く前にひきこもりを脱出していました。
ですが、大学受験という「新たな一歩」を踏み出す原動力となったのは、社会の厳しさを知ったことで生まれた危機感でした。
このように、「このままではまずいかも…」「将来どうなるんだろう」などの危機感が、ひきこもりからの脱出につながるのです。
内田さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
特徴④「とりあえず行動する」ができる
最後に紹介する特徴は、「とりあえず行動する」ができることです。
石巻さん(仮名)は、受験を経て進学した中学校で授業についていけず自信を失い、先生や友達との人間関係も悪くなり、学校に行くことが怖くなりました。
そして、学校に限らず他人からの視線が怖くなり、ひきこもり状態に。当時は「自分はダメな人間だ」という思いで頭がいっぱいになっていたそうです。
しかし、そんな石巻さんに転機が訪れました。
そんな中、親がキズキ共育塾を見つけてきてくれて、とりあえず面談に行ってみることにしました。
久しぶりの外出にドキドキしたのを覚えています。当日は、キズキ共育塾に着いたはいいものの、入口のトビラを開ける勇気がなかなか出ず、教室の前でマゴマゴしていました。
そしたら、代表の安田さんがニュッとドアの後ろから現れて、「どうぞ」と招き入れてくれました。
そのまま面談をしてくれたのですが、あらゆることに疑心暗鬼になっていた当時の僕でも「この人は信頼できる」と思いました。
このように、不安に感じていることや確信を持てないことでも、とりあえず行動することでひきこもりから脱出できることがあるのです。
石巻さんも、親から学習塾に行くことを提案されたときに、拒否することもできたと思います。
ですが、「とりあえず面談に行ってみよう」と思うことで、自分が信頼できると思える人・環境に出会えたのです。
石巻さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
ひきこもり脱出につながる4つのきっかけ
ひきこもりの状態が長く続いていると、「これからもずっと、このままなのかも…」と落ち込むことがあると思います。
ですが、あなたの小さな行動がひきこもり脱出のきっかけになることがあるのです。
この章では、キズキ共育塾の生徒さんの経験に基づいて、ひきこもり脱出につながるきっかけについて解説します。
きっかけ①病院・支援機関などを利用したこと

1つ目のきっかけは、病院や支援機関などを利用したことです。
高校3年生の10月に不登校になった木村さん(仮名)は、生活リズムが崩れたり祖母の介護をする母の重荷になっていると感じたりしていたことで、自己否定を繰り返していました。
しかし、病院に行ったことがきっかけとなり、状況が変わりました。
病院に行ったところ、うつ病の診断を受けました。
その後、心療内科への通院を続け、卒業後にメンタルが安定してきたタイミングで受験勉強をサポートしてくれる学習塾を探しはじめました。
こちらでお伝えした通り、病気によって外出できない状態は、定義の上ではひきこもりの状態には該当しません。
ですが、今、ひきこもりの状態に苦しんでいる人の中には、自分では気づいていないものの何らかの病気が要因で家から出られない人もいるでしょう。
そして、要因が病気である場合、適切な治療を受けることが、ひきこもり脱出のきっかけになる可能性があります。
そのため、原因がわからない体調不良や精神的な落ち込み・不安感などがある場合は、一度病院を受診してみることをオススメします。
また、病気でなかったとしても、自分一人で今の状況をどうにかしようとする必要はなく、支援機関のサポートを受けることで状況が変わることも多いです。
誰かを頼ることに怖さや恥ずかしさを感じるかもしれませんが、「ひきこもり脱出のきっかけになるかもしれない」と思って、勇気を出して行動してみてください。
木村さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
きっかけ②定期的に通える場所を作ったこと
定期的に通える場所を作ったことが、ひきこもり脱出のきっかけになることもあります。
久保さん(仮名)のお子さんは、中学生のころ不登校で外出が苦手でした。しかし、キズキ共育塾に通い始めたことがきっかけとなり、少しずつ外出することへの抵抗がなくなったそうです。
入塾にあたっての面談で、スタッフさんが、引きこもっていることを全く否定せず、昼夜逆転についても自然なこととして受け入れてくれたのが印象的でした。
おかげで、子どもがホッとしていたのを覚えています。親としても、本人を肯定することから変化していくのだと学びました。
コンスタントに通えるのか少し不安でしたが、塾に行く日には必ず時間通りに用意して、出かけるようになりました。
このように、定期的に通える場所を作ると外出する機会が増えるため、ひきこもり脱出のきっかけになり得るのです。
今回の体験談の中では、定期的に通える場所として塾が挙げられていましたが、フリースクールや習い事でもよいでしょう。
また、学校に復帰したい気持ちがある場合は、教育支援センター(適応指導教室)や学校の保健室・別室なども、候補となります。
久保さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
きっかけ③信頼できる人に出会えたこと

3つ目のきっかけは、信頼できる人に出会えたことです。
中村さん(仮名)は、高校でいじめを経験し不登校に。そして、約半年間ひきこもりの状態になりました。その当時は、外に出ることを拒否し自分の世界に閉じこもっていたそうです。
そんな中村さんがひきこもり脱出のきっかけは、キズキ共育塾での講師との出会いでした。
キズキ共育塾では、二人の先生から物理を教えてもらいました。一人は大学生、もう一人は社会人です。どちらの先生もすごく優しかったんです。
それまでの先生からは、成績が悪いと怒られてばかりだったんですが、キズキ共育塾の先生たちは、僕を責めたりしませんでした。
問題を間違えても、何か罰を課すのではなく、また間違えないように丁寧に解説してくれました。また、授業では、大学に入った後や将来についても話し合うこともありました。
このように、「自分を理解してくれる」「信頼できる」と思える人との出会いは、外の世界への安心感に繋がり、ひきこもりから脱出するきっかけになるのです。
「信頼できる人と出会うのは、難しいのでは…?」と思うかもしれません。
ですが、支援機関には、あなたのひきこもり脱出をサポートしたいと心から思う人たちがたくさんいます。
また、あなたが気づいていないだけで、家族や兄弟姉妹、友人など、すでに繋がりのある人の中にも、信頼できる人がいるかもしれません。
今の状況を誰にも話したくない気持ちもあると思います。ですが、信頼できる人が1人見つかるだけでも、心が軽くなったり、状況が一変したりすることもあるのです。
中村さんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
きっかけ④自分に合う環境に出会えたこと
最後に紹介するきっかけは、自分に合う環境に出会えたことです。
高校で部活動を退部したことをきっかけに不登校、ひきこもりとなった金井さん(仮名)は、学校に行っていないという危機感から、あるドロップアウトした生徒向けの集団塾へ通うようになりました。
受験のためということに加えて、「居場所がほしい」という気持ちが強かったそうです。しかし、実際通い始めるとクラスに馴染めず授業にも全くついていけず、金井さんには合わない環境でした。
そして、この経験から自分に合う学習塾を探すようになり、キズキ共育塾を見つけました。
授業では勉強だけをするのではなくて、いろいろ雑談をしたりして、僕が通いやすくなるように配慮してくれたんです。僕の気持ちが落ち込んでいるときには、先生やスタッフが声をかけてくれて、支えてくれました。
気づいたときにはキズキ共育塾に通うことが習慣になっていて、勉強にも自然と取り組めていました。雰囲気もすごく僕に合っていたんです。
僕は、集団の授業だと周りからプレッシャーを感じるんですが、完全個別指導のキズキ共育塾では僕のペースで勉強に集中することができました。
自分に合った環境に出会うと、その場所に通うことが増えるため、ひきこもり脱出のきっかけとなります。
はじめは、自分に合う環境がどんな環境かわからないかもしれません。ですが、支援機関に相談することで、そういった場を見つけられることがあるのです。
また、学習塾以外にも、習い事やサークル、ボランティアなどでも、自分の居場所だと感じられる場があるはずです。
まずは、第一歩として「ここなら自分を理解してくれる人がいるかも」「安心できそう」と思える場所を探してみてください。
ひきこもりから脱出するための3つの考え方
この章では、ひきこもりから脱出する考え方について解説します。
実際にひきこもりを経験した人の体験談に基づく考え方なので、ぜひ参考にしてみてください。
考え方①考えることを一度やめる
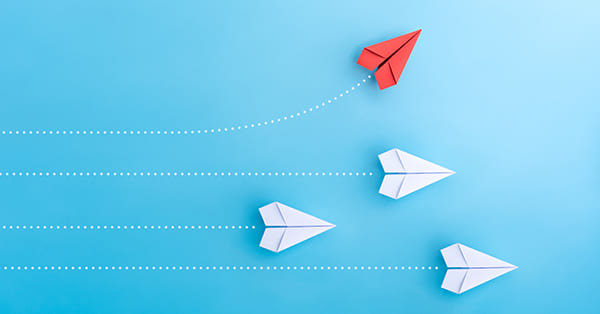
「考えていてもしようがないので、とりあえず行動しました」
これは、ひきこもり経験のAさんから聞いた言葉です。
Aさんは、ひきこもり期間を、「とにかくいろんなことを考えてばかりいた」と振り返ります。
「時間はたくさんあったし、昼間に一人でテレビをぼーっと見ていても『自分は何をしているんだろう』と考えたりしていました」と話していました。
考えることばかりが先だって、行動が追いつかずひきこもりになっていたのです。
Aさんは、それが自分のひきこもりの原因だと考え、「一切考えずに、飛び込む気分で行動するようにしたら、うまくひきこもりから脱出できた」と教えてくれました。
その行動の一つに、キズキ共育塾への相談と入塾があったのです。
Aさんは、キズキ共育塾に通いながら、同じく飛び込む気分でアルバイトも始めました。
授業とアルバイトのシフトで生活リズムができ、人との関わりが増えたため、充実した表情を見る機会が増えました。
また、学力を着実に伸ばしていることと、アルバイトで自分で収入を得られるようになったことから、自分に自信が持てるようにもなったようでした。
もし自分がアレコレと考えすぎてひきこもりになっているなと思う方は、Aさんのように一度考えることをやめてとにかく行動してみるのもよいかもしれません
その行動が、ひきこもり脱出のきっかけにつながることがあるのです。
考え方②低空飛行でもよいと思う
Bさんは、キズキ共育塾に入塾する前は、数年ほど家から出ずに過ごしていました。
Bさんはキズキ共育塾で学び、大学に合格しました。
その報告をしてくれたとき、今後の抱負として、「まあ、低空飛行からやっていければいいかなと思います。でないと続かないので」と語ってくれました。
思い返せば、Bさんの受験勉強のモチベーションは、入塾から間もないころがピークでした。
授業で新しいことを学び始めた直後は、「もっとできます!」と前のめりな姿勢になって、しばらくして息切れする…ということも何度かありました。
自分の経験から、受験勉強のみならず、今後の生活においても低空飛行から始めて続けていく、徐々にできることを増やしていくことが必要だと思ったのかもしれません。
Bさん以外にも、ひきこもりを経験した人は、他人よりも遅れた分を急いで取り戻さなければと、より完成度の高いことから取り組み始めがちです。
ですが、いきなり高い幹線井戸を目指して取り組んでいると、しばらくして息切れします。
ひきこもりからの脱出にあたっては、最初は続けることを意識してまずは低空飛行からと行動することが、よい結果につながりやすいのです。
勉強の例で言えば、いきなり難関大学の過去問に取り組むのではなく、基礎的な部分を学び直すところからじっくり取り組むイメージです。
また、就労の例で言えば、いきなりフルタイムの正社員で働く(ことを目指す)のではなく、まずは人とのコミュニケーションを再開するために支援団体を訪れる、まずは週に何時間のアルバイトから始める(ために応募を続ける)といったイメージです。
あせらずに、継続できることから始めてみましょう。
考え方③「原因」ではなく「意味」を考える

ひきこもりである今の自分について、「どうして?なぜ?」と原因ばかり考えてすぎていませんか?
例えば、以下のような感じです。
- 自分の何がいけなくてひきこもりになったのだろう
- あのとき、ああしなければこんなことにはならなかったのに
このように考えていると、過去の自分を責めているようで、どんどんつらくなっていくと思います。
また、ひきこもっている期間が長ければ長いほど、思考がマイナスになったり、堂々巡りになったりしがちです。
時間の経過が、実情と違ったよくない考えを生むこともあります。そうなると、脱出はどんどん遠のくばかりです。
そこで、一度ひきこもりになった意味を考えてみませんか?
「ひきこもりにいい意味なんてない」と思われるかもしれません。
でも、少しでも、一つでもいいんです。
「そういえば、ひきこもる前の自分はすごくがんばってたから、ひきこもって休めたかも」とか、「ずっとテレビを見ていたから、芸能人に詳しくなったな」とか、そんなことでいいんです。
ひきこもりやひきこもっている自分について、一つでも意味を見つけられると、「ひきこもりで得られるものは得たから、次に進もうか」と心を切り替えてひきこもりから脱出できる場合があります。
ひきこもりから脱出するための3つの行動
この章では、ひきこもりから脱出する3つの行動について解説します。
行動①趣味を開始・再開してみる

ひきこもりから脱出しようと思っても、じゃあ実際に何のために外出するかがすぐに思い浮かばないこともあるかと思います。
そんなとき、何か大きな目的をいきなり設定する必要はありません。
まずは、ひきこもりからの脱出が目的なので、楽しめるようなこと、例えば趣味のためでよいのです。
ひきこもり期間で新たに興味を持ったことを趣味としてはじめてみるのもよいですし、中断していた趣味を再開してみるのもよいでしょう。
しかし、残念ながら興味を持ったことをできる場所や団体が家の近くにない場合もあると思います。
そんなときは、散歩を新たな趣味にしてみてはいかがでしょうか。
散歩は、一人でできるのはもちろん、簡単な運動にもなり四季も感じる、ひきこもりの経験がある方にもハードルが低い趣味だと思います。
ご近所の目が気になる…と思う場合は、夜の散歩やサイクリングがおすすめです。
行動②機会があれば人と会ってみる
家にいる時間が長いほど、家族以外の人と会うことに、より勇気が必要になると思います。
無理に自分から連絡を取って約束をとりつける必要はありません。ですが、成人式や同窓会などのイベントや懐かしい人から連絡があったときに、その機会に乗ってみるのはいいかもしれません。
大きなイベントでなくても、人に誘われて出かけたことで、前向きな気持ちになれることもあります。
ご家族と一緒に暮らしている場合は、ご家族が買い物や趣味で出かけるときについて行くと、店員さんやご家族の知り合いと接することもできます。
そうした人とのふれあいが、ひきこもりから脱出につながることもあるのです。
キズキ共育塾の生徒であるCさんは、大学受験の失敗をきっかけにひきこもりになっていました。
そして、ひきこもりが長引くにつれ、「ひきこもりが長引いた自分はみじめだ。悪い意味で『特別』だ。再び受験しても落ちるに決まっている。もうひきこもりから脱出できない」と、どんどんマイナスな思考になっていました。
そんな中、ある夏の日、Cさんは友人から中学校の同窓会に誘われました。
Cさんは、最初は「ひきこもりの自分はみじめだから行きたくない」と答えました。
ですが、その友人から「みんなそんなに人のことを気にしないよ。話し相手がいなければ僕と話してればいいし、嫌になったら途中で帰ればいいし」と言われ、渋々ながらも参加しました。
そして同窓会に参加したCさんは、同級生たちが多様な人生を送っていることを知りました。大学生、社会人、結婚した人、離婚した人、シングルマザー、資格試験のために勉強中の人、会社を辞めて求職中の人などなど…。
Cさんは、人生は多様であるということは頭ではわかっていました。
ですが、実際に身近な同級生たちが多様な人生を歩んでいることを目の当たりにしたことで、「ひきこもりは『特別』じゃなくて、多様の中の一つに過ぎないんだな。みんな、自分の人生を一生懸命に生きているんだな」と実感したそうです。
その同窓会をきっかけに、Cさんは、自身のひきこもり(歴)をみじめだと思うことをやめ、ひきこもりから脱出できました。そして、改めて大学受験に向けて勉強するため、キズキ共育塾に入塾しました。
Cさんは、その後、志望する大学に見事合格しています。
行動③出かけやすい場所・時間を選んで外出してみる

外に出かけようと思ったとしても、いきなり無理をする必要はありません。
例えば、「人混みは苦手だけど、がんばらなきゃ!」といきなり気負って繁華街に出かけようとしても、結局出かけられなかったり、出かけられても心身の調子が悪化したりすることがあります。
そうすると、それが新たな失敗となり、ひきこもりからの脱出は遠のく可能性があるのです。
もし「ひきこもりじゃない人は、いつでもどこにでも出かけられるはずだ。自分もそうならなければ」と考えているようでしたら、それは思い込みです。
ひきこもりじゃない人でも、繁華街に行くと気分が悪くなるから行かないようにしている人は割といますよね。
特にひきこもりからの脱出の第一歩としては、自分が行きやすいと思う場所・時間で十分です。こちら述べた夜の散歩にも共通しますね。
人目が気になるようであれば人の少ない場所・時間帯、人が多い方が気がまぎれるようであれば賑やかな場所・時間帯などがよいでしょう。
そして、徐々に外出に慣れていくにつれ、行動できる範囲がだんだんと広がっていきます。
まとめ〜小さなきっかけがひきこもりからの脱出につながります〜

今、あなたはとても苦しいかもしれませんが、必ず次の一歩に進めます。
そして、自分の考え方や行動を変えることが、次の一歩に進むきっかけになることがあるのです。
このコラムが、あなたのひきこもり脱出のお役に立つことを願っています。
さて、私たちキズキ共育塾は、ひきこもり・不登校・中退などの方のための個別指導塾です。
キズキ共育塾では、十代から数年間のひきこもり期間がある生徒さんや、大学に進学したけれど通えずひきこもっている生徒さんが多数在籍しています。
勉強そのものや、授業でのコミュニケーション、学習塾に通うという定期的な外出などを通じて「ひきこもりから脱出したい」と思われたときは、お気軽にご相談ください。
オンラインでのご相談・授業も行っていますので、外出が難しい方は、まずそちらで徐々に人とのコミュニケーションに慣れて、次第に外出を目指す、といったご利用も可能です。
Q&A よくある質問


























