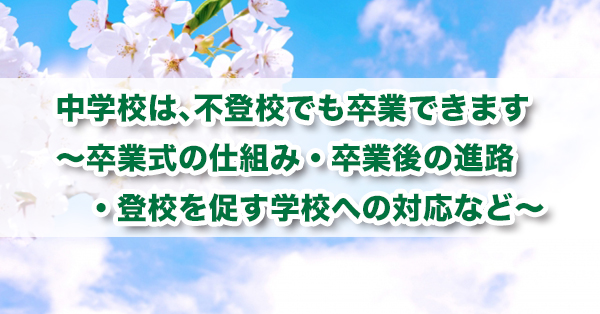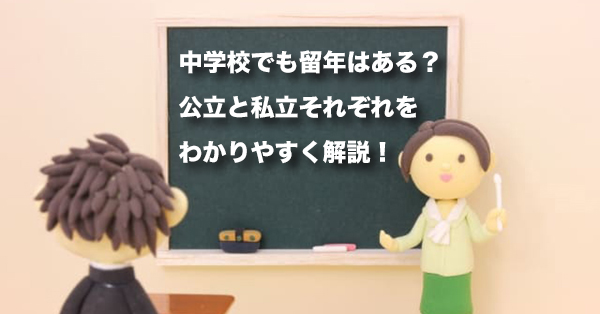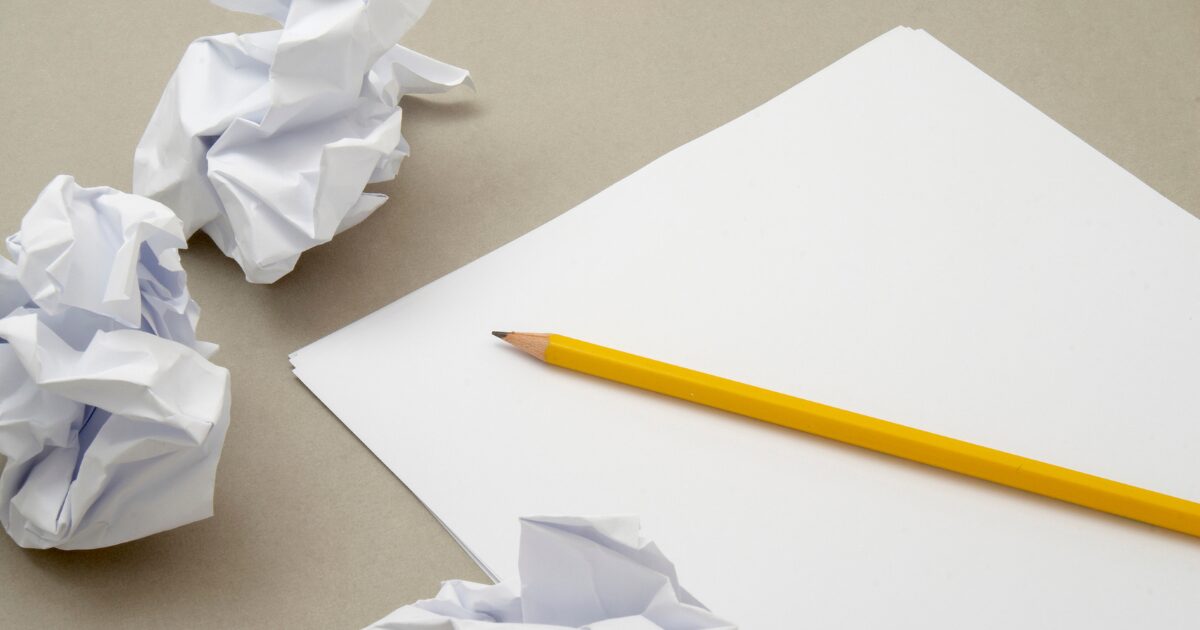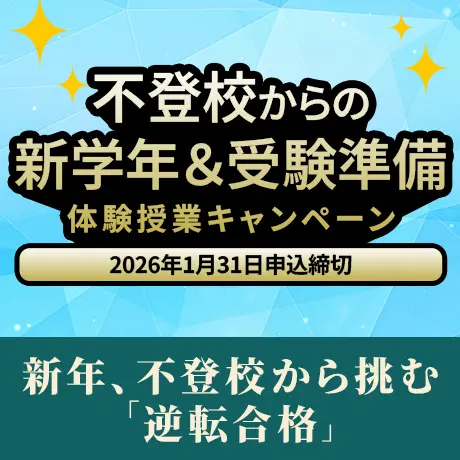中学生が朝起きられない原因は? 起きられるようになる方法も解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
このコラムにたどり着いた人の中には、以下のようなことでお悩みの方がいるのではないでしょうか。
- 朝起きられない
- 朝起きられなくて学校に行けない
- 朝起きられない原因を知りたい
- 朝起きられない子どもを起きられるようにしたい
- 朝起きられないことと不登校の関係性について知りたい
このコラムでは、朝起きられないことに悩む中学生に向けて、中学生が朝起きられない原因や不登校との関係性、起きられるようになる方法について解説します。あわせて、朝起きられないことに悩む中学生がいる親御さんやご家族に向けて、お子さんを朝起きられるようにする方法についても解説します。
このコラムが、朝起きられないと悩む毎日から少しでも抜け出すきっかけにつながれば幸いです。
私たちキズキ共育塾は、朝起きられない中学生のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
中学生が朝起きられない原因
中学生が朝起きられない原因には、睡眠の量と質、そしてストレスや心理的要因といったことがらが関係しているようです。(参考:厚生労働省「Adolescence- わからないことがここにある。」)
この章では、中学生が朝起きられない原因について解説します。この章をもとにこれまでの生活を振り返り、どの原因に該当している可能性が高いか確認してみましょう。
原因①睡眠の量と質

よくある原因のひとつとして、睡眠不足や良質な睡眠が取れていないなどがあります。中学生になると、小学生と比べて学習時間や部活動が増えるため、毎日やるべきことに追われた結果、慢性的な睡眠不足に陥りやすいと言われています。
理化学研究所の調査によると、全ての年代において、おおむね半分以上の子ども達が小学生では9〜12時間、中学・高校生では8〜10時間とされる推奨睡眠時間を満たしていないそうです。(参考:理化学研究所「「子ども睡眠健診」プロジェクトで見えてきた実態-プロジェクト参加校(小・中・高)の第三次(2024年度後期)募集を開始-」)
さらに、平日に不足した睡眠を休日に補填する傾向がみられます。また、学年が上がるにつれて平日と休日の起床時間に大きな乖離が生じ、一定数の子どもが社会的時差ぼけと呼ばれる状態にあることも分かっています。
そして、寝具や自室の温度が睡眠に適さないなど、さまざまな理由から睡眠の質が低下することがあるようです。
睡眠不足や良質な睡眠が取れていないという人は、こちらを参考にしてみてください。
原因②ストレスにつながる心理的要因
学校や日々の生活の中に、ストレスにつながる心理的要因を抱えている場合も、朝起きられないことにつながるようです。具体的に、以下のような心理的要因が挙げられます。
- 学校の勉強が難しい
- 勉強と部活動の両立が大変
- 友だちや家族とうまくいっていない
- いじめられている
- 苦手な先生がいる
どんなに悩んでも解決策が見つからないままであれば、現状にモヤモヤすることになり、さらにストレスを感じるでしょう。
何か悩みごとがある人は、親御さんや友だち、学生からの相談を受け付ける専門機関に相談してみると、解決策が見つかるかもしれません。
悩みを抱えている人は、こちらを参考にしてみてください。
原因③病気・障害

朝起きられない原因として、病気や障害の特性や症状が潜んでいる可能性もあります。考えられる病気としては、以下のようなものがあります。
- 起立性調節障害
- 睡眠相後退症候群
一番可能性の高い病気は、起立性調節障害です。
起立性調節障害(OD、Orthostatic Dysregulation)とは、自律神経である交感神経と副交感神経の機能が低下することで発生する血行不良に伴い、さまざまな症状が引き起こされる病気のことです。(参考:一般社団法人 日本小児心身医学会「(1)起立性調節障害(OD)」、一般社団法人 起立性調節障害改善協会「起立性調節障害とは?子ども・大人別に特徴を解説」)
起立性調節障害の具体的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。(参考:一般社団法人 日本小児心身医学会「(1)起立性調節障害(OD)」、つだ小児科クリニック「起立性調節障害 OD (自律神経失調症)」、恩賜財団済生会「起立性調節障害」)
- 朝起き上がれなくなる
- 頭痛がする
- 立ちくらみがする
- 倦怠感がある
- 食欲がなくなる
- 動悸や息切れがする
- 失神発作を起こす
- 顔色が優れない、青白い
- 乗り物酔いする
朝起きられないことに加えて、上記のような症状がみられる場合は、睡眠外来や心療外来などを受診してみましょう。
起立性調節障害の概要については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
もう一つ考えられる病気は、睡眠相後退症候群です。
睡眠相後退症候群とは、体内時計のズレから、入眠時間が遅い時間帯にずれる状態のことです。(参考:e-ヘルスネット「睡眠相後退(前進)症候群」、新潟薬科大学「薬科大健康だより10月号」)
スマートフォンを夜遅くまで見ている、夜遅くまで勉強をしているなど、さまざまな理由によって、就寝時間に遅れが出ることがあります。
そのような日々が続いた結果、睡眠時間が極端に短くなり、朝起きられないという状態を招いている可能性があります。
就寝時間が遅くなることと、睡眠そのものの質や体調不良との関係性について知りたい人は、こちらを参考にしてみてください。
原因④カフェインの過剰摂取
朝起きられない原因として、カフェインの過剰摂取も考えられます。
1度カフェインを摂取すると、血液中のカフェイン濃度を半分にするまでに4時間ほどかかります。(参考:大阪暁明館病院「快眠クラブ通信」)
例えば、就寝1時間前と3時間前にコーヒーを一杯ずつ飲んだ場合、寝付くまでの時間は10分ほど長くなり、睡眠時間は30分ほど短くなるそうです。
また、エナジードリンクにも注意が必要です。あるエナジードリンクでは355mlの内容量に対して142mgもカフェインが入っているそうです。(参考:千葉県医師会「エナジードリンクとカフェイン~カフェインのとり方に注意~」)
健康な成人が短時間でカフェインを摂取する場合、200mgまでは安全とされています。しかし、体がまだ発達途中の中学生にとっては、多すぎる場合があります。(参考:食品安全委員会「食品中のカフェイン」)
日常の中でついついカフェインを取りすぎる人は、カフェインの過剰摂取によって睡眠時間に遅れが生じ、熟睡したころにちょうど朝を迎えるために、起きられなくなっているのかもしれません。
カフェインの過剰摂取に思いあたる人は、エナジードリンクやコーヒーの飲み過ぎに注意するとともに、こちらを参考にしてみてください。
原因⑤生活リズムの乱れ

生活リズムの乱れによって、朝起きられなくなることもあります。スマートフォンを夜遅くまで見たり、勉強と部活動の両立でやむを得ず寝る時間が遅くなることがあるでしょう。
成績維持や向上のために勉強するのは、大切なことです。ですが、そのために就寝時間が遅くなる可能性も伴います。
スマートフォンの使用が理由で就寝時間が遅れている人は、この機会にこちらの方法を試してみてください。
一方、勉強や部活動の両立などによってやむを得ず就寝時間が遅れているという人は、こちらの方法を試してみてください。
原因⑥運動不足
運動不足が原因の可能性もあります。
厚生労働省によると、快眠のための就活習慣のひとつとして運動を挙げています。
運動習慣がある人には、不眠が少ないことが分かっています。また、1回の運動がある人に比べて、習慣づいている人の方が寝付きが良くなるとされています。(参考:eヘルスネット「快眠と生活習慣」)
小学生の頃に比べて運動をする時間が極端に減ったという人は、体を動かす機会が減り、肉体的疲労を感じていないのかもしれません。
当てはまると思う人は、こちらを参考にしてみてください。
朝起きられないことと不登校の関係性
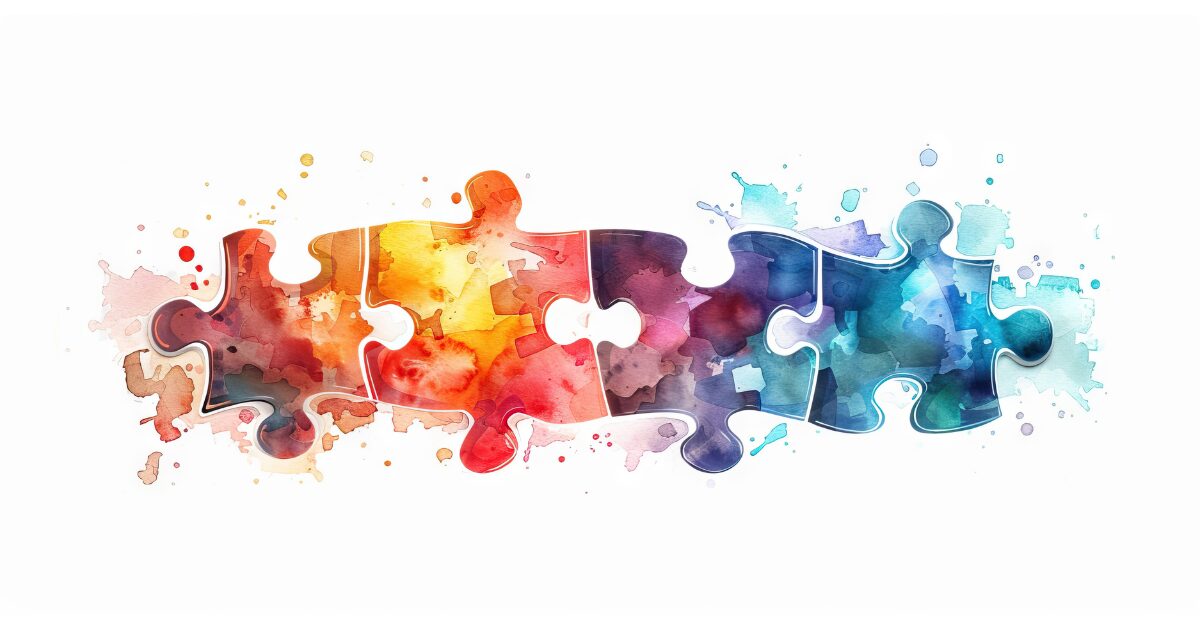
朝起きられないことが原因で、不登校になる可能性はあると考えられています。(参考:大阪大学大学院連合小児発達学研究科 平田郁子「不登校と睡眠」)
文部科学省が実施した、小学生6年生713人、中学2年生1303人の不登校児童を対象にしたアンケートによると、学校に行きづらいと感じ始めたきっかけとして、「身体の不調((学校に行こうとするとおなかが痛くなったなど)・生活リズム(朝起きられなかったなど)」が多く挙げられています。
回答数をみると、小学生が291人(約26.5%)だったのに対し、中学生では約2倍の573人(約25.7%)にまで増えています。(参考:文部科学省「不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書」)
朝起きられないことは不登校の直接的原因ではないとはいえ、理由の一つにはなりうることは知っておく必要があるでしょう。
中学生が朝起きられるようになる方法10選
この章では、中学生が朝起きられるようにする方法について解説します。
今日から試せる方法ばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「朝スッキリ起きる方法20選 朝・昼・夜ごとに実践できる方法を解説」
方法①生活リズムを整える

生活リズムの乱れを自覚している人は、意識的に生活リズムを整えることから始めましょう。
朝起きられるようになるためには、睡眠環境や生活習慣などの見直しが重要になります。
厚生労働省は、小学生では9〜12時間、中学・高校生は8〜10時間の睡眠時間を推奨しています。(参考:健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会「健康づくりのための睡眠ガイド 2023(案)」)
自分で改善できることがあれば、睡眠時間を確保するため、この機会に生活リズムを意識的に整えてみましょう。
例えば、スマートフォンをついつい見過ぎるのなら、見る時間をある程度決めて、就寝時は布団から手の届くところに置かないようにする、という方法がオススメです。
布団から離れたところに置いておけば、アラームが鳴ったときなどは必ず起きて取りに行くことになります。
スマートフォンを物理的に自分から離すことで、睡眠時間を確保するきっかけにつながるだけでなく、いやでも起きなければならない環境となるため、今までと比べてスムーズに起きられるかもしれません。
生活リズムが乱れる原因を改めて見直し、あなたにあった方法を検討してみてください。
方法②布団の中で身体を動かし体温を上げる
寒い季節になると、温かい布団の中にいる方が快適に感じることがあります。これは、睡眠中の身体が休息モードになり、体温を低い状態に維持しているためです。
低い体温のまま布団から出ようとしても、寒い季節では難しいです。そのようなときは、布団の中で手を握ったり開いたりする、もしくは両腕を左右に大きく伸ばして何度か回転させるなど、体温が上がる方法を試してみましょう。(参考:須田智也「寒さと睡眠」)
身体を動かさずに起きるときよりも、身体がぽかぽかした状態で起きることができます。特に、朝晩と肌寒くなる季節は、どうしても布団から出ることが辛く感じます。
手を握ったり開いたりすることや、両腕を左右に大きく伸ばして何度か回転させるだけでも効果があります。
自分に無理のない方法で身体を簡単に動かして、身体が温まってから起きる習慣を心がけてみましょう。
方法③カーテンを開けて太陽を浴びる

この機会に、カーテンを開けて太陽の光を浴びることも習慣づけてみてください。
太陽の光を浴びる行動には、体内時計をリセットする力があります。(参考:農林水産省「よい生活リズムと生活習慣を身につけよう」)
朝起きられないことに悩み、改善させたいと思っている人は、ぜひ試してみてください。
方法④栄養バランスを考えた食事をとる
好き嫌いで食べるものを選んでいたりする人は、この機会に栄養バランスを考えた食事を意識してみてください。
特に、朝起きられないため朝食を取らないことが習慣になっている人は、朝食を食べることを続けてみましょう。
朝食を食べると、眠っていた脳や身体を起こすことにつながります。また、朝食を食べない日が続くと、脳を働かせるためのエネルギーが不足し、勉強に身が入らないほか、体調不良や集中力の低下につながります。(参考:農林水産省「よい生活リズムと生活習慣を身につけよう」)
朝起きられるようにするため、さらには朝起きた後も効率よく動けるよう、栄養バランスを意識した朝食を心がけてみてください。
方法⑤好きな音楽を聴く
朝一番に、好きな音楽を聴くのもオススメです。
特に、アラーム音を好きな音楽に替えると、自然とやる気が湧いてきてスムーズに起きられるようになるかもしれません。
スマートフォンに内蔵された正規のアラームでは、音楽を自由に設定できない場合もあります。そのような場合は、アラームアプリをインストールすれば、自由に設定できるようになります。
方法⑥朝シャワーを浴びる

朝起きた後にシャワーを浴びるなどにも、効果があります。
シャワーを浴びるときに、お気に入りの香りが楽しめるボディーソープやシャンプーを使うと、気持ちをリフレッシュさせることができるでしょう。
方法⑦家族や友だちにモーニングコールを頼む
朝どうしても起きられないときは、家族や友だちにモーニングコールを頼むのも方法のひとつです。
自分用のスマートフォンを持っている人などに限定される方法ですが、モーニングコールしてもらうことで、これまでよりもスムーズに起きられるかもしれません。
特に友だちからモーニングコールが届くと、友だちはこの時間にはもう起きているんだと、心強い気持ちで起きることができます。
方法⑧二度寝用に早めにアラームを設定する
あえて二度寝をするつもりで、二度寝用に早めにアラームを設定する方法もオススメです。それでも起きられないと不安に思うときは、分刻みでアラームを設定するのも効果的です。
朝起きるべき時間から逆算して、30分、20分、15分、10分、5分、1分といったイメージでアラームを設定するのもいいかもしれません。
そうすると、1度アラームを切っても、その後も何度かアラームが鳴ります。
アラームのどれかで起きられる可能性があるため、全部が鳴り終わる前に起きられるようになるでしょう。
方法⑨睡眠外来を受診する

睡眠外来とは、夜間の睡眠や日中の眠気などで困っている人が相談できる専門外来のことです。
不眠症や過眠症などの睡眠障害に適した治療が受けられるので、どうしても起きられない人は受診してみると良いかもしれません。
ただし、身体がだるい日が続く、気持ちが晴れないなど、睡眠以外にも症状がみられるときは、別の病気が潜んでいる可能性もあります。
そのようなときは、心療内科の受診も検討しましょう。
方法⑩悩みごとを専門家に相談する
学校や友だちとの関係性、家庭についてなど、自分の中で悩みごとがある場合は、専門家に相談し、解決の糸口となるアドバイスを受けましょう。
相談先としては、以下のような相談機関があるので、積極的に活用してください。
補足:夜にやると効果的な早く眠れる方法

朝起きられないことに悩むときに試せる、夜に実施するのが効果的な早く眠れる方法もあります。
例えば、入浴時間を短くしてみる方法です。厚生労働省によると、入浴によって身体が温まることは、運動をした後に身体が温まることと同じ効果があるとしています。
深い睡眠を取りたいときは、就寝直前の入浴が良いとされているものの、身体が温まりすぎると逆に寝付きを悪くしてしまうそうです。
そのため、寝付きを優先させるには、就寝時間の2〜3時間前に入浴するのが理想としています。
体温の上昇が0.5度以上でも寝付きの効果は認められていることから、38度のぬるめのお湯であれば25~30分、42度の熱めのお湯であれば5分程度の入浴を試してみてください。(参考:e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」)
ほかの方法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
中学生のお子さんを朝起きられるようにする方法5選
この章では、朝起きられないことに悩むお子さんがいる親御さんに向けて、起きられるようにする方法を解説します。
お子さんが朝起きられない日が続くと、どうしても心配になったり、つい小言を言いたくなったりするものです。
そのような日が続くと、お子さんは、起きられないことを責められているように感じるかもしれません。また親御さんは、さまざまな気持ちで揺らぐことが増えるでしょう。これは、お互いにとって良い環境とは言いえません。
そうならないよう、これから解説する方法を参考にしながら、お子さんと一緒に取り組んでみてください。
方法①よく観察する

朝起きられないお子さんを、できるだけ観察してみてください。
原因はひとつではなく、さまざまな原因が複雑に絡んでいる可能性も考えられます。
お子さんの顔色が良くない、体調不良を訴えるなど、朝起きられないことに加えてこのようなことがある場合、起立性調節障害などの病気・障害が潜んでいる可能性があります。
また、親や家族に気付かれないよう夜ふかしをしているかもしれません。
学校に行くことそのものに辛そうな印象がうかがえるときは、学校に何らかの理由があると考えられます。
このように、お子さんの様子をしっかりと見て、朝起きられないこと以外にも何かないかを探してみましょう。
そうすることで、朝起きられない根本的な理由が見つかるかもしれません。
方法②良好な親子関係を心がける
中学生は、多感な時期でもあります。そのため、学校や家庭でストレスを抱えることが増えやすいです。
このような時期には、家庭がストレスを和らげられる唯一の場所になります。
心配のあまり、小言を言いたくなるときもあるでしょう。お子さんが親や家族の目を盗んで夜ふかししている様子が続けば、つい叱りたくなるときもあるはずです。
ですが、お子さんは、過保護すぎれば窮屈さを、逆に放任しすぎると愛情不足を感じます。そうすると、うまく口には出せないストレスを家庭で解消することができなくなります。
そのため、行動に対して直接小言を言ったり叱ったりするのではなく、間接的に「あなたのことは見ているよ」というアピールをしてみてください。
お子さんが多感な時期は、適度な関係性を築くことが望ましいです。心配のあまり気持ちのままを口に出すのは控え、間接的な言葉で伝えるよう心がけてみてください。
方法③生活リズムを一緒に整える

お子さんが朝起きられるよう、親御さんが一緒に生活リズムを整えるのも効果的です。
お子さんだけ生活リズムを整えようとしても、親御さんが夜遅くまで起きていると、不公平さを感じるかもしれません。
これまで、親御さんは夜遅くまで起きている、お子さんだけ早く寝かせるようにしていたという状態が続いていたのであれば、この機会に一緒になって就寝時間を整えてみると良いでしょう。
方法④専門家や医療機関に相談する
こちらで解説したとおり、お子さんが朝起きられない原因には、生活リズムの乱れだけでなく、病気・障害が関係している可能性もあります。
病気・障害の関係が疑われる場合、専門家や医療機関を訪ね、相談し、適切なアドバイスを受けていただくことを推奨します。
睡眠外来や心療外来の受診が、十分な睡眠が取れない原因や解決の糸口を見つけるきっかけになるかもしれません。
方法⑤学校以外でも勉強できることを伝える

朝起きられないことが続いたことで、お子さんが通学に対して不安に感じているときは、学校以外でも勉強ができることを伝えてみましょう。学校以外でも勉強できることを知れれば、勉強に対する不安をいくらか解消できるかもしれません。
例えば、フリースクールなどがあります。
フリースクールとは、さまざまな理由で、学校に行かない選択をした子どもたちが通える学校以外の学びの場のことです。
お子さんの学びたいという意欲を、学校以外の場所で伸ばすことができるので、検討してみるのもよいかもしれません。
フリースクールについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
また、生活リズムに合わせて無理なく学ぶことができる通塾・オンライン対応の学習塾もあります。そのような塾であれば、まずは丁寧な面談を行い、生徒さん一人ひとりに合わせたカリキュラムを提案してくれるはずです。
私たち、キズキ共育塾もそのひとつです。朝起きられないために通学が難しくなったときは、これまでとは違った方法でも学べることを、お子さんに伝えてみてください。
まとめ~朝起きられないときはできることから試してみましょう~

朝起きられないことは、子どもに限らず、大人になっても抱えることのある問題です。朝起きられない人は、あなただけではないので安心してください。
ですが、朝起きられないことが長期的に続き、通学にまで支障を来している場合、何らかの理由で起きられなくなっている可能性があります。
まずは、このコラムで紹介した方法を試してみてください。それでもやはり朝起きられないときは、ご両親やスクールカウンセラー、睡眠外来など頼れる人に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。
このコラムが、あなたが朝起きられるようになるきっかけにつながれば幸いです。
Q&A よくある質問
朝起きられるようになる方法を知りたいです。
以下が考えられます。
- 生活リズムを意識して整える
- 布団の中で身体を動かし体温を上げる
- カーテンを開けて太陽を浴びる
- 栄養バランスを考えた食事をとる
- 好きな音楽を聴く
- 朝シャワーを浴びる
- 家族や友だちにモーニングコールを頼む
- 二度寝用に早めにアラームを設定する
- 睡眠外来を受診する
- 悩みごとを専門家に相談する
詳細については、こちらで解説しています。
中学生の子どもが全く起きません。どうしたら起こせますか?