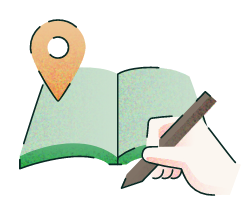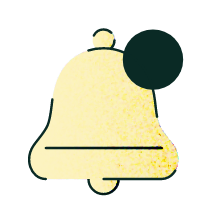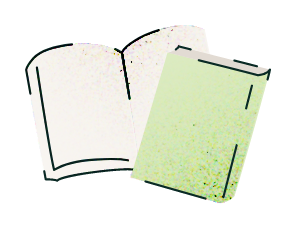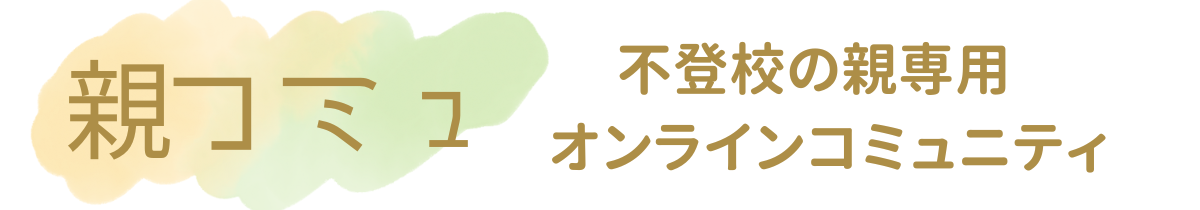眠れないあなたへ タイプ別不眠の解消法を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾の佐野澪です。
- いろいろ考えすぎて眠れない。対処法が知りたい
- 眠れないまま朝になってしまった
眠れない夜はつらく苦しいですよね。このコラムを読んでいるあなたのため息が聞こえてくるようです。
筆者も不眠症には過去6年間苦しめられました。お気持ちはよくわかります。
このコラムでは、眠れない夜を過ごすあなたに向けて、眠れない原因や今すぐ眠りたいときの対処法について解説します。あわせて、筆者の経験に基づき、効果のあった快眠グッズを紹介します。
ぐっすり眠れると、心身ともにスッキリとした状態で過ごすことができます。
本コラムが、あなたの快眠ライフに役立ちますように!
私たちキズキ共育塾は、眠れない人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
夜眠れない原因
生物にとって、眠ることはとても大切です。ヒトは十分な睡眠をとることで、心身を健やかな状態に保つことができます。
眠れないのは誰にとってもつらいものですが、現代では不眠症に悩む人は少なくありません。
成人の3人に1人は少なくとも時々は不眠になり、約10%から15%の人は慢性的不眠であるとも言われています。
この章では、夜眠れない原因について解説します。(参考:渡辺範雄『自分でできる『不眠』克服ワークブック』、厚生労働省「不眠症 | e-ヘルスネット」、厚生労働省「睡眠・覚醒リズム障害 | e-ヘルスネット」、厚生労働省「昼間の眠気 -睡眠時無呼吸症候群・ナルコレプシーなどの過眠症は治療が必要 | e-ヘルスネット」)
原因①ストレス

眠れないという悩みに大きくかかわってくるのが、ストレスです。
中でも仕事や学校、家庭の悩みや人間関係のトラブルが元で眠れないという人が多いのではないでしょうか?ほかにも経済的な不安が不眠の原因になることもあります。
心配事によって入眠が妨げられたり、眠りが浅く夜中に起きてしまったりすることが続くと、「今夜も眠れないのではないか」「早く眠らなければ」と不安や焦りが出て、ますます眠れなくなるという悪循環におちいることもあります。(参考:厚生労働省「不眠症 | e-ヘルスネット」)
原因②生活リズムの乱れ
眠れないという人の場合、生活リズムが乱れているケースがとても多く見られます。
私たちの体内時計の周期は約25時間。地球の周期とは約1時間のずれがあります。このずれを修正できず、睡眠・覚醒リズムに乱れが生じることがあります。
それによって起こる睡眠の障害を睡眠・覚醒リズム障害と呼びます。
朝に太陽の光を浴びて食事を摂り、学校や仕事に行くというようなリズムができていれば、体内時計の周期が補正できます。
明るくなったら起き、暗い時間帯に寝るという、いわゆる規則正しい生活が大事なのです。
しかし、夜に照明の光やブルーライトを浴びたり、就寝・起床時間が不規則になったりすると、この周期のずれを補正できなくなっていきます。運動不足も原因の一つという説もあります。
その結果、望ましい時間帯に入眠・起床することができなくなり、日常生活に影響が出てくるのです。(参考:厚生労働省「睡眠・覚醒リズム障害 | e-ヘルスネット」)
原因③カフェインやアルコールの摂取

特に心配事や生活リズムの乱れがないのに、夜になると目が冴えて眠れない場合は、自分が飲んでいるものを気にかけてみましょう。
コーヒーや紅茶、日本茶などのカフェインを含んだ飲み物は覚醒効果があるので、夜の眠りを妨げることがあります。
また、実はコーラやエナジードリンクにも大量のカフェインが含まれています。
「昼間、元気を出したい」「頭と体をしゃきっとさせたい」そんな目的で飲んでいるものが、眠れない原因になっているかもしれません。
加えて、アルコールも不眠の原因となります。
特に、寝付きを良くする目的で飲む寝酒はNGです。確かに入眠はしやすくなる場合が多いですが、その効果は短時間しか続きません。
深い睡眠ができなくなったり、早朝覚醒が増えてしまったりといったデメリットがあります。(参考:厚生労働省「不眠症 | e-ヘルスネット」)
原因④病気
不眠の原因には、病気が隠れていることもあります。
例えば、うつ病や不安障害などの精神疾患の場合、眠れないという症状が出ることもあります。
「単なる不眠だと思っていたけれど、病院を受診してみたらうつ病と診断されたというケースもあります。
また、睡眠・覚醒リズム障害や不眠症、過眠症などの睡眠に関する病気・障害と診断される場合があります。
ほかにも、睡眠中に何度も呼吸が止まったり浅くなったりして体の低酸素状態が発生する病気である睡眠時無呼吸症候群などの疾患が原因で眠りが浅くなっている場合もあります。
単に、眠れない、寝付きが悪いケースと診断がつくケースの区別は、私たち一般の人には難しいものです。(参考:厚生労働省「昼間の眠気 -睡眠時無呼吸症候群・ナルコレプシーなどの過眠症は治療が必要 | e-ヘルスネット」)
今すぐ眠りたい!そんな時の対処法8選
翌日に大事な予定がある場合など、いつまで経っても眠れないと焦りますよね。
「眠らなきゃ」と思えば思うほど、かえって目がパッチリ冴えていくという経験を持つ人は、少なくないでしょう。
しかし、その晩限りの眠れない場合は、わりとカンタンに対処することができます。
布団に入ってもなかなか眠れないのは、神経がたかぶっているためです。
交感神経が活性化して頭が働きすぎており、心身が眠る態勢に入れていないのです。
五感に働きかけてリラックスすることで副交感神経が優位になり、寝つきやすくなりますよ。
こちらの章では、今すぐ眠りたい時の対処法について解説します。
ただし、病気が関係する不眠を除きます。ご自身の眠れない状態が病気に関係するかどうかは、病院に行って確認しましょう。
対処法①アイマスクや耳栓を使う

人間は、視覚で多くの情報を取り入れています。
アイマスクをして目を覆うことで、意識を体の内側へ向けることができます。
すると呼吸を意識しやすくなり、体の力が抜きやすくなり、眠れるようになります。
また、周囲の音が気になって入眠できないときは、耳栓をすると落ち着くことができます。
ご自分に合ったものなら、どんなものでも構いません。
対処法②ヒーリングミュージックや自然環境音を流す
波や自然の音などの環境音、α波(リラックスした状態の時に発生する脳波)が出る音や音楽を聴くことで、リラックス効果が得られ、安眠につながることがあります。
オススメはヒーリングミュージックや自然環境音です。
そうした音を、アプリを利用して聞くのです。筆者が利用しているアプリを2つご紹介します。
- 目覚ましアプリ「熟睡アラーム」:熟睡を促すサウンドが流れるほか、睡眠の記録をとることもできます。
- 睡眠計アプリ「BetterSleep」:いくつかの音源をミックスして自分の好みのサウンドを作ったり、読み聞かせを聞いたりすることもできます。
いずれのアプリも基本的には無料で利用できます。いろいろなアプリを試して、自分に合ったものを選んでみましょう。
なお、YoutubeやSpotifyで聴くこともできますが、広告が入ったり、関係のない動画を見たりすることがあるかもしれないので、積極的にはオススメしません。また、眠った後も音が鳴っていると睡眠を妨げることがあります。
紹介したアプリなどのように、寝ついた後は音が切れるようにタイマーを利用できる再生装置を使うといいでしょう。
対処法③アロマを活用する

アロマテラピーは、香りで脳に働きかけることによって、リラックスを促してくれます。
心地よい香りに包まれることで、身体の緊張が緩み、副交感神経が優位な状態をつくりやすくなります。
入眠前にはラベンダーやオレンジ、ベルガモットなどの香りがおすすめです。
また、それらをブレンドした睡眠向けのオイルも販売されています。
アロマの代わりにピローミストを用いてもよいでしょう。
ピローミストは、さまざまな量販店などで売られています。
筆者は、東急ハンズ、ロフト、生活の木などのお店で購入しました。
近くに店舗がない場合は、ネット通販も見てみましょう。
対処法④リラクゼーション法を行う
リラクゼーション法は、緊張を解き、ストレスの悪影響を和らげるために行われることがあります。
また、リラクゼーション法は睡眠の誘導、痛みの軽減、落ち着いた気持ちを得るために用いられることもあります。(参考:厚生労働省eJIM「ストレスに対するリラクゼーション法について知っておくべき5つのこと」)
世の中には、呼吸法、自律訓練法、漸進的弛緩法、マインドフルネスなど、さまざまなリラクゼーション法があります。
これらの方法に慣れて、リラックス状態を10分程度続けられるようになると、覚醒と睡眠の中間にあたる半覚醒状態をつくることができます。
半覚醒状態には睡眠導入効果があり、この状態を経て眠りにつくと、より良質な睡眠がとれるといわれています。
ただ、独学でリラクゼーション法を実践するのは、そう簡単ではありません。また、覚えることがストレスになってもいけません。
書籍や動画サイトでいろんな方法が紹介されていますが、ここでも手軽に試せるのはアプリです。
例えば、瞑想アプリ「MEISOON」やヨガ&瞑想アプリ「寝たまんまヨガ」は、インストラクターの誘導に従えばよいだけなので、おすすめです。
さらに気軽にできるのが、深呼吸やストレッチ、ツボ押しです。日常生活の中でちょっと疲れを感じたときや寝る前に行うだけで、心と体のリラックスにつながります。
不眠に効くツボとしては、以下の3つが挙げられます。(参考:久喜整骨院「頭にある万能のツボ 【百会】」、美容鍼・鍼灸サロンカリスタ「オススメのツボ「合谷」」、IKOSHI東西鍼灸院・東西漢方院「経絡経穴の紹介」)
- 百会(ひゃくえ)…頭頂部の真ん中あたりの少しへこんでいる部分です。頭痛や肩こり、目の疲れのほか、自律神経の働きも整えると言われています。
- 合谷(ごうこく)…手の甲の親指と人指し指の骨が交差した部分から、人差し指へ向かって押していき、痛みを感じるくぼみの部分です。脳の疲れに効くと言われています。
- 内関(ないかん)…手のひらを握ったときに出る2本の腱と腱の間で、手首の関節から指3本分離れた部分です。ストレスや緊張に効くと言われています。
いずれも、「痛気持ちいい」と感じるくらいの強さで押してみましょう。
対処法⑤睡眠導入法を行う

ストレスや緊張など、眠りにつくことが難しい状況の方でも短時間で眠るための「睡眠導入法」というものがあります。
ここでは、「米軍式睡眠法」をご紹介します。
「米軍式睡眠法」は、ストレスや緊張にさらされている状況下でも「一瞬で寝る方法」として有名になった睡眠法です。(参考: Lloyd Bud Winter 『Relax and Win: Championship Performance』)
大まかには以下のようなプロセスで眠りを促します。
- 力を抜いて横たわり、ゆっくりと深呼吸し、顔の筋肉をリラックスさせます。
- 深呼吸して体全体をリラックスさせます。上半身から始め、太ももから膝下まで脚の緊張を解いていきましょう。
- 全身を10秒間リラックスさせたら、心をクリアにしていきます。
青空のもと、静かな湖に浮かべたカヌーに寝そべる自分や、真っ暗な部屋でハンモックに乗っている心地よい状態をイメージします。
「考えるな、考えるな、考えるな」と、10秒間何度も繰り返して言うのも効果的です。
対処法⑥額や首の後ろを冷やす
夜の仕事や考え事等で頭を使いすぎたときには、頭部に熱が溜まっています。
頭に血が上った状態では寝つくのが難しいので、布にくるんだ保冷剤を当てたりして、脳をクールダウンさせましょう。
春から夏にかけて、室温が高めの時季に特におすすめの方法です。
対処法⑦あたたかい飲み物を飲む

布団の中で考え事をしたり心配事に悩んでいたりすると、無意識に呼吸が浅くなりがちです。
呼吸が浅いと血流が悪くなるので、あたたかいものを飲んで、固まった筋肉をほぐしましょう。
こちらで解説したように、コーヒーや日本茶などはカフェインを含んでいるので避ける必要があります。
ノンカフェインの飲み物にも、美味しいものがたくさんあります。スーパーでもさまざまな種類が売られていますので、色々試してみるのがおすすめです。
ちなみに、筆者は、夜にはカモミールティー、クロモジ茶、黒豆茶を好んで飲みます。
対処法⑧どうしても眠れないときは、横になるだけでも休まる
「これだけいろいろ試しているのに、どうしても眠れない……」
そんな状況におちいると、焦りや不安が出てきますね。
しかし、横になっているだけでも、体を休めることはできています。「眠れなくても、疲労は少しずつ軽くなっている」―そう考えるだけで、少し気が楽になるのではないでしょうか。(参考:一般社団法人起立性調節障害改善協会「眠れない時に横になるだけで効果はある?目を瞑るだけで体が休まるのか解説」)
これまでご紹介した方法を試しながらソファなどで横になり、リラックスして、眠気が出てきたら寝室に移動しましょう。
「すぐに眠れる人」になるための生活習慣の改善法5選
眠れない日が何日も続くと、心身ともにつらくなってきますよね。
健康な睡眠をとるためには、よい習慣・環境が大切です。
一時的な不眠と違い、慢性的な不眠症になっている場合は、リズムを整えるためには最低でも2週間必要になることが多いです(時差ボケと同じですね)。
というのも、慢性化した不眠症は、その晩限りの不眠に比べて、習慣化しているからです。
慢性化した不眠は一朝一夕には改善しませんが、気長に取り組めば大丈夫です。
では、どんな習慣・環境がより適切なのでしょうか。いくつか挙げてみましょう。
改善法①規則正しい生活をする

こちら(記事内リンク「眠れない原因とは?」「生活リズムの乱れ」)でも解説しましたが、生活リズムの乱れは、眠れない原因の1つです。そのため、規則正しい生活を心がけましょう。
起床と就寝の時刻を一定にすることで、体内時計の調整がスムーズになります。週末の夜ふかし、休日の昼寝などを避け、できるだけ毎日同じリズムで生活するようにしましょう。
昼食のあとなど、どうしても眠くなったときの昼寝は、「午後3時よりも前に」「30分以内で」を心がけるのがおすすめです。
また、食事時間も重要です。朝食は簡単なもので良いので、糖分を補給し、日中元気に活動できるようにしましょう。そうすることで、質の良い睡眠につながります。
寝る直前に食事をとると、消化のため体に負担がかかり、眠りが浅くなります。夕食から就寝までは、できるだけ時間を空けるようにしましょう。
改善法②運動量を増やす
運動は睡眠の構造を変え、睡眠の質を高めることがわかっています。
運動自体が睡眠に影響するというよりは、運動による体温変化がキモのよう。
運動後、しばらくすると体温が下がります。
ヒトは体温が下がるときに眠りやすくなるので、睡眠が促進されやすくなるのです。
自分は運動してないな、と思う方は、運動量を増やしてみましょう。
運動のタイミングにもコツがあります。夕方から夜にかけて、就寝の3時間くらい前の運動が良い睡眠には効果的だと言われています。
改善法③入浴時間に注意する

入浴時間にも気を配ってみましょう。
ヒトは、体温が高い状態だと眠りづらくなるのです。
入浴直後は体温が上がるので、なかなか眠れません。
入浴は、寝る直前ではなく、寝る2〜3時間くらい前を心掛けましょう。
改善法④過集中を解消する
休憩中・OFFの日にPCやスマホをいじらないことが大切です。
頭が冴え続けていると、リラックスできません。
つくるべきは「普段と違う、余暇・余時間」です。
しっかり休みたいときは、活動と休息のバランスをとることが重要です。
改善法⑤眠くなるまで布団(寝室)に入らない

眠くないときに無理に布団(寝室)で過ごす日が続くと、ヒトの頭は「布団(寝室)=眠れない場所」と認識するようになります。
慢性的な不眠では、次のような悪循環に陥っていることが多いのです。
- ストレスから眠れない→
- 眠れない日が続く→
- それがまたさらなるストレスになる→
- 布団で眠れないことが当たり前になる→
- 布団=眠れない場所という認識が根づく→
- ストレスになる
そうすると、布団(寝室)にいると、ますます眠れなくなります。
眠くなるまでは布団(寝室)に入らず、本を読んだりラジオを聴いたりなどして過ごすのがよいでしょう。
特に、興味のない分野の本やラジオを試してみると、退屈して眠くなることもあります。(参考:厚生労働省「休養・こころの健康 | e-ヘルスネット」 厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針 2014」)
「すぐに眠れる人」になるための睡眠環境の改善法5選
眠れない場合は、睡眠環境を整えるところからはじめるのもいいでしょう。
おすすめの睡眠環境の改善方法をいくつか紹介します。
改善法①寝具を変える

ふだん使っている寝具が、実は自分に合っていない…なんてこともあります。
枕の高さはあなたの体型に合っているでしょうか。
一般に、仰向けでベッドやマットレス、敷布団の表面から首の角度が約5〜15°、頸部のすき間の深さが1〜6cmが適していると言われています。
マットレスの硬さも重要です。柔らかすぎると眠りにくいだけでなく腰痛の原因になり、硬すぎると骨が当たり痛みを感じたり血流が妨げられたりします。
「熟睡できていないような気がする」という場合は、一度見直してみるのがよいでしょう。
パジャマやシーツなど、肌に触れるものを、自分にとって心地のよいグッズに変えるのもよいでしょう。
また、季節性も重要です。例えば、暑い季節には通気性のよい寝具を使うと寝つきがよくなることがわかっています。(参考:厚生労働省「快眠のためのテクニック -よく眠るために必要な寝具の条件と寝相・寝返りとの関係 | e-ヘルスネット」)
改善法②眠りにつく前は間接照明を利用する
運動する前に準備運動するように、睡眠前もくつろぐ準備をしましょう。
間接照明の光はたかぶった神経を静めやすく、呼吸も穏やかになります。
白っぽい昼白色の蛍光灯は体内時計を遅らせる作用があると言われています。赤っぽい暖色系の蛍光灯が理想的でしょう。(参考:厚生労働省「快眠と生活習慣 | e-ヘルスネット」)
昨今ではさまざまな種類の間接照明が販売されていますが、筆者のオススメは、「LUMINARA(ルミナラ)」という、ロウソクのようなLEDライトです。
暗闇のなかでゆらゆら揺れる炎のような光をじっと眺めていると、眠りやすくなりますよ。
改善法③眠りにつくときは余計な光をシャットアウトする

いざ眠るときには、あなた自身が不安にならない範囲で、部屋はできるだけ暗くしましょう。
都市部にお住まいの方の場合、夜でも家の外は街灯やネオンなどで明るい場合があります。それらの光がカーテンを通して入ってくると、深い眠りが妨げられます。
おすすめは遮光カーテンを使用することです。驚くほど部屋が暗くなりますよ。
またエアコンなどの家電製品のランプも、意外と気になるもの。設定を変えることで消せる明かりがあれば、できるだけOFFにするのがおすすめです。
改善法④寝室の温度や湿度を調整する
明るさと同じくらい重要なのが、寝室の温度や湿度です。
厚生労働の「睡眠指針12箇条」では、寝室で寝具や寝間着を使用した状況では、室温はおおむね13〜29℃の範囲、寝具の内部は33℃前後になるよう調整することが望ましいとされています。(参考:厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針2014」)
また湿度が高すぎると、質の良い睡眠が妨げられると言われています。
もちろん、温度や湿度の感じ方は人それぞれ。自分が暑がりなのか寒がりなのか、湿度に対する敏感さはどうかなど知っておくと良いですね。
ご家族などと一緒に寝ている方の場合は、お互いにとっての「適温」が食い違い、どちらかがぐっすり眠れないことがあります。そういった場合は、寝具などで調整すると良いでしょう。
改善法⑤寝床で悩まない

何か不安や心配ごとがある場合は、寝床につく前に紙に書き出す、リスト化するなどしておきましょう。
そうすると、布団の中で悩まなくなり、眠れるようになります。
そもそも、夜中には考える力が落ちているので、布団の中で悩んでも空回りに終わることも少なくありません。
悩みが解決しないために毎晩同じことを悩み続け、毎晩眠れない…という悪循環も避けられます。
筆者の不眠改善に最も効果があった短期睡眠行動療法

短期睡眠行動療法は、筆者の不眠改善には最も効果がありました。
短期睡眠行動療法は、精神療法の一種である認知行動療法を改良して、うつ病の不眠を治すための精神療法として開発されたものです。
「精神療法」と聞くとちょっと大掛かりに思えるかもしれませんが、医者にかかっていなかったり、うつ病の方でなかったりしても、実践可能です。
市販のワークブックを使って、一人で実践することができます。
短期睡眠行動療法の趣旨は、下記の通りです。(参考:渡辺範雄『自分でできる『不眠』克服ワークブック』)
- 自分の不眠の状態を観察しながら、それに合わせて睡眠行動療法を行っていく
- 8週間で不眠をよくすることを目指していく
- 最初の4週間でやり方を覚え、次の4週間でそれを続ける
まずは、毎朝起きたとき、専用の書式に昨晩の睡眠の日記をつけ、睡眠の概要を記録します。
1週間分のデータが溜まったら、そのデータをもとに、自分に合った治療プログラムを作成していきます。
第2週目は睡眠のスケジュールをつくり、第3週目でそれを調整します。
こういった具合に、少しずつステップアップしていき、それを8週間続けることで、自分で自分の「睡眠力」を把握・改善して、不眠を治療することができるようになっていきます。
眠れない場合は睡眠外来・心療内科への通院も

慢性的な不眠そのものも大変なことですが、不眠が長引くとうつ病などの精神疾患に発展することもあります。
「不眠なんて、医者にかかるほどのことじゃない」と決めつけず、睡眠外来や心療内科を受診することもオススメです。
睡眠導入剤に抵抗がある方も多いと思いますが、近ごろは依存しにくいタイプの薬も存在します。
副作用などもしっかり確認しつつ、自分に合う治療法や薬の服用を行いましょう。
なお、残念ながら薬には合う合わないがありますし、別の薬を服用していたりすると処方が難しいこともあります(筆者自身の場合、あまり効果がありませんでした)。
ですが、筆者の知人は、処方薬を飲むことで不眠があっさり解決しました。
いずれにしても、「通院」や「服薬」を変に重く考えず、リラックスして受診してみましょう。
一般的に、不眠が一定期間続く場合や、そのことで不安な気持ちが強くなるような場合、病院を受診したほうが良いと言われています。(参考:厚生労働省「不眠症 | e-ヘルスネット」)
不安や心配そのものが、不眠を悪化させてしまうことがあります。
受診して不眠について相談するだけでも不安な気持ちは和らぎます。「眠れない」ということを1人で抱え込まず、誰かに相談することを優先しましょう。
書籍を読んで、睡眠への理解を深めよう

睡眠の科学的・医学的な知識を高めることは、睡眠の質を高めることに繋がります。睡眠への理解を深める書籍を紹介します。
『子どもの睡眠ガイドブック ―眠りの発達と睡眠障害の理解―』
- 駒田陽子・井上雄一/編、朝倉書店/刊
- 子どもたちの睡眠を阻害する要因に対応すべく、子どもの睡眠の関する科学的知識・生活習慣の指導のあり方を模索する医師・教師に座右の一書です。(朝倉書店ウェブサイトから)
多くの専門家が関わって執筆された一冊です。
- 川端裕人・三島和夫/著、集英社/刊
- 『ためしてガッテン』や『名医にQ』でおなじみの専門家が、理想の眠りを解き明かす。社会人や学生のパフォーマンス向上だけでなく、子育てから高齢者の認知症ケアまで網羅した「睡眠」本の決定版!(集英社ウェブサイトから)
とても読みやすい一冊です。
- 河合真/著、香坂俊/監修、丸善出版/刊
- 著者は米国の睡眠医学臨床研究を行った唯一の日本人医師。科目横断的な疾患テーマで睡眠医学を語る。OSAS(睡眠時無呼吸症候群)、不眠、ナルコレプシー、パラソムニア、概日リズムと睡眠覚醒リズム障害などを解説。「入院病棟」「救急外来」「ICUの現場」で役立つ睡眠医学の究極のアプローチ。米国スタンフォード大学睡眠医学センター直伝の「睡眠医学」が満載。(丸善出版ウェブサイトから)
タイトルは過激ですが、内容は実にオーソドックスでよい一冊です。
まとめ〜あなたに合う眠る方法が見つかりますように〜

人は、十分な睡眠をとることで、心身を健やかな状態に保つことができます。
現代では不眠症に悩む人が少なくありませんが、その原因にはストレスや生活リズムが関係しています。また、カフェインやアルコール、病気が原因となっている不眠もあります。
いかに生活リズムを整え、リラックスした状態をつくるかが不眠改善のポイントになります。
休息に必要な副交感神経を優位にさせるためには、五感に働きかけて、心地よさを感じることがポイントです。
寝る前の飲酒やスマホ・パソコンの操作は、睡眠には悪影響なので注意しましょう。
このコラムで解説した方法を試し、ぐっすり眠れるようになり、あなたの生活が充実するよう願っています。
さて、私たちキズキ共育塾は、不登校やひきこもりの当事者・経験者などの悩みを抱える人の学び直しを支援する個別指導塾です。
お悩みのテーマには、不眠もあります。
「勉強をやり直したいけど、不眠症状がつらくて不安…」など、ご興味のある方はお気軽にご相談ください。ご相談は無料です。
勉強方法とともに、あなたのための寝る方法や睡眠の質を高める方法を提案できると思います。
Q&A よくある質問