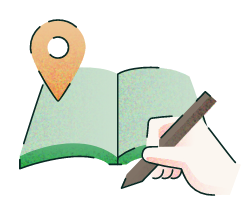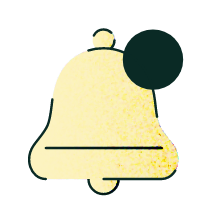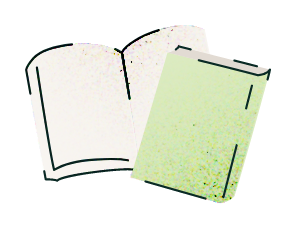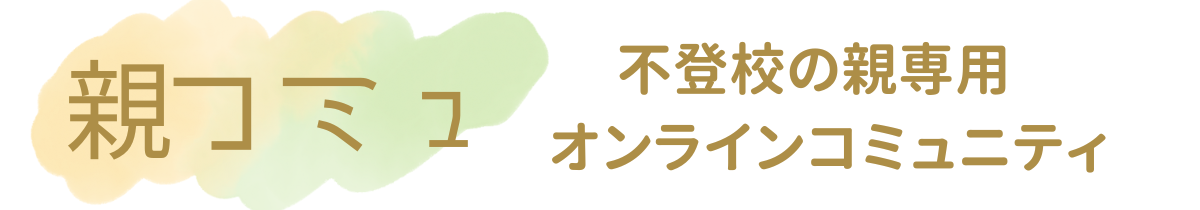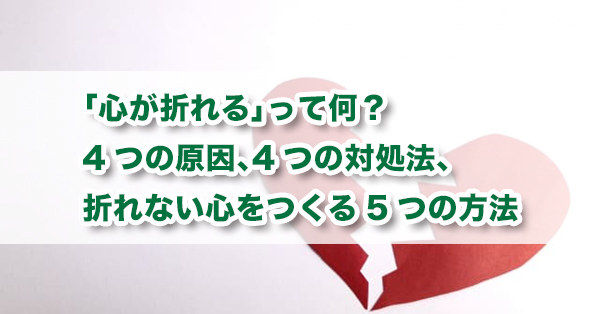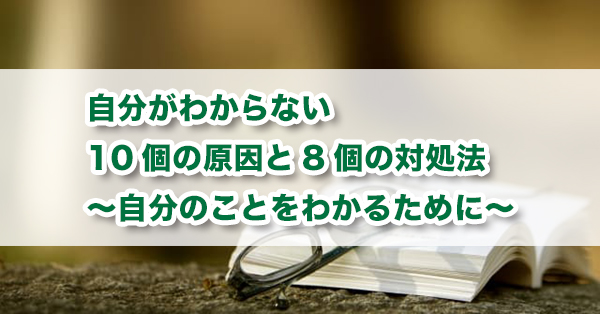病み期を抜け出す5つの方法 病み期になる原因や心理的症状も解説
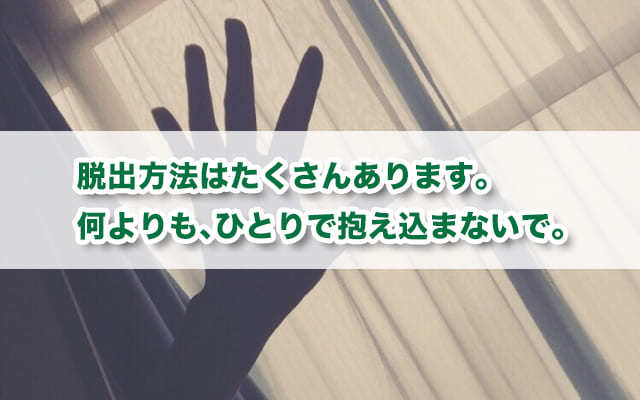
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
気持ちが落ち込み、何に対してもやる気が出ない時期ってありますよね。
以下のような状態が2、3日以上しばらく続くいているあなたは、病み期にいるのかもしれません。
- やる気が出ない
- 悲しい曲や物語ばかりが気になる
- 疲れているのにどうしても眠れない
- 食欲が湧かない
- ネガティブ思考だ
大前提として、これらの症状が深刻だったり長引いたりするようであれば、病み期ではなくうつ病などの心身の病気である可能性があります。
うつ病などに心当たりがある人や心配な人は、一度病院で診察を受けることを検討してください。
その上でここでは、以下のような軽い程度のものを病み期として取り扱うことにします。
- 気分が優れない状態が続く
- ここ数日間~1、2週間くらい気分が落ち込んでいる
このコラムでは、病み期の概要や病み期に現れる症状、原因、対処法などについて解説します。
このコラムが、病み期に陥って苦しんでいるあなたの助けとなり、病み期から抜け出すきっかけとなりましたら幸いです。
私たちキズキ共育塾は、病み期でお悩みの人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
病み期とは?

病み期とは、心が疲れているため気持ちが落ち込み、無気力や無欲、不眠、過度なネガティブ思考などが継続している状態・期間のこととされています。
ただし、病み期はネット上で使われる俗語の一種であり、医学用語ではありません。明確に定められた定義などはありませんが、一般的には以下のような状態・期間のことを指すようです。
- 気分が落ち込んでいて学校に行きたくない
- 何もやる気が起きない
- 不安や心配事であまり眠れない
しかし、こちらで挙げる心理的症状が、深刻だったり長引いたりする場合は、なんらかの精神障害や病気の影響が考えられます。病院の受診を検討しましょう。
病み期とうつ病の違い
病み期には明確な定義がないため、うつ病の違いも曖昧です。
しかし、うつ病は、治療が必要な精神障害の1つです。
うつ病とは、気分の落ち込みや憂うつ感、さまざまな意欲の低下などの精神的症状と、不眠、食欲の低下、疲労感などの身体的症状が一定期間持続することで、日常生活に大きな支障が生じる精神障害・気分障害のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「1 うつ病とは:」、厚生労働省「うつ病に関してまとめたページ」、、厚生労働省「うつ病」、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「うつ病」、MSDマニュアルプロフェッショナル版「抑うつ症候群」)
また、脳の機能が低下している状態、脳のエネルギーが欠乏した状態を指し、脳の中で神経細胞間のさまざまな情報の伝達を担うセロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンなどの神経伝達物質のバランスの乱れや、感情や意欲を司る脳の働きに何らかの不調が生じているものと考えられています。
うつ病の症状に当てはまる場合はもちろんですが、病み期の状態が継続していてつらい場合は、病院を受診しましょう。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「うつ病とは? 症状や治療方法を解説」
病み期に現れる5つの心理的症状
この章では、病み期に現れる5つの心理的症状について解説します。
症状①無気力・無欲
病み期に現れる症状の1つ目は、無気力・無欲です。
なにもやる気が起きない、つまり無気力な状態になるのです。
いつもだったら楽しめる趣味や習慣が、病み期になるとまったく手が付かなくなったり、「楽しくない、面白くない」と思うようになったりします。
外出やお風呂に入ることも面倒でできなかったり、食欲や物欲が湧かなかったりする人もいるようです。
症状②眠れない

2つ目の症状は、眠れないことです。
具体的には、「眠いのに寝れない」「寝なきゃいけないのに眠れない」などの状態です。
病み期になると、身体を動かす時間や日光を浴びる時間が減ったり、不安や心配な気持ちが大きくなったりして心身が不安定になったりすることで、夜に眠りづらくなります。
夜眠る方法については以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
症状③寝すぎる
さきほどの眠れない症状とは逆に、必要以上に寝すぎる人もいます。
身体を動かすのがダルかったり、何も気力が起きなかったりすることで、1日の大半を布団の中で過ごすような状態です。
これは筆者の体験談にもとづく考えですが、ストレスを日常的に感じているときは、いつも以上に睡眠時間が多くなります。
現実逃避なのか、心身の負荷を和らげようとしているのか分かりませんが、いずれにしてもストレスへの対処を無意識に行っているのかもしれません。
症状④ネガティブ思考

病み期になると、考え方や受け止め方がネガティブになりやすいです。
- 他人の言動が自分を否定しているように思える
- 自分はいつも失敗ばかりしていると思う
- 生きていても良いことはない気がする
このように、病み期になると無意識に思考がネガティブになります。
ネガティブ思考になると、いつもよりも心が折れやすくなることもあります。
心が折れた時の対処法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
症状⑤不安・心配でいっぱい
4つ目は、不安や心配でいっぱいになることです。
漠然とした不安で頭がいっぱいになったり、心配なことがあって勉強や仕事が手につかなかったりするのも、病み期の症状の1つです。
不安や心配は感情の1つなので、「不安があるとよくない」「心配なんてするものではない」などと、思う必要はありません。
ただ、それらの感情によって心身の健康や生活が崩れる場合は、何らかの対応を行う必要があります。
また、病み期の最中に不安や心配が大きくなる理由として、自分がわからない状態になることがあるのではないでしょうか?
特に、受験や就職活動、転職活動など、人生の大きな選択や挑戦をする時に、自分自身のことが分からなくなることもあると思います。
「自分がわからない」と思ったときの原因や対処法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
病み期になる原因

ここまで、病み期とは何か、病み期に現れる症状をお伝えしました。
しかし、そもそも人はなぜ病み期になるのでしょうか?
病み期の原因として、以下のことが考えられます。
- いじめやパワハラなどの被害に遭った
- 先生、親、上司に叱られた
- 友達に裏切られた
- 恋人や好きな人に振られた
- 大きな失敗をした
- がんばりすぎて疲れた(バーンアウト)
- 目標を失った
- 生活する環境が変わった
- ふとしたきっかけに過去の嫌な出来事を思い出した
病み期になる原因を挙げ出すと、キリがありません。
また、特に原因は思い当たらないけれど、病み期になる人もいます。
気温や気圧の影響によって病み期に入る人もいるでしょう。
とはいえ、あなたがどういう時に病み期に入りやすいのか(=原因、トリガー)の傾向を把握することはできます。
また、病み期に入った時にどうするとよいかのアイデアを持っておくと安心につながるでしょう。
体調がよいときにぜひ、あなたなりの病み期の原因やトリガーを探し、あわせて解消する方法も考えてみてください。
補足:女性はPMS・PMDDの可能性がある
女性の場合、気分が落ち込む原因として、月経前症候群(PMS)や 月経前気分障害(PMDD)の可能性が考えられます。
月経前症候群(PMS)とは、月経の3~10日間程前から下腹部や乳房の痛みなどの身体症状に加えて、憂うつになったり気分が落ち込んだりするなどの精神症状が現れ、日常生活に支障をきたす病気のことです。
また、月経前気分障害(PMDD)は、月経の1週間~2週間ほど前から、月経前症候群(PMS)の中の精神症状が強く表れる病気のことです。抑うつや不安、イライラから学校や仕事に行けなくなることもあります。(参考:社会福祉法人 恩賜財団 京都済生会病院「月経前症候群(PMS)と月経前不快気分障害(PMDD)」、医療法人東横会 たわらクリニック「月経前症候群(PMS)/ 月経前気分障害(PMDD)」)
月経前に気分の落ち込みや不安が大きくなる場合は、婦人科に相談することをオススメします。
病み期で悩みやすい人の特徴
この章では、病み期で悩みやすい人の特徴について解説します。
特徴①自己肯定感が低い

1つ目の特徴は、自己肯定感が低いことです。
自己肯定感(じここうていかん)とは、よい部分も悪い部分も含めて、自分のあり方を積極的に評価できる状態、自分の価値や存在意義を肯定的に評価できる状態のことです。(参考:実用日本語辞典「自己肯定感」)
つまり、自己肯定感が低い状態は、自分自身を肯定的に評価ができない状態と言えます。 具体的には、「私なんて」と思っていたり、他人の言動を自分のせいだと感じたりするため、そういった考えから気持ちが落ち込み、病み期に陥りやすい可能性があるのです。 自己肯定感の高め方については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。 2つ目の特徴は、完璧主義の傾向があることです。 完璧主義とは、さまざまな物事に高い目標を設定して、その達成に向けて行動する姿勢を指す言葉です。また、そのような姿勢の人物を完璧主義者といいます。(参考:中野敬子、臼田倫美、中村有里『完璧主義の適応的構成要素と精神的健康の関係』) 完璧主義の人は志を高く持っているため自分に厳しく、理想に向かって努力し続けます。 一方で、ささいなミスを許せず、自分を責め続けたり、自分に厳しくなりすぎて、心身ともに負担がかかったりすることがあり、結果的に気分が落ち込むなどの病み期の症状が現れることがあります。 完璧主義からくるつらさを和らげる方法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。 3つ目の特徴は、マイナス思考が強いことです。 マイナス思考とは、あらゆるものごとや場面において、「どうせ失敗する」「私なんてダメだ」などと悪い方向に考えが向くこと、否定的にとらえる考え方のことを指します。(参考:小学館「デジタル大辞林 」) マイナス思考は、失敗やトラブルを回避できるなどのメリットもあります。 しかし、何事もマイナス思考で考えていると、過度に不安を感じたり気分が落ち込む原因になったりすることが考えられます。 マイナス思考を改善するためのポイントについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。 4つ目の特徴は、自分と他人を比較することです。 ほかの特徴と同じく、自分と他人を比較することは悪いことばかりではありません。 しかし、常に自分と他人を比較していると、「周りはできているのに、自分はできていない」「自分だけ劣っている気がする」などと、自分に対して否定的な考えが強まります。 そして、そういった思考が続くと、気分の落ち込みや不安が大きくなる原因になり、病み期に陥りやすくなります。 自分と他人を比較することへの対処法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。 最後に、病み期から抜け出すためのアイデアを5つご紹介します。 いずれの方法を試してみるにしても、重要なのは以下の2点です。 すぐに実践できるものもあるので、病み期から抜け出したい人は、ぜひ今日から実践してみてください。 病み期は、精神的な疲労の現れである場合もあれば、気温・気圧の変化や過労など、身体的な疲労が現れている場合も考えられます。 「原因はわからないけど落ち込んでいる」「なんだか悲しい」などの気持ちのときは、思いっきり休みましょう。 具体的な休み方としては、半身浴やマッサージ、ストレッチなどをしたり、たくさん睡眠をとったりするのがオススメです。 病み期の状態では、不安や心配から眠れず、生活リズムが乱れているかもしれません。 しかし、生活リズムの乱れはていると、さらに気分が落ち込む原因となる可能性があるため、少しずつ生活リズムを整えていく必要があります。 生活リズムを整えるためには、朝にしっかりと起きることが大切です。そして、朝に起きるためには、必要な睡眠時間を確保しましょう。 厚生労働省は、小学生では9〜12時間、中学・高校生は8〜10時間の睡眠時間を推奨しています。(参考:健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会「健康づくりのための睡眠ガイド 2023(案)」) この推奨されている睡眠時間を確保できるように、1日の時間の使い方を見直し、就寝時間を決めてみてください。 また、寝る前にスマートフォンをついつい見過ぎて睡眠時間が短くなっている場合は、スマートフォンを見る時間を決めておく、就寝時は布団から手の届かないところに置く、などの方法がオススメです。 朝起きられるようになる方法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。 病み期の状態でいると、身体を動かすのが面倒になりますよね。 ですが、身体を動かさずにいると、生活習慣が乱れたり体力が低下したりすることで、さらに病み期が深まる可能性があります。 そのため、無理のない範囲でちょっとした散歩やラジオ体操、筋トレなどをするのがオススメです。 始める前は面倒くさいかもしれませんが、ストレスの発散や爽快感を得られるでしょう。 また、日光を浴びることでセロトニンが分泌し、鬱々とした気分が晴れていくはずです。 音楽を聴くと、嬉しくなったり悲しくなったりするでしょう。 また、「この曲を聴くと、楽しい気持ちが倍になる!」「悲しいときにこの曲を聴くと、気持ちが落ち着く」など、人それぞれ場合に応じて聴いている曲があると思います。 そのため、病み期に落ちいた際に聞くためのプレイリストを作っておき、病み期がきたらそれを聴くのがオススメです。 さきほどご紹介した「思いっきり休む」「身体を動かしてみる」などと組み合わせると、さらに病み期から脱出しやすくなるでしょう。 病み期の最中は、無気力になりだらだらと過ごすことが多くなるかもしれません。 しかし、そういった時間の使い方をしていると、「こんなにだらけている自分はダメだ」と、さらに気持ちが落ち込む可能性があります。 そのため、趣味や好きなことをして、充実した時間を過ごすように心がけてみてください。 また、趣味や好きなことをするのは、レジリエンスを鍛えることにもつながります。 レジリエンスとは、ストレスや困難に直面したときに回復する力のことで、レジリエンスが高まればネガティブな出来事に対して柔軟に対応でき、速やかに気持ちを切り替えることができるのです。 気持ちの切り替え方については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。 病み期に関する悩みは、1人で抱え込まないでください。家族や友人などの周囲の人に相談することが大切です。 しかし、場合によっては、以下のような考え、状況の人もいるでしょう。 このような場合は、医療機関や支援機関などへの専門家に相談することを検討しましょう。 医療機関や支援機関への相談と聞くと、大げさに感じるかもしれませんが、そんなことはありません。 むしろ、予防の観点から、早い段階で受診することに大きなメリットがあるのです。 はじめから医療機関や支援機関に行くことにためらいがある場合は、学校の先生やスクールカウンセラーに相談するのもオススメです。 そのほかの相談先については、以下のコラムで紹介しています。ぜひご覧ください。 病み期がくると気持ちが落ち込み、いつものように行動できなかったり前向きになりづらかったりすると思います。 ですが、病み期の対処法はたくさんありますので、ご紹介した方法をぜひ実践してみましょう。 一番避けていただきたいのは、病み期による悩みや不安を1人で抱え込んだり、自罰的になったりすることです。 そうした行動によって、自尊心をひどく損なうことになる可能性があります。 私たちキズキ共育塾は、お悩みを抱える人のための個別指導塾です。 勉強や悩み相談、雑談などを通じて、病み期にある生徒さんに寄り添い、病み期からの脱出を応援します。 少しでも気になったら、お気軽にご相談ください(ご相談は無料です)。
Q&A
よくある質問
特徴②完璧主義の傾向がある
特徴③マイナス思考が強い

特徴④自分と他人を比較する
病み期から抜け出す7つの対処法
対処法①思いっきり休む

対処法②生活リズムを整える
対処法③身体を動かす

対処法④音楽を聴く
対処法⑤趣味や好きなことをする

対処法⑥自分以外の誰かに相談する
まとめ〜病み期になったら対処法を実践しましょう〜