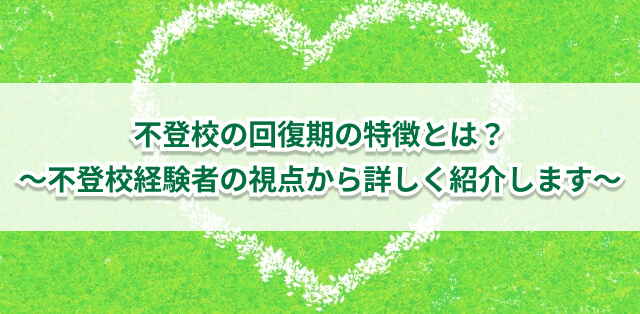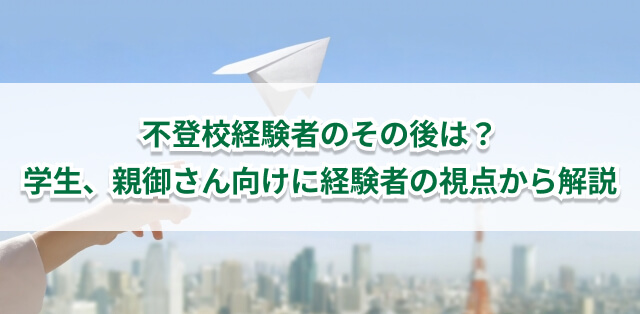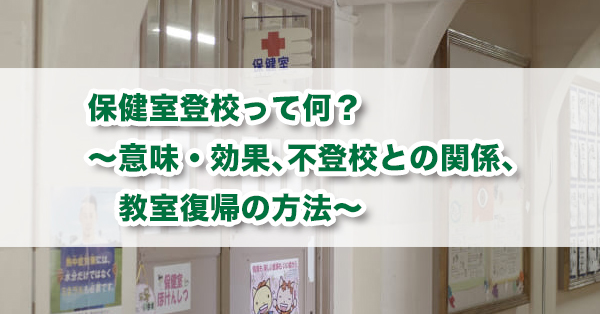子どもが不登校から復帰する前後に親ができる行動 不登校から復帰した人の体験談を紹介

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
不登校のお子さんがいる親御さんの中には、以下のような不安や思いを抱えている方が多いと思います。
- もう1年以上不登校だけど、復帰できる…?
- 休みがちでもいいから、少しでも学校に行ってほしい…
不登校から学校に復帰するまでには、たくさんのエネルギーが必要になります。
さらに、学校に一瞬だけ復帰すればいいというわけではなく、学校復帰後もエネルギーを維持しなくてはなりません。
このコラムでは、子どもが不登校から復帰するために親ができる行動、不登校復帰後にまたエネルギーが大きく落ちないようにするための注意点、子どもが不登校から復帰した後に親ができる行動などについて解説します。
また、不登校で悩むお子さん自身が学校復帰のためにできることや、不登校から復帰できたキズキ共育塾の生徒さんの体験談も紹介します。
お子さんが不登校から復帰するきっかけ、次の一歩を踏み出すヒントになれば幸いです。
共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの
アドバイス
お子さんを理解し、支えることが大切です
不登校と学校復帰は、何度も繰り返すものです。親御さんは、まずそれを理解し、覚悟しましょう。
繰り返す理由は、お子さん本人が「よりよい人生を送りたい」ともがいてるからです。
お子さんの選択には失敗もあるかもしれません。
しかし、お子さんの失敗や下手なやり方も含めて、親御さんはお子さんを支えてほしいと思います。
このコラムには、「学校復帰後にどんなパターンがあるのか」や「どんな心境で学校復帰や不登校になるのか」が書いてあります。
せひ参考にしてみてください。
私たちキズキ共育塾は、不登校からの復帰を目指す人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
不登校の子どもの原因

この章では、文部科学省の調査に基づき、小学生・中学生、高校生の不登校の原因について解説します。(参考:文部科学省「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」)
ただし、この調査は教員側に原因を尋ねたものです。ご本人やご家族の実感とは少しずれる点もあるかもしれません。
小学生・中学生の場合の不登校の原因TOP5
- 無気力・不安:約51.8%
- 生活リズムの乱れ・あそび・非行:約11.4%
- いじめをのぞく友人関係をめぐる問題:約9.2%
- 親子の関わり方:約7.4%
- 該当なし:約5.0%
高校生の場合の不登校の原因TOP5
- 無気力・不安:約40.0%
- 生活リズムの乱れ・あそび・非行:約15.9%
- いじめをのぞく友人関係をめぐる問題:約9.2%
- 入学・転編入学・進級時の不適応:約8.4%
- 該当なし:約8.0%
以上のように、さまざまな原因から不登校になる可能性があり、不登校の原因を取り除くことが学校復帰につながる場合もあります。
一方で、不登校の原因を考える際は、以下のことも理解しておくことが大切です。
- 不登校の原因は一人ひとり違っている
- 不登校の原因は複数の原因が複雑に絡まっていることが多い
- 子ども本人も不登校の原因がわからない場合がある
- 原因を取り除いても、学校復帰につながらないこともある
- 逆に、原因を取り除かなくても、学校復帰できる場合もある
このように、不登校の原因との向き合い方は難しく、原因を探し解消することだけが、不登校からの復帰につながるわけではないのです。
不登校の原因については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
不登校から復帰までの3つの段階
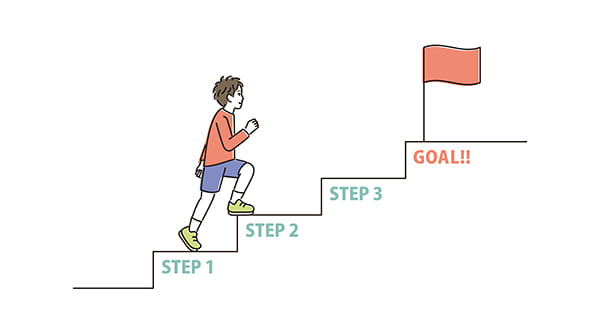
この章では、特別支援教育士の下島かほる氏の指摘に基づき、不登校から学校復帰までの段階について解説します。(参考:下島かほる・監修『登校しぶり・不登校の子に親ができること』)
ただし、これらは下島氏の経験に基づくものであり、不登校から学校復帰までの期間は、個人差はもちろん不登校の原因や環境によっても異なります。それらを踏まえた上で、参考にしていただければと思います。
- 不登校開始期(初期)
- ひきこもり期(中期)
- 回復期(後期)
それぞれの段階の期間や様子は、人によって異なりますが、各段階の特徴は以下のとおりです。
①不登校開始期(初期)
- 「不登校開始期」では、腹痛や頭痛といった体調不良などで学校を休む日が増え始める
- 遅刻・早退・保健室での勉強をすることなどが増え、本格的な不登校に移っていく境目
②ひきこもり期(中期)
- 「ひきこもり期」では、学校に行かずに、ほとんどの時間を家で過ごすようになる
- 昼夜逆転生活になったり、学校の話をイヤがったり、家族との関わりを避けたりするなどの様子が見られる
③回復期(後期)
- 回復期は、学校での人間関係、勉強、将来への悩みなどで疲れた心に、エネルギーが溜まってくる
- 回復期を経て、それぞれの不登校の、次の一歩へ進めるようになっていく
このように、不登校の子どもたちは、少しずつ段階を経て復帰できる状態になっていくのです。
また、不登校から復帰できるコンディションになったとしても、もとの学校への復帰を望まず、フリースクールや転校などを希望するお子さんもいます。
そのため、学校への復帰だけでなく、お子さんの希望やお子さんとの相性などを踏まえた上で、広い視野を持って、お子さんの次の一歩を考えることが大切です。
不登校の回復期やその後の選択肢については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
子どもが不登校から復帰するために親ができる5つの行動
この章では、お子さんが不登校から復帰するために親ができる行動について解説します。
お子さんのために何かしたいと考えているものの、何をすればいいかわからないと困っている親御さんは、ぜひ参考にしてください。
行動①不登校への罪悪感を減らす

1つ目の行動は、お子さんが抱えている不登校であることへの罪悪感を減らすことです。
不登校状態にあるお子さんは周囲の人に対して、以下のような罪悪感や絶望感でいっぱいになっていることが多いです。
- 親御さんへ:せっかく一生懸命育ててくれたのに、こんな自分でごめん…
- 部活の仲間へ:チームの人数が減って迷惑をかけている…
- 世間へ:自分だけ取り残されてしまっている…
このような気持ちでいると、学校の授業のある朝や昼間に起きていることがつらくなり、日中を寝て過ごすようになることがあります。
そして、日中もカーテンを閉め切っていると、体内時計が乱れ、だんだん昼夜逆転の生活になっていくのです。
筆者が見てきた限り、どんな悩みを抱えている人であっても、昼夜逆転の生活がずっと続くと、よい結果につながったケースはほとんどありません。
学校復帰についても、昼夜逆転の生活になると気持ちがどんどん沈み込み、復帰のために必要なエネルギーが生まれづらくなります。
そのため、親御さんはお子さんが不登校への罪悪感を減らせるように、以下のような対応や行動を心がけてみてください。
- 不登校であることに目を向け過ぎない
- 「健康でいてくれればいいよ」など子どもの現状を肯定する声掛けをする
以上のような対応をすると、お子さんの罪悪感・絶望感が軽減されます。また、昼夜逆転の生活になりづらくなるため、学校復帰や次の一歩に進みやすくなるでしょう。
お子さんが不登校であることに、どうしても目が向くようであれば、「不登校の子どもには普通の人と違った感受性やよさがあるかもしれない」と、発想を変えてみるのもよいかもしれません。
行動②生活習慣を少しずつ改善する
2つ目の行動は、お子さんの生活習慣の乱れを防いだり、すでに乱れているなら少しずつ改善できるように取り組んだりすることです。
こちらでご紹介したような理由から、不登校状態にあるお子さんは、生活習慣が乱れがちな場合が多いです。
昼夜逆転の生活になっていたり、昼夜逆転まではいかなくても睡眠や食事が乱れがちだったりすると、気力が湧きづらくなります。
そのため、お子さんに対して以下のような働きかけを行ってみてください。
- 明るいうちに予定を入れることを提案する
- 昼寝をしない、または昼寝の時間を短くするように言う
- 「睡眠クリニック」に通うことを勧める
生活習慣が整うと、少しずつ気力・体力が回復し、不登校から復帰しやすくなります。
ただし、強い口調で「規則的な生活をしなさい」と言い、無理矢理生活リズムを整えさせようとしてはいけません。
不登校状態にあるお子さんは、「授業のある時間に起きていたくない」と思っていることは少なくありません。無理に生活リズムを整えさせようとすると、お子さんが反発する原因になったり、精神的な負担になったりするのです。
そのため、お子さんと接する際は、「私はあなたの味方だよ」という姿勢を見せた上で、生活習慣を改善するように提案しましょう。また、不登校であることを責めないことも大切です。
不登校からの復帰について、「段階的でもよい」と考えて、粘り強くはたらきかけるようにしましょう。
こちらでは、親御さんのサポートによって昼夜逆転を解消し、不登校から復帰したキズキ共育塾の生徒さんの体験談を紹介しています。
行動③学校以外の安心できる居場所を作る

3つ目の行動は、学校以外でお子さんが安心できる居場所を作ることです。
不登校になり学校という居場所をなくしたお子さんにとって、学校以外の安心できる居場所があるかどうかは非常に重要な問題です。
以下のような、学校以外の安心できる居場所があると、お子さんの気持ちは安定していきます。
- 家庭
- 学習塾
- 習い事
- 趣味や遊びの団体・場所など
一番わかりやすい例は、家庭でしょう。
「家庭が安心できる場所であったから、または安心できる場所になったから、気力・体力が満たされて不登校から復帰した」という人たちを多く見てきました。
そして、安心できる居場所は、家庭以外にも複数あると、より気持ちが安定します。
ただし、たくさんのコミュニティに所属しすぎると疲れることもあるので、お子さんの性格を考慮したり、希望を聞いたりしながら安心できる居場所を作っていきましょう。
以下、いくつかの居場所の特徴について、紹介します。
学習塾
- 勉強面での学校復帰に対するハードルを下げられる
- 学校に復帰しなくても、進学のための勉強ができる
- お子さんが通いたいと思う、相性が良い学習塾を選ぶことが大切
趣味や遊びの団体・場所
- 興味のあることの開始・再開が、復帰につながることがある
- 趣味や遊びなどの楽しいことが、気分転換や気力・体力の充電になる
不登校状態にあるお子さんは、気晴らしであれ趣味であれ、「学校へ行っていない自分にはやる資格はない」と思いがちです。
ですが、そんなことは決してありません。
また、家族同様、信頼できる居場所での人との交流は、今後がんばりたいとき、がんばる必要があるときの心の支えになります。
つまり、学校以外の居場所に充実した人間関係があると、それらが支えになるため、不登校から復帰できる可能性が高まるのです。
こちらでは、趣味の市民劇団に通い続けて不登校から復帰したキズキ共育塾の生徒さんの体験談を紹介しています。
行動④学校との連絡を保つ
4つ目の行動は、学校との連絡を保つことです。
特に、担任の先生と連絡しておき、必要な時に連携できれば、学校に復帰しやすくなります。
本格的な復帰以外にも、以下のようなことを相談していれば、部分的な学校復帰ができ、進級や卒業ができる場合もあります。
- 保健室登校での出席日数カウント、別室での定期テスト受験などは認められるか
- 高校生の場合、あとどのくらい休んでも進級・卒業できるか
筆者自身も高校3年生のときに不登校になりました。ですが、親が担任の先生と相談してくれていたおかげで、別室でのテスト受験、課題の提出、出席日数の考慮などをしてもらうことができました。
その結果、学校に復帰し、卒業と大学進学をすることができました。
学校や先生によっては、柔軟な対応を行っている場合があるので、毎日教室に登校する復帰以外の方法がないか、相談してみましょう。
ただし残念ながら、以下のような先生の場合、相談できなかったり協力を得られなかったりすることがあるのも事実です。
- 聞く耳を持たない先生
- 勉強が苦手な生徒は相手にしない先生
- 生徒や、特に女親に高圧的に接する先生
- 多忙で話せない先生
- 正論や一般論しか言わない先生
- 自身もいっぱいいっぱいな先生
このような場合、不登校から一時的に復帰できても学校からのケアがあまりなく、再び不登校になるというケースも見受けられます。
先生や学校を悪いと決めつけるつもりはありません。ほとんどの先生は、生徒思いのいい先生なのかもしれません。
ですが、こういう先生もいるというのは、親御さんご自身の学校生活を振り返ると、覚えがあるのではないでしょうか。
また、お子さんも先生や学校も悪いわけではないのに、どうしてもソリが合わないということもあります。
万が一、学校や先生に相談できない、協力を得られない、ソリが合わないなどの状況であれば、無理にその学校に復帰する必要がありません。
以下のように、次に進む方法はたくさんあるのです。
- お子さんに合う学校に転校する
- 学校には行かず、塾などで勉強する
- 高校生の場合は、中退して高卒認定資格を取得する
キズキ共育塾の生徒さんにも、先生や学校に相談してもうまくいかず、学校に見切りをつけて、前向きに次に進んだ人は大勢います。
「どうしてもこの学校に復帰しなくてはならない理由」があるかどうか、お子さん本人ともよく話し合いましょう。
行動⑤無理のない範囲で勉強を再開する

5つ目の行動は、無理のない範囲で勉強を再開することです。
不登校からの復帰を妨げる1つの要因として、不登校中の勉強の遅れが挙げられます。
勉強の遅れがあると、以下のような不安から学校復帰が難しくなるのです。
- 学校には復帰したいけど、授業についていける自信がない…
- 学校に復帰しても、勉強で周りに置いて行かれるかも…
また、学校に復帰できたとしても、勉強の遅れがあると自信を失い、再び不登校になる可能性もあります。
自信をもって復帰できる、復帰後も継続して学校に通えるようにするためにも、無理のない範囲で勉強を再開することが大切なのです。
また、不登校中の勉強方法には、以下のようなさまざまな種類があります。お子さんに合った方法を探してみてください。
- 自主学習
- 通信教育・映像授業
- オンライン・リモート型個別指導
- 家庭教師
- 学習塾
- フリースクール
- 教育支援センター(適応指導教室)
ただし、お子さんの気力や体力が回復していない状態で、無理に勉強に取り組もうとすると、大きな負担になる恐れがあります。
そのため、お子さん自身が「そろそろ勉強しようかな」「家で勉強したいんだけど…」などと感じたタイミングから取り組むことがオススメです。
不登校中の勉強方法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
不登校復帰後にまた休むことがないようにするため注意点
この章では、不登校復帰後にまた休むことがないようにするための注意点について解説します。
「不登校から学校に復帰してほしい」と思う一方で、「復帰してもまた不登校になるのでは…?」と不安な親御さんは、ぜひ参考にしてみてください。
注意点①無理に復帰させようとしない
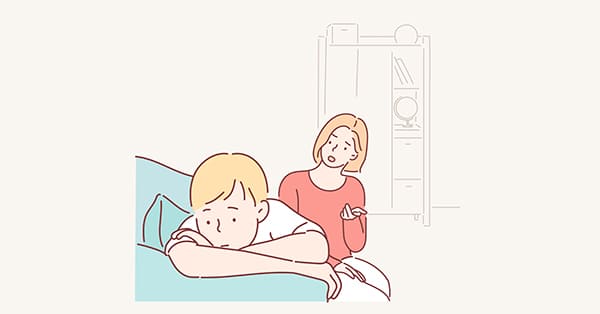
1つ目の注意点は、無理に復帰させようとしないことです。
多くの親御さんは、お子さんの将来や進学などのことを考えて、「できるだけ早く復帰してほしい」と思っているかもしれません。
しかし、学校への復帰は早ければいいというものではありません。十分に気力や体力が回復していない状態で復帰しても、また学校を休むことになる可能性が高いのです。
また、「もう今の学校には通いたくない」「学校という場所が自分には合わない」と思っているお子さんもいます。
そういったお子さんの思いや考えを無視して、学校に復帰させると、お子さんの心理的な負担が大きくなり、不登校を繰り返すことになる恐れがあるのです。
そのため、親御さんは無理に復帰させようとしたり、お子さんの思いや考えを無視したりしないように、注意しましょう。
お子さんのことを思い、焦る気持ちはよくわかりますが、お子さんの状態や思いを把握した上で、「今、学校に復帰することが子どもにとって最善策か」を考えることが大切です。
注意点②不登校の兆候を見逃さない
2つ目の注意点は、不登校の兆候を見逃さないことです。
親御さんは、お子さんが学校に復帰すると、「もうこれで大丈夫」と安心するかもしれません。
しかし、お子さんは不登校復帰後に様々な不安を抱え、悩んでいることが多いです。
そして、以下のような行動が、不登校の兆候として現れていることがあります。
- 頭痛や腹痛などでの欠席が多くなる
- 休日の翌日や特定の曜日に欠席が多くなる
- 部活を休みがちになる
- 前の晩には学校へ行く準備をするが、翌朝になると起きてこない
- 学校に行く時間になると体調が悪くなるが、親が欠席連絡をすると元気になる
- 朝、登校の準備に時間がかかる
- 自分の部屋に閉じこもりになり、家族との会話が少なくなる
このような行動がないか、日々お子さんを見守ることはもちろん、このような行動が見られた場合はすぐに対応することが大切です。
注意点③出席日数・学校にいる時間を意識しすぎない

3つ目は、出席日数・学校にいる時間を意識しすぎないことです。
「不登校から復帰する」と聞くと、「毎日すべての授業を受けて、部活にも参加できる状態」を想像する親御さんは多いかもしれません。
しかし、不登校だったお子さんは、気力も体力も低下していることが多いため、はじめから毎日すべての授業に出席することは、かなりハードルが高いです。
そのため、以下のように出席日数や学校にいる時間、学校で過ごす場所などについて、ハードルを下げるようにしましょう。
- まずは1週間のうち3日間学校に行ければOK
- 午前中で疲れたら早退してもOK
- 保健室登校・別室登校でもOK
- 部活は体力がついてきてからでOK
また、このような考え方は、親御さんが意識するだけでなく、お子さん本人にも伝えてあげましょう。
そうすることで、学校復帰に対する心理的なハードルが下がり、お子さんも学校に通い続けやすくなります。
ただし、伝え方によっては、お子さんが「親は自分に期待していない」と思う可能性があります。そのため、「少しずつ学校に慣れていこうね」といったこともあわせて伝えるようにしてみてください。
保健室登校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
子どもが不登校から復帰した後に親ができる4つの行動
不登校だったお子さんが学校に復帰すると、親御さんはホッとすると思います。しかし、お子さんにとって学校復帰は、がんばり続ける日々のスタートです。
不登校からの復帰直後は、多かれ少なかれ、先生やクラスメイトたちの「今までどうしていたの?」といった質問や噂話が、お子さん本人の耳にも入ってきます。
授業ごとに先生や生徒が異なる場合は、授業が変わるたびに同じ状況を味わうことになります。
久しぶりの登校で緊張していることに加えて、周りの反応や状況によって、お子さんはしばらくの間は体力のみならず精神的にもエネルギーを使い切って帰宅する、ということです。
こういった状況の中でも登校を継続させるためには、復帰前に引き続き親御さんのサポートが必要不可欠です。
この章では、子どもが不登校から復帰した後に親ができる行動について解説します。
前提:復帰後のケアと復帰までの道のりは共通しています

不登校から復帰した後のお子さんに対するケアは、こちらで解説した内容と共通しています。
しかし、不登校から復帰する前と復帰した後では、お子さんの取り巻く状況や心情がまったく違ってきます。
そのため、不登校から復帰した後のお子さんの状況や心情を踏まえて、改めて親御さんにできる行動を解説します。
行動①不登校だったことへの罪悪感を減らす
復帰後は、お子さんが感じている不登校だったことへの罪悪感を減らしましょう。
不登校から復帰したお子さんは、学校で何か失敗をしたときに、自身の不登校経験について必要以上に気にする傾向があります。
- 自分は不登校だったから、こんなこともできない…
- 自分が不登校だったことを、みんなが気にしている…
確かに、長く学校に通っていないことによる失敗は、起こりうるでしょう。
しかし、不登校だったことを気にしすぎると、最終的には「不登校を経験した自分は、何をやってももうダメだ」と考えるようになり、再度不登校になる可能性があります。
親御さんから見ると、「不登校だったことを、そんなに気にしなくていいのに」と思うかもしれません。ですが、お子さん本人としてはどうしても気になるのです。
不登校経験への罪悪感は、親御さんが「不登校だったことは悪いことじゃないよ」「不登校だったことを気にする必要はないよ」と、はっきり伝えることによって、軽くなっていきます。
そして、次第に不登校経験について気にならなくなり、学校に通い続けられるようになるでしょう。
行動②生活習慣を引き続き改善していく

登校を継続するためには、復帰前に引き続き生活習慣を改善していくことが大事です。
- 昼夜逆転がなかなか治らない
- 学校で体力や集中力が続かない
以上のような状態のお子さんは、学校に復帰できても、週に何日か欠席したり、遅刻や早退をしたりすることがあるでしょう。
そのため、復帰前に引き続き、お子さんの生活習慣が改善するように取り組むことが大切なのです。
また、復帰後は学校を休んだ日や学校に行けなかった時間が気になるかもしれません。
しかし、登校できた日や登校できた時間に目を向けましょう。「完全じゃないけど、通学を持続できている」とポジティブに考えることが大切です。
そうするとお子さんも「自分は完全復帰に向けて歩んでいる」と自信を持つことができます。
逆に、親御さんが以下のようなネガティブな側面ばかりに目を向けていると、そのことがお子さんに伝わることがあります。
- どうして夜型の生活が治らないんだ
- どうして全部の授業を受けられないんだ
このような思いが伝わると、お子さんは「やっぱり自分はダメなんだ…」と思い、不登校に逆戻りする可能性があります。
生活習慣の改善と不登校からの復帰・持続は、少しずつ進むものと割り切って考えることが重要です。
行動③学校以外の安心できる居場所を作る
復帰後も復帰前と同じく、学校以外の安心できる居場所があることが重要です。
不登校から復帰した子どもは、居場所を一つ取り戻しますが、「学校が安心できるか」は別問題です。
- 復帰後すぐにリラックスして通学できるわけではない
- そもそも学校が安心できる場所とは限らない
こういった状況の中で、学校に通い続けるためには、家や習い事、学習塾など、学校以外の安心できる居場所で十分な休息をとることが必要なのです。
そのため、親御さんは「不登校から復帰したから、学校以外の居場所がなくても大丈夫」と考えるのではなく、「引き続き、子どもにとって安心できる場所を保とう」と考えましょう。
不登校中に通っていた居場所や団体などがあり、お子さんがその居場所を楽しんでいたり、安心できていたりするようであれば、復帰後も通い続けることをオススメします。
とはいえ、ご家庭については、無理にいい家庭であり続けようとすると、親御さんが追い詰められる可能性があります。
家族の誰もが無理をせずに、安心して過ごせる家庭を目指して、無理のない範囲でお子さんの居場所作りに取り組んでみてください。
また、お子さんと同じく親御さんも、家庭以外の居場所を作ることが大切です。
カウンセリングに行ったり友人に相談したりするなど、家庭以外の場所や家族以外の人の力を借りることを考えてみましょう。
行動④学校との連絡を取り続ける

復帰後も、学校と連絡を取り続けましょう。
不登校から復帰したばかりのお子さんは、心身ともに不安定になっていることが多いです。
学校と連絡を取り続けることで、以下のようなことがわかり、お子さんを的確にサポートできます。
- お子さんの学校での様子
- お子さんが通学を持続するために必要なこと
- 親御さんにできる具体的な対応
また、学校と連絡を取り続ける中で、お子さんへの対応方法や配慮など、親御さんの要望を学校に伝えることも可能です。
さらに、連絡を取り続けて、学校や担任の先生との信頼関係を築いておくことで、お互いに情報や要望を伝えやすくなり、結果的に復帰後のお子さんをサポートすることにつながります。
不登校で悩むあなたが学校復帰のためにできる6つの行動
この章では、不登校で悩むあなたに向けて、学校復帰のためにできる行動について解説します。
「学校に復帰したいけど、復帰後が怖い」「今の状態では復帰できる気がしない」などの悩みや不安を抱えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
行動①生活リズムを整える

学校復帰のためにできる行動の1つ目は、生活リズムを整えることです。
生活リズムを整えるといっても、はじめから早寝早起きをするといった理想的な生活リズムを目指す必要はありません。
はじめは、何時でもよいので朝起きる時間をそろえることから始めてみましょう。毎日同じ時間に起きることで、生活リズムが整いやすくなるのです。
逆に、早起きや早寝ができていたとしても、毎日バラバラの時間に起きていると生活リズムが整いづらくなります。
毎日同じ時間に起きられるようになったら、寝る時間も一定にしたり、起きる時間を少しずつ登校時間に近づけたりするようにすると、復帰がしやすくなります。
行動②体力をつける
2つ目は、体力をつけることです。
不登校の状態であると外出する機会が減り、自分でも気づかないうちに体力が落ちていることがあります。
十分な体力がない状態で学校に復帰すると、学校に行くだけで疲れたり、学校に行っても授業や友達との会話に集中できなかったりするため、学校に通うことがつらくなってしまうかもしれません。
そういった状態にならないためにも、復帰前に体力をつけておきましょう。
具体的な方法としては、まず学校ではなくてよいので公園や図書館、デパートなど、自分が行きたいと思える場所に、週に何度か出かけてみてください。
どこかに定期的に出かけるだけでも、外出するための体力がつくので、学校に復帰した際も疲れにくくなります。
また、保健室登校から学校への復帰を始め、少しずつ学校に行く日数を増やしながら、徐々に体力をつけるという方法もあります。
ほかにも、体力づくりと合わせて、放課後や夜に学校に行き、学校や教室に入って雰囲気などに慣れておくこともオススメです。
行動③勉強を再開する

3つ目は、勉強を再開することです。
学校に復帰することを考えると、以下のように勉強面の不安を感じる人もいると思います。
- 学校に復帰したいけど、授業についていけるか不安…
- 勉強についていけない状態が続いたら、学校に行くのがつらくなりそう…
不登校の状態で勉強から離れている期間が長いと、こういった不安が出てくるのは当然です。
しかし、はじめから不登校期間中の勉強の遅れをすべて取り戻そうとするのは、現実的ではありません。また、はじめから頑張りすぎると、自分自身を追い込んでしまう可能性もあります。
そのため、まずは理科や社会などの単元ごとに区切りがある教科の勉強から取り組んでみましょう。そして、復帰した際に学校の授業で進められている単元を予習しておくことがポイントです。
このように予習をしておくと、1つの教科だけでも学校の授業についていけるため、学校の授業についていけないかもしれないという不安が軽減されます。
ほかの教科や予習を行った単元よりも前の範囲は、後から取り戻すことができるので、今の時点では心配する必要はありません。
まずは、少しでも安心して学校に復帰できるように、1つの教科の1つの単元から勉強を再開してみてください。
行動④不登校から復帰した人の経験談を聞く
4つ目は、不登校から復帰した人の経験談を聞くことです。
身近な人に不登校から復帰した経験がある人がいれば、その人の経験談を聞くのもよいですし、そういった人がいなければ、ネットで体験談を読むだけでも構いません。
また、万事順調に不登校復帰ができた経験談よりも、大変なことやつらいこともあったけれど最終的に何とかなったという経験談を知ることが大切です。
このような経験談を知っておくと、「自分でも何とかなりそう」「順調じゃなくても少しずつ復帰すればいいんだ」と思うことができ、気持ちが軽くなるからです。
以下のページでは、不登校を経験したキズキ共育塾の生徒さんの体験談を読むことができます。ぜひご覧ください。
キズキ共育塾「不登校の体験談」
行動⑤復帰することへの怖さや不安に対する心構えをしておく
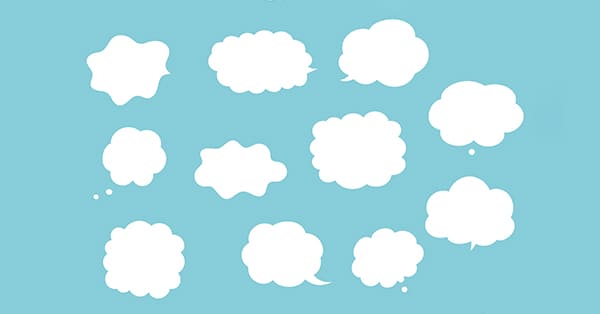
5つ目は、復帰することへの怖さや不安に対する心構えをしておくことです。
学校に復帰することを決めて、復帰までの期間に自分なりの準備をしていたとしても、復帰する日が近づいてくると怖さや不安が出てくることがあります。
この感情は当然のことであって、怖さや不安を感じているあなたが弱いということでも、ダメということでもありません。しかし、怖さや不安から復帰をあきらめてしまう可能性があることも事実です。
そのため、「復帰が近づいてくると不安や怖さが強くなってくるだろうな」と自分なりに心構えをしておきましょう。こうした心構えをしておくと、実際に怖さや不安が出てきたとしても、ネガティブな気持ちに飲み込まれづらくなります。
また、復帰が怖くなった時の対応策を考えておくことも大切です。たとえば、以下のような対応策が考えられます。
- 不安や怖さがあっても制服には着替えるようにしよう
- 学校に入らなくてもいいから門の前まで行ってみよう
- 教室に入るのは不安だったら職員室か保健室に入ってみよう
復帰しようと決めていた初日から、必ず登校時間に教室に行かなければならないということはありません。予定通りにいかなくても大丈夫です。
少しずつ自分が無理のない範囲でハードルを越えていくことで、少しずつ怖さや不安が減り、学校復帰につながっていきます。
行動⑥弱音を言える相手を見つけておく
6つ目は、弱音を言える相手を見つけておくことです。
いざ学校に復帰できたとしても、上手く行かないことやつらいと感じることがあり、学校がイヤになることもあります。
そんな時につらい気持ちを1人で抱えてしまうと、ネガティブな気持ちや思考が強くなり、学校に通い続けることが難しくなる場合があるのです。
もちろん、無理に学校に行く必要はありません。しかし、学校に行きたい気持ちがあるにもかかわらず、誰にも弱音を言えないことで学校に行けなくなるのは、不本意なことだと思います。
そのため、自分1人でつらい気持ちや不安な気持ちを抱えないようにするために、弱音を言える相手を見つけておきましょう。
弱音を言える相手は、できれば家族以外の人であることがオススメです。家族が一番相談しやすい相手かもしれませんが、家族のほかにも相談できる人がいると、安心感が大きくなります。
弱音を言える相手や相談相手は、家族や学校の先生、スクールカウンセラーなど、周りの大人の力を借りながら、探してみてください。
不登校から復帰した人の体験談
この章では、不登校から復帰したキズキ共育塾の生徒さんの体験談を紹介します。
不登校からの復帰を考える上でのヒントになる情報がたくさんあります。ぜひご覧ください。
体験談①生活習慣を少しずつ改善して、不登校から復帰

A君は中学3年生のときに、キズキ共育塾に入塾しました。
不登校状態が続いており、深夜番組が好きなことも影響して生活リズムが乱れていました。
A君の親御さんは、段階的に規則正しい生活になるよう、毎日協力していました。
- 「学校には行かなくてもいいから、健康に過ごしてほしい」と伝える
- 朝食を一緒に食べる
- 朝食を食べられないときは、冷たい飲み物で目を覚まさせるようにする
- ドライブや買い物、海に行くなど、午前中に外出する用事をつくる
- 深夜番組は録画して午前中に見るようにする
- 夜はスマホを見ないよう約束する
キズキ共育塾への入塾も、勉強のためであることに加えて、生活リズムを整える目的がありました。
A君の親御さんの取り組みは、どれも無理やりではなく、A君の心身の調子を見ながら少しずつ行っていました。
その甲斐あってA君は次第に気力が回復し、学期が変わるタイミングで学校に復帰できました。
復帰してすぐの頃は、登校時間のギリギリに起きてなんとか準備して学校に行く、という状態でした。
しかし、その状態について親御さんは、「ギリギリの登校とはいえ復帰できたので、まずはこれでいいと思っています」と話していました。
次第にA君は余裕を持って登校できるようになり、再び不登校になることはありませんでした。そして、A君は、復帰後もキズキ共育塾への通塾を続け、志望する高校に合格しました。
A君の経験談から、学校復帰・通学継続の秘訣として、以下のことが考えられるでしょう。
- 親御さんが「復帰=いきなり完璧な生活リズム」という状態を求めなかったこと
- 学校復帰や生活リズムの改善などを、段階的にとらえて継続的に取り組んだこと
体験談②趣味で気分転換をして不登校から復帰
Bさんは、中学2年生のときにキズキ共育塾に入塾しました。
学校には行っておらず不登校の状態でしたが、演劇が趣味で、演劇の制作に携われる市民劇団に精力的に参加していました。
演劇について生き生きと話す姿はとても印象的で、親御さんも「市民劇団に友人がいるから、外出や人との交流はできている」と話していました。
つまり、親御さんは子どもが不登校であることに目を向けすぎず、お子さんの趣味を尊重する姿勢だったのです。
Bさんは、市民劇団で公演を成功させるなどの経験をしたことで、自信をつけたようでした。
また、市民劇団では、学校では出会ったことのないタイプの人たちと知り合い、人間関係やコミュニケーションも楽しめていました。
これらの経験が、Bさんにとっての充電期間であり支えになったようで、学年が変わるタイミングで学校に復帰しました。
復帰後も、休日は市民劇団に精力的に参加することによって気分転換ができ、その後も継続して通学することができました。
また、学校復帰後もキズキ共育塾で受験勉強を行い、演劇について学べる高校に合格しました。
Bさんの経験談からは、学校復帰・通学継続の秘訣として、以下のことが考えられるでしょう。
- 親御さんが「不登校であること」に目を向けすぎなかったこと
- 学校以外に、楽しく過ごせる・安心できる居場所があったこと
不登校からの復帰について、キズキ共育塾の講師からのアドバイス
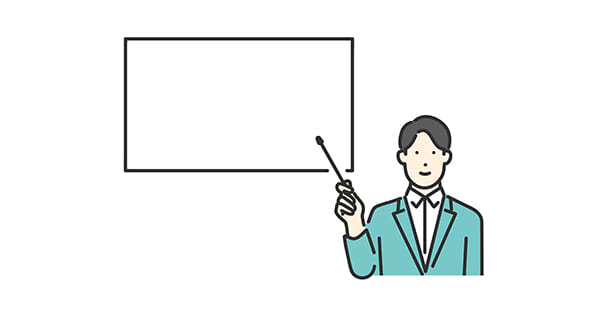
この章では、不登校からの復帰について、キズキ共育塾の講師たちからのアドバイスを紹介します。
実際に不登校の生徒さんと日々接している講師の生の声です。きっと参考になると思います。
カトウアイ講師のアドバイス
私は公立小学校の教員でした。その視点も含めて、不登校から復帰して登校を再開するためのアドバイスをお伝えします。
①朝に起きて夜に寝る生活
学校の授業時間は、午前中が4時間、午後が1~2時間と、午前中の方が多いです。午前中の授業に集中できれば、2/3の授業は集中できたことになります。
また、将来的に受験することになった場合、受験も午前9時から始まることが多いです。受験の時間に集中力のピークを持っていくためにも、午前中に活動できる・集中できる状態にしておくことは、重要だと思います。
②適度な運動
家にいる時間が増えると、どうしても体力が落ちる傾向にあり、復帰後は疲れやすくなります。復帰後に疲れやすくならないためにも、復帰前から適度な運動をしておきましょう。
運動と言っても、いきなり○km走りなさい!ということではありません。最初はコンビニまで歩いて行ってみるだけでもよいと思います。
慣れてきたら、精神面でも運動面でも一番効果的なのは、縄跳びをしてみたり、自分が好きだなと思える運動をしてみたりすることです。また、親御さんがお休みの日などは、親子で一緒に運動すれば、コミュニケーションをとれるよいチャンスになると思います。
以上、主に生活面に関すること2点を挙げました。勉強は後からでもなんとかなります。まずは生活リズムや体調面を整えて、学校に復帰したときの土台を固めるように心がけるとよいと思います。
選択肢を絞らず、いろいろな機関や専門家を利用してほしい
私は、キズキ共育塾の他に、民間のフリースクールでも不登校の小中学生や高校生の学習支援に携わっています。お子さんが不登校になることでパニックになったり1人で抱え込んだりする親御さんは大勢いらっしゃいます。ぜひ、キズキ共育塾やフリースクールなど、専門家を利用してほしいです。
私がフリースクールで関わった、ある小学生の例をお話しします(個人の特定につながらないようにしています)。
その子は発達障害があり、集団生活が苦手だったりこだわりが強かったりする面が見られ、理由は明確ではありませんが、なんとなく学校へ行けなくなったそうです。そして、親御さんに連れてこられるかたちでフリースクールを利用することになりました。
初めての来所時に、その子・親御さん・私で、3人での面談を行いました。ですが、その子は携帯ゲームに熱中していて、私のことは知らんぷりな様子でした。ところが私が「何のゲームしてるの?」と尋ねると、画面を見せながらたくさん話をしてくれました。
その後は、親御さんと一緒に定期的に来所するようになりました。勉強をすることもありましたが、ほとんどはその子がいま何を楽しんでいるかを聞く時間でした。
私自身、「このような関わり方でいいのだろうか」と思ったこともあります。ですが、あるとき親御さんから電話があり、それまで行こうとしなかった適応指導教室へ通うことになったとお聞きしました。本人も嫌がる様子はなく、学校にもまた行くとも話していたそうです。
不登校になる理由はさまざまで、この子のようにはっきりと原因がわからない場合もあります。この子の場合は、自分の好きなものを認めてくれる人と出会えたことで、「もう少しがんばってみよう」という気持ちが芽生えたのかもしれません。
大人には遊んだり逃げたりしているように見える行動も、子どもたちには必要な時間です。親御さんは変わらない現状に不安が募ることでしょう。しかし、決してあせらず選択肢を絞らないで、いろいろな支援機関・専門家を利用してほしいです。
参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校ジャーナリスト・石井しこう、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。
このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。
このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。
公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら
- 【オリジナル書籍プレゼント】学校外で友だちができるBranchコミュニティ(Branch公式LINEが開きます)
私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。
まとめ〜不登校からの復帰は可能です〜

親御さんが適切なサポートを行うことで、お子さんが不登校から学校に復帰することは、十分に可能です。
ただし、必ずしも今の学校への登校再開を、目指さなければならないわけではありません。
どうしても、今の学校・クラスが合わないお子さんもいるのです。
いずれにしても、ご家族だけで考えすぎず、不登校の子どものことを相談できる支援機関などを頼りましょう。
そうすることで、お子さんもご家族も、よりよい、次の一歩に進む方法が見つかると思います。
このコラムが参考になったなら幸いです。
私たちキズキ共育塾の生徒さんには、中学不登校から学校復帰と受験合格を果たした人や、高校不登校から大学進学を果たした人が多くいます。
お子さんのこと、ぜひ私たちにご相談ください。それぞれのお子さんやご家庭の事情に応じて、このコラム以上に具体的なお話ができると思います。
キズキ入塾に関して少しでもご興味があれば、まずはLINEで友だち追加を。キズキのカリキュラムなど塾についての全般を知りたい方は「資料請求」を。お名前、電話番号、メールアドレスだけの入力で、電子パンフレットをすぐにメールアドレスへお送りいたします。
電子パンフレットなら場所を取らないのでとっても気軽。卒業生の声なども載せていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
Q&A よくある質問