学校に行く意味とは? 不登校経験者の視点から解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたは今、「学校に行く意味がわからない…」と悩んでいるのではないでしょうか?
- 親から学校へ行くように言われているけど、学校に行く意味がわからない…
- 学校に行きたくないけど、がんばって登校している
- どうして学校に行かなきゃいけないのだろうか?
このように、学校に行く意味を考えるきっかけは、人それぞれでしょう。
ほかにも、納得できる答えを得られないことで、「学校の先生や親も、学校へ行く意味をわかっていないのでは?」と不信感がつのったことがあるかもしれません。
筆者も、中学生と高校生のときに不登校を経験し、あなたと同じように学校に行く意味を考えたこともあります。
このコラムでは、不登校を経験し、現在は塾講師として生徒に接している筆者の視点から、学校に行く意味や学校に行くことが当たり前ではない理由、学校以外の学びの場について解説します。
結論からお伝えすると、学校に行く意味が分からなければ行かなくても問題ありません。ただし、行かないなりの苦労があることは知っておく必要があります。
あなたの学校に行く意味について悩む気持ちを、少しでも解消できましたら幸いです。
共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの
アドバイス
不登校を通じて、自分の「核」が見つかるかもしれません
「学校へ行く意味は何か」。これは、とても大事な問いです。
あなたが学校に行く意味に悩んでいるのならば、あなたは大人への階段を上っている途中、だということです。この問いを大切にすることで、自分の中で譲れない「核」を見つけられるかもしれません。
自分の核は、自分でつかむものです。学校で教わることでも、親が教えてくれることでも、YoutubeやSNSの情報から得られるものでもありません。
「なぜ自分は、学校に行くことに疑問や違和感を持つのか」という問いへの答えを、「自分はみんなと違うから」と片付けずに、自分なりに考えてみてほしいと思います。
私自身も、不登校の経験を通じて、自分の核を見つけられました。あなたも、もし気づきがありましたら私まで教えてください。
私たちキズキ共育塾は、学校に行く意味がわからない人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
誰にでも当てはまる学校に行く意味があるわけではない

具体的に学校に行く意味を考える前に、まず前提としてお伝えしておきたいことがあります。
それは、誰にでも当てはまる学校に行く意味があるわけではないということです。
これまで、学校に行く意味を真剣に考えてきた人であればあるほど、「誰もが納得できる意味があるはず」と思っているかもしれません。
しかし、学校に行く意味に正解はなく、どんな意味を見出すかは人それぞれです。
つまり、周りが納得しなくても、あなたが納得できる意味を見つけられれば、それがあなたにとっての学校に行く意味になるのです。
また、学校に行く意味を見出せないのであれば、それもあなたにとっての答えであり、悪いことでも悲観することでもありません。
この前提を踏まえた上で、あなたにとっての学校に行く意味を考えていきましょう。
一般的に考えられる学校に行く意味

こちらの章で学校に行く意味は人それぞれだとお伝えしましたが、世間で一般的に考えられている学校に行く意味を知りたい人もいるでしょう。
直接的に学校に行く意味が述べられているわけではありませんが、文部科学省によると、義務教育の目的、つまり学校に行く意味は以下のとおりです。(参考:「義務教育に係る諸制度の在り方について(初等中等教育分科会の審議のまとめ)」)
義務教育の目的については、次の2点を中心にとらえることができるものと考える。
1.国家・社会の形成者として共通に求められる最低限の基盤的な資質の育成
2.国民の教育を受ける権利の最小限の社会的保障
義務教育を通じて,共通の言語,文化,規範意識など,社会を構成する一人一人に不可欠な基礎的な資質を身に付けさせることにより,社会は初めて統合された国民国家として存在し得る。このように,義務教育は国家・社会の要請に基づいて国家・社会の形成者としての国民を育成するという側面を持っている。
また,一方で,義務教育には,憲法の規定する個々の国民の教育を受ける権利を保障する観点から,個人の個性や能力を伸ばし,人格を高めるという側面がある。子どもたちを様々な分野の学習に触れさせることにより,それぞれの可能性を開花させるチャンスを与えることも義務教育の大きな役割の一つであり,義務教育の目的を考える際には,両者のバランスを考慮する必要がある。
少し難しい内容ではありますが、以上の内容をまとめると、学校に行く意味は以下のとおりと考えられるでしょう。
- 大人になって社会に出るときに必要となる、物事の考え方や能力を身に着けるため
- 自分の個性や能力を伸ばしたり、人柄を磨いたりするため
- 自分が得意なことや好きなことを見つけるため
もちろん、これらの学校に行く意味が必ずしも正しかったり、正解であったりするわけではありません。
自分が納得できる学校に行く意味があれば取り入れ、納得できない場合は、これから紹介する学校に行く意味も参考にしてみてください。
学校に行く意味7選
この章では、筆者自身の経験や周囲の人から聞いた話などに基づいて、学校に行く意味について解説します。
ただし、ここで紹介する学校に行く意味は、ほんの一部です。
学校に行く意味が分からず、悩んでいるあなたの考えを整理するために、あくまで参考としてご覧ください。
意味①友だちと会うため

友だちと会うこと、友だちと会うのが楽しいことは、学校に行く意味になります。
学校そのものや授業を受けることに意味を感じられなくても、休み時間に友だちと話すことが楽しいと感じられるため、学校に行くという人は少なくありません。
意味②部活のため
学校に行く意味を部活に見出す人もいます。
「放課後の部活のためなら授業もがんばれる」と考える人もいるでしょう。
「部活で県大会に出場する!」など、部活に関する具体的な目標を持つことで、学校に行く意味を感じられる場合もあるかもしれません。
意味③勉強のため

学校生活はほとんどが授業時間なので、勉強は学校に行く意味の一つになります。
好きな教科があったり、楽しいと思える授業があったりすることで、学校に行く意味を見いだせることもあるかもしれません。
また、面白い授業をする先生がいて、その先生の授業を受けることが学校に行く意味になる場合もあります。
意味④学校生活を経験するため
特定の理由はないものの、学校生活全体が好きで学校に行っている人もいます。
授業を受けて、休み時間は友だちと遊び、部活をして帰る、といった一連の学校生活が楽しいと感じられていれば、それは学校に行く意味となります。
意味⑤進学のため

高校受験や大学受験など、将来進学することを考えて、学校に通っている人もいます。
「一般受験のための勉強をする」「内申点のために部活や生徒会活動などに取り組む」など、学校では進学の準備ができるためです。
意味⑥学校行事のため
体育祭や文化祭などの学校行事は、学校に行っているからこそ経験できることです。
そうした学校行事に参加できることや楽しめることに、学校に行く意味を感じる人もいるでしょう。
意味⑦給食・弁当などお昼ごはんのため

給食や弁当が、学校に行く意味になっている人もいるかもしれません。
私自身も、「今日の授業は憂うつだなあ…」と思う日でも、給食のメニューが好きなものだと「給食のためにがんばろう」と思えていました。
学校に行くことが当たり前ではない2つの理由
そもそも学校に行くことは当たり前ではありません。
学校に行くかどうかは、最終的には自分で選べるのです。
この章では、学校に行くことが当たり前ではない理由について解説します。
理由①学校に行くのは義務ではない

小学校や中学校は義務教育なので、「学校に行くのが義務である」と思っている人は多いでしょう。
しかし、ここで使われている義務とは、子どもが学校に行く義務ではありません。
義務があるのは、子どもではなく親や保護者なのです。
義務教育の義務とは、「親や保護者が、子どもが教育を受けられる環境を整える義務」という意味です。
つまり、子どもには学校に通って教育を受ける権利はありますが、必ず行かなければならない義務があるわけではありません。
理由②学校で学べることは学校以外でも学べる
学校で学べることはたくさんあります。
しかし、学校で学べることは、学校でしか学べないことではなく、学校以外の場所でも学べる場合もあるのです。
例えば、「勉強は学習塾や家庭教師に教わる」「人間関係は習い事教室などで周囲の人から学ぶ」などができます。
学校以外の場所で学ぶ方が向いている人もたくさんいます。
つまり、学校が合わなかったり、より自分らしく学べる場が学校以外に見つかったりすれば、学校以外の場で学んでもよいのです。
実際に、私は学校以外の場で、自分に合った学習方法で勉強したことによって、成績が伸びた人をたくさん見てきました。
学校に行かないことで苦労する可能性がある
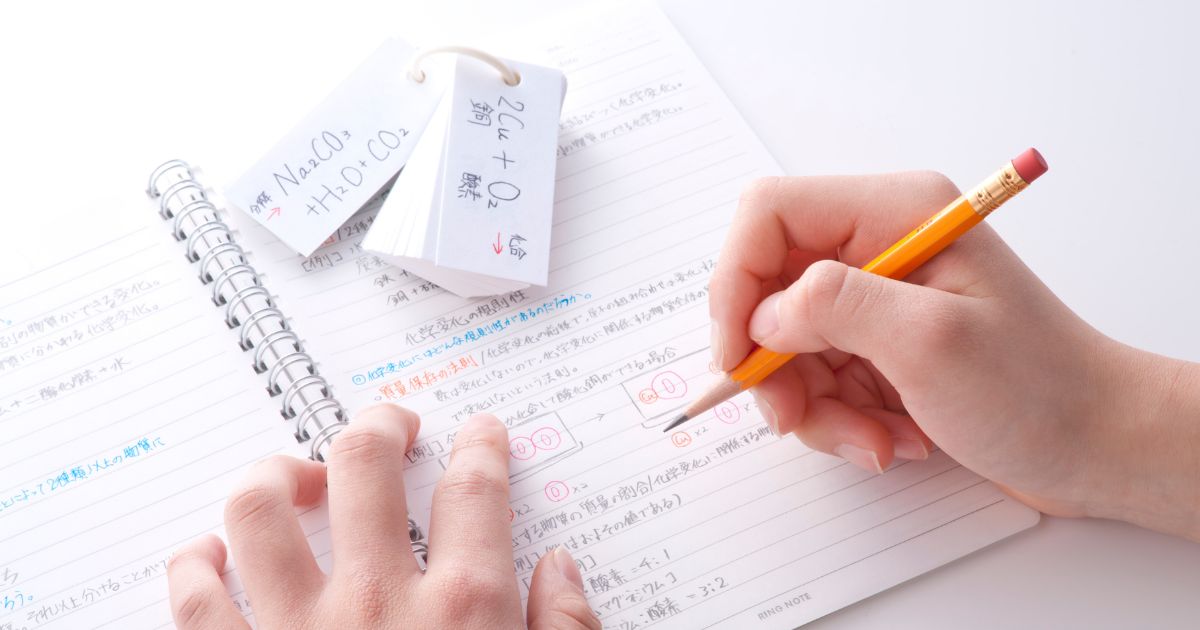
学校に行く意味を見出せず、学校に行かないことを選択をする場合、それなりの苦労があることも事実です。
例えば、学校では授業や宿題などのかたちで勉強の機会が整えられています。
そのため、学校に行っていれば授業レベルの勉強をするための場所や機会を探す必要は、基本的にはありません。
つまり、学校の授業を受けて行くうちに、勉強が自然と身についていくのです。
一方、学校以外の場で勉強をする場合は、受験レベルの高度なものではない、授業レベルの勉強であっても、学習塾や家庭教師、通信教育などの勉強方法を、自分で探す必要があります。
また、中学生の場合は、出席日数が足りないことが内申点に影響し、一部の高校に進学できなくなることもあるかもしれません。
学校が合っている人もいますし、学校以外の場所や勉強方法が合っている人もいます。
どちらがよい・悪いということではありません。
ただし、それぞれによいところ・苦労するところがあることは知っておきましょう。
「学校に行かない=社会に出られない」ではない

学校に行かないことで社会に出られないと、不安に思う人もいるでしょう。
そう思った人は、もしかしたら「学校に行かない=社会に出られない」と思っているかもしれませんね。
筆者も昔はそう思っていました。
筆者が中学1年生で初めて不登校になったときは、「このまま学校にも行けず、社会に出られないのではないか?」と、とても不安で将来が心配でした。
「一度の決断で、これからの人生のすべてが決まったのでは…?」と、当時は激しく後悔したこともありました。
しかし、冒頭で自己紹介したように、現在は塾講師として働いています。つまり、無事社会に出られたのです。ちなみに、大学にも通っています。
学校に行かなくなると、人生が悪い方向に進んで行くような感覚があるかもしれません。
ですが、大学生になるタイミングや社会人になるタイミングから学校に復帰する人もいます。
社会に出ることを目的とする場合、学校以外にもさまざまなルートがあるのです。
例えば、小学校・中学校で学校に行く意味を感じられず、学校に行かない選択をしても、その後、中学校や高校から学校に復帰するケースもあります。
また、高校に行く意味を感じられずに中退しても、高等学校卒業程度認定試験に合格し、専門学校や大学へ進学する人もいるのです。
他には、就職したりアルバイトとして働いたりすることも1つの選択肢です。自分で起業する方法もあります。
学校は、社会に出るための手段として、多くの人が経験するわかりやすいルートです。しかし、学校以外にもさまざまな方法・ルートで、社会に出ることはいくらでも可能です。
学校以外にもさまざまな方法・ルートがあることを知っておくと、少し気持ちが楽になるかもしれません。
学校以外の学びの場5選
学校以外でも学びの場はたくさんあります。
この章では、学校以外の学びの場を紹介します。
学びの場①学習塾

学習塾を利用すると、一人で勉強するよりも効率的に勉強を進められます。
各教科の勉強ができるだけではなく、勉強のペースや進め方を管理してもらえたり、進学の情報も入手できたりするからです。
特に集団塾の場合は、気の合う友だちに出会う機会になるかもしれません。
筆者の場合は、勉強すること以上に、友だちに会うことを目的に塾に行っていたくらいです。
学校を離れることで、友だちと会ったり、人と話したりする機会も少なくなりました。そのため、学習塾を人と会う場所として活用していたのです。
また、「◯月までに◯個の英単語を覚える!」などの目標は、1人では達成しづらいかもしれません。
ですが、学習塾に通っていれば、講師や友だちなどの周囲の目があるので、目標を達成しやすくなります。
目標を立てて達成することで、計画を立てる力・実行する力・継続する力を身につけられます。
インターネットを通じて学習塾を探したり、気になるところがあれば資料請求や体験入塾をしたりして、あなたに合う学習塾を探してみてください。
中には、私たちキズキ共育塾のように、不登校状態の人の支援を目的とした学習塾もあります。
そんな不登校からの受験・進学の実績を持った学習塾へ問い合わせてみるのもオススメです。
学びの場②フリースクール
フリースクールとは、何らかの理由で学校に通っていない人が学校の代わりに通える場所のことです。(参考:文部科学省「フリースクール・不登校に対する取組」)
フリースクールでは、勉強ができたり、友人関係を学べたりします。
定期的に通う場があると、外出する機会にもなり、生活のリズムを整えるのにも役立ちます。
また、フリースクールでは、自分の好きなことを探究できたり、行事で周りの人と協力したりするなど、様々な経験ができるのです。
フリースクールには、それぞれの特徴があります。「通えそうなところに見学に行く」「ひとまず資料を請求する」などをすることで、自分に合った場所が見つかるはずです。
フリースクールは、「渋谷区 フリースクール」などと、住んでいる自治体や近場の自治体の名前と組み合わせて検索すると、候補となるところが見つかると思います
最寄りのフリースクールを探すときは、以下のサイトから調べてください。
学びの場③通信教育・動画授業

通信教育や動画授業には質の高い教材も多く、勉強する上で役立ちます。
学習塾やフリースクールと異なり、自分で勉強の計画を考える必要があり、計画を立てる力や計画を実行し継続する力などが身につきます。
また、動画授業を見ていてわからない部分を、自分で調べることを習慣にすると、自分1人で勉強をする力も養われるでしょう。
以下、独学で利用するのにオススメのサービスをご紹介します。ぜひ活用してください。
独学にオススメのコンテンツ
- ちびむすドリル
株式会社パディンハウスの運営です。
幼児・小学生・中学生向けのプリントが揃っています。 - 漢字検定WEB問題集
漢字検定(漢検)に出題される漢字をサイト上で学べるファンサイトです。
漢検のレベルに合わせて問題が整理されています。 - Try IT(トライイット)
「家庭教師のトライ」でおなじみの株式会社トライグループによる運営です。
中学生・高校生向けの映像授業を無料で視聴できます。 - 【YouTube】Historia Mundi
「ムンディ先生」の愛称で親しまれている高校の社会科教師、山崎圭一先生によるYouTubeチャンネルです。
世界史を中心に、日本史、地理といった大学受験に必要な科目をわかりやすく解説しています。
学びの場④習い事
習い事は、目標に向かってコツコツ進めていく力を養う場になります。
習い事を通じて友だちができることもあります。また、ライバルのような関係の友だちと切磋琢磨する経験もできるかもしれません。
さらに、習い事がきっかけで自信がつくことも少なくありません。進学先や将来の仕事が見つかる人もいます。
個人的に私がオススメする習い事は、体を動かす習い事とプログラミングです。
体を動かす習い事には、野球、サッカー、テニス、バスケ、陸上など、様々なものがあります。
体を動かす習い事をオススメする理由は、学校へ行かないことで、運動の機会が減るからです。
運動不足が続くと、肩こりなどの体調不良につながる可能性があります。
運動をすることで、そのような体調不良を未然に防げたり、基礎体力がついたり、ストレス解消になったりするなど、さまざまな良い効果が得られるのです。
プログラミングもオススメの習い事の1つです。
2020年度から小学校でも学習が始まり、今後必要とされるスキルの1つになります。
プログラミングの魅力は、将来の可能性が広がるだけでなく、何かを作ることの喜びや達成感も味わえることです。
学びの場⑤趣味のコミュニティ

趣味を通じて、さまざまなことを学ぶ機会が得られます。
趣味を探究することで、好きなことを極める能力にもつながるかもしれません。また、趣味のコミュニティで気が合う友だちに出会うこともあるはずです。
趣味が、将来的に仕事につながった人もいます。
筆者は学生時代に、趣味として囲碁をやっていました。
囲碁を通じて、同世代はもちろん、地域の大人やインターネットで出会った人など、色々な人と交流できました。
その当時出会った友だちとは、今でも付き合いがあります。
また、囲碁をがんばることで、周りに認められるという経験ができ、自信にも繋がりました。
親が学校に行く意味を考える子どもと向き合う際の2つのポイント
この章では、親後さんが学校に行く意味がわからず悩むお子さんと向き合う際のポイントについて解説します。
学校に行く意味を聞く子どもがどんな気持ちなのか、子どもに質問されたときにどう答えればいいのか、などを考える際のヒントになるはずです。ぜひご覧ください。
ポイント①子どもが学校に行きたくない可能性を考慮する

お子さんが学校に行く意味を考え悩んでいたり、学校に行く意味を親御さんに聞いたりする場合、お子さんは学校に行きたくないと思っている可能性があります。
そもそも、毎日学校に楽しく通っている子どもであれば、わざわざ学校に行く意味を考えることはなく、学校に行く意味を考えたとしても、「楽しいから」という理由で納得できるでしょう。
つまり、学校に行く意味を考えているお子さんは、学校が楽しくない、学校に行きたくないなどの学校に対するネガティブな気持ちを抱えている可能性が高いのです。
学校に行きたくないと思っているお子さんに対して、「勉強・将来のために学校に通いなさい」などのありふれた意味を伝えたり、学校に行くことを強引に勧めたりしても、お子さんの心には響きません。
そのため、まずは大前提として、お子さんが学校に行く意味がわからず悩んでいたり、学校に行く意味を聞いてきたりした場合は、学校に行きたくない気持ちがあるのかもしれないと考えるようにしましょう。
ポイント②学校に行く意味がわからなければ「わからない」でいい
お子さんから学校に行く意味を聞かれると、親御さんは「子どもが納得できる良い回答や模範的な回答を伝えなければ…!」と思うかもしれません。
しかし、実際のところ親御さんであっても明確な答えが見つからないことはあると思います。そういった時は、「本当のところ、わからないんだ」と本音で答えても問題ありません。
本音で答えたほうが、お子さんに親御さんの誠実な気持ちが伝わります。また、単にわからないというだけではなく、「一緒に考えよう」と言えば子どもとのコミュニケーションのきっかけにもなるでしょう。
逆に、無理に立派な答えを言おうとしたり、親御さん自身も納得していない意味を伝えたりすると、お子さんは「自分を説得するために、嘘をついている」と感じ、不信感を抱くかもしれません。
そのため、学校に行く意味についてお子さんに聞かれた際は、無理に答えようとはせずに、親御さんの本音や正直な気持ちを伝えることを大切にしてください。
キズキ共育塾の講師が考える学校に行く3つの意味
この章では、キズキ共育塾の講師が考える学校に行く意味を紹介します。
こちらで解説したしたポイントを踏まえて、お子さんへの回答として活用してみてください。
学校に行く意味①経験値を稼ぐことができる

1つ目の学校に行く意味は、経験値を稼ぐことができるということです。
学校では、以下のようなさまざまな経験をすることができます。
- さまざまな教科を勉強でき知識を得られる
- 多様な人とのコミュニケーションを学べる
- スポーツや芸術に取り組める
中には、こういったたくさんの経験が一度にできすぎるあまり、学校に行くことに疲れたりしんどくなったりするお子さんもいると思います。また、これらの経験は、学校でなければ経験できないものというわけでもありません。
しかし、1つの場所に通うだけで、これだけたくさんの経験ができる場所は、学校以外にはあまりないでしょう。そういった意味では、さまざまな種類の経験値をお得に稼ぐことができる場所と考えることができるのです。
学校に行く意味②いろいろな経験をつまみ食いできる
2つ目の意味は、いろいろな経験をつまみ食いできるということです。
こちらでも解説したとおり、学校はさまざまな経験ができる場所で、少しずつつまみ食いするように、勉強や部活、人間関係、学校行事などの経験ができます。
こういった経験のつまみ食いを、小学校や中学校、高校でしておくことで、自分の得意不得意や好き嫌いがわかるようになるのです。
とはいえ、学校に通っていれば、苦手な人間関係もやりたくない勉強もつまみ食いではなく、しっかりと取り組まないといけないと考えているお子さんや親御さんもいるでしょう。
しかし、絶対に毎日学校に行かなければならないわけではありませんし、登校したとしてもすべての授業に出ないといけないわけでもありません。
特に、今学校に行きたくないという気持ちが強いお子さんの場合は、出られる授業だけ、週に3日だけ、教室ではなく保健室や別室に登校するなど、さまざまな学校の活用方法があります。
そのため、お子さんが無理なく学校に通いながら、いろいろな経験をつまみ食いできるように、学校の活用方法を模索することも踏まえて、お子さんに学校に行く意味を伝えてみてください。
学校に行く意味③自分自身への理解が深まる

3つ目の意味は、自分自身への理解が深まるということです。
自分自身への理解が深まるというのは、自分の得意・不得意、好きなこと・苦手なこと、向いていること・向いていないことなどが、わかりやすくなるということです。
そして、実際にさまざまなことに取り組み経験をしなければ、自分自身への理解を深めることはできません。
例えば、音楽に興味がありピアノを習ったとしても、思っていたよりも好きになれず、音楽を聴くことが好きだということに気付くこともあるでしょう。また、ピアノが苦手なだけで、ギターであれば楽しめるということもあるかもしれません。
学校では、さまざまな教科の勉強、スポーツ、芸術、人間関係など、ありとあらゆることを経験できます。そして、それらの経験を通して、自分の得意・不得意、好き・嫌い、向き・不向きなどがわかってくるのです。
また、はじめはまったく興味がなかったことでも、学校で取り組んだことによって興味を持つようになり、進路や将来に大きな影響を与えるということもあるでしょう。
まとめ〜学校に行く意味は「人それぞれ」です〜

学校に行く意味は、人それぞれ異なります。中には、どうしても学校に行く意味を感じられない人もいるはずです。
ですが、学校に行く意味を感じられないことは、決して悪いことではありません。
また、これまでお話ししてきたように、学校以外にも学びの場や人間関係を学べる場はたくさんあります。
もし、学校に行くことに意味を感じられない場合は、学校以外の場にも目を向けてみてください。そして、自分が行く意味を感じられる場所を探しましょう。
学校だけにこだわりすぎず、行く意味を見出せる場所を見つけ、自分らしく学んでいくことが大切なのではないかと私は思います。
私たちキズキ共育塾では、学校以外の学びの場として、みなさんの勉強をサポートしています。
無料での相談も可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
Q&A よくある質問









