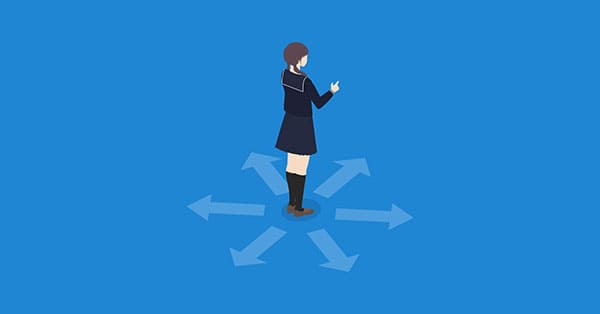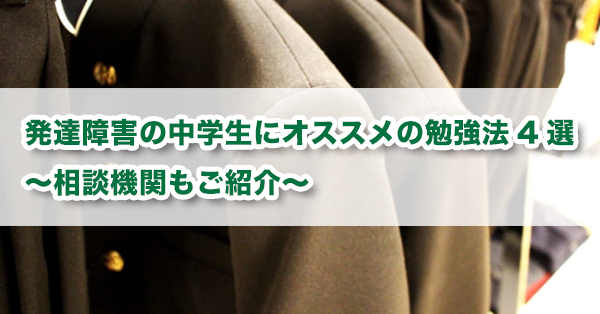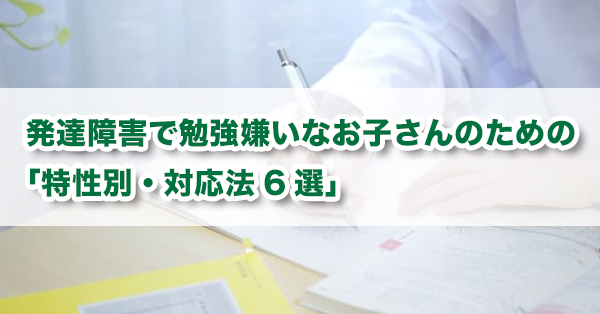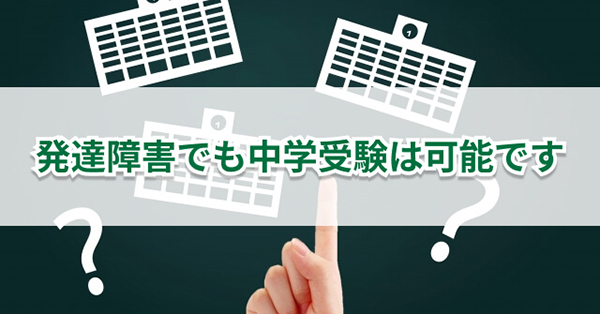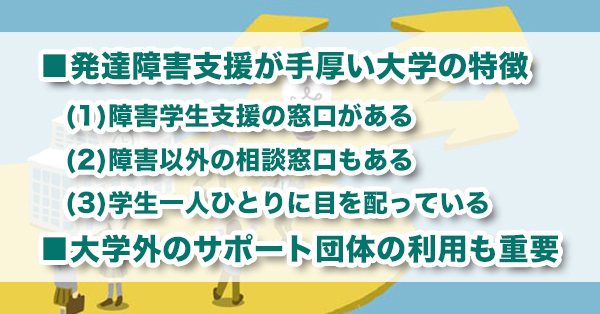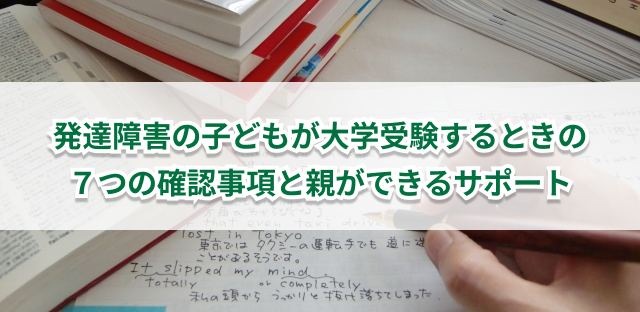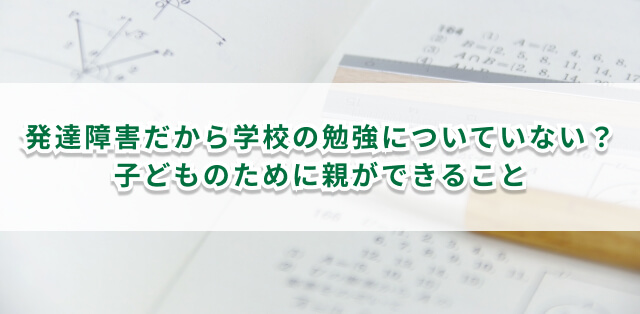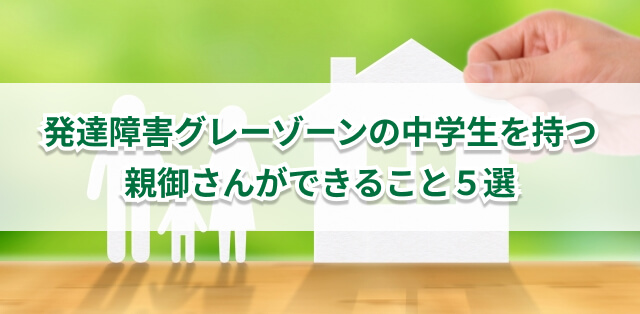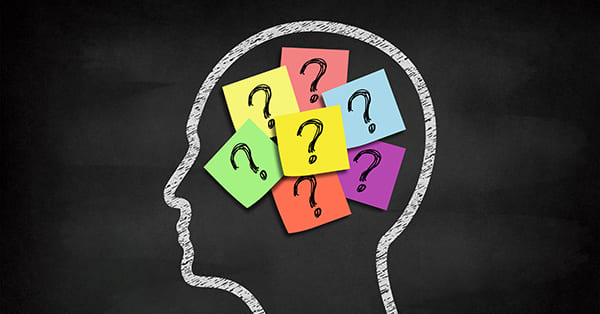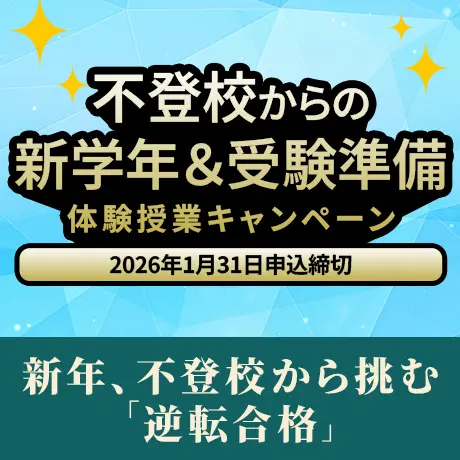発達障害のある小学生の特徴とは? 困りごとや親ができる対応を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートするキズキ共育塾です。
発達障害のある小学生のお子さんがいる方のなかには、特性にまつわる困りごとへの適切な対応がわからずに、悩んでいる方もいるのではないでしょうか?
このコラムでは、発達障害のある小学生が抱えやすい困りごとや、親ができる対応などについて解説します。
発達障害の種類や特徴がわからないという人にもわかりやすく解説しますので、発達障害のあるお子さんをサポートしたい人にも参考になるはずです。
私たちキズキ共育塾は、発達障害のある小学生のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
発達障害とは?
発達障害は、脳の機能面での問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に特性が生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害です。
発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)
近年では、こちらで詳しく解説するように、DCD(発達性協調運動症/発達性協調運動障害)も発達障害の一種として注目されつつあります。
診断名が同じでも、人によってさまざまな特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人が、他の発達障害を併存している可能性もあります。
種類①ADHD

ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害、Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)とは、不注意性や多動性・衝動性の特性から日常生活などに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、田中康雄・監修『大人のAD/HD』、岩波明『大人のADHD─もっとも身近な発達障害』、司馬理英子『ササッとわかる 「大人のADHD」 基礎知識と対処法』、星野仁彦『それって、大人のADHDかもしれません』、e-ヘルスネット「ADHD(注意欠如・多動症)の診断と治療」)
ADHDの特性は、大きく以下の2つの特性に分けられます。
- 不注意性:忘れ物やケアレスミスが多い、注意散漫、整理整頓・管理が不得意
- 多動性・衝動性:落ち着きがない、気が散りやすい、後先考えず行動する
ADHDのある人だからといって、すべての特性が生じるというわけではありません。いずれか1つの特性、または複数の特性から困難が生じている人もいます。
ADHDのある人は、必ず不注意性や多動性・衝動性が現れるというわけではなく、人によって特性の現れ方や、得意なこと・不得意なことが異なる点が大きな特徴です。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)とは? 特性や診断基準を解説」
種類②ASD
ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害、Autism Spectrum Disorder)とは、人とのコミュニケーションなどに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、e-ヘルスネット「ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」、CDC「Autism Spectrum Disorder (ASD) 」、厚生労働省「No.1 職域で問題となる大人の自閉症スペクトラム障害」、福西勇夫、福西朱音『マンガでわかるアスペルガー症候群の人とのコミュニケーションガイド』)
かつて使用されていた以下の診断名・分類は、ASDという診断名・分類に統合されています。
- アスペルガー症候群
- 自閉症
- 高機能自閉症
- 広汎性発達障害(PDD)
それぞれ異なる発達障害として、診断基準も異なっていましたが、2013年に行われた『DSM-5』の改訂の際に、厳密に区分するのではなく、地続きの=スペクトラムな障害として捉える、現在のASDに統合されました。
ただし、変更前の診断名・分類が、法令や病院、日常会話などで現在も使用されることはあります。また、かつてアスペルガー症候群などと診断された人が、現在のASDという名称を認知していないこともあります。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)とは? 特性や診断基準を解説」
種類③LD/SLD

LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害、Learning Disorder/Specific Learning Disorder)とは、読む・書く・計算する・推論するなど、特定の学習行為のみに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』、厚生労働省「学習障害(限局性学習症)」、小池敏英・監修『LDの子の読み書き支援がわかる本』、バーバラ・エシャム・文、マイク&カール・ゴードン・絵、品川裕香・訳『算数の天才なのに計算ができない男の子のはなし 算数障害を知ってますか?』)
LD/SLDは症状別に、以下の3つの種類に分類されます。
- 読字障害(ディスレクシア)
- 書字表出障害(ディスグラフィア)
- 算数障害(ディスカリキュリア)
LD/SLDのある人に、全ての学習行為に困難が生じるというわけではありません。
いずれか1つの学習行為、または複数の学習行為に困難が生じている人もいます。読むことと書くことが不得意、計算することのみが不得意などのように、人それぞれです。
また、いずれの学習行為においても、人によって得意なこと、不得意なことは異なってきます。
例えば、読字障害のある人のなかでも、音読はできてもその内容を理解することが難しいという人もいれば、スムーズな音読が不得意な人もいます。
このように、LD/SLDのある人は、学習する事柄が全般的に不得意というわけではなく、ごく一部の事柄に困難が生じるという点が大きな特徴です。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)とは? 特性や診断基準を解説」
種類④DCD
DCD(発達性協調運動症/発達性協調運動障害)とは、大きな病気やケガがないにもかかわらず、手先の不器用さや運動能力の低さから、日常生活などに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:厚生労働省「DCD支援マニュアル」、岡田俊「発達障害のある子と家族によりそう安心サポートBOOK 小学生編」
DCDの特性は大きく、以下の2つに分けられます。
- 手先の不器用さ:ボタンの留めはずし、チャックの開閉、鉛筆やはさみの使用などが不得意
- 全身運動が苦手:自転車の運転、なわとび、ダンスや球技といった協調運動が苦手
DCDの特性の現れ方は人それぞれですが、原因はいずれも自分の身体感覚をうまくつかめないことにあるとされています。
つまり、一種の脳機能障害により、体の動きをイメージした動作に合わせることが難しいのです。
そのため、一見すると単に運動が苦手なだけと思われがちです。ですが、慣れや努力による改善は難しいため、特性への無理解から体育の授業などで反復練習を課され悩むお子さんも少なくありません。
場合によっては、不登校やひきこもりなどの二次的な心理・社会的問題につながる可能性もあります。
そのため、小学校などの学童期や幼児期での早期発見が望まれます。
なお、ASDと併存することが多いのもDCDの特徴です。また、DCDの特性により文房具をうまく使えないことで、LD/SLDの特性が強まっていることもあります。
補足①:発達障害のグレーゾーンとは?
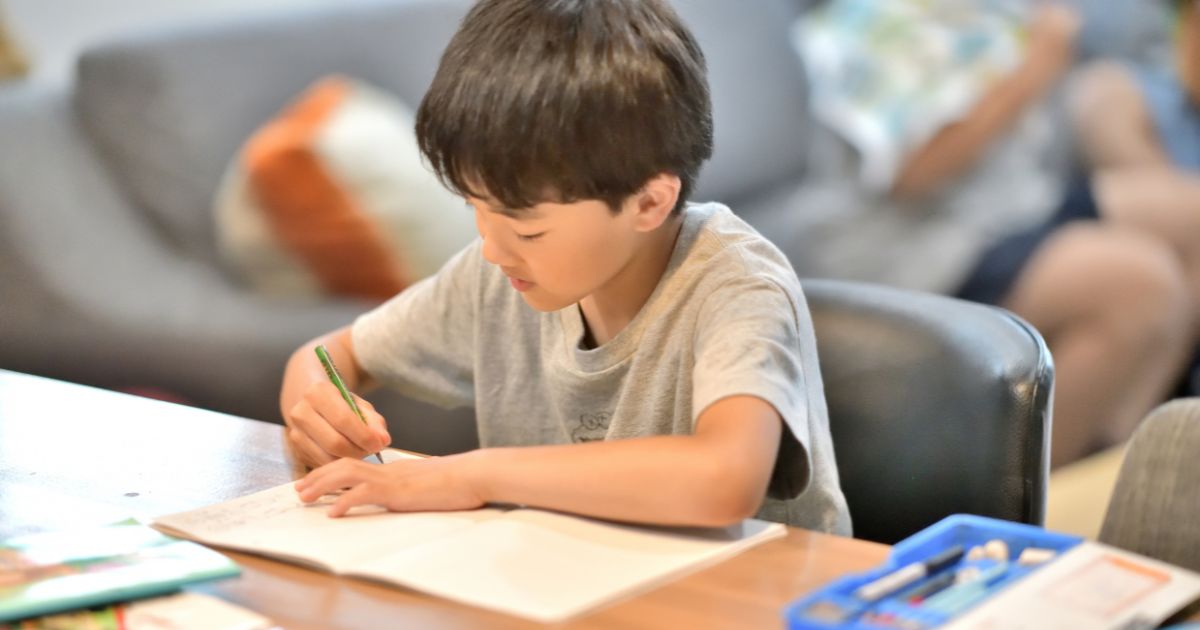
発達障害グレーゾーンとは、発達障害と同様の特性や傾向がいくつか認められるものの、診断基準を満たすほどではないため、発達障害と診断されるには至らない状態のことです。(参考:姫野桂『発達障害グレーゾーン』)
発達障害グレーゾーンという言葉は、医学的に正式な診断名称ではありません。
複数ある発達障害の診断基準の一部を満たしていないために、発達障害の確定診断をつけることができない状態のことを、発達障害グレーゾーンと表現しています。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「発達障害グレーゾーンとは?特徴は? 仕事上の困難を解説」
補足②:二次障害とは?
二次障害とは、主障害に起因して起こる副次的な障害のことです。ここで取り上げている発達障害の二次障害とは、発達障害や発達障害グレーゾーンの傾向・特性に伴って発生する、精神障害やひきこもりなどの二次的な困難や問題のことを指します。(参考:齊藤万比古『発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート』、小栗正幸『発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ』)
発達障害の二次障害は、うつ病といった精神面に現れることもあれば、暴力などの行動面で現れることもあります。発達障害に関連して起こる二次的な問題を総称して、二次障害と呼んでいます。
発達障害や発達障害グレーゾーンの傾向・特性が原因で発生する、以下のような困難や問題は、発達障害の二次障害に該当します。
- 周囲とのコミュニケーションが上手く取れずに適応障害になる
- うつ病や不安障害などの精神障害を発症する
- ひきこもり状態になる
なお、発達障害があるからといって、必ず二次障害が発生するわけではありません。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「発達障害の二次障害とは? 抱える悩みや予防策、対処法を解説」
男女で傾向が異なる小学生の発達障害の特徴

発達障害の種類によっては、診断数や特徴に男女差があることが報告されています。(参考:厚生労働省「発達障害児の親に必要な育児支援の男女差について― ペアレントトレーニングの自発的受講者の分析を通して ― 」、国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター「かかりつけ医等発達障害対応力向上研修テキスト」)
特にADHDとASDには、それぞれ以下のような違いが見られます。
- ADHDの男女差:一般的に男の子が多く、男女比は4:1とされている
※軽症例を含めた調査では、男女比が1:1に近づくという結果もあり - ASDの男女差:一般的に男の子が多く、男女比は3:1とされている
ただし、これは必ずしも発達障害のある男の子の方が女の子より多いということを意味しているわけではありません。
日本小児臨床研究会の調査によると、女の子は幼少期の行動特性が軽微な場合が多いため、ADHDに気づかれにくく、診断が男の子よりも遅れる傾向があります。
同様に、ASDについても、女の子は症状が目立ちにくく、周囲に適応しようと努力するため、発達特性が見過ごされやすい傾向があります。
このように、まだ診断がなされていないだけで、ADHDやASDの困難を抱えている女の子が多数いる可能性もあるということです。
ADHD、ASDともに、学童期に学校生活での困難が顕在化してから診断されるケースが多いと言われています。
表面的には問題がないように見えても、内面では強いストレスを抱えていることがあるので、性別にかかわらず、お子さんの小さなサインに気がつくことが大切です。
発達障害のある小学生の特徴〜種類別に解説〜
お子さんに発達障害の傾向が見られるものの、診断を受けるべきか迷っている人もいるでしょう。発達障害のあるお子さんの特徴を知っておくと、参考になるかもしれません。
この章では、発達障害のある小学生の特徴について、種類別に解説します。
ADHDのある小学生の特徴

ADHDのある小学生の特性には、注意散漫や忘れ物の多さ、計画の苦手さが挙げられますが、一方で発想力や好奇心の強さなどの長所もあります。
ADHDのある小学生に見られる特徴は、以下のとおりです。
- 忘れ物や失くし物が多い
- 気が散りやすい
- じっとしていられず落ち着きがない
- ケアレスミスが多い
- 確認作業が苦手
- 整理整頓が苦手
- 片づけができない
- 人の話を聞いていない
- 直接話しかけられても、話を聞いているように見えない
- マルチタスクやスケジュール管理が苦手
- 時間の経過を正確に把握できない
- 時間の見積もりが甘い
- 未来の予定を具体的にイメージできない
- 時間に対する焦燥感を感じにくい
- 思いついたままに発言し、行動する
- 他人の会話をさえぎったり、割り込んだりする
- おしゃべりが止まらず、人が口を挟む隙を与えない
- 我慢をすることが苦手
- 順番を待つのが苦手
- 衝動買いをすることがある
- 金銭管理が苦手
- 指示を最後までやり遂げず、仕事を終えられない
- 課題や仕事を計画的に進めることが困難である
- 特定のものごとに極端に熱中する
ADHDの特性は個人ごとに異なります。特性は、必ずしも困難さにつながるとは限らず、強みになる場合もあります。
ADHDの小学生の特性や対応については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ASDのある小学生の特徴
ASDのある小学生には、コミュニケーションや社会的な関わり、こだわりの強さなどの特徴が見られます。
ASDのある小学生に見られる特徴は、以下のとおりです。
- 相手の身振りや表情の意味、意見・気持ち、発言の意図・意図などを察しづらい
- コミュニケーションの齟齬が生じやすい
- 会話による意思疎通をうまくできない、会話がかみ合わない
- 「空気が読めない」と言われる
- 一方的なコミュニケーションになりやすい
- 場の状況や上下関係に無頓着
- 他人の発言をそのまま繰り返す
- 人と目線が合いにくい
- 名前を呼ばれても反応しない
- 人に関心がない
- 自分の考えと別の可能性を想定しづらい
- 相手の立場に立って考えることが苦手
- 比喩や冗談を理解しづらい
- 交友関係を広げるのが苦手
- 臨機応変な対応が苦手
- 自分だけのルールにこだわる
- 特定領域の記憶力が優れている
- こだわりが強い
- 興味関心の範囲が狭い
- 好きなことには精通している
- 一つのことに集中しすぎる
- 興味関心のない領域に関する知識が著しくない
- 予定が急変するとパニックになる
以上の特性が、すべてのASDのある小学生に当てはまるわけではなく、個人差が大きい点には注意してください。
ASDの小学生の特性や対応については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
LD/SLDのある小学生の特徴
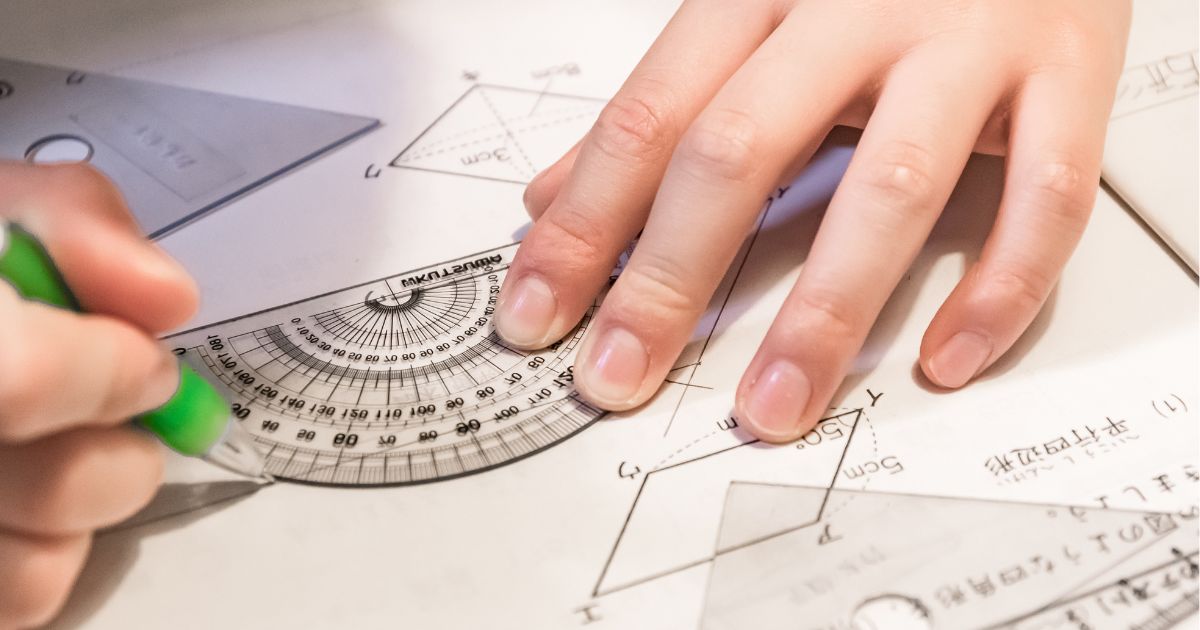
LD/SLDのある小学生には、足し算や引き算ができない、教科書の文章をスムーズに読むのが難しい、などの特徴が見られます。
ASDのある小学生に見られる特徴は、以下のとおりです。
- 教科書の音読で読み飛ばしたり、つっかえる頻度が高い
- 「っ」や「きゃ」などの特殊音節が読めない
- カタカナが苦手
- 文字を書くときに左右が反転した鏡文字になる
- 黒板を写しているとどこまで書き写したのか見失う
- ノートのマス目に収まるように書けない
- 「わ」と「れ」などの形が似ている文字を間違えやすい
- 暗算ができない
- 数の表記ミスが多い
- 数をかぞえるのが難しい
- 2桁以上の計算がわからない
- 文章を計算式に置き換えられない
- 長さや多寡の比較をすることが難しい
- 図形・グラフ・表などを使った計算が苦手
- 「この次はどうなる?」という推測ができない
- 文法的に誤った話し方をする
- 聞き間違いが多い
- 指摘しても言葉遣いを間違えたまま話す
これらの特性は、読字障害や書字障害など抱えている症状によって異なり、併存している場合もあります。
LD/SLDのお子さんの特性や対応については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
DCDのある小学生の特徴
DCDのある小学生には、全身運動が苦手、手先を使って道具を操るのが不得意などの特徴が見られます。(参考:岡田俊「発達障害のある子と家族によりそう安心サポートBOOK 小学生編」)
DCDのある小学生に見られる特徴は、以下のとおりです。
- ボタンの留めはずしに時間がかかる
- チャックの開閉がうまくできない
- 鉛筆をうまく握れず、筆圧が弱い
- はさみが上手に使えない
- お絵かきや工作が苦手
- 分度器やコンパスをうまく使えない
- なわとびが不得意
- 自転車に乗れない
- ダンスやマット運動が苦手
- うんていや鉄棒が苦手
- ドッチボールなどの球技が苦手
- すぐに座り込む
- 姿勢が崩れやすい
特性の強さには個人差があり、複数の特性が併存していることもあります。
また、症状があっても、周囲の理解とサポートがあれば学校生活で困ることはない、という小学生もいます。
発達障害のある小学生が学校生活で抱えやすい15の困りごと

発達障害のある小学生が学校生活で抱えやすい困りごとの例は、以下のとおりです。(参考:井上雅彦「発達障害&グレーゾーンの小学生の育て方」、岡田俊「発達障害のある子と家族によりそう 安心サポートBOOK 小学生編」)
ADHD
- マイペースな言動が目立つ
- 教室移動を忘れたり遅れやすい
- 日直当番や係の仕事を忘れやすい
- 集団生活の決まりごとを守りづらい
ASD
- 授業の内容を理解するのが難しい
- 書くこと・読むことが苦手
- コミュニケーションのすれ違いが起きやすい
- 集団行動が苦手
- 特定の手順やルールへのこだわりが強い
- 予定変更や環境の変化にストレスを感じる
LD/SLD
- 集団授業のペースに慣れない
- 質問や発表がうまくできない
- 掲示物やプリントを読むのに時間がかかる
DCD
- 体育の授業への苦手意識が強い
- 遊びで運動をするときにからかわれる
発達障害のある小学生が勉強面で抱えやすい12の困りごと
発達障害のある小学生が勉強面で抱えやすい困りごとの例は、以下のとおりです。(参考:井上雅彦「発達障害&グレーゾーンの小学生の育て方」、岡田俊「発達障害のある子と家族によりそう 安心サポートBOOK 小学生編」)
ADHD
- 頭の回転は早いが作業が極端に遅い
- 集中力が持続しない
- 落ち着いて考えればできる問題でもミスをする
ASD
- 作文や読書感想文が極端に苦手
- 心情や意図をたずねる質問に答えるのが難しい
- たとえ話を用いた説明が理解しづらい
LD/SLD
- 教科書の文章をスムーズに音読できない
- 黒板の文字を書き写すのが難しい
- 足し算や引き算ができない
- 文章問題がわからない
DCD
- 筆圧が弱くてノートを取るのが苦手
- コンパスや分度器を使う勉強が苦手
発達障害のある小学生が日常生活で抱えやすい13の困りごと

発達障害のある小学生が日常生活で抱えやすい困りごとの例は、以下のとおりです。(参考:井上雅彦「発達障害&グレーゾーンの小学生の育て方」、岡田俊「発達障害のある子と家族によりそう 安心サポートBOOK 小学生編」)
ADHD
- じっとしていられない
- 忘れ物が多い
- 順番やルールを守るのが難しい
- 宿題や課題を期限内に提出できない
ASD
- 身の回りのことをスムーズに行うことが苦手
- 感覚が敏感または鈍感
- 睡眠リズムが乱れやすい
- 注意がそれやすい
- 公共の場でのマナーが守りづらい
LD/SLD
- 自分の名前を丁寧に書くのが難しい
- お金の計算がうまくできない
DCD
- ボタンやチャックのある服の着脱に時間がかかる
- 自転車にうまく乗れない
発達障害のある小学生に親ができる8つの対応

発達障害のある小学生に対応する際には、「お子さんに関する悩みを親御さんだけで抱え込まないこと」「特性を理解して適切な対応策を考えること」が大切です。
発達障害のある小学生に親ができる対応として、以下が挙げられます。
- 学校の先生やスクールカウンセラーに相談する
- 発達障害に詳しい医師や支援機関に相談する
- お子さんの特性を理解して受け入れる
- 適度に休ませる
- 長所や得意なところをほめる
- 進路や進学先の準備を早めに進める
- 親の会に参加して、発達障害の理解を深める
- ペアレントトレーニングを受ける
学校関係者や適切な支援機関を頼りながら、発達障害の理解を深めていくことで、より良いサポートができます。
発達障害のある小学生の親ができる対応の詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害のある小学生のお子さんと親が利用できる支援機関
発達障害のある小学生のお子さんがいる親が利用できる主な支援機関は、以下のとおりです。
- 発達障害者支援センター
- 教育センター
- 精神保健福祉センター
- 保健所、保健センター など
発達障害の確定診断を受けていなくても、相談できる支援機関もあります。まずは、お近くの支援機関に問い合わせてみてください。
学習面の悩みについては、発達障害に理解がある学習塾や家庭教師や、発達障害のあるお子さんの指導実績がある学習塾や家庭教師に相談するのもオススメです。
個別指導の塾なら、より手厚いサポートを受けられます。特性やこだわりについて理解してもらいながら、お子さんの進路相談に乗ってもらえるでしょう。
キズキ共育塾でも、発達障害のある小学生の指導を行っています。興味のある方は、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
小学生の発達障害に関するよくある3つの質問
この章では、小学生の発達障害に関するよくある質問について解説します。
Q1.発達障害の診断・検査について教えてください

発達障害の診断は、医師による問診や心理士が実施する心理検査を中心に行われます。
発達診断の診断は、医師だけが可能です。
なお、小学生の発達障害の検査では、WISCという知能検査が行われるのが一般的です。
WISC(ウェクスラー式児童知能検査)とは、全般的なIQを測ったうえで、包括的に知的能力を測ることができる児童向けの知能検査のことです。精神科病院やクリニック、児童思春期科などにて、医師や臨床心理士によって行われます。(参考:日本文化科学社「WISC™-V知能検査」
具体的には、特定の認知領域の知的機能である以下の5つの項目と全般的な知能を表す全検査IQ(FSIQ)について検査します。
- 言語理解(VCI):言語的な情報や、自分自身が持つ言語的な知識を状況に合わせて応用する能力
- 視空間認知(VSI):空間における視覚情報を処理して解釈する能力
- 流動性推理(FRI):抽象的な思考や新しい問題の解決など、さまざまな文脈での論理的に推論する能力
- ワーキングメモリー(WMI):情報を記憶に一時的にとどめ、その情報を操作する能力
- 処理速度(PSI):単純な視覚情報を素早く正確に、順序良く処理する、あるいは識別する能力
WISCの受診を希望する場合は、お近くの精神科病院や心療内科のクリニックに確認してみてください。
Q2.発達障害のある小学生の親が注意すべきポイントは?
発達障害のある小学生の親が見落としがちなのが、ご自身のケアです。
親は大なり小なり育児に関するストレスを抱えるものですが、なかでも発達障害のあるお子さんの育児には、特性ゆえの育てにくさが伴うのでストレスを感じやすいでしょう。
そのため、ときには自分のためだけの時間を作ったり、家族や親戚に協力を求めて負担が集中しないようにすることも大切になります。
お子さんの成長を見守るためにも、親御さん自身が気持ちに余裕を持てるよう、工夫してみてください。
Q3.発達障害がある小学生の学級選択や進路について知りたいです

発達障害がある小学生の場合、学級・進路の候補として、以下が選択肢に入ってきます。(参考:文部科学省「特別支援教育」、文部科学省「特別支援学級及び通級指導に関する規定」
- 通常学級:大人数でクラスが編成される、スタンダードな学級
- 特別支援学級:障害のある子ひとりひとりに応じて適切な教育を行うために編成された、少人数(上限定員8人)の学級
- 特別支援学校:幼稚部・小学部・中学部・高等学部があり、心身に障害のある児童・生徒専門に教育指導を行っている学校
上に挙げた学級・進路は、それぞれ一長一短があります。
進路を選択する際には、学校の先生やスクールカウンセラー、医師や支援機関などと相談しながら、お子さんに合ったものを選びましょう。
また、通常学級に通うお子さんがいる親御さんのなかには、担任の先生から通級指導教室(通称:通級)を勧められた人もいるかもしれません。
通級指導教室とは、障害のある本人が通常の授業のほかに一部の授業を別の教室で受ける制度のことです。
勉強とは別に、障害に応じた特別指導を受けられる通級を組み合わせることで、大きな困難を感じることなく進級・卒業できる場合もあるでしょう。
発達障害のお子さんの進路については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害のある小学生の通塾体験談2選~キズキ共育塾の事例~
この章では、発達障害のある小学生のお子さんへの対応として、私たちキズキ共育塾を選ばれた親御さんの事例・体験談を紹介します。
体験談①ADHDとASDがある小学生の親の体験談
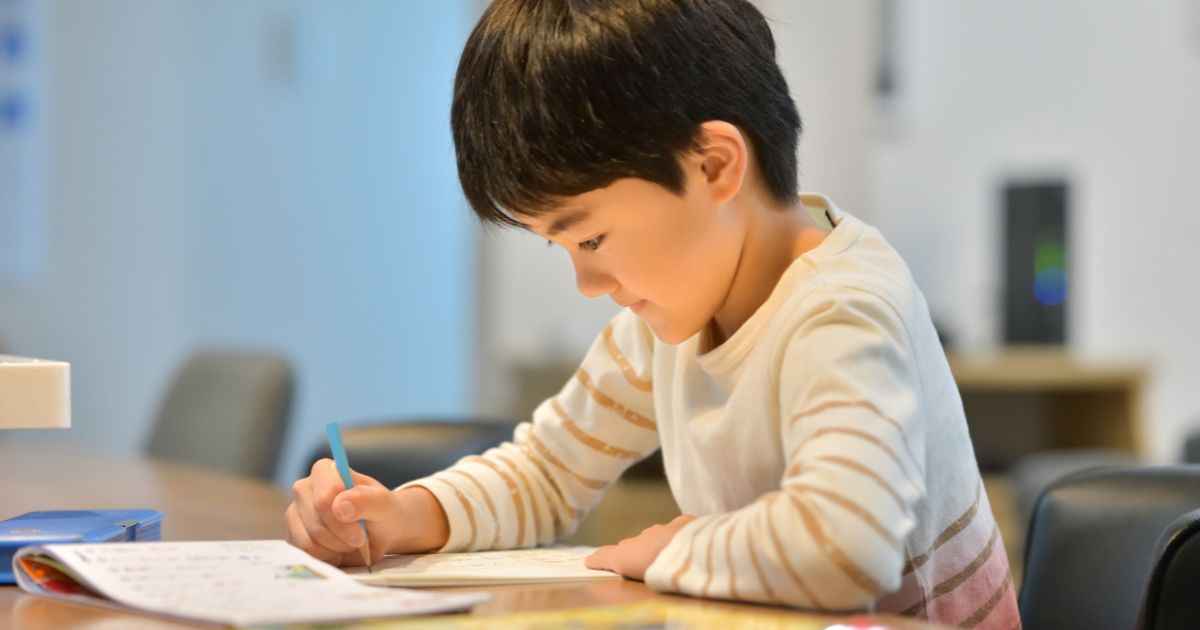
私の子どもにはADHDとASDがあります。
そのため、発達障害への理解があり、特性に合った授業を受けられるキズキ共育塾を選びました。
入塾の際には、本人の特性をふまえて、寄り添った指導をお願いしました。
実際、入塾後は本人に合わせて丁寧な対応を受けられています。
キズキ共育塾に通うようになってから、本人が自分から進んで勉強に取り組むようになり、良い変化を感じています。
体験談②LD/SLDがある小学生の親の体験談
小学生の息子は、2人ともLD/SLDで、2人とも「自分は勉強ができない」という漠然とした不安を常に抱えていました。
彼らに勉強の楽しさを実感してもらうには、年頃の彼らの自尊心を傷つけずに、近い目線からアドバイスや励ましをくれるお兄さん・お姉さんの役割を担ってくれる講師との出会いが必要なのではないかと考え、キズキ共育塾を訪れました。
実際にキズキ共育塾に通ってみると、とことん個人に寄り添ってくれるという印象を受けました。
キズキ共育塾の講師は、どうすれば面白く教えることができるかを常に考えているようでした。
ある講師は、「化学反応を授業中に実際に見せる」「息子が好きなアニメを題材に英語の授業を行う」といった工夫をしていました。
そのおかげか、息子たちは毎回楽しそうな様子で帰宅してきましたね。
キズキ共育塾に通い始めてからは、息子たちは自分から学ぶことに積極的になってくれました。
まとめ~発達障害の特性を適切に理解して小学生のお子さんをサポートしましょう~

発達障害の特性はさまざまで、人によっては、複数の特性が併存していることもあります。
そのため、一般的な知識を踏まえたうえで、お子さんがどのような困りごとを抱えているかを個別に理解することが大切です。
また、小学生の時期は発達や変化が著しいため、発達障害のあるお子さんがいる親御さんは戸惑うことも多いでしょう。
そんなときは、一人で悩みを抱え込まずに、ぜひ周囲の人や専門家を頼ってください。
私たちキズキ共育塾でも、発達障害のある小学生の個別指導を行っています。
気になる方はぜひ、お気軽にご相談ください。