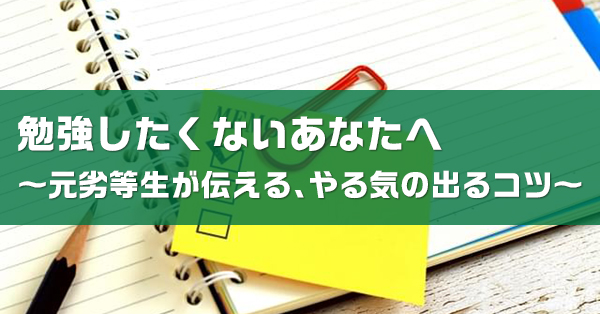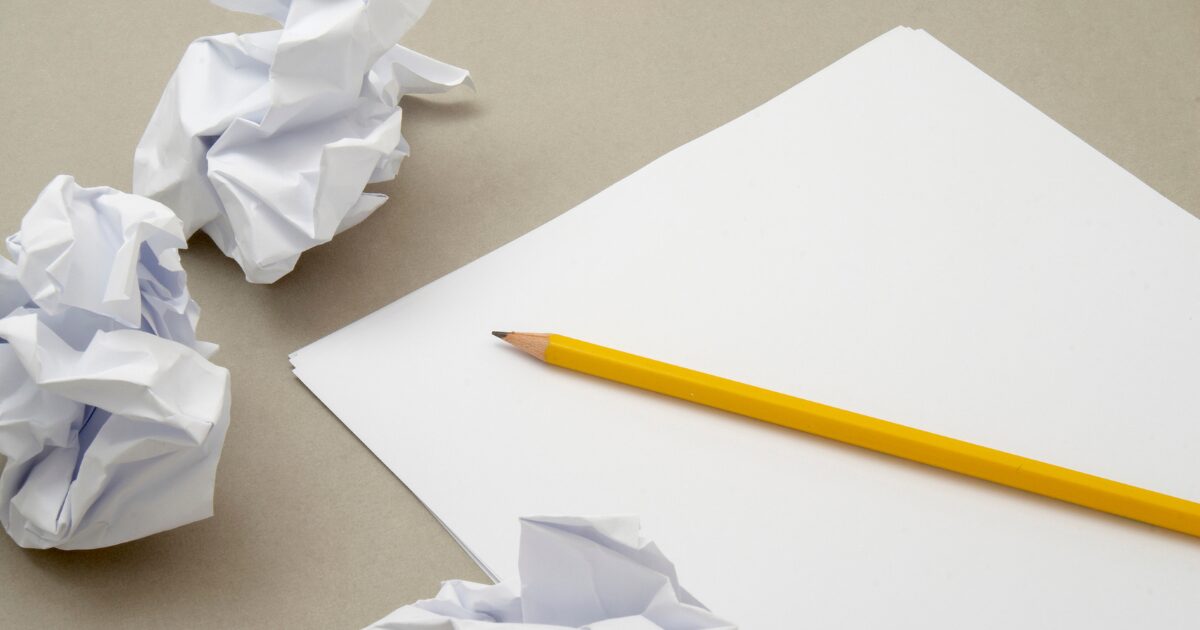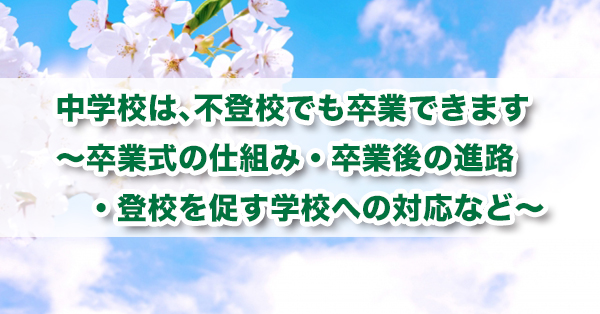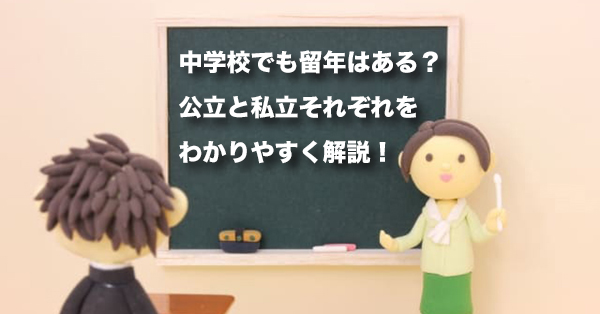ストレスに悩む中学生のあなたへ ストレス解消法を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
このコラムを読んでいる中学生のあなたは、以下のような悩みを抱えていませんか?
- 理由はわからないがイライラする
- 学校に行きたくない・家に帰るのがつらい
また、中学生のお子さんがストレスを抱えていそうだけど原因がわからない、話してもらえないといった親御さんもいるのではないでしょうか?
このコラムでは、中学生のストレスの原因や種類、ストレスによって引き起こされる症状、ストレス解消法などについて解説します。
また、中学生のお子さんがいる親御さんに向けて、ストレスが溜まった中学生に親ができる対応についても解説します。
このコラムが、ストレスで悩むあなたの助けになれば幸いです。
私たちキズキ共育塾は、学校でストレスを感じている人のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
中学生のストレスの原因
そもそも、中学生のストレスの原因にはどのようなものがあるのでしょうか?
この章では、中学生のストレスの原因について解説します。
原因①学校生活や人間関係

中学生は学校生活の多くをクラスメイトや部活動の仲間と過ごすため、学校生活や友人関係がうまくいかないと、大きなストレスを感じやすくなります。(参考:文部科学省「学校における子供の心のケア」-サインを見逃さないために-)
特に、いじめや仲間外れ、無視などの問題に直面すると精神的な負担がさらに増します。
さらに、先生との関係や授業・テストのプレッシャーも影響を与えることがあります。
原因②親子関係・家庭環境
親や家族との関係が良好でない場合、子供は悩みを相談できずに孤独を感じることがあります。
例えば、過度な期待をかけられたり、厳しいルールを強いられたりすると、プレッシャーが積み重なりストレスにつながります。
反対に、家庭内での放任や無関心も中学生にとってはストレスとなることがあります。家庭内の雰囲気が不安定だと、学校生活にも悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。(参考:狐塚貴博「家族構造と青年のストレスに関する臨床心理学的研究―家族バランス仮説の生成とその検討―」)
原因③コンプレックスの自覚

思春期の中学生は容姿や性格、能力などに対するコンプレックスを強く意識する時期でしょう。特に、他人と比較して自分に自信を持てない場合、ストレスを感じやすくなります。
例えば、体型の変化や声変わりなど、思春期特有の成長による変化も自己評価に影響を及ぼし、ストレスの原因となることがあります。
最近ではSNSの普及で良い情報だけでなく悪い情報も入ってきやすくなっており、より優秀な人や自分の欠点を気にする機会が増えているのも問題点です。
原因④進路や将来に対する不安
中学生は、高校進学や将来の職業について考え始める時期でもあります。
成績や学力が進路選択に大きく関わるため、次第に勉強に対するプレッシャーが高まっていくでしょう。
また、親や教師からの期待も重圧となり、自分の将来に対して漠然とした不安を感じる人は少なくありません。将来に対する不安は誰にでもあるもので、適度な緊張感を保つ上で悪いことではありませんが、強いストレスに発展することもあるので注意が必要です。
逆に、将来に対して明確な目標が持てない場合、周囲と比べて焦りを感じることがストレスの原因になるケースもあります。
原因⑤第二次反抗期

思春期の中学生は自主性や自立心が芽生える一方で、親や先生との対立が増える時期です。特に、親の価値観と自分の考えにズレが生じると、強いストレスを感じることがあります。
例えば、自発的にやりたいと考えた勉強やスポーツなどに対して、親や先生に干渉されると自身を否定されているような気持ちになり、強い不満を覚えることがあります。
また、大人の指示に反発したくなる気持ちがあるものの、実際にはまだ経済面や生活面で依存している部分もあり、その葛藤が精神的な負担となります。(参考:齊藤諒・青木真理「思春期における第二反抗期に関する研究―第二反抗期のプロセスと親との葛藤に着目して―」、心理科学第19巻第1号「青年心理学の観点からみた「第二反抗期」)
原因⑥勉強に関する悩み
中学校は小学校に比べて学力の向上を求められる機会が多く、勉強が大きなストレス要因の一つになるケースが多く見られます。
成績が伸び悩んだり、苦手科目が克服できなかったりすると自信を失いやすく、大きなコンプレックスとなってその後の勉強する姿勢にも影響するでしょう。
また、学習塾や家庭学習の負担が増えることで自由な時間が減り、精神的な余裕をなくすこともあります。さらに、テストや受験のプレッシャーが重くのしかかることで、不安や焦りを感じることも少なくありません。
中学生が勉強をしたくない、できない理由については以下のコラムで詳しく解説しているので、ぜひ併せてご覧ください。
中学生が感じやすいストレスの種類
中学生はさまざまなストレスを感じる時期ですが、男女によって感じるストレスに違いがあります。
この章では、中学生が感じやすいストレスの種類について解説します。
ストレス①男子が感じやすいストレス
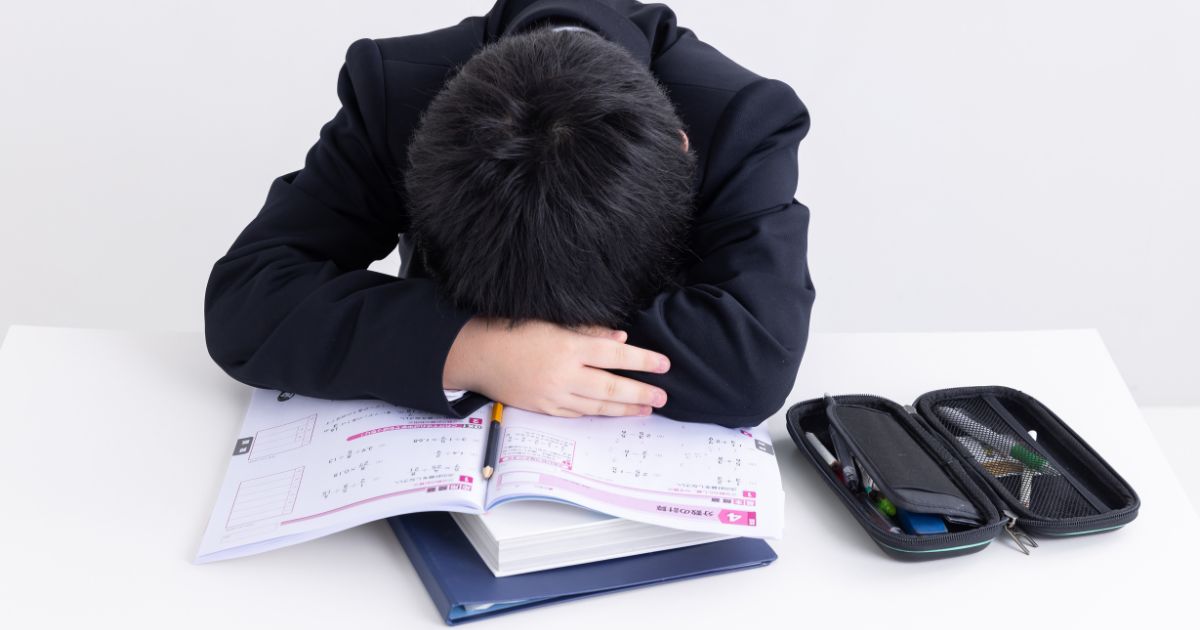
男子中学生は友人関係や部活動・学業での競争、親の期待によるプレッシャーを感じやすい傾向があるとされています。(参考:三浦正江・坂野雄二「中学生における心理的ストレスの継時的変化」)
また、声変わりや体毛の増加など身体の成長に伴う変化に対して戸惑いやコンプレックスを抱くこともあります。
さらに、男性特有の「強くあらねばならない」という価値観により、弱音を吐けずにストレスを溜め込むケースもあると考えられます。
ストレス②女子が感じやすいストレス
女子中学生は友人グループ内での人間関係が複雑になりがちで、それがストレスの主な要因となるとされています。
特に、最近ではグループ内の派閥だけでなくSNS上のやり取りが精神的な負担になっていると考えられます。(参考:三浦正江・坂野雄二「中学生における心理的ストレスの継時的変化」)
また、見た目や体型に対する意識が高まり、理想と現実のギャップに悩むことが増えます。(参考:北海道教育大学教育学部札幌校「児童・生徒の体型認識の歪みとセルフエスティームおよび生活習慣との関連」)
さらに、男子と比較して成績や将来に対する不安を強く感じる傾向があるため、進路についてのストレスも抱えやすいのです。
ストレスが原因で引き起こされる症状
ストレスが原因で引き起こされる症状は多岐にわたります。
この章では、ストレスが原因で引き起こされる症状がどんなものか具体的に解説します。
症状①うつ病

うつ病とは、気分の落ち込みや憂うつ感、さまざまな意欲の低下などの精神的症状と、不眠、食欲の低下、疲労感などの身体的症状が一定期間持続することで、日常生活に大きな支障が生じる精神障害・気分障害のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「1 うつ病とは:」、厚生労働省「うつ病に関してまとめたページ」、、厚生労働省「うつ病」、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「うつ病」、MSDマニュアルプロフェッショナル版「抑うつ症候群」)
また、脳の機能が低下している状態、脳のエネルギーが欠乏した状態を指し、脳の中で神経細胞間のさまざまな情報の伝達を担うセロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンなどの神経伝達物質のバランスの乱れや、感情や意欲を司る脳の働きに何らかの不調が生じているものと考えられています。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「うつ病とは? 症状や治療方法を解説」
症状②適応障害
適応障害とは、仕事や職場の人間関係などから生じる特定可能な明確な心理的・社会的ストレスを原因に、心身がうまく対応できず、情緒面の症状や行動面の症状、身体的症状が現れることで、社会生活が著しく困難になっている状態のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、松﨑博光『新版 マジメすぎて、苦しい人たち:私も、適応障害かもしれない…』e-ヘルスネット「適応障害」)
適応障害は、原因から離れることで、病状はよくなっていきます。職場では調子が悪く、やる気がまったく出ないのに、家に帰ると元気で、趣味に熱中して取り組めるということが往々にしてあります。こうした症状の現れ方から、甘えていると勘違いされやすく、理解されづらいこともあります。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「適応障害とは? 原因や治療方法、うつ病との違いを解説」
症状③強迫性障害

強迫性障害(OCD、Obsessive Compulsive Disorder)とは、不安やこだわりが過度になり、生活に支障が現れる障害のことです。(参考:こころの情報サイト「強迫性障害」)
戸締まりや火の元を何度もしつこく確認しても安心できなかったりする場合は、強迫性障害であることが考えられます。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「強迫性障害のある人に向いてる仕事 仕事を続けるコツを解説」
症状④統合失調症
統合失調症とは、考えや気持ちがまとまらなくなったり、妄想や幻覚が現れたりする慢性的な精神疾患のことです。(参考:American Psychiatric Association『DSM-5』、春日武彦「統合失調症」、松岡広樹『統合失調症の人と働くために知っておきたいこと みんなが幸せになる精神障害者雇用』)
約100人に1人が発症するといわれているほど、誰でもなる可能性があります。統合失調症は若い世代に多く見られており、発症のピークは20代、次いで10代、30代、40代です。
幻覚や妄想、感情表現の鈍化、認知能力の低下などの症状により、社会生活がスムーズに営みづらくなる特徴があります。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「統合失調症のある人に向いてる仕事 仕事を続けるコツを解説」
症状⑤胃潰瘍・十二指腸潰瘍

精神的なストレスは自律神経のバランスを狂わせ、消化管が正常に働かなくなります。軽い症状では腹痛や下痢、便秘などがありますが、悪化すると胃潰瘍・十二指腸潰瘍につながる危険性もあります。(参考:北條麻理子・渡邊純夫「ストレスと消化器疾患」)
胃潰瘍や十二指腸潰瘍とは、胃あるいは十二指腸の壁の粘膜が深く傷つき、みぞおちや背中の痛み、胸焼け、吐血、下血などさまざまな症状を引き起こす病気のことです。
さらに合併症として穿孔や出血が起こることもあるので、一刻も早い治療が必要になります。(参考:慶応大学病院「胃潰瘍と十二指腸潰瘍」)
中学生のストレス解消法12選
ストレスの原因や引き起こされる症状について理解が深まったら、解消法を実践してストレスを緩和しましょう。
この章では、中学生のストレス解消法について解説します。
解消法①友人との時間を楽しむ

友人と過ごすことは、ストレス解消に非常に効果的です。気の合う仲間と会話をしたり、一緒に遊んだりすることで、日々の悩みやプレッシャーを一時的に忘れることができるでしょう。
また、友人との交流を通じて、自分の気持ちを素直に話せる場ができることも重要です。
特に、共通の趣味を持つ友人と一緒に過ごせば、一緒に趣味に没頭することで気分がリフレッシュされるでしょう。
解消法②趣味に没頭する
自分が好きなことに集中する時間を持つことで、ストレスの原因を一時的に忘れて気分転換できます。
例えば、読書やゲーム、絵を描くこと、手芸やプログラミングなど、その時の気分に合わせて一番効果的なものを選ぶと良いでしょう。創作活動は自己表現の手段となり、自信を高めるきっかけにもなります。
大学生を対象としたアンケートでは、趣味は「生きがい」「死なない理由」などと回答している人もおり、趣味がストレス軽減だけでなく日常の活力を生んでいるのだと考えられます。(参考:帝塚山大学心理科学論集「大学生の趣味がストレスに及ぼす影響」)
解消法③適度な運動をする
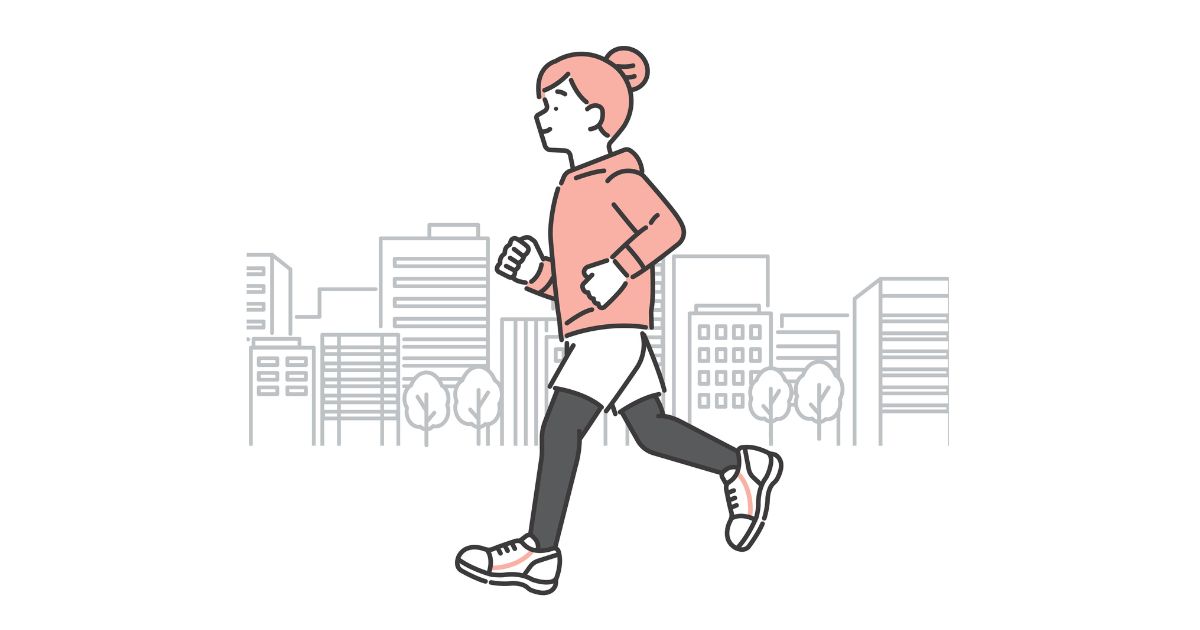
運動はストレス解消に非常に効果的で、ジョギングやウォーキング、ストレッチなどの軽い運動をするだけでも交感神経が優位になり、リラックス効果があります。
運動をすると脳内でセロトニンやエンドルフィンという物質が分泌され、心が安定することがわかっています。
セロトニンは心身をリラックスさせ、不安や意欲低下を防ぐ働きがあるホルモンです。(参考:量子科学技術研究開発機構「セロトニン低下によってやる気が下がる仕組みを明らかに-うつなど疾患の病態理解や治療法開発のための重要な手がかり-」)
一方、エンドルフィンは痛みの緩和やリラックス効果など、気分を良くする効果があります。(参考:国立消化器・内視鏡クリニック「「幸せホルモン(幸福物質)4つ」ドーパミン・セロトニン・オキシトシン・βエンドルフィンとは?」)
部活動や体育の授業以外でも、日常的に体を動かす習慣をつけることで、心身ともに健康を維持しやすくなるでしょう。(参考:運動・身体活動と公衆衛生「運動・身体活動とストレス・メンタルヘルス」)
解消法④質の良い睡眠を取る
睡眠はストレスを軽減するために重要な要素の一つです。睡眠には疲労回復だけでなく自律神経を整えることでストレス解消につながります。
睡眠不足が続くとストレスホルモンであるコルチゾールが過剰に分泌され、免疫力や記憶力の低下リスクが高まるので注意しましょう。(参考:鎌倉市「【新型コロナウイルス関連】『感染予防の基本と免疫力アップ』で健康づくり」)
特に、夜更かしやスマホの使用による睡眠不足はストレスを増幅させる原因となります。寝る前にリラックスする時間を作ったり、決まった時間に寝る習慣をつけたりすることで、質の良い睡眠を確保することが重要です。(参考:佐野真莉奈・北原祐理・河合啓太朗・下山晴彦「睡眠がメンタルヘルスに与える影響に関する研究動向と今後の展望――交替制勤務者に着目して――」)
解消法⑤人と比べずに自分のペースで行動する

周りと比較することは、知らず知らずのうちにストレスの原因になります。
成績や部活、外見など、誰かと比べて自分の弱さや欠点にばかり目がいきがちな人もいるでしょう。しかし、できないことばかりにとらわれていてもストレスが増すばかりです。
それよりも、自分のできることや得意なことに目を向けて、得意なことを伸ばす行動を心がけましょう。そうすることで、ストレスを増やさずポジティブな行動ができ、自己肯定感も上がります。(参考:厚生労働省「こころもメンテしよう 若者のためのメンタルヘルスブック」)
解消法⑥今の気持ちを書いてみる
ストレスを抱えたとき、自分の気持ちを整理することは非常に重要です。そのために有効なのが、今の気持ちを書き出してみることです。(参考:厚生労働省「こころもメンテしよう 若者のためのメンタルヘルスブック」)
例えばノートや日記などといった紙に今感じていることや悩みを書き出すことで、自分の心の中を客観的に見つめ直すことができます。
また、書き出した内容を見直すことで、新しい解決策や選択肢が思いつく可能性が高まります。
書く際は文章や箇条書きなど自分の言葉でわかりやすくまとめるのがおすすめですが、うまく文章にまとめられない場合は落書きやイラストでも問題ありません。頭の中だけで難しく考えず、とにかく手を動かすことを意識しましょう。
解消法⑦腹式呼吸を意識する

ストレスを感じると呼吸が浅くなり、汗をかいたり心臓がドキドキしたりといった症状が表れます。そんなときにおすすめなのが腹式呼吸です。(参考:厚生労働省「腹式呼吸をくりかえす」)
腹式呼吸は息を深く吸い込み、お腹を膨らませながらゆっくりと吐き出す呼吸法です。立った状態や座った状態でお腹に手を当てて、3秒ずつ数えながら吸ったり吐いたりを繰り返しましょう。
腹式呼吸をすることで副交感神経が優位になり、リラックス効果が得られます。緊張や不安を感じたときに深呼吸を意識するだけでも気持ちが落ち着くので、日常的に取り入れるのがおすすめです。
解消法⑧音楽を聴いたり歌を歌ったりする
音楽にはリラックス効果があるため、自分の好きな音楽を聞いたり歌ったりすることで、気持ちが明るくなり、心が軽くなることがあります。(参考:厚生労働省「音楽を聞いたり、歌を歌う」)
例えばアップテンポな曲は活力を沸かせ、スローなクラシックは不安を和らげて気持ちを落ち着かせる効果があります。
また、音楽は聴くだけでなく歌うこと自体もストレス解消に効果的です。大きな声を出すことで気分がスッキリすることがあるでしょう。
解消法⑨泣いてスッキリする

感情を押し殺しているとストレスが蓄積し、精神的に不安定になりやすくなります。そんなときはあえて涙を流すことで気持ちをスッキリさせることが可能です。(参考:山口県立大学看護栄養学部「情動性の涙のストレス緩和作用に関する研究」)
例えば悲しい映画を観たり、感動する本を読んだりして涙を流すことで、心が洗われるような気持ちになるでしょう。
また、涙にはストレスホルモンを減少させる働きがあるため、泣いた後には心が軽くなったと感じることが多いでしょう。
解消法⑩悩みを抱え込まず人に相談する
ストレスの多くは考えすぎることから生まれます。また、悩みを抱え込んでいるといつまでも解決しないままストレスが蓄積し、心身に悪影響を及ぼす危険性があります。
心身への影響を予防・解決するにはひとりで悩みを抱え込まず、信頼できる人に相談することが大切です。誰かに話すだけでも心が軽くなり、解決への糸口が見つかるでしょう。
親や先生に話すことで具体的なアドバイスをもらえるだけでなく、自分の気持ちを整理するきっかけにもなります。
特に、学校生活や進路について悩んでいる場合は、先生に相談することで適切なサポートを受けられることがあります。
親には日常生活での悩みを話すことで、共感してもらったり解決のサポートをしてもらったりできます。
また、専門の医療機関や公的機関の窓口に相談すると、心の悩みに詳しい専門家からのアドバイスが受けられるのでより効果的です。
専門の医療機関には、以下のようなものがあります。(参考:文部科学省「「学校における子供の心のケア」-サインを見逃さないために-」、厚生労働省「こころもメンテしよう 若者のためのメンタルヘルスブック」)
- 精神科、精神神経科
- 心療内科
- 小児科
- 神経内科
公的機関の主な相談窓口は以下のとおりです。
- 保健所、保健センター
- 精神保健福祉センター
- 児童相談所、児童相談センター、児童家庭支援センター
- 教育センター
- ひきこもり地域支援センター
- こころの健康相談統一ダイヤル
解消法⑪わかるところから勉強し直す
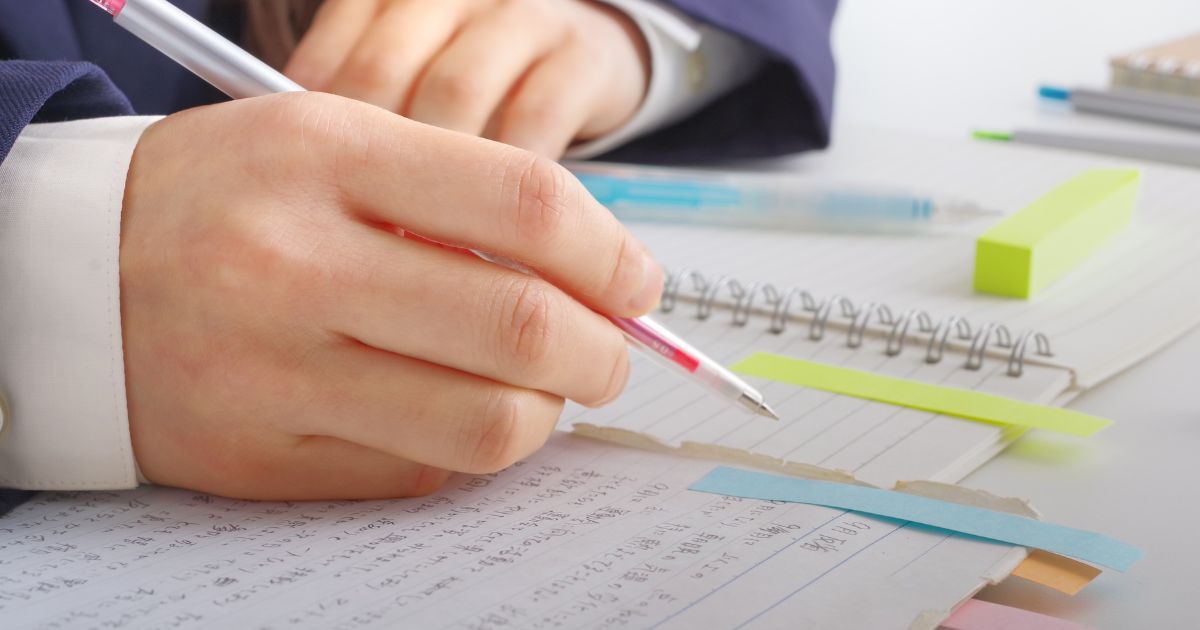
勉強が原因でストレスを感じる中学生は多くいますが、学習方法を変えることでストレスを軽減できることがあります。
例えば、分からない部分をそのままにせず、一から基礎を学び直すことで理解が深まり、勉強が楽しくなることがあります。
学校や自宅で学び直すのが難しい場合は、個別指導塾や家庭教師を利用して自分に合ったレベルから勉強しましょう。
キズキ共育塾では勉強に関するお悩みの相談をいつでも受けつけております。ぜひご相談ください。
解消法⑫自分に合った勉強法を見つける
勉強方法があっていないと効率が悪くなり、ストレスが増える原因になります。自分に合った学習スタイルを見つけることで、ストレスを軽減しましょう。
例えば、視覚的に覚えやすい人はカラフルなノートを作ったり、音声で学ぶのが得意な人はリスニング学習を取り入れたりすると効果的です。
また、友達と一緒に勉強することでモチベーションを維持しやすくなることもあります。
ストレスが溜まった中学生に親ができる5つの対応
中学生のお子さんのストレスが溜まり過ぎている場合、適切な対応が求められます。
この章では、ストレスが溜まった中学生に親ができる対応について解説します。
対応①専門家に相談する

ストレスが深刻な場合は、カウンセラーや医師などの専門家に相談することも検討しましょう。専門家はストレスの原因を分析し、適切なアドバイスや対処法を提案してくれます。
特に、強い不安や落ち込みが続く場合は、心身に影響が出る可能性があるので早めに相談することが重要です。
専門の医療機関には、以下のようなものがあります。(参考:文部科学省「学校における子供の心のケア」-サインを見逃さないために-」、厚生労働省「こころもメンテしよう 若者のためのメンタルヘルスブック」
公的機関の主な相談窓口は以下の通りです。 学校には先生だけでなく、心理の専門家であるスクールカウンセラーも在勤しているため、連携することで学校生活を多方面からサポートしてもらうことでストレスを軽減できます。 すぐには解決に至らないような問題でも、伝えておくことで学校側も問題を認識できるので一度相談してみましょう。 思春期のお子さんは自分のことで頭がいっぱいで、親が過度に心配することが鬱陶しく感じたり、かえってプレッシャーになってしまったりします。 また、学校で悩みを抱えている場合、家に帰っても心配されると気持ちの切り替えができなくなるかもしれません。 そのため、親はできるだけ普段通りに接して、子供が悩みを忘れ安心して過ごせる環境を作ることも重要です。 子供が相談してきたら、たとえ解決できなくても、話をしっかり聞いて悩みに寄り添いましょう。悩みは誰かに話すだけでもスッキリするものです。 悩みに寄り添って信頼関係を築いておくことで、お子さんは定期的に相談してくれるようになるかもしれません。そうすれば、深刻な事態になる前に対処できる可能性が高まるでしょう。 お子さんの悩みを解決してあげたいという気持ちは誰にでもあるものですが、過干渉し過ぎると逆効果になる場合があるので注意しましょう。 例えば、子供の価値観を否定して「こうするべきだ」というアドバイスばかりしていると、子供は自分の考えに自信が持てなくなります。 また、積極性が失われて無気力になったり、親の意見と対立して罪悪感を感じたりする可能性もあります。そのため、悩みに寄り添う程度に留め、アドバイスを求められた際に解決策を提示しましょう。 過干渉がもたらす子供への影響や過干渉にならないためのポイントについては以下のコラムで詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。 中学生のストレスは避けられないものですが、適切な解消法を取り入れることで、心身の負担を軽減できます。日常的にストレス対策を行い、早めに対処することが大切です。 また、ストレスが深刻なときは先生や専門家と連携を取り、適切なアプローチを実践しましょう。 このコラムがストレスで悩む中学生の助けになれば幸いです。
対応②学校と連携する
対応③普段通りに接する

対応④子供の話をしっかり聞く
対応⑤過干渉しない
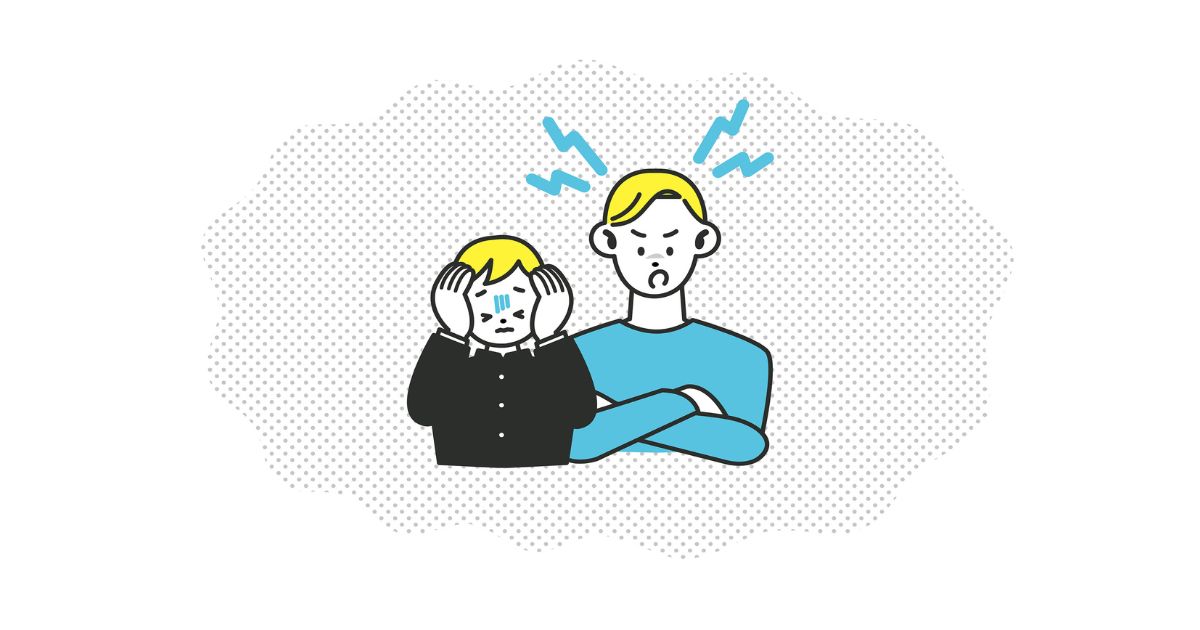
まとめ:ストレスを抱え込み過ぎる前に対処することが重要