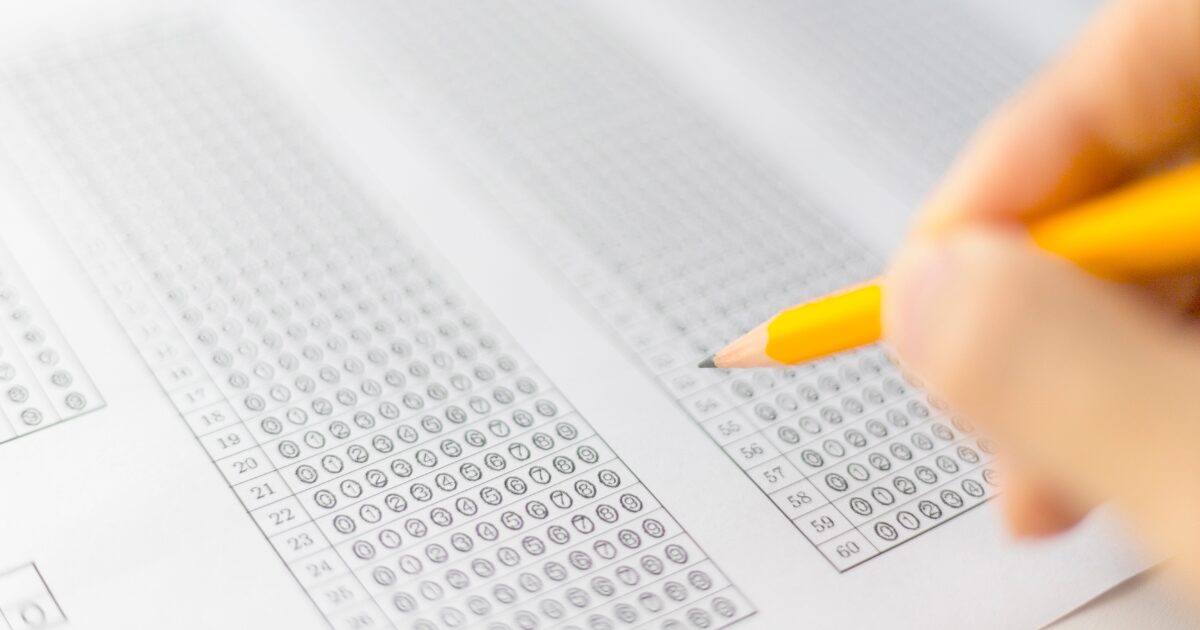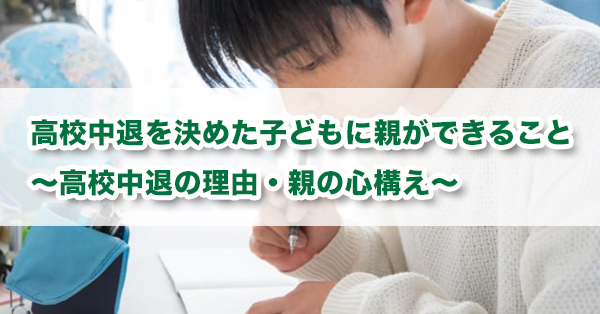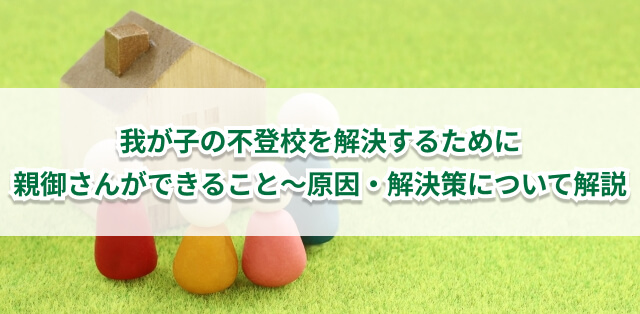不登校の末路はどうなる? 不登校=人生終了ではありません
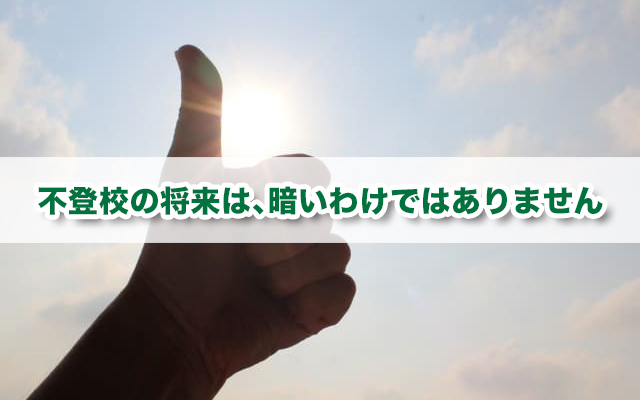
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
不登校になると、次のような不安を感じることが増えるでしょう。
- 自分の将来は、悲惨な末路が待っているのかも…
- 「不登校=人生終了」とネットで見たけど本当?
- 不登校になってから自分の将来を考えるのが怖い…
また、親御さんも不登校のお子さんの将来を心配していらっしゃると思います。
このコラムでは、不登校の末路や、不登校から進学・就職を果たした実例、そして親ができる3つの対応について解説します。
「不登校の末路」と聞くと、暗い話のように思うかもしれません。ですが、不登校だからといって、必ずしも暗い将来が待っているわけではないのです。
このコラムを読んで、少しでも将来に対して希望を抱いていただければ幸いです。
不登校のご本人はもちろん、親御さんやすでに高校を卒業した年齢になっている「元不登校」の方のお役にも立つ内容となっています。ぜひ最後まで読んでみてください。
共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの
アドバイス
思い込みを捨てて、客観的な情報に触れていきましょう
よくある誤解ですが、「不登校なら、必ずひきこもる」は間違いです。そうした思い込みは、親御さん自身もお子さんも「追い詰める」状況につながります。また、現在ひきこもっている場合(将来的にひきこもりになった場合)でも、そこからの社会復帰はもちろん可能です。
不登校関連の書籍を読んだりイベントに参加したりして、客観的な情報や当事者体験談を見聞きして、そうした思い込みを捨てていただければと思います。不登校の専門家や支援団体とも相談しながら、親御さんがいまできることを少しずつ整備していきましょう
私たちキズキ共育塾は、不登校に悩む人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
不登校本人・親が感じる「末路」への不安

不登校になると、親子とも将来に不安を感じます。
「悲惨な末路」を想像することもあるはずです。私たちキズキ共育塾でも、次のような不安をご本人や親御さんからよく伺います。
- 不登校になったから、進学や就職ができないのでは…?
- 不登校を経験した自分は、恋愛も結婚もできないかも。
- 子どもは、引きこもったまま大人になるの…?
不登校の本人や親御さんには、不登校の「大変さ」があると思います。
また、テレビなどでは「中高年の引きこもり」や「ニート」などが取り上げられることも多く、そのような番組を見て不安に駆られることもあるかもしれません。
しかし、結論からお伝えすると、不登校だからといって「悲惨な末路」を辿るわけではないのです。
確かに、不登校を経て、引きこもりやニートのような不本意な境遇にある方もいらっしゃいます。
しかし、全ての(元)不登校の子どもが、引きこもりやニートになるわけではありません。
また、引きこもりやニートになったからといって、そこで人生が終わるわけではないのです。
何歳からでも、未来を切り拓けます。
(元)不登校でも、(その後)進学したり、社会に出たりできるのです。
ここからは、不登校経験者がどのような進路に進んだかの調査や体験談を紹介します。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「ニートになる原因は? なりやすい人の特徴や脱出方法を解説」
不登校の人の「その後」

不登校を経験した人は、その後どのような進路を歩んでいるのでしょうか?
やや古いデータなのですが、内閣府の「平成21年版青少年白書」のデータを紹介します。
この調査では、「中学不登校者」と「高校中退者」のその後を調べています。
「高校中退者」は「高校での不登校」と全く同じではありませんが、「高校不登校を経て中退した」人もいますので、合わせてお伝えします。
中学不登校者は、卒業後、約4年が経過した時点で、次のように過ごしています。
- 学校に行っている:39.4%
- 仕事をしている:26.6%
- 仕事をしながら、学校に行っている:7.3%
- 仕事にはついておらず、学校にも行っていない:16.5%
このうち、「学校に行っている」「仕事をしながら、学校に行っている」人の行っている「学校」の内訳は、次のとおりです。
- 四年制大学:29.4%
- 専修学校,各種学校:25.5%
- 通信制高校:21.6%
- 定時制高校:11.8%
- 全日制高校:5.9%
高校中退者は、中退後、約4年が経過した時点で、次のようになっています。
- 仕事をしている:47.6%(約半数)
- 学校に行っている:17.3%
- 仕事をしながら、学校に行っている:8.3%
- 仕事にはついておらず、学校にも行っていない:20.8%
このうち、「仕事をしている」「仕事をしながら、学校に行っている」人の「仕事」の内訳は、次のとおりです。
- パート・アルバイト:41.2%(最も多い)
- 正社員:36.3%
- 派遣社員・契約社員:12.7%
非正規雇用の割合が多いことが気になるかもしれませんが、正規雇用で働いている人の割合も少なくはありません。
また、非正規雇用が「悪い」わけではありませんし、改めて高校を卒業したり職業訓練などを受けたりして非正規雇用から正規雇用になることもできます。
このように、中学不登校、高校中退であっても、その後、多くの人が進学したり働いたりしているのです。
不登校であっても、その将来が必ず「暗い末路」になるわけではありませ。
なお、「仕事もしておらず、学校にも行ってない」人が一定いることは事実です。ですが、それはあくまで「調査時点」の話です。
私たちキズキ共育塾の生徒さんの事例だけ見ても、中学不登校や高校中退から4年以上経過してから高卒認定や大学受験に合格している人は少なくありません。
不登校から進学・就職した実例
不登校のを経験した人の将来は、「末路」と言われるほど悲観的なものではないことを、データの観点からお伝えしました。
ここからは、不登校から進学・就職をしたキズキ共育塾の講師・生徒の体験談を紹介します。
実例①中学不登校から大検を経て大学・大学院へ。就職・結婚もしました

まずは、キズキ共育塾の、桐山久美子講師(仮名)の体験談です。
小学生の頃にいじめに合っていた私は、人から見下されることを極度に恐れていました。
そのため、中学に入ってからは、勉強や部活をがんばり、「優秀な人」であろうと必死でした。
クラス3位以内の成績をキープしつつ、全国大会に出場するような厳しい部活の活動をがんばっていました。
しかし、中2のとき、燃え尽き(バーンアウト)で急に「何もしたくない」気持ちになり、学校に行けなくなったのです。
そこから中3まで教室に戻れず、何とか入学させてもらった高校も、半年ほどで中退しました。
高校中退後、「現状を少しでも変えたい。早く勉強をがんばりたい」と思っていた私は、学校以外の環境に望みを託し、フリースクールに通いました。
そのフリースクールで数学の勉強にハマりました。
「大学で、数学の勉強をしてみたい」という目標ができ、大学入学資格検定(大検、現:高卒認定試験)に16才で合格し、19才で早稲田大学へ進学しました。
受験勉強は、基礎的なところは独学で行い、入試に向けた実践的な内容は予備校の授業を受けながら行いました。
大学と大学院では、望んだとおり数学を学び、とても充実した学生生活を送りました。
大学院修了後は、システムエンジニア(SE)として民間企業に就職し、優秀な方たちに囲まれながら、素晴らしい社会人経験を積めました。
そして、結婚を機に、いろいろと検討した上で退職し、現在はキズキ共育塾の講師をしています。
「不登校や高校中退をした自分(や我が子)は、進学も就職も結婚できないかもしれない…」と悩みをお聞きすることもあります。ですが、そんなことはありません。
私のほかにも、不登校を経験したもののその後に進学や就職をしている人はたくさんいます。
不登校であっても、好きなことを見つけたり、進学・就職・結婚したりすることは可能なのです。
実例②不登校からの高校中退。アルバイトをしながら受験勉強をし慶応大学へ

続いて、キズキ共育塾の卒業生、内田和也さん(仮名)の体験談です。
小・中学校時代は、野球部でキャッチャーをしたり、生徒会に入ったりと、楽しい学生生活を送っていました。
勉強にも自信があり、「高校受験も難なく終わる」と思っていましたが、不合格だったんです。
初めて挫折を経験した瞬間でした。
そして私は、滑り止めで受験・合格していた高校に通うことになりました。
高校入学後は、「勉強ができない自分」に対する劣等感から、大学受験に向けて、休日返上で猛勉強を開始し、1年生のときは、本当に勉強漬けの毎日でした。
ただ、がんばりが続いたのも、高校1年生の終わりまででした。
高校2年生の初め、疲労性の体調不良によって学校に通えなくなったのです。
それ以来、自室に引きこもりがちになり、好きなゲームをする毎日でした。
2年生の半ばで、進級のための出席日数も足りなくなり、中退しました。
高校中退後も引きこもってゲームばかりの生活を1年ほど続けていたところ、だんだん気持ちに余裕ができてきました。
体調も安定して、「高校に在籍していれば、3年生の後半」くらいの時期からは、(小遣い稼ぎ程度ではありますが)アルバイトを始められるまでになりました。
アルバイトの開始によって徐々に生活リズムも安定しました。一方で、「高校中退」や「フリーター」に対する社会の厳しさも知ることになりました。
そして、19歳になる年の春、大学受験を決心しました。
しかし、「高認も大学も独学で受験・合格する自信がないので、塾(予備校)にも通わなくてはいけない…」と悩みはつきず、また、受験に向けて具体的にどう行動していいかもわかりませんでした。
悩み続けていたある日、キズキ共育塾を新聞記事でたまたま見つけ、相談に行き、入塾することにしました。
アルバイトをしながらの勉強は大変で、体力的にも精神的にもつらく、ゲームに「逃避」することもありました。
結果として、普通の受験生と比べたら勉強量は少なかったかもしれません。
ですが、1年間がんばりきることができ、以前から志望していた慶應義塾大学に合格しました。
今は、大学に通えることに喜びを感じ、大学生活に期待を膨らませています。
不登校から「進学・就職・結婚」した人はたくさんいます
ご紹介した講師・生徒のように、不登校を経験していても、進学・就職・結婚した人はたくさんいます。
不登校や高校中退に「つらさ」や「大変さ」が伴うことは否定しません。
ですが、「不登校には、必ずしも悲惨な末路が待っているわけではない」とご理解いただければ幸いです。
以下の体験談参考になるかと思いますので、あせてご覧ください。
不登校の末路として「引きこもり」になったら?

万が一、不登校から悲惨な末路を辿りそうになった場合は、どうすればいいのでしょうか?
「不登校からの悲惨な末路」と聞いて、「長期の引きこもり」を想像する方は多いと思います。
不登校から引きこもりになる可能性は、否定できません。
内閣府の「令和元年版子供・若者白書」によると、引きこもりのきっかけに「小・中・高校生時代の不登校」を挙げた人は、複数回答69件中4件(約5.8%)が該当しました。
この数字・割合を多いと見るか少ないと見るかは人によって異なるかもしれませが、現実として「不登校は、引きこもりのきっかけたりうる」のです。
また、引きこもりが長期化し、年齢が上がって行くにつれて、社会復帰が難しくなることも否めません。
しかし、引きこもりも不登校と同じく、解決できないものではありません。
現在の年齢が何歳であれ、引きこもりの解決を目指す支援者は大勢いるのです。
ここでは、「宮城県ひきこもり地域支援センター」の、ある事例をご紹介します。(宮城県精神保健福祉センター※PDF「ひきこもり相談事例から支援を考える」から抜粋・編集)
直接的には不登校と関係しないかもしれませんが、引きこもりになってもそれが「末路」ではない話としてご覧ください。
実例:引きこもり地域支援センターとデイケアを通じて「次の一歩」へ進んだ

相談時に26歳だったある男性は、本人、両親、父方祖父母の5人家族。
小中学校時代は両親が不仲で、ストレスから学校をときどきズル休みをしていました。
中学校時代は、友達から無視されたり、女子生徒から陰口を言われたりした経験がありました。
高校に入学後は人といる空間が苦痛になり、体調不良が続き3年生の9月に中退。
高校中退後はアルバイトを始めたものの続かず、以後6年間自宅にひきこもっていました。
ひきこもり状態にあることへの不安や自責の念から、イライラや不眠があり、本人自身が相談を希望し、本人と母親で引きこもり地域支援センターに相談しました。
面談は、自己肯定感が低く対人緊張が強かった本人に合わせ、生活の様子を聞いたり、本人の好きな将棋やスポーツの話題を出したりと、リラックスできる形で進められました。
不眠や抑うつを改善するための薬物療法も行い、デイケアの利用も開始しました。
デイケアでは「体を動かしたい」とスポーツを中心に参加。
以前と比べ気持ちが前向きになり、また地域の将棋道場に自分から連絡を取り参加するようになりました。
今は、「好きな将棋の対戦相手が得られて楽しくて仕方がない」と話し、社会参加に向けてのステップを踏み出したところです。
また、センターは、本人だけではなく、関係性は良好ながらもイライラもぶつけられがちだった母親のケアも行いました。
不登校・引きこもりは「家族だけで抱え込まない」ことが大切

このように、引きこもりになったとしても、少しずつ社会復帰を目指すことはできます。
各都道府県や政令指定都市には、「引きこもり地域支援センター」が設置されていますし、民間の支援団体もあります。
引きこもりも、不登校と同様、家族だけで悩まずに適切に支援者を頼ってください(後述します)。
ぜひ、ご家族だけでも構いませんので、支援機関に相談しましょう。
不登校の子どもために親ができる対応
不登校をつらい末路につなげないために、親はどんなことができるでしょうか?
ここからは、不登校の子どものために、親ができる対応を3つお伝えします。
対応①不登校の原因にこだわりすぎない

お子さんの学校に行けなくなった原因を追究しても、不登校の解決にはつながらないことがあります。
反対に、不登校になった原因は解決しないままでも、「次の一歩」に進めることがあるのです。
たとえば、先生のある一言がきっかけで不登校になったとします。
この場合、先生からの謝罪があったとしても、学校や先生への不信感が拭えない、不登校中に生活リズムが乱れたなどの場合は、不登校が続く可能性が高いでしょう。
しかし、謝罪がなくても、次のようなきっかけで登校を再開したり次の一歩に進んだりすることもあります。
- その先生が異動になる
- 進級のタイミングでクラスが変わる
- 他の場所で自己肯定感を育んで先生のことが気にならなくなる
- 転校する
お子さんの不登校の原因を追究・解決したいお気持ちは、とてもよくわかります。ですが、原因の追究は不登校の次の一歩に進むために「絶対に必要なこと」ではありません。
「なぜ不登校になったのか」よりも、お子さんの現状の把握と今後の対策に目を向けることが大切です。
ただし、次のように「原因」を無視してはいけないケースがあります。
- うつ病、統合失調症など精神的な疾患(精神疾患から無気力になる、生活リズムが崩れることで不登校になることもあります)
- 発達障害学業や人間関係に困難を抱えやすい(発達障害は一見「普通」に見えて、ある部分の能力は高いケースもあります。ですので、親が気づかないことも多いのです)
- 夫婦の問題、経済的問題など、子どもに悪影響を与える家庭内の問題
- いじめ
- 虐待
このような場合は、未来に向けての対策を考えると同時に、「原因」への対応に取り組む必要があります。
また、精神疾患や発達障害の可能性があるときは、すぐに精神科や心療内科を受診してください。
その他の問題についても、ご本人やご家族だけで抱え込まず、「その分野の専門家」の力を借りることが大切です。
対応②第三者(専門家)に相談する
不登校解決のためには、親子が社会や学校から孤立し、家庭の中にひきこもらないことが大切です。
不安にさせるつもりはありませんが、そうなるとお子さんの不登校の長期化を招き、長期の引きこもりという「末路」につながりやすいためです。
不登校の改善には、第三者の援助が不可欠になります。
第三者とは、不登校に詳しい人や、不登校支援を行う団体などの専門家のことです。
学校に在籍しているのであれば、担任、学年主任、スクールカウンセラーなどに相談してみてください。
次のような、お住まいの市区町村の相談窓口に相談する方法もあります。
名称などは自治体によって異なりますので、お住まいの自治体のウェブサイトで確認してみましょう(窓口がわからない場合は、代表電話に連絡して確認してください)。
- 児童相談所、児童相談センター(18歳未満)
- 引きこもり地域支援センター
- 発達障害支援センター
- 教育センター(高校相当年齢)
民間の不登校の支援団体には、全国の「不登校の親の会」や、キズキ共育塾などがあります。
親御さんだけ、または子どもだけで相談できる場所もあります。「まずは自分だけで」と思う場合はそういった相談先を探しましょう。
また、最近はインターネットや電話で不登校の相談を受け付けているところも多いので、家の近くに相談機関がなくても頼れます。
相談先については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
なお、こういった相談先に在籍する専門家には守秘義務があるため、相談に行ったからといってそれが周囲に知られることはありません。
ご本人だけ、親子だけ、ご家族だけで悩まずに、積極的に専門家の助けを借りましょう。
対応③親は親の生活を充実させる

親は親で、自分の生活を充実させてください。
「子どもが不登校なのに、私だけが仕事に行ったり、趣味のサークルを楽しんだりしていいのだろうか…?」
そのように思われるかもしれませんが、親は親で自分の人生を楽しむことが、不登校の解決に繋がることがあるのです。
親が自分の生活を充実させることには、次のような効果があります。
(1)親子が社会から孤立することを防ぐ
親子とも外との繋がりがなくなって、家庭ごと地域から(世間・社会から)孤立するケースがあります。
親が働きに出ている場合でも、子どものことで心にずっと不安を抱えていると、社会との心理的な距離が開いていきます。
そして、地域や社会から孤立すると、親の心・視点は子どもに向かう一方です。
家族という密閉した空間の中では、親子の不安がますます増幅します。
親の過度な不安や心配が子どもの心を圧迫していく…といった悪循環にも陥ることもあるのです。
「親が生活を楽しむ」ことで、視野も適切に広くなり、親子ともに社会からの孤立を防げます。
(2)親が大人のロールモデルになれる
充実している親の姿を見ることで、子どもは「今は不登校で苦しいけど、大人になったらこんなふうに生活したいな」と考えられるようになることがあります。
子どもに「外の世界は楽しいよ」「大人になるっていいものだよ」と示すことが、不登校の「次の一歩」につながるのです。
まとめ:不登校の末路は暗いものだけではありません

不登校の「末路」は、決して暗いものではありません。
不登校であるがゆえの「大変さ」があることは否定しません。ですが、不登校を経て進学・就職・結婚した人はたくさんいるのです。
そして、不登校の次の一歩に進むためには、第三者(専門家・支援者)に相談しサポートを受けることが重要です。
仮に不登校が長期化して引きこもりになったとしても、同じく支援者はたくさんいます。
親子で「不登校の次の一歩」に進み、「末路」ではなく「将来」に進めますよう、心から祈っています。
さて、私たちキズキ共育塾も、不登校の相談を受け付けています。
また、授業でも、勉強や勉強方法を教えるだけでなく、進路相談や雑談もできます。そうしたお悩みを抱える方々一人ひとりのための完全個別指導を行っています。
少しでも気になるようでしたら、ぜひ一度無料相談・教室見学にいらしてください。
Q&A よくある質問
不登校の子どもために親ができる対応を教えてください。