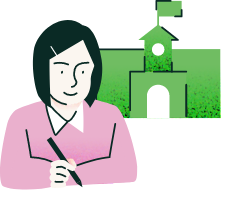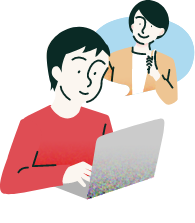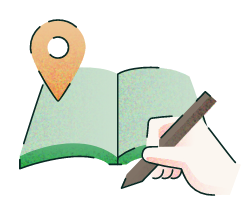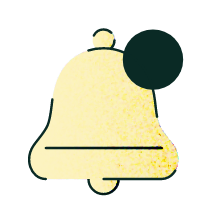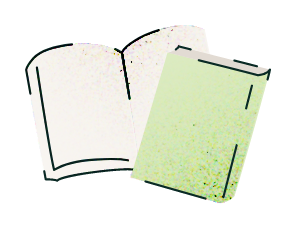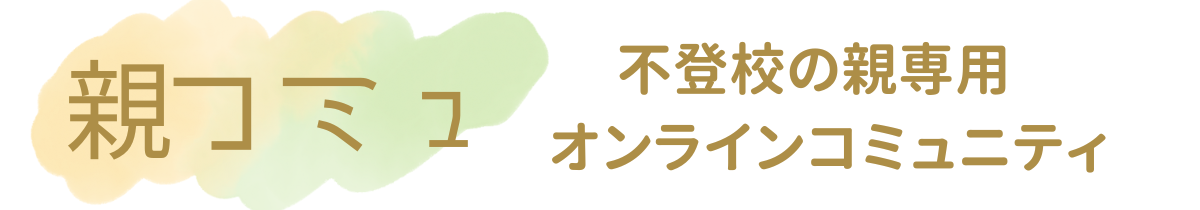学校に行かない子どもの気持ち 行かない理由や子どもへのアプローチを解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
このコラムをご覧のあなたは、「学校に行かない」と言い出したお子さん、または実際に学校に行かないお子さんに、困惑しているのではないでしょうか?
- どうして急に学校に行かないと言ったのだろう…
- このまま学校に行かないとどうなるの?
このコラムでは、小・中学生の子どもが学校に行かない理由や学校に行かない子どもの気持ち、学校に行かない子どもへのアプローチ、親にしてほしい対応、学校に行かないで勉強する方法について解説します。あわせて、学校に行かない経験をした人の体験談を紹介します。
学校に行かない不安を解消するための助けになるはずです。このコラムが、少しでもあなたとお子さんの役に立ちましたら幸いです。
共同監修・不登校新聞社 代表理事 石井志昂氏からの
アドバイス
やるべきことを整理してみましょう
本コラムには、「学校に行かない子にどんなアプローチをするべきか」が書かれています。
アプローチについては、親をはじめ、お子さんの周りにいる人たちにはやることがたくさんあります。情報を入手することや、親御さん自身の不安を整理しておくことなどです。
子どもは不登校になるまでに、必ず傷ついています。無知であることで本人を傷つけたり、本人に不安をぶつけるような行動をしたりすることで、さらに追い詰めないようにしましょう。
私たちキズキ共育塾は、学校に行きたくない人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
小・中学生の子どもが学校に行かない理由
文部科学省は毎年、不登校に関する調査をしています。(参考:文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」、文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」)
不登校という状態は、文部科学省によって以下のように定義されています。
何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者をのぞいたもの
(出典:文部科学省「不登校の現状に関する認識」)
学校に行かないお子さんが、現時点で不登校の定義に当てはまるとは限りません。ですが、傾向として参考になると思います。
文部科学省の調査に基づくと、小・中学生の不登校の理由は、大きく以下の4つに区分できます。
- 学校に係る状況:いじめ、人間関係、進路の悩みなど
- 家庭に係る状況:近親者の死、家族の不仲、親の過干渉など
- 本人に係る状況:無気力、不安、生活リズムの乱れなど
- その他:以上のいずれにも当てはまらないもの
この章では、小・中学生の子どもが学校に行かない理由について解説します。
理由①学校

教師や友人との人間関係、学校の環境が理由で学校に行かなくなることはあります。
進級・進学でクラスの顔ぶれや担任が変わると、再び学校に行ける場合もあります。
不登校の理由が学校そのものである場合、主に以下の理由が考えられます。
学習面の悩み
- 授業内容が理解できない
- 友人の前で発表をすることがストレスになっている
- 成績が下がっている、または思うように上がらない
- 進路選択に悩んでいる
人間関係
- 友人とのコミュニケーションがうまくいかない
- 同級生や先輩などからいじめを受けている
- SNSやインターネットでのトラブルがあった
- 教師から叱責や厳しい指導を受けている
校内の環境
- 学校が遠く通学が大変
- 校舎が古く暗い
- 清掃が行き届いていない
- 居心地が悪い
- 給食が口に合わない
- 給食で食べられないメニューが多い
理由②家庭
家庭環境や家族関係が理由となって、学校に行かなくなる場合もあります。
この場合、子どもは居場所を失い、不安定になることもあります。
家庭内の不和
- 夫婦喧嘩
- 家庭内暴力(DV)
- 家族間の暴力
- 以上のいずれかが原因による精神的に不安定な状態
養育
- 親が仕事などで忙しい
- 子どもとコミュニケーションが取れない
- 必要なケアができない
- 学校の支度や食事のサポートが不十分である
過干渉・過保護
- 親が心配しすぎる
- 子どもが自立できない
- 学校生活に自信を持てなくなる
理由③本人

本人の心や体にも、学校に行かなくなる理由がひそんでいる場合があります。
最初は単なる体調不良だったけれど、回復したあとも学校に行くのが難しくなるケースや、生活習慣が乱れて決まった時間に起きられなくなるケースも見られます。
体の問題
- 病気やケガ
- 慢性的な体調不良
- 睡眠不足
- 生活リズムの乱れ
- 自律神経の失調
- 朝起きるのがつらくなる
心や行動の問題
- 思春期特有の悩みや無気力、不安
- 自分への自信のなさから、家にひきこもりたくなる
- ゲームや動画視聴に依存し、やめられなくなる
- 家出や歓楽街の徘徊などの非行に走っている
理由④その他
以上のいずれにも当てはまらない理由で学校に行かなくなることもあります。
地域の問題
- 治安が悪い
- 支援機関が不足している
- 子どもが安心して生活できない
社会的な偏見や差別
- 外国にルーツがあるで、差別や偏見を受けている
- 性的マイノリティーであることで、差別や偏見を受けている
災害や事故
- 地震や台風などの災害で登校できない期間が続いている
- そのまま学校に行きづらくなった
- 不安がぬぐえない
- コロナ禍で学校に行かなくなったことをきっかけにいきづらくなった
学校以外の習い事
- 行き過ぎた指導にプレッシャーを感じて不安定になる
- 友達とのトラブルがあった
補足:大切なことは、無理に理由を特定しようと思わないこと
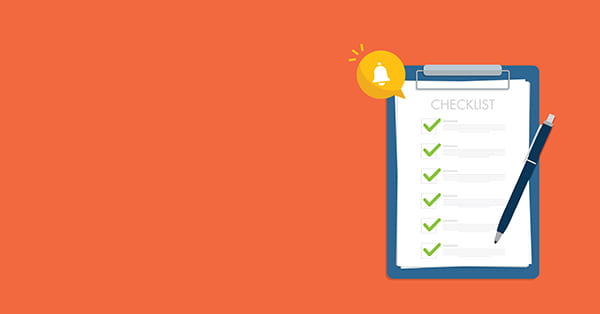
学校に行かない子どもたちには、共通する一つの理由があるわけではなく、一つないし複数の理由が存在します。子どもが学校に行かない理由は多岐にわたります。
親として大切なことは、無理に理由を特定しようと思わないことです。
親としては学校に行かない理由を知りたくなりますが、「学校に行かない理由はひとつではないかもしれない」「本人が言っている理由以外にも、もしかしたら何か原因があるのかもしれない」と考えておく程度にとどめましょう。
学校に行かない子どもの気持ち〜段階別に解説〜
子どもが「学校に行かない」と言うときの原因はさまざまです。
子どもが学校に行かない原因がなんであれ、そのような状態の子ども、そして不登校になった子どもには、ある程度共通した心境があります。
この章では、キズキ共育塾の知見に基づき、学校に行かない子どもの気持ちについて解説します。
段階①学校に行かない前兆が出始めたときの気持ち

登校はしているものの、遅刻が増えたり、学校の話題にイライラしたりする様子が見られる場合、それは子どもが学校に行かなくなる前兆かもしれません。
この時期、子どもは人間関係に悩んだり、授業内容が理解できず、焦りや劣等感を感じたりしている可能性があります。加えて、進路選択など将来への不安もあるかもしれません。
さまざまな理由から、食欲がわかない、寝つきが悪く朝になっても起きられないなどの症状が出ている場合もあります。
不安の中で、必死に自分と戦っている。それが、この時期の子どもの気持ちだといえるでしょう。
段階②「学校に行かない」と言い始めたときの気持ち
子どもが「学校に行かない」と言い始めたときにはすでに、さまざまな悩みや不安に苦しんで、がんばりきった後であることが多いです。
まず、多くの子どもは、家庭と学校以外の場所をほとんど知りません。
つまり、子どもにとって学校は、世界の半分を構成する場所なのです。
そんな、自分にとっての多くを占める学校に「行かない」と言う勇気や苦悩は、どれほどのものでしょう。
そして、多くの子どもは、「学校を休むことはよくない」という価値観を持っています。
そのため、「学校に行きたくないけど、でも休むのはよくなくて、だけど学校に行くのはつらくて…」と、苦しんでいるのです。
やりきれない気持ちのはけ口が見つからず、暴言を吐いたり、物を壊したりするケースもあります。
それまで見たことのない姿に驚き、悲しむ親も多いのではないでしょうか。
段階③学校に行かないようになってからの気持ち

さて、「学校に行かない」と言い、実際に学校に行かないようになったら、子どもはどんな気持ちなのでしょうか。
悩みが解決することもあるでしょうし、解決しなくても一時的に学校から解放されることで気が楽になることもあるかもしれません。
また、そうした気持ちの変化や、「家にいてもつまらないな」などと思うことで、「やっぱり学校に行こう」と、すぐに気が変わることもあるでしょう。
しかし、学校に行かないことで、「みんなは普通に学校に通っているのに、自分にはできない」という、新たな劣等感や苦しみが生じるケースもあるのです。
休んだ期間が長くなると、勉強や友人とのコミュニケーションから離れることにもなります。
これらの新たな悩みは、以下のような状態につながることがあるのです。
- 近所の目を気にして昼間に外出ができなくなる
- 気持ちの上でも学校が遠ざかる
- 進路や将来に悲観してマンガやゲームといった現実逃避に没頭する
こうした状況の子どもは、親の目からは「ただ逃げて、遊んでいるだけで何もしない」と見えるかもしれません。
ですが、子ども自身も手探りで、その状況をなんとかしたいと悩んでいるのです。
段階④次のステップに進む時期の気持ち
学校に行かない時期を経て、次第に次のステップへと向かう子どももいます。
例えば、登校を再開したり、別室登校や時間差登校などこれまでとは異なるかたちでの登校を始めたりします。
もちろん、全員が再び登校するようになるわけではありません。学校以外に学びの場を見つけたり、家庭で過ごす場合でも気持ちが明るく前向きになったりするケースもあります。
このようなとき、子どもは、自分自身を認められるようになり将来への希望がわいてきます。
また、家族や周囲の人への感謝や将来の目標をはっきりと感じることもあります。
学校に行かない子どもへの5つのアプローチ
「学校に行かない」と言い出した子どもや、実際に学校に行かない子どもに対して、親はどのようなアプローチをすればいいのでしょうか?
この章では、学校に行かない子どもへのアプローチについて解説します。
アプローチ①学校に行かないことを許し、子どもに伝える

まず大切なことは、子どもに「休んでもいい」と直接伝えることです。
こちらで解説したとおり、子どもが「学校に行かない」と言い出したときには、すでにさまざまな葛藤に苦しんで、がんばりきった後であることがほとんどです。
親の目からはがんばっているように見えなかったり、子ども自身もがんばった自覚がなかったりすることもあります。
ですが、がんばって悩み抜いた結果、「学校に行かない」という結論に達したのだと、受け止めるようにしましょう。
そして、「がんばったね」「学校に行かなくていいよ」と、直接言葉にして伝えてください。子どもは、親から直接「学校に行かなくていい」と言われることで安心できます。
休んで回復した後、子どもは必ず前に向かって歩き出せるはずです。
アプローチ②現在の子どもを気遣う
いまの、目の前のお子さんを気遣いましょう。
あなたは、お子さんが学校に行かないことに対して、「どうしても不安が消えない…」「学校に行かないことを心から肯定できない」などと思うかもしれません。
その気持ちは、とてもよくわかります。
ですが、学校に行かない子どもに対して心配を口にしたり、登校を再開させようとしたりすることが、親子関係の悪化や子どもの悩みが深まることにつながる場合もあるのです。
繰り返すとおり、「学校に行かない」と言うまでには、本人も散々悩み、がんばりきっています。
親が心配や不安を口にすることで子どものストレスが増え、その様子を見た親の心配や不安がさらに増える、といった悪循環に陥らないことが大切です。
そして、そうならないためのコツが、子どもの将来を心配するのではなく、現在の子どもを気遣うことなのです。
子どもはいま現在、悩みを抱えたり傷ついたりしていて、次の一歩に進むために「なんとかしたい」と思っています。
将来のことは、いまの悩みや傷が癒えてから考えても、決して遅くはありません。
まずは、現在の子どもと向き合ってみてください。
アプローチ③学校と連携する

子どもが学校に行かないことを、学校に相談しましょう。
必ずしも、すぐに学校に行かせることが目的ではありません。大切なことは、学校とのつながりを維持し続けることです。
担任の先生や特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラーなどと、子どもの学校生活で気になったことや家庭での様子を共有し、問題解決に向けて一緒に取り組みましょう。
学校から連絡があれば子どもに伝え、「先生たちが気にかけているよ」とさりげなく話すのもオススメです。場合によっては、家庭訪問をお願いし、子どもの様子を直接見てもらうのもよいでしょう。
決して、学校に行くことを無理に促すという姿勢ではなく、現状を共有しながら、今できることを学校と一緒に探るスタンスを大切にしてください。
学校やクラス以外の楽しく過ごせる場所があると、それが支えになったりつらいことが気にならなくなったりして、クラスへの登校も再開できる可能性があります。
また、クラスへの登校は再開できないままでも、保健室登校と学習塾を併用したり放課後に登校したりすることで、クラスへの通学とは異なるかたちで前に進めるようになることも考えられます。
アプローチ④学校に行かない理由の追求・解決にこだわらない
子どもが学校に行かない理由は、親にはよくわからないケースが多くあります。
子ども自身も原因を言語化できないことも、少なくありません。
その上で、子どもが「学校に行かない」と言う理由・原因は、追求・解決が必要な場合もあります。しかし、必要ない場合もあるのです。
例として、担任の先生からの心ない一言で学校に行きたくなくなったケースを考えてみましょう。
この場合、直接的な解決は、担任の先生からの謝罪・再発防止を受け入れることが考えられます。
もちろん、それによって子どもが次の一歩に進めることもあるでしょう。
しかし、担任の先生からの謝罪がなかったり、謝罪があっても受け入れられなかったりしたからと言って、お子さんが次の一歩に進めないわけではありません。
逆に、学校に行かない間に勉強の遅れという悩みが生じた場合、謝罪を受け入れても学校に行きたくない気持ちが消えないこともあります。
このように、学校に行かない理由は、直接的な追及・解決を目指さなくてもよいケースがあるのです。
また、子どもには、それぞれの性格や特性といった個性があります。
学校に行かない原因も、その子の性格や特性が色濃く反映します。紋切型に分類できるわけではありません。
無理に原因を突き止めようとすると、子どもはまるで取り調べを受けているように感じ、罪悪感や悩みが増える可能性があります。
また、お子さんにもはっきりとした自覚がないことも多いですし、親には原因を言いたくないという場合も考えられます。
ただ、病気や障害が関係するケース、いじめが関係するケースなどは、原因の解決とまでは言わずとも、何らかの対応は必要でしょう。
どちらにせよ、お子さんが学校に行かないことを親御さんだけで抱え込む必要はありません。
「自分の子どもだから、親である自分だけでなんとかしなければ…」などとは決して思わず、こちらで紹介する専門家や支援機関などを積極的に利用しましょう。
アプローチ⑤落ち着いたら、さまざまな選択肢を示す

子どもが落ち着きを取り戻し、前向きになってきた場合、次に大切なことは選択肢を提案することです。
なぜなら、意欲や自信を取り戻し、社会とのつながりを築くきっかけになるからです。
再び学校に行けることはもちろん、学校以外にも学びの場があることを子どもに伝え、自分の気持ちや将来のビジョンに応じて選べるのだと知ってもらいましょう。
同じく将来の進路についても、さまざまな可能性があることを伝えてあげてください。
子どもは「学校に行けなくなった自分は、もう就職できない」などと悲観的に考えることがあります。
しかし、多様性が尊重される時代である現在は、進学や就職、起業、フリーランスなどいろいろな生き方があります。少しのあいだ学校に行けなかったからといって、将来が閉ざされるわけではありません。
また、親や教師には言いづらい思いを抱えている子どもには、専門家や支援機関への相談を提案するのもオススメです。学校以外の学びの場はこちらで紹介します。また、支援機関についてはこちらで紹介します。
いずれにしても大切なのは、将来への希望をもたせること。そのために、子どもが将来についてどのような夢や目標を持っているのか、話をじっくりと聞きましょう。
子どもが抱えている思いやビジョンは、親の考えとは違うかもしれません。それでも、頭ごなしに否定するのではなく、積極的に応援する姿勢を見せてあげてください。
回復期の子どもにとって、学校以外の学びの場や支援機関の存在、さまざまな選択肢を知ることはとても大事です。将来に向けて希望を持って歩めるよう、焦らずじっくりとサポートしていきましょう。
学校に行かない子どもがいる親にしてほしい4つの対応
この章では、学校に行かないと子どもがいる親にしてほしい対応について解説します。
子どものためのみならず、あなた自身のために、ストレスや不安を緩和・解消するようにしてください。
対応①友人や親戚など周りの人に相談する
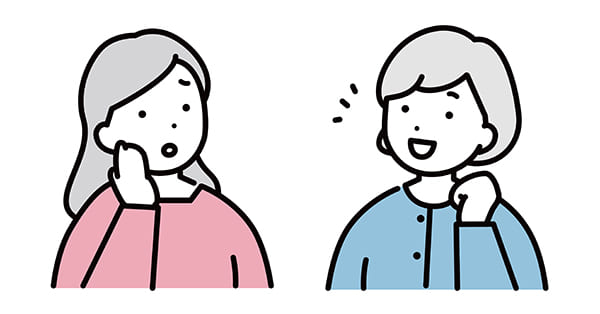
友人や親戚などの周囲の人の中に、悩みを話せる人や、同じような悩みを抱える人はいないでしょうか?
一人で悩んでいると、行き詰まることが多いです。
他者の視点によるアドバイスをもらうことで、具体的な解決策に繋がったり、話すだけでスッキリしたり、共感をもらえて安心したりできる可能性が高まるでしょう。
かつてお子さんが学校に行かなかったという人などに相談することで勇気づけられる人も多いようです。
周囲に相談できそうな人がいたら、勇気を出して話してみましょう。
対応②子どもから離れて自分の時間を持つ
お子さんが学校に行かないことに悩むあまり、ストレスをためこんではいないでしょうか。睡眠不足にも気をつけたいものです。
そんなときは、お子さんから離れて、自分の時間を持つことも有効です。有意義に過ごすことで、ストレスが緩和されるからです。
一人の時間を楽しむのもよいですし、ほかの家族や友人などと過ごすのもよいでしょう。大切なのはあなたがリラックスできる過ごし方を選ぶことです。
有意義に過ごすには、必ずしも何かをしなければならないわけではありません。
日常の悩みから一時的に避難し、ほっとできる環境に身を置くことが大切です。
ぜひ、あなただけのお気に入りの時間を見つけてください。具体例として、以下のような過ごし方があるでしょう。
- カフェに行く
- 温泉やスーパー銭湯に行く
- 映画を見る
- 好きな本やゲームに浸る
- アロマやマッサージを利用する
- ゆっくり眠る
あなた自身の心と体のケアは、ご家族のためにも大切なことです。決してご自分を後回しにしないでください。
対応③支援機関を利用する

少しハードルが高いと感じるかもしれませんが、ぜひ、支援機関も利用してみてください。
専門的な見地から、お子さん個人に合った的確なアドバイスをもらえます。
また、親御さん自身の悩みへのアドバイスももらえるでしょう。
以下は、自治体が運営している、子どもの悩みに関する相談窓口の一例です。
- 児童相談所
- 児童相談センター
- 教育センター
- ひきこもり地域支援センター
- 発達障害支援センター
地域によって名称が違っていることもあります。詳細は、お住まいの自治体の公式サイトから確認することをオススメします。窓口がわからない場合は、代表電話や代表窓口から確認できるでしょう。
また、公的な相談窓口以外にも支援機関はあります。例えば以下のようなものです。
- 子育ての支援機関 フリースクール 学校に行きたくない子どもたちの支援実績が多い学習塾 病院などの医療機関
専門家と話すうちに、以下のようなこともわかっていきます。
- お子さんの状況はどうか いま在籍している学校への登校再開を目指すべきかどうか いま在籍している学校にはこだわるかどうか どのような次の一歩に進むべきかどうか
お子さんのことを、親だけ、夫婦だけ、ご家庭だけで抱え込まず、ぜひ専門家や支援機関を利用しましょう。
対応④親は親で、自分の人生を楽しむ
こちらで解説した内容とも似ていますが、親は親で、自分の人生を楽しむことも重要です。
つまり、子どもにかかりっきりになる必要はまったくないのです。
どんな親子関係においても、一貫して大切なのは、子どもと適度な距離感を保つことです。
学校に行かない子どもは、常に親が子どものそばにいると「いつも親に心配をかけて、自分に時間を割いてもらって申しわけない」などの罪悪感を抱く可能性もあります。
逆に、子どもは、親が自分の時間を有意義に過ごしていると安心できるのです。
また、楽しそうな時間を過ごす親を見ることで、自分の将来に対して希望が湧くこともあります。
ぜひ、あなたはあなたで人生を楽しく過ごしてください。
とはいえ、お子さんのことを放っておいてよいわけではもちろんありません。適切な距離感で世話をすることは大切です。
お子さんとの適切な距離感は人それぞれ。「自分とわが子の距離感はこれでいいのだろうか?」と不安に思った場合は、こちらで紹介した支援機関にアドバイスを求めてみましょう。
学校に行かないで勉強する3つの方法
お子さんが実際に学校に行かない場合、お子さんも親御さんも、勉強の遅れが気になるでしょう。
勉強に遅れがあると自覚している子どもは、登校の再開が不安になることも少なくありません。
この章では、学校に行かないで勉強する方法について解説します。
なお、学校に行かないお子さんは、悩みがあって勉強どころではない時期もあります。
それぞれのお子さんにとっての勉強再開の適切なタイミングは、こちらで解説した支援機関などに相談することが大切です。
方法①フリースクール

フリースクールとは、主に何らかの理由で学校に行きづらい人たちのための教育機関のことです。
スクールと名はついていますが正式な学校ではなく、多くの場合、NPO法人や個人によって運営されています。
団体によって運営方針が違っており、勉強に力を入れているところ、精神面や生活面での支援が中心のところ、人との交流がメインのところなど、それぞれのスクールで特徴が大きく異なります。
共通するのは、通う人にとって安心できる居場所としての面が強いことです。
なお、正式な学校ではないものの、フリースクールへの出席を、学校への出席としてカウントできる場合があります。
どんなフリースクールがあるか、学校の出席日数にカウントされるかなどは、インターネットで調べたり、見学に行ったり、学校に確認したりしてみてください。
方法②教育支援センター(適応指導教室)
教育支援センター(適応指導教室)も、学校に馴染めない人たちのための教育機関です。なお、自治体によって名称は異なります。
フリースクールと比べると、自治体の教育委員会が運営している点が主な違いとなります。
また、フリースクールに比べた場合のメリットは、費用がかからない点でしょう。
教育支援センター(適応指導教室)への出席も、一定の条件のもとで、学校の出席日数にカウントできます。
教育支援センター(適応指導教室)の利用は、お子さんが在籍している学校や、自治体の教育委員会に確認してみてください。
ただし、教育支援センター(適応指導教室)は、学校に行かない小・中学生の、在籍している学校への登校再開を目的としています。
教育支援センター(適応指導教室)の先生との相性に加えて、お子さんがいま在籍している学校への拒否感が強かったり、しばらくは登校再開を考えていなかったりする場合には、向いていないかもしれません。
方法③学校に行っていない人の支援を行う学習塾・予備校

学校に行っていない人たちの勉強を支援する学習塾や予備校もあります。私たちキズキ共育塾もその一つです。
インターネットで「不登校 塾」「不登校 予備校」などと検索してみると、候補が見つかると思います。
フリースクールとの違いは、勉強がメインであることです。
その上で、学習塾・予備校によって、それぞれ以下のような特徴があります。
- 完全個別指導か集団指導か
- 進路相談ができるか
- 授業は勉強がメインか、雑談などもできるか
- 塾への出席が学校への出席とみなされるか
- 生徒同士の交流があるか
- 居場所としての機能があるか
お子さんに合いそうなところを探して、積極的に問い合わせてみましょう。
学校に行かないとどうなる?学校に行かない経験をした人の体験談
この章では、実際に学校に行かない経験をした人の体験談を紹介します。
体験談①不登校を乗り越え、夢の高校へ進学

Aさんは、私立小学校から希望の中学校に合格しました。
しかし、誰も知り合いがいない新しい環境、内部進学者のグループ、想像を超える高い勉強レベルに戸惑ってしまいます。こうして入学後すぐに、学校に行かなくなりました。
その後、別の私立中学校へ転校。前の中学校よりも楽しく学校生活を送ることができました。
ただ、これまでの経験から学校への不安が消えなかったため、毎日通学できたわけではありませんでした。
そこで、Aさんは、人間関係がみんな同じ地点からスタートする環境に身を置きたいと考え、内部進学ではなく外部の高校を受験すると決意。キズキ共育塾に入塾しました。
不安を抱えていたAさんですが、「進学できる高校はたくさんありますよ」という先生の言葉で、入塾を決断したのだといいます。
まずは、英語と数学を受講。英語では英検にチャレンジし、3級と準2級を取得しました。数学は、ゲーム感覚で問題を解くことが楽しくなり、勉強が順調に進んだといいます。
「キズキ共育塾の完全個別指導では、わからないところをすぐに聞けてありがたかったです。また、先生との雑談や、スタッフとの会話を通して、世界が広がり、学び続けることができました」とAさん。学ぶ楽しさを実感できたようです。
キズキ入塾当時には志望校すら決まっていない状態でしたが、塾での学びを経て見事高校に合格。「自分が行動したことで状況が大きく変わりました」と語ってくれました。
Aさんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
体験談②不登校・高校中退から立教大学合格!キズキで「なんとかなる」と思えるように
課題の多さや将来への漠然とした不安から、高校2年生の夏に学校に行かなくなったBさん。昼夜逆転の生活を送った末、高校を中退しました。
しかし、Bさんには「将来は大学に行きたい」という思いがありました。そこで、高卒認定試験合格を目指してキズキ共育塾に入塾したのです。
スタッフと相談しながら調べてみると、受験する必要があったのは、世界史、倫理、政治・経済、地学基礎の4科目だけと分かりました。
そこで、キズキ共育塾では地学基礎と政治・経済を受講。楽しく勉強しながら、18歳になる年度の夏の試験に合格し、高卒認定資格を取得しました。「想像以上に楽だった」と笑顔で語ります。
そんなBさんは、キズキ共育塾で受けた政治・経済の授業をきっかけに、哲学に興味を持ちはじめました。そこで、立教大学文学部を第一志望に定め、英語、現代文、古文の個別指導を受けました。基礎からの学び直しでしたが、どの科目も面白く感じ、勉強を続けられたのだといいます。
結果、第一志望の立教大学文学部をはじめ、明治大学文学部、中央大学文学部にも合格。Bさんは、地道な努力と前向きな気持ちで夢を叶えました。
キズキ共育塾でさまざまな先生と出会い、視野が広がったBさん。「なんとかなる」と思えるようになり、将来について前向きに考えるようになったといいます。
「高校をやめるという選択は、アリだった」と語るBさん。「いくらでもやり直せる」と感じているのだそうです。
Bさんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
学校に行かない選択をしても次の一歩に進めます

親や子どもにとって一番気になるのは、「学校に行かないとどうなるのか」だと思います。
結論からお伝えすると、いま在籍している学校に行かなくても、進学や就職などの次の一歩に進むことは可能です。
小・中学校ならば、学校に行かないままで卒業できます。出席日数が少なくても進学できる高校もあります。転校という方法もあるでしょう。
高校ならば、中退しても高等学校卒業程度認定試験(高卒認定、高認)に合格すれば、大学や専門学校の受験・入学資格を得られます。
いま在籍している学校に行かなくても、将来が閉ざされるわけではないのです。この点、まずはご安心いただければと思います。
私たちキズキ共育塾の講師やスタッフにも、学校に行かないことを選択した人たちがたくさんいます。
また、いろいろな人に相談するうちに、お子さんの気持ちや状況が変わって登校を再開することももちろんあります。
ただし、いま在籍している学校に行かない期間には、勉強と社会性から一時的に離れるというデメリットに繋がることは、事実です。
お子さんが「学校に行かない自分はダメな人間だ」と悩んだり、親としても「自分の育て方が悪かったのだろうか」と苦しんだり、進学できる高校の数が少なくなったりする可能性があります。
ただ、そういうお悩みは、こちらで解説した専門家や支援機関、勉強できる場所を頼ることで、次第に解決していきます。
そして、お子さんや、あなたをサポートする人たちは、たくさんいるのです。
ぜひ、そうした人たちと繋がり、積極的に相談しましょう。
参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校新聞、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。
このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。
このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。
公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら
私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。
まとめ〜学校に行かない子どものことは、専門家に相談しましょう〜

繰り返すとおり、いま在籍している学校に行かなくても、将来は広がっています。
お子さんのこともご自身のことも責めることなく、「私も生活を楽しんでいるから一緒に楽しもう!」とお子さんに伝えてください。
そして、いま在籍している学校で登校を再開するにしても、別のルートを探すにしても、お子さんのことをご家族だけで抱え込む必要はありません。
ぜひ、専門家や支援機関に、お子さんのことを相談してみてください。
このコラムが、あなたとお子さんのお役に立ったなら幸いです。
さて、私たちキズキ共育塾は、お悩みを抱える人たちのための個別指導塾です。
生徒さんには、在籍している学校に行かない選択をして、別のルートで将来に進もうとしている人も大勢います。
LINEや問い合わせフォームでの無料相談も承っております。
親御さんのみのご相談も可能です。キズキ共育塾の概要をご覧の上、少しでも気になるようでしたらお気軽にご相談ください。
Q&A よくある質問