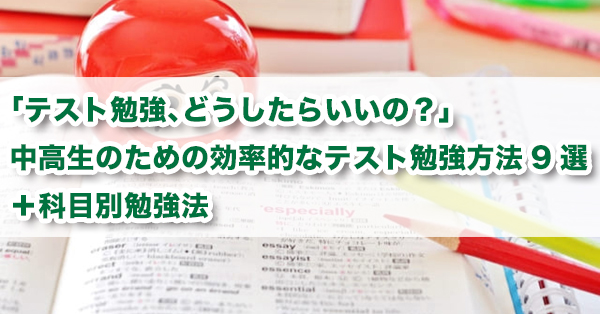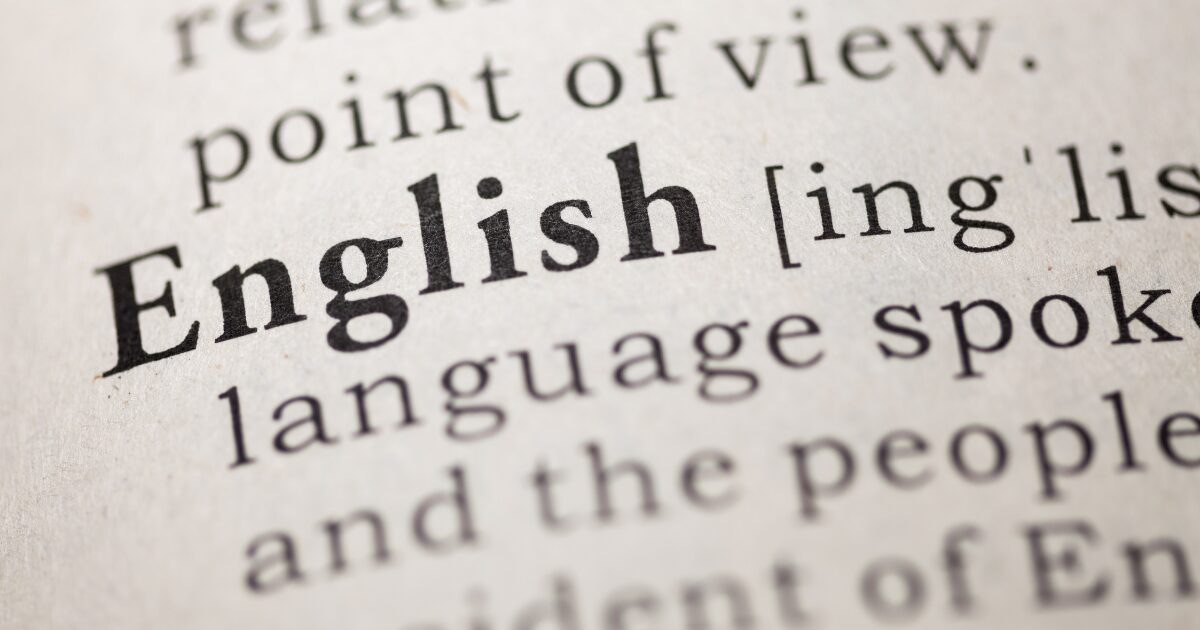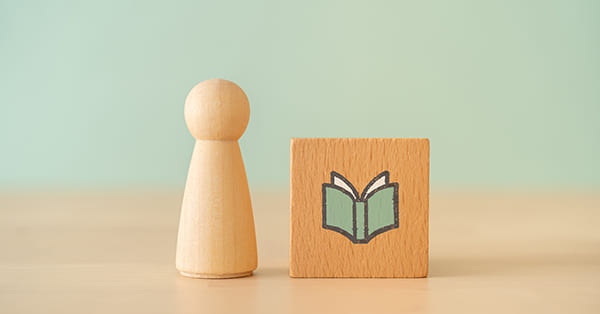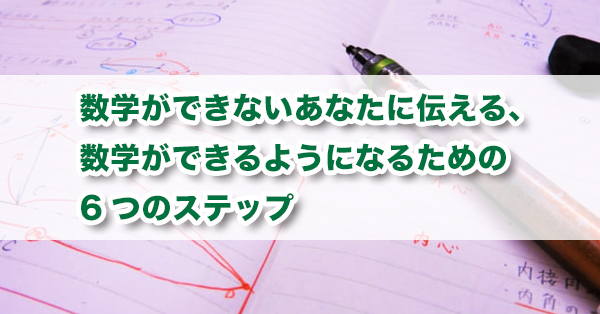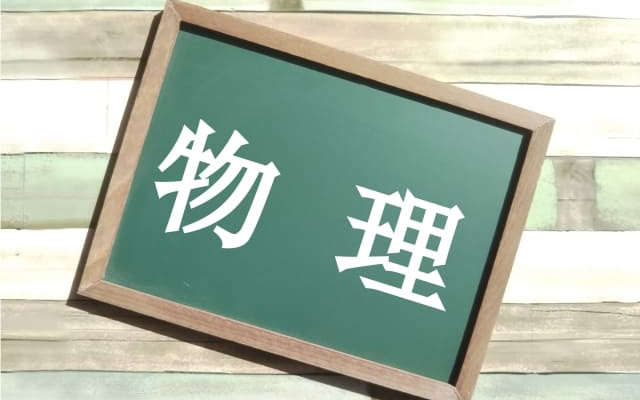オススメの暗記方法7選 人間の記憶の種類と性質を解説
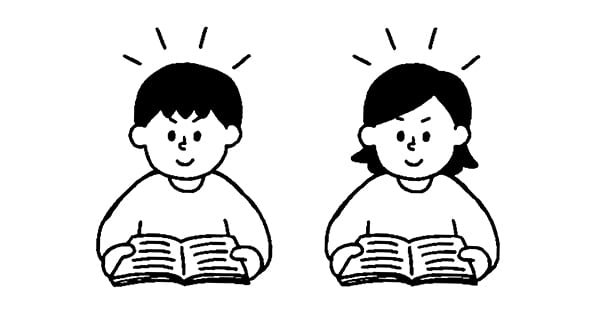
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
勉強してもなかなか覚えられない…という悩みを抱えていると辛いですよね。決まったことを暗記するのは退屈だし、なかなかやる気もでないと思います。
もし、たった2秒の学習を繰り返すだけで効果があるとしたらどうでしょうか。どんなに難しい情報でもスルスル覚えることができたら、勉強が楽しくなりませんか?
このコラムでは、認知心理学を専攻している筆者が、人間の脳の特性から効率のいいオススメの暗記方法や人間の記憶の種類と性質、効果が薄い暗記方法、お悩み別の暗記方法を解説します。
どんなことにも応用できます。記憶力に自信がないという人にぜひ読んでいただきたいです。
私たちキズキ共育塾は、暗記方法を知りたい人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
暗記とは?
暗記とは、文字・数字などを、書いたものを見ないでもすらすらと言えるように、よく覚えることです。(参考:goo辞書「暗記/諳記(あんき) とは?」)
「理解を伴わず、ただ材料を覚えること」を暗記と呼び、「理解して覚えること」を記憶と呼び分けることもあります。
このコラムでは、暗記と記憶を細かく区別せず、あなたが覚えたい内容をなるべく早く、楽に覚えられる方法を解説します。
人間の記憶の種類と性質

暗記方法を解説する前に、人間の記憶の種類と性質について解説します。
人間の記憶は「短期記憶」と「長期記憶」に大きく分類されます。
文字通りではありますが、短期記憶とは、短時間覚えている記憶のことです。そして、長期記憶とは、長い間覚えている記憶のことです。
短期記憶には、視覚や触覚などの感覚を一瞬だけ覚えている感覚記憶と、暗算や会話の内容をごく短時間覚えている作動記憶(ワーキングメモリ)があります。
長期記憶には、以下の種類があります。
- 固有名詞や知識を覚える意味記憶
- 過去の出来事を覚えるエピソード記憶
- 自転車の乗り方などのスキルを覚える手続き記憶
私たちが「暗記したい」と思う時には、長期記憶である意味記憶やエピソード記憶が深くかかわっています。
意味記憶に記憶されている情報は学習していた時や場所には依存しませんが、エピソード記憶は学習時の個人的経験と強く依存します。
意味記憶の例
「日本で一番高い山は富士山である」という知識/p>
エピソード記憶の例
小学生のころ、地理の時間に富士山について勉強したのを覚えていること
長期記憶のなかでも、意味記憶とエピソード記憶を促進するための方法を、こちらで解説します。(参考:日本認知心理学会・監修 太田信夫・厳島行雄・編集『現代の認知心理学2 記憶と日常』)
オススメの暗記方法7選
「暗記が苦手だ」「記憶力に自信がない」と考えている人は安心してください。
暗記方法にはコツがあり、意識的な努力はさほど必要ありません。
また、人間の長期記憶は無限の情報を蓄えることができ、時間経過の影響を受けないとされています。したがって、「記憶力が悪い」のではなく、「適切なタイミングで情報を取り出せていない」という方が近いという説もあります。
この章では、オススメの暗記方法を解説します。
方法①繰り返す

暗記したい情報は何度も繰り返して覚えるようにしましょう。
長期記憶に保存したものは消えないという説があります。しかし、その情報を適切な時に引っ張り出せるとは限りません。
これを忘却のメカニズムでは、「検索失敗説」と呼びます。
物が雑多に置かれた部屋よりも、よく整理整頓された部屋の方が物を見つけやすいですよね。それと同じことが記憶にも言えるのです。
何度も繰り返して覚えることで情報の重要性が増し、適切なタイミングで取り出しやすくなります。
「繰り返し暗記するのはめんどくさい…」と思われた方は、おそらく繰り返しのハードルが高い状態にあります。
たった1、2回単語カードを見るだけの学習でも問題ありません。2秒程度の学習だとしても、習慣づけると効果を発揮するという研究結果があります。
ぜひ、覚えたいことのリストを枕元やトイレに置いておき、数秒の暗記を習慣にしてみてください。意識的に頑張らなくても、潜在記憶によって勝手に覚えることができます。(参考:寺澤 孝文・吉田 哲也・太田 信夫「英単語学習における自覚できない学習段階の検出」)
方法②五感を活用する
五感を活用して暗記するようにしましょう。
人間の記憶は適切な手がかりがあると思い出しやすくなります。五感を使えば、その手がかりを増やすことができるので、記憶が促進されるという説が有力です。
また、環境を整えることも重要です。
例えば、静かな環境でテストを受けることが分かって入れば、同じように静かな環境で記憶した方が思い出しやすくなります。これを「記憶の状態依存性」と呼びます。
鍵の置き場所を忘れた時、通った覚えのある場所を回っているうちに「あっ」と思い出したことはないですか?これは、環境の状態をそろえることで、記憶を促進しようとする働きなのです。
自分の教室の机で単語テストを受けるのであれば、同じ机で英単語を覚えるのが効果的です。(参考:日本認知心理学会・監修、太田信夫・厳島行雄・編集『現代の認知心理学2 記憶と日常』)
方法③アウトプットする

記憶を定着させるためには、積極的にアウトプットすることが効果的です。つまり、「思い出す」という行為がとても重要なのです。
例えば、熟読を4回繰り返しても1週間後には忘却が進みますが、熟読が少なくてもテストをすると忘却が緩やかになることが実験で分かっています。(参考:Roediger & Karpicke 「Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention.」)
このように「思い出す」ことで記憶が促進される現象は「テスト効果」と呼ばれています。
テスト効果が生じるのは、「思い出す」という処理を行うことで、細胞同士のつなぎ目であるシナプスを増強させるからだと考えられています。
したがって、試験の前に自分で小テストを作って解くのは、積極的に情報を思い出すことで学習が促進されるため、効果的な勉強法だといえます。
方法④自分と関連付ける
単語を覚える時、ただ音で覚えたり形で覚えるよりも、自分と関連付けたほうが記憶成績が優れていることが分かっています。
これを「自己関連付け効果」と呼びます。(参考:堀内 考「エピソード記憶と自己―自己関連付けをめぐる問題―」)
ある言葉に対して、「『自分の性格や特徴にあてはまるか?』と考える」「ある知識から自分の過去の経験を思い出す」などで自分と知識を関連付けることができます。
また、身体の動きと関連付けることで、言葉に関する記憶が促進されることが分かっています。
「指を組め、ドアを指せ」などの動作を示す文章を示した後に、その動作を実演した人の方が文章をよく覚えていた、という研究があります。(参考:Zimmer「Action events in everyday life and their remenbering.」)
この現象のメカニズムには様々な説明が存在します。
「身体で覚える」というのは、運動スキルだけでなく、言葉の知識にも有効なのです。
ある言葉を覚えておきたい時、身体で軽く実演することがオススメです。
方法⑤意味を理解する
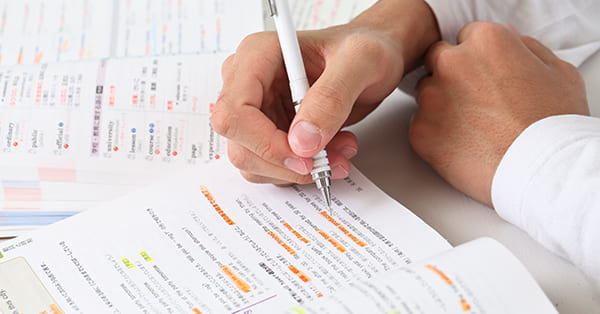
暗記したい時は、暗記したいことの内容をできる限り理解して覚えるようにしましょう。
知識は、意味のある単語同士でネットワークをつくることによって蓄えられているという説が有力です。
単語の意味を理解することで近い概念同士が結びつき、記憶のネットワークが活性化されるため、長期記憶に定着すると考えられています。
暗記しにくい例を紹介します。
3.14よりも長い範囲の円周率を覚えようとしたことはありますか?
ある場合、おそらくは、「さんてんいちよんいちごーきゅーにー」など「意味のない、音の塊」で覚えようとした方も多いはずです。このように、数字や意味のない羅列を丸暗記しようとすると、覚えるにも限界があるのです。(参考:Collins & Loftus「A spreading-activation theory of semantic processing.」)
方法⑥内容に興味を持つ
内容に興味を持つことはすばやい暗記に繋がります。
暗記自体を楽しむだけでも、記憶は促進されます。何かを覚える時に感情が動けば、その情報は重要なのだと脳が認識するのです。
例えば、好きなキャラクターの名前などは簡単に覚えることができますよね。それと同じように、なるべく楽しみながら暗記するようにしましょう。
ただし、作業記憶が働くためには落ち着きが必要です。楽しむにしても穏やかな楽しさが重要であるそうです。(参考:安藤 則夫・長谷川 修治 「『楽しさ』と『反復練習』は記憶強化に役立つか?―外国語が身につく学習方法について考える―」)
方法⑦適度な休息をとる

暗記には、適度な休息が不可欠です。
例えば、テスト前日の一夜漬けでなんとか覚えられるのは、覚えようとしてすぐに睡眠をとることで情報の干渉が少ないからだという理由が考えられます。
しかしながら、記憶を長期的に定着させるためには、こまめに休息を取り、集中力の高い状態で学習を進めることが大切です。
学習後に睡眠をとると、情報の理解や問題解決のパフォーマンスが向上するという研究結果もあります。(参考:De Vivo et al., 「Ultrastructural evidence for synaptic scaling across the wake/sleep cycle.」)
詰め込み学習をできるだけ避け、休息をとりながら学習をすすめましょう。
効果が薄い暗記方法2選
この章では、一般的に広がっている学習方法のなかでも、学習の効果が薄い暗記方法を解説します。
暗記を頑張っているがなかなか効果がでないという人は、自分の学習方法を改善するヒントにしていただければ幸いです。
ただし、人の特性は実にさまざまです。
ここで紹介する暗記方法が自分にとってなじみ深く、スタイルに合っている人もいると思います。そうした人は、この方法を無理にやめる必要はありません。参考程度に考えてみてください。
NG①一回の暗記に時間をかける

こちらでも解説しましたが、暗記の鉄則は、なんども繰り返すことです。
一度の暗記に時間をかけても、適切なタイミングで思い出すことは難しいとされています。
忘却のメカニズムの一つに「干渉説」があげられます。干渉説とは、一度覚えたことに他の情報が干渉して、忘れてしまうという説のことです。
完璧に覚えたとしても他の情報が入り込んできたら忘れるのは仕方がありません。定期的に振り返って、脳に「この情報は重要だ」と認識させることが大切なのです。
NG②単語を書いて覚える時に色にこだわる
英単語などを覚える時、赤色のペンを使って赤シートで隠したり、青色のペンでひたすら書いたりする人は多いと思います。
しかしながら、英単語とその意味は赤や青で示すのではなく、黒で示すのが最も効果的であるという研究結果があります。
すなわち、書いて暗記しようとする時にあえて色ペンを使用する必要はないということです。
英単語とその意味が赤で書かれていて、赤シートで隠すタイプの単語帳は暗記できる量が減る可能性があります。暗記したい時に赤色を使用するのは避けた方がよいでしょう。
また、青のペンを選択した場合は短期記憶と長期記憶の両面であまり効果がないとされています。ただし、青色には鎮静効果があるため、暗記の量よりもまず集中力を高めたいという場合にはよいそうです。(参考:藤原 采音「英単語の記憶と色の関係 ─英単語を効果的に暗記するために ─」)
お悩み別の暗記方法〜場面別に解説〜
この章では、認知心理学に基づき、お悩み別の暗記方法を解説します。(参考:山田 祐樹・日本語版監修、ヤナ・ワインスタイン、メーガン・スメラック、オリバー・カヴィグリオリ『認知心理学者が教える最適の学習法―ビジュアルガイドブック―』)
場面①速攻・短時間で暗記したい時
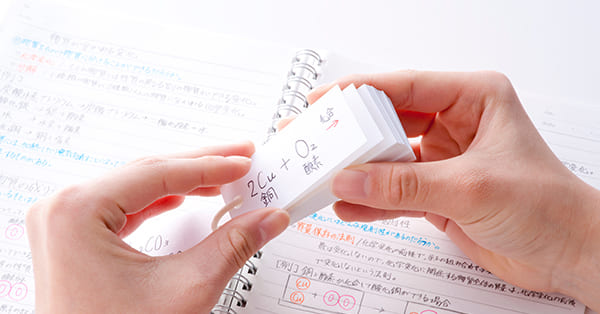
もうすぐテストがあるという人や、とにかく楽に暗記したいという人にオススメなのは、目で見ながら音読し、覚えた内容を後から紙に書き出したりして何度も思い出すことです。
暗記用の赤フィルターや暗記ペンは必ずしも必要でなく、黒い文字をただ見るだけでも暗記できることが研究から分かっています。
この時、以下の3つのポイントに注意してください。
- 必ず何回も繰り返すこと
- ぼーっと眺めるのではなく、自分と関連付けて考えながら覚えること
- 一回の周回に時間をかけないこと
ゲームのアイテムを集めるために、同じステージを何度も繰り返すことをイメージしてください。繰り返せば繰り返すほど、脳が重要な情報であると認識して、記憶に定着します。
繰り返し読むだけでも効果はありますが、それよりも大切なことは、たとえ頭の中だけでも内容を何度も思い出すことです。
「読んだ回数」より「思い出した回数」を意識して暗記するようにしましょう。
学習していて集中力が切れそうな時には、部屋を歩き回ったり、軽く運動しながら覚えるとより効果的です。
場面②少ない情報を確実に暗記したい時
少ない情報を確実に覚えたい時にオススメなのは、テスト形式で記憶を確認し、間違えたところだけ整理しなおす方法です。
テスト形式で記憶を確認することは、暗記の進み具合を客観的に把握するだけでなく、記憶の定着にも役立ちます。
また「苦手なところを重点的に整理する」というのは、途切れた回路を繋ぎなおすような役目があり、非常に効果的な暗記方法です。
人間が物事を忘却するメカニズムとして、細部の情報は省略されやすく、似た概念は混同しやすいという特徴があります。
自分と関係のあることは覚えやすくても、はじめて知ることや、複雑に思える情報は覚えにくいという経験がありませんか?
充分繰り返して暗記したことでも、自分にとって馴染みのない概念は知識のネットワークが活性化していないため、記憶の定着が弱くなります。
英単語ならば、一度小テストを自分で作り、間違えた単語のみ復習をしましょう。この時、イラストを描いて視覚的に表すのも効果的です。
ただし、まとめノートにたくさんの時間をかける必要はありません。黒のペンで簡単に整理しておくのが効率的です。
場面③理解をともなって記憶したい時

理解しながら覚えたい時には、人に説明するのが効果的です。特に歴史の勉強など、「なぜそうなったのか?」という流れが重要な情報には強力です。
深く理解できていないものは説明できませんし、説明しているうちに自分が分かっていない部分に気付くことができます。
人に説明しようとする時、ただの文字が意味のある情報へと変化します。一般的に、無意味な情報よりも意味のある情報の方が記憶に定着するとされているので、この方法は効果的なのです。
ちなみに、授業相手はぬいぐるみやフィギュアなどでも代用可能です。
まとめ〜最も大切なことは何度も学習を繰り返すこと〜

暗記する際に最も大切なことは、一度で覚えようとせず、何度も学習を繰り返すことです。
あなたにとって取り入れやすい方法を日々の学習に活かしていただけると幸いです。
Q&A よくある質問