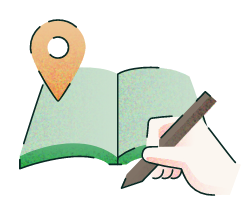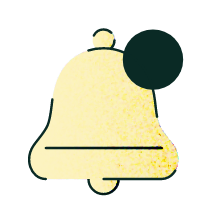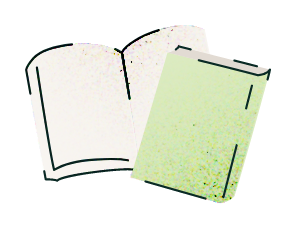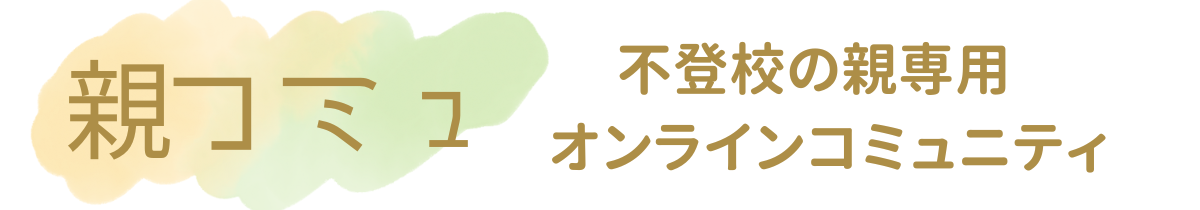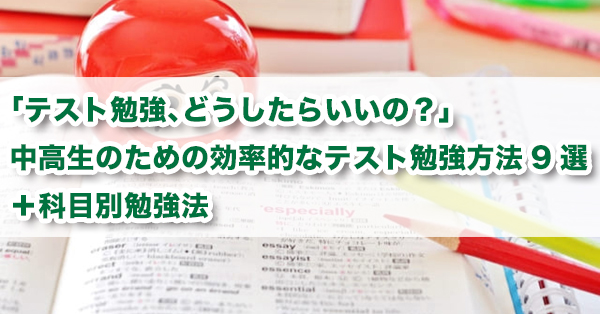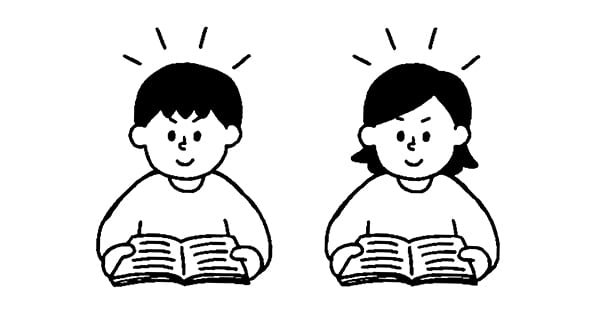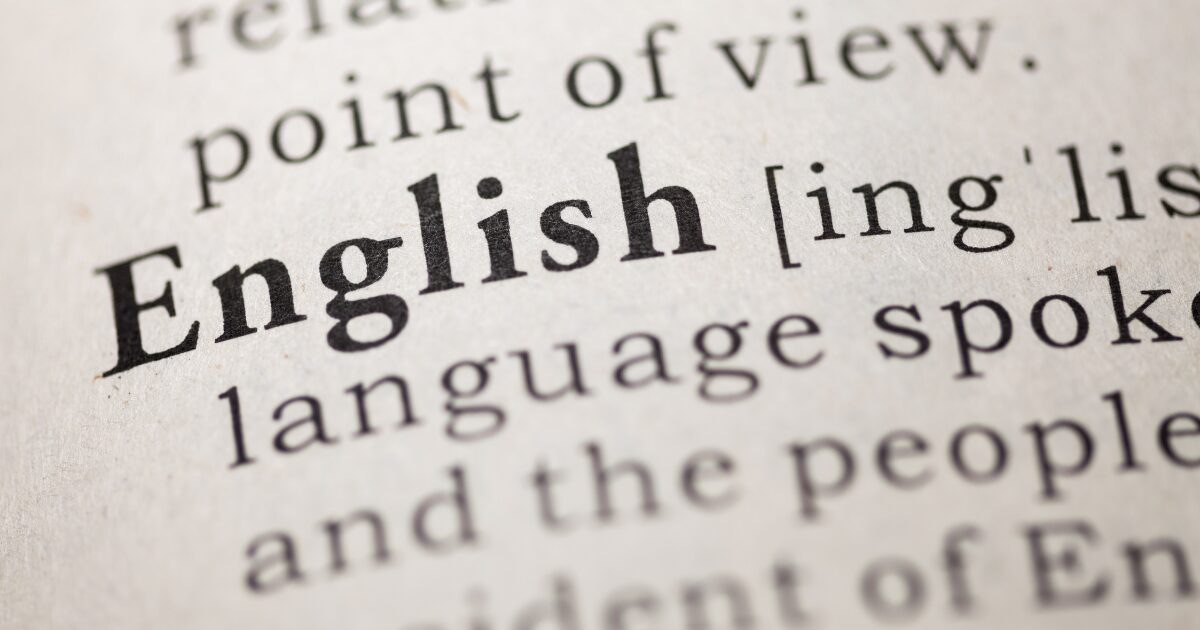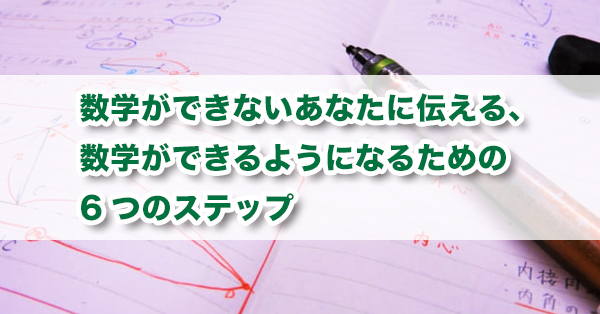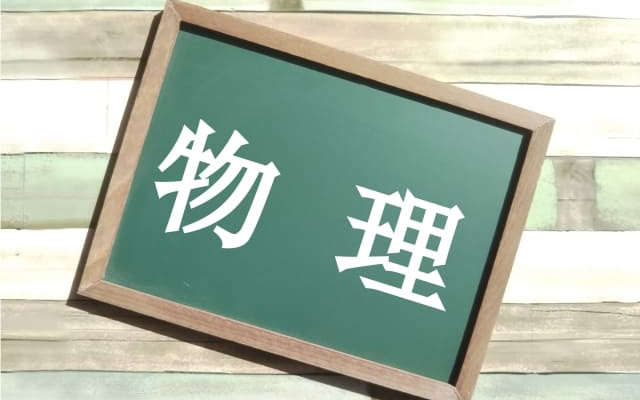現代文が苦手なあなたへ オススメの勉強法を解説
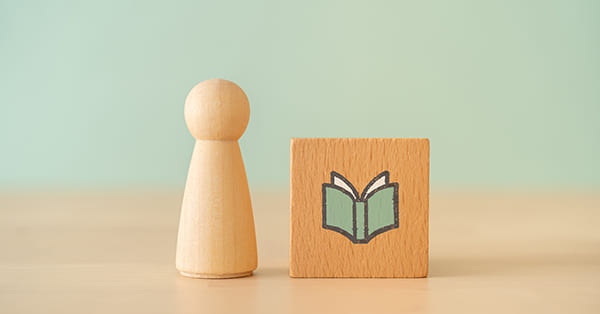
こんにちは。一人ひとりに合った現代文の勉強法を一緒に考える完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
このコラムでは、元国語教師として、現代文という科目のお話をしようと思います。
このコラムの内容は、やや高度な内容を含むため、難しく感じるかもしれません。難しく感じた方は、現代文の勉強をし始めませんか?
反対に、この文章がスラスラ読めれば現代文読解力はついているも同然です。
それなのになぜか成績が上がらないという方は、解答のテクニックが身についていないのかもしれません。そんな方も、ぜひ勉強してみましょう。
成績が上がると同時に、よりよく生きることができるようになると思います。
私たちキズキ共育塾は、現代文の勉強方法がわからない人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
現代文はちゃんと勉強すれば解けるようになる
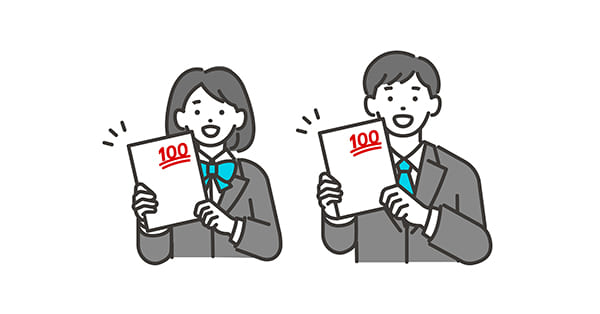
私が現役の教員時代には、生徒さんから次のようなことをよく言われました。
- 現代文は勉強しても成績が上がらない
- 現代文はセンスで解くものでしょ?
断言しますが、現代文はセンスや感覚で解くものではなく、論理的に解くものです。
センスで解いているように見える人にも、論理的な解き方が身についているのです。
これは、現代文に限らずどの科目においても同じことです。
ただしもちろん、論理的思考力があっても、知識がなければ問題は解けません。これもどの科目にも言えることです。
現代文の場合、どんな知識が必要かということをまとまったかたちで教えられていないことがほとんどなので、勉強しても解けないと思われがちなのです。
例えば現代文は勉強しても成績が上がらないと言う人に詳しく話を聞くと、こんなことを言います。
- 数学や英語は問題演習すればするほど解けるようになるけど、現代文はそうではない
- 同じ文章は二度と出ないし、問題を解く意味が感じられない
これは本当でしょうか。
まず、大学受験の現代文の試験で同じ文章の同じ部分が使われることはよくあることです。あなたが同じ文章に二度出会っていないのは偶然です。
英語や数学では同じような問題によく出会うと感じる場合、それはあなたが英語や数学の過去問はよく解いているけど、現代文の過去問はあまり解いていないということかもしれません。
次に、問題を解く意味を感じられないについてはどうでしょうか。
英語や数学で問題演習をすれば解けるようになるのは、問題を解いた後、なぜ間違えたのかを振り返って学習するからです。
英語で解答を間違えたのは、英文が読めていなかったから、正しく理解できていなかったからだと思い、単語や熟語・構文の見直しをしますよね。
数学でも公式の使い方を確認したりしますよね。それが現代文ではなぜか行われないことが多いのです。
あなたは、現代文のテストや模試の結果をきちんと見直し、なぜ間違えたのかを確認していますか?
読めているのになぜか解けなかった、と思っていませんか?
そこであえて問いますが、あなたは、本当にその文章が読めていますか?
英語で言うところの単語や構文、数学で言うところの公式などをきちんと理解し、読めていますか?
日本語を母語としている人が日本語の文章は読めると思うのは当然ですが、実際には読む技術を身に着けていない=解く技術を身に着けていないから解けないわけです。
現代文の勉強の第一歩は語彙力
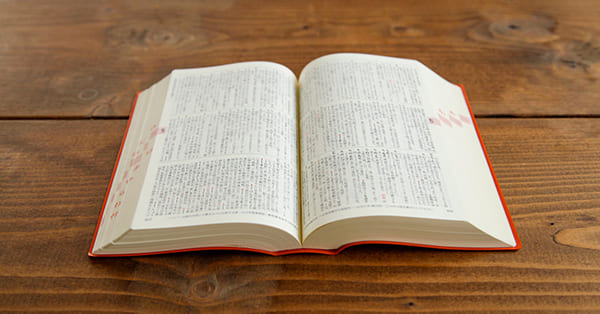
例えば、日本語による日常会話が難なくできても、受験現代文の文章には、日常会話では使わない言葉や表現がたくさん出てきます。
例えば、以下の例文を見てみましょう。いずれも現代文の評論で頻出の執筆者による文章です。
黄色いマーカーのある言葉や表現の意味を、きちんと理解し説明ができますか?
できないものは、辞書で調べて覚えようとしていますか?
フロイトなら、これを幼児が理由もわからずに母親から拒絶される原体験に遡行して考えるかも知れない。
(参考:柄谷行人『反文学論』)
要するに現実の言語では、あるクレタ島人が「すべてのクレタ島人は嘘つきである」と言ったとして、実際にここにいわれているようなアポリアやパラドクスを受けとって困るような人は一人もいないのだ。
(参考:竹田青嗣『哲学ってなんだ』)
ニュートンにとって、彼の理論の正しさは、世界のいたるところに遍在する神によって支えられていたのである。
(参考:廣重徹リ『近代科学再考』)
どうでしょうか。わからなかったら、辞書を引いて調べてみましょう。
英単語の勉強をするのと同じく、現代文の単語も、勉強しなければ受験現代文を読めるようにはなりません。
現代文の勉強の第一歩として、語彙力を強化するところから始めるのがよいでしょう。
現代文で必要なことは文章が書かれた背景への理解を深めること
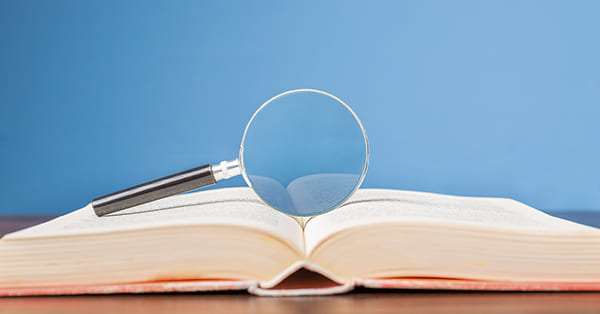
語彙力を強化するだけでも読める度合いは上がりますが、実はもう一つ、もっと大事なことがあります。
それは、文章が書かれた背景への理解を深めることです。
当然の話ではありますが、現代文とは、現代のことについて書かれた文章のことですね。
そして現代のこととは、より詳しく言えば現代が抱える問題点のことです。
ですから、現代が抱える問題とは何か、またそれが生まれた原因は何か、といったことを知っていれば、文章を把握することが容易になるのは言うまでもないでしょう。
もちろん現代が抱える問題とは挙げればキリがない程に存在しますし、その原因も単純明快なものではありません。
例えば、一つの出発点として近代化という概念を押さえることがとても重要です。
一般的に近代化とは、17〜19世紀に起こった産業革命およびそれに伴う市民革命」以降の考え方の枠組みのことを指します。誤解を恐れずに単純化すれば、理性的な人間中心主義の時代が近代です。
現時点で、近代化がどういう意味かよくわからないかもしれません。おおよそそういうものがあるのだなと思ってもらえれば結構です。気になるのであれば、ぜひ調べてみてください。こちらでも解説しますが、わからない言葉が出てきたら都度調べていくといいでしょう。
近代化によって、植民地主義が生まれ、世界大戦が勃発しました。これによって、自然環境破壊が生まれました。
もちろん、人が人を支配したり、闘争が起こったり、自然と対峙したり、ということは太古の昔からありましたが、昔のそれと現代のそれでは、問題点が異なるということです。
問題の出発点を理解していなければ、核心を捉えることはできません。
さらに現代ではポストモダン(近代の後)ということも言われて久しく、問題はより複雑になりつつあります。
その複雑化したあらゆる問題の解決へのヒントを探る文章が、現代文なのです。
まずは、どんなテーマがあるのか、ということだけでも押さえておくと、ずいぶん読み方が変わってくるでしょう。
その中で、自分の興味がある分野から、少しずつ知識を増やしていくのがよいと思います。
例えば、限りあるエネルギー資源に対する姿勢を問う評論文はこれまでもたくさんありました。
産業革命以降、工業が活発になりエネルギーを大量消費したことで資源が枯渇してきたからです。
さらに近年では、原発問題とも絡んで大きなトピックとなっています。
また、文化・文明の違いを乗り越えグローバル社会にどう対応していくかということも議論されて久しいです。
文化・文明的衝突が世界中で頻発し、予断を許さない状況となっている昨今、知っておきたいテーマの一つです。
あるいは、女性の活躍についてどう考えるか。情報化社会についてどう考えるか。
などなど、これらは総合型選抜入試をはじめとした小論文課題でも頻出のテーマです。
最近では、これらの主要テーマと語彙が一気に勉強できる簡便な参考書もたくさん出ています。一冊手元にあるとよいでしょう。
参考書については、こちらで紹介します。
現代文のおすすめの勉強法3選
この章では、現代文のおすすめの勉強法を解説します。
現代文でなかなか点数が伸びないという人は、以下の勉強法を試してみましょう。
勉強法①わからない言葉は辞書で調べる
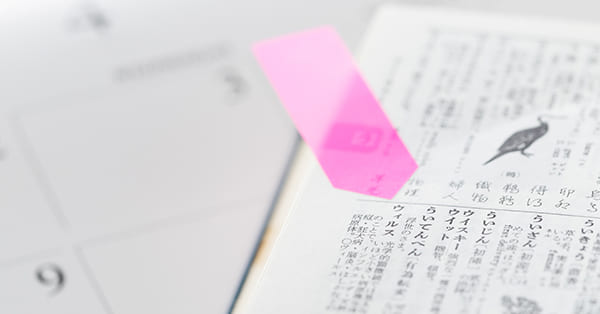
現代文を勉強する上で大切なことの一つは、わからない言葉が出てきたら辞書で調べることです。
こちらでも解説しましたが、現代文には難しい言葉や専門的な言葉が使われることがあります。それらを理解するためには辞書が頼りになります。
辞書を使うことで、わからない言葉の意味を調べるだけでなく、その言葉がどのような文脈で使われているのかも理解できるでしょう。
これによって、文章全体の意味や流れを把握できます。また辞書を使うことで、わからなかった言葉の類義語も学べるでしょう。
現代文の勉強では、辞書を頻繁に使うことが必要です。辞書を使ってわからない言葉を調べる習慣を身につけると、文章の理解力が向上し、より深い読解ができるようになります。
「知らない言葉だらけで辞書で調べてたら間に合わない…」とお悩みの方は、こちらで紹介する現代文キーワード集を併用するといいでしょう。
現代文の評論文で頻出の単語がまとめられているため、辞書で調べる時間を短縮できるかもしれません。
勉強法②筆者の主張や登場人物の気持ちにはチェックをつける
論説文や説明文は、筆者の主張に線を引いてみましょう。
文章が長くなると、どうしても文章全体のポイントがわからなくなります。筆者の主張に線を引いておけば、すぐに文章全体の主張が振り返れます。
こちらでも解説しましたが、現代文とは、現代のことについて書かれた文章のことです。そして評論文は、その文章で取り扱う現代のことに対する筆者の主張を表現を変えて繰り返し論じている文章であると言えます。
文章内で同じ内容を示している箇所が複数あるのであれば、それが筆者の主張です。そういった評論文の構造に気付ければ、正答率も高まるでしょう。
記述問題では筆者の主張をまとめる問題も多いため、自分で線を引いた部分を活用できるはずです。文章の内容理解だけでなく、設問の解答にも役立つわけです。
物語文は、登場人物の気持ちに線を引いてみましょう。物語文は、登場人物の気持ちや気持ちの変化を問われることが多くあります。
その際のヒントの1つとして、情景描写があります。情景描写は、登場人物の気持ちや気持ちの変化を印象づけたり、その後の展開を暗示したりするものとして書かれます。
これは、過去に実際のセンター試験(現:大学入学共通テスト)で出題された内容なのですが、夕暮れの海を見つめている老婆に関する情景描写があった場合、あなたにはどのようなイメージが浮かびますか?
もしかしたら、物寂しい、悲しいなどのネガティブな印象を受けたかもしれません。まさしく、この情景描写は、老婆の死の暗示を意図して書かれた文章でした。
このような情景描写を意識しつつ、その前後に書かれた登場人物の気持ちに関する文章には線を引くようにしましょう。
その際に線を引いた部分を活用することで解答できます。ぜひ実践してみてください。
勉強法③指示語や接続詞を意識して文章を読む

文章を読む際に、指示語や接続詞に意識を向けることは非常に重要です。
指示語は、物事や人物を指し示す言葉です。たとえば、「これ」「それ」「あれ」などが指示語になります。
これらの言葉は、前後の文脈から何を指しているのかを理解する必要があります。文章を読む際には、指示語がどのような意味を持っているのかを把握することが大切です。
接続詞は、文や文と文をつなぐ役割を持つ言葉です。たとえば、「だから」「そして」「しかし」「また」などが接続詞になります。
これらの言葉は、文章の流れや関係性を示す役割を果たしています。文章を読む際には、接続詞がどのような関係性を示しているのかを理解することが重要です。
こちらでも触れたとおり、現代文において重要な筆者の主張は、表現を変えて繰り返し書かれていると解説しました。
例えば、「だから」などの接続詞などを使って、前の文章から結論を導く順接表現などがあります。「〇〇はAである。だから、Bなのである」と書かれていた場合は、「Bなのである」が筆者の主張である可能性が高いです。
また、文章によっては、「しかし」などの接続詞などを使って、対比の関係を示す逆説表現で書かれていることもあります。
「一般的にAと言われている。しかし、実際はBである」と書かれているのであれば、筆者の主張は「実際はBである」という点になるでしょう。
指示語や接続詞を意識して文章を読むことで、文章の意味や流れをより正確に把握できます。また、文章の論理的な構造や関係性を理解できるため、より深い理解が可能となります。
指示語や接続詞を意識して文章を読むことは、文章理解力を高めるために非常に効果的です。ぜひ、日常の読書や勉強の中で意識してみてください。
現代文でやってはいけない勉強法3選
この章では、現代文のおすすめしない勉強法とその改善方法を解説します。
現代文ではやってはいけない勉強法があります。
もし、このような勉強をしている場合は、改善していきましょう。
NG①漢字や知識の勉強に時間を割かない

漢字や知識の勉強に時間を割かないことは、現代文の勉強においてはNGです。
文章を理解し、自分の意見を的確に表現するためには、漢字や知識をしっかりと学ぶ必要があるからです。
たとえば、論説文や物語文などの文章を読むと、専門的な言葉や漢字がよく出てきます。これらの言葉や漢字の意味を知らないと、文章の内容を正しく理解できません。
現代文の勉強には、漢字や知識の学習に時間を割くことが大切です。漢字の読み方や意味について積極的に学んでいきましょう。そうすることで、より深い理解を身につけられます。
ただし、大学受験レベルの文章には、日常で用いることが少ない難読漢字も多数使われている可能性があります。そういった難読漢字については、こだわって調べすぎず、適度に自分なりのペースで勉強を進めましょう。
NG②解説を読まないで直しを行う
現代文の答え合わせのとき、解説を読まないのはNGです。逆に、解説を読んで間違いを理解することが非常に重要です。
解答とただ比較するだけではなく、なぜ間違えたのかを理解することで、次回の試験やテストで同じ間違いを繰り返さないようにできます。
解説を読む際には、まずは自分の解答と比較しましょう。どのような点で間違えたのか、どのような情報を見落としたのかを確認した上で、正しい解答や解法を理解するために、解説をじっくり読みましょう。
解説には、問題のポイントや解法の手順が詳しく説明されています。それぞれの解答の選択肢がなぜ正しいのか、またなぜ間違いなのかを理解することが重要です。
解答の根拠となる具体的な文や表現を覚えることで、同じような問題に出会った際に正しい解答を選べます。
また、解説を読むだけでなく、自分の解答に対して反省点を見つけましょう。どのような知識やスキルが不足しているのか、どのように学習を進めればよいのかを考えることが重要です。解答の間違いを振り返り、次回に生かしましょう。
正しい解答を見つけるだけでなく、解説を読んで問題を理解することは、現代文の成績向上につながります。解答の選択肢を比較するだけではなく、問題文や解答の根拠を理解することで、より深い読解力や論理的思考力を身につけられます。
ただし、解説が充実していない参考書や過去問も少なからず存在します。そういった場合は、学習塾や家庭教師に個別で相談するといいでしょう。
NG③文章の意味がわからなくてもそのままにしてしまう

文章の意味がわからないところをそのままにしておくのはNGです。
現代文の勉強をする上で大切なことは、文章の意味がわからなくてもそのままにせず、しっかりと理解しようとすることです。
現代文は、難しい表現や複雑な文構造が使われることがあります。そのため、文章を読むときには、まずはじめに全体の意味を把握することが重要です。
文章の結論や理由、具体例や結論など、文章の流れを追いながら読むと、より理解しやすくなるでしょう。
わからない部分があったら、こちらで解説したとおり、辞書を使って調べてください。また、自分なりに要点をまとめることや、他の人と話し合うことも効果的です。そうすることで、自分の理解を深められます。
もちろん、大学受験レベルになると、難解な文章が多く存在します。きっとわからない文章も多く出てくるでしょう。
とは言え、わからないところにこだわりすぎると先に進めません。そういった場合は、その文章のおおよその意味を理解できれば問題ないと考えるのも大切です。
現代文の問題演習をする際の注意点3点
この章では、より具体的に現代文の勉強について解説するために、問題演習をする際の注意点について解説します。
問題演習をする際には、以下の3つのポイントに注意して行う必要があります。
注意点①時間を測って行う

現代文の問題演習をする上で大切なことの一つは、時間を測って行うことです。
現代文の問題は、文章を読んで理解し、それに対する適切な回答をすることが求められます。しかし、試験の際に、時間を測って行わないと、問題を解くための時間が足りなくなることがあります。
時間を測るためには、問題集や過去の問題を使って練習することが有効です。問題を解く際には、制限時間を設けて取り組むことで、実際の試験に近い状況を作れます。
また時間を測ることで自分のペースを把握できます。問題ごとにどれくらいの時間を使っているのかを把握することで、自分の苦手な箇所や時間をかけすぎている箇所を見つけられるでしょう。
時間を測って行うことで、現代文の勉強を効率的に進められます。時間を意識しながら問題に取り組むことで、試験本番でも冷静に対応できるでしょう。
注意点②間違い直しは、なぜ間違えたのかを考える
現代文の勉強において、間違いを直すことは非常に重要です。しかし、間違いをただ直すだけではなく、なぜその間違いが起こったのかを考えることも大切です。
間違いを直すためには、まず間違いの原因を理解する必要があります。
たとえば文章の解釈の間違い、設問の読み間違いなど、さまざまな種類の間違いがあるでしょう。
それぞれの間違いには、その間違いの起こった理由があります。間違いを直すだけでなく、その理由を考えることで、同じ間違いを繰り返さないようにすべきです。
繰り返し演習していくと、自分の間違いの特徴や間違いやすい問題の傾向も見えてきます。気持ちの読み取りで間違いが多いなら、登場人物の気持ちにチェックを入れて読むなど、改善していきましょう。
注意点③記述問題は添削してもらう

記述問題は自分で採点することも可能ですが、どうしても採点が甘くなりがちです。
また、採点の基準もあいまいになるでしょう。国語の記述問題は重要なワードやポイントが含まれていると、プラス何点というように基準があります。
国語の現代文の先生であれば、そうした採点基準がわかりますので、あなたの解答が何点で、どのようなポイントが抜けているか指摘できるはずです。国語の記述問題の添削は先生に依頼しましょう。
現代文の受験対策の2つのポイント
大学受験では、現代文は文系であれば必ず出題されます。また、理系の場合も国公立や私立の大学入学共通テスト利用型では共通試験で必要となるのが一般的です。
ここでは受験対策として大事なポイントについて解説します。
ポイント①過去問を解く
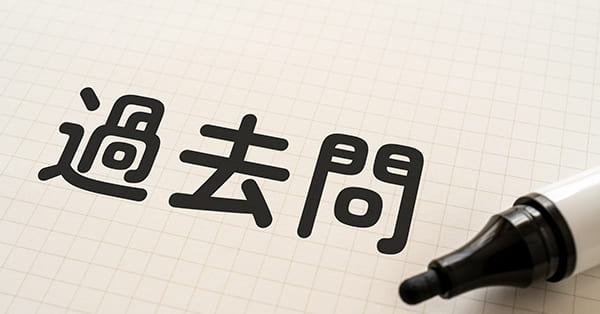
現代文の受験対策において、ほかの科目と同様に、過去問を解くことは非常に重要です。
過去問を解くことによって、現代文の出題傾向や問題の解き方を理解できます。過去に出題された問題であれば、実際の試験に近い形式で問題を解くことができます。
過去問を解く際には、まずは問題文をよく読み、問題の意図や要点を把握しましょう。
次に、問題用紙の余白などに自分の考えや意見を書き込み、論理的にまとめることが大切です。具体的な例や理由を挙げることで、自分の主張を裏付けられます。
解答を確認し、誤字や脱字、記入漏れや記入ズレがないかを注意深くチェックしましょう。
現代文の勉強では、過去問を解くことを積極的に取り入れてみてください。過去問を通じて、自分の弱点や改善点を見つけられるでしょう。過去問を解くことで、自信を持って現代文の試験にのぞめます。
2025年以降の大学入学共通テストでは、試験時間が10分増えて90分になると同時に、実用的な文章という資料読解型の問題が追加されると発表されています。
実用的な文章とは、契約書や報告書、グラフなどの実生活に関連性の高い具体的な目的達成のために作成された文章や資料のことです。(参考:文部科学省「【国語編】高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説」)
実用的な文章に関する問題については、当然過去問はありません。しかし、文部科学省は試作問題を公開しているため、部分的には対策が可能です。(参考:文部科学省「令和7年度大学入学共通テスト試作問題『国語』」 )
過去問に限らず、新設される問題に関する情報を集めながら、それらの問題についても対策をしていきましょう。
ポイント②記述対策を行う
現代文の試験の一部では、記述問題があります。記述問題がある場合、その対策は当然重要です。
文章を書く際には、文法や表現に気をつけることが必要です。文章を読みやすくするためには、簡潔で明確な表現を心がけましょう。
さらにこちらで解説しますが、文章の添削は先生に行ってもらいましょう。そうすることで自分の解答に何が足りないのか、わかるはずです。
現代文の勉強では、これらのポイントに注意しながら、練習を重ねることが大切です。
文章を読んだり書いたりすることで、文章の構造や表現力が向上します。受験対策のためにも、日常的に現代文の勉強を続けましょう。
現代文を勉強する際のオススメの参考書
この章では、キズキ共育塾の生徒さんがよく使っていた参考書を紹介します。
基礎から応用まで、幅広くご紹介しています。ご自分にあった参考書で学習を進めましょう。
参考書①『現代文 キーワード読解[改訂版]』

『現代文 キーワード読解[改訂版]』では、現代文に頻出するキーワードを160語が、科学・哲学・近代などのテーマ別に解説されています。
図解やイラスト付きで、抽象的なキーワードも視覚的に理解できるようになっています。
参考:Z会出版編集部・編『現代文 キーワード読解[改訂版]』
参考書②『ことばはちからダ!現代文キーワード』
『ことばはちからダ!現代文キーワード』では、現代文の読解に必要な重要語を解説しています。
入試に頻出のテーマも紹介されています。
参考:前島良雄、牧野剛、三浦武、吉田秀紀、後藤禎典『ことばはちからダ!現代文キーワード』
参考書③『読解を深める 現代文単語 評論・小説 改訂版』

『読解を深める 現代文単語 評論・小説 改訂版』では、テーマ別に現代文の頻出単語を紹介しています。
改訂に伴い、最新の入試評論文の傾向をふまえて、ポピュリズム、エスニシティなどの近年の入試で取り上げられやすい単語を追加されています。
参考:晴山亨、立川芳雄、菊川智子、川野一幸『読解を深める 現代文単語 評論・小説 改訂版』
まとめ〜テストのためだけではなく、「よりよく生きる」ために重要な現代文〜

現代文は、勉強できない科目、勉強しても意味がない科目ではなく、勉強すれば力がつく科目です。
このことを、頭にとどめてもらえればと思います。
さらに、テストで点が取れるだけでは、本質的には現代文は勉強しても意味がないという主張への答えになっていないかもしれません。
そこで最後に一言だけつけ加えると、現代文は、よりよく生きるためにも重要な科目です。
なぜなら、現代文を勉強することは社会と向き合うこととも言えるからです。
あらためて、現代文とは現代社会を反映した文章です。
自分が生きている社会が、どんな社会なのかを知らなければ、その中で自分がどのように生きて行きたいかをポジティブに考えることは難しいでしょう。
そして、現代を読み解き、その中で自分の望む生き方を言語化する力ひいては実現する力も、現代文の勉強によって養うことができる能力です。
私たちキズキ共育塾には、そういった背景知識を興味深く解説してくれる魅力的な講師がたくさんいます。ぜひ一緒に勉強してみませんか?
Q&A よくある質問