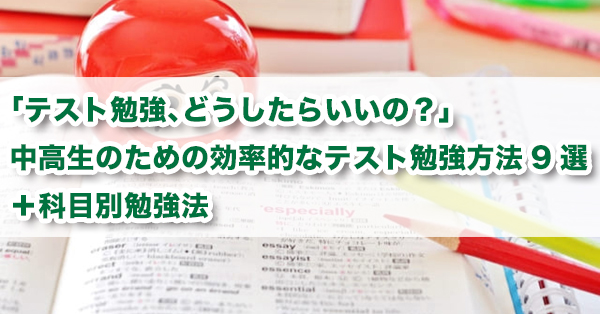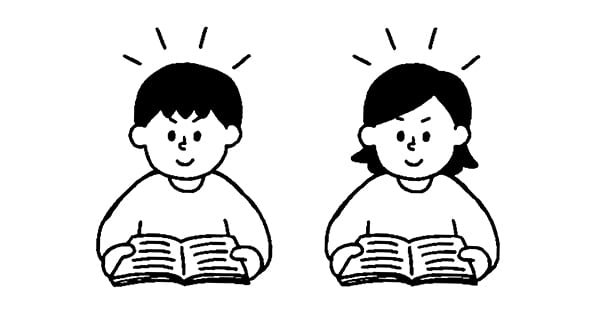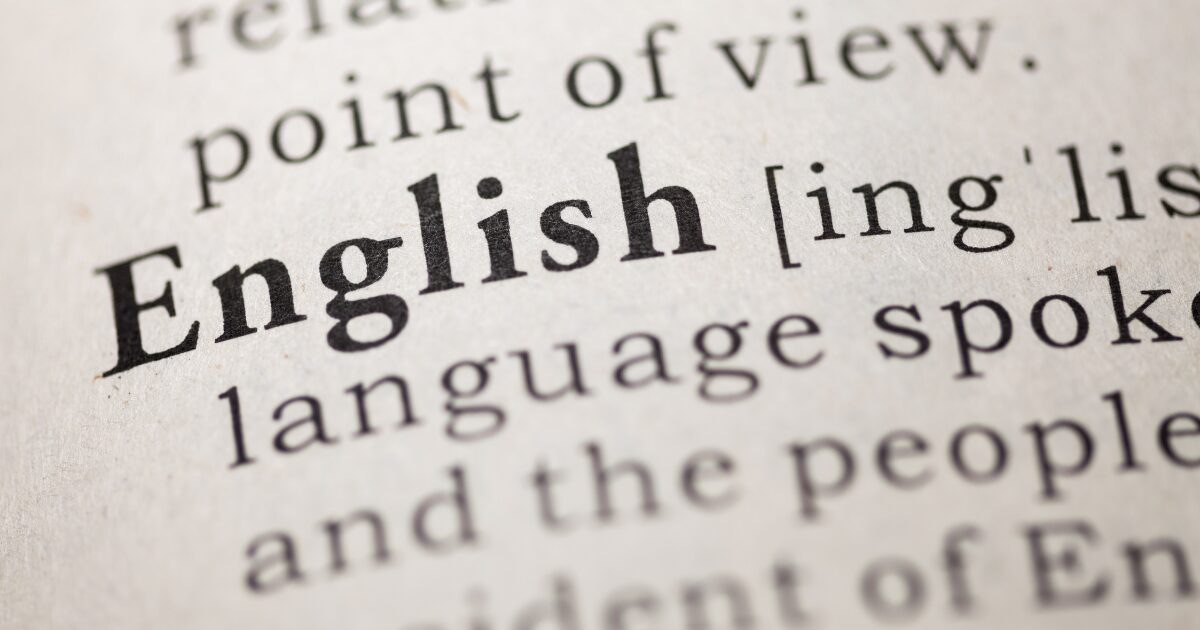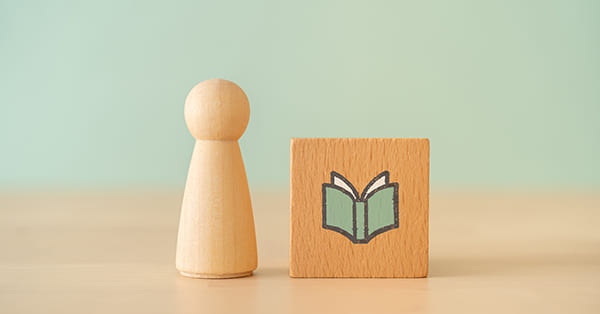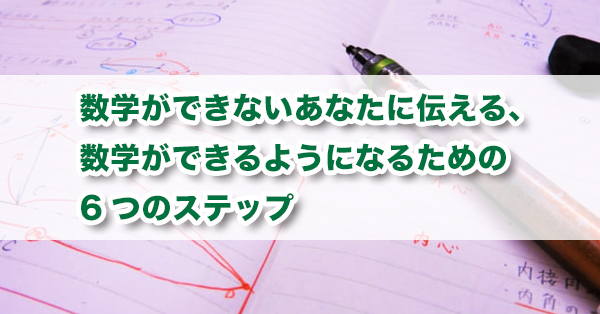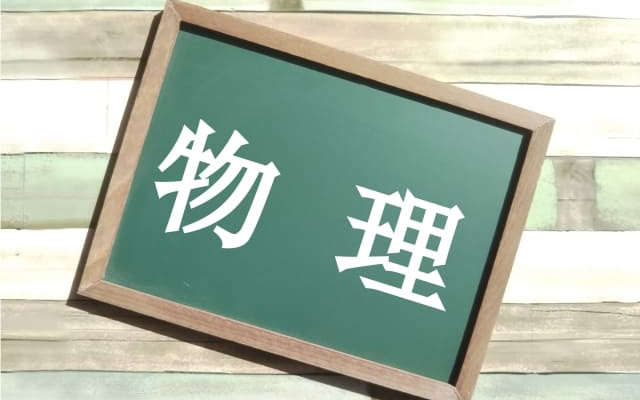古文が苦手なあなたへ 具体的な勉強方法を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたは今、古文の勉強に苦戦しているのではないでしょうか?
たしかに同じ言葉でも現代と意味が違ったり、覚えるべき単語が多かったりするなど、なかなか学習が進まないことはあるはずです。
しかし、古文もほかの科目の勉強と同様に、順を追って勉強すれば必ずできるようになります。
このコラムでは、元古文講師である筆者の知見から、古文の具体的な勉強方法や古文を勉強する際のコツなどを解説します。
私たちキズキ共育塾は、古文の勉強に悩むの人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
古文を勉強する目的
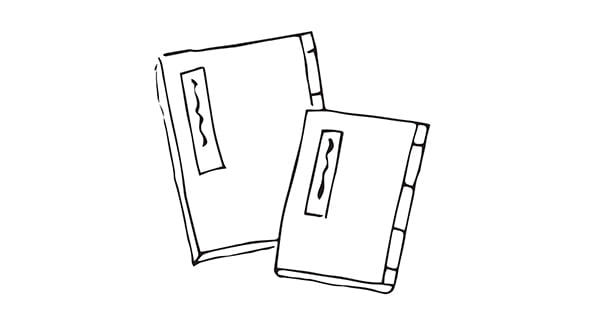
古文の勉強をする目的は、日本の古典文学や歴史への理解を深めることにあります。
古文では、日本語の歴史的な形態で書かれた、上代(飛鳥時代〜奈良時代、6世紀〜8世紀頃)から近世(安土桃山時代〜江戸時代、16世紀〜19世紀頃)にかけての文章や文学作品を読み解きます。つまり、古文の勉強を通して、日本の文化や歴史に触れられるのです。
しかし、日本の文化に触れることにどんな意味があるのでしょうか。
文部科学省が学校教育法などに基づいて定めている、教育課程を編成する際の基準である学習指導要領では、古典を学ぶ目標を次のように定めています。(参考:文部科学省「高等学校学習指導要領(平成 30 年告示)」)
第6 古典探究
1 目標
言葉による見方・考え方を働かせ,言語活動を通して,国語で的確に理解し効果的に表現する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1)生涯にわたる社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに,我が国の伝統的な言語文化に対する理解を深めることができるようにする。
(2)論理的に考える力や深く共感したり豊かに想像したりする力を伸ばし,古典などを通した先人のものの見方,感じ方,考え方との関わりの中で伝え合う力を高め,自分の思いや考えを広げたり深めたりすることができるようにする。
(3)言葉がもつ価値への認識を深めるとともに,生涯にわたって古典に親しみ自己を向上させ,我が国の言語文化の担い手としての自覚を深め,言葉を通して他者や社会に関わろうとする態度を養う。
(参考:文部科学省「高等学校学習指導要領(平成 30 年告示)」)
少し難しい内容になりましたが、以上の内容から古文を通して日本の文化に触れることが、次のようなことにつながることがわかります。
- 社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付ける
- 伝統的な言語文化に親しむ
- 昔の人々のものの見方や感じ方、考え方などを学ぶ
- 物事を考える力や共感力、想像力などを養う
- 言葉を通して他者や社会に関わろうとする態度を身に着ける
つまり、古文を学ぶことは日本の歴史や文化に触れるだけにとどまらず、生きていくうえで必要なさまざまな力を身に着けることにつながっているのです。
もちろん、大学受験のために古文の勉強をしなければならないということもあります。
しかし、受験科目であるという理由だけで古文を勉強しても、なかなかやる気が出ないと思います。
そんな時は、古文の勉強を通して学力以外にどんな力が身についたか、ものの見方や考え方が広がったか、などを意識すると、古文の勉強も将来に役立つかもと感じられるでしょう。
また、今とはまったく異なる昔の文化を面白がったり、1000年以上も前に生きた人が自分と同じ感覚を持っていたことに驚いたりしながら勉強すると、古文を面白いと感じられるようになるはずです。
古文の勉強の流れ

古文の勉強は、主に以下の3つの段階に分けられます。
この3つの段階を踏んで勉強することで、古文を読めるようになったり、問題を解けるようになったりします。
また、古文の勉強と聞くと、次のように思う人もいるでしょう。
- 古文が読めるかどうかって、センスじゃないの…?
- 自分にはセンスがないから、どうせ勉強しても変わらない…
そんなことはありません。
必要な知識をしっかりと暗記し、その知識を活用する方法を身に着けられれば、誰でも古文を理解できるようになり、大学受験でも高得点を狙えます。
もちろん、知識を身に着けていなくてもなんとなく読めるという人もいるでしょう。
しかし、なんとなく読めるだけでは、読める文章か・読めない文章かによって点数が大幅に変わり、受験本番で安定した点数を取ることは難しくなります。
なんとなくではなく知識に基づいて古文を読めるようになるためにも、インプット・アウトプット・大学受験対策の3つの段階を踏みながら勉強を進めましょう。
なお、どの段階についても、最初から常に完璧にできる必要はありません。
あなた一人で取り組む必要もありません。また、「これまで同じようなことをやってきたはずなのに、できるようになっていない…」という場合も、落ち込まないでください。
これは、この後に続く章についても同じです。学校や学習塾などの先生とも話しながら、これから少しずつステップアップしていきましょう。
古文の勉強方法〜インプット編〜
こちらでお伝えしたとおり、古文の勉強ではインプットが欠かせません。
この章では、古文の勉強の1段階目であるインプットの方法を解説します。
方法①古文単語を暗記する

古文の勉強は、まず古文単語を暗記することから始めましょう。
古文単語には、「あはれなり」「をかし」など現代では使わない言葉や、「あした」「ありがたし」など現代の言葉と意味が異なる言葉などがあります。
勉強し始めたころは、覚えづらいと感じるかもしれませんが、根気強く覚えていきましょう。
具体的な暗記方法としては、1日10単語を覚えることから始めましょう。
古文単語の意味はもちろんですが、言葉が使われる場面や言葉の成り立ち、単語帳に書かれているイラストなども一緒に確認しておくと、記憶に残りやすくなるのでオススメです。
また、一般的な大学を受ける場合に最低限必要な古文単語の数は約300単語で、英単語と比べるとかなり少ないです。そのため、1日10単語覚えれば1カ月で1周することができます。
ただし、1周目ですべてを完璧に覚えようとする必要はありません。1周目は45%、2周目は60%、3周目は80%と、少しずつ覚えられている単語を増やすことを意識すると、勉強を継続しやすくなるでしょう。
古文単語のオススメの単語帳については、こちらで紹介します。
方法②古典文法を覚える
古文単語と並行して、古典文法も覚えましょう。
古典文法も古文単語と同様に独特であり、現代の文法とは異なります。
例として、古文学習の肝とも言える、助動詞を挙げましょう。
たとえば、助動詞の「なり」は断定の助動詞で、「〜だ」という意味があります。
また、「けり」には「過去」の意味があり、「〜だった」という意味になり、「昔男ありけり」は「昔男がいた」という訳になります。
ほかにも、「今宵は十五夜なりけり」という文章が、「今夜は十五夜だなあ」と訳されるように、「過去」ではなく、「詠嘆」の意味として使う場合もあります。
このように、古典文法は非常に複雑です。しかし、しっかりと古典文法の暗記をできていれば、古文を正しく現代語訳することができます。そして、正しく現代語訳ができれば、問題も解けるようになっていくのです。
古典文法で、まず覚えるべきなのは、以下の4点です。
- 用言(動詞・形容詞・形容動詞)の活用
- 助動詞の意味・活用・接続
- 主要な助詞
- 敬語
「用言(動詞・形容詞・形容動詞)の活用」「助動詞の意味・活用・接続」については、活用表を使って覚えるのがオススメです。
手書きで構わないので空白の活用表を作り、その活用表に繰り返し書き込むことで少しずつ覚えられます。また、活用はリズムを刻みながら声に出すと覚えやすいでしょう。
「主要な助詞」については、基本的には問題を解きながら調べつつ覚えていきましょう。ただし、「係助詞」は「係り結び」として問題に出題されることが多いため、早い段階で法則や意味を覚えることをオススメします。
「敬語」は、主語を判別するために大きく役立つため、必ず覚えましょう。それぞれの意味はもちろんですが、「敬意の向き(誰から誰に敬意を表しているのか)」を理解することが必須です。
「敬意の向き」は理解が難しいため、解説がわかりやすいテキストを読み込んだり、学校の先生や塾の先生に解説してもらったりするようにしましょう。
また、時間に余裕がある場合は、和歌の修辞についても暗記しておくことがオススメです。
具体的な方法としては、古文の単語帳や文法書を使って単語や文法を学ぶことがオススメです。また、古文のテキストや問題集を使って練習することも効果があります。
古文の勉強は、継続的な努力が必要です。毎日少しずつでも勉強することで、徐々に古文の知識が身についていきます。
古典文法のオススメの参考書については、こちらで紹介します。
方法③古典常識を学ぶ

古典常識とは、古文の時代背景や書かれている内容を理解するために必要な知識のことです。
例えば、古文の世界には次のような常識がありました。
- 成人の儀を行うのは「10代前半」
- 結婚は同居ではなく「通い婚」
- 病気の原因は「物の怪」
このように、古文が書かれた時代は、身分による違いが明確であり、風俗や風習も現代とは全く異なります。
そのため、古文の世界を正しく理解するためには、古文が書かれた時代の常識を知る必要があるのです。
古典常識の勉強法は、古典常識専用の参考書を購入して読み込むことがオススメです。
古文単語や古典文法のようにしっかりと暗記する必要はありませんが、繰り返し読みながら理解を深めましょう。
また、問題演習を行う中で、知らなかった文化や風習に出会うこともあるので、その都度その文化や風習について調べるようにすると知識の幅が広がっていきます。
古典常識のオススメの参考書については、こちらで紹介します。
方法④文学史の主要な作品を押さえる
文学史の主要な作品を押さえることも、古文の勉強では役立ちます。
なぜなら、『源氏物語』や『徒然草』などの主要な作品は、古文の問題で出題されることが多く、その作品の基本的な情報を知っていると、文章を読みやすくなるためです。
作品への理解を深める際に押さえておきたいポイントは次の4点です。
- 作品名
- 作者
- ジャンル(物語、説話、日記・紀行、随筆、評論など)
- 大まかな内容(あらすじ、主要な登場人物など)
まずは、文学史専用の参考書を使って、主要な作品の作品名と作者を覚えます。作品が主要なものかどうかは、参考書で赤字や太字になっているものかで判断するとよいでしょう。
作品のジャンルも実は重要な情報です。例えば、作者目線で体験や感想などがつづられる随筆を、ジャンルを知らないまま物語だと思って読み進めると、混乱することになるでしょう。
「ジャンルは文章を読めばわかるのでは?」と思うかもしれませんが、知識として知っておくほうがジャンルの見極めを間違えることなく、文章を読む上での確実なヒントにできるのです。
作品の大まかな内容についても、大きなヒントになります。
予告を見た映画と何の情報も知らない映画とでは、内容のイメージのしやすさが大きく変わってきますよね。それと同様に、大まかな内容を知っているだけでも、古文の読解がしやすくなるのです。
また、大学によっては文学史に関する問題が出題されることもあるので、文学史を覚えることは過去問対策としても役立ちます。
方法⑤品詞分解をできるようにする

品詞分解とは、言葉のとおり、文章を「動詞・名詞・形容詞・形容動詞・助動詞・助詞」などの品詞ごとに分けていくことです。
例として、中学で学習する『竹取物語』の一節を使って品詞分解をしてみましょう。
今は昔、竹取の翁といふ者ありけり。
→今/は/昔/、/竹取/の/翁/と/いふ/者/あり/けり。
(名詞/係助詞/名詞/、/名詞/格助詞/名詞/格助詞/動詞/名詞/動詞/助動詞/。)
このように品詞分解をすることで、文章」というかたまりではなく、品詞ごとに認識できます。
そして、品詞ごとにインプットした古典文法と古文単語の知識を当てはめていけば、基本的な文章の意味を読み取れるようになるのです。
はじめは、スムーズに品詞分解できないかもしれませんが、何度も繰り返し行うことで、頭の中で自然とできるようになっていきます。
また、主要な作品であれば、ネットに品詞分解を行ったものが載っていることがあるので、慣れるまでは参考にするとよいでしょう。
古文の勉強方法〜アウトプット編〜
必要な知識をインプットできたら、次は覚えた知識を使って問題を解き、知識の使い方を覚えていきましょう。
受験勉強でよく言われることですが、どれだけ知識を蓄えてもその使い方を知らなければ、問題を解くことはできません。
例えば、数学の公式をどれだけ覚えたとしても、どの問題でどのように使うかわかっていなければ、解答は導き出せません。
古文においても同様です。どんなにたくさんの古文単語や古典文法を覚えても、使い方を知らなければ、古文を読めるようになりませんし問題も解けません。
この章では、古文の勉強の2段階目であるアウトプットの方法を具体的に解説します。
方法①インプットした知識+品詞分解で現代語訳の練習をする

古文のアウトプットは、インプットした知識と品詞分解を組み合わせて、現代語訳をする練習から始めましょう。
こちらで例に挙げた『竹取物語』の一節で、実践してみますので、参考にしてみてください。
今は昔、竹取の翁といふ者ありけり。
今は昔、:連語(今となっては昔のことだが、)
竹取:名詞(竹取)
の:格助詞(の)
翁:名詞(おきな・男の老人)
と:格助詞(と)
いふ:動詞・ハ行四段活用「いふ(言ふ)」連体形(いう)
者:名詞(人)
ありけり:動詞・ラ行変格活用「あり」連用形+助動詞・過去「けり」終止形(いた)
→今となっては昔のことだが、竹取の翁という人がいた
このように、品詞分解をしたものに、古文単語や古典文法でインプットした意味をあてはめていくと、現代語訳ができます。
はじめは正しく品詞分解できなかったり、知識が足りなかったりすることでスムーズに現代語訳ができないこともあるでしょう。
ですが、その都度調べてインプットしながら進めることで、スムーズに現代語訳できるようになっていきます。はじめは上手くできなくて当然という気持ちで開き直りつつ、根気強く取り組んでください。
方法②問題集を解いて問題の解き方を学ぶ
現代語訳の練習と並行して、問題集を使って問題の解き方を学んでいきましょう。
古文の問題集には、詩歌や散」、平安時代の文章、平安時代以降の文章など、さまざまな文章が載っています。
まずは、文章が短いものや中学の時に一度学んだことがある作品のものなどから解くと、取り組みやすいです。
ちなみに、筆者が古文の授業をしていたとき、はじめて古文を勉強する人にオススメしていたのは、一度は耳にしたことがあるであろう『百人一首』や『竹取物語』でした。
また、問題を解く際も、さきほど紹介したインプットした知識+品詞分解でじっくりと読み解いていくことで、本文の意味をつかみましょう。
問題集を解く際は、本文だけでなく設問も注意深く見るようにしてみてください。例えば、設問の中にも以下のようにさまざまな種類があるのです。
- 語彙:古文単語の意味を問う問題
- 文法:文法の知識を問う問題
- 主語:敬語などと絡めて動詞や会話文の主語を問う問題
- 現代語訳:本文の中の一文を現代語訳する問題
- 読解:本文の内容について問われる問題
どのようなことが問われるかが分かれば、どのような知識が必要か、本文を読むときに何に注意して読めばいいのかもわかってくるでしょう。
また、問題を解き終われば終わりというわけではありません。問題集には解答が載っているので答え合わせをし、足りない知識があればインプットしましょう。
その際に、古文単語帳や文法書、国語便覧など、古文の知識がまとめられている参考書にチェックを入れておくと、あとから確認しやすくなります。
加えて、解答に書かれている現代語訳を一通り読みながら、自分が考えていた訳と比べてみましょう。そうすることで、自分の理解が正しかったのかどうかを確認できます。
方法③記述問題の対策をする

志望している大学の受験で、古文の記述問題が出題される場合は、記述問題の対策を行いましょう。
古文の記述問題では、現代語訳の問題が出題されることが多いです。そのため、まずは知識のインプットと品詞分解で、正確に素早く現代語訳ができる力を身につけましょう。
また、記述問題の場合、省略されている主語や指示語の内容を補う必要があるので、現代語訳をする部分の前後の内容もある程度は品詞分解をして内容をつかむことが大切です。
現代語訳以外に、本文の内容について聞かれる記述問題もありますが、基本的に現代語訳をする力があれば対応できます。
ただし、解答を制限文字数内に収めたり伝わりやすい文章にしたりする必要があるので、慣れるまでは繰り返し練習しましょう。
また、問題集を使って記述対策をする場合、解答に採点基準が書かれています。採点基準を見れば、どういった部分が見られるのかがわかるので、記述対策のヒントにしましょう。
古文の勉強方法〜受験対策編〜
大学受験で古文を使う場合は、受験対策も必要です。
この章では、古文の勉強の3段階目である受験対策の方法を具体的に解説します。
方法①過去問を解き現状を把握する

過去問対策を行う前に、まずは過去問を解いて自分自身の現状を把握しましょう。過去問を解くと、次のことがわかります。
- 受験当日の目標点(正答率)と現状の差
- 差を埋めるために必要な勉強
- これまでの勉強での成長具合
このように、過去問を解くと、これからの勉強の方向性が見えてきます。
例えば、過去問を解いて本文が読めなかった人は、インプットの段階から改めて勉強をし直す必要があることがわかります。
本文は読めたものの時間がかかりすぎた人は、現代語訳の練習や問題演習を重ねる必要があるでしょう。
また、これまでまったく古文が読めなかったのに、少しでも読めるようになっていれば、これまでの勉強の成果を感じられるはずです。
そのため、「まだ過去問を解けるほど力がついてない…」と思っている人でも、受験対策を本格的に行う前に一度過去問を解いておきましょう。
方法②過去問から出題傾向を把握する
受験対策として、過去問から出題傾向を把握することも大切です。
受験対策といっても、受ける大学によって試験で出題される問題の形式はまったく異なります。
例えば、文法問題が複数出題される大学もあれば、問題のほとんどが読解問題という大学もあります。
また、本文の文量も大学によって大きく異なりますし、大学受験に頻出される作品がある大学もあります。
そのため、赤本の解説や5年分程度の過去問を見ながら、次のようなことを把握しましょう。
- 配点・試験時間
- 頻出作品・ジャンル
- 本文の長さ
- 設問の数
- 各設問の問題形式
ただし、古い過去問では、今と出題傾向が違っていることがあります。また、同じ大学・学部によっても、受験形式(公募・一般)や日程によっても異なる場合があるでしょう。
そのため、自分が受ける予定の大学・学部・日程が同じもので、できるだけ新しい過去問を分析しましょう。
方法③現代文・漢文との兼ね合いを考えて解答時間を決める

出題傾向を把握したタイミングで、古文の解答時間についても考えておきましょう。
大学受験では、国語の試験の中で現代文・古文・漢文が出題されることが多いため、古文の回答時間を決めるためには、現代文と漢文の時間配分も決める必要があります。
ネットなどに各大学の国語の試験の時間配分目安などが載っているかもしれません。ですが、あくまで自分の得意・不得意、必要な時間を踏まえて考えましょう。
どうしても自分で決められない場合は、学校の先生や学習塾の先生など、自分の学力や得意・不得意を把握してくれている人に相談することがオススメです。
また、現状で制限時間内に解けない場合は、どこで時間を短縮するか、時間を短縮するためにはどんな勉強が必要かなどを考え、具体的な対策を練りましょう。
加えて、解答時間を考える際には、受験当日に現代文・古文・漢文をどのような順番で解くかも考えておきましょう。
方法④制限時間を設定して5~10年分の過去問を解く
過去問演習は、事前に決めた制限時間にタイマーをセットして行いましょう。
ただし、はじめから制限時間内に解き切る必要はありません。はじめは、制限時間を意識することから始め、制限時間内にどこまで解けたかを記録しておき、制限時間が過ぎても解き続けましょう。
とはいえ、受験本番では制限時間内に解く必要があります。そのため、どこに時間がかかっているのか、時間短縮のためにどんな工夫ができるか、を試行錯誤しながら、解答時間を縮めていきましょう。
過去問はできる限り多く解くことが大切です。具体的には、5〜10年分の過去問を用意して解きましょう。
たくさんの過去問を解くと、その大学の試験の傾向を把握でき問題に慣れることができるからです。
また、たくさんの問題を解き、間違った問題や解けなかった問題を分析することで、自分に足りない知識や力が身についていきます。
ただし、こちらでも解説したとおり、古い過去問では今と問題の形式が大幅に変わっていることがあります。
また、受験形式や日程によっても傾向が異なることもあります。自分が受ける予定の大学・学部・日程の最新の過去問と似た傾向の過去問で演習しましょう。
また、併願校が多い人は、1つの大学の過去問演習に時間をかけすぎるのはよくないので、志望順位や問題の難易度などを踏まえて、何年度分の過去問を扱うかを決めましょう。
方法⑤過去問演習後は現代語訳と足りない知識のインプットを行う

過去問演習後は、答え合わせと見直しをして終わりではありません。本文の現代語訳を行い、足りない知識をインプットしましょう。
本文の現代語訳は、現代語訳をする力を養うことはもちろんですが、自分に足りない知識や抜けている知識をあぶりだすためにも役立ちます。
そのため、現代語訳をしていて、わからない単語や文法、知らなかった古典常識などが見つかれば、その都度覚えるようにしましょう。
また、現代語訳をしていて一度覚えた知識を忘れてしまっていたことに気付いた場合も、しっかりと覚え直すようにしてください。
ただし、ほかの科目の勉強などが遅れており、古文よりも優先すべき科目がある状況であれば、現代語訳をする範囲を狭めたり、回数を減らしたりするなどの工夫をしましょう。
方法⑥過去問は「全問正解」「解答理由を答えられる」まで繰り返し解く
過去問演習は、全問正解、解答理由を答えられる、まで繰り返し解きましょう。今の時点では「無理だよ…」と思うかもしれませんが、勉強していくうちにできるようになるはずです。
繰り返し解くことで、試験の傾向に慣れられるのはもちろん、必要な知識を記憶に定着させられるからです。
ただし、なんとなく答えを覚えていたから解けるではなく、解答の理由がわかった上で解けることが大切です。
解答を導き出すまでの過程を説明でき、必要な知識をしっかりとインプットできている状態を目指しましょう。
また、過去問を繰り返し解く際は、以下のことを記録することがオススメです。
- 点数・正答率
- かかった時間
- 誤答分析(問題を間違えた・解けなかった理由の分析)
専用のノートやシートを作って自分の成長を記録すると、モチベーションにつながります。
古文の勉強が苦手にならないための4つのポイント
ここまで、古文の勉強方法を解説してきましたが、古文に苦手意識があると「自分には無理かも…」と思うかもしれません。
しかし、少しの工夫で、古文への苦手意識をやわらげられたり、払拭できたりすることがあります。
この章では、古文の勉強が苦手にならないための4つのポイントを解説します。
ポイント①古文の土台はインプットであることを理解する

古文に苦手意識がある人は、「頑張って勉強しても古文を読めるようになる気がしない」と思っているかもしれません。
しかし、こちらで解説したとおり、古文は古文単語や古典文法などの基本的な知識をインプットすることで読めるようになります。
少し話はそれますが、英文を読むためには英単語や文法の知識が必要であることは、多くの人が理解しているでしょう。逆に、英単語や文法を勉強しないまま、英文を読もうとする人はあまりいないと思います。
古文でも同じことが言えます。古文は日本語ではありますが、現代の言葉とはまったく違うため、一から単語や文法を覚える必要があるのです。
言い換えれば、古文単語や古典文法などの必要な知識をしっかりとインプットし、それらの知識を使えるようになれば、古文は読めるようになるのです。
そのため、古文単語や古典文法などの基本的な知識がしっかりと身につくように、しっかりとインプットすることが大切です。
また、インプットの段階が一段落しても、問題演習ばかりに目を向けるのではなく、基本的な知識も定期的に復習しましょう。
ポイント②現代語訳は例文の真似ることから始める
古文の勉強の中で最も苦戦する部分が、現代語訳だと思います。
こちらで現代語訳の方法を解説しましたが、古文が苦手な人からすると、進んで取り組もうとは思えないでしょう。
そんな人は、問題集の解答として載っている例文の現代語訳を真似ることからはじめましょう。
具体的な方法としては、本文と現代語訳を照らし合わせながら、次のことを意識しつつ、現代語訳を書いていきましょう。
- どこで品詞分解ができるか
- どの単語とどの訳が対応しているのか
- どの文法がどの訳になっているか
- 省略されている部分はどこを見れば補えるか
また、次のように段階を踏んで現代語訳に慣れていくことがオススメです。
- はじめは本文と照らし合わせながら例文をそのまま写す
- わかる部分が出てきたらその部分だけ訳してみる
- 最終的にはすべて自分で訳してみる
ポイント③問題の解説と現代語訳が丁寧な問題集を選ぶ
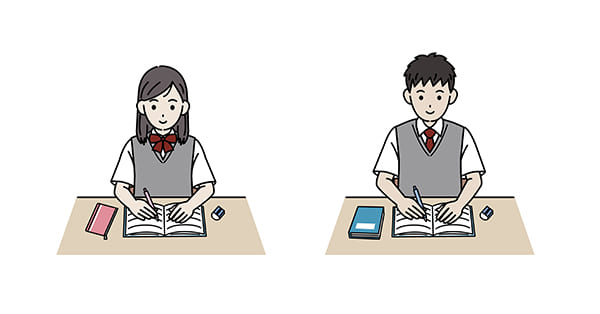
古文の勉強が苦手になる原因の1つとして、問題集などの解答を見ても意味がわからないということがあると思います。
問題集の中には、基礎的な古文単語や古典文法などの解説を省いているものがあります。
解説が丁寧でない問題集を使用すると、解答を見ても意味が分からず、古文の勉強を投げ出したくなるのも仕方ありません。
そのため、古文の参考書や問題集を選ぶ際は、解答の解説や現代語訳が丁寧に書かれているものを選びましょう。
また、時間に余裕がある場合は、書店に立ち寄って自分で問題集を手に取り、内容を確認してから購入することをオススメします。
ポイント④問題演習は短い文章から無理なく行う
古文の問題演習は、初めから長文の問題に取り組むのではなく、短い文章のものから解くようにしましょう。
短い文章の問題の方が、問題演習をすることへのハードルが低くなり、「これならやってみようかな」と思いやすくなります。
また、文章が短いと設問の数も少ない場合が多いため、問題を解く時間はもちろん、答え合わせや見直しの時間も短くなるはずです。
このように、自分のペースで嫌にならない範囲で取り組める問題から勉強を始めることで、古文の勉強を毎日継続しやすくなるでしょう。
基礎を学べる初歩的な問題集であれば、短い文章の問題がたくさん載っているので、演習を通して少しずつ古文に触れ、古文を読むことに慣れていきましょう。
古文の勉強を効率よく進めるための5つのコツ
この章では、古文の勉強を効率よく進めるための5つのコツを解説します。
受験本番までの日数が限られている、ほかの科目の勉強が大変で古文にあまり時間をかけられないという人は、ぜひ実践してみてください。
コツ①学習漫画などを活用して時代背景を知る

1つ目のコツは、学習漫画などを活用して時代背景を知ることです。
こちらでも解説したとおり、古文の読解において、時代背景やその時代の文化・風習などの古典常識を理解することは非常に重要です。しかし、あまり古典常識に時間をかけられない場合もあるでしょう。
そのような場合は、漫画で手軽に効率よく歴史を知れる学習漫画を活用することがオススメです。
例えば、平安時代について書かれている学習漫画を読むだけでも、『源氏物語』や『枕草子』などの世界観をイメージしやすくなるでしょう。また、平清盛や源頼朝などに関する学習漫画を読むと、『平家物語』や『源平盛衰記』などの作品への理解も深まります。
ほかにも、『竹取物語』『伊勢物語』『徒然草』など、作品ごとの学習漫画も出ているため、文学史の勉強に活用するのもオススメです。
また、少し話はそれますが、受験科目に日本史Bを使う人や学校で日本史を選択している人は、そこで学んだ知識を古文と結びつけると、さらに理解が深まります。
コツ②問題演習後は復習を忘れずに行う
2つ目のコツは、問題演習後は復習を忘れずに行うことです。
古文の勉強以外でも言えることですが、問題演習後に復習を行うことで、今の自分に足りないものが見えてきます。そして、その足りないものを補うための勉強をすることで、効率よく自分の弱点や苦手を克服できるのです。
具体的な復習の方法は、以下のとおりです。
本文の復習
- 本文を現代語訳する
- 解答例の日本語訳と比較して間違っている部分・足りない部分をチェックする
- 自分に足りない知識をピックアップしインプットする
問題の復習
- 解けなかった理由・間違えた理由を明確にする
- 理由への対策方法を考える
まずは、問題の本文を現代語訳したうえで解答例と比較し、間違っている部分・足りない部分をチェックしましょう。
例えば、敬意の向きが正しく理解できておらず、主語を間違えていた場合は、文法の敬語をインプットし直す必要があります。また、訳せない古文単語があれば、古文単語の参考書でチェックしたり、単語帳に追加したりしましょう。
問題の復習では、解けなかった問題や間違えた問題を見直し、解けなかった理由・間違えた理由を明確にします。そして、理由への対策を行いましょう。
例えば、文法問題で助動詞の意味が曖昧になっていて間違えたのであれば、助動詞を改めて復習することが必要です。また、設問の選択肢を十分に検討しないまま解答し間違えたのであれば、選択肢を消去法で選ぶ癖をつける必要があるでしょう。
このように、復習を行う際は、これからどんな勉強に取り組むべきかまで明確にし、今後の勉強のヒントにすると効率よく勉強が進みます。
コツ③記述問題は自分以外の誰かに添削してもらう

3つ目のコツは、記述問題は自分以外の誰かに添削してもらうことです。
自分の解答を自分で添削すると、次のように客観的な判断ができないことがあります。
- なんとなく模範解答に似ているから正解
- 解答には書いていないけど、書くときに同じようなことを考えていたからOK
このように、採点が甘くなったり、曖昧な基準で答え合わせをしたりするのです。
また、自分は読みやすいと思って書いた文章が、他人からすると読みづらい、意味が分からない、と思われる文章になっていることもあります。
そのため、自分以外の誰かに客観的に添削してもらうことが必要なのです。
自分以外の誰かに添削をしてもらうと、自分の文章の不足点や改善点がわかることはもちろん、他の人の意見や表現方法を学ぶこともできます。
自分以外の人の考えや表現を積極的に取り入れることで、自分の考えや表現の幅も広がるでしょう。
自分以外の誰かに添削してもらうことが面倒に感じるかもしれませんが、点数につながる解答を作成できる力を身に着けるためには、最も効率の良い勉強方法なのです。
コツ④過去問演習中はほかの参考書で類似問題に取り組む
4つ目のコツは、過去問演習中はほかの参考書で類似問題に取り組むことです。
大学受験が近づいてくると、過去問を集中的に解くことも大切ですが、過去問だけを解いていればいいというわけではありません。
特に、過去問の中に苦手な問題がある人は、その問題の類似問題をほかの問題集から見つけて、演習を重ねましょう。
具体的な例として、志望校の過去の試験問題に和歌や文学史が出題されている場合、それらのインプットを行うのはもちろん、文学史に関する問題をたくさん解くことが大切です。
また、最近新しくできた大学や新設された学部の場合、過去問が1、2年分しかないこともあります。そういった場合も、過去問だけでなく類似問題を探して演習を重ねましょう。
問題集以外にも、「A大学の大問1とB大学の大問3の問題形式・難易度が似ている」といったこともあるので、時間があれば志望校以外の過去問もチェックしてみましょう。
コツ⑤志望校の過去問で出題されることが多い作品は個別で勉強しておく

5つ目のコツは、志望校の過去問で出題されることが多かった作品は個別で勉強しておくことです。
こちらでも少し触れましたが、大学によって受験で出題されることが多い作品がある場合があります。自分の志望校の過去問でよく出題されていた作品があれば、その作品への知識を深めておきましょう。
例えば、次のようなポイントを押さえるとよいでしょう。
- 作品の全体の流れ
- 作品の主題・テーマ
- 主要な登場人物とその関係
- 作品の舞台
これらの情報を少しでも知っていると、受験本番で本文の内容を想像しやすくなるため、現代語訳がしやすくなったり、読解のスピードが上がったりします。
ただし、あくまで頻出なのであって、必ずこの作品から出題されるというものではありません。そのため、あまり時間をかけすぎず、時間があるときに取り組む、過去問演習の際に理解を深めるといったやり方がオススメです。
古文を勉強する際のオススメの参考書11選
この章では、キズキ共育塾の生徒さんがよく使っている古文を勉強する際のオススメの参考書を紹介します。
基礎から応用まで、幅広く紹介します。ご自分にあった参考書で学習を進めましょう。
参考書①『マドンナ古文単語230 パワーアップ版』

単語数は大学受験には少ないですが、初学者が見やすく、古典常識も身に付きます。
参考書②『読んで見て聞いて覚える 重要古文単語315 四訂版』
通常の大学受験レベルの単語帳です。イラストで暗記できるので覚えやすいです。
参考書③『新・古文単語ゴロゴ』

語呂合わせで楽に覚えたい人や、古文に時間をかけたくない学生にオススメです。男子学生に特に人気が高いです。
参考書④『ステップアップノート30 古典文法基礎ドリル ー三訂版ー』
基礎から勉強するのに最適。演習問題も充実しています。
参考書⑤『基礎からのジャンプアップノート 古典文法・演習ドリル 改訂版』

演習問題がわかりやすく基礎からの勉強にオススメです。
参考:望月光、上田慶子『基礎からのジャンプアップノート 古典文法・演習ドリル 改訂版』
参考書⑥富井の古典文法をはじめからていねいに【改訂版】
塾などに通っておらず、自習する学生にオススメです。
参考書⑦『古文上達 基礎編 読解と演習45』

文章問題とともに、文法問題もしっかりと出題されている参考書です。
文章問題を解きながら文法の学習をすすめることができます。
参考:仲光雄『古文上達 基礎編 読解と演習45』
参考書⑧『古典文法10題ドリル 古文基礎編』
中学校の教科書レベルの文章を10題のドリルで学べます。
参考:菅野三恵『古典文法10題ドリル 古文基礎編』
参考書⑨『古文上達 読解と演習56』

基礎が習得できた人向けの、難関私大レベルの応用編の参考書です。
参考:小泉 貴『古文上達 読解と演習56』
参考書⑩『マドンナ古文常識217 パワーアップ版』
古典常識はもちろん、平安時代の歴史人物、主要な文学史を学べる参考書です。
オールカラーのイラスト付きなので、古文に苦手意識がある人でも読み進めやすいでしょう。
参考:荻野文子『マドンナ古文常識217 パワーアップ版』
参考書⑪『みんなのゴロゴ 古文出典』

受験まで時間がない学生にオススメです。
受験によく使われる古典作品のあらすじや登場人物が書かれています。
よく出る作品のあらすじを知っておくだけで点が上がる可能性があります。
参考:ゴロゴネット『みんなのゴロゴ 古文出典』
古文の勉強に関する古文講師からのアドバイス〜古文の勉強で世界が広がる。効率的に楽しく学んで、豊かに生きましょう〜
この章では、キズキ共育塾の講師で元国語教師である村田綾香さん(仮名)からのアドバイスを紹介します。
このアドバイスを読めば、古文の勉強が楽しくなるかもしれません。
文法の知識で、和歌が情熱的なラブレターになることも

国語教師の経験がある私ですが、高校に入ったばかりのころは、古文があまり好きではありませんでした。
細かい文法や古文単語を覚えるのが面倒だったからです。
しかし、ある和歌と出会ったことで、「もっと勉強してもっと古文のことを知りたい!」と思い、古文の勉強が楽しくなりました。
まずは、その和歌を紹介します。
ひさかたの 天つみ空に 照る月の 失せなむ日こそ 吾が恋やまめ」
(引用:萬葉集 三〇〇四)
細かい文法の説明はここでは控えますが、まずは簡単に直訳をお伝えします。
「天空に輝いているお月様が消え失せてしまうような日にこそ、私の恋は止むのだろう」となります。
これだけでは、あまり魅力的な歌には思いません。
しかし、この歌には助詞による隠し味が潜んでいます。
隠し味を含めて解釈を付け足すと、以下のとおりです。
「(天空に輝いているお月様が消え失せてしまうような日にこそ、私の恋は止むのだろう)けれど、天から月が消えることはあり得ないので、私のあなたへの恋心が止むことは生涯ありません!!」
というように、情熱的なラブレターであることがわかります。なぜこうなるのかについては、こちらで説明します。
「勉強して古文の文法を身につけることによって、見えなかったものが見えるようになった。こうして世界が広がっていくのかな」。こんなふうに思ったことを覚えています。
これは、古文に限ったことではなく、すべての勉強に対して言えることでしょう。
より豊かな世界を知ることが、勉強することの楽しみの一つではないでしょうか?
千年以上の昔と今で、変わらないもの、同じものを知って、世界が広がる
さて、『万葉集』には、この和歌のように恋愛感情を詠んだ相聞歌(そうもんか)というものも多く含まれています。
その他にも、故郷から遠い地へ単身赴任した人の心情を詠んだ防人の歌(さきもりのうた)や、死者を悼む挽歌(ばんか)など、現代を生きる私たちも共有できる場面での感情が込められた和歌がとても多いです。
もちろん昔の歌なので、今の感覚とすべてが一致するわけではありません。ですが、「千年以上経っても片思いの甘酸っぱさは変わらないな」なんて思えるものもあります。
千年以上経っても変わらない人間らしさのようなものを感じると面白いですね。
その一方で、現代と感覚が全く違う歌もあります。
たとえば、「こんなことを言う人は、現代にはいないな」と思うことがあれば、千年前には普通で、今は普通ではないことから、時代や社会を考えることにつながります。
すると、私たちが普段当然のように受け止めている感情が、いかに今の時代や今の社会に特有のものであるかに気づかされるはずです。
古文の世界には、今の時代の今の社会の当たり前以外の世界が広がっています。
そこから、あなたにとって新しい世界が広がっていく可能性があります。
これも、見えなかったものが見えるようになり、世界が広がることの一つで、古文を勉強してよかったことだと思っています。
「温故知新」。効率的に楽しく学んで、豊かに生きましょう
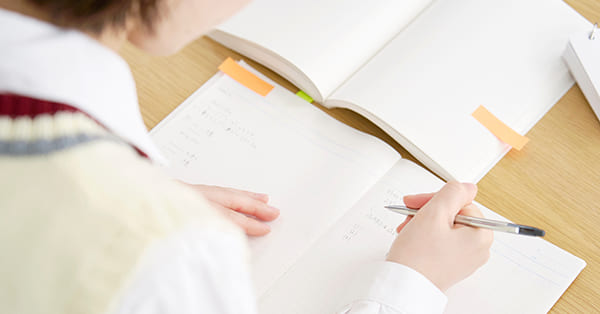
古文の授業で私が生徒さんによく言っていたことに、「温故知新(おんこちしん)」という教えがあります。
この言葉の出典は『論語』で、元々は漢文、つまり昔の中国語です。
これを日本の古文風に訓読すると、「故きを温ねて新しきを知る(ふるきをたずねて あたらしきをしる)」となります。
現代の日本語での意味は、過去の教えを基礎として、そこから新しい見解を見出すこととなります。
『万葉集』の様々な和歌からも、たくさんの「故きを温ねる」ことができます。
「故きを温ねる」からこそ見えてくる新しきと出会えたとき、古文を勉強するよさが実感できるのではないでしょうか。
たくさんの新しきを得て、より豊かな世界で生きて行きたいものです。
そして豊かな世界に想いを馳せると同時に思ったのは、豊かな世界を知るために遠回りしているのはもったいないなということです。
「効率よく勉強して、楽しく学び、より豊かな人生を歩もう!」というのが、高校生のときに立てた目標で、高校で教師をしていたときにも大切にしていました。
助動詞を覚えると、古文がわかるようになります
古文を効率よく勉強するひとつのアイディアをお伝えします。
古文の学習において、助動詞の種類・活用・接続方法・意味を覚えることは最も重要です。
残念ながら、助動詞を覚えずに古文を読めるようになることはありません。
しかし、助動詞の活用や接続までをひととおり把握できるようになれば、古文を解釈でき、テストなどでも問題の答えを導けるようになります。
あとは各助動詞の使われ方を意識しながら考えるトレーニングをすることが大事です。
助詞・助動詞の読み解き方の例を解説します

ひさかたの 天つみ空に 照る月の 失せなむ日こそ 吾が恋やまめ
最初に紹介したこの和歌のうち、「失せなむ日」という部分の助動詞の見分け方と意味、そしてこの和歌が情熱的なラブレターである理由を、合わせて解説します。
下線をつけているところは、覚えておかないとわからない部分です。
なお、今のあなたは、解説を読んでも古文の専門用語ばかりで何を言っているのかわからないと思うかもしれません。ですが、勉強していくうちにわかるようになります。
現時点でわからないからといって不安にならなくても大丈夫です。
では、解説に入ります。
パッと見て意味がわからないものが「助詞」「助動詞」ですから、「なむ」の部分がそれにあたります。
ただ、「なむ」という助動詞はありません。
どんな助動詞があるかを把握しておく必要があります。
では、「な」と「む」に分けるとどうなるでしょうか。
「な」は登場頻度が低いのですぐに思いつかないかもしれませんが、「む」は基本形でもあるのですぐにわかります。
推量その他の助動詞「む」の終止・連体形ですね。
ここでは、下に「日」という名詞(=体言)があるので連体形です。
では、「む」の接続(上に何系の活用形がくるか)は?……正解は「未然形」です。
接続についても必須項目です。
未然形で「な」の形になる助動詞は、「ぬ」があります。
「ぬ」の意味はほとんどの場合「完了」です。ですが、下に推量系の助動詞がきている場合は「強意」の意味になるので、この「なむ」は、「~してしまう(=な)ような(=む)」という意味になります。
また、この和歌を解釈するための「文法の隠し味」は、「こそ」にあります。
「こそ」は、「係助詞」と言われるもので、強調のために使われ、通常はあまり訳に出しません。
テストや受験などで重要視されるのは、「文末の活用語を已然形にする」という働き(係り結び)です。
ただし、この「こそ~已然形」が和歌の句末で使われた場合、逆接を強調する(そちらが真意になる)という働きが生まれます。
そこで、「お月様が消え失せてしまうような日にこそ、私の恋は止むのだろう」という直訳ではなく、「月が消えることはあり得ないので、私のあなたへの恋心が止むことは生涯ありません!!」という解釈になるのです。
「何を覚えると何がわかるようになるか」を意識しましょう
さて、解説の下線部を見て、「覚えることばかりじゃないか……」と嫌になった人もいるかもしれません。
しかし、この順番に考えるトレーニングを重ねることで、考えることに必要な時間は確実に減っていきます。
重要なのは、何を覚えれば、何がわかる・できるようになるかを意識することです。
それを考えずにすべてをとにかく覚えようとすれば無駄がたくさん出てきます。常に「今自分に必要な知識は何か?」を心に留めておくとよいでしょう。
少し細かい古文のお話しもしましたが、「今自分に必要な知識は何か?」「これを知っていれば何ができるか?」を考えることは、すべての教科において重要なことではないでしょうか。
このアドバイスでは、私が勉強してよかったと思えたことと、効率よく勉強するためのヒントについてお伝えしました。
キズキ共育塾には、指導力のある、しかし単純に問題を解説するだけにとどまらない授業をしてくれる個性豊かな講師がいます。
あなたも、ぜひ一緒にキズキ共育塾で勉強してみませんか?
相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
まとめ〜まずは基礎を鍛えましょう〜

ここまで古文の学習の具体的な方法と注意点について解説してきました。
ここで紹介していることは基本的な方法です。
まずは基礎を鍛えて、過去問を参考にして、さらに知識を深めていきましょう。
Q&A よくある質問
古文の勉強が苦手です…。
古文の勉強が苦手にならないためのポイントとして、以下が考えられます。
- 古文の土台はインプットであることを理解する
- 現代語訳は例文の真似ることから始める
- 問題の解説と現代語訳が丁寧な問題集を選ぶ
- 問題演習は短い文章から無理なく行う
詳細については、こちらで解説しています。
古文の勉強を効率よく進めたいです。
古文の勉強を効率よく進めるためのコツとして、以下が考えられます。
- 学習漫画などを活用して時代背景を知る
- 問題演習後は復習を忘れずに行う
- 記述問題は自分以外の誰かに添削してもらう
- 過去問演習中はほかの参考書で類似問題に取り組む
- 志望校の過去問で出題されることが多い作品は個別で勉強しておく
詳細については、こちらで解説しています。