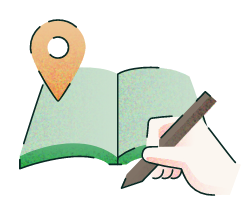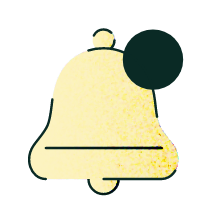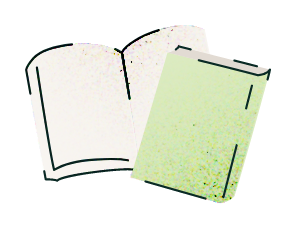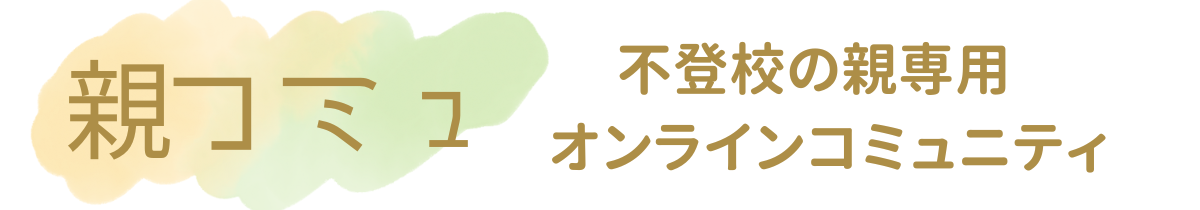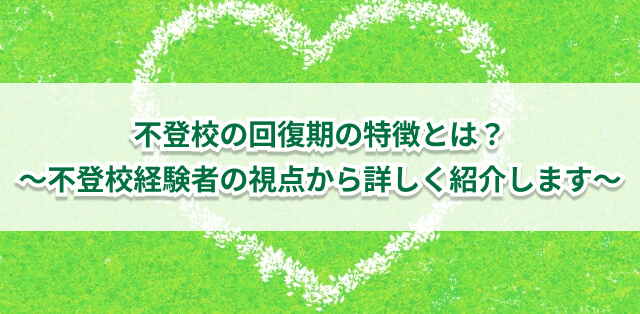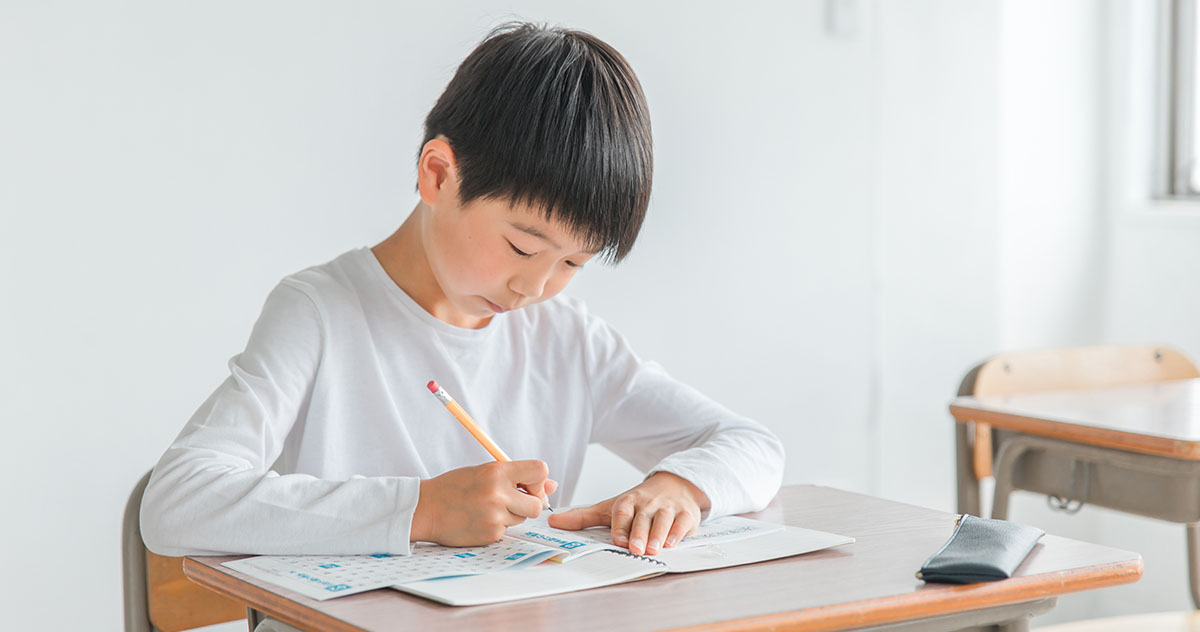ASDのあるお子さんが不登校になる理由 保護者ができる対応を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたはASD(自閉症スペクトラム症)のあるお子さんの不登校について、以下のような疑問や不安を抱えていませんか?
- ASDと不登校はどのような関係があるの?
- ASDのある不登校や登校しぶりの子どもに親ができることって?
このコラムでは、そうしたお悩みを持つ親御さんに向けて、不登校の現状やASDの概要、ASDの診断基準、ASDの原因、ASDのあるお子さんが不登校になる理由について解説します。
あわせて、不登校の進行段階や不登校中の過ごし方、不登校中に保護者や周囲ができる対応、支援機関についても解説します。ぜひ参考にしてください。
私たちキズキ共育塾は、不登校状態にあるASDのある人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
不登校の現状
この章では、文部科学省の調査に基づき、不登校の現状について解説します。文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」
小・中学校における不登校

2023年度の小・中学校における不登校児童生徒数は34万6482人と、前年度より4万7000人増えて過去最多となりました。在籍児童数の約3.7%が不登校で、出席日数が0日の生徒は約3.1%にのぼります。
不登校増加の背景には、休養の必要性を認める保護者の意識の変化、ASDなど特別な配慮を必要とする生徒への早期支援や指導の課題などがあると考えられています。
また、不登校の生徒からは「学校生活にやる気が出ない」という相談が最も多く、続いて「不安・抑うつ」「生活リズムの不調」などの相談が多く挙げられています。
高等学校における不登校
高等学校でも不登校生徒数は増加しており、2023年度は6万8770人と、過去最多の人数となりました。前年度から8195人増加しており、在籍生徒数の約2.4%が不登校です。
不登校増加の背景には、進学やクラス替えなど新しい環境への不適応や、コロナ禍による登校意欲の低下などの影響があると考えられています。
不登校の高校生からの相談も小中学生同様、「学校生活にやる気が出ない」という内容が最も多く、続いて「生活リズムの不調」「不安・抑うつ」などの相談が多く寄せられています。
ASD(自閉症スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)とは?
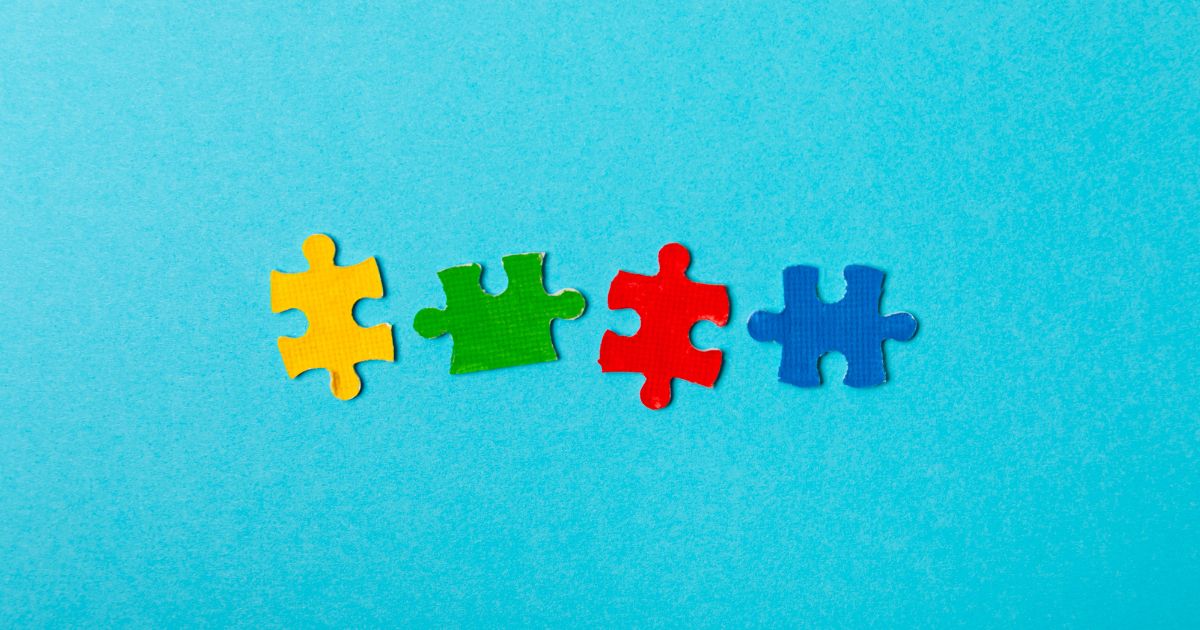
ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害、Autism Spectrum Disorder)とは、人とのコミュニケーションなどに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、e-ヘルスネット「ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」、CDC「Autism Spectrum Disorder (ASD) 」、厚生労働省「No.1 職域で問題となる大人の自閉症スペクトラム障害」、福西勇夫、福西朱音『マンガでわかるアスペルガー症候群の人とのコミュニケーションガイド』)
かつて使用されていた以下の診断名・分類は、ASDという診断名・分類に統合されています。
- アスペルガー症候群
- 自閉症
- 高機能自閉症
- 広汎性発達障害(PDD)
それぞれ別の発達障害として、診断基準も異なっていましたが、2013年に行われた『DSM-5』の改訂の際に、厳密に区分するのではなく、地続きの=スペクトラムな障害として捉える現在のASDに変更されました。
ただし、変更前の診断名・分類が、法令や病院、日常会話などで現在も使用されることがあります。また、かつてアスペルガー症候群などと診断された人が、現在のASDという名称を認知していないこともあります。
ASDの診断基準
アメリカ精神医学会が定めた精神障害の診察基準『DSM-5』によると、ASDの診断基準は以下のとおりです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』)
A.複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的欠陥がある
- 相互の対人的-情緒的関係の欠落で、例えば、対人的に異常な近づき方や通常の会話のやり取りのできないことといったものから、興味、情動、または感情を共有することの少なさ、社会的相互反応を開始したり応じたりすることができないことに及ぶ
- 対人的相互反応で非言語的コミュニケーション行動を用いることの欠陥、例えば、まとまりのわるい言語的、非言語的コミュニケーションから、アイコンタクトと身振りの異常、または身振りの理解やその使用の欠陥、顔の表情や非言語的コミュニケーションの完全な欠陥に及ぶ
- 人間関係を発展させ、維持し、それを理解することの欠陥で、例えば、さまざまな社会的状況に合った行動に調整することの困難さから、想像上の遊びを他者と一緒にしたり友人を作ることの困難さ、または仲間に対する興味の欠如に及ぶ
B.行動、興味、または活動の限定された反復的な様式が2つ以上ある
- 情動的または反復的な身体の運動、ものの使用、または会(例:おもちゃを一列に並べたり物を叩いたりするなどの単調な常同行動、反響言語、独特な言い回し)
- 同一性への固執、習慣への頑ななこだわり、または言語的、非言語的な儀式的行動様式(例:小さな変化に対する極度の苦痛、移行することの困難さ、柔軟性に欠ける思考様式、儀式のようなあいさつの習慣、毎日同じ道順をたどったり、同じ食物を食べたりすることへの要求)
- 強度または対象において異常なほど、きわめて限定され執着する興味(例:一般的ではない対象への強い愛着または没頭、過度に限局したまたは固執した興味)
- 感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ、または環境の感覚的側面に対する並外れた興味(例:痛みや体温に無関心のように見える、特定の音または触感に逆の反応をする、対象を過度に嗅いだり触れたりする、光または動きを見ることに熱中する)
ASDの原因

ASDの原因は、現在の医学では明確に特定されていません。現在のところ、生まれつきの脳機能の障害が原因であると考えられています。
少なくとも、本人の努力不足や親の育て方、ストレス、環境などが原因ではないことは明らかになっています。ASDは、原因不明かつ生まれつきのものであり、誰かに責任があるわけではありません。
ASDのあるお子さんが不登校になる理由
この章では、ASDのあるお子さんが不登校になる理由について解説します。
理由①コミュニケーションの困難

ASDのあるお子さんは、自分の気持ちを言葉で表現することや、相手の気持ちを汲み取ることが苦手な傾向があります。そのため、コミュニケーションに困難を感じやすいのが特徴です。(参考:発達ナビポータル「自閉スペクトラム症」、一般社団法人日本自閉症協会「自閉スペクトラム症(ASD)について学ぶ」、厚生労働省「発達障害の理解」)
学校生活の中では、クラスメイトとの何気ない会話やグループ活動など、他人との交流は避けられません。
しかし、ASDのあるお子さんは会話のタイミングがわからなかったり、一方的に話してしまったりして、周囲とうまく馴染むことができない場合があります。
このようなコミュニケーションのすれ違いが重なることで、対人関係に苦手意識を抱きやすくなり、登校へのハードルが高くなった結果、不登校になることがあります。
理由②こだわりによるストレス
ASDのあるお子さんには、自分なりのやり方への強いこだわりがみられることが多く、周囲の変化に柔軟に対応するのが難しい傾向があります。(参考:発達ナビポータル「自閉スペクトラム症」、一般社団法人日本自閉症協会「自閉スペクトラム症(ASD)について学ぶ」)
例えば、机の上の文房具の配置や登下校の道順など、自分なりのルールやパターンが崩れると強い不安やストレスを感じることがあります。
こうしたこだわりは本人が安心して過ごすための大切なものです。そのため、周囲が理解せずに無理にやり方を変えさせようとすると、余計にストレスが強まることも考えられます。
また、急な予定変更や環境の変化などにも不安や抵抗感を抱きやすいため、混乱やパニックを起こしてしまうこともあります。
このようなストレスが日常的に積み重なることで、学校生活への不安や恐怖が大きくなり、不登校につながることがあります。
理由③感覚過敏

ASDのあるお子さんは、周囲の人が気にしないような些細な光や音、匂いなどに対してとても敏感である場合があります。(参考:厚生労働省「発達障害の理解」)
例えば、蛍光灯のちらつきや時計の針の音、他人の咳払い、特定の匂いなどが、強いストレスにつながることがあります。また、他人に軽く触れられるだけで苦痛を感じるケースも見られます。(参考:生駒市「『感覚過敏』をご存知ですか?」)
このような感覚の過敏さがあると、学校という環境自体が大きな負担となりやすくなります。その結果、登校が苦痛となり、不登校につながることも珍しくありません。
理由④いじめや孤立
ASDの特性によるこだわりやコミュニケーションの困難さから、クラスメイトとの関係性がうまく築けず、孤立やいじめにつながるケースもあります。
例えば、周りが気にならないことへのこだわりや刺激に対する行動から変わり者扱いをされて、仲間外れになることも考えられるでしょう。
また、ASDのお子さんは自分からうまくSOSを出せず、悩みや不安を一人で抱え込んでしまう傾向があります。
このような心理的な負担が積み重なると、学校に行くこと自体が辛くなり、不登校につながる場合があります。
ASDのあるお子さんの特徴については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
不登校の進行段階
不登校は、すぐに明確な形で現れるわけではなく、いくつかの段階を経て進行することがわかっています。
この章では、不登校の進行段階を3つに分けて解説します。(参考:下島かおる『登校しぶり・不登校の子に親ができること』、西東京市教育委員会「不登校を通して見る子どもの気持ちと保護者の思い〜子どもの心と成長を考える〜」)
段階①不登校前兆期

不登校前兆期は、お子さんが学校を休みがちになったり、体調不良を訴えることが増えてくる時期です。
例えば、朝になるとお腹が痛い、頭が痛いと訴える、遅刻や早退が増える、保健室で過ごす時間が長引くなど、少しずつ変化が現れてきます。
お子さんによっては習い事には休まず通ったり、自宅では笑顔を見せたりするため、どうしたらいいのか対応に悩むことも多いでしょう。
しかし、この時期のお子さんは自分の心身の不調に混乱しているケースが少なくありません。
無理に不調の理由を聞き出そうとするのではなく、慌てず、焦らず、急がずに声をかけてみることをおすすめします。
時には苛立ちをぶつけられたり、泣き出したりすることもあるかもしれませんが、どんな反応が返ってきても落ち着いて対応し、お子さんの気持ちや変化に優しく寄り添うことが大切です。
段階②不登校混乱期
不登校混乱期は、お子さんが外へ出ること自体を避けるようになる段階です。
家の中で過ごす時間が長くなり、昼夜逆転の生活リズムになったり、家族との関わりを避けたりする様子が見られます。
この時期は、お子さんが使い切ってしまったエネルギーを再度充填する期間と言えるでしょう。
そのため、まずはお子さんが元気を取り戻して、自分から動き出すのを待つことが大切です。
学校の先生やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの力も借りながら、焦らずお子さんのペースを尊重しながら見守りましょう。
段階③不登校回復期

不登校回復期とは、不登校状態の次の一歩に踏み出す元気が出てきた段階・時期のことです。
家族との会話が増える、お子さんから学校や進路について気にする発言が出てくる、暇を持て余すようになるなどの様子が見られます。
ただし、回復の傾向やスピードは一人ひとり異なるため、このサインがあれば回復したという正解はありません。不登校回復期であっても焦らずお子さんのペースで過ごすことが大切です。
また、不登校回復期はお子さんのエネルギーが湧いてくる時期のため、外出が増えたり友人と遊んだりする機会が増えることがあります。学校へ行ってほしい、勉強してほしいと、親御さんにとっては複雑な心境になることもあるかもしれません。
しかし、登校再開を焦らせてしまうと、不登校回復期から不登校混乱期に逆戻りしてしまう可能性があります。お子さんの意思や気持ちを尊重しながら、焦らず一歩ずつ進んでいくことが大切です。
不登校回復期については、以下のコラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
不登校中の過ごし方
不登校中のお子さんは不安や焦りを感じていることが多くありますが、まずは心と身体を休めることが最優先です。
この章では、不登校中のお子さんの過ごし方について解説します。お子さんを見守る際の参考にしてください。
過ごし方①自宅で休息する

不登校になったばかりの時期は、まずはしっかりと休むことが大切です。
とくにASDのあるお子さんは、集団生活に強いストレスを感じやすく、本人が思っている以上に心と体が疲れていることが多くあります。
学校に行っていない自分を「何もしていない」と責めがちですが、大切なのは罪悪感を持たず「何もしない」時間を作ってリフレッシュすることです。
十分な休息を取り、心と体が回復してきたら、自分の好きなことをして過ごす時間を取るのも良いでしょう。勉強をしても良いですし、勉強以外の好きなゲームや動画を楽しんでも大丈夫です。
しっかり休むことで、少しずつ前を向くエネルギーが戻ってきます。
過ごし方②自宅や学校以外の居場所を作る
十分な休息を取り、疲れた心と体にエネルギーが溜まってきたと感じたら、少しずつ新しい居場所を見つけてみるのもおすすめです。
不登校生向けの学習塾やフリースクール、地域のコミュニティスペースなど、安心できる場所はたくさんあります。学校生活では出会えない多様な人たちと話す機会が生まれることで、新しい価値観に触れたり、将来について相談したりもできるでしょう。
お子さんが高校生なら、アルバイトにチャレンジするのも選択肢のひとつです。
自分のペースを大切に、少しずつ世界を広げていく中で、自分らしい過ごし方が見つかるかもしれません。無理をせず安心できる場所を探してみてください。
フリースクールについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
不登校中に保護者や周囲ができる4つの対応
お子さんが不登校になると、親として何をすれば良いのか、不安を感じることも多いのではないでしょうか。
この章では、お子さんの不登校中に保護者や周囲ができる具体的な対応について解説します。
なお、前提として、お子さんの不登校のことや発達障害のことは、親御さんだけで対応する必要はありません。専門家や支援機関に相談するようにしましょう。
(参考:西東京市教育委員会「不登校を通して見る子どもの気持ちと保護者の思い〜子どもの心と成長を考える〜」、文部科学省「不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書」)
対応①不安や悩みの傾聴

不登校中に大切なのは、お子さんの気持ちや悩みをしっかり聞くことです。
特に不登校前兆期のお子さんは、自分でも何が何だかわからなくて困っているということが多くあります。
お子さんから話してくれたときには、否定や批判をせずに受け止めることが、お子さんの安心につながります。
また、お子さんの話を聞くことで、不登校のきっかけや状況を把握できるため、これからのことを考えるヒントになるかもしれません。
一方で、お子さんが話してくれない場合は、無理に話を聞き出そうとしないことも大切です。
親御さんから不登校の理由を問い詰めたり、無理に話をさせようとしたりすることは、お子さんを精神的に追い詰めることにつながります。
ときには静かに様子を見守り、まずはお子さんから自分から話してくれるまで待つようにしましょう。
対応②ASDの特性の理解
ASDの特性を学び、理解することも、不登校中の大切なサポートの一つです。
専門家や支援機関に相談したり、関連する資料や書籍を読んだりすることで、ASDのあるお子さんの適切な接し方やサポート方法が見えてきます。
また、専門家からの指導を受けられるペアレント・トレーニングや、同じ悩みを持つ保護者同士の集まりである親の会への参加もおすすめです。
ASDの特性を理解したうえでお子さんと向き合うことで、本人に合った生活スタイルや進路を一緒に考えやすくなるでしょう。
対応③生活リズムを崩さない工夫

不登校の期間は、昼夜逆転などでお子さんの生活リズムが乱れやすくなります。
しかし、生活リズムが乱れた生活を続けすぎると、心身の健康が損なわれ、場合によっては不登校回復期から不登校混乱期に逆戻りすることもあります。
例えば「おはよう」「おやすみ」と毎日声をかけたり、一緒にご飯を食べたりすることが、生活リズムの安定につながります。
お子さんの無理のない範囲で、睡眠や食事など安定した生活リズムを作る工夫をしてみましょう。
対応④安心できる環境づくり
お子さんが安心して過ごせる環境づくりは、不登校からの回復において大切なポイントです。
自宅がリラックスできたり、安心してわがままが言える場所であれば、体も心も休まり、前向きな気持ちが芽生えやすくなるでしょう。
学校という居場所を失った時期だからこそ、家庭でのあたたかな見守りが、お子さんが次に一歩踏み出す力になります。焦らず、温かく見守ることを意識しましょう。
不登校になったASDのあるお子さんに親ができる対応については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
ASDのあるお子さんの不登校に関する4つの支援機関
この章では、ASDのあるお子さんの不登校に関する支援機関を紹介します。
支援機関①教育支援センター(適応指導教室)

教育支援センター(適応指導教室)とは、主に不登校状態にある児童生徒の学校復帰を支援し、社会的自立をサポートする施設のことです。集団生活への適応や情緒の安定、基礎学力の補充などのサポートを行っています。(参考:文部科学省「適応指導教室(学校支援センター)の取り組みについて」)
学校支援センター(適応指導教室)は約63%の自治体で設置されており、設置を予定している自治体も多くあります。(参考:文部科学省「『教育支援センター(適応指導教室)に関する実態調査』結果」)
なお、教育支援センターの旧名称は「適応支援教室」で、同じ施設を指します。不登校状態にある児童生徒の増加や文部科学省の通知などを受けて、2003年に正式名称が適応支援教室から教育支援センターに変更されています。(参考:立川市教育委員会「適応指導教室から教育支援センターへの名称変更について」)
教育支援センター(適応指導教室)については、以下のコラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
支援機関②発達障害者支援センター
発達障害者支援センターとは、発達障害の早期発見と早期支援を目的として、発達障害のある人とその家族などをサポートするための支援機関のことです。(参考:国立障害者リハビリセンター 発達障害情報・支援センター「発達障害支援センターとは」
センターでは、家庭での療育についてのアドバイスや、発達検査の実施、発達段階に応じた支援計画の作成などを実施しています。
また、必要に応じて福祉制度やその利用方法、関係機関の紹介、学校や企業と連携した環境整備なども行っています。
ただし、人口規模や面積、地域資源の有無などによってセンターの事業内容は異なります。詳しい内容については、お住まいの地域にある発達障害者支援センターにお問い合わせください。
発達障害者支援センターについては、以下のコラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「発達障害者支援センターとは? 支援内容や利用の流れを解説」
支援機関③親の会

親の会とは、不登校のお子さんを持つ親御さん同士が集まるコミュニティのことです。
同じ経験や思いを持つ親御さんと話すことで、前向きな気持ちを取り戻せたり、気持ちが軽くなったりすることも少なくありません。
最近では、過去にASDのあるお子さんを育てた親や、不登校状態にあったお子さんを育てた親が、現在悩んでいる親をサポートするペアレント・メンターという活動も盛んです。
インターネットで「不登校 親の会」「発達障害 親の会」と検索すると、お住まいの地域にある親の会を見つけることができるでしょう。
近所の人に知られたくない場合は、隣の自治体にも参加できる場合があります。一人で悩まず、気軽に足を運んでみてください。
支援機関④フリースクール
フリースクールとは、さまざまな理由で、学校に行かない選択をした子どもたちが通える学校以外の学びの場のことです。
主に学習活動、教育相談、体験活動を行い、同年代の友達との交流ができます。2015年度の文部科学省の調査では、全国に474のフリースクールが確認されています。(参考:文部科学省「フリースクール・不登校に対する取組」)
なお、多くのフリースクールは、NPO法人や民間企業、個人が運営しています。
フリースクールについては、以下のコラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校ジャーナリスト・石井しこう、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。
このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。
このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。
公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら
- 【オリジナル書籍プレゼント】学校外で友だちができるBranchコミュニティ(Branch公式LINEが開きます)
私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。
まとめ:ASDによる不登校は支援機関に相談しよう

ASDの特性によってさまざまなストレスが生じた結果、お子さんが不登校になるケースは少なくありません。
しかし、不登校という経験をきっかけに、自分らしく過ごせる居場所や学習方法を見つけることも十分に可能です。
不登校中は親御さんだけで悩みや負担を抱えるのではなく、ASDや不登校の支援機関やカウンセラー、医療機関などに早めに相談することが大切です。専門家と協力しながら、お子さんの意思や気持ちに寄り添い、無理のないペースで進んでいきましょう。
このコラムが、お子さんの不登校で悩むあなたの一助となれば幸いです。
Q&A よくある質問