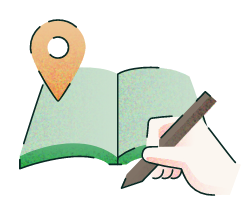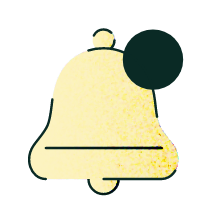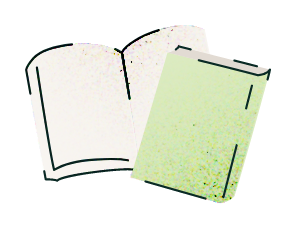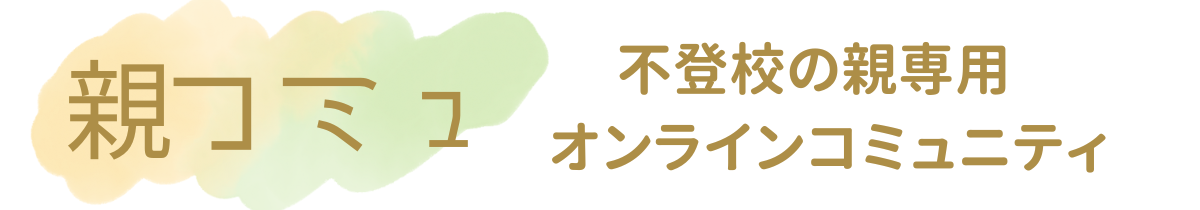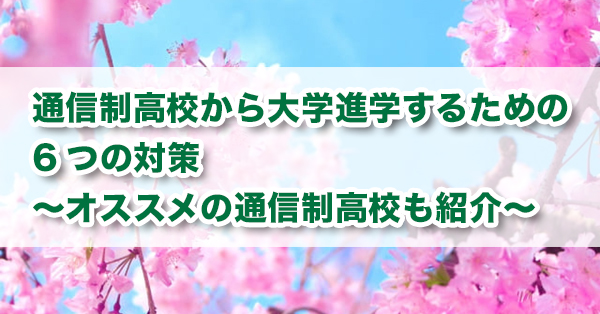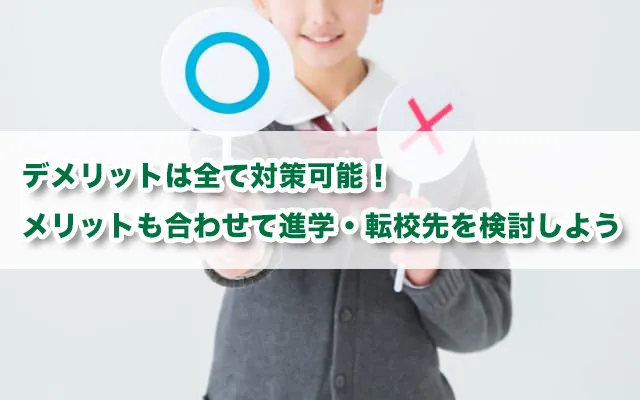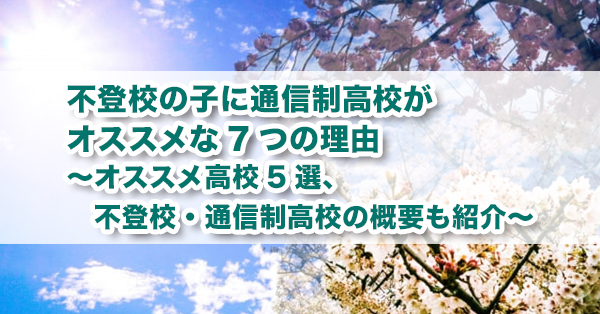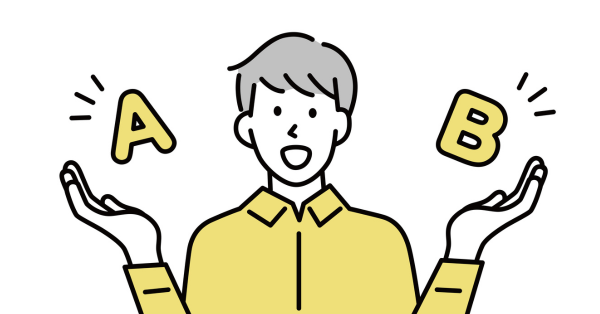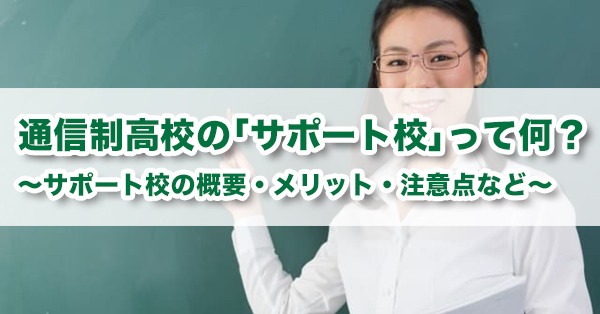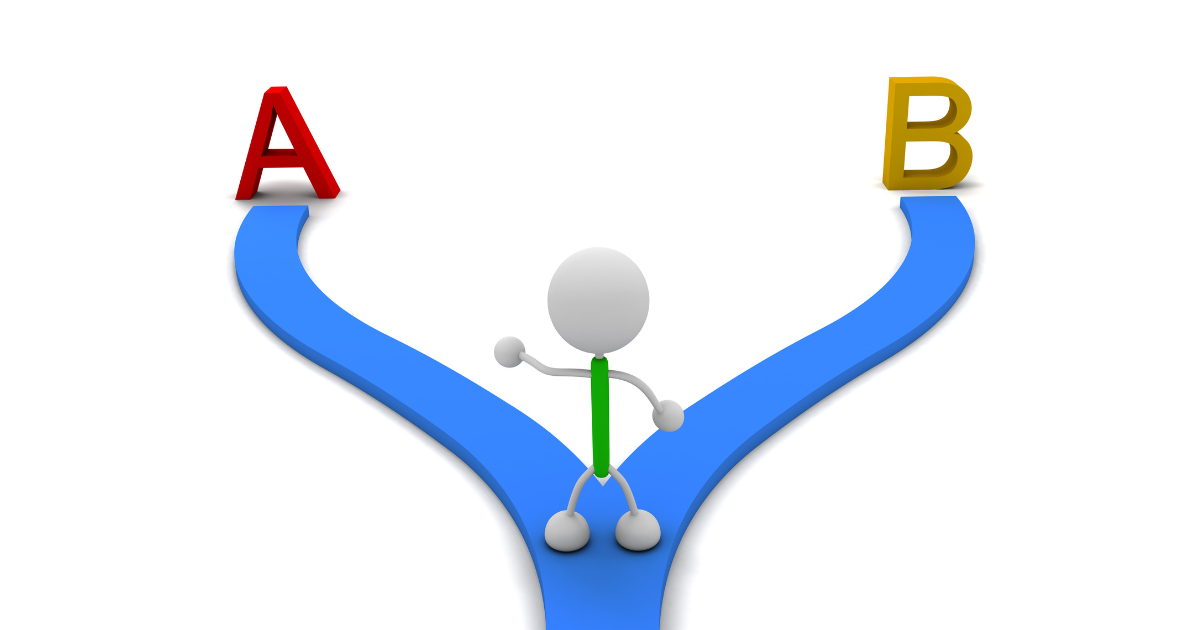通信制高校からの大学進学は不利? 進学率や大学進学を勝ち取るポイントを解説

こんにちは。勉強・メンタルの両面から完全個別指導で応援するキズキ共育塾です。
「通信制高校って大学進学には不利なのですか?」というお悩みをよく聞きます。
いろいろな事情で通信制高校を検討しているご家庭にとって、大学進学への道がどうなのか、心配になりますよね。
このコラムでは、通信制高校からの大学進学について、実際の大学進学率や大学進学を勝ち取るポイント、オススメの通信制高校、大学進学以外の選択肢を解説します。
あわせて、通信制高校から大学進学した人の体験談を紹介します。
通信制高校に進んだからといって、大学進学で不利になるということはありません。
しかし、通信制高校から大学に行くためには、きちんとした対策が必要です。それは通信制高校からの進学率にも現れています。
私たちキズキ共育塾は、通信制高校から大学受験を目指す人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
通信制高校からの大学進学は、不利ではありません
早速ですが、通信制高校からの大学進学は、不利ではありません。
それでも、「全日制の進学校と比べたらやっぱり不利なのでは?」と不安になるかもしれません。
確かに、難関大学への合格者を多数出している進学校で学ぶ生徒と比べると、学習内容で不利と言えるかもしれません。
ですがそれは、「通信制だから」不利というわけではなく、「進学校じゃない、普通の全日制高校」でも同じでしょう。
つまり「通信制かどうか」ではなく「学習の中身」を考えることが大切です。
それぞれの通信制高校のカリキュラムをふまえ、足りない面は学校以外で補うようにすれば、大学進学も十分に目指すことができます。
大学入試において、単に「通信制高校出身だから」というだけで評点マイナス、といったことはありません。
補足:大学進学の際に出身高校は合否に関係しない?

もう少しだけ、「出身・在籍高校」の大学への影響について掘り下げていきます。
まず基本的には、出身・在籍高校名が直接的に合否に影響を与えることはありません。
ただし、指定校推薦、というものがあります。これは、「大学側が指定した高校の生徒」のみが出願できる選抜方法です。
生徒は校長先生の推薦をもらって、出願します。逆に言うと、「自分の学校に指定校推薦の枠が来なければ、この方法では出願できない」ということになります。
ここは在籍高校が直接的に大学進学に影響する部分、と言えそうです。
私立大学は指定校推薦の枠も比較的大きくなっていますので、これがあるかないかで多少影響が出ることは、予備知識として押さえておくとよいでしょう。
通信制高校からの大学進学率とその理由
この章では、通信制高校からの大学進学率とその理由を解説します。
通信制高校からの大学進学率

文部科学省によると、高等学校卒業後の進学状況は以下のとおりです。(参考:文部科学省「学校基本調査-令和5年度 結果の概要-」)
全日制・定時制
- 大学等進学率:約60.7%
- 専門学校進学率:約16.2%
- 就職率:約14.2%
通信制
- 大学等進学率:約24.1%
- 専門学校進学率:約22.7%
- 就職率:約14.9%
全日制高校・定時制高校の大学等進学率が60%を超えているのに対して、通信制高校の大学等進学率は約24.1%です。比較すると、通信制高校の方がやや低い結果になっています。
通信制高校卒業後の大学進学以外の進路としては、専門学校への進学率は約22.7%です。他に、公共職業能力開発施設や自営業やアルバイトを含む就職などもあります。
ですが、実はそれらのどこにも属さない「その他(進学も就職もしていない)」というものがあるのです。
この「その他」が通信制高校の場合、約31.4%と高い比率になっているのが大きな特徴です。
ちなみに全日制高校・定時制高校の「その他」は約4.5%ほどです。ここに大きな開きがあると言えます。
キズキ共育塾の見る限り、通信制高校生の進路に「その他」が多い理由は、こちらで解説する大学進学率が低い理由と重なる部分が多いです。
通信制高校からの大学進学率が低い理由
こちらで紹介したデータを見ると不利なように見えますが、ここで注意したいのは、紹介したデータはあくまでも「卒業者全体」の中の割合であるということです。
「大学を志望した人」の中で、実際に進学した人の割合ではないのです。
そのことも含めて、通信制高校からの大学進学率が低い要因は以下のとおりです。
- そもそも大学進学を志望していない
- 学校や先生との接点が少ない
- 大学を目指して刺激しあえる友人が少ない
- 全日制に比べ、学習内容が比較的カンタン
「そもそも大学進学を志望していない」人は、多数いると思われます。
例えば、次のような人たちです。
- 心身の状況的に、通信制高校の卒業はできるけれど、大学に通うとなると厳しい人
- 高校卒業後にどうしたいか、定まっていない人
- 就職を目指している人
「そもそも大学進学を志望していない」以外の3つの項目については、大学を志望したにも関わらず、大学進学に至らなかった理由として挙げられます。
先生や友人など「人との関わり」が少ないこと、学習内容が比較的カンタンなことは、通信制高校全般の傾向でもあります。
ここを早めに認識して対策を取ることが大切です。
通信制高校から大学進学を勝ち取る4つのポイント
この章では、通信制高校から大学進学を勝ち取る4つのポイントについて解説します。
ポイント①本人のモチベーションが何よりも大切

受験する本人が「ここで〇〇を学びたい」「憧れの〇〇大学に行きたい」など、モチベーションを高めることが最も大切な事項です。
大学受験は、本人のモチベーションによるところが非常に大きいです。
そもそも大学とは、「皆が行くべきところ」ではなく、「学びたい人が行くところ」だからです。
もちろん、「学びたいことがなければ大学に行ってはいけない」というわけではありません。
大学進学の理由やモチベーションは、「大学で目標を見つけたい」「素敵なキャンパスライフを送りたい」などでもOKです。
大学のオープンキャンパスに行ったり、先輩の話を聞いたりするのも、具体的なキャンパスライフをイメージしやすいのでオススメです。
ポイント②大学進学のための学習環境を整えている高校を選ぶ
通信制高校で学ぶ内容は、基礎的な内容が多く、比較的容易な傾向が見られます。
そのため、希望する大学の学力試験に対応できない、といったことが起こります。
そこで通信制高校の中でも大学進学への対策をしている高校を選んでみましょう。
こちらで、大学進学にオススメの通信制高校をリストにしてご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
ポイント③情報に広くアンテナを張る

大学入試の方法は多様です。
様々な選択肢の中から、自分にあった方法を選べるのは嬉しい反面、どんな方法があるのかといった情報をしっかりと把握することが大切になります。
そのため、学校の先生や進路指導窓口へは、欠かさず相談をするようにしましょう。
大学進学への対策をしている高校なら、きっと手厚いサポートが期待できると思います。
ですが、通信制高校では登校する日数そのものが少ないため、先生や友人との何気ない接点から情報を得る、という機会が少ないのも事実です。
そのため常に情報にアンテナを張っておくことが不可欠になります。
ポイント④学習塾や家庭教師をサポーターとして上手に利用
大学進学向けの学習塾や家庭教師などをサポーターとして上手に利用しましょう。
これらは、大学受験の実績があるプロです。
学習塾の形態は、集団や個別指導、そしてオンラインなど様々にあります。
家庭教師の方も、実際に家に来てもらうほか、最近ではオンライン型も増えています。
それぞれに難関大学向け・中堅大学向け・高校の定期テスト対策などの特色がありますので、ぜひ確認してみましょう。
特に、一人一人に寄り添った指導ができる「個別指導型」は人気が高いようです。
学習塾や家庭教師には、例えば次のようなメリットがあります。
- 時間が決まっているので生活リズムのアクセントになる
- 情報収集がしやすくなる
- 受験のテクニック的なところを教えてくれる
- 志望する大学に絞った対策ができる
これらの他にも、模試の利用も考えてみましょう。
模試とは、様々な学習塾が実施する、「大学受験を想定した学力テスト」のことです。
模試を受けることで自分の偏差値、他の受験生と比べたときの自分の学力がわかります。また、志望大学への合格可能性A〜Eといった判定まで出ます。
模試は、進研模試や河合模試など、いくつかの種類があります。高校や学習塾の案内に従って定期的に受けることで、受験への意識が高まるでしょう。
大学進学体制を整えているオススメの通信制高校7選
この章では、大学進学コースなどの体制を整えている通信制高校をご紹介します。
大学進学にオススメの通信制高校について、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
オススメ①ヒューマンキャンパス高等学校

ヒューマンキャンパス高等学校では、通信制高校初の「AI技術」の活用による、生徒一人一人に合った個別カリキュラムで、大学合格への最短ルートを導き出してくれます。
- エリア:北海道から沖縄まで全国ネット
- 大学進学サポート:AI大学進学コースあり
オススメ②鹿島朝日高等学校
鹿島朝日高等学校は、学習センターが日本各地に300ヶ所以上ある最大級の通信制高校です。
また、インターネットを通じて学ぶこともできます。
- エリア:全国すべての都道府県から入学可
- 大学進学サポート:大学進学コースあり
参考:鹿島朝日高等学校
オススメ③飛鳥未来高等学校
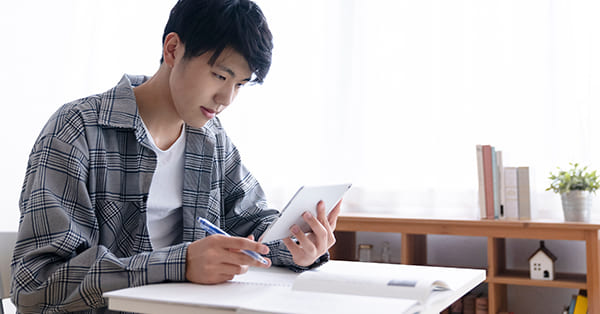
飛鳥未来高等学校は、進路決定率が93.4%(2019年3月卒業生実績)と非常に高い通信制高校です。
学校法人三幸学園グループ内の東京未来大学・小田原短期大学・様々な専門学校へ優先的に進学できます。
- エリア:札幌・仙台・東京・千葉・横浜・名古屋・大阪・奈良本校・広島・福岡
- 大学進学サポート:大学受験を目指す進学コース(キャンパスによる異なる)
参考:飛鳥未来高等学校
オススメ④鹿島学園高等学校
鹿島学園高等学校では、全日制と通信制が併設されています。
全日制は難関大学への進学実績が多数で、その教育が通信制にも活かされています。
- エリア:22の都府県から入学可(本拠地は茨城県鹿嶋市)
- 大学進学サポート:大学進学コースあり
参考:鹿島学園高等学校
オススメ⑤目黒日本大学高等学校

目黒日本大学高等学校は、全日制と通信制が併設されています。本拠地は東京都目黒区にあります。
日本大学付属校の全生徒が受ける「基礎学力到達度テスト」の結果によっては、日本大学へ進学することができます。
- エリア:東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・栃木・山梨から出願可
- 大学進学サポート:スタンダードコース進学クラス
参考:目黒日本大学高等学校
オススメ⑥松陰高等学校
松陰高等学校は、寺子屋式少人数の授業で、大学進学をバックアップする通信制高校です。
「総合型選抜」「学校推薦型選抜」の対策を強化しているのも特徴です。
- エリア:19の都府県に学習センターあり(本拠地は山口県)
- 大学進学サポート:進学(大学・短大・専門学校)コースあり
参考:松陰高等学校
オススメ⑦一ツ葉高等学校

一ツ葉高等学校は、早稲田大学に8年連続合格など、難関大学への合格実績が多数あります。
また、大学受験を知り尽くした講師による少人数指導には定評があります。
- エリア:東京・千葉・横浜・福岡・熊本
- 大学進学サポート:大学進学コース・アメリカ大学進学コース
参考:一ツ葉高等学校
通信制高校卒業後の大学進学以外の選択肢
通信制高校卒業後の選択肢は、大学進学だけではありません。
他の選択肢を知ることで、視野が広がり選択肢が増えることもあります。ぜひ一度読んでみてください。
選択肢①大学以外の学校への進学

選択肢の1つが、大学以外の学校への進学です。大学以外の進学先の主な選択肢は次のとおりです。
- 短期大学
- 専門学校
短期大学とは、「短期間で、大学としての教養教育やそれを基礎とした専門教育を提供する」大学のことです。(参考:文部科学省「短期大学について」)
一般的な在籍期間は2年もしくは3年です。幼稚園教諭や保育士、栄養士、介護福祉士などの専門的な免許を取得できる学部が多くあります。
また、四年制大学よりも比較的受験の難易度が易しいという特徴もあります。
そして、短大を卒業した後には、大学の2年次や3年次からの編入も可能になります(試験はあります)。
専門学校とは、大学や短大と同じく高等教育機関の1つで、実践的な職業教育が行われている学校のことです。(参考:文部科学省「専門学校とは」)
在学中に、仕事や就職に直結する技術を身につけることができます。
専門学校には、医療や語学、コンピューター、ファッションなど様々な種類があり、特定の分野に特化したカリキュラムで授業が行われます。
専門学校については、以下のコラムで解説しています。主に高校を中退した方に向けたコラムですが、専門学校の仕組みそのものはどなたが読んでも参考になると思います。ぜひご覧ください。
選択肢②就職
2つ目の選択肢は、就職です。
「通信制高校卒業という経歴は、全日制高校よりも就職で不利になるのでは?」と不安な人もいるかもしれません。
しかし、そんなことはありません。文部科学省の調査によると、通信制高校卒業生の就職率は約19.6%、全日制高校は約17.2%と、全日制高校を上回っているのです。(参考:文部科学省「学校基本調査」)
また、通信制高校の中には、キャリア教育や就職活動などのサポートが手厚い学校もあるため、そういった学校を選ぶことで不安を軽減できます。
ほかにも、通信制高校在学中に、先ほど紹介したような専門的な知識や資格について学べるコースで学んでおけば、就職に有利に働くこともあるでしょう。
通信制高校からの就職については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
選択肢③休養

通信制高校の学生の中には、体力・体調が万全ではない人もいます。
そうした人たちは、「通信制高校を卒業できるくらいの体力・体調ではあるけれど、受験勉強・大学生活や就職活動・労働は難しい」ということもあります。
あなたがそういう状況なら、休養するという選択肢があります。
体力・体調に不安があるなら、医師などとしっかり相談しつつ、体を大事にすることの方が優先です。
現役で進学・就職した人よりも少し「遅れる」ことは事実です。しかし、長い人生では大した差にはなりません。
「高校を卒業したら、すぐに必ず進学・就職しなくてはいけない」と思い込まないようにしましょう。
通信制高校から大学進学した体験談

この章では、通信制高校卒業後に大学に進学したキズキ共育塾に通う生徒さんの体験談をご紹介します。
谷本さん(仮名)は、通信制高校を卒業した後に、起立性調節障害が完全に治癒していない状態で大学受験にチャレンジしました。
体調面への不安から、「どのように勉強を進めるか」「大学を選ぶか」などの悩みがあったそうです。
ですが、キズキ共育塾に通うことで、自分に合った環境で無理なく受験勉強に取り組むことができ、無事大学に進学することができました。
親御さんからは、次のようなコメントをいただいています。
キズキ共育塾に決めたのは、娘のペースに合わせた勉強方法や先生を紹介してもらえると思ったからです。塾に通うのは久しぶりでしたが、不安はありませんでした。
無理のないペースで通塾したため、娘も前向きに通えていたようです。小論文の先生には、大学の推薦入試に向けて対応してくれました。無事に大学に合格でき、とても感謝しております。
通信制高校から大学進学を目指す人の中には、谷本さんと同じく体調面などに不安を抱えている人が少なくないかもしれません。
また、通信制高校から大学進学を目指す場合、学校での学習内容が全日制高校よりも比較的簡単なことから、勉強面の不安が大きいかもしれません。
ですが、学校以外に学習塾や予備校、家庭教師などで勉強のサポートを受けることで、体調面や勉強面の不安は解消できるのです。
谷本さんの体験談をより詳しく知りたい方は、以下の体験談をご覧ください。
通信制高校とは?
通信制高校とは、通信教育で学習する高等学校課程のことです。 基本的に毎日通学する必要がないため、場所を選ばずに勉強できる点が特徴です。(参考:文部科学省「高等学校通信教育の質の確保・向上」)
学校から送られてくる教科書や動画などの教材を利用して、自宅で学習します。成績は、レポートの提出やテストの点数で決まります。卒業の要件を満たせば、高校卒業資格が得られ、最終学歴は高校卒業(高卒)になります。
学習以外の時間を確保したい人や、自分のペースで学習したい人にオススメです。
通信制高校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ~通信制高校からでも大学進学で不利にはなりません~

繰り返しになりますが、単に「通信制高校出身」という理由だけで大学進学に不利になることはありません。
文部科学省の通知にも、「特定の属性による差別的な取扱いが行われないように」とちゃんと記載されています。
自分の学力を知るためには、模試の利用も意識していきましょう。
Q&A よくある質問
通信制高校から大学進学を目指したいです。
通信制高校から大学進学を勝ち取るためのポイントとして、以下が考えられます。
- 本人のモチベーションが何よりも大切
- 大学進学のための学習環境を整えている高校を選ぶ
- 情報に広くアンテナを張る
- 学習塾や家庭教師をサポーターとして上手に利用
詳細については、こちらで解説しています。
大学進学を目指しやすい通信制高校ってありますか?
大学進学体制を整えているオススメの通信制高校として、以下が考えられます。
- ヒューマンキャンパス高等学校
- 鹿島朝日高等学校
- 飛鳥未来高等学校
- 鹿島学園高等学校
- 目黒日本大学高等学校
- 松陰高等学校
- 一ツ葉高等学校
詳細については、こちらで解説しています。