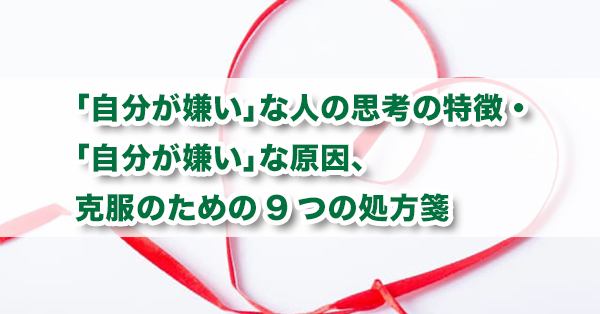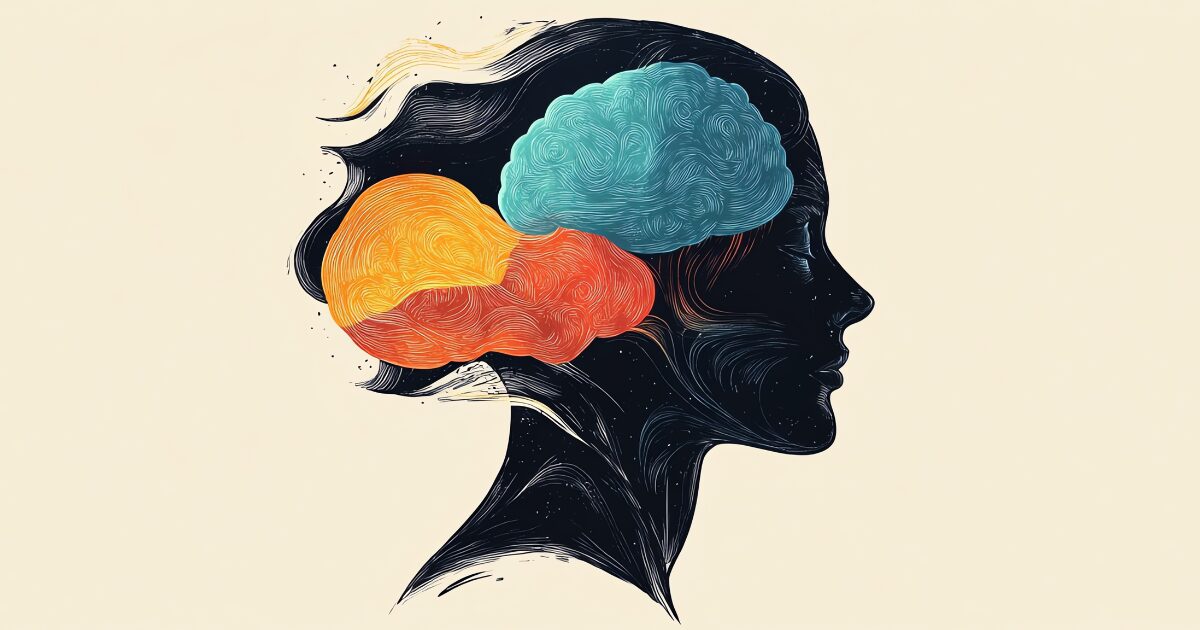自分らしく生きたいあなたへ 自分らしく生きる方法を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたはどんなときに「自分らしく生きたい」と思いますか?
- 周りの目ばかりを気にしている自分が嫌になったとき
- 嘘をつかなければならない環境や人間関係が苦しくなったとき
- さまざまな役割やキャラにがんじがらめになっているとき
- 社会規範・役割に違和感や疑問を感じたとき
このコラムでは、筆者の体験談やキズキ共育塾の知見をもとに、自分らしく生きることの意味や自分らしく生きることが難しい理由、自分らしく生きる方法などについて解説します。
少しでも、自分らしく生きる方法を模索しているあなたのお役に立ちましたら幸いです。
私たちキズキ共育塾は、自分らしく生きたい人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
自分らしく生きることとは?
自分らしく生きたいという思いは、誰もが一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。
しかし、自分らしく生きることの具体的な内容を問われると、はっきりと答えられないかもしれません。
どうすれば、自分らしく生きられるのでしょうか?
この章では、自分らしく生きることとはどういうことなのかについて解説します。
自分らしさは他者との関わりの中で見つかる

自分らしさとは、一般的にはアイデンティティと表現できます。では、アイデンティティとは、何なのでしょうか?
アイデンティティとは、自分はどんな人間なのか、ほかの人と何がちがうのか、どういうところに、どういう人と共通点があったりなかったり、どういう個性、特性をもっているのか。自分はどんな能力をもっているのか。どんな弱点や欠点をもっているのか。こういうことを明確に意識すること、実感すること、自覚することです。
(参考:佐々木正美「完 子どもへのまなざし」)
以上の内容から自分らしさを簡単に説明すると、自分はどんな人間なのかを自覚することと言えるでしょう。
とはいえ、自分はどんな人間かを自覚するのは、簡単なことではありません。また、自分らしさについて考えるとき、多くの場合、自分だけでじっくりと考えることが多いのではないでしょうか。
しかし、自分の頭のなかだけで考えていても、なかなか自分らしさを見つけることはできません。
以上の言葉にもあるように、ほかの人と何がちがうのかを意識することで、自分らしさを自覚できるようになることがあるからです。
よい意味で、他者との違いを知るということが、自分らしさを発見する手がかりになるでしょう。
例えば、「得意なことは何ですか?」と聞かれたとき、普通にはできることはたくさんあるけれど、得意というほどのものはないと思う人は多いでしょう。
しかし、周りの人と自分を比べてみると「あの人は上手にこなしているけれど、自分は苦手だな、できないな。それよりもこういった分野のほうが好きだし上手にできるな」といった視点が得られます。そして、自分の特徴をより意識しやすいのではないでしょうか?
つまり、自分らしさは、人との関わりを通して見つけていくものなのです。
精神分析家であるエリク・H・エリクソン氏も、以下のように述べています。
自分を主観的に見ているうちはアイデンティティはできません。自分を客観的に見つめること。
(参考:みすず書房「エリク・H・エリクソン」)
他者と直接コミュニケーションをとらなくても、一緒の空間に偶然居合わせる、街ですれ違う、といったわずかな関わりであっても構いません、いろいろな人と直に接してみると、人との違いをさまざまに感じることができるのです。
そこで感じた違いや共通点を集めていくと、自分らしさが見つかる手がかりになるはずです。
自分らしさを見つけるためには試行錯誤が必要
周りのいろいろな人を日々見ていると、このような気持ちになることがあるのではないでしょうか?
- 自分もあんなふうになりたいけれど、うまくいかない
- 得意だと思っていたけれど、もっと上手な人がたくさんいる
これは一見、ネガティブな感じ方のように見えますが、これこそが自分らしさ、アイデンティティであると言えます。
自分の希望と実際の自分の素質、能力、個性とは、かならずしも一致するものではありません。本当はこうなりたかったけれど、これは自分にはむりだ、ほかにできるひとはたくさんいる。だから自分はこういうほうに進路を選ぼう。そのもとになるのがアイデンティティです。
(参考:佐々木正美「完 子どもへのまなざし」)
このように、「自分には無理かな」と感じることを否定せず受け入れた上で、次のように自分らしさを探すことが大切なのです。
- それでは自分はどのような社会的役割を担っていこうか
- この分野ならけっこう関心がある
- どんな趣味や仕事を選ぼうか
「あなたはどんな人ですか?」「あなたの得意なことは何ですか?」と問われると、「これだ!」という特筆すべき何かを見つけなければいけないような気になるものです。
しかし、すぐにはっきりと即答できる必要はありません。
いろいろな周りの人を見ながら、自分の感性や特徴、つまり自分らしさに基づいて、迷ったり失敗したり路線変更をしたりしながら、見つけていけばよいものです。
「自分にはこれができそうだ」「これなら納得できる」という、自分にとってのベストなものを探していくと、自分らしく生きることにつながっていくでしょう。
苦手なことややりたくないことも含めた自分の感性や特徴、自分らしさに基づいて、自分に合うものを選んでいくことは、あきらめではなく、前向きな自分らしさの選択といえるでしょう。
自分らしく生きることが難しい9つの理由
自分らしく生きるためには、自分の感性を大切にする必要がありますが、自分軸では生きさせてもらえない・生きていけないと感じる場面が、日常の中にはたくさんあるでしょう。
他者からの要求や世間にある暗黙の了解など、他人軸を求められることが多いためです。
この章では、自分らしく生きることが難しい理由について解説します。
理由①ありのままを認めてもらえない環境にいる

自分の感性のままに生きたくても、それを認められる環境がなければ、自分らしさを出すことはできません。
家族や友達、職場の人などに合わせて、相手の望むキャラクターを演じていると、自分が自分ではないように思えてくるものです。
TPOに合わせて、適度に自分の中のキャラクターを使い分けることは必要かもしれません。
ですが、他人の価値観や要求に関係なく、「これだけは譲れない」という感覚を持つときがあると思います。そういった気持ちに完全に蓋をすると、心のエネルギーを消耗します。とはいえ、家庭の中や学校、職場などでは、その場に合わせた行動をするしかない場面が多く発生します。
そのため、日常的にありのままの自分を認めてもらえないと感じているのであれば、自分らしくいられる場所を、どこかに一つでも見つけていきましょう。
理由②「〇〇らしく」「こうあるべき」という役割・規範に縛られている
以下のような役割や社会規範は、昨今はかなり意識改革が進んでいるとはいえ、世代や個人により考えかたに未だ大きな差があります。
- 学歴が一番大事
- 安定した仕事につくべき
- 辛いことを我慢しないのはわがまま
- 親の言うことを聞くべき
- 母親は家にいるべき
- 女は女らしく、男を立てるべき
- 長男なんだから、家を継ぐべき
- 結婚したら一人前
- 年長者の言うことには絶対に耳を傾けるべき
あなたにうまく合致する役割や規範であれば、問題ないかもしれません。ですが、「自分には合わない」「役割や規範に囚われずに生きたい」と思う場合、自分らしい生き方ができない原因の1つになりえます。
役割や規範から完全に逃れるのは難しいですが、必要以上に役割に縛られる必要はありません。
理由③自己否定しすぎる

自分らしく生きるために、自尊心や自己受容が必要です。逆に、自己否定の傾向が強いと、自分らしく生きることが難しくなります。
例えば、自分が考える自分らしさが社会規範などと反する場合、「そんな理想を持つなんて自分はダメだ」などと、自分自身を否定してしまう場合もあるでしょう。
しかし、自分が感じている自分らしさや自分の感性は、自分だけの大切な感覚です。まずは、「自分の感性は大切にしてよい」と思うことから始めてみてください。
また、自分の自分らしさを理解してくれる人がいることも、とても大切です。自分の生まれ持った感性を無理矢理変えるのではなく、自分らしさを活かせる環境や、肯定してくれる人を探してみましょう。
自己否定や自分嫌いについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
理由④親の支配から抜けられない
支配的な親のもとで育つと、自尊心を育めなかったり、自分の考えや意見が尊重される経験を得られなかったりします。
その結果、自分らしく生きられなくなる場合があります。このような人は、アダルトチルドレンと言われます。
親子だからといって、何もかも許されるわけではありません。親と子どもは、別々の感性と心を持った独立した人間です。そういったことを、理解してもらうのは難しいとしても、自分自身で心に境界線を引くことはできます。
親を大切に思う気持ちから、心の境界線を引くことに抵抗がある人もいるかもしれませんが、何も悪いことではありません。
アダルトチルドレンについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
理由⑤努力を認められる場がない

自分なりに頑張っているのに誰にも認めてもらえないとき、誰しもやる気を失うものです。
努力をしても、褒められることもなく、何かの成果を感じられることもない。このようなことが続けば、努力する意味も感じられなくなります。
特に、自分の苦手分野に取り組んでいる場合、苦手なことや失敗体験ばかりがクローズアップされ、自分には何もできないような気持ちになるでしょう。
自分には得意なことや好きなことがある、という自分らしさにつながる大切な事実も忘れ、すべてのことがうまくいかない自分であるように感じられます。
その結果、自分らしく生きようと思う気持ちやエネルギーもなくなり、自分らしく生きる余裕がなくなっていくのです。
しかし、実際は、取り組んでいることが自分に向いていないだけであったり、自分に合った目標設定ができていないだけであったりすることが多いです。
自分に向いていることや自分に合っている目標が見つかるだけで、「自分にもできることがある」と思い出すことができ、自分らしく生きやすくなっていくはずです。
理由⑥自信をなくしている
自信をなくしていると、自分らしく生きることが難しくなります。
例えば、以下のようなことから自信をなくすことがあります。
- 自分に合わないことに取り組んでいて上手くいかない
- 経験不足で失敗を繰り返している
- 完璧主義者で自分を認めてあげられない
- 周りと比較する癖があり常に劣等感を抱いている
このように、自分が今いる環境、自分のスキルや能力、性格や考え方によって自信をなくすと、自分らしく生きる気力が湧いてこなくなります。
また、自分に自信がなければ、自分らしさよりも他者からの要求や世間にある暗黙の了解を優先しなければいけないと思うかもしれません。
自信をなくしていることで自分らしく生きられないと感じている場合は、まずはありのままの自分を受け入れる気持ちを育ててみてください。
自己肯定感や自己受容感などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
理由⑦助けてくれる人や味方がいない

今の学校や職場について、「なんとなく自分に合わない」「色々とうまくいかない」「でもその理由がうまく説明できない」などと感じることがあると思います。
また、この気持ちを家族や友人などの周りの人に相談すると、「気にしすぎ」「わがまま」「努力不足」などの一言で片づけられ、「とにかく頑張るべき」と言われることがあるかもしれません。
このような誰にも理解されない、助けてくれる味方がいないという状況では、精神的に追い詰められ、自分らしく生きる余裕がなくなります。
一方、「そう感じるんだね」と共感してくれるような理解者が一人でもいれば、勇気をもらえるものです。
そして、「自分が感じていることはおかしいことじゃないんだ」と感じられ、自分らしく生きてもいいと思いやすくなります。また、苦しい環境でも頑張ってみようと思えてきたり、ほかに自分に合う環境はないかと、前向きに考える余裕が出てくるでしょう。
理由⑧合わない環境から抜け出せない立場にいる
自分に合わないと感じても、その環境や状況から抜けられないという場合も多くあると思います。
- 仕事をやめるわけにはいかない
- 学校を休めない
- 希望の進路を認めてもらえない
- 子育てを途中でやめるわけにはいかない
以上のような状況では、抜け出したくてもその環境や状況から抜け出せず、抜け出す場合は大きな犠牲を払う必要がある場合もあるでしょう。
このような状況にいると、精神的に追い詰められるのはもちろん、自分らしさの片鱗すら感じられなくなっていきます。
こういった場合は、まずは以下のような簡単にできることから始めてみてください。
- 全てやめるのではなく、少しお休みをする
- 少し評価が下がってもよいと考え、手を抜く
- 誰かに代わりにやってもらう
- 自分らしくいられる活動、楽しく感じられる活動をしてみる
今の状況に小さな風穴をあける行動をするだけで、追い詰められた状況から少しずつ抜け出せることがあります。また、自分だけで抱え込まずに、誰かに相談することも大切です。
理由⑨心の調子がすぐれない

心に大きな負荷がかかっていると、自分の意思とは関係なく、体が動かなかったり、頭が働かなくなったりすることが、本当に起きてきます。
うつ病や不登校なども、心が疲れ切ったときのSOSサインです。
このように心の調子がすぐれない時は、ネガティブな考えになりやすいですが、自分の性格やこれまでの行動を責めたりしてはいけません。
心の調子がすぐれない原因は、あなたが努力できない、頑張れない、心が弱い、といったことではありません。心や神経が疲労しすぎると、性格に関わらず、誰しも調子を崩すことがあるものです。
そして、心の調子がすぐれないときに、自分らしく生きようとしても、気持ちが落ち込んだり、前向きに行動することが難しかったりするため、上手くいかないことが多いです。
心の調子がすぐれない場合は、まず医療機関を受診し、心の調子を回復させることから始めましょう。
自分らしく生きる8つの方法
この章では、自分らしく生きる方法について解説します。
無理なく取り組めそうなことから気軽に始めてみてください。
方法①安心感を持つ

自分らしく生きる上で一番大切なことは、今の自分でよいという安心感を自分で持つことです。
こちらで解説したように、自分らしさを認識するためには、他者との関わりを通して自分を発見する必要があり、これは一朝一夕にできるものではありません。
今から探していくという気持ちでよいのではないでしょうか?
そして、自分らしさを探すためには、安心感が必要です。安心感がない中で、他者と接していると、以下のような気持ちになります。
- 私の私らしさなんて周りの人と比べるとちっぽけに見える
- 〇〇さんの考えの方が説得力がある気がする
- 私らしいことよりも周りにあわせたほうがみんな喜んでくれる
このような気持ちになると、自分らしさを見つけることが難しくなることはもちろん、実際に自分らしい生き方を見つけられても、その生き方に自信を持てません。
そのため、一日の中で少しでも自分がほっとできる時間を作ってみたり、気の合う人と話してみたりして、少しずつ安心感を持てるようにしていきましょう。
そして、現状の自分に満足できていなかったとしても、「今の自分で大丈夫」と自分自身にOKを出すことも大切です。
方法②自分の意見を持つ
周囲に言う・言わないは別にして、自分の意見を持つことは大事です。
人は、場面に応じて大なり小なりキャラクターを使い分けながら生きています。
しかし、その場面に適応しすぎると思考が停止し、自分らしい考えや感性が失われていきます。「自分だったらどう考えるかな」「みんなはこう言っているけど、本当かな」と自問してみてください。
そのような習慣ができると、自分の考え方の癖や大事にしたい価値観が見えてくるため、自然と自分らしさが確立されていくでしょう。
方法③他者の要求や意見と距離を置く
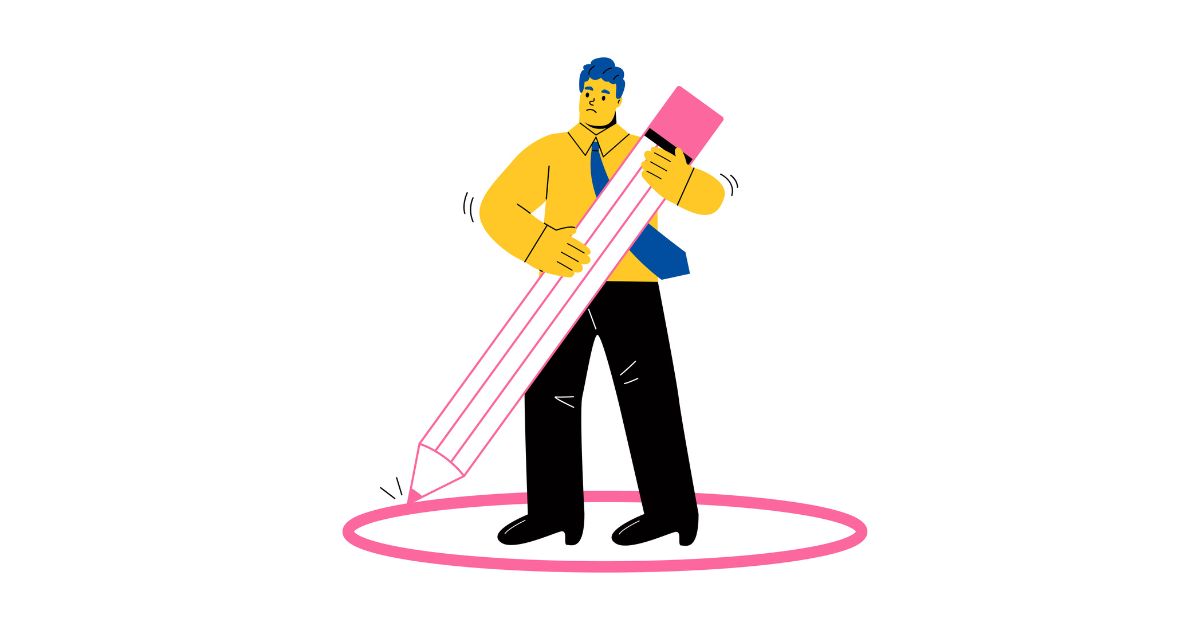
家族や恋人、友人など、他者の要求や意見ばかりを聞いていると、自分らしく生きることが難しくなります。
他者の要求や意見に惑わされないようにするためには、以下のような考え方を減らしていくことが重要です。
- 親がどう思うだろう
- 恋人がこう言ったから…
- 友人に嫌われたくない
とはいえ、このような気持ちを抱くことは当然のことであり、相手が大切な人であるほど、「要求に応えてあげたい」「意見を聞かなければ」という気持ちが大きくなるでしょう。
また、他者が自分に対してさまざまな要求をしてくることを、やめてほしいとおもっていても、こちらがコントロールすることは難しいものです。
そのため、要求してくること自体にはあまりとらわれず、「そう思うのだな」ととらえるだけにとどめるようにしましょう。
そして、要求されたからといって従う必要はない、と考えましょう。必要以上に周りの要求に答えなくても大丈夫です。
万が一、相手が気分を害したとしても、その気持ちを収めるのはあなたの役割ではなく、相手の課題です。周りの要求や意見に振り回されないように、心の中で線引きをするように心がけてみてください。
方法④肯定的に見てくれる環境を探す
環境は、習慣や考え方、生活、つまり生き方すべてに大きな影響を及ぼします。特に、自分らしく生きるためには、自分自身を肯定的に見てくれる環境にいることが重要です。
例えば、運動が苦手な場合、文武両道をよしとする校風の学校にいると、どんなに勉強ができても劣等感を抱くことになるでしょう。
しかし、運動ができなくても日常生活で困ることはありません。そして、運動に重きを置いていない環境に身を置けば、劣等感がなくなり、自分に自信を持つことができ、勉強がさらにはかどるかもしれません。
これはひとつの例ですが、自分らしさのなかにある苦手を不必要に意識させられる環境を、わざわざ進んで選ぶ必要はないということです。
また、自分に合った環境を、すぐに見つけられなくても大丈夫です。なぜなら、実際に体験しないことには、その環境が自分に合うか分からないからです。
自分が気になる環境が見つかれば一度飛び込んでみて、「やっぱり違うな」と思えば、また環境を変えればよいのです。失敗しながら自分に合う環境を探してもよいのだと考えましょう。
そして、その過程で新しい自分らしさを発見できることもあります。
また、これまでの環境では受け入れられなかった自分らしさが、新しい環境では受け入れられるケースも多々あります。自分を肯定的に見てくれる環境を探していきましょう。
方法⑤SNSやインターネットを断つ

現代社会では、気が付いたら一日中SNSやインターネットを見ていた、ということになりがちです。
SNSでは、どうしても見た目が映えるものばかりがよいとされます。SNSに投稿される内容は、その人のありのままの生活ではなく、一部を切り取り加工・演出されたものです。
頭ではわかっているかもしれませんが、実際にキラキラした投稿を目にすると、劣等感やコンプレックスが刺激されます。そして、「自分ももっと輝かしい生き方をしなければ」と自分軸ではない考えになることもあるのです。
また、SNSを見ているだけだと、他者が発信する他人軸の情報をずっと見続けることになります。
他人軸に溢れた世界から少しは離れる時間がないと、自分軸で物事を考えたり、感じ取ったりする時間を持つことができません。
そのため、適度にSNSを断つ時間を設けるようにしてみてください。
方法⑥自分らしさに惑わされない
SNSを含め、メディアを通して演出される自分らしく生きる人々の姿を見聞きすると、「自分らしく生きなければ」と焦ることがあるかもしれません。
しかし、こちらでも触れたように、自分らしさとは他者との関わりを通し、試行錯誤をしながら見つけていくものです。
そして、自分らしさはすぐに見つけられるわけではありませんし、急ぐ必要もありません。自分らしさは、少しずつ発見しながら集めていくものなのです。
必要以上に焦ったり急いだりせずに、自分らしい生き方を模索していきましょう。
自分が得意なことや好きなこと、心地いいと思うことを求め、苦手なことや、コンプレックスなども、自分らしさとして前向きに感じていく過程が大切なのです。
方法⑦好きや得意のハードルを下げる

得意なことや好きなことというと、何年もこつこつと続けてきたことや、コンクールに入賞したことなど、誰が聞いても納得するようなことだけが当てはまるように感じるかもしれません。
しかし、あなたの好きや得意について、誰かを納得させる必要は全くありません。
少し好き・少し得意といった程度でも、十分に好きや得意の範囲に入ります。
100%好きや得意といえるものが自然にあるという状況は、ほとんどありませんし、そうである必要もないのです。
好きと得意のハードルを下げ、少しでも関心や情熱を感じたら試してみたり、周りに話してみたりしてみましょう。そういったことの積み重ねが、自分らしさを見つけることにつながります。
方法⑧困ったら助けを求める
自分らしく生きるためには、色々な壁にぶつかることも多いでしょう。
しかし、一度きりの人生を自分らしく生きたいと願うのは、皆が持っている当然の思いです。
そして、誰もがはじめから自分らしく生きられるものではありません。失敗したり、あれこれと迷ったりしながら、追い求めていくのです。
そして、1人で自分らしさを探すことは孤独でさみしいものです。また、1人の力だけでは限界があることも少なくありません。
そのため、自分らしさを探す過程や自分らしく生きるための努力の過程で困ったときは、ぜひ周りに助けを求めていきましょう。
ただ気軽に話すだけでも、自分だけでは思いつかなかった解決策が浮かんだり、前向きになるパワーをもらったりするものです。
まとめ〜無理なく自分らしく生きられますように〜

そもそも自分らしさや自分らしい生き方は、ぼんやりしているものです。
確固とした自分らしさを持つと、柔軟性が失われるとも言えます。
しかし、その一方で、しがらみや社会的な役割、他人の目、親の支配などに自分の人生を奪われることを望む人は、いないでしょう。
そのため、自分に厳しくなりすぎず、無理のない範囲で気長に自分らしさを模索していきましょう。
さて、私たちキズキ共育塾は、お悩みを抱える方のための個別指導塾です。
授業では勉強だけでなく、悩み相談や雑談などを通じて、自分らしさに思い悩む生徒さんに寄り添い、応援しています。
少しでも気になったら、お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。
Q&A よくある質問
なぜ自分らしく生きることは難しいのでしょうか?
以下が考えられます。
- ありのままを認めてもらえない環境にいる
- 「〇〇らしく」「こうあるべき」という役割・規範に縛られている
- 自己否定しすぎる
- 親の支配から抜けられない
- 努力を認められる場がない
- 自信をなくしている
- 助けてくれる人や味方がいない
- 合わない環境から抜け出せない立場にいる
- 心の調子がすぐれない
詳細については、こちらで解説しています。
自分らしく生きる方法を教えてください。
以下が考えられます。
- 安心感を持つ
- 自分の意見を持つ
- 他者の要求や意見と距離を置く
- 肯定的に見てくれる環境を探す
- SNSやインターネットを断つ
- 自分らしさに惑わされない
- 好きや得意のハードルを下げる
- 困ったら助けを求める
詳細については、こちらで解説しています。