アダルトチルドレンとは? 特徴や原因、対処法を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
アダルトチルドレンという言葉をご存知ですか?
近年よく耳にする言葉ではありますが、実際にどのような人を示すのかは、あまり知られていないかもしれません。
このコラムでは、アダルトチルドレンの概要や特徴、原因、タイプ、影響、対処法などについて解説します。
このコラムが、なんらかの形で少しでもあなたのお役に立てば幸いです。
私たちキズキ共育塾は、アダルトチルドレンで悩む人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
アダルトチルドレンとは?

アダルトチルドレン(Adult Children、AC)とは、何らかのトラウマ・心的外傷をもたらしうる家族・家庭環境の中で育ち、成長してから生きづらさを感じている状態、またはその状態にある成人のことです。(参考:信田さよ子『アダルト・チルドレン:自己責任の罠を抜けだし、私の人生を取り戻す』)
なお、アダルトチルドレンは、医学的に正式な診断名称ではない俗語です。アダルトチルドレンと呼ばれるような気質の影響から病気・障害を発症する可能性はありますが、アダルトチルドレン自体は病気や障害などではありません。
アダルトチルドレンは、機能不全家族のもとで育つことでなると言われています。
機能不全家族とは、親が親としての十分な責任と機能が果たさないために、子どもが子どもらしく生きることのできない、安心・安全感のない家族・家庭のことです。アルコール依存症やギャンブル依存症の親によって、暴力や虐待が日常的にくり返されている家庭などが該当します。
もともとは、アルコール依存症の親がいる家族・家庭の中で育った成人のことのみを指していた概念でしたが、近年ではアルコール依存症の親がいる家庭環境に限らず、虐待や育児放棄、家庭内不和などのある環境で育った成人にも一般化されるようになっています。
この概念は1970年代のアメリカで注目されはじめ、1990年代には、日本でもこの概念が浸透し、カウンセリング現場でも広く認知されるようになりました。
アダルトチルドレンの特徴
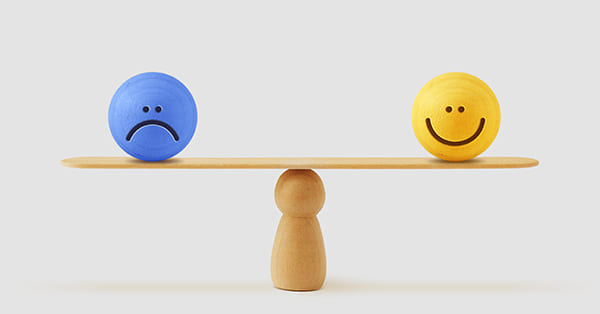
アダルトチルドレンには、エネルギッシュでイキイキした部分=リアルな自己(インナーチャイルド)と、機能不全家族によりリアルな自己を窒息させ、否認したことで生まれた共依存自己の2つが現れる言われています。(参考:C.Lウィットフィールド『内なる子どもを癒す アダルトチルドレンの発見と回復』)
リアルな自己については、以下のような特徴が挙げられます。
- 哀れみ深い
- 無条件に愛する
- 傷付きやすい
それに対して、共依存自己については、以下のような対照的な特徴が挙げられます。
- 他者中心的、過度に適合する
- 条件的に愛する
- つねに強いふりをする
アダルトチルドレンにつながる5つの原因・背景
アダルトチルドレンになる原因は、育ってきた環境にあると言われています。
この章では、アダルトチルドレンにつながる原因・背景について解説します。あなたが「自分はアダルトチルドレンかもしれない」と感じるのであれば、参考にしてみてください。(参考:C.Lウィットフィールド『内なる子どもを癒す アダルトチルドレンの発見と回復』)」
原因①虐待・ネグレクト

1つ目の原因は、虐待・ネグレクトです。
ネグレクトとは育児放棄のことで、以下のような種類があります。
- 病院で必要な治療を受けさせない医療的ネグレクト
- 必要な教育を受けさせない教育的ネグレクト
- 子どもが貯めたお金を搾取する経済的ネグレクト など
子どもはこのような環境の中でも、なんとかして生き抜こうと考え、無意識のうちにさまざまな対策を講じます。
しかし、そういった場面における対策は、通常の人間関係や社会では不適切と思われることが多く、なじまないものがほとんどです。
例えば、お酒がないと怒鳴る親のもとで育った場合、子どもは子どもなりに親を怒らせないよう、いつもいい子を演じるため、笑顔でいるよう努めます。
幼少期の生き抜く策であっても、大人になってもそのままでいれば、「本当は何を考えているのか分からない」「人間関係を築くのが難しい」など、さまざまな問題が生じるのです。
原因②機能不全家族
2つ目の原因は、機能不全家族のもとで育ったことです。
家族とはお互いを尊重し、いたわりながら暮らすもの。しかし、機能不全家族はそれらができず、一人ひとりの人格が尊重されず、アダルトチルドレンにつながるのです。
原因③アルコール依存症を患う親による育児

3つ目の原因は、アルコール依存症を患う親による育児です。
アルコール依存症になった親は、意識がお酒ばかりに向き、子どもや周囲への配慮・関心がどうしても薄れます。
そうした育児環境は、子どもへの経済的ネグレクトなどにつながるなど、さまざまな懸念があることを示唆しています。
原因④毒親による育児
4つ目の原因は、毒親による育児です。
毒親とは、一般的に、子どもにとって毒と揶揄されるほどに悪影響を及ぼす親、子ども側が厄介と感じる親などを指す俗称のことです。医学的な診断名でも学術的な用語ではありません。
毒親の特徴として、一般的に以下が挙げられます。
- 適切ではない過干渉や過剰な管理
- 過度な期待
- 価値観の押し付け
- 一方的な価値観・行動の否定
毒親と呼ばれるような親がいる環境で育った場合も、リアルな自己と共依存自己を生成し、アダルトチルドレンになりやすいと考えられています。
原因⑤子どもの特性を理解しない親による不適切な養育

5つ目の原因は、子どもの特性を理解しない親による不適切な養育です。
子どもは生まれながらさまざまな特性を持っているものです。
特性の中には、注意力や集中力が乏しい、理解力が低い、忘れっぽいなど、親にも子ども本人にも気になるものがあることがあります。
そのような特性に対して親がストレスを抱えると、子どもに対して支配的になったりするほか、手を挙げることも少なくありません。
このように、子どもの特性をうまく理解できていないと、親は虐待などの不適切な教育を続け、アダルトチルドレンになる原因になることがあります。
アダルトチルドレンの6つのタイプ
この章では、高倉久有氏と小西真理子氏による研究結果に基づき、アダルトチルドレンのタイプについて解説します。(参考:高倉久有、小西真理子「毒親概念の倫理 : 自らをアダルトチルドレンと「認める」ことの困難性に着目して」、井村文音、松下姫歌「サブシステムに着目した家族機能とアダルトチルドレン傾向との関連について」)
ACは機能不全家族の中で生き残る(survive)ために、特徴的な役割を演じ、その心的特徴を内面化する。それは、大人になった後も引き継がれ、生きづらさの原因となる。こうした役割は、事実上強制された受動的なものであると同時に、機能不全な家庭の中で自らと自らの家族を守るための主体的な生存戦略だったのである。AC の代表的な役割として、①ヒーロー、②スケープゴート、③ロストチャイルド、④ピエロ、⑤プラケイター、⑥イネイブラーがあげられる。
引用:高倉久有、小西真理子「毒親概念の倫理 : 自らをアダルトチルドレンと「認める」ことの困難性に着目して」
タイプ①ヒーロー

1つ目のタイプは、ヒーローです。
『毒親概念の倫理 : 自らをアダルトチルドレンと「認める」ことの困難性に着目して』では、ヒーローについて以下のように説明しています。
勉強やスポーツなどで好成績をあげて、家族がよく見えるようにする子ども。子どもは努力を積み重ね続ける。しかし、努力をしても上には上が存在するし、そのなかで 1 位を取れない「私」は無価値である。他人から見ればすばらしい子どもに見えても、本人は自分のことを「不完全」で「無価値な」存在だと考えている。
引用:高倉久有、小西真理子「毒親概念の倫理 : 自らをアダルトチルドレンと「認める」ことの困難性に着目して」
ヒーローは、自分がよく見えるように知らないうちに努力し続け、親が納得する成績を取れなければ「不完全」「無価値」のように感じる特徴を持ちます。
タイプ②スケープゴート
2つ目のタイプは、スケープゴートです。
『毒親概念の倫理 : 自らをアダルトチルドレンと「認める」ことの困難性に着目して』ではスケープゴートについて以下のように説明しています。
犯罪行為や逸脱行為、非行を繰り返したり、病気や怪我を頻繁にしたりする子ども。自分の存在に注目してもらうためや、家族内に問題があることを代表して表現するために、反社会的な行動を取る。
引用:高倉久有、小西真理子「毒親概念の倫理 : 自らをアダルトチルドレンと「認める」ことの困難性に着目して」
要約すると、家族や周囲の気を引くために、悪いことや問題を生じさせる特徴のある子どものことです。
タイプ③ロストチャイルド

3つ目のタイプは、ロストチャイルドです。取り上げるメディアによっては、ロスト・ワンと呼ばれることもあります。
『毒親概念の倫理 : 自らをアダルトチルドレンと「認める」ことの困難性に着目して』ではロストチャイルドについて以下のように説明しています。
家族と何をするにもいっしょに行動しなかったり、気がついたらいなくなったりしている子ども。家族内の人間関係を離れ、自分の心が傷つかないようにしている。
引用:高倉久有、小西真理子「毒親概念の倫理 : 自らをアダルトチルドレンと「認める」ことの困難性に着目して」
ロストチャイルドは、一人で遊んだり部屋に閉じこもったりするなど、孤独な行動を取る人のことと言えるでしょう。
タイプ④ピエロ
4つ目のタイプは、ピエロです。取り上げるメディアによっては、マスコットと呼ばれることもあります。
『毒親概念の倫理 : 自らをアダルトチルドレンと「認める」ことの困難性に着目して』では、ピエロについて以下のように説明しています。
家族のなかでおもしろく振舞い、家族の葛藤を減少させる子ども。家族のなかではペットのような扱いを受けており、当人もそれを楽しんでいるかのようにみえる。しかし、道化の仮面の後ろに寂しさを抱えている。
引用:高倉久有、小西真理子「毒親概念の倫理 : 自らをアダルトチルドレンと「認める」ことの困難性に着目して」
ピエロとは、辛さや孤独といったネガティブな感情を抑え、常に明るく振る舞い、家族や周囲に気を遣う特徴をもった人のことと言えるでしょう。
タイプ⑤プラケイター

5つ目のタイプは、プラケイターです。
『毒親概念の倫理 : 自らをアダルトチルドレンと「認める」ことの困難性に着目して』では、プラケーターについて以下のように説明しています。
家族の混乱を最小限に抑えるため、仲介役を取る子ども。「小さなカウンセラー」、「リトルナース」とも呼ばれている。他人にばかり注意を向けるので、自分の感情を認識できない。
引用:高倉久有、小西真理子「毒親概念の倫理 : 自らをアダルトチルドレンと「認める」ことの困難性に着目して」
プラケイターは、他人の感情や他人からの評価を気にする人と言えるかもしれません。
タイプ⑥イネイブラー
最後のタイプは、イネイブラーです。
『毒親概念の倫理 : 自らをアダルトチルドレンと「認める」ことの困難性に着目して』では、以下のような特徴を挙げています。
幼いころから、他人の世話を焼いて動き回っている。両親が不仲な場合、男の子が母親と、女の子が父親と、「まるで夫婦のような」関係を築く。この状態は、情緒的近親姦とも呼ばれており、性虐待を招くこともある。
引用:高倉久有、小西真理子「毒親概念の倫理 : 自らをアダルトチルドレンと「認める」ことの困難性に着目して」
イネイブラーは、他人の世話を過剰にすることによって、逆に相手の問題行動を助長することもあると言えます。
アダルトチルドレンが生活などにおよぼす3つの影響
この章では、アダルトチルドレンが生活などにおよぼす影響について解説します。
当てはまるものがあってもなくても、悩みをあなた一人で抱え込む必要はありません。適切な相談先を見つけ、話をしていく中で、あなたにあった対策・改善策が見つかっていくと思います。
なお、繰り返すとおり、アダルトチルドレンは正式な病名などではありません。アダルトチルドレンは治療できる対象では、精神科やメンタルクリニックを利用することはできません。
ただし、アダルトチルドレンと呼ばれるような気質に関連して病気・障害を発症している場合には、もちろん病院を利用することは可能です。
そして、自分が病気かどうかは自分では判断がつきません。「アダルトチルドレンは病気ではないから…」と思わず、最初から病院に相談してみるのも一つの方法です。その他の相談先の例は、こちらで紹介します。
影響①生活

アダルトチルドレンは、その性格や生き方のために、毎日の生活に生きづらさを感じることがあります。
いわゆる機能不全家族によって形成された現在の人格は、自己愛を感じたり、落ち込みから立ち上がったりする能力がうまく育たず、ストレスを抱えやすいのです。
そのため、抱え込んだストレスから、以下のような精神疾患につながりやすいと言われています。
- 摂食障害
- アルコール依存症
- 不安障害
- 適応障害
- パーソナリティ障害
- 心的外傷後ストレス障害(PTSD)
病気や障害の可能性がある場合は、迷わず病院に行きましょう。
影響②仕事・キャリア
アダルトチルドレンは、自分や周囲を守る気持ちが強いとされています。また、人に嫌われないような生き方を選ぶ傾向にあると言われています。
そのため、組織で働かなければならない仕事では、周囲の目が気になり過ぎるあまり、ストレスを抱えることもあります。
このような場合、個人事業主やフリーランスとして働いたり、コミュニケーションの少ない職種を選んだりすることで、ストレスを軽減できる場合があります。
影響③恋愛

アダルトチルドレンの概念は恋愛関係にも適用されるとし、幼少期の特異な家族体験に起因するアダルトチルドレンの症候が、過度な愛情への期待と恐れにより、恋愛関係上の不全ももたらすとされています。(参考:諸井克英「家族機能認知とアダルト・チルドレン傾向」)
例えば、親に愛されていなかった経験のために、周囲の人にも「また愛されないのではないか」といった不安<を抱えることがあるとされています。/span>
そのため、いつも愛されていたい、自分を認めてもらいたいといった思いが強く、恋愛では相手に愛情を強く求めたりいつもそばにいてほしいと望んだり、嫌われたくない思いから必要以上に尽くしたりするなど、自己犠牲にまでおよぶ場合も少なくないそうです。
このような恋愛を続けていると、相手にあわせすぎたことで自分を見失ったり、相手に依存している状況を恋愛と勘違いすることにつながりかねません。
恋愛に対して違和感をもつときは、パートナーへのこれまでの言動を振り返り、自分を見つめ直すのが望ましいでしょう。
アダルトチルドレンの特徴への対処法
この章では、アダルトチルドレンの特徴への対処法について解説します。
対処法①自助グループや専門機関を利用する

1つ目は、自助グループや専門機関の利用です。
アダルトチルドレンを含めて、「アルコール依存症のある人に影響されてさまざまな障害が生じている家族」が回復の為に参加する自助グループがあります。(参考:こころの情報サイト「相談しあう・支えあう」、厚生労働省「アラノン・アラティーン」、特定非営利活動法人ASK「自助グループ 一覧」)
自助グループや専門機関の利用は、病気とは違うアダルトチルドレンにとって有効な情報を共有し合える場所になるでしょう。
また、アダルトチルドレンと呼ばれるような気質に関連して病気・障害を発症している場合には、病院での相談も可能です。
検索エンジンを活用し「お住まいの自治体名 アダルトチルドレン 自助グループ」などと検索し、実際に相談してみると良いでしょう。
なお、主な相談先としては、以下のものがあります。
- アラノン
- ACA(アダルト・チルドレン・アノニマス)
- ACoA Japan
- 三森自助グループの森
- カウンセリングルーム
- 医療機関
- 精神保健福祉センター
対処法②書籍を参考にする
アダルトチルドレンのことは、書籍で理解を深めることもできます。
他にも、アダルトチルドレンに関する著名人のインタビュー記事やエッセイ漫画などもインターネット上の複数のメディアで掲載されています。
自分だけでは解決の糸口が探しきれないこともあるでしょう。さまざまな書籍や経験をもとに語られたインタビュー記事などを参考にすることで、俯瞰して自分を見ることができ、生きづらさの改善に役立つでしょう。
まとめ〜一人でお悩みを抱え込まないでください〜

アダルトチルドレンであることを克服するためには、当事者である親を含め、周囲との信頼関係構築が大切であると考えられています。
まずは書籍などを参考にすると、生きづらさを少しでも解消に導けるでしょう。
その上で、あなた一人でお悩みを抱え込まず、カウンセリングや互助会を利用してみてください。
このコラムをきっかけに、あなたやあなたの周りのアダルトチルドレンの生きづらさが改善されることを心から祈っています。
Q&A よくある質問









