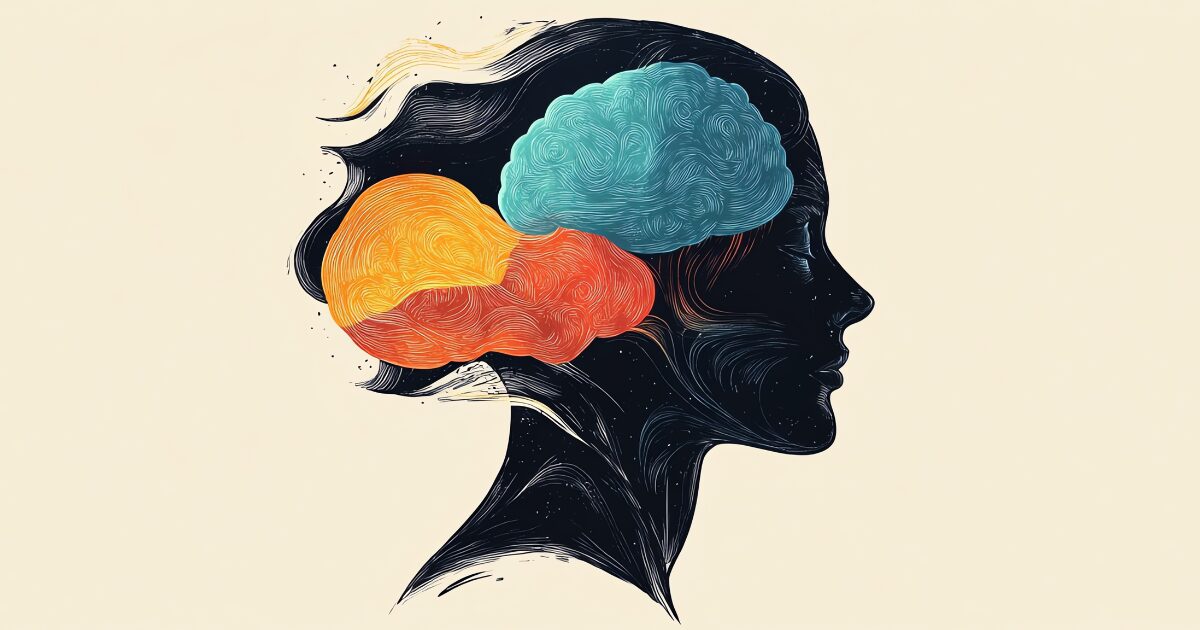自己効力感を高める方法 自己肯定感との違いやメリットを解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたは自己効力感を高めたいと思いつつ、どう高めればよいかわからずお困りではないでしょうか?
自己効力感を高めることで、目標に対して前向きに取り組め、生産性を高める上で効果を発揮します。
自己効力感を高めるためには、そのための環境を整えて、意識的に行動することが大切です。
このコラムでは、自己効力感の概要や高めるメリット、高める方法、高い人の特徴、高める際の注意点について解説します。
自己効力感をどのように高めればよいか、お困りの方はぜひ参考にしてください。
私たちキズキ共育塾は、自己効力感を高めたい人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
自己効力感とは?
自己効力感(Self-efficacy)とは、自分が目標や目的を達成できる能力があると感じている状態のことです。簡単にいえば、「自分ならやれる」と思えている状態を示します。(参考:江本リナ「自己効力感の概念分析」)
アメリカの心理学者アルバート・バンデューラ氏が提唱し始めた概念で、「自己効力感が強い人ほど、実際に行動できる傾向にある」としています。
自己効力感と自己肯定感の違い

自己効力感と似た言葉に自己肯定感があります。
自己肯定感とは、よい部分も悪い部分も含めて、自分のあり方を積極的に評価できる状態、自分の価値や存在意義を肯定的に評価できる状態のことです。(参考:実用日本語辞典「自己肯定感」)
自己効力感は自分のありのままの状態はさておき、自分の自信や能力を対象にしていることが大きな違いです。
自己効力感と自尊心の違い
自尊心とは自分の人格や思想、言動を大切にする気持ちのことです。
自尊心が高い状態は自分の能力や実績など、自分の存在に対して価値を感じている状態で、何らかの根拠があることが多々あります。
自己効力感は、目標や課題を対象にしていることや、根拠を必ずしも必要としていないことが大きな違いです。
自尊心は過去の実績や能力など何らかの裏付けがあることがあります。しかし、自己効力感の場合は、過去の実績や自信など根拠がなくても、「自分にはできる」と思える状態です。これまで体験したことがない目標でも関係なく、自信を保ち続けられます。
自己効力感の3つの種類
自己効力感は大まかに3つの種類に分けられます。
この章では、自己効力感の種類を解説します。
種類①自己統制的自己効力感

自己統制的自己効力感とは、自分自身の行動を自分でコントロールして正しい選択ができるという認識のことです。
自己統制的自己効力感が高ければ、部長やチームリーダーのような責任の重い役職であっても、感情的にならず、自分がやるべきことを把握し、適切な行動を取りやすくなります。
種類②社会的自己効力感
社会的自己効力感とは、対人関係に対して「自分ならうまく関係を築ける」という自己効力感のことです。
社会的自己効力感が高いことで、他者と積極的に関わる姿勢ができ、共感しながら良好な関係を構築しやすくなります。
種類③学業的自己効力感

学業的自己効力感とは、勉強に関する自己効力感のことです。「大学受験で目標となる大学に合格できた」「難易度の高い資格を取得できた」などの経験から育まれます。
学業的自己効力感が高ければ、自分から学びにいく姿勢が強まり、自分のスキルを積極的に高める姿勢がみられるようになります。
自己効力感が高い人の3つの特徴
自己効力感が高い人にはいくつかの特徴があります。
この章では、自己効力感が高い人の特徴を解説します。
特徴①ポジティブな振る舞いが多く自信に満ちている

自己効力感が高い人は日頃から自信に満ちていることが特徴です。
何気ない日常会話でも、ネガティブな考えを持っていないため、そのような話題も出てこない傾向にあります。
特徴②ストレスに強い
自己効力感が高い人はストレスのある環境でも、落ち込みにくいことが特徴です。
厳しいプレッシャーや状況下にある場合、自己効力感が高くない人はネガティブな言動が増えてしまいます。
自己効力感が高い人はストレスがかかる状況であっても、不安感を感じにくくなり、あきらめるような行動を取りにくく、「自分には悪い状態も解決できる」という気持ちを持っていることが特徴です。
今の現状をマイナスに考えず、自分に何ができるかを考えて行動できる傾向にあります。
特徴③コミュニケーション能力が高い

自己効力感が高い人はコミュニケーション能力が高い傾向にあります。
他者と話すときに「この人とよい関係を作れる」という気持ちが強い傾向にあり、積極的なコミュニケーションを取れるためです。
また、コミュニケーション上でトラブルがあった場合も、感情的にならず「何が問題だったのか」を冷静に考えられます。そのため、自己効力感が高いことで、トラブルがあった際もスムーズに対処可能です。
自己効力感を高めるメリット5点
自己効力感を高めることで、仕事でもプライベートでもメリットがあります。
この章では、自己効力感を高めるメリットを解説します。
メリット①あらゆるものごとにチャレンジしやすくなる

自己効力感が高い人は、難しい目標でも積極的にチャレンジをするようになります。
たとえ目標が難しくても、「自分にはできる」という思いがあり、失敗する怖さが軽減されるためです。
メリット②失敗からの立ち直りが早まる
自己効力感が高い人は失敗しても、それほど落ち込まず立ち直りが早い傾向にあります。
一度失敗しても「次は成功できる」という気持ちがあり、失敗から学びを得て次に生かそうという気持ちが強い傾向にあるためです。また失敗した後も、再チャレンジを積極的にするようになります。
メリット③モチベーションが高い状態で安定する

自己効力感が高い人は、モチベーションが低い状態になりにくくなります。
「自分にはできないかもしれない」というネガティブな気持ちを持つことが少なくなり、向上心をなくしにくいためです。
メリット④目標を達成しやすくなる
自己効力感が高い人は、目標を達成するまで取り組み続ける姿勢があり、目標達成をしやすくなります。失敗しても、落ち込まず、すぐに目標達成に向けての取り組みを開始できるためです。
また、周囲に対してもポジティブな働きかけができ、チーム内外問わず、周囲の協力を引き出せる傾向にあります。その結果、難易度が高い目標でも、目標を大幅に超えて達成できるというケースも0ではありません。
メリット⑤周囲と良好な関係を作りやすくなる

自己効力感が高いことで、周囲との良好な関係を作りやすくなります。自分自身に対してポジティブな気持ちを持っていることで、周りにもポジティブな気持ちが伝わるためです。
「自分は〇〇さんと仲良くできる」という気持ちを持っており、友好的な立ち振る舞いが自然とできることも要因の1つです。
自己効力感を高める方法6選
自己効力感を高めるには6つの方法があります。
この章では、自己効力感を高める具体的な方法について解説します。
方法①成功体験を積む

何らかの目標を自分の力で達成する経験があることで、自己効力感は高まります。特に時間や労力が必要で、難易度が高い目標であるほど効果的です。
目標を達成する経験が増えることで、成功するイメージや具体的な行動がイメージしやすくなります。
他の方法と比較すると簡単ではありません。しかし、確かな裏付けができるため、自己効力感を高める上で特に重要な方法です。(参考:坂野雄二・前田基成・編著 『セルフ・エフィカシーの臨床心理学』)
方法②他人を見本にする
他人の成功体験を自分の目で観察することも自己効力感を高める方法のひとつです。
他人の成功を身近で経験することで「自分にもできる」という気持ちを持つことにつながります。
具体的な方法として挙げられるのは、「目標についてすでに達成している人の話を聞く」「本やブログで似た経験のある人を探す」などの方法です。
何をすべきか、具体的なイメージが持てることで、成功のイメージが湧いてきます。
ただし、自分よりも実力や距離が遠すぎる人はイメージしにくく、「できる」というイメージが湧きにくくなります。そのため、イメージがしやすい身近な人や体験を知ることが効果的です。
また、反対に失敗した経験や話の場合は自己効力感を下げることもあります。
方法③ポジティブな言葉をかけてもらう

周囲の人から「あなたならできる」という肯定的な言葉掛けによって、自己効力感は高まります。
そのため、ポジティブな声掛けをしてくれるグループやチームに所属することが効果的です。
反対に「絶対に失敗するな」というような声掛けは失敗のイメージを強めてしまいます。そのため、ポジティブな声掛けをもらいやすい環境ほど自己効力感を高めやすくなるでしょう。
方法④心身ともに健全な状態に保つ
身体の状態は自己効力感に影響を与える大きな要素です。
日々の生活リズムを整え、健康的な生活を意識することで、自己効力感は徐々に高まります。睡眠・食事・適度な運動を心がけ、身体が安心できる状態ができていることが大切です。
方法⑤成功する様子をイメージする

成功の具体的なイメージができていることで、自己効力感は高まります。想像でもよいので、成功したらどうなるかをイメージすると効果的でしょう。
「具体的には成功したらどのような結果になるか」「周りの様子はどう変化するか」「どのような声掛けがされるのか」など、映画やアニメのワンシーンのようにイメージしてみましょう。
また、過去の経験を振り返ってみると、自分では気づいていないだけで類似の成功体験がある場合もあります。
方法⑥カウンセリングを受ける
カウンセリングは自己効力感を高める方法として効果的です。カウンセリングは自分の問題や悩みの解決に向けて、相談や援助を受けることです。
カウンセリングを受けることで、悩みや問題を客観的に見つめられ、悩みの解消や対処法の発見に役立ちます。
ネガティブな要因が解消し、問題解決のイメージができるなどの効果が期待できるためです。
カウンセリングは、精神疾患がある人だけではなく、悩みや解決できない課題がある人にも効果を発揮します。
自己効力感を高める際の注意点4点
自己効力感を高めたい場合には、いくつか注意したいことがあります。
この章では、自己効力感を高める際、どのような点に注意すべきかを解説します。
注意点①目標は難しすぎず、簡単すぎないことが大切

自己効力感を高めるためには、達成経験を積むことが効果的です。
しかし、その目標は難しすぎず簡単すぎない目標であることが大切です。目標が高すぎると挫折する可能性が高まり、目標が簡単すぎると自己効力感が上がりません。
現状のスキルや経験を踏まえ、「ちょっと努力すれば達成できそう」と思える難易度の目標であることを意識し、適切な難易度になっていない場合は、目標を見直し調整していきましょう。
注意点②過剰なアドバイスを求めない
自己効力感を高めるためには「自分で達成した」という経験が大切です。
過剰なアドバイスをもらってしまうと「自分の力で達成した」と思いにくくなります。成功は自分の力ではなく、周りの援助(外的統制)によるものと考えてしまうためです。
もしそのような言葉を多くもらう場合には、過度なアドバイスを控えてもらうよう相談したり、環境を変えたりするとよいでしょう。
注意点③失敗した際のフォローが大切

自己効力感を高めるためには、少し難しいくらいの目標を達成させることが大切ですが、失敗するリスクもあります。
失敗した際の状況をそのままにしておくと、自己効力感が下がる可能性があるため、注意が必要です。
自分が失敗した場合には、前向きな声掛けがもらえる場所にいることを意識し、気持ちが落ち込みすぎないように心がけましょう。
注意点④本人がやりたいと思うことが大切
自己効力感を高めるためには、目標が本人がやりたいと思えること(内発的動機づけ)であることが重要です。
例えば、昇給や評価など周囲から得られる動機づけ(外発的動機づけ)のみで、内発的動機づけがない場合には、成功しても自己効力感につながりません。
そのため自己効力感のためには、周囲からやれといわれたものではなく、自分自身が何をしたいのか、しっかりと見極めることが大切です。(参考:坂野雄二・前田基成 編著『セルフ・エフィカシーの臨床心理学』)
まとめ〜自己効力感は成功体験を積み重ねることが大切〜

自己効力感を高めるためには、自分で何かを達成したという目標を積み重ねることが大切です。
簡単すぎず難しすぎない目標を設定し、成功する経験が増えていくことで、徐々に自己効力感は高まります。
また、成功体験ができていないタイミングであれば、成功のイメージを持てるよう、近くの人に話を聞いたり、調べたりすることも効果的です。
自己効力感を高めたい人は、自分の過去の成功体験の振り返りや、少し難しいくらいの目標に取り組むことから始めてみてください。
Q&A よくある質問