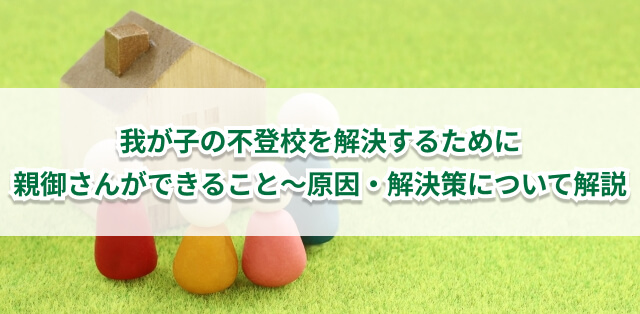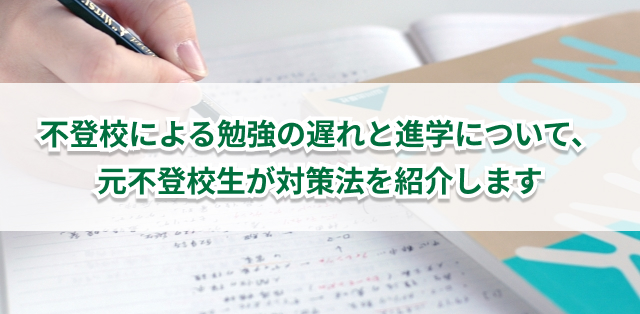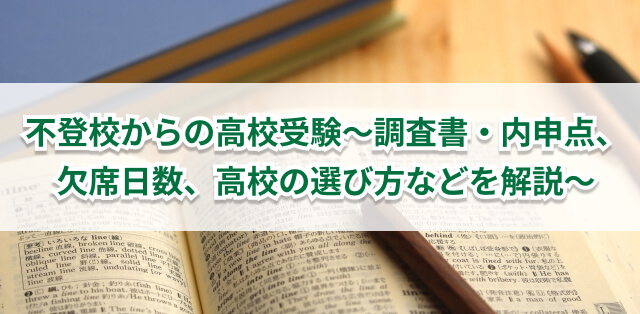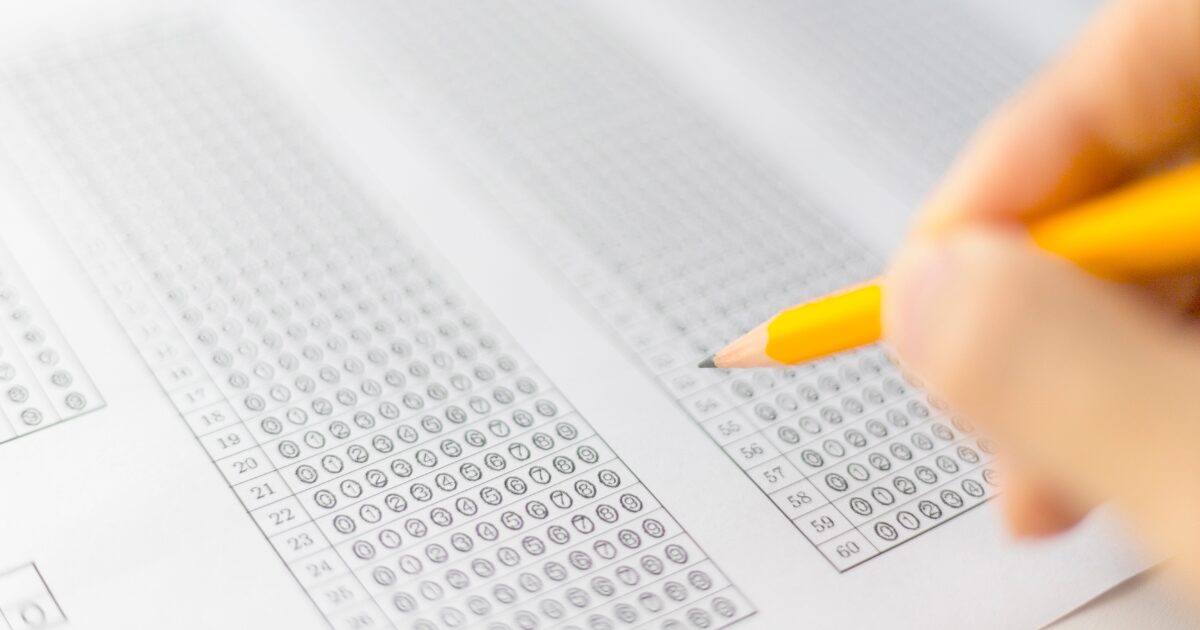教室に入れない子どもの心理 原因や親ができる対応を解説
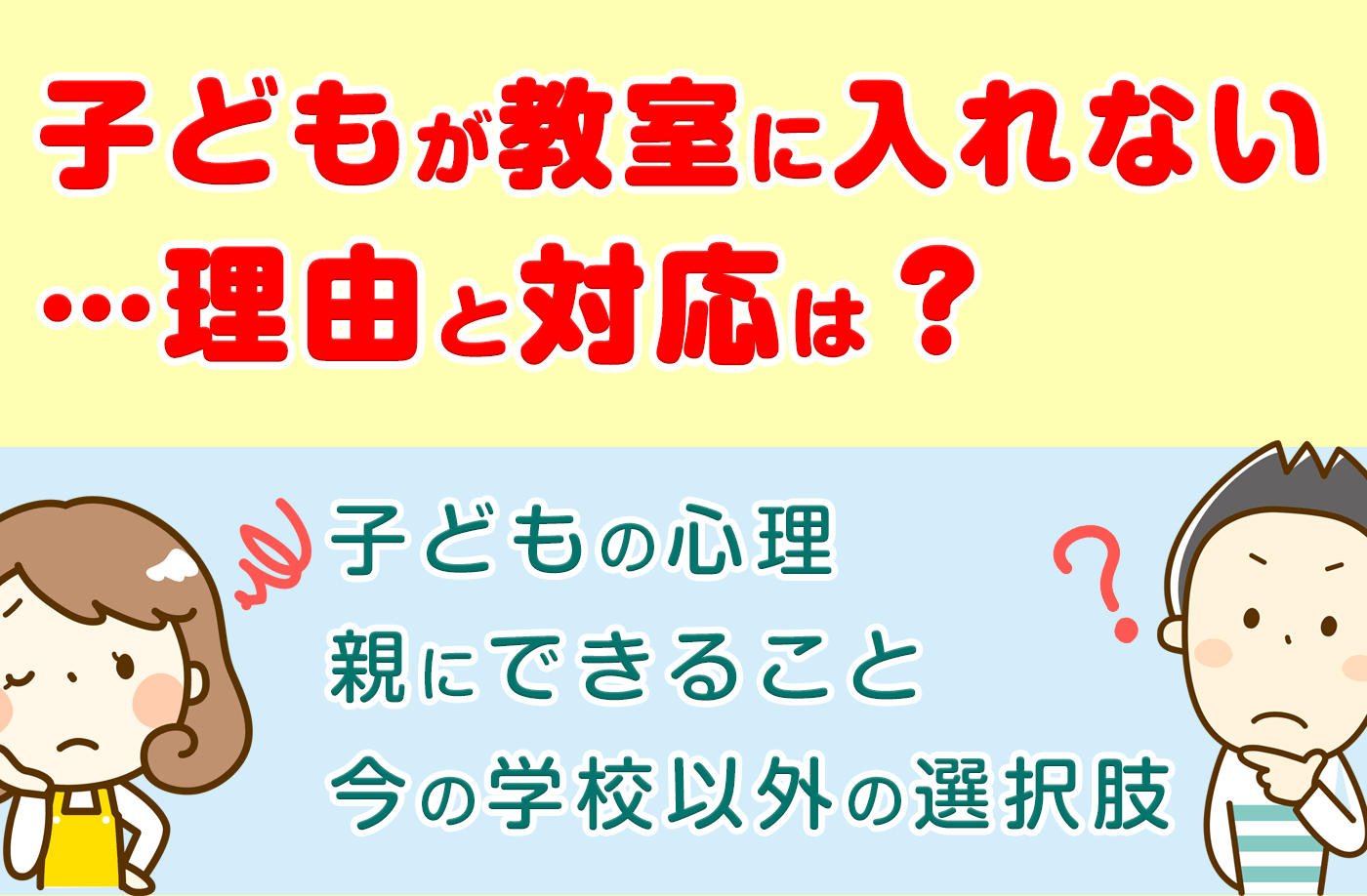
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾の内田青子です。
あなたは子どもが「学校の教室に入れない、入りにくい」と悩んでいませんか?
- 教室に入れず、「休みたい」と言い出した
- 連休が明けてから、教室に入れずに保健室に通っている
このように、子どもが教室に入れない原因がわからず、困惑している親御さんは多くいらっしゃいます。
このコラムでは、子どもが教室に入れない原因や親ができる対応などについて解説します。
このコラムをお読みいただくことで、教室に入れないお子さんの「次の一歩」につながり、親であるあなたのお悩みを減らすことができると思います。
共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの
アドバイス
教室に入れないお子さんの意思を大切にしてください
教室に入れない理由や心理は、子ども自身が説明できるケースはとても少ないです。このコラムに書いてある「子どもが教室に入れない心理・原因9選」は、多くの子に当てはまる内容だと思います。
それぞれを見ると、とてもネガティブに感じられるかもしれません。ですが、絶望的な状況ではありません。教室に入れない子に、「教室への登校」を無理強いすることこそ、将来にわたって深刻な影響を残します。
ぜひ、本人の意思を大切にしてほしいと思います。
私たちキズキ共育塾は、教室に入れないことに悩む人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
子どもが教室に入れない心理・原因9選
この章では、キズキ共育塾の事例から、教室に入れない子どもによくある心理・原因を解説します。
心理・原因①一人ぼっちが苦痛

人の輪に入っていけない子や、クラスに仲のよい友達がいない子は、休み時間やグループ活動のときにどうすればいいのかわかりません。
子どもの心理
- 授業を受けるだけならいいけれど、それ以外の時間が苦痛で、教室に入れない
- 「一人でいること自体は気にならないけれど、周りから『一人ぼっちだ』と思われるのが嫌」で教室にいることがいたたまれない
心理・原因②人がたくさんいる空間が怖い
「人がたくさんいる空間が苦手」で教室に入れない場合があります。
子どもの心理
- 単純なにぎやかさが苦手
- 突然声をかけられたり、周りが何をするのかわからなかったり、といった無秩序が苦手
- 「ある程度の、周りに合わせた行動」を求められる雰囲気が苦痛
特に「保健室登校はできていても、教室には入れない」という場合には、当てはまるかもしれません。
保健室では基本的に「養護教諭と自分」の関係性で過ごしますが、教室では何十人ものクラスメイトや先生と過ごさなくてはならないためです。
心理・原因③繊細で、人に共感しすぎる

教室では、次のように、いろんな場面で「人が責められる」機会があります。
- 問題に答えられなかった生徒が先生に怒られる
- 先生やクラスメイトが何かミスをした生徒を問い詰める
- 言葉のきついクラスメイトが大声で話す
繊細で、人の気持ちに過剰に共感して疲れるお子さんは、こうした場面が苦手で教室に入れないのです。
子どもの心理
- 人が責められる・叱られているのを見ると、自分も怒られているような気がしてつらい
感性が豊かなのはよいことかもしれませんが、共感性が強すぎる性質(HSP・HSC)が関連している可能性もあります。
心理・原因④人の視線が過剰に気になる
クラスメイトや先生の視線が自分に向いているのではないかと過剰に気にして、教室に入れない子もいます。
子どもの心理
- みんなが僕を見ている
- 私を見てみんな笑っている
誰しもある程度は人の目を気にするものですが、それが過剰なタイプです。
ほとんどの場合は実際には注目されていない一方、不登校や入院などでしばらく登校できていない場合などには、実際に好奇の視線を向けるクラスメイトがいることもあります。
心理・原因⑤勉強についていけないのがつらい

クラスメイトと学力的にかなりの差がついた場合、授業を受けたくないと感じ、教室に入れなくなることがあります。
子どもの心理
- 授業で理解できない話をずっと聞き続ける時間が苦痛
- 先生に当てられても答えられなくて、恥ずかしい・怖い
- 勉強そのものが苦手・嫌い
- 勉強はしたいけれど、周りとの差が気になって授業を受けられない
心理・原因⑥いじめがある
いじめも、教室に入れない原因となります。
いじめの例
- 生徒同士のいじめ
- 先生によるいじめ
- 本人が自覚できていないいじめ
自覚できているいじめはもちろん、自覚できていないいじめも、知らず知らずのうちに自己肯定感などを損ない、教室に行く気力をなくします。
子どもが自覚できないいじめの例①
一見すると正義・正論による行動で、「クラスのルールに従わない人は責めてもよい」などのこと。「ルールが正しい。ルールに従えない自分が悪い」と思い込んでしまう。
子どもが自覚できないいじめの例②
悪意を持った先生に「お前はバカだなあ」と言われ続けた子どもが、「自分ががんばって勉強しないから先生にあきれられているのだ。そんな自分は教室に入る資格はない」などと思い込んでしまう。
また、自分がいじめられていなくても、別の人がいじめられていることで、教室に入れなくなることもあります。
子どもの心理
- いじめがある場所は嫌だ
- 次は自分がいじめられるかも
- いじめに対して何もできない自分が嫌だ
心理・原因⑦発達障害が関係する

発達障害が関係して、「学校」や「教室」に苦手意識を持っている場合もあります。
また、これまでにご紹介した心理・原因の裏に発達障害が関係する可能性もあります。
発達障害の次のような「特性」のために、教室で過ごすことが苦痛になっているのです。
音・触覚・味覚などの過敏
- 教室の騒音や突然声をかけられることが怖い
- 味覚過敏で給食が食べられず怒られてしまう
- 体操着や靴の感触が気持ち悪くて耐えられない
衝動性
- じっとしていられない
- 順番を守れない
- 忘れ物が多い
- 上記特性によって、先生に怒られたり周囲に笑われたりする
コミュニケーションの困難
- 人の輪に入れない
- 友達とどう話したらいいかわからない
- 休み時間が孤独で苦痛
勉強面での困難
- 特別なサポートなしで勉強することが困難
発達障害による上記の困難のために「変な子」「できない子」とレッテルを貼られていじめを受けるなど、二次被害を受けることもあります。
発達障害は、努力や叱責で「治る」ものではありません。
発達障害は「一見普通の子に見える」ため、親が気づかないケースも多くあります。
心理・原因⑧家庭環境に問題がある
家庭に子どもが傷つくような「問題」がある場合、それが「教室に入れない」という形で表面化することもあります。
家庭で子どもが傷つく例
- 両親の不仲
- 親の多忙
- 親の再婚や不倫
- 経済的問題
- 家族の死
- きょうだいとの問題
両親の不和が不登校に影響しているケースは、少なくありません。(出典:『公認心理師の基礎と実践⑰ 福祉心理学』中島健一、遠見書房)
それぞれの家庭にはそれぞれの事情があるため、もし今あなたの家庭に上記のような「問題」があるとしても、責めるつもりはありません。
ここではまず、ご家庭の問題が子どもに影響する可能性があることをご理解ください。
心理・原因⑨社交不安障害、過敏性腸症候群などの病気が関係する

「教室に入れないこと」そのものは病気ではありませんが、病気が関係して教室に入れないというケースはあります。
例えば、次のような場合です。
子どもの心理
- 下痢やオナラが頻繁で、恥をかくのではないかと心配(過敏性腸症候群など)
- 人の集まる場所に行くと、動悸や汗が止まらなくなる(社交不安障害)
教室に入れない子どもにできる、親の対応4選
この章では、教室に入れない子どもに親ができる対応を4つ解説します。
対応①子どもに寄り添い、ゆったりと構えつつ、相談先を探す

ご紹介してきたように、子どもが教室に入れない原因は様々です。
子どもに「どうして教室に行かないの?」と聞いても、正直に答えてくれるとは限りません。
子どもは、「みんなと同じようにできない」「いじめられている」といった自分を恥ずかしく思い、その事実を一番親に知られたくないと思うことがよくあります。
大好きなお父さんお母さんだからこそ、自分の情けない姿を見せたくないのです。
親御さんは、子どもの気持ちを受け止めつつ、子どもが原因を話す気になるまでゆったりと待ってください。
ただし、特にいじめや病気が関連する場合などには、ゆったり待つのはオススメできません。
「そもそも、いじめなどが関係するかどうか」「原因に対応すべきかどうか」というところから、詳しい人に相談することが重要です。
子どもに対してはゆったりと構える姿を見せながら、次のようなことを行ってみてください。
- 担任や保健室の先生に、学校での子どもの様子を聞く
- スクールカウンセラーに相談する
- 役所の子育て相談窓口に相談する
- 学校に通いたくない子どもを支援する機関(フリースクールなど)に相談する
- 不登校の親の会に相談する(後述します)
- 病気や障害について、子どもに、病院で検査を受けさせる
親だけで子どものことを抱え込まないようにしましょう。
相談内容は「子どものこと」とは限らず、先述のような「家庭環境のこと」も考えられます。
なお、お子さんも、上記の相談先を利用できることもあります。
特にいじめなどがない場合でも、スクールカウンセラーなどの「他人」が相手ならば、子どもも自分の気持ちを話せることがあります。
原因の追求についての補足
「教室に入れない原因の追求」は、それほど重要ではない場合もあります。
確かに、いじめや病気が関連する場合などには、原因に対応することで次の一歩に進めるようになるでしょう。
一方、「人の輪に入るのが苦手」などの原因で教室に入れない場合、原因がわかったところで、すぐに子どもの性格を変える(=今の教室に入れるようになる)方法が見つかるとは限りません。
そんなときは、「原因の解決」を目指すのではなく、「原因とは別の部分で自己肯定感を養ったりすること」が次の一歩のためには有効だったりもするのです。
そうした、それぞれの子どものための具体的な「方法」も、詳しい人や団体に相談することで見つかります。
対応②子どもの意思を尊重する
子どもに寄り添い、相談先も頼りながら、「これからどうしたいのか」については、子どもの意思を尊重してください。
- 子どもは、教室に戻りたくないのかもしれません
- 保健室ですら、もう行きたくないのかもしれません
無理に教室に向かわせるのではなく、子どもの気持ちをよく聞いた上で、「どうしたら教室に行けるのか」「今の学校(教室)に行きたくないのであれば、これからどうしたいのか」を親子で一緒に考えてください。
ただ、子どもの気持ちは、よくも悪くも揺れ動くことがあります。
「もう今の学校に行きたくない」と言っていても、気持ちを尊重してしばらく休ませると、再び教室に戻れることも珍しくありません。
また、子どもの意思は尊重すべきではありますが、子どもは「知識・経験・判断力が未熟」でもあります。
子どもだけでは「どうしたい」がわからないこともよくありますので、先述の相談機関なども頼ることでアドバイスをもらえます。
対応③先生や学校と良好な関係を築く

特に今の教室(学校)への登校再開を目指している場合には、先生・学校と良好な関係を築きましょう。
先生の状況
- 担任の先生が抱えている生徒は、あなたの子どもだけではありません
- 先生は、多くの子どもたちの問題に対処しながら、授業や生活指導なども行っています
- 残念ながら、「一人ひとりの生徒のことを、いつも、しっかり見守る」ことは、現実としては難しい状況です
多忙な先生(学校)にあなたの子どもの事情をきちんと説明するためには、良好な関係が重要、ということです。
変にへりくだる必要はないのですが、少なくとも、最初から「学校に問題がある!」と決めつけたりせず、丁寧に対応しましょう(残念ながら、結果として学校に問題がある場合はあるでしょうが)。
丁寧な対応がお子さんのためになる例
子どもが発達障害による味覚過敏で給食を食べられなくて教室に入れないため、お弁当を持たせたいと相談するとしましょう。
先生には、一人だけお弁当にすることについて、周りに説明したり、何かの「手続き」があったりするかもしれません。
そうしたことを考えると、丁寧に接することで、先生側の負担が減り、結果として子どもへの対応に使える時間や対応策が増える、ということです。
学校関連では、担任以外にも、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー、PTAなどが頼りになる場合もあります。
そうした相手とも、まずは丁寧に接するようにしましょう。
対応④同じような体験談を聞く
自分の子どもと同じような状況の人、同じような状況を経験した人の体験談を聞くことも、大変参考になります。
他の子どもの体験談から、教室に入れるようになるためのヒントや、登校を再開しない場合の解決策が見つかることもよくあるからです。
不登校の体験談を聞く(読む)ことができる場には次のようなものがあります。
インターネット
「不登校 小学生」「教室に入れない」などと検索し、体験者(またはその保護者)のブログを読んでみましょう。
不登校の親の会
「不登校の親の会」とは、「そういう名前の、一つの団体」のことではなく、「全国にある、不登校の子どもを持つ親御さん同士の交流会」の総称です。
親の会の情報をまとめてくれているウェブサイト(全国の不登校親の会)もあります。
気になる会が見つかったら、電話をかけたり、会合に参加したりしてみましょう。
近所や職場の人に知られたくない場合には、少し離れた町の親の会に参加してみるといいでしょう。
情報収集には、以下のメリットがあります。
- 直接的には、お子さんのためになる「情報」を見つけられる
- 間接的には、親が「外部」に目を向けることで、子どもにかかりっきりになることを防げる
親が子どもにかかりっきりになると、お互いに不安が増幅しやすいのです。
教室に入ることだけが解決策ではありません

「今の学校」「今のクラス」そのものや、「今の集団生活のルール」に馴染めないことは、「悪い」ことではありません。
また、一部の独創的で個性的な子どもは集団に馴染めないことがあるそうです。
例えば、詩人の谷川俊太郎さんは不登校だったそうです。(出典:『子どもと悪』河合隼雄、岩波書店)
どうしても今の教室に入れない場合は、子どもに合った学校への転校や、「学校に行かない選択肢」も考えてみてください。
まず、義務教育である小中学校は、通わなくても卒業できます。高校も、内申書が考査されない高校への進学・転校も可能です。
「今の学校」が合わなくても、「将来に進むための、別のルート」は意外とたくさんあるのです。
今の教室に行かない場合の、3つの選択肢
この章では、「進路」という観点から、義務教育の終了後(中学卒業後)を想定して、3つのルートについて解説します。
お子さんが義務教育中の方も、将来の参考になると思います。
進路①通信制高校に進学・転校する

通信制高校とは、次のような特徴がある高校です。
通信制高校の特徴
- 毎日の通学が必要ない
- 入試は面接や作文のところも多く、無試験の学校もある
- 勉強は、学校から送られてくる教材を利用して、自宅学習を中心に進める
- 単位取得は、レポート提出・年に数回の登校授業・定期テストなどで行う
最大の特徴は「毎日の登校が必要ない」ことですので、教室に入れない人に向いている高校と言えるでしょう。
また、入学・転校のための試験が比較的カンタンであることも、教室に入れなくて勉強が苦手だった人に向いているポイントです。
中学校卒業後に進学する場合、内申書の内容もほとんど問われません(中学校まで欠席がちだったとしても進学しやすい学校と言えます)。
また、他の高校からの転校生も積極的に受け入れています。
進路②高等学校卒業程度認定試験に合格する
高校卒業程度認定試験(高卒認定、高認)に合格すると、高校を卒業せずに大学や専門学校に進学できます。
高認の特徴
- 試験に合格すれば、高卒資格が必要な大学や専門学校の受験・入学が可能になる
- 試験内容は、比較的カンタン
- 満16歳以上であれば受験できる
- 年に2回、各都道府県で実施される
- 昔は「大検」と呼ばれていた
「今は学校に行きたくないけれど、将来的には大学や専門学校に行きたい」と思っているお子さんにはオススメです。
なお、高認合格は履歴書に書くこともできる資格ですが、学歴としては「高校卒業」にはなりません。
高認に合格したとしても、その後大学や専門学校などを卒業しなければ、最終学歴は「中卒」のままであることには注意が必要です。
進路③就職する

中卒後(または高校中退後)にすぐに就職して働く、というルートがあります。
しかし残念ながら、現代日本では、中卒に対する求人はあまり多くないということは、正直にお伝えします。
「中卒で働くなんて絶対に無理」「やめておいた方がいい」とまでは言いません。
ですが、将来の選択肢を広げるためには、次のような方法をお子さんに伝えることをオススメします。
- 働きながら通信制高校(定時制高校)に通う
- 働きながら高認に合格する
以上、「今在籍している学校に行かない選択肢」を選んだ場合のルートをご紹介しました。
キズキ共育塾には、「それまで所属していた学校に行かない」という選択の後に、高認や大学受験を目指す生徒さんが多くいらっしゃいます。ぜひお気軽にご相談ください。
教室(学校)に行かない選択肢を選んだとしても、社会性を養う場を見つけてください
教室に入れない子どもにとって、教室復帰(今の学校への登校再開)だけが道ではないとお話をしてきました。
「勉強」という観点だけで考えると、無理やりに学校に行く必要はありません。
「勉強」は、「塾、問題集、ネット教材などを利用すれば、なんとかなると言えばなんとかなる」ものだからです。
しかし、「学校」は、「勉強を学ぶ場」だけではなく、「社会性を身につける場」でもあります。
ここからは、学校に行かなかった場合や、学校には行けていても人と交流できていない場合の「社会性」について、私自身の経験をもとに考えてみたいと思います。
「教室に入れないかどうか」に限らず重要な話として、先ほどの対応4選とはあえて分けてご紹介します。
社会性を身につけることの重要性〜筆者自身の経験から〜

私は、小中高校とまったく学校に馴染めませんでした(小学生時代は、もう30年も前の話です)。
当時は、「不登校」「スクールカウンセラー」などという言葉はなく、「学校に行かない選択肢」など考えられなかった時代です。
クラスに馴染めない子は「困った子」として、一般的には担任にもクラスメイトにも放置されていました。
私は、学校には我慢をして通いつつも、人の輪に入れず、休み時間には逃げるように図書館に通っていました。
そして、ずっと一人で本を読んでいました。
私の場合は、友達の輪には入れなくても、本を読んでいたおかげか勉強は得意でしたので、「問題はない子」という認識を大人たちにされていました。
その結果、世間的には高学歴といわれる大学に進学しましたが、私の社会性は、皆無ではないものの大きく欠けていました。
そして、社会性の欠如は、社会人になる頃から災いしてきました。
- 就職しても、チームで協力して仕事をすることができない
- 組織で働くことをあきらめてフリーランスの仕事を選んでも、取引先との関係でつまづいて仕事がもらえない
- 恋愛も友人関係もうまくいかず、人との間に壁を感じるばかり
30歳を過ぎるまで、「他人とどう接すればいいのか」と悩み続ける毎日でした。
人間形成期に社会性を養わなかった弊害を、ずっと感じてきました。
しかし、一方では、小学生のときにぽつんとしていた私に話しかけてくれた先生や親切なクラスメイトたちのことを思い出します。
当時は、先生やクラスメイトに話しかけられたり遊びに誘われたりするのが怖くて仕方ありませんでした。
ですが、先生や友達が強引にでもコミュニケーションを取り続けてくれていたおかげで、私の社会性は「皆無」ではなくなり、なんとか社会の一員として、人間関係の中で生活できているのではないかと思うのです。
また、もっと人と交流していれば、より社会性を持てていたのかも、とも思います。
そんな私から、私と同じようなお子さんを持つ親御さんに伝えたいことは、次のようなものです。
子どもを無理に登校させる必要はありませんし、「たまたま同じクラスになった人たち」とうまくやっていけなくても大きな問題はありません。
しかし、子どもが家族以外の人と交流する場を、どこかで見つけてください。
次のように、学校に何らかの形で参加できるのであれば、子どもの背中を押してください。
- 保健室登校で学校に行く
- 参加できそうな授業や学校行事だけ参加する
- 別室登校をして、安心できるお友達や先生に来てもらう
また、学校以外にも、交流を持てる(=社会性を養える)場はたくさんあります。
先ほど紹介した「相談先」、フリースクール、習い事、ボランティア活動、好きなアーティストのオフ会、アルバイト、趣味のコミュニティなどなど。
キズキ共育塾のような塾が交流の場になることもあるでしょう。
フリースクールや塾を利用すると、交流に加えて、勉強そのものや勉強の仕方も学ぶことができます。
子どもが「参加してもいいな」と思える場があれば、ぜひそこに参加し、「社会性」を身につけるように、協力していただければ幸いです。
参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校ジャーナリスト・石井しこう、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。
このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。
このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。
公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら
- 【オリジナル書籍プレゼント】学校外で友だちができるBranchコミュニティ(Branch公式LINEが開きます)
私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。
まとめ〜無理をして学校に行く必要はありません〜

学校、担任、その他相談先と協力しつつ、どうしても学校に馴染めないようであれば無理をして学校に行く必要はありません。
ただし、学校に行かない場合も、勉強や社会性を学べる学校以外の場所を見つけることはオススメします。
あなたのお子さんが、自分に合った次の一歩を見つけられるよう、心から祈っています。
私たちキズキ共育塾では、「学校の教室に入れない」とお悩みの生徒さんが大勢学んでいます。
キズキ共育塾の生徒さんは、穏やかな講師と一対一で会話をしながら、学校での遅れを取り戻したり、コミュニケーションの練習をしたりしています。
「学校に行かない選択肢」を選んで、大学受験に向けてがんばっている生徒さんも多くいらっしゃいます。
子どもが教室に入れずにお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください(親御さんだけのご相談も受け付けております)。
/Q&Aよくある質問
子どもが教室に入れない原因はなんでしょうか(教室に入れない子どもはどのような心理なのでしょうか)。
- 一人ぼっちが苦痛
- 人がたくさんいる空間が怖い
- 繊細で、人に共感しすぎる
- 人の視線が過剰に気になる
- 勉強についていけないのがつらい
- いじめがある
- 発達障害が関係する
- 家庭環境に問題がある
- 社交不安障害、過敏性腸症候群などの病気が関係する
教室に入れない子どもに、親ができることを知りたいです。
- 子どもに寄り添い、ゆったりと構えつつ、相談先を探す
- 子どもの意思を尊重する
- 先生や学校と良好な関係を築く
- 同じような体験談を聞く