HSCとは? 繊細すぎる子どもの特性や対処法、強みを解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたは今、お子さんのHSCについてお悩みではありませんか?
- 子どもがHSCかもしれない
- HSCの子どもとの接し方がわからない…
筆者自身、HSP(Highly Sensitive Person)であるため、日々知識をつけたりさまざまな工夫をしたりしています。
このコラムでは、HSCのお子さんを持つ親御さんに向けて、HSCの概要やHSCのチェックリスト、HSCの特性、HSCの特性による困りごと・対処法、HSCの特性による強み・活かし方について解説します。あわせて、HSCへの理解向上に役立つ書籍・専門家を相談します。
HSCのお子さんを育てたり教育するうえで、困難に直面することは多いものです。一方で、HSCの特性を大切に育むことで、お子さんの強みとして伸ばすこともできるのです。
このコラムが、あなたとあなたのお子さんの、よりよい未来のために役立ちますよう願っております。
私たちキズキ共育塾は、HSC、繊細すぎる子どものための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
HSCとは?

HSCとは、「Highly Sensitive Child(ハイリー・センシティブ・チャイルド)」の略語で、生まれつき感受性が高く敏感で繊細な気質のある子どものこととされています。ただし、HSCは、その人が生まれながらに持っている感受性や気分の傾向など心の特徴・気質を表すための俗称であり、医学的な診断名として認証されているわけではありません。(参考:武田友紀『「繊細さん」の本』、杉本景子・著、はしもとあや・イラスト『一生幸せなHSCの育て方』、エレイン・N・アーロン著、明橋大二・訳『ひといちばい敏感な子』)
「highly sensitive」は、刺激に対して反応しやすいことを意味しており、HSCは精神的なことだけでなく体質的なことについても、「感覚処理に対する神経が、生まれつき敏感・繊細な子ども」という意味で使われることがあります。
HSCとされる子どもは、同じ刺激を受けても他の子どもより強く反応するとされており、刺激の強い環境に長時間いると神経が消耗し、疲弊しやすい傾向があると言われています。
HSCと言われるような苦痛を実際に抱えているという人は、他の病気・障害である可能性があります。気になる人は医療機関に相談することをオススメします。
HSCとHSPの違い
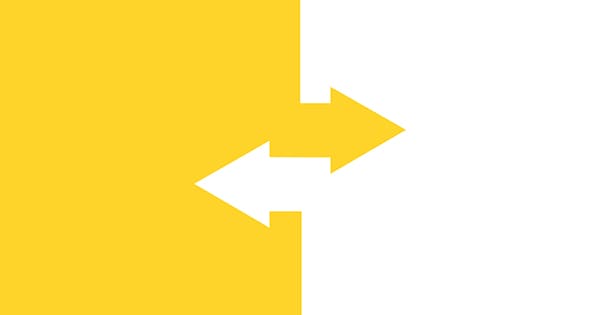
HSCと似た概念として、HSPがあります。
HSPとは、「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)」の略語で、生まれつき感受性が高く敏感・繊細な気質のある人のこととされています。(参考:武田友紀『「繊細さん」の本』)
なおHSC同様、HSPは、その人が生まれながらに持っている感受性や気分の傾向など心の特徴・気質を表すための俗称であり、医学的な診断名として認証されているわけではありません。
HSPは、一般的に敏感・繊細な心の特徴・気質がある大人のことを指す言葉として使われています。一方、HSCはこちらでも解説したとおり、敏感・繊細な心の特徴・気質がある子どものことを指す言葉として使われています。
つまり、HSPとHSCの違いは、「大人のことを指しているか、子どものことを指しているか」の違いと言えるでしょう。
そもそもHSCとは、アメリカの心理学者・エレイン・N・アーロン氏が提唱した概念であるHSPから派生して生まれたものです。
1996年に出版されたHSPに関する書籍『the highly sensitive person』が反響を呼び、以来、HSPが俗称として一般的に使われるようになり、派生してHSCも使われるようになりました。
HSCと発達障害の違い
HSCと発達障害は、まったくの別物です。
こちらでも述べているとおり、HSCは心の特徴・気質を表すための俗称であるため、病気や障害ではありません。また、医学的な診断名でもありません。(参考:杉本景子・著、はしもとあや・イラスト『一生幸せなHSCの育て方』)
一方で、発達障害とは、日常生活や社会生活、学業などにおいてみられる機能障害のことです。そして、医学的に正式な病気や障害です。(参考:厚生労働省「発達障害」)
つまり、HSCと発達障害には、医学的に正式な病気や障害であるかどうかという大きな違いがあるのです。
HSCとADHD(注意欠如・多動性障害)の違い
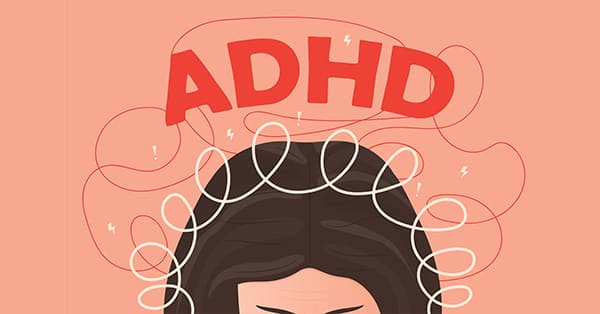
HSCの子どもと似た行動をする発達障害として、ADHD(注意欠如・多動性障害)があります。
しかし、その行動をとる理由や脳の機能は、まったく異なります。(参考:杉本景子・著、はしもとあや・イラスト『一生幸せなHSCの育て方』)
似た行動
- キョロキョロあたりを見渡したり、そわそわしていて落ち着かない
行動の理由
- HSCとされる子ども:ささいな変化によく気付くため、キョロキョロあたりを見渡したり、人や物事を心配したりして落ち着かない
- ADHDのある子ども:色々なものに関心が移り、そわそわキョロキョロする
脳機能の違い
- HSCとされる子ども:左脳に比べて右脳の血流が活発。「冒険することを優先させる働き」よりも「用心することを優先させる働き」の方が強い状態
- ADHDのある子ども:右脳に比べて左脳の血流が活発。「用心することを優先させる働き」よりも「冒険することを優先させる働き」の方が強い状態
HSCとASD(自閉スペクトラム症)の違い
HSCの子どもと似た行動をする発達障害として、ASD(自閉症スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)もあります。
しかし、その行動をとる理由や脳の機能は、ADHD同様まったく異なります。(参考:杉本景子・著、はしもとあや・イラスト『一生幸せなHSCの育て方』)
似た行動
- 着替えや片付けなどができない
行動の理由
- HSCとされる子ども:過度な刺激にさらされ続けると、ストレスから普段はできる作業ができなうなることがある
- ASDのある子ども:予定にない行動が苦手で、突然指示されると固まってしまう
脳機能の違い
- HSCとされる子ども:脳の共感性に関する部位や神経細胞が活発な働きにより、他者に極めて高いエンパシーを示し、人の気持ちがよくわかるため、他者のことでも気になることがあると大きなストレスとなることがある
- ASDのある子ども:場の空気を察することや相手の立場になって考えて行動するのが苦手
HSCのチェックリスト

このコラムをご覧いただいているあなたは、お子さんの様子を見て「HSCもしくはHSCに近い特性がある」と感じているのではないでしょうか?
この章では、HSCの概念の生みの親であるアーロン氏によるHSCのチェックリストを紹介します。
あなたのお子さんの様子や特性と照らし合わせて、どんな部分がお子さんと一致するのかをチェックしてみてください。(参考:エレイン・N・アーロン著、明橋大二・訳『ひといちばい敏感な子』)
HSCかどうかを知るための、23のチェックリスト
以下の質問に、感じたままを答えてください。子どもについて、どちらかといえば当てはまる場合、あるいは、過去に多く当てはまっていた場合には「はい」、全く当てはまらないか、ほぼ当てはまらない場合には、「いいえ」と答えてください。
- すぐにびっくりする
- 服の布地がチクチクしたり、靴下の縫い目や服のラベルが肌に当たったりするのを嫌がる
- 驚かされるのが苦手である
- しつけは、強い罰よりも、優しい注意の方が効果がある
- 親の心を読む
- 年齢の割りに難しい言葉をつかう
- いつもと違う臭いに気づく
- ユーモアのセンスがある
- 直感力に優れている
- 興奮したあとはなかなか寝つけない
- 大きな変化にうまく適応できない
- たくさんのことを質問する
- 服がぬれたり、砂がついたりすると、着替えたがる
- 完璧主義である
- 誰かがつらい思いをしていることに気づく
- 静かに遊ぶのを好む
- 考えさせられる深い質問をする
- 痛みに敏感である
- うるさい場所を嫌がる
- 細かいこと(物の移動、人の外見の変化など)に気づく
- 石橋を叩いて渡る
- 人前で発表するときは、知っている人だけのほうがうまくいく
- 物事を深く考える
得点評価:
13個以上に「はい」なら、お子さんはおそらくHSCでしょう。
しかし、心理テストよりも、子どもを観察する親の感覚のほうが正確です。
たとえ「はい」が1つか2つでも、その度合いが極端に強ければ、お子さんはHSCの可能性があります。(引用:エレイン・N・アーロン著、明橋大二訳『ひといちばい敏感な子』(1万年堂出版)
HSCの4つの特性
この章では、HSCをさらに深く理解するために、アーロン氏が提唱した内容に基づき、HSCの特性について解説します。(参考:エレイン・N・アーロン著、明橋大二・訳『ひといちばい敏感な子』)
最近、私はこの根底にある性質には「4つの面がある」と説明しています。つまり、人一倍敏感な人には、この4つの面が全て存在するということです。
4つのうち1つでも当てはまらないなら、おそらくここで取り上げる「人一倍敏感」な性質ではないと思います。以下の4つを、DOESと覚えてください。
D 深く処理する:Depth of processing
O 過剰に刺激を受けやすい:being easily Overstimulated
E 全体的に感情の反応が強く、特に共感力が高い:
being both Emotionally reactive generally and having high Empathy in particular
S ささいな刺激を察知する:being aware of Subtle Stimuli
(引用:エレイン・N・アーロン著、明橋大二訳『ひといちばい敏感な子』(1万年堂出版)
特性①深く処理する

HSCとされる子どもは、内外から受け取った情報を深く処理する傾向が見られるとされています。
そのため、決断や判断をする際にさまざまな選択肢を考慮して慎重に行動したり、相手の感情の機微にすぐ気がついたりするそうです。
こちらで紹介したチェックリストからいくつか抜粋すると、以下の項目がこの特性に該当します。
- 17.考えさせられる深い質問をする
- 21.石橋を叩いて渡る
- 23.物事を深く考える
特性②過剰に刺激を受けやすい
HSCとされる子どもは、感覚処理に対する神経が生まれつき敏感であるため、神経の興奮が疲労感につながることが多いそうです。
たとえ、嬉しい感情であっても刺激が強すぎると、疲労として身体反応にあらわれやすいため注意が必要になります。
こちらで紹介したチェックリストからいくつか抜粋すると、以下の項目がこの特性に該当します。
- 1.すぐにびっくりする
- 10.興奮したあとはなかなか寝つけない
- 11.大きな変化にうまく適応できない
特性③全体的に感情の反応が強く、特に共感力が高い
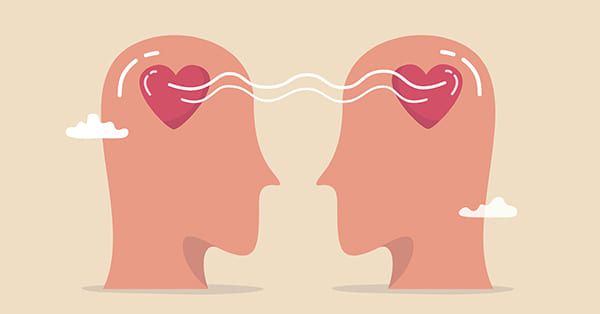
HSCとされる子どもは、共感性や同調性が高い傾向があるとされてます。
心の境界線がもろいため、自己の感情のみならず他者の感情が自然と手に取るようにわかることがあるようです。
こちらで紹介したチェックリストからいくつか抜粋すると、以下の項目がこの特性に該当します。
- 5.親の心を読む
- 15.誰かがつらい思いをしていることに気づく
特性④ささいな刺激を察知する
HSCとされる子どもは、大多数の人が感知しない身の周りに存在するさまざまな刺激に対して、敏感に反応するとされています。
そのため、一見何もしていないように見えていても、本人は多くのエネルギーを消費していることがあり、疲れやすいそうです。
こちらで紹介したチェックリストからいくつか抜粋すると、以下の項目がこの特性に該当します。
- 7.いつもと違う臭いに気づく
- 9.直感力に優れている
- 18.痛みに敏感である
- 20.細かいこと(物の移動、人の外見の変化など)に気づく
HSCの特性による困りごとに対する対処法
HSCとされるお子さんを持つ親御さんやお子さん自身にとって、HSCについて理解を深めることはもちろんのこと、今後どのようにHSCの特性と向き合っていくかを考えることも重要です。
この章では、HSCの特性による困りごとに対する対処法について解説します。
前提:お子さんに味方であることを言葉で伝えましょう

HSCとされるお子さんと接する上で一番重要なのは、どんなときも親御さんがお子さんの味方であることを言葉にして伝え、寄り添う姿勢を示すことです。
親御さんのそういった声掛けや姿勢は、お子さんの安心感につながり、HSCの特性によるストレスや疲れを和らげることにつながります。
とはいえ、親御さん自身がストレスや疲れを抱えていると、心に余裕がなくなり、お子さんと上手く接することが難しくなる場合もあります。
そのため、親御さん自身もお子さんのHSCについて深刻に考えすぎず、適宜休憩を取りながら、お子さんと向き合うようにしましょう。
困りごと①学校などの環境に上手くなじめない
HSCの特性上、不安や緊張などの神経回路が活発と言われています。そのため、集団生活で人よりも疲れを感じやすい傾向にあるそうです。
特に、学校などの長時間大人数の中で過ごさなければならない環境は、つらく感じやすいのでしょう。
そんなHSCとされるお子さんにとって、ご家庭でリラックスできる時間は、消耗した神経を回復させる上でとても重要になるはずです。
お子さんに疲れている様子が見られる場合は、1日がんばったお子さんをねぎらったり、肯定的な声掛けをしてみましょう。
また、疲れが回復しやすくするための行動を促したり、環境を整えたりすることも大切です。
声掛け例
- あなたはあなたのままでいいよ
- 毎日よくがんばっているね
対処例
- ペットを飼い、気持ちがほぐれるようにする
- 日記をつけて感情を解放するよう促す
- 安心できる場所でこまめに休憩をとるように意識させる
困りごと②学校に行きたがらない

がんばって学校に適応しようとした結果疲れ果てると、登校を渋ったり拒否したりする可能性があります。
その一方で、HSCとされるお子さんは、親御さんに心配をかけていることを理解していることが多く、負い目や罪悪感を覚えやすいと言われています。
そのため、親御さんはお子さんに「疲れたときは休んでいいんだよ」と言葉にして伝えるようにしましょう。
声掛け例
- 疲れちゃったね。今日は学校お休みしようか?
- 私に何かできることや、してほしいことはある?
対処例
- 家庭や環境の合う習い事など、学校ではない逃げ場を見つける・用意しておく
- じっくり話を聞く時間を設ける
- 一緒に料理したり、アロマを焚くなど、五感を通じてリラックスできることを行う
困りごと③身体症状が現れたとき
HSCとされる子どもは、ほかの子どもより頭痛や不眠などを引き起こしやすい傾向があるとされています。
また、過剰な神経の興奮が続いて抑うつ状態などが生じた場合、これまでに無理を重ねていた可能性が高いでしょう。
そのため、親御さんはお子さんをいたわり、抱えているストレスを発散できるように工夫しましょう。
身体症状が現れる場合、ほかの病気や障害の可能性があります。もし気になるのであれば病院などの医療機関に相談するといいでしょう。
声掛け例
- がんばりすぎちゃったね、無理しないで
- 今はゆっくり休むことが大切だよ
対処例
- スクールカウンセラーや心理士などのカウンセリングを受ける
- 引っ越しや転校など、思い切って生活環境を一新する
補足:専門家・支援機関に相談しましょう

HSCと言われるような苦痛を実際に抱えているという子どもは、他の病気・障害である可能性があります。気になる場合、医療機関に相談することをオススメします。
クリニック・心療内科などの医療機関を利用することで、HSCとされるお子さんを客観的に理解でき、その後の対応に活かせるアドバイスを得られます。
また、クリニックの仲介やインターネット検索を行うことで、HSCの親の会のような、悩みを相談し合えるコミュニティを見つけられます。
HSCとされるお子さんの悩みについて、親御さんやご家庭だけで抱え込む必要はありません。積極的にいろいろな人を頼ってください。
HSCの特性による強み・活かし方

HSCの特性は、困りごとにつながる可能性がある一方で、強みとして活かすこともできるかもしれません。
特に、HSCとされるお子さんは、共感性が高く感性も豊かであるため、表現活動や創作活動に取り組むことで強みを活かしやすいとされています。
例えば、以下のような活動がオススメです。(参考:杉本景子・著、はしもとあや・イラスト『一生幸せなHSCの育て方』)
- ダンス
- 音楽
- 絵画
- プログラミング
また、HSCとされるお子さんは、自分の好きなことや興味のあることに対して努力することが得意と言われています。
そのため、親御さんも、お子さんから「〇〇に挑戦したい!」「〇〇には興味があるかも」などと言われた際は、無理のない範囲で協力するようにしてみてください。(参考:杉本景子・著、はしもとあや・イラスト『一生幸せなHSCの育て方』)
HSCへの理解向上に役立つ書籍4選
HSCとされるお子さんとよりよく関わっていくためには、日々、情報収集を行い、正確な知識を得ることが大切です。
そして、得た知識からお子さんの傾向を知り、お子さんに適した環境を整えましょう。
この章では、HSCへの理解向上に役立つ書籍を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
繰り返しになりますが、HSCは医学的な根拠がある疾患ではなく、あくまで心の特徴・気質を表すための俗称です。
HSCに関する情報を集める際は、信頼できる人・機関などが発信している情報かを確認した上で、参考にするようにしましょう。
書籍①『ひといちばい敏感な子』

長年の研究によるHSCに関する豊富な知識、お子さんの時期別のアドバイスが掲載されています。
参考:エレイン・N・アーロン・著、明橋大二・訳『ひといちばい敏感な子』
書籍②『子どもの敏感さに困ったら読む本』
多くのHSPを診察してきた第一人者による情報です。
5章にわけ、HSCとされる子どもの子育てにまつわるアドバイスが載っています。
参考:長沼睦雄・著『子どもの敏感さに困ったら読む本』
書籍③『HSCの子育てハッピーアドバイス』

漫画やイラストが多く、HSCとされる子どもへの対処法がわかりやすく学べる一冊です。
参考:明橋大二・著、太田知子・イラスト『HSCの子育てハッピーアドバイス』
書籍④『鈍感な世界に生きる敏感なひとたち』
HSPとされる人向けの内容ですが、巻末のアイデアリストにはさまざまな休息法が載っており、参考になります。
参考:イルセ・サン・著、枇谷玲子・訳『鈍感な世界に生きる敏感なひとたち』
まとめ〜HSCの特性である敏感さを宝物に〜

HSCの特性は、親御さんが接し方や声掛けを工夫することで、お子さんの強みとすることができるかもしれません。
HSCとされるお子さんとよりよく関わっていくためにも、まずは情報収集を行ってみてください。
そして、お子さんのHSCの特性について親御さんやご家庭だけで抱え込まず、医療機関や専門家、支援機関に相談し、お子さんに合った対応や環境を模索していきましょう。
このコラムが、少しでもHSCとされるお子さんの生きやすさにつながったなら幸いです。
敏感で繊細な気質が、あなたとお子さんの宝物になるよう、心から願っております。
さて、私たちキズキ共育塾は、HSCも含めて、不登校、ひきこもり、高校中退など、多様な生徒さんの勉強を支援する個別指導塾です。HSPの特性を持つ講師も多数在籍しています。
もしお力になれることがございましたら、お気軽にキズキ共育塾にご相談ください。ご相談は無料です。また、親御さんだけでのご相談も可能です。
Q&A よくある質問









