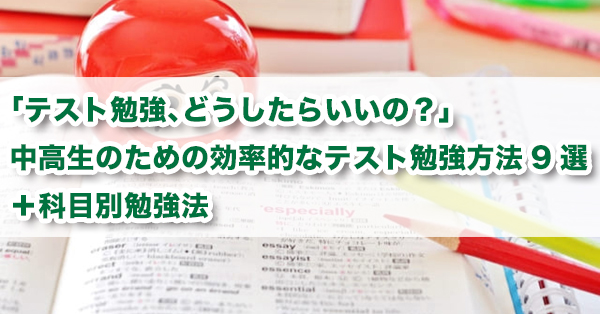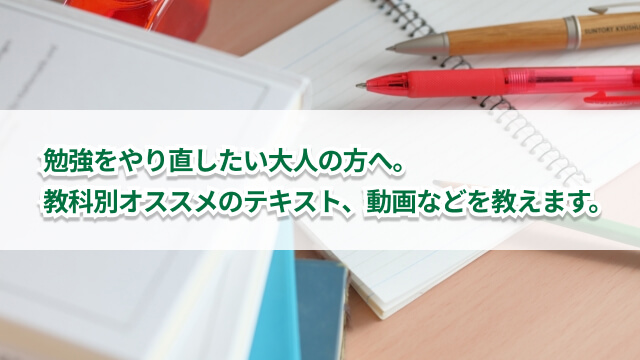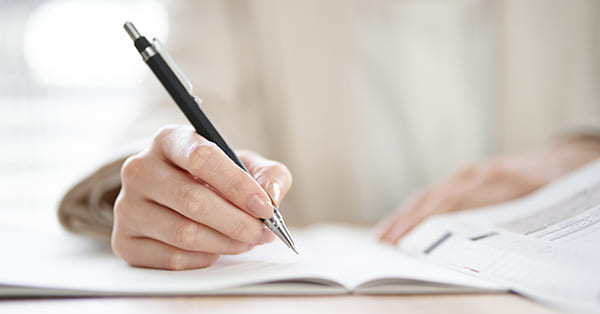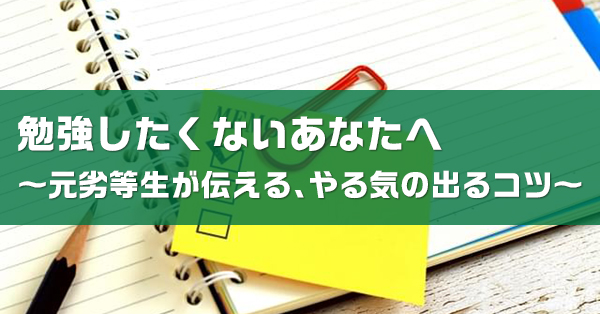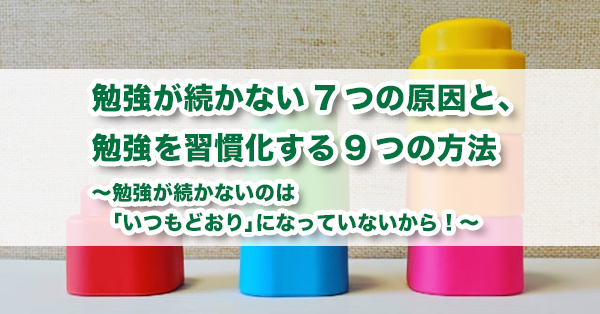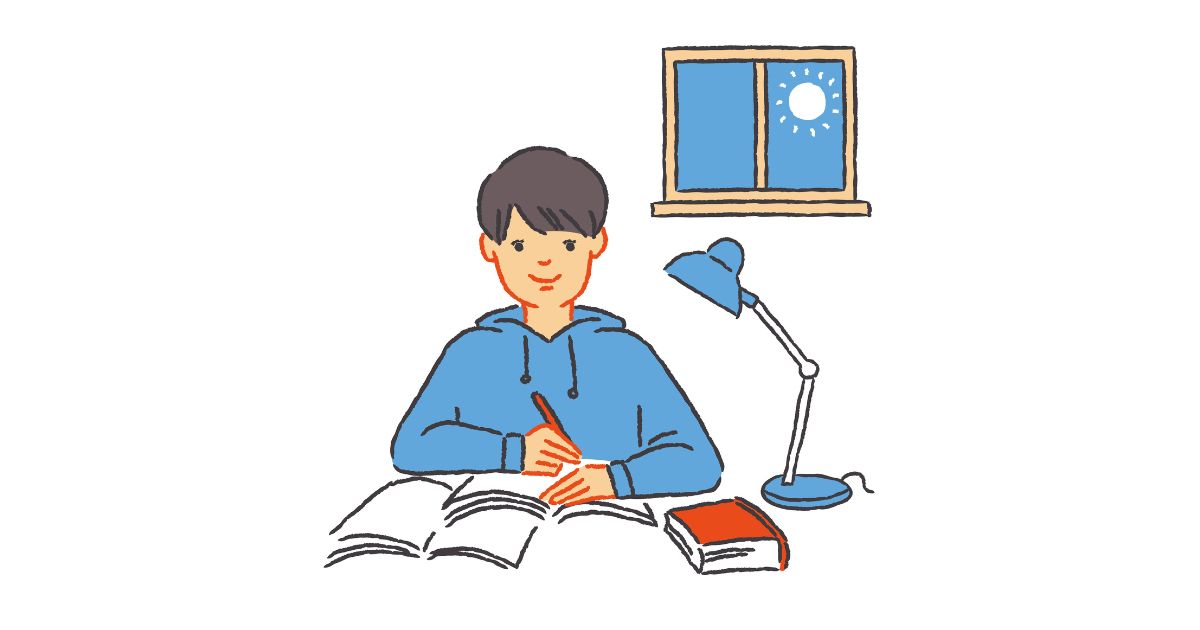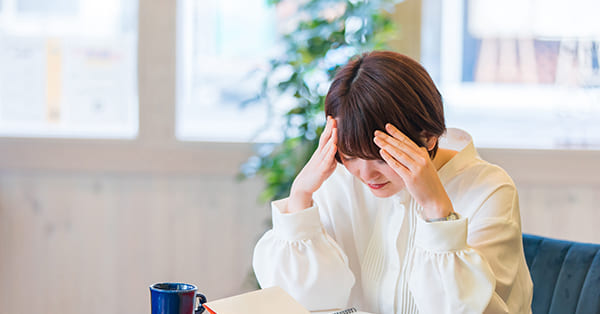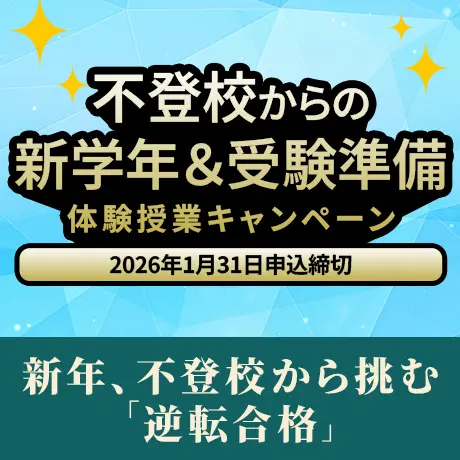ヤングケアラーに勉強する時間はある? 実態や具体的な支援を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
ヤングケアラーのあなたは、以下のようにお悩みではないですか?
- ヤングケアラーの勉強する時間はどのくらい?
- ヤングケアラーが勉強するのにどんなサポートが利用できるの?
このコラムでは、ヤングケアラーの実態や特徴、直面する課題、活用できる具体的な支援策について詳しく解説します。
私たちキズキ共育塾は、家事や介護などで勉強時間が取れない人のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
ヤングケアラーとは?

ヤングケアラーとは、本来大人が担うべきとされる家事や家族の世話などを、日常的に過度に行っている18歳未満の子どものことです。18歳以上からおおよそ30歳未満の若者の場合は、若者ケアラーと呼ばれることもあります。(参考:こども家庭庁ヤングケアラー特設サイト「ヤングケアラーのこと|ヤングケアラーを知っていますか?」、政府広報オンライン「「ヤングケアラー」を知っていますか? ヤングケアラーを支える取組と私たちができること」、日本財団「ヤングケアラーと家族を支えるプログラム」)
子ども・若者育成支援推進法では、以下のように定義されています。
家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者
主なケアの対象は、病気・障害のある家族や高齢の祖父母、幼いきょうだいなどです。
ヤングケアラーは、食事の準備や洗濯などの家事に加え、家族の介助や通院の付き添いなど、多岐にわたるケアを担っています。
しかし、この役割が本人にとって大きな負担となっていても、自分自身や周囲がその状況を問題と認識していないために、福祉サービスを利用せず、ひとりまたは家庭のみで負担を抱え込むケースが少なくありません。
ヤングケアラーの実態
厚生労働省が実施した全国調査により、2020年に中学2年生・高校2年生、2021年には小学6年生・大学3年生を対象に調査が行われ、ヤングケアラーの実態が明らかになりました。 (参考:株式会社 日本総合研究所「令和 3 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 ヤングケアラーの実態に関する調査研究」、三菱UFJリサーチ&コンサルティング「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」)
家族のケアを行っていると回答した割合は以下のとおりです。
- 小学6年生:約6.5%
- 中学2年生:約5.7%
- 全日制高校2年生:約4.1%
- 定時制高校2年生相当:約8.5%
- 通信制高校生:約11.0%
- 大学3年生:約6.2%
平均すると、18人に1人はヤングケアラーがいる計算です。
また、ヤングケアラーがケアする対象は学年ごとに変化することもわかっています。
- 小学6年生:きょうだいの世話が最も多い(約71.0%)
- 中学2年生:父母の障がい・病気によるケア増加
- 高校2年生:祖父母の介護や認知症のケアが増加
- 大学生:母親や祖母の世話が増加
成長するにつれて、より介護の負担が重い家族のケアを担うケースが増える傾向にあります。
社会全体でヤングケアラーの存在を認識し、彼らが自分の将来を諦めることなく成長できる環境を整えていくことが重要です。
ヤングケアラーの特徴

ヤングケアラーの特徴は、以下のような家庭環境・生活状況に該当する子どもたちです。 (参考:こども家庭庁ヤングケアラー特設サイト「ヤングケアラーのこと|ヤングケアラーを知っていますか?」、一般社団法人「日本ケアラー連盟」)
- 買い物・料理・掃除・洗濯などの家事
- きょうだいの世話・育児
- 目を離せない家族の見守りや声掛け
- 日本語が第一言語でない家族のための通訳
- 家計維持を目的とした労働
- アルコール・薬物・ギャンブルなどの問題を抱える家族への対応
- がん・難病・精神疾患など慢性的な病気・障害のある家族の看病・通院の付き添い
- 家族の介助
- 入浴やトイレの介助
- 投薬管理
- 金銭管理
- 情緒面のサポート
ヤングケアラーの負担は家庭によってもさまざまで、学業や日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
ヤングケアラーは、本来享受できるはずの勉強や部活、交友などの時間と引き換えに、ケアに従事している場合があります。
ヤングケアラー支援の法改正
2024年6月12日にヤングケアラーの支援を強化するため、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において子ども・若者育成支援推進法の一部改正が施行されました。 (参考:こども家庭庁「ヤングケアラー支援の強化に係る法改正の経緯・施行について」、e-Gov 法令検索「子ども・若者育成支援推進法」)
この法改正により、ヤングケアラーを「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義し、国や地方自治体が支援に努めるべき対象として明確化されたのです。
改正法では、ヤングケアラーに対し、以下のような支援が規定されています。
- 相談、助言または指導の提供
- 医療および療養の援助
- 生活環境の改善
- 修学または就業の援助
- 社会生活を営むために必要な知識・技能の習得やその他の援助
これらの支援を通じて、今後ヤングケアラーが必要なサポートを受けられる体制の整備が期待されています。
ヤングケアラーが直面する4つの学業面の課題
この章では、ヤングケアラーが直面する学業面の課題について解説します。(参考:株式会社 日本総合研究所「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」、こども家庭庁ヤングケアラー特設サイト 「ヤングケアラーのこと|ヤングケアラーを知っていますか?」、家庭と仕事の両立支援ポータルサイト 「ヤングケアラーと若者ケアラーの実態 -本人と周囲の関わりについて- | コラム|介護と仕事の両立」)
課題①勉強時間の確保ができない

1つ目の課題は、勉強時間の確保ができないことです。
ヤングケアラーの多くは、家族の世話などを優先しなければならないため、勉強時間の確保が難しくなります。
例えば、試験前であっても家族の介護や家事などを優先しなければならず、勉強計画を立てるのが難しいケースがあります。
特に病気・障害のある親がいる家庭では、食事の準備や掃除などの家事も子どもが担うため、日々の勉強時間の確保が困難な状況です。
厚生労働省の調査によると、大学進学の際に苦労したこと・影響のうち、「受験勉強をする時間が取れなかった」と回答した人は約21.6%でした。(参考:株式会社 日本総合研究所「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」)
ヤングケアラーが勉強時間の確保ができないのは、成績の低下だけでなく、進学の選択肢を狭める要因にもなり得ます。
課題②授業についていけない
2つ目の課題は、授業についていけないことです。
ヤングケアラーは、家庭でのケアの負担によって学校を休みがちになると、授業についていけなくなるリスクが高まります。
厚生労働省の調査によると、ヤングケアラーの中で学校を休みがちと回答している割合は以下のとおりです。
- 小学6年生:約97.3%
- 中学2年生:約99.5%
- 全日制高校2年生:約97.6%
- 定時制高校2年生相当:約96.3%
- 通信制高校:約54.3%
- 大学3年生:約13.2%
小中高生の多くが学校を休みがちと感じており、特に中学生では99.5%とほぼ全員が影響を受けていることがわかります。
また、「学校や大人に助けてほしいこと、必要な支援」として、「学校の勉強や受験勉強など学習のサポート」と回答した中学2年生は約21.3%、全日制高校2年生は約18.9%と、最も多くの回答を集めています。(参考:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」)
課題③学業へのモチベーションが低下し成績が下がる

3つ目の課題は、学業へのモチベーションが低下し成績が下がることです。
ヤングケアラーの多くは、宿題や試験勉強の時間も十分に取れないことが多いため、成績が下がるケースが見られます。
例えば、親の介護をしている場合、夜間も世話に追われているため、試験勉強の時間を確保できず、次第に成績が下がる可能性があります。
また、経済的な理由から学習機会が制限されることも、学業意欲の低下につながる要因の一つです。
学校の先生や周囲の理解が十分でない場合、努力していないと誤解され悩んでいるヤングケアラーもいます。そのため、学校生活そのものが精神的な負担になることも少なくありません。
課題④進学を断念するケースもある
4つ目の課題は、進学を断念するケースもあることです。
進学には学費や受験勉強の時間の確保が必要なため、ヤングケアラーは家族のケアを優先し、準備が難しくなる場合があります。
厚生労働省の調査では、ヤングケアラーの中には、希望する就職先・進路の変更を考えざるを得なかったと回答したのが約11.8%と、進学の選択肢を制限せざるを得なかったヤングケアラーがいることも明らかになっています。(参考:株式会社 日本総合研究所「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」)
また、大学進学の際に苦労したこと・影響として、「学費等の制約や経済的な不安があった」(約26.7%)「実家から通える範囲等の通学面の制約があった」(約13.1%)などの回答が多く集まっています。(参考:株式会社 日本総合研究所「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」)
ヤングケアラーが進学を断念する背景には、経済的な問題や家庭の事情が深く関係しています。
ヤングケアラーが直面する4つの生活面の課題
この章では、ヤングケアラーが直面する生活面の課題について解説します。
課題①自分の時間が取れない

1つ目の課題は、自分の時間が取れないことです。
ヤングケアラーは、家庭でのケアが日常的に求められるため、自分自身の時間を持つのが困難です。
厚生労働省の調査によると、ヤングケアラーの中で自分の時間が取れないと感じている割合は、以下のとおりです。
- 小学6年生:約15.1%
- 中学2年生:約20.1%
- 全日制高校2年生:約16.6%
- 定時制高校2年生相当:約19.4%
- 大学3年生:約32.2%
特に、親の介護やきょうだいの世話を日常的にしている子どもは、遊ぶ時間を確保できず、次第にストレスが溜まるケースもあるでしょう。
ヤングケアラーは自由な時間を確保しづらく、精神的な負担が大きくなりやすい状況にあります。(参考:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」、株式会社 日本総合研究所「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」)
課題②自分の悩みを相談しづらい
2つ目の課題は、自分の悩みを誰かに相談しづらいことです。
ヤングケアラーの多くは幼い頃から家族のケアをするのが当たり前だと考えているケースが多く「自分がヤングケアラーだとは思わなかった」「特別なことをしているわけではない」と感じているため、支援を求めること自体が難しい状況にあります。
また、「相談してもどうにもならない」と考え、悩みを打ち明けるのをためらう子どもも少なくありません。
ヤングケアラーは、自分が支援を必要としていることに気付かないまま、日常的に大きな負担を抱えている場合があります。そのため、学校や地域での実態調査を進め、困ったときに相談してもいいという意識を育てる環境づくりが求められます。
課題③友人と遊ぶ時間がない

3つ目の課題は、友人と遊ぶ時間がないことです。
厚生労働省の調査によると、ヤングケアラーの多くがほぼ毎日家族の世話をしています。(参考:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」、株式会社 日本総合研究所「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」)
- 小学6年生:約52.9%
- 中学2年生:約45.1%
- 全日制高校2年生:約47.6%
- 定時制高校2年生相当:約35.5%
- 通信制高校生:約65.3%
- 大学3年生 約24.3%
また、 最も回答が多かった1日あたりに世話に費やす時間は、以下のとおりです。(参考:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」、株式会社 日本総合研究所「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」)
- 小学6年生:1〜2時間未満(約27.4%)
- 中学2年生:3時間未満(約42.0%)
- 全日制高校2年生:3時間未満(約35.8%)
- 定時制高校2年生相当:3〜7時間未満(約25.8%)
- 通信制高校生:3〜7時間未満(約34.7%)
- 大学3年生:1時間以上3時間未満(約36.2%)
小学6年生や中学生の段階から、友達と過ごす時間を持てないことで、孤立感を深める子どももいます。ヤングケアラーが家族の世話と自身の生活を両立できるよう支援が必要です。
課題④睡眠が十分に取れない
4つ目の課題は、睡眠が十分に取れないことです。
ヤングケアラーの多くは、家族のケアによって夜間の睡眠時間が削られ、十分な休息を取ることができません。
例えば、夜中に家族のトイレの介助をしなければならない、薬の管理をしなければならないとなどの理由で、夜間に何度も起きることを余儀なくされるヤングケアラーもいます。
また、病気や障害のある家族がいる場合、夜間も安心して眠ることができず、常に気を張っているため、質の良い睡眠を取ることが難しいケースもあるでしょう。
睡眠時間が削られると、ストレスも溜まりやすくなります。十分な休息を取れるよう、家庭内での役割分担の調整や支援機関の活用が必要です。
ヤングケアラーが利用できる学業支援3選
この章では、ヤングケアラーが利用できる学業支援を紹介します。
なお、2025年3月時点で、自治体ごとに具体的な支援内容は異なります。くわしくは、お住いの自治体にお問い合わせください。
支援①学校や地域の学習支援プログラムの活用

1つ目の支援は、学校や地域の学習支援プログラムの活用です。(参考:厚生労働省「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告」、品川区「ヤングケアラーについて」)
国では、教育委員会を通じてスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの配置を支援し、行政機関との連携を強化しています。
例えば、品川区では2024年度の取り組みとして、ヤングケアラーや若者ケアラーへの訪問型学習支援を実施し、長期休暇を利用した課外学習の場を提供することが決定されています。
ヤングケアラーが学業を諦めることなく、安心して学べる環境を作るためには、学校や地域の学習支援プログラムの活用が不可欠です。
行政・学校・民間が連携し、訪問型支援や課外学習の場を提供することで、より効果的な学習サポートが求められます。
支援②オンライン学習ツールの活用
2つ目の支援は、オンライン学習ツールの活用です。(参考:厚生労働省「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告」、品川区「ヤングケアラーについて」)
ヤングケアラーは、家族の介助や家事を優先せざるを得ず、授業の時間に間に合わなかったり、宿題に取り組む時間を確保できなかったりする場合があります。
オンライン授業の録画配信やアーカイブ機能があれば、空いた時間を活用して自分のペースで学ぶことが可能です。
品川区では、2022年度からオンライン学習の活用を推進し、モデル校での成功事例を全校に共有する取り組みを進めています。ヤングケアラーのように家庭の事情で学校に行けない生徒にも、柔軟に学習を続けられる環境を整えています。
ヤングケアラーは、オンライン学習ツールの活用ができれば、自分のペースで無理なく勉強を続けられるでしょう。
支援③スクールソーシャルワーカーとの連携

3つ目の支援は、スクールソーシャルワーカーと連携し必要なサポートを提供できる環境づくりを進めていくことです。
ヤングケアラーの一部は、子どもであるにもかかわらず介護力と見なされ、大人の介護者と同等に扱われる場合があります。その結果、本当に必要な福祉サービスが受けられず、一人で頑張り続けなければならない状況が生まれています。
この課題の解決のためには、ヤングケアラーの状況を正しく理解してもらうことが重要です。国も家族介護者がいるのを理由に福祉サービスの対象外としないように自治体へ通知を出し、必要な支援が行き届くように取り組んでいます。(参考:厚生労働省「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告」)
ヤングケアラーが介護を当たり前と思い込まず、自分の時間を大切にできるようにするためにも、学校や地域の支援機関とつながり、頼れる場所を増やしていきましょう。
ヤングケアラーに関する相談先3選
この章では、ヤングケアラーに関する相談先を紹介します。
相談先①学校の先生やスクールソーシャルワーカーなどの信頼できる大人
悩んでいるときは、一人で抱え込まずに信頼できる大人に相談することが大切です。
学校の先生やスクールソーシャルワーカーは、ヤングケアラーの状況を理解し、必要な支援につなげてくれる存在です。
家のことで忙しくて勉強時間が取れなかったり、宿題や受験準備に不安を感じたりする場合もあるでしょう。
学校では、スクールソーシャルワーカーやカウンセラーが配置され、必要な支援につなげられる体制が整えられています。また、NPOなどの学習支援の活用で、学校の勉強を続けるサポートを受けられます。
自分はヤングケアラーなのかもしれないと自覚したら、悩みを一人で抱えず、まず信頼できる大人に相談してみましょう。(参考:厚生労働省「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告)
相談先②オンラインサロンや当事者会
同じ立場の仲間と気持ちを共有できる、オンラインサロンや当事者会の活用もオススメです。(参考:厚生労働省「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告、こども家庭長「ヤングケアラー支援体制強化事業の実施について、こども家庭庁「ヤングケアラー当事者・元当事者同士の交流会、家族会など)
ヤングケアラーの中には、自分の状況を理解してくれる人が周囲にいないと感じる人も多いです。
厚生労働省は、ヤングケアラー支援の一環として、SNSやICTを活用したオンラインサロンの設置・運営を推進しています。また、自治体や支援団体もオンラインでの相談支援を強化しており、対面で話しにくい悩みも気軽に相談できる環境が整いつつあります。
ヤングケアラー向けのオンラインコミュニティや当事者会では、同じ立場の人と悩みを共有できるため、孤独感を和らげる効果も期待できるでしょう。
ヤングケアラーとしての悩みを一人で抱え込まず、オンラインサロンや当事者会を活用することで、気持ちを整理し、新たな解決策を見つけられるでしょう。
相談先③匿名で相談できるSNSやオンライン相談窓口

匿名で相談できるSNSやオンライン相談窓口の活用もオススメです。(参考:子ども家庭庁「相談窓口検索結果」、文部科学省「子どものSOSの相談窓口」)
周囲に相談しづらい悩みでも、匿名なら気兼ねなく本音を話せるため、心の整理がしやすくなります。
最近では、LINE相談やチャット相談ができるNPO団体や、公的機関によるSNS相談窓口も増えており、無料で利用できるものもあります。
相談できる窓口は、以下のとおりです。
- 全国のヤングケアラー向け相談窓口を検索できる
- SNS相談対応の窓口を選べば、LINEやチャットを通じて気軽に相談が可能
- 24時間対応の「こどもSOSダイヤル」(通話無料)
- SNS相談が可能な窓口の紹介
- 地域ごとの相談窓口検索機能
- 休日や24時間対応の相談窓口もあり
「学校に行きづらい」「家のことで悩んでいる」「誰にも話せないことがある」場合に、安心して相談できる窓口が整備されています。
SNSやオンライン相談を活用することで、より気軽に悩みを打ち明けることができるでしょう。自分を守るためにも一人で悩みを抱え込まず、こうした支援を積極的に活用することが大切です。
ヤングケアラーが利用できる進路支援
この章では、ヤングケアラーが利用できる進路支援について解説します。
支援①進学・キャリア相談窓口の活用

1つ目の支援は、進学やキャリアについて相談できる窓口の活用です。
ヤングケアラーは、家庭の事情から進学や就職に関する十分な情報を得られない場合があります。そのため、専門的なアドバイスを受けることで、適切な進路を選びやすくなります。
以下のような相談窓口が活用可能です。(参考:埼玉県におけるヤングケアラー支援スタートブック「進学に向けた相談」、一般社団法人ヤングケアラー協会「ヤングケアラーズキャリア」)
- 学校・教育委員会、学習支援教室:進学の選択肢や学習支援について相談可能
- ヤングケアラーズキャリア(LINEやオンライン相談):進学や就職の悩みをオンラインで匿名で相談可能
進学や就職に関する不安がある場合は、これらの相談窓口を活用し、専門家のサポートを受けましょう。
支援②各自治体の進学費用の支援制度の利用
2つ目の支援は、各自治体が実施する進学費用の支援制度の活用です。
ヤングケアラーの中には、家族が十分に働くことができず、進学に必要な費用の工面が難しいケースもあります。自治体の支援制度を活用することで、進学の道を開ける可能性が高まるでしょう。(参考:埼玉県におけるヤングケアラー支援スタートブック「進学に向けた相談」、一般財団法人あしなが育英会「Canpass」、全国社会福祉協議会「市区町村社会福祉協議会のホームページ(検索方法)」)
例えば、市町村社会福祉協議会であれば、生活福祉資金貸付制度(教育支援資金貸付)や奨学金制度についての相談や進学費用の支援制度を案内してもらえます。
参考:全国社会福祉協議会
また、奨学金の情報を検索できるサービスとして、Canpass(一般財団法人あしなが育英会運営)があります。このサービスを利用すれば、自治体や大学独自の奨学金制度を簡単に検索可能です。
参考:Canpass
進学を諦める前に、利用できる支援制度について調べ、必要なサポートを受けましょう。
ヤングケアラーの周囲の人ができる2つの対応
この章では、ヤングケアラーの周囲の人が学校や家庭でできる対応について解説します。
対応①ヤングケアラーとしての自覚を促す

ヤングケアラーの多くは、自身がヤングケアラーであることを自覚していません。
そのため、以下のアプローチを通じて、自分の状況を理解し、必要に応じて支援を受けられる環境を整えることが重要です。
ヤングケアラーの自覚を促し、必要な支援につなげるためには、以下のような対応が有効です。
対応①自然な会話の中で気づきを促す
「最近、家でどんなことをしてる?」「毎日どれくらい家のことをしている?」「やりたいことがあるのに、できないことってある?」など、日常的な会話の中で負担の有無を確認し、共感を示しながら気づきを促す
対応②「YC気づきツール」を活用する
ヤングケアラーの負担を可視化するために、YC気づきツール(こども向け・大人向け)を活用する、学校の教育相談や保健室、スクールソーシャルワーカーの面談時にこども自身にチェックしてもらう
YC気づきツールは、子どもの負担を客観的に評価し、必要な支援につなげやすくすることを目的としています。また、教育・福祉・医療の専門家が、子どもの状況を適切に評価するための指標としても活用可能です。
このツールを通じて子どものケア状況を把握し、早期の支援につなげられるでしょう。(参考:こども家庭庁「ヤングケアラー支援について」)
方法②ヤングケアラーに関する知識を深める
ヤングケアラーを理解し、適切にサポートするには、まず知ることから始めるのが重要です。
ヤングケアラーについて勉強するには、出前講座への参加やオンラインでの情報収集、専門機関が提供する研修を活用する方法があります。
教育機関や自治体、専門機関では、ヤングケアラーについて学べる機会を提供しており、社会全体の理解を深める以下のような取り組みを行っています。
①ヤングケアラー出前講座
- 2024年度は全国9か所の中学校・高校で実施され、ヤングケアラーについて学べる機会を提供
②一般社団法人ケアラーワークスによる研修・相談支援
- 自治体の支援施策にも協力し、研修の講師派遣を実施
③オンラインでの学習・相談
- こども家庭庁の情報発信・公式サイトや資料を活用
- ヤングケアラー関連の動画・記事の閲覧
- 自治体やNPOが提供するオンライン相談窓口の活用
ヤングケアラーについて勉強するには、オンラインでも情報を得られます。興味のある人はぜひ活用してみてください。(参考:こども家庭庁「2024年度のプロジェクトについて」)
まとめ〜ヤングケアラーでも勉強は続けられる!明るい未来を描こう〜

ヤングケアラーの子どもたちは、家族の世話や家事を日常的に担うため、勉強時間を確保するのが難しい状況にあります。
しかし、ヤングケアラーだからといって、学ぶことを諦める必要はありません。
もし「自分はヤングケアラーなのかもしれない」と感じたら、一人で悩まず、信頼できる大人や支援機関に相談することが大切です。学校や自治体の支援制度を活用すれば、自分に合った学びの環境を整えられるでしょう。
ヤングケアラーとしての経験は、あなたの強みになることもあります。支援を活用しながら、安心して学び続け、明るい未来を切り開いていきましょう。