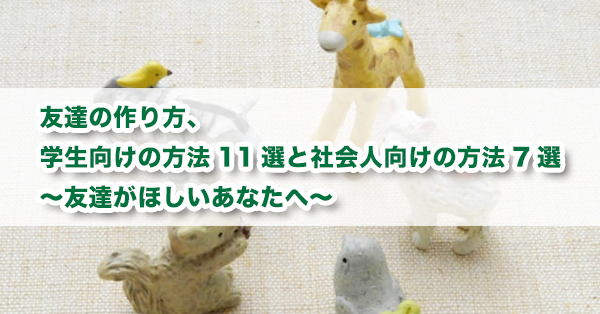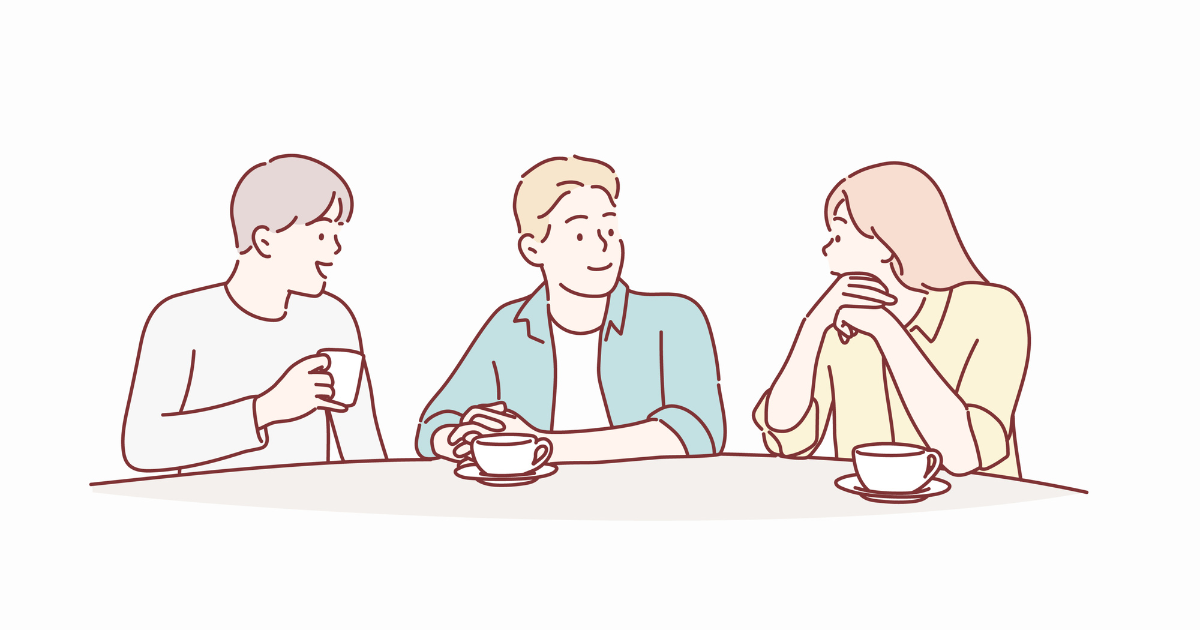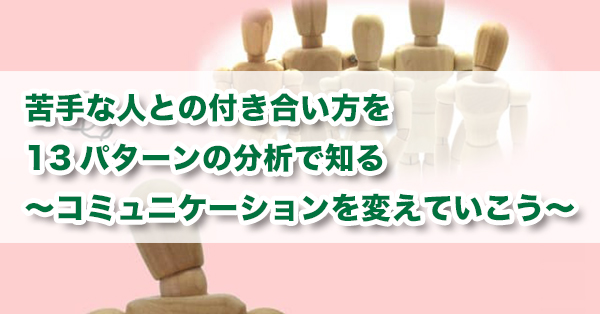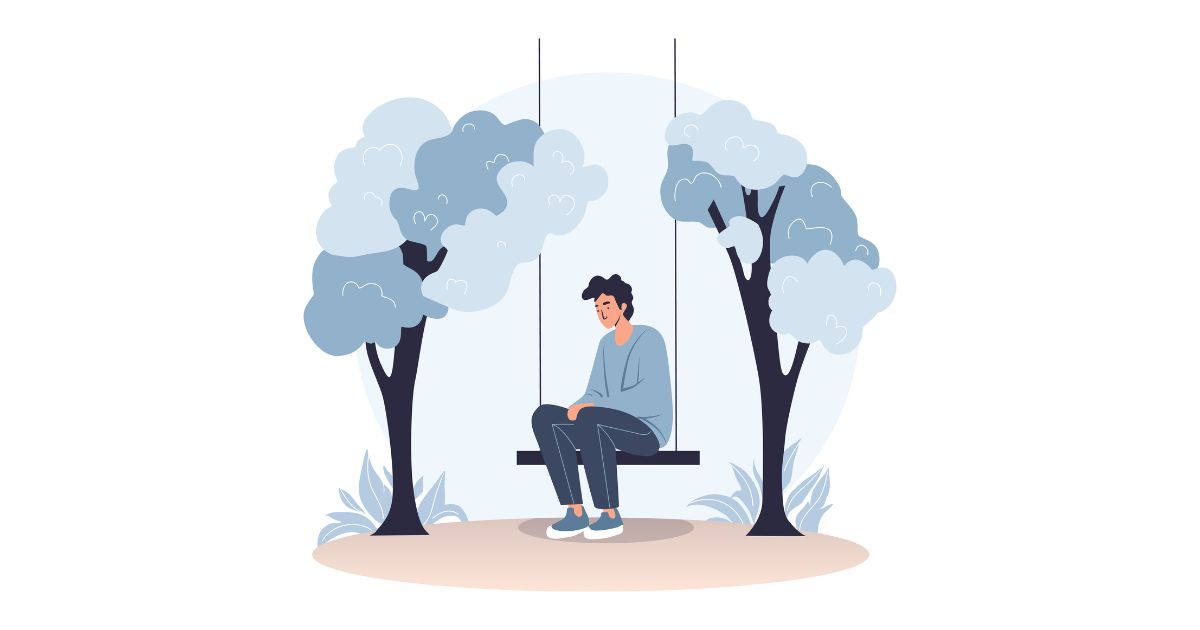集団行動が苦手なあなたへ 乗り切るための対策を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたは、以下のような悩みや疑問を抱えていませんか?
- みんなに合わせて行動できない
- 集団で行動すると息苦しい
- そもそも、なぜ集団行動が必要なの?
集団行動が苦手なことは、決して欠点ではありません。ですが、必要な場面では集団行動もできると、精神的なダメージが少なくてすみますよね。また、発達障害が関係しているケースでは、専門家や周囲の人の支援が必要です。
このコラムでは、集団行動が苦手な人に向けて、集団行動が苦手な人の特徴、集団行動を乗り切るための対策などを解説します。
あわせて、集団行動が苦手なお子さんがいる親御さんに向けて、集団行動が苦手な子どもに親ができる対応も解説します。さらに、集団行動が苦手な人が利用できる支援機関を紹介します。
ぜひ参考にしてください。
私たちキズキ共育塾は、集団行動が苦手な人のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
どうして集団行動をしないといけないの?

集団行動が苦手な人は、「なぜみんなと一緒に行動しなければいけないの?」と疑問を感じることがあるでしょう。
結論から言うと、どんな場合でも集団行動を取らなくてはいけないということはありません。個人の自由が尊重され、それぞれが自発的に動くことを求められる場面も多くあります。
しかし、学校生活やアルバイトの職場では、集団で動く必要がある場面もあります。多くの人がお互いに尊重し合って過ごすためには、みんなで守るルールが必要だからです。
集団行動が苦手な人でも、自分の特徴をしっかりと理解しておけば、集団行動をしなくてはいけないときの対策ができます。まずは、集団行動が苦手な人の特徴から見ていきましょう。
集団行動が苦手な人の特徴
この章では、集団行動が苦手な人の特徴を解説します。
特徴①性格が内向的
内向的な人は、他者との交流よりも自分の内面に意識を向ける傾向があります。そのため、大勢の人と一緒にいることにエネルギーを消耗しやすく、集団行動に苦手意識を感じることが多いのです。
あなたは以下のように思っていませんか?
- 静かな環境で過ごす時間を大切にしたい
- 自分の考えを整理したい
- (心身の)充電をしたい
集団の中にいると、自分の思考や感情に集中することが難しくなり、ストレスを感じやすくなりますよね。
こうした特徴は、決して短所ではありません。しかし、学校や職場など、集団行動が求められる環境では、ときに困難を感じることがあるのです。
特徴②周囲の目が気になる

集団行動が苦手な人は、他人からの評価や判断を過度に意識する傾向があります。
集団の中にいると、自分の言動が周囲にどう映るかが気になり、「間違ったことを言わないだろうか?」「変に思われないだろうか?」といった不安に悩まされがちになります。
こうした意識が強すぎると、集団の中で自然体でいることが難しくなります。本来の自分の姿を出すことに戸惑い、周囲の期待に応えようとするあまり、無理をして疲れるのです。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「周りの目を気にするあなたがすぐできる7つの対処法 楽になる3つの考え方も紹介」
特徴③他人とのコミュニケーションが苦手
コミュニケーションが苦手な人は、集団での行動も苦手なことが多いようです。
特によく知らない人とは、会話の糸口を見つけるのに苦労したり、相手の言葉の真意を理解するのに時間がかかったりすることがあります。また、自分の気持ちや考えをうまく言葉にすることに難しさを感じる傾向もあります。
親しい友人との行動は問題がなくとも、新しい環境や大人数の集まりなどでは集団行動を苦痛に感じるのです。
特徴④意図せず自己中心的に見える
集団行動が苦手な人は、自己中心的であると評価されやすいことがあります。しかしこれは、必ずしも「実際に自己中心的である」とは限りません。
誰にでも、集団の決定やルールに従うことに抵抗を感じることはあります。それがあなたの価値観と大きく違う場合、従うことができないこともあるでしょう。そうした行動が、なにも知らない周囲の人からは、自己中心的に見えていることがあります。
また、発達障害などの特性のため、本人の意図とは違う評価を受けることもあり得ます。
みんなのためと思ってしたことが、かえって裏目に出ることもあるでしょう。こうした経験が積み重なると、集団で行動すること自体に苦手意識を抱くようになるのです。
特徴⑤周囲と価値観が違う

価値観は人それぞれ違います。育った環境が違えば、周囲と違った感覚を持つのも当然のことです。
個性を持ち、自分の意見があることは素晴らしいことなのですが、それがほかの人の価値観と違う場合に衝突することがあります。
学校や職場などの集団だと、より多くの人が共感する価値観をもとに規則が作られる傾向にあります。その価値観に違和感を感じる人は、孤独を味わうこともあるでしょう。そうした行き違いから、集団行動が苦しくなるのです。
特徴⑥自分の役割が分からない
集団の中では、周囲の意見をまとめる人、サポートが得意な人など、それぞれの人が役割を持っています。そこで自分の役割がわからなくなると、居場所がないように感じる人もいるでしょう。
実際には、集団の中で、肩書がつくのはほんの一握りの人だけです。そのほかの人は一人ひとりが小さな力となって、集団全体を支えています。そうした一体感をうまく得られない場合、集団行動は難しいと感じることがあるのです。
特徴⑦自分に自信がない

自分に自信がない人は、自分の価値や能力を低く見積もる傾向があります。集団の中で意見を言ったり、行動を起こしたりする際に、「批判されるのではないか?」「間違っているのではないか?」と強く不安を感じるのです。
また、他者と比較して自分が劣っていると感じる場合もあります。そのために自分の意見や考えを言うことをためらい、結果として本来の能力を発揮できないことも少なくありません。
そうすると、自分の存在意義が集団の中で感じられず、一人でいることを好むようになります。
補足:集団行動が苦手なのは、発達障害の特性が関連している可能性がある
集団行動が苦手だからといって、必ずしも発達障害があるわけではありません。
しかし、一部の特徴は発達障害の特性と重なる部分があることも事実です。
例えば、ASDの場合、対人関係の困難さやコミュニケーションの苦手さ、興味の偏り、こだわりの強さなどの特性があります。こうした特性は、集団行動の際、周囲の人と摩擦を起こすことも少なくありません。(参考:政府広報オンライン「発達障害って、なんだろう?」)
自分一人で発達障害の特性を抱え込むと、うつ病の発症などを引き起こす可能性もあります。「もしかしたら、自分は発達障害かも?」と思ったら、医師や専門に相談してみましょう。
集団行動の3つのメリット
集団行動には、メリットもあります。この章では、集団行動のメリットを解説します。
メリット①多様な視点や考え方に触れられる

集団の中にいると、自分とは異なる経験や背景を持つ人たちと交流できます。さまざまな価値観に触れ、多角的な視点を持つことは、自分自身の成長にもつながるはずです。
また、気の合う仲間や、新しい友達と出会うことも増えるでしょう。親しい相手ができると、集団の中でも、うまく過ごせるようになるかもしれませんよ。
メリット②協調性やコミュニケーション能力が向上する
コミュニケーションは、最初からうまく取れるわけではありません。失敗を繰り返しながら、たくさんの人と関わる中で少しずつ上達するものです。
集団行動は、そうしたコミュニケーション能力や協調性を養う機会ともなります。
集団で活動する中では、役割分担をしたり、ほかの人と意見を交換したり、時には対立したりします。こうした経験を通じて、ほかの人の価値観を尊重しつつ自分の考えを伝える力や、チームワークを大切にする姿勢が養われるのです。
メリット③自己理解や成長の機会が得られる

集団の中で行動していると、自分の強みや弱みに気づいたり、ほかの人からのフィードバックを通じて、新たな自分の一面を発見したりすることがあります。ほかの人を鏡として、自分を顧みる機会もあるでしょう。
また、集団での成功体験は自信につながりますし、失敗からは学びを得ることができます。
集団の中で多感な思春期を過ごすことは、大きな成長の機会にもなり得るのです。
集団行動を乗り切るための6つの対策
この章では、集団行動を乗り切るための対策を解説します。
対策①自分のペースで集団行動に慣れる
集団行動を乗り切るためには、自分のペースで集団行動に慣れることが効果的です。まずは親しい友人との行動や、短時間の活動から始め、徐々に経験を積んでいきましょう。
小さな成功体験を積み重ねて自信をつけていくと、もっと大きな集団行動にも挑戦しやすくなります。
対策②少人数のグループから慣れていく

集団行動に慣れるまでは、少人数のグループへの参加がオススメです。少人数のグループでは、一人一人と関わる時間が長く、コミュニケーションの負担が軽減されます。
慣れてきたら、グループのみんなで参加できるイベントやサークル活動などに挑戦するのもよいでしょう。まずは安心できる集団で過ごし方を学び、少しずつ新しい環境へと入ってみてくださいね。
以下のコラムで、友達の作り方について解説しています。ぜひご覧ください。
対策③自分の得意なものを活かす
集団行動では、自分の得意なものを活かすことも有効です。
集団の中でも、得意なものが活かせる環境なら自信が持てるかもしれません。自分の長所が伸びる環境を選ぶことも、無理なく集団行動するためのポイントです。
対策④休憩時間を設定する

長時間の集団活動は、ストレスが溜まりやすいものです。休憩時間を意識的に設けましょう。
休憩時間には、一人になれる場所を見つけて過ごすことをオススメします。屋外のベンチや静かな部屋など、自分が落ち着ける場所を事前に探しておくとよいでしょう。
5分程度の小休憩でも効果があります。ずっと集団の中にいるのではなく、適度な距離を保つようにしましょう。
対策⑤自分の好きな活動を見つける
集団行動では、その集団自体を好きになれるかどうかも重要です。あなたの趣味や、好きな活動ができる環境であれば、周囲の人とも仲よくなれる可能性が高まります。
学校が苦手であれば、地域のクラブ活動や集まりでもいいですし、フリースクールや学習塾などで方向性が合う場所があれば、利用するのもオススメです。
心のよりどころとなる場所は、苦手な環境を乗り切る力にもなります。自分が安心して長く過ごしたいと思える場所を、探してみてくださいね。
対策⑥全員と仲よくしようとしない

多くの人が、集団で行動する際、全員と良好な関係を築かなければならないと思い込んでいます。しかしこれは、現実的ではありません。
どんな人にも、仲よくなれない相手がいるものです。そんなときはそっと距離を取り、適度な関係を保つことが大切です。
また、友達はいらないと思うのであれば、無理につくる必要はありません。マナーと礼儀を守って、穏やかに過ごすことができれば、集団での生活は大成功です。
集団行動だからといって、無理に(全員と)親しくなる必要はないのです。
友達がいないことのメリットなどについて、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
集団行動が苦手な子どもに親ができる4つの対応
この章では、集団行動が苦手な子どものいる親御さんに向けて、親ができる対応を解説します。
対応①子どものペースに合わせる
心配のあまり、集団行動が苦手な子どもに対してあれもこれもとしたくなるのは親心です。しかし、大切なのは、子どものペースにあわせることです。子どもの不安や苦手意識を理解し、受け入れることから始めましょう。
子どもが集団活動に参加する際は、初めは短時間からスタートし徐々に時間を延ばしていくなど、段階的にアプローチしてみてください。また、活動の頻度も子どもの様子を見ながら調整します。子どもが集団から離れたいと感じたときは、一時的に休憩を取りましょう。
焦らず、子どもの成長を長期的な視点で見守ることが大切です。
対応②肯定的な言葉で褒める

集団行動が苦手なこと自体は、悪いことではありません。否定したり、欠点として扱ったりしないでください。必要なのは、本人も周りも無理なく過ごすための対策です。
子どもの特質を認め、できることを褒めるところから始めましょう。集団行動をしたい子どもであればその意欲を、集団行動はしなくてすむようにしたいと考える子どもに対してはその合理性を、褒めてください。それから、一緒にどうしたらいいかを考えましょう。
肯定的な言葉をかけて子どもの自己肯定感を高め、集団行動に対する前向きな姿勢を支援していきましょう。
対応③居心地のよい環境をつくる
集団行動が苦手な子どもは、居心地のよい環境をどこかにつくることも重要です。
まずは家庭を、安全基地として整えましょう。子どもが自由に自分の気持ちを表現できる雰囲気をつくり、親はそれを受け入れる態度で接します。
子どもが(苦手な)集団活動から帰ってきたときは、ゆっくりと休ませてください。活動でのことを話したくない様子なら、無理には聞き出そうとせず、子どもから話し出すのを待ちます。
また、必要に応じて、学校や活動先の先生と連携し、子どもが安心して過ごせる環境づくりへの協力を求めることも効果的です。
子どもが安心して過ごせる環境を整えることで、集団行動への不安も軽減されていくのです。
対応④こころの病気や発達障害の場合は、特性・症状にあわせた支援をする

こころの病気や発達障害のある子どもの場合、集団行動に対するアプローチには、専門家のアドバイスが必要です。病院を受診し、医師のアドバイスを求めましょう。
子どもの特性や症状を理解し、それに合わせたサポートを行うことで、集団行動への適応を無理なく進めていくことができます。また、病院以外の支援機関のサポートも、積極的に利用しましょう。
集団行動が苦手な人が利用できる支援機関4選
この章では、集団行動が苦手な人が利用できる支援機関を紹介します。
支援機関①スクールカウンセラー

スクールカウンセラーとは、学校現場で児童生徒や保護者、教職員を対象に心理的サポートを提供する専門職のことです。主に学校に配置され、心理学や臨床心理学の専門的な知識をもとに、児童・生徒の悩みや問題に対応します。(参考:文部科学省「スクールカウンセラーについて」)
スクールカウンセラーの主な業務は、児童生徒への相談面接です。相談面接には、個別カウンセリングやグループカウンセリング、コンサルテーション(助言・協議)が含まれます。必要に応じて、教職員へ専門的な立場から助言を行います。(参考:文部科学省「スクールカウンセラー業務」)
学校という身近な場所で専門的なサポートを受けられる存在なのが、スクールカウンセラーです。利用方法については、各学校の担任教師や養護教諭に問い合わせてみてください。
スクールカウンセラーの概要や支援内容などは、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援機関②教育相談センター
教育相談センターとは、公的な相談支援機関で、主に地方自治体が設置しています。
児童・生徒・学生、保護者、教職員を対象に、教育に関する様々な問題について相談を受け付けています。
このセンターでは、相談員として学校心理士や臨床心理士などの専門家が配置されており、集団行動の苦手さを含むさまざまな悩みに対して、専門的な立場からアドバイスや支援を提供します。
相談は対面のほか、電話相談、オンライン相談など、相談者の希望や状況に応じて選択できます。また、必要に応じて継続的な相談も可能です。
集団行動だけでなく、学習面や進路に関する悩み、友人関係の問題など、総合的な観点からサポートを受けられるのが特徴です。
教育相談センターは無料で利用でき、秘密は厳守されます。集団行動に悩む児童・生徒やその保護者にとって、安心して相談できる場所です。(参考:東京都教育相談センター「東京都教育相談センター」)
支援機関③教育支援センター(適応指導教室)
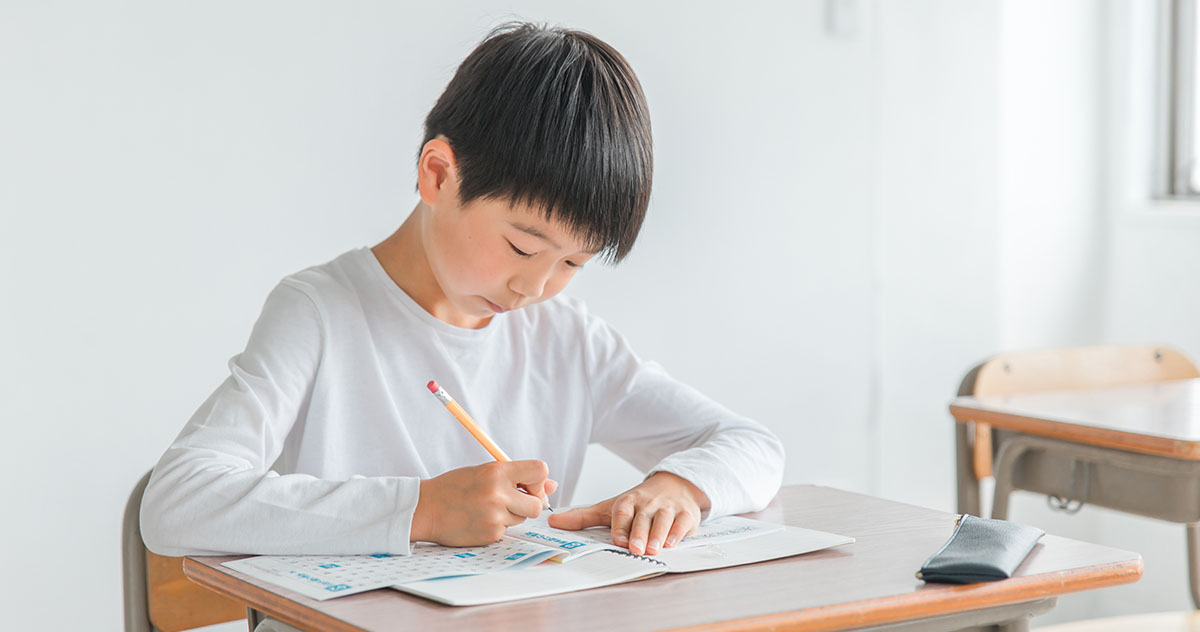
教育支援センター(適応指導教室)とは、主に不登校状態にある児童生徒の学校復帰を支援し、社会的自立をサポートする施設のことです。集団生活への適応や情緒の安定、基礎学力の補充などのサポートを行っています。(参考:文部科学省「適応指導教室(学校支援センター)の取り組みについて」)
なお、適応支援教室とは、教育支援センターの旧名称で、同じ施設を指します。不登校状態にある児童生徒の増加や文部科学省の通知などを受けて、2003年に正式名称が適応支援教室から教育支援センターに変更されています。(参考:立川市教育委員会「適応指導教室から教育支援センターへの名称変更について」)
集団生活が苦手で不登校状態になっている人は、ぜひ相談してみてください。
以下のコラムで、教育支援センター(適応指導教室)について解説しています。ぜひご覧ください。
支援機関④発達障害教育推進センター
発達障害の特性が原因で集団行動が苦手な場合は、発達障害教育推進センターも力になります。
発達障害教育推進センターとは、発達障害にかかわる教員や保護者をはじめとする関係者への支援を図る施設のことです。発達障害に関する情報提供や啓発活動などを行います。
また、発達障害のある子どもの特性に応じた、教育的支援に関する研究や、文献、研究会など、発達障害に関する教育についての情報を提供しています。(参考:発達障害教育センター「発達障害教育センター」)
「集団行動が苦手な人」の状況が、よい方向に変わっていったエピソード
特に学生年齢で「集団行動が苦手な人」について、キズキ共育塾が見聞きした「状況がよい方向に変わっていったエピソード」を紹介します。ぜひ、参考になさってください。
※個人の特定につながらないよう、複数の事例を統合した部分や、趣旨を変えない範囲で事実と異なる部分などがあります。
「学校の外に、心がほどける場所があった」――フリースペースとの出会い
高校1年生の隆太さん。入学した高校は、思っていた以上に「厳格な環境」でした。授業や行事での、ルールの厳しい集団行動がストレスになり、次第に登校をためらうようになりました。
そんなとき、母親が見つけた「地域のフリースペースでの集まり」に通うようになりました。
それは、「学校が合わない」という思いがある中高生が集まる会で、ただ静かに過ごす人もいれば、勉強する人も、楽しく会話する人もいる、自由な空間でした。
初めは会話も少なかった隆太さんでしたが、スタッフの自然な声かけや、同じような状況の仲間との関わりの中で、少しずつ表情が明るくなっていきました。
隆太さんは、今でも「厳格な高校」に慣れたというわけではありません。ですが、安心して過ごせる“もう一つの場所”があることで、大きく心の負担を減らして、登校も集団行動への参加もできるようになりました。
「“ちゃんとしなきゃ”を手放せた」――カウンセリングで見えた心の整理
中学生の陽菜さん。「集団行動は苦手。でも、集団で行動するというルールがあるなら、きちんとしなければならない」と小学生の頃から強く思っていました。
中学校では、小学校よりも集団行動が増えていきました。陽菜さんは、そんな集団行動に対して、絶対に参加する、遅刻しない、全力で行う、成果を出す、自分の発言で場を乱してはいけない…という気持ちで参加し続けました。そして次第に、心身の調子が悪くなっていきました。
スクールカウンセラーに相談したところ、「集団行動は、社会の中で生きていくためには、ある程度はできなきゃいけないかもね。でも、自分の安心を優先することも大切だよ」とアドバイスを受けました。
陽菜さんは、「ちゃんとしなきゃ」に縛られすぎていた自分を客観的に見られるようになりました。
集団行動について、「自分が苦しくない範囲で取り組む方法」を考えたり、先生に「どれくらいの力で取り組んだらいいか」を相談したりできるようになりました。
「給食の時間がつらかった」――一人で食べられる環境が心を守った
中学1年生の彩香さんは、給食の時間が苦手でした。みんなは楽しそうに話していますが、彩香さんには興味のない話題ばかり。
彩香さんは、興味のない会話が交わされていること自体は気になりませんでした。でも、周りから「彩香はどう思う?」と発言を求められることが苦痛だったのです。
興味のない話題で、何をどう発言したらいいのかわかりません。みんな悪気がないことも、彩香さんの悩みを深めます。彩香さんは毎日、緊張しながら昼休みを迎えていました。
ある日、その悩みを保健室の先生に打ち明けけたところ、「給食、保健室でも食べていいよ」と言われました。彩香さんは、戸惑いもありましたがその提案を受け入れました。
「無理に人と話さず、自分のペースで食べられること」は、彩香さんの心の安定につながっていきました。
彩香さんは、「苦手な集団行動があっても、自分を守る選択肢がある」と知って、「これからも、同じようなことがあったら対策を考えよう」と思えるようになりました。
まとめ〜無理して集団行動になじまなくてもいい!〜

集団行動が必要な場面は、社会には多くあります。自分の個性を潜めて集団になじもうとするのは、苦しいことです。
少しずつ、自分のペースで集団になじむ練習をしたり、自分にあった環境を見つけたりして、無理のないやり方を模索してみてください。
周りの大人や、公的な支援機関のサポートも重要です。発達障害などの要因が疑われるときは、医師へ相談しましょう。
自分らしく過ごせる場所や環境を、見つけてくださいね!