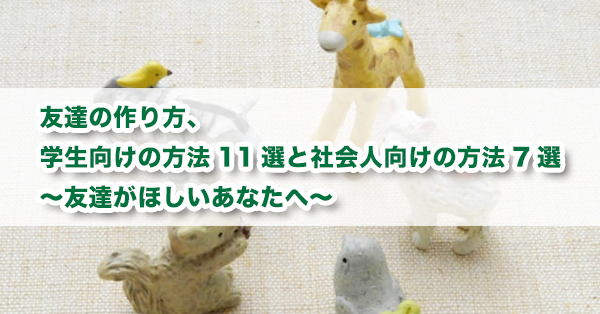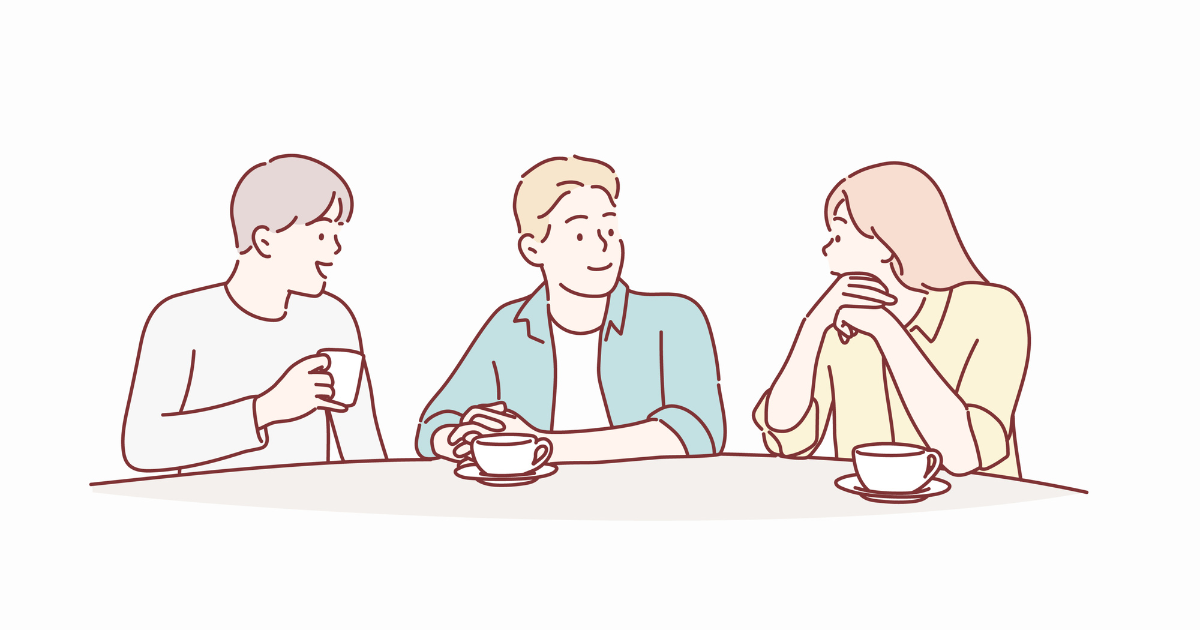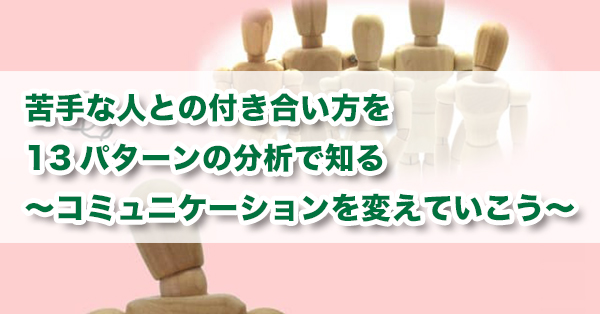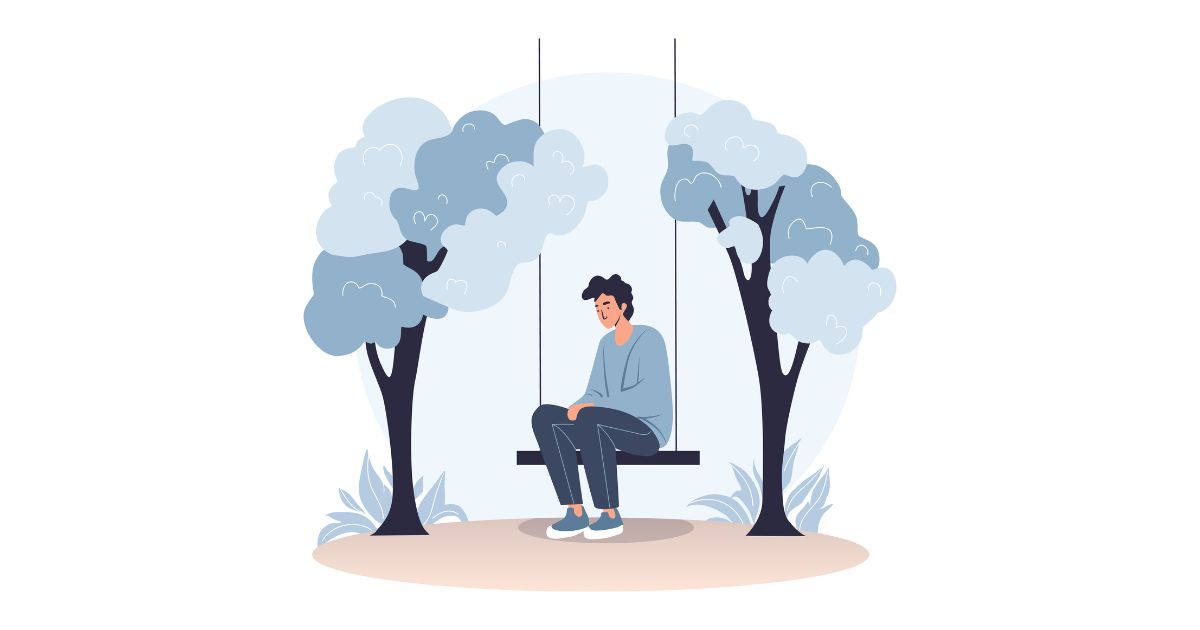コミュ障とは? コミュニケーション障害との違いを解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
お子さんに以下のような特徴がある保護者さまは、お子さんが「コミュニケーション障害」なのではないかと悩まれることがあるのではないでしょうか。
- 言葉の発達が同年代の子どもと比べてゆっくりな気がする
- 学校で友だちとうまく話せないみたい
「コミュニケーション障害」という言葉には、医学分野でもいくつかの定義があるうえに、インターネット上では「コミュ障」という、似ている、別の俗語も存在します。
このコラムでは、医学現場でのコミュニケーション障害の概要から、種類と特徴、コミュニケーションに困難が生じる別の障害、原因や診断・治療、生活しやすくなる工夫、相談先や支援機関について、解説しています。
あわせて、俗語としてのコミュ障(コミュ症)との違いについても解説しています。ぜひ参考にしてください。
私たちキズキ共育塾は、コミュニケーションが苦手な人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
いわゆるコミュ障(コミュ症)とは?
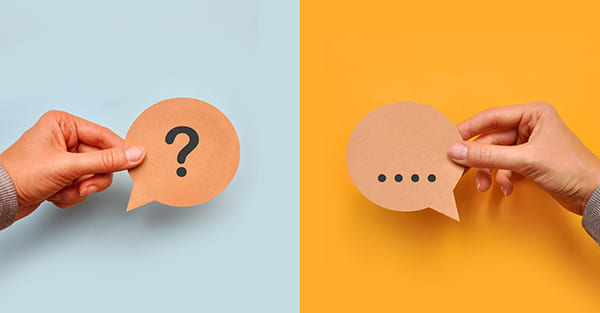
インターネット上の投稿などでよく見かけるコミュ障(コミュ症)とは一般的に、他人とのかかわりを避ける人、他人との会話が苦手な人、他人に無関心な傾向がある人のこととされています。ネットスラングに由来する俗語の一種のことで、医学用語ではありません。
明確に定められた定義や特徴はありませんが、一般的には以下のような特徴を指すようです。
- 常に周りの人に対して遠慮しがちで、自分の意見が話せない
- 空気を読まない発言や言葉遣いで話す
- 人見知りや緊張が激しく、人と話すときに動揺する
- 人前に立つと緊張して頭が真っ白になる
- 人の話をさえぎってまで自分の話をするため、周りが迷惑していることに気づかない
- 周りの会話のペースについていけず、押し黙る
- 会話や質問などにうまく受け答えできない
なお、いわゆるコミュ障(コミュ症)ではなくても、急に発言を求められる無茶振りに対応することができなかったり、人との会話のペースについていけなかったりなどは、誰もが経験しうることです。
「自分はコミュ障(コミュ症)だから、どうしようもない」などと、自分を卑下しないようにしましょう。
コミュニケーション障害とは?
コミュニケーション障害という用語には、いくつかの異なる定義があります。
コミュニケーション障害について考える際は、どの定義に基づいた話なのかを意識するのが大切です。
この章では、コミュニケーション障害の定義や使われ方について解説します。
前提:コミュニケーション障害は、医学的にはコミュニケーション症群・コミュニケーション障害群とされている
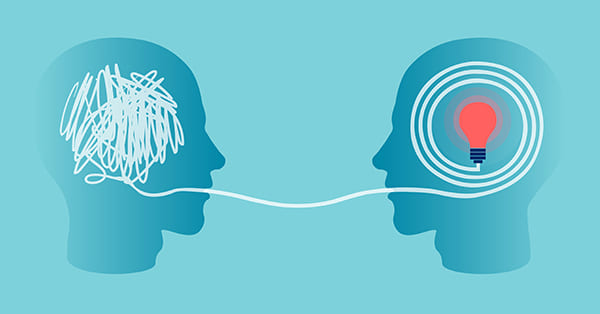
アメリカ精神医学会がまとめた診断基準である『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』では、コミュニケーション障害は、コミュニケーション症群・コミュニケーション障害群と呼ばれています。(参考:日本精神神経学会・監修『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』)
しかし、日常会話の中ではコミュニケーション障害という言葉が使われる場面は多いです。
それらを受けて、このコラムで医学的なコミュニケーション障害に触れる部分では、内容的には現行のコミュニケーション症群・コミュニケーション障害群のものを紹介しつつ、表記としてはコミュニケーション障害とします。
医学分野におけるコミュニケーション障害とは?
コミュニケーション障害(コミュニケーション症群・コミュニケーション障害群)とは、「発声や発音、文法の組み立てが難しい」「社会の場で人とやりとりするのが難しい」など、人とのコミュニケーションに困難が生じる障害のことです。
『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』によると、発達期に発症する神経発達症群/神経発達障害群のグループに含まれます。そして、コミュニケーション症群・コミュニケーション障害群は、人とのコミュニケーションに困難が生じるグループを指します。
『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』に基づいた「コミュニケーション症群・コミュニケーション障害群」についてわかりやすく説明すると以下のとおりです。(参考:日本精神神経学会・監修『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』)
- 発達期に発症する障害である
- 発声や発音、文法や単語の使い方、対人関係の場でのやりとりなど、コミュニケーションに関するさまざまな困難がある
リハビリ分野などにおけるコミュニケーション障害とは?
リハビリ分野などで用いられるコミュニケーション障害は、発達時期の障害だけではなく、他者とのやりとりに支障が出る状態全てを指すことがあります。(参考:深津 玲子・永井知代子「コミュニケーション障害の様々」)
例えば、難聴や、脳の病気の影響でなる言語障害などです。
コミュニケーション障害の種類と特徴
3つの定義が異なることがわかったうえで、『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』をもとに、医学的な意味でのコミュニケーション障害について、さらにご説明します。(参考:日本精神神経学会監修『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』)
コミュニケーション障害には、5種類の疾患が含まれます。1つずつ見ていきましょう。
種類①言語症/言語障害

言語症は、言葉の理解や発信(話したり書いたりして自分の気持ちを外に出すこと)することに困難が生じる症状です。話し言葉だけでなく、文字や手話なども困難になります。
症状の例を示します。
- 使える単語が少ない
- 複雑な構文が理解できない
- 単語や構文をうまく使えない、言い誤る
- 同年齢の子どもと比べて、言語能力が低い
言葉が発達するための土台には、言葉の理解が必要です。言語症で言葉の理解に困難が生じると、言葉を発信する面にも影響して、話し始めが遅れたり、使える単語が少なくなったりします。(参考:子どもの心の診療ネットワーク事業「よくある子どもの心のQ&A」)
種類②語音症/語音障害
語音症とは、発声や発音に関して困難が生じる症状のことです。それらの症状の原因が、口やのどなどの構造や神経の問題ではないものを指します。
症状の例を以下に示します。
- 舌足らずな発音
- 音の言い誤り
語音症は、言語聴覚士によるリハビリが多く行われていて、改善が見込まれる症状です。
種類③小児期発症流暢症(吃音症)/小児期発症流暢障害(吃音)
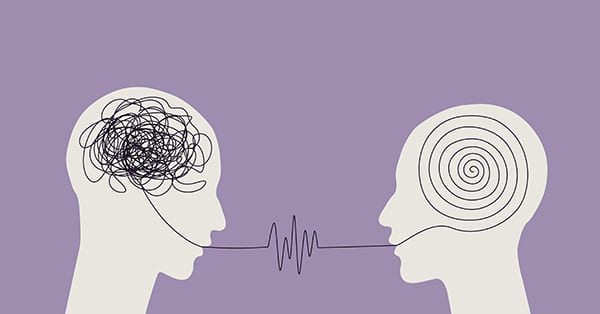
小児期発症流暢症とは、言葉をなめらかに話しにくい症状のことを指します。吃音とも呼ばれます。
症状の例は以下の通りです。
- 言葉の一部や全体を繰り返す(例:「ぼ、ぼ、ぼく」)
- 言葉の一部を引き伸ばす(例:「ぼーーーく」)
- 話したいことが頭にあるのに、言葉がつまってなかなか出ない(例:「………っぼく」)
幼児期に発症した吃音の場合、7割程度は自然に改善するとされていますが、症状が残る人もいます。(参考:発達性吃音(どもり)の研究プロジェクト「吃音の解説」)
種類④社会的(語用論的)コミュニケーション症/社会的(語用論的)コミュニケーション障害
社会的(語用論的)コミュニケーション症は、言葉や言葉以外でのやりとりが、社会生活の中でうまくできない症状を指します。
症状の具体例を示します。
- 場にそぐわない返答をする
- 遊び場と教室、友だちと先生などで話し方を変えられない
- ユーモアや慣用句など、言葉の裏の意味を読み取れない
言葉上でのやりとりが行えても、社会的なルールに従った会話ができないため、学業や仕事といった、対人関係が必要な場で困難を生じることがあります。
種類⑤特定不能のコミュニケーション症/特定不能のコミュニケーション障害

特定不能のコミュニケーション症は、コミュニケーションに障害がある人のなかで、他の判断基準に完全には当てはまらない場合などに分類されます。
コミュニケーションに困難が生じるその他の障害
コミュニケーション障害でなくても、コミュニケーションに困難が生じる障害は多くあります。
1つずつご紹介しましょう。
障害①その他の神経発達症群/神経発達障害群
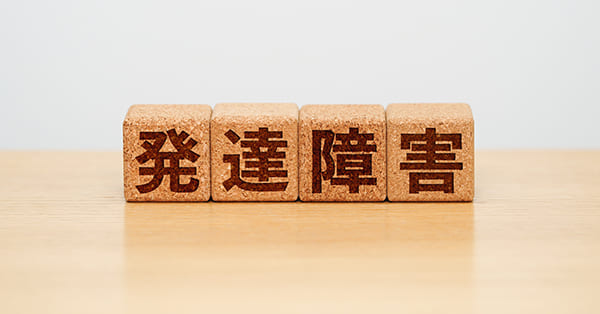
「コミュニケーション症群(障害群)」は、「DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル」において「神経発達症群」に分類されていますが、コミュニケーション症群(障害群)以外のグループでも、コミュニケーションの困難が生じます。
たとえば知的能力障害(知的発達症/知的発達障害)やASD(自閉スペクトラム症、自閉症スペクトラム障害)、ADHD(注意欠如・多動性障害)などです。
知的能力障害(知的発達症/知的発達障害)は、抽象的思考やコミュニケーション、日常生活動作などにかかわる、全般的知能の低下を認める症状です。症状の程度に応じて、人とのコミュニケーションにもなんらかの困難が生じます。(参考:こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」)
ASD(自閉スペクトラム症、自閉症スペクトラム障害)は、以下のような症状が特徴のグループです。
- 対人コミュニケーションの困難
- 興味や関心が限定的
- 特定の行動を繰り返す
コミュニケーションでは、言葉の発達の遅れやオウム返し、会話が成立しにくいなどが生じることがあります。
ADHD(注意欠如・多動性障害)は、気が散りやすく、衝動的に周囲に反応することがある疾患です。会話に集中しにくい場合には、以下のような状態が想定されます。
- 最後まで聞かず、指示に沿った行動ができない
- 複数の内容を一度に伝えると聞き落とす
それぞれの障害では、症状の出かたに応じて、コミュニケーションの困難さが異なります。
ASD(自閉スペクトラム症、自閉症スペクトラム障害)、ADHD(注意欠如・多動性障害)などの発達障害については、下記コラムで解説しています。ぜひご覧ください。
障害②聴覚障害
聴覚障害は、言葉の理解に影響します。
生まれつき重度な聴覚障害があると、言語発達に大切な、周囲の人の声や言葉を受け取れません。そのため、言葉の理解や発信、両面に困難が生じます。
言葉の習得のために、発達早期から補聴器や人口内耳などの聴力を補う手段を用いたり、手話や指文字などを練習したりするなど、なんらかのコミュニケーション手段の確立が重要視されています。(参考:日本産婦人科医会「新生児聴覚スクリーニングマニュアル」)
障害③後天性の障害

後天性の障害には、さまざまなものがあります。たとえば、脳卒中などの脳の疾患や精神疾患などです。
脳の疾患や転倒や交通事故による頭部損傷では、ダメージを受けた脳の部位に合わせて、失語症などの言葉の障害が生じたり、発声や発音の障害が生じたりします。
コミュニケーション障害の原因や診断・治療
コミュニケーション障害の原因や診断、治療についてご説明します。
コミュニケーション障害は複数の疾患を含むグループを指します。そのため、全ての症状に共通した内容ではないことを押さえておきましょう。
コミュニケーション障害の原因

コミュニケーション障害は発達期の障害で、生まれつきの脳機能の障害によるものと考えられています。
脳機能の障害をもたらすはっきりとした原因はわかっていませんが、親の育て方などのせいではないことが明らかになりました。
言語症や小児期発症流暢性では、遺伝的要素も大きいとされています。(参考:日本精神神経学会監修『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』、国立障害者リハビリテーションセンター「親に伝える」)
コミュニケーション障害の診断
診断には医師の診察が必要です。大人の診断は精神科や心療内科、小児であれば小児科、精神科、心療内科などです。語音症や小児期発症流暢症(吃音)の診断は、耳鼻咽喉科やリハビリテーション科で行います。
症状の境界はあいまいで、いくつかの症状を併せ持つ人もいます。そのためはっきりとした診断がつきにくいことや、途中で診断が変わることも多くあるのです。(参考:政府広報オンライン「大人になって気づく発達障害 ひとりで悩まず専門相談窓口に相談を!」、発達障害情報のポータルサイト「発達障害支援に関する地方自治体等の取組および関連情報データベース」)
コミュニケーション障害の治療方法

コミュニケーション障害は脳の発達期の障害であり、なんらかの根本的な治療で完治するものではありません。しかし、診断結果をもとに、治療や支援を受けることで、社会で過ごしやすくなることが見込めます。
一言でコミュニケーション障害といっても症状はさまざまで、必要な治療も異なります。治療内容の例は以下の通りです。
- 周囲への働きかけによる環境調整
- 正しい発音の練習(語音症)
- 言葉の理解、発信の練習(言語症)
- 想定される場面ごとに、対応方法をアニュアル化して練習する(社会的コミュニケーション症)
- 細かいルールもわかりやすく提示する(社会的コミュニケーション症)
本人に働きかけるだけでなく、周囲に合わせてもらえるように働きかける「環境調整」も大切です。周囲の理解や支援によって、コミュニケーションにおける困難さが軽減される場合が多いものです。(参考:東京都保健医療局「支援者のための地域連携ハンドブック~発達障害のある子供への対応~」、 厚生労働省「発達障害のある同僚への接し方」、 島根県「発達障害を正しく理解しよう」)
コミュニケーションに困難がある人が生活しやすくなる工夫
医学的にコミュニケーション障害と診断を受けていなくても、コミュニケーションに困難がある場合は、本人と周囲の両方で工夫できると、生活しやすくなります。
工夫の具体例について、ご説明します。
コミュニケーションに困難がある本人ができる工夫

コミュニケーションが難しい本人は、症状に対してどうしたらよいのかわからず、悩んでいるかもしれません。まずは医療機関や支援機関、先生などに相談するのが大切です。
ご家族には言いにくいことも、専門機関には遠慮なく相談できることがあるでしょう。社会生活が楽になるアドバイスがもらえます。
そのうえで、以下を目指せるとよいでしょう。
- コミュニケーションに関する力自体をのばす
- 自分の得意なこと、苦手なことを知る
- 自分の得意なこと、苦手なことを周囲にも伝えて、苦手なことは手助けを依頼する
コミュニケーションに関する力は、リハビリをしたり、生活の中でコミュニケーションの機会をもったりすることで、伸びが期待できます。
場面に合わせたコミュニケーションが難しければ、治療の項目で説明したように、場面を設定して、対応方法をマニュアル化した練習もよいでしょう。
自分の得意なこと、苦手なことを知ったことで、強みを活かせるようになった人がいます。苦手なことは助けを依頼するのも1つの方法です。(参考:とくしま発達障がい総合サイト「診断について」、政府広報オンライン「大人になって気づく発達障害 ひとりで悩まず専門相談窓口に相談を!」)
コミュニケーションに困難がある人の周囲の人ができる配慮
周囲の人ができる配慮は、本人の特性を理解して、適切なサポートをすることです。まずは専門家にサポートの方法を聞くのがよいでしょう。
その人ごとに合ったサポートは異なりますが、一般的にできる配慮の例をご紹介します。
言葉の理解や、社会生活の中でのやりとりに困難がある場合
- 絵や図なども提示して、わかりやすいように伝える
- 何をすればよいのか、手順を具体的に、わかりやすく伝える
- 1度にいくつも伝えず、1つずつ伝える
発音や言葉を発する部分に困難がある場合
- 発音が聞き取りにくくても、言い直しを要求せず、正しい言葉を聞かせる
- 言葉だけにこだわらず、言葉以外を使ったコミュニケーションも活用しながら楽しくコミュニケーションする機会を増やす
上記はあくまでも一例です。その人に合った配慮をしましょう。(参考:厚生労働省「発達障害の特性(代表例)」、 独立行政法人日本学生支援機構「合理的配慮ハンドブック」、福知山市「コミュニケーション手段にかかる合理的配慮について」)
コミュニケーション障害がある人の相談先・支援機関
コミュニケーションに困難がある人の相談場所は、相談する症状や自治体ごとに異なります。
相談先の例を1つずつ見ていきましょう。
コミュニケーション障害の症状や障害についての相談先・支援機関

症状についての検査や診断、訓練は、医療機関などで行っています。受診する科は以下を参考にしてください。
- 児童精神科・小児精神科
- 小児科の発達外来
- 耳鼻咽喉科(語音症、小児期発症流暢症)
- リハビリテーション科
- 精神科
- 心療内科
相談できる病院は限られるので、事前に電話で相談するとよいでしょう。
言語聴覚士が在籍している医療機関などは、日本言語聴覚士協会のホームページから検索できます。発達障害に関しての相談は、政府が協力しているホームページ「発達障害情報のポータルサイト」でも探せます。(参考:子どもの心の診療ネットワーク事業「子どもの心の診療機関マップ」、 一般社団法人 日本言語聴覚士協会「病院・施設検索」、発達障害情報のポータルサイト「発達障害支援に関する地方自治体等の取組および関連情報データベース」)
小、中学校のお子さんの場合には、通級指導教室(「きこえとことばの教室」など)も相談場所としてよいでしょう。
通級指導教室は、小中学校の通常学級に通学しているお子さんたちが、言葉や発達の困難について、障害による困難を改善・克服するため、一人一人の状況に応じた指導を行うところです。普段在籍しているクラスとは別に設けられていて、決められた日の決められた時間にだけ通います。(参考:文部科学省「通級による指導を担当する教師のためのガイド」、文部科学省「通級による指導実施状況調査結果(概要)」)
通級指導教室では、コミュニケーション障害についても相談できます。
コミュニケーション障害の学校生活などに関する相談先・支援機関
学校生活についての困りごとは、学校の先生やスクールカウンセラーに相談しましょう。
必要な支援先を紹介してもらえるとともに、お子さんが過ごしやすくなる対策を一緒に考えてもらえるでしょう。
その他には以下の相談先もあります。(参考:独立行政法人日本学生支援機構「合理的配慮ハンドブック」、東京都福祉局「児童相談所とは」、国立障害者リハビリテーションセンター「発達障害者支援センターの事業内容 」)
児童相談所
- 18歳未満のお子さんの心身に関して相談できる
- 児童福祉司、児童心理司、医師、保健師などの専門スタッフがいる
- アドバイスや情報提供、カウンセリングなどを行ってくれる/li>
発達障害者支援センター
- 発達障害がある人と家族などからの相談に応じる
- 関係機関や福祉制度を紹介する
- 発達支援に関するアドバイスをもらえる
学校に通いにくいお子さんの場合には、キズキ共育塾にもご相談いただけます。
キズキ共育塾では、不登校や引きこもり、発達障害などあらゆる悩みを抱える人の相談を受けて、コミュニケーションのサポートもしています。
お気軽にお問合せください。
コミュニケーション障害の仕事に関する相談先

生活や仕事について相談する先としては、以下があります。
仕事を探したいのか、仕事をするためのスキルも取得したいのかなどによって、相談先が異なります。(参考:政府広報オンライン「大人になって気づく発達障害 ひとりで悩まず専門相談窓口に相談を!」、 厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」、厚生労働省「ハローワーク」、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」)
障害者就業生活支援センター
- 障害がある人の生活・仕事についての相談ができる
ハローワーク
- 就職を希望する人に、仕事を紹介する
- 障害の種類や程度に応じて、職業の相談や紹介、職場定着指導も行う
地域障害者職業センター
- 障害がある人に対する専門的な職業リハビリテーションを実施
- 事業主に対しては、障害がある人を雇用する際の相談や援助を実施
就労移行支援事業所
- 仕事に役立つ専門スキルの習得など、さまざまな支援が受けられる
- 最低0円から利用可能
まずは気になる所に相談することがオススメです。相談先として合わない場合でも、適切な場所を紹介してもらえるでしょう。
就労移行支援事業所については、下記コラムで解説しています。ぜひご覧ください。
キズキビジネスカレッジ就労移行支援とは? 支援内容や利用の流れを徹底解説
コミュニケーション障害についてのよくある質問
この章では、コミュニケーション障害についてのよくある質問を紹介します。
Q1.発達障害と「コミュニケーション障害」の違いはなんでしょうか?

A.順を追ってお伝えします。
まず、『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』には、「発達障害」という診断名はありません。
発達障害と言われる特性の診断名は、これまでにも述べてきたASD、ADHD、SLDなどであり、それらは『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』では「神経発達症群/神経発達障害群」に分類されます。
そして、コミュニケーション障害も、同じく「神経発達症群/神経発達障害群」の分類です。
また、「発達障害」という言葉は、「医学的な場面での、医学的に正確な定義」以外でも、法令、支援の現場、日常生活などの様々な場面で、それぞれの定義で利用されています。(参考:e-ヘルスネット(厚生労働省)「発達障害」、日本精神神経学会監修『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』)
Q2.アスペルガー障害と「コミュニケーション障害」は違いますか?
A.違います。
まず、アスペルガー症候群や自閉症、広汎性発達障害などのいろいろな名称で呼ばれていた障害は、『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』の発表以降、ASD(自閉スペクトラム症、自閉症スペクトラム障害)としてまとめて表現するようになりました。
そして、ASD(自閉スペクトラム症、自閉症スペクトラム障害)とコミュニケーション障害は、診断基準が異なるのです。
例えば、ASDの診断基準の一つに「行動、興味、または活動の限定された反復的な様式があるか」というものがあります。
この診断基準は、コミュニケーション障害にはありません。
ただし、両者ははっきり区別しにくい場合も多く、医師によって診断が異なったり、数年後に診断が変わることもあります。また、両方の特性がある人もいます。(参考:e-ヘルスネット(厚生労働省)「ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」)
まとめ〜社会生活が楽になることを目指しましょう〜

「コミュニケーション障害」には、複数の異なる定義があります。
中でも医学分野で使われるコミュニケーション障害と、インターネット上のいわゆる「コミュ障(コミュ症)」は全くの別物です。
医学分野のコミュニケーション障害では、発達期の障害によって、人とのコミュニケーションが難しくなる状態のことを指します。
学校や生活場面、社会生活において多くの困りごとが生じます。
コミュニケーション障害に悩む場合には、医療機関や支援機関に相談することをおすすめします。
診断結果をもとに治療や支援を受けて、人とのコミュニケーションや社会生活が楽になることを目指しましょう。
Q&A よくある質問
「コミュ障」とはなんですか?
インターネット上の投稿などでよく見かける「コミュ障(コミュ症)」とは、ネットスラングに由来する俗語の一種のことで、医学用語ではありません。
いわゆる「コミュ障(コミュ症)」は一般的に、他人とのかかわりを避ける人、他人との会話が苦手な人、他人に無関心な傾向がある人のこととされています。
詳細については、こちらで解説しています。
「コミュニケーション障害」について相談できるところを知りたいです。