過干渉とは? 過干渉をする親の行動や悪影響を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
子どもに対して「過干渉になっているかもしれない」とお悩みではありませんか?
- どこからが過干渉になる…?
- 子どものことが心配で、何かと口出しや手出しをしている…
- 子どもへの適切な接し方がわからない…
このコラムでは、過干渉の概要について紹介しつつ、過干渉な親の口癖や行動、過干渉がもたらす子どもへの悪影響、過干渉への対処法について解説します。
また、自分の親が過干渉かもしれないと悩むお子さん向けに、親の過干渉な行動への対処法も紹介します。
なお、このコラムには、過干渉にはこんな悪影響があるなどの、不安にさせるかもしれない内容もあります。しかし、あなたを不安にさせることや親子の対立を煽ることは、このコラムの趣旨ではありません。
このコラムの内容はあくまでも参考としてご覧いただいた上で、実際のあなたの親子関係については、子どもや親子関係に関する悩みをサポートする人たちに相談することで、具体的に改善されていくはずです。
相談先については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
私たちキズキ共育塾は、親御さんもお子さんも過干渉について気軽に相談できる、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
過干渉とは?

過干渉とは、なんらかの対象に対して、一般的な限度を超えて必要以上に干渉したり、行き過ぎた制限をしたりすることです。一般的に、親による子どもに対する過剰な干渉を指す言葉として使われることが多いです。(参考:goo国語辞書「過干渉(かかんしょう)とは? 意味・読み方・使い方をわかりやすく解説」、金子書房『児童心理 2002年9月号 特集:過干渉の親・放任の親』、高橋リエ『気づけない毒親』、おのころ心平『人間関係 境界線(バウンダリー)の上手な引き方』)
特に、親子関係における過干渉とは、親が子どもの選択に必要以上に干渉したり、行動を制限したりすることを指します。
「子どもが心配だから」「子どものためを思っての行動だから」と、親御さん自身が過干渉に気付かないことは少なくありません。
また、お子さん側も「自分のことを考えてくれているからだろう」「私が気にしすぎているだけだ」と考え、見過ごすことも少なくありません。
しかし、そのまま放置すると、お子さんは親を疑う前に自分を疑う癖がつき、自信が持てなくなることもあります。
また、親が過干渉な傾向がある場合、お子さんはやがて自信を失ったり、無気力になったりすることがあるため、心の成長を考える上では重要な問題にもつながっていきます。
さらに、過干渉は、親や家族だけが行うとは限らず、学校が関連するケースもあります。
世田谷区立桜丘中学校長に就任した経歴を持つ西郷孝彦氏や教育評論家である尾木直樹氏、麻布中学校・高等学校理事長の吉原毅氏らによると、過干渉について、学校の校則を例に以下のように指摘しています。
「校則でがんじがらめにするのもそのひとつで、教員側が子どもを信じていない。でもね、信じてあげれば、子どもはちゃんとやるんです。むしろ、ああしろ、こうしろと過干渉になることで、子どもたちから「考える力」を奪っている。」
(参考:西郷孝彦・尾木直樹・吉原毅『「過干渉」をやめたら子どもは伸びる』)
専門家たちは、子どものためを思う気持ちが行きすぎた厳しすぎる校則やルールも、子どもを信じられていない結果であり、1つの過干渉であると考えているのです。
過干渉をする親の心理

過干渉をする親の心の底には、自分が抱えている不安や心配といった強迫観念があると考えられています。
例えばカウンセラーの高橋リエ氏は、毒親という用語を使いながら、過干渉をする親を以下のように定義しています。(参考:西郷孝彦・尾木直樹・吉原毅『「過干渉」をやめたら子どもは伸びる』)
- 不安が強く、強迫観念から子どもをコントロールしがちで、子どもの気持ちを思いやれない親
つまり、お子さんの現状や将来を考えて伝えているアドバイスであっても、それが行き過ぎている場合には過干渉になるのです。
親御さんの善意によって、お子さんがが追い詰められるというのが、過干渉の問題の難しいところです。
過干渉というのは、善意の裏に以下のような点があるかどうかがポイントになるでしょう。
- 自分の不安や欲求を満たそうという意識が働いていないか
- 本当に子どものためなのか
親御さんは、以上のポイントを含めて、自分の行動が過干渉になっていないかを考える必要があります。
過干渉の原因〜バウンダリー・オーバー〜

過干渉の原因の1つとして、バウンダリー・オーバーが挙げられます。
バウンダリー・オーバーとは、自分と他人の境界線=バウンダリーを越えて侵入を許している状態を指す心理学用語のことです。(参考:おのころ心平『人間関係 境界線(バウンダリー)の上手な引き方』)
つまり、過干渉になっている場合、親御さんの心の中で、お子さんと自分自身の境界線があいまいになっており、お子さんのことを独立した一個人ではなく、自分の一部だと考えている可能性があるのです。
この場合、親御さん自身の領域とお子さんの領域の線引きを行うことが大切になってきます。
過干渉は母娘関係に多い?
過干渉は、特に母娘関係に多いと言われています。(参考:六角大地『毒親問題と回復アプローチ (Mフォーラム) Kindle版』)
イクメンという言葉が流行語になり父親による育児が浸透しつつあるとはいえ、家庭教育の多くはまだ母親が担っているのが現状です。
そうした状況の中で、母親は娘を見て自分の子どもだったころを思いだし、自分と娘を同一視する傾向を強めることから過干渉に陥りやすいと考えられています。
- 私が若いころはこうだった
- 私があなたの立場だったらこうするのに
<同性であるがゆえにこうした考えが娘にも受け入れられやすく、よりこじれた関係が生まれやすいため、いっそうの注意が必要になります。
母娘関係の過干渉に興味のある人は、以下の書籍がオススメです。この書籍では、母親の過干渉を軸に、マンガ家の萩尾望都氏との対談などが掲載されています。母娘関係を考える、考え見直すきっかけに最適と言えるでしょう。
補足:過干渉と過保護の違い
過干渉という言葉と近いもので過保護という言葉があります。
過保護との違いは、子どもの自主性を重んじているかどうかです。(参考:西郷孝彦・尾木直樹・吉原毅『「過干渉」をやめたら子どもは伸びる』)
過干渉の場合、子どもが「こうしたい」と言っても、否定したり何か行動を始める前に「ああしなさい」と命令したりするケースが考えられます。
過保護の場合、子どもがしたいことや欲求をすべて満たしたり、したくないことをすべて避けていたりするようなケースが挙げられるでしょう。
しかし、過干渉と過保護のいずれも、子どもの自立が遅れる恐れがあるという点では共通しています。
とはいえ、こちらで解説した過干渉の原因などを理解した上で、きちんとした対処法を取れば大丈夫です。ご安心ください。
過干渉をする親の3つの口癖
この章では、過干渉をする親の口癖について解説します。
口癖①あなたのためを思って言っているのに

「あなたのためを思って言っているのに」というのは、過干渉の親御さんが使いがちな口癖の1つです。
確かにアドバイスのつもりで、「ああしなさい」「こうしなさい」と勧めることはあるでしょう。
しかし、アドバイスが行き過ぎて子どもの自由を奪う命令になると、過干渉になります。
よかれと思って言ったことでも、子どもの自発性を損ねている可能性があるのです。
親御さんは「あなたのためを思って言っているのに」という言葉を日頃から使っていないか、思い返してみてください。
また、親御さんを過干渉ではないかと思っているお子さんは、「あなたのためを思って言っているのに」と言われたことがないかを思いだしてみてください。
口癖②だって、心配だから…
「だって、心配だから…」も過干渉な親御さんの口癖の1つです。
ただし、この場合の親御さんは自分が過干渉をしていることに、ある程度自覚がある可能性があります。
あくまでも自分が心配だからということに気づいているからです。
つい心配して過干渉になる親御さんは、一度立ち止まって、それが本当にお子さんのためを思っての言動かを考えてから接するようにしてください。
また、親御さんから「だって、心配だから…」と言われるお子さんは、自分に問題があるわけではないと割り切ってみるとよいでしょう。
口癖③どうして言うことが聞けないの?

「どうして言うことが聞けないの?」という口癖は、典型的なバウンダリー・オーバーの一種です。
「どうして言うことが聞けないの?」が口癖の親御さんは、お子さんを自分の一部と考えている可能性があります。
子どもと親は違う存在であることを理解し、しっかりと線引きができていれば、こうした発言は出てこないはずだからです。
とはいえ、お子さんがあまりにも小さい場合や、子どもがTPOを理解しない行動をした場合などは、「どうして言うことが聞けないの?」というのは仕方がないことかもしれません。
そのため、「どうして言うことが聞けないの?」が、子どもの自由な選択や価値観を否定しているのかどうかを意識するようにしてみてください。
過干渉をする親の7つの行動
この章では、過干渉な親の行動について解説します。
ここで解説する行動に共通するのは、子どもの自主性を重んじることができない点です。
行動①子どもが答える前に話し始める
1点目は、子どもが答える前に話し始めることです。
初対面の人と話すときや学校の先生との面談などの際に、子どもに向けられた質問に対して、お子さんが回答する前に答える親御さんがいます。
この行動は、お子さんの考えや意見を述べる機会を奪うことになりかねず、お子さんも「自分の意見が尊重されていない」と感じる原因になります。
お子さんが口下手であったり引っ込み思案だったりする場合、親としてどうしても口を出したくなるものです。ですが、それがあまりに続くと過干渉になる恐れがあります。
行動②子どもの意見や進路を尊重しない

過干渉を見わける行動の1つが、子どもの意見や進路を尊重しないことです。
親御さんは、お子さんの判断力が未発達な部分を手助けしようとしたり、将来のためを思ったアドバイスをしたくなったりするものです。
しかし、自分の考えを頭ごなしにぶつけてお子さんの意見を尊重しないようであれば、過干渉になります。
例えば、お子さんの「A高校に進学したい」「テニス部に入りたい」という意見について、納得できる理由もなく「B高校にしなさい」「吹奏楽部にしなさい」などと言う場合です。
こういった過干渉は、お子さんの自信を失わせるだけでなく、自主性や考える力を奪う可能性もあります。
また、親御さんが過干渉かもしれないと感じているお子さんは、自分の意見や進路が尊重されているかどうかを判断基準の1つにしてみてください。
ただし、進路などについて特に自分の希望がない場合は、親御さんのアドバイスに従うこと自体は悪いことではありません。
ですが、親御さんのアドバイスに従うばかりで自分で考える練習ができないままだと、物事を自分で決められなくなるかもしれません。
過干渉が関係してもしなくても、自分で考えることは大切であると認識し、普段の生活でもできるだけ意識しておきましょう。
行動③人間関係を勝手に決める
3つ目は、人間関係を勝手に決めることです。
親御さんの中には、子どもの遊び相手を勝手に制限する人がいます。例えば、以下のような理由で制限する事例があります。
- あの家の子は荒っぽいという噂があるから遊んではいけない
- あの子はマナーがなっていないからつき合ってはいけない
お子さんの人間関係はお子さんが決めるものです。もちろん犯罪などに巻き込まれるなどの危険がある場合は、アドバイスをする必要がありますが、そういった場合でないのであれば、お子さんを尊重しましょう。
また、親御さんから友人関係にいろんな理由をつけて制限されているお子さんは、注意が必要かもしれません。
行動④子どもの好きなものを否定する

子どもの好きなものを否定するというのも、過干渉な親御さんの取りがちな行動の1つです。
お子さんが選択したものが自分の好みに合わないと、「こっちの方がいいからこれにしなさい」と命令したり「そんなものはダメだ」と否定したりするのです。
例えば、お子さんが「少女マンガが好き」と言ったら、「そんなものはくだらないから、純文学を読みなさい」と言うようなイメージです。
子どもの好きなものを否定する親御さんは、親子であっても子どもと親は違う好みを持った別の存在だということに気づけていない可能性があるため、注意しましょう。
行動⑤褒めずに問題点や課題ばかりを指摘する
褒めずに問題点や課題ばかりを指摘するも、過干渉をする親によく見られる行動の1つです。
特にこれは、教育熱心ゆえに過干渉になる親御さんによく見られる行動です。
親御さんとしては、よかれと思ってアドバイスをしているつもりかもしれません。ですが、全く褒めずに要求ばかりを突きつけるようであれば、お子さんの自信を損ねる結果になりかねません。
例えば、以下のような状態が常に続くと、お子さんを追い詰めることになるかもしれません。
- 90点を取ったテストに対して「どうしてあと10点分がんばれなかったんだ」と言う
- スポーツの大会で3位入賞したことについて「あそこで気を抜かなければ1位になれたのに」と言う
親御さんは、お子さんの良い部分や頑張った部分を褒めずに、結果や問題点ばかり指摘しないかを振り返ってみてください。
また、親御さんの過干渉を疑っているお子さんは、自分は褒められたことがあるかなと思い返してみてください。
行動⑥完璧を求めすぎる

完璧を求めすぎるのも注意が必要です。
親御さんが完璧主義者である場合、子育てについてある程度の信念を持って取り組んでいる場合があります。
しかし、その信念がかえってお子さんを縛りつけるきっかけとなり、過干渉につながっている可能性があります。
完璧を求めすぎると、次第に自分の信念・理想・目的に沿って育児をするようになり、子どもをコントロールしようとすることも少なくありません。
自身に完璧主義の傾向がある親御さんは、子育てや子どもに対して完璧を求めていないかを考えてみてください。
また、親御さんに完璧を求める傾向があると感じているお子さんは、全てを受け入れようとはせず、自分なりの信念や考えを持ち、話し合いをしていくのが望ましいでしょう。
行動⑦過程ではなく結果を重視する
過干渉な親御さんの場合、どれだけがんばったかという過程よりも、結果を注視する傾向にあるようです。
これは、親御さんの子育てに対する考え方や目的などが原因であるケースが多いです。
結果ばかりに目を向けるために、その環境で育てられたお子さんは、かえって挑戦しづらくなったり努力することを避けたりするようになります。
そして次第に、お子さんまでもが結果ばかりに固執するようになったり、成功ばかりを追い求めたりするでしょう。
生きていくなかでは、勉強に限らず失敗や挫折を味わい、乗り越えていかなければならないときがあります。
それも一度ではなく、人生の分岐点である状況に何度も訪れることもあります。
過程ではなく結果だけを追い求めることが癖になると、人生の分岐点でもこの考え方が影響し、お子さんは生きづらさを感じるようになるかもしれません。
精神科医の井上智介氏は、過程ではなく結果を重視する親御さんに関して、以下のように指摘しています。(参考:井上智介『子育てで毒親になりそうなとき読んでほしい本』)
親の期待にこたえられなかった、親を悲しませてしまったと自分を責める子は、自己肯定感がなかなか育ちません。親は結果ではなく、プロセスをもっとほめてあげてください。プロセスの前に、子どもの存在に感謝する、子どもがいるだけでありがたいことに気がついてほしいです。
(参考:井上智介『子育てで毒親になりそうなとき読んでほしい本』)
過干渉がもたらす子どもへの悪影響8選
この章では、過干渉がもたらす子どもへの悪影響について解説します。
いずれにも共通しているのは、お子さんの心の成長をさまたげて自分で決められない状態にする可能性がある点です。
ただし、子どもの性格などによって影響の程度には個人差があります。必ず解説するような状態になるというものではありません。
大切なのは、干渉されることがストレスになっていないかを見極めることです。(参考:ダン・ニューハース『不幸にする親 人生を奪われる子供』、根本橘夫『「自分には価値がない」の心理学』)
ここで解説することは、親御さんやお子さんを不安にさせるためのもの、親子の対立を煽るためのものではありません。不安や悩みは1人だけ・親子だけ・家庭だけで抱え込まず、支援機関などにぜひご相談ください。
悪影響①自分に自信が持てなくなる

1番の悪影響は、自分に自信が持てなくなることです。
過干渉な親御さんは、お子さんが考えて決めたこと、価値観、好きなことなどを否定します。
はっきりと否定しなくても「こうした方がいい」というアドバイスしたり、褒めたり認めたりすることを滅多にしないだけでも、子どもは自分の選択に自信が持てなくなるものです。
そうした経験の結果、いつも人に確認を求めたり、自分は何か間違っているのではないかと不安になったりします。
悪影響②無気力になる
無気力になることも、過干渉がもたらす悪影響としてよく挙げられます。
お子さんが、いつも親御さんの指示に従ってばかりいると、積極性が失われて自分から行動しようという気持ちが失われます。
加えて、やってみたいと思った趣味や好きなことを否定される過干渉が続くと、お子さんはさらに無気力になっていきます。
悪影響③罪悪感を覚えやすくなる
悪影響の3つ目は、罪悪感を覚えやすくなることです。
過干渉をする親御さんの中には、お子さんが親の意に沿わないことをしようとすると「どうして言うことを聞いてくれないの」と涙ながらに訴える人がいます。
こういった場合、お子さんは「自分は何か悪いことをしている」「親不孝者だ」と、罪悪感に苦しむことになります。
また、親御さんの言うことを聞くお子さんであっても、実は罪悪感に駆られて従っているだけというケースもあります。
こういったお子さんは、大人になって自立して行動しようとするときにも、心のどこかに後ろめたさを感じるようになると言われています。
親に確認を取らないと不安になったり、いつも誰かに叱られるのではないかという気がしたりするのです。
悪影響④いじめに加担する・反抗期が強まる

親御さんの過干渉によるストレスを発散するべく、同級生に対して攻撃的になるケースもあるようです。
その結果、いじめに加担したり激しい反抗期が始まったりすることにつながります。
親御さんにコントロールされ続けて育ったお子さんは、親子関係と同様に他者を同様にコントロールしようとすることがあります。
他者を思いどおりにコントロールしようとした結果、人間関係が思ったように構築できず、いじめなどにつながるのです。
なお、西郷氏、尾木氏、吉原氏は、厳しすぎる校則、学校からの過干渉といじめについて以下のように指摘しています。(参考:西郷孝彦・尾木直樹・吉原毅『「過干渉」をやめたら子どもは伸びる』)
「「学校に遅れる」という背景には、もっと複雑な事情が隠されていることが多いのです。発達障害の問題もあるかもしれない。貧困など家庭の事情もあるでしょう。何らかの精神疾患を抱えているのかもしれない。
でも、そういう事情を鑑みないで、「遅刻をしてはいけない」というルールで、一方的に切って捨てる。一事が万事この調子で、みんなと違う行動を即座にとがめられる、という環境が形成されてしまうと、それがいじめになっていくのです。
ルールや規則があればあるほど、いじめは発生しやすい。これは動かしがたい事実です。西郷校長が「校則をなくして以降の桜丘中学校にはいじめがほとんどない」とおっしゃっていましたが、それを考えても、規則といじめの因果関係を裏づけていると思います。」
(参考:西郷孝彦・尾木直樹・吉原毅『「過干渉」をやめたら子どもは伸びる』)
このように、あまりに厳しすぎる校則によってがんじがらめになった子どもは、やがてその環境で受けたストレスによって、いじめや激しい反抗期といった他者を傷つける行為へと進んでいるとしています。
そして、この結果を動かしがたい事実と考え、厳しすぎる校則に対して警鐘を鳴らしています。
ただでさえ縛りつけられるような厳しい校則に加えて、さらに親御さんからの過干渉が加われば、お子さんはストレスによって、周囲をより強い力でコントロールしようと考える可能性も懸念されるでしょう。
悪影響⑤自分の意思で行動・決断できなくなる
親御さんの過干渉が強すぎると、自分で考える時間・きっかけが奪われます。
- 子どもに失敗してほしくないから
- 子どもを大切にしているから
- 子どもに自分らしい人生を送ってほしいから
このように、親御さんの多くはお子さんのことを第一に考えているはずです。しかし、その思いが強すぎると、かえってお子さんを縛り付けることにつながります。
過干渉によってお子さんがすべき決断や判断を親御さんが行っていると、お子さんは親御さんにすべてを委ねるようになります。
- 親が全部決めてくれた
- なにかあったら親に相談すれば親がなんとかしてくれる
- 親に全部任せればなんとかなる
さらには、親御さんの顔を見て決めるようになることもあるでしょう。
子どもの間であればこのような環境は珍しくありません。しかし、大人になってもこのままの環境だと、自分で決断することができなくなる恐れがあります。
また、思い切って自分の意見を親に伝えてみても否定や親の思いを強制されることが続けば、自分の意思を告げることそのものに無駄を感じ、無気力になることにもつながります。
悪影響⑥親や周囲の顔をうかがう

過干渉な親御さんのもとで育ったお子さんは、親御さんのの意見に従うことに慣れている状態です。その環境が当たり前になればなるほど、少しでも親の考える正解を選ぼうとします。
その結果、失敗しないよう、怒られないよう、親の顔色をうかがうようになります。
この環境さえも当たり前と感じるようになれば、周囲の顔色までうかがうようになります。
高橋リエ氏は、過干渉だった自身の母親を毒母と表現した上で、当時の状況を以下のようにまとめています。(参考:高橋リエ『お母さん、私を自由にして!毒母だった本人が書いた、母親の呪いを解く方法』)
「母親がいつ怒りだすかと警戒していたせいで、おとなになって実家から出ても、社会に出ても、つねに周囲の人を警戒せずにはいられないのです。」
親・周囲に対しても顔色をうかがわなければならない状態に対して、やがて子どもは本人でも気づかないうちに、強いストレスを抱え込むようになるでしょう。
井上智介氏は、自身の家の違和感について、以下のようにまとめています。(参考:井上智介『子育てで毒親になりそうなとき読んでほしい本』)
自分の家や親のおかしさに気づくチェックポイントが2つあります。
一つ目は「家の中に安心感や安全感があったかどうか」です。家に帰ると、どこか緊張感があって、親のきげんや顔色をずっとうかがう状態で過ごさなければいけなかったならば、もうそこは異常な場所です。
そして2つ目は「1回実家を出たら、また戻りたいか?」です。病院を受診している人は、だいたい「絶対に戻りたくない」と言います。そこで、やっと自分の家が異常で、親が毒親だったと気がつけるのです。それくらい誰もが自分の家をふつうだと思っているのです。
(参考:井上智介『子育てで毒親になりそうなとき読んでほしい本』)
、このように自分の育ってきた環境ほど異常と気づけないケースが非常に多いと考えられます。
親御さんの立場であれば、子どものためにという気持ちはとても大切です。
しかし、まずは親としての考えや言葉遣い、育児における意識について、冷静に見直す機会を設けてみてください。
また、自分の親が過干渉かもしれないと悩んでいるお子さんであれば、現在の状況について俯瞰で考えてみることをオススメします。
悪影響⑦親がいるときといないときで表情が変化する
過干渉な親に育てられると、怒らせないように顔をうかがう生活が一定化します。
怒られたくないがために自分を出すことを控えるので、怯えたような表情や暗い表情を見せることがあるようです。
このような生活が定着すると、学校のような親の居ない環境ほど、明るく無邪気に遊ぶ姿を見せることも珍しくありません。
そして、友だちが帰宅するにつれて帰らなければならないという現実を思い出し、次第に表情が暗くなっていくこともあるようです。
悪影響⑧学力に影響がある
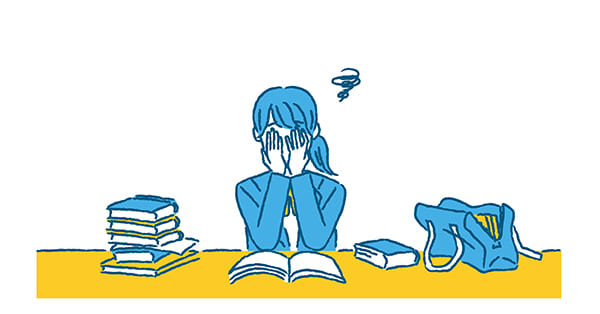
親御さんの過干渉を受けて育った子どもは、>発達面・知能面において明確な理由がないにもかかわらず、学力が低い水準で留まる可能性があると言われています。
その理由は自分の意思で行動・決断できなくなる、親や周囲の顔をうかがい過ぎたことで失敗を恐れるなどが考えられます。
学びの基本は、自分で考え、試し、結果を知ることです。
親御さんの過干渉によって考えることや試すことができず、結果を知る機会そのものが減少することで、学力にまで影響を及ぼす恐れがあると考えられています。
西郷氏、尾木氏、吉原氏は、自由が担保されている環境での子どもたちの学力についてこのようにまとめています。
「『自由』が担保されている環境では、子どもたちは自分で考えるようになります。そういう環境だと、いじめも生まれにくい。やらされる勉強より、自主的な勉強のほうが伸びますから、学力も高くなる。」
(参考:西郷孝彦・尾木直樹・吉原毅『「過干渉」をやめたら子どもは伸びる』)
このように教育に携わった有識者も、過干渉の環境に比べて自由な環境ほど、学力が高くなる傾向にあるとしています。
過干渉をする親にならないためのチェックポイント
この章では、「自分は過干渉かもしれない」と悩む親御さんに向けて、過干渉をする親にならないためのチェックポイントについて解説します。
チェックポイント①見守る姿勢を持てているか
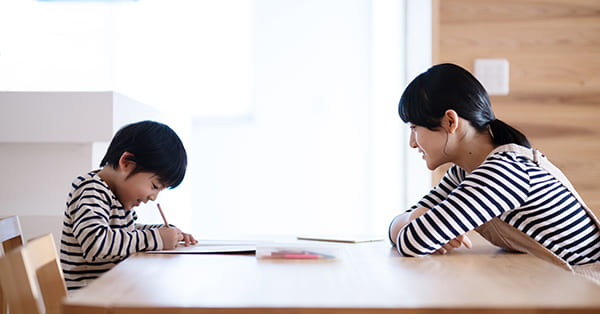
1つ目のチェックポイントは、見守る姿勢を持てているかです。
お子さんのことを心配するあまり、見守ることができていないということはありませんか?
お子さんが小さい場合、目を離さずにしっかりと見守る必要があり、場合によっては直すべきところを伝えなければなりません。
しかし、それによってお子さんの自主性を損ねると、過干渉につながります。
大ケガや犯罪などにつながらないための助言・注意はしつつ、ある程度はお子さんを自由にし、親見守る姿勢を大切にましょう。
思うがままの結果として、小さなケガをしたり、人を少し傷つけたりするといった、取り返しのつく範囲で、良くない状況につながる場合もあります。
そのようなときは、改めて、次につながるような注意や助言をしたりなどするのが良いでしょう。
過干渉かもしれないとお悩みの場合、どこまでの助言・注意なら過干渉ではないのかがわからないかもしれません。
そうしたお悩みはあなた一人で抱え込むのではなく、親子関係などに詳しい支援機関などに相談することをオススメします。
チェックポイント②子どもへの心配や不安を自分でコントロールできているか
2つ目のチェックポイントは、子どもへの心配や不安を自分でコントロールできているかです。
お子さんについて、さまざまな不安や心配があり、自分だけではコントロールできない状態になっていませんか?
親雄さんが不安や心配に駆られて過干渉につながる行動をしている場合、親御さんが安心するための行動と考えることができます。
つまり、気づかないうちに、お子さんのことを思っての行動ではなく、親御さん本位の行動になっているということです。
そのため、過干渉かもしれないと感じたときは、「この行動は、子どものため?自分が安心したいため?」と問いかけてみてください。
ただし、より具体的な行動については、実際のあなたやお子さんの状況にもよるため、精神科医などにご相談することをオススメします。
チェックポイント③すぐに手出し・口出ししていないか

3つ目のチェックポイントは、すぐに手出し・口出ししていないかです。
「これはダメ」「言うことを聞きなさい」と言った言葉はもちろんですが、「こうした方が良いんじゃない?」「これはお母さん・お父さんがやっておくね」などと、子どもの行動を先回りして手出しや口出しをしていませんか?
これまでにさまざまな経験をしてきた親御さんからすると、お子さんの行動はスピードが遅かったり、非効率だと感じたりすることは少なくないでしょう。そして、なにかと口を出したくなるものです。
しかし、お子さんからすると「自分のことを信頼していないから口出し・手出ししてくるんだ」という思いにつながることがあります。
育児や子育てには、見守る心、つまり忍耐力が必要不可欠です。そして、子どもの意思や行動を理解し尊重することも欠かせません。
子どもが失敗や挫折しないよう、道を踏み外さないように、つい口や手が出るときもあるでしょう。
しかし、子どもの人生は子ども自身で切り開くものであり、そのためのフォローをするのが親の務めではないでしょうか。
そういった意味でも、「あなたのため」「あなたを思って」といった言葉で押さえつけ、子どもの自尊心・自己肯定感を奪ってしまわないよう、普段の言動には気をつけることが大切です。
補足:何も言わない・対処しないのも問題

ここまで過干渉について解説してきましたが、何も言わない・対処しないのもことも問題です。
親御さんの多くは、たとえどれだけ過干渉であったとしても、第一に子どもには幸せな人生を歩んでほしいと考えているでしょう。
過干渉の親御さんの肩を持つというわけではなく、これが一般的な親心であることをご理解ください。
そして、大切に育ててきた子どもだからこそ、他者に傷つけられたくない、そして長い人生のなかで失敗・挫折ばかりの道はできるだけ自分の助言で知らせ、避られるようにしたいと思っています。
子育てにさまざまな葛藤を抱える親御さんだからこそ、つい干渉しすぎるケースも少なくないのです。
しかし逆に、過干渉を避けるあまり、何も言わない・対処しない親御さんも少なくありません。
子どもの自主性を優先しすぎるあまり、注意したり叱ったりすることさえもしないケースもあるのです。
そのことを踏まえ、親が子どもに対して言うべきことは、以下の3つあると考えられます。
- 他人に迷惑をかけないこと
- 法律・ルールを守ること
- 他者を傷つけないこと
親御さんが過干渉かもしれないと考えている子どもさんも、この3点を親御さんの言葉などから振り返ってみてください。
人として生まれ、人生を進むなかでは守らなければならないものがたくさんあります。以上の点について注意する親御さんであれば、それは親として子どもを守るための助言と考えて良いでしょう。
しかし、これ以外「あれはしてないけない」「これもしてはいけない」「私の言ったとおりにすれば良い」といった言葉を受けたときは過干渉である可能性を考え、専門家も交えつつ、親子で話し合う場を設けることをオススメします。
親の過干渉な行動への対処法5選
この章では、親御さんの過干渉に悩むお子さんに向けて、親の過干渉な行動への対処法について解説します。過干渉に苦しんでいるひとは実行できそうなことを試してみてください。(参考:キャリル・マクブライド『毒になる母 自己愛マザーに苦しむ子供』)
大切なのは、自分と親御さんとのあいだに境界線を引き適切な距離を保つことです。
対処法①専門的な知識のある専門家や支援機関に相談する

対処法の1つ目は、専門的な知識のある専門家や支援機関に相談することです。
親御さんの過干渉に悩んでいても、「このくらいはよその家でも普通だ」と言われると、お子さんの立場として抵抗しづらいところがあるからです。
また、これまでにご紹介した方法も、実際に親御さんを前にすると、どうしても言えない・できない場合もよくあります。
そういうとき、過干渉を受けている人をたくさん見てきた専門家や支援機関に相談すれば、適切なアドバイスをもらえるでしょう。
相談することで、過干渉かどうかを判断できるようになるとともに、実際のあなたの状況に合わせてどのように行動したらよいかがわかるでしょう。
具体的には、学校の先生やスクールカウンセラー、心療内科、自治体の相談窓口、関連するNPO法人などを利用するとよいと思います。
学校の先生・スクールカウンセラー以外は、インターネット検索で見つかります。例えば、「○○市 中学生 親子関係 相談」「○○区 子ども 悩み相談」のような検索をしてみましょう。
相談先の一覧については、以下のコラムで紹介しています。ぜひご覧ください。
対処法②混乱したら紙に意見を書きだす
2つ目の対処法は、混乱したら紙に意見を書きだすことです。
過干渉を受けているとき、あなた自身も、どこからが自分の考えでどこからが親御さんの考えかがわからなくなっている可能性があります。
「自分はこうすべきだ」と考えていても、それをしないと親御さんに叱られるからそう考えているだけかもしれません。
そこで、紙に意見を書きだすことで、自分の考えと親御さんの考えを分けられるようになります。
過干渉のために頭が混乱しているときは、意見を書きだしてその考えが誰のものかを整理してみましょう。
対処法③親御さんとルールを決めて守る

過干渉を受けている人は、親御さんとルールを決めて守るようにしてください。
例えば、同じ時間に帰宅しているのに、日によって「遅い!」などと怒られたり小言をいわれたりするときには、親御さんとの間で門限を定めるなどするとよいでしょう。
門限より早く帰ったのに、心配だからという理由で文句を言われたような場合でも、一緒に定めたルールを持ちだして説得することができます。
また、門限に遅れそうなには前もって連絡しておくなどして、過干渉をされる前に自分から線引きをして、それを守ることをオススメします。
対処法④ときには親に問題があると思い切って主張してみる
少し大胆な対処法ではありますが、ときには思い切って親に主張するというのも有効です。
特にこれは、罪悪感を盾に過干渉されている人に効果のある対処法です。
親の言いつけを守れない自分は親不孝者だと思いがちな人は、親御さんとの間で問題が起こると、ついすべて自分が悪いのだと思う傾向があります。
思い切って親の問題だと主張してみることで罪悪感から解放されて楽になれます。
「自分の全てを親御さんのせいにする」という意味ではなく、明らかに過干渉に問題の原因があると思ったときには思い切って主張してみるということです。
対処法⑤一人暮らしをするなど距離を置く

親御さんからの束縛があまりにも強ければ、一人暮らしをする、学校や職場の寮に入るなどして距離を置くのも1つの手です。
これはあなただけでなく、過干渉になりがちな親御さんのためでもあります。
距離を置くことで互いに冷静になり、境界線を意識できるようになるからです。
とはいえ、何の相談もなく家を出ることは親御さんを変に心配させるだけです。
大切なのは、話し合って取り決めをした上で距離を置くことです。
話し合いや決断の1つひとつが、あなたの主体性や自立心を高めることにつながります。
まだ一人暮らしのできない年齢の人は、夏休みの間だけ親戚などの家に泊めさせてもらえないか、提案してみるとよいでしょう。
まとめ〜困ったらひとりで抱え込まないで〜

自分が過干渉になっているか悩んでいる親御さんは、不安や心配を自分1人で抱え込みがちです。
また、過干渉を受けているお子さんも、「正当なアドバイス」や「過保護」などとの違いがわからずに、1人で悩むことが少なくありません。
しかし、親御さんもお子さんも1人で悩んでいると、解決の糸口が見つけづらく、ストレスがかかることになります。
大切なのは信頼できる専門家や支援機関に相談することです。このコラムが過干渉で悩んでいる人の助けに少しでもなれば幸いです。
Q&A よくある質問















